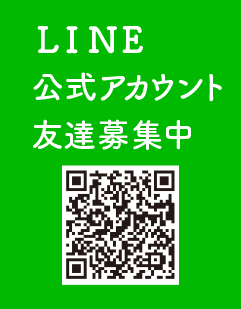ニュース&トピックス
誰もが「老い」の当事者になる。自身の老化を深く楽しく考察するエッセイ『はじめての老い』(伊藤ガビン著)
書籍・アーカイブ紹介
- トップ
- ニュース&トピックス
- 誰もが「老い」の当事者になる。自身の老化を深く楽しく考察するエッセイ『はじめての老い』(伊藤ガビン著)

誰もが当事者になる「老い」についてのエッセイ集
順当にいけば、誰しもが年をとって老いていく。そんなよく考えると当たり前のことを、編集者・伊藤ガビンさんによる新著『はじめての老い』は改めて気づかせてくれます。
本著は、ガビンさんがこれまでネット上で配信してきた連載をまとめて、書籍化にあたりエピソードを書きし足した、老いにまつわるエッセイ集です。ガビンさんは50代末あたりから「自分の中の老いがいま急速に始まっている!」と感じ始めたそうですが、それらに対する実感と考察がガビンさん流の”昭和軽薄体(時々むやみにカタカナが混じる)”で綴られます。
本の中では、老眼や歯茎の衰え、毛量が減る、身長が縮む、眉毛が伸びる、握力が落ちる、おしっこが近くなる、滑舌が悪くなる、手が信じられないほどカサカサになる……、数えきれないほどの老いにまつわるエピソードを披露。それでも、インターフェイスを統一することで老眼をハックしてみたり、映画を観る前には大福を食べて尿意を抑えたりと、老いてもただでは起きない、ガビンさんの気概が伺えます。
伊藤ガビンさんってどんな人?

パソコン雑誌のライター・編集者としてキャリアをスタートした後、1993年に起業。編集的手法を使って、書籍、雑誌のほか、映像、webサイト、広告キャンペーンのディレクション、展覧会のプロデュース、ゲーム制作などを行ってきました。さらに、〈あいちトリエンナーレ〉や〈東京ビエンナーレ〉にインスタレーション作品を発表するなど現代美術家としても活動。現在は京都に在住して、京都精華大学メディア表現学部で新しい表現について研究・指導を行っています。近年のテーマには、自身の「老い」があり、国立長寿医療研究センター「あたまとからだを元気にするMCIハンドブック」の編集ディレクション、日本科学未来館の常設展示「老いパーク」に関わるなど活動を広げています。
失い、手放すことで「老害」になることに抗う

40代の頃に「老害」に関する投稿をSNSで触れて以来、「老害」としての視点のスイッチが入り、それ以降、いろいろな老害に対する言説を「老害の側」として受け止め、”罵詈雑言に勝手にボコボコに打たれてきた”(p.30)というガビンさん。この本では、「失う」「手放す」といった言葉が繰り返し現れます。
歯医者に行けば、先生の態度の変化にいつのまにか「男性の特権」を失っていることに気がつき、瓶の蓋がなかなか開かなかった時には、狼狽えつつも「力強い父親」という役割をいまだに手放せていなかった自分にショックを受けます。それから、健康診断で身長が縮んだと大騒ぎした後、高身長=高価値という昭和の価値観を手放せていないことに気がつき恥ずかしさを感じたりもします。そして、話は運転免許の返納にまで及びます。
「返納」ってそんなに使わへん言葉やと思いますが、老いると気になる言葉ですね。これまで持っていた権利を自ら手放すというタイミングが近づいてくる。(中略)そして返納することは、ある種の気持ちよさがあるのではないかと思う。断捨離にも似た「脱いでいくこと」の気持ちよさよ。(「返納について考える」p.166)
権利を失うことを恐れて意気消沈するよりも、自ら返納(=手放)していく方がメンタルによさそうだと、ガビンさんは続けます。「男らしさ」や「仕事」「筋力」「記憶力」「尿意の我慢」「性欲」など、自分が失いつつあるものにすがりたい気持ちはあると正直に語りつつも、自分が持っていた権利や古い価値観を手放すことに前向きです。
ガビンさんの何かを「失う」「手放す」という行為は、自身の老いを見つめることで、自分自身が築き上げてきた価値観や「あたりまえ」と思っていたことを改める作業のように感じられます。そしてそれは、変わりゆく「あたりまえ」を受け入れて「老害」にならないよう抗う姿のようにも思えるのです。
老化という体験を通じて自身の「あたりまえ」を疑う
この本における「老害」の定義はいささか複雑で、その視点は、当事者ならではの混乱とシンパシーに満ちたものです。その上で、ガビンさんは、”老害の問題は、原因が老人その人に求められがちだけど、もし本当に老人による迷惑を蒙りたくないのなら、それはシステムを変えなければ難しいと思う(p.37)”と語ります。
「古い価値観の人が古い価値観のまま暮らせる社会」の実現というのも面白いテーマだと思うのです。 新しい価値観の人たちの迷惑にならず、古い価値観で暮らすことなんて不可能なのでは? 世代毎の価値観をどう混じり合わせていくのか。簡単なアップデート戦略じゃない道を考えてもよいのかもしれないよね。(「こんにちは老害ですー老害の側から考える老害ー」p.37)
特定の人たちが生きづらく感じる責任を個人に求めるのではなく、個々人の偏見や社会のシステムを変えることで解消していこうというのです。
では、ガビンさんの言う、システムを変えうる“世代毎の価値観の混じり合わせ”はどのように実現できるのでしょうか。それを実現するのは、先に老いゆく人たちの声を聞き、来るべき「老い」について学び、 自分事として考えるという地道な作業の繰り返しにほかならないのではないかと思います。そして、それこそが、この本を読む理由となるのではないでしょうか。
※MUESUMの多田智美さんの主催で、5月5日19:00〜大阪市にある〈graf porch〉にて、「勝手に出版記念 こどもの日の『はじめての老い』オ〜イ、老い!」が開催されます。著者の伊藤ガビンさんを囲んで、美味しいものを飲みながら食べながら、「老い」についてお話をします。詳しくはInformation欄をご覧ください。
Infomation
書籍『はじめての老い』
著者:伊藤ガビン
発売日:2025年3月18日
出版社: Pヴァイン
ページ数:336ページ
Webページ:ele-king books
■目次
はじめに
【老いに入りかけた時に感じていること】
老いの初心者として 初めての老眼/見えてきた! 私がキレる老人になるまでの道/こんにちは老害です-老害の側から考える老害-/らくらくホンを買う日を想像する/人間ドックの見え方が変わった話/ただ老いている
【アップデートできる できない?】
服装がずっと同じ問題/等速じいさん/太るのか痩せるのか/四季にように髪の毛を
【じじいのしぐさ、これだったのか】
シーシー問題/ブランコが怖いということ/おじいさんのような動き
【意外と早くきた(逆にまだきてない)】
身長が縮んだ話/ついに眉毛が伸び始めた!/握力の低下にショックを受けた話/未入荷の老い/シモジモの話/見つめたくない滑舌
【センパイから学ぶ】
センパイの話/手が信じられないほどカサカサになるという話/老猫との対話/メモを片手に綾小路きみまろ公演
【老いと時間】
「返納」について考える/老化が開く知覚との扉/[朗報]時間が経つのは年々それほど早くならないのではないか、という話/記憶のサブスク/死んでも驚かれないサイド/「逃げ切る」という考え方
おわりに
Information
イベント|勝手に出版記念 こどもの日の『はじめての老い』オ〜イ、老い!
日時:2025年5月5日(月/こどもの日)18:00開場/19:00開始
会場:graf porch
参加費:①1,500円(ソーセージ・ビール付)
②3,000円(ソーセージ・ビール・書籍付)
*カレー、追加注文はキャッシュオンでお願いします
ー
ゲスト:伊藤ガビン[編集者/『はじめての老い』著者]
聞き手:服部滋樹[graf]・中川和彦[スタンダードブックストア]
進行:多田智美+竹内厚 [編集者/BYEDIT]
カレー:松村貴樹[インセクツ編集長]
ー
お申し込み:Googleフォームより
お問い合わせ:t@muesum.org(MUESUM多田)・06-6459-2100(graf shop)
協力:graf、ウルトラファクトリーBYEDIT

Information
〈こここ〉公式LINE、友達募集中!
毎週水曜日に編集部おすすめの新着記事を厳選してお届けしています。
・新着記事を確認するのは大変!
・記事のおすすめはある?
・SNSでは、追いかけきれない!
・プッシュで通知がほしい!
という方におすすめです。
友達追加はこちらから