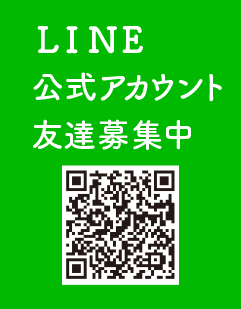ニュース&トピックス
ケアとフェミニズムの視点から「ひつようなかたち」を探る展覧会。東京中野にて7月16日〜20日まで
展覧会情報
- トップ
- ニュース&トピックス
- ケアとフェミニズムの視点から「ひつようなかたち」を探る展覧会。東京中野にて7月16日〜20日まで

〈13番館〉と模索する、現代に「ひつようなかたち」
日記本・ZINE・短歌集の発行や、社会や権威へのメッセージを掲げるグッズ制作、それらを携えての文学フリマ出店、ケア的な視点に立ったワークショップの開催など、ユニークな表現や実践を展開するアートコンビ〈13番館〉。
そんな〈13番館〉が2025年7月16日(水)~20日(日)の5日間、東京都中野区のアートスペース〈水性〉にて、「ひつようなかたち」という名の展覧会を開催します。
本展では、多摩川河川敷で行われたワークショップ「石を拾う会」で参加者が拾った石や日記、旅先で出会った“つるし雛”文化から着想を得た小作品を展示。石を拾うことと見せ合うこと、ひとりで日記をつけること、伝統的な家族観・ジェンダー観を反映したつるし雛に注目し、ケアとフェミニズムの視点から、現代に「ひつようなかたち」を探ります。

生活と地続きの表現の模索、“つるし雛”との出会い
本展を主催するのは〈13番館〉のメンバー・きらかなこさん。日々の生活のなかでの気づきや、フィールドワークを通じて出会ったもの、忘れたくないと思ったものを、写真、映像、立体、パフォーマンスなど、手法を限定せずに展開するアーティストです。
「生活と地続きの表現を模索したい」という思いのなかで、日記をかくこと、ZINEをつくること、石を拾って友人と見せ合うことなど、日々の実践の延長にある営みそのものを作品にできないかと考えてきたといいます。
また、〈13番館〉のもうひとりのメンバー・ヒロノアユミさんと静岡県の稲取に出かけた際、ふたりは“つるし雛”に出会います。地域の女性たちによって、さまざまなモチーフが一つひとつ手づくりされていることに感動したと同時に、「桃=可愛らしさ」「ハマグリ=貞操」といった伝統的なジェンダー観が反映されているモチーフへの違和感も覚えたといいます。
自分たちにとって「ひつようなかたち」とはなにか。それらを模索する作品をつくってみようと思い立ったきらさんとヒロノさんによって、本展は企画されました。

自分にとって必要なものを見定め、向き合う「石を拾う会」
本展の開催に先立って実施されたワークショップ「石を拾う会」。それぞれが自由に石を拾って見せ合ったり、おしゃべりをしてみようという趣旨で参加者を募集し、2025年4月に東京の多摩川河川敷にて行われました。
![ワークショップ「石を拾う会」のチラシ画像。「—ワークショップ参加者募集—石を拾う会 日程①:4月20日(日)、日程②:4月22日(火)、参加費500円、助成:公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京[スタートアップ助成]」](https://libs.co-coco.jp/images/2025/07/09155808/hitsuyonakatachi_1440_04.jpg)
この石拾いは、もともときらさんが友人と始めた活動のひとつ。無数の石の中から、あるひとつの石を選び取ることは、自分にとって必要なものを見定めたり、自分の気持ちと向き合うことであるとし、「石を拾って見せ合うことが、なにか自分自身へのケアにつながっている感覚がある」というきらさんの実感に端を発し、このワークショップが開催されました。
当日は、参加者全員が呼ばれたい名前を共有し合い、主催側から場を安全に進めるためのセーファースペースポリシーを伝えたあと、自由に散らばり、石拾いへ。

場や時間を共有しながら、それぞれのペースや感覚が尊重されることで、安心してひとりになれるような環境が自然と生まれたという本ワークショップ。参加者からは「集団でありながら、個人でいられる時間が多くてとても安心した」という感想が寄せられたそう。

ワークショップ後は、任意で参加者に「日記」を書いてもらっており、今回の「ひつようなかたち」展で、拾った石と一緒に展示される予定です。
「川原で石を拾って見せ合うことや、家族観・ジェンダー観をめぐる対話を経て、自分にとって『ひつようなかたち』を、自分の手で、なるべく安全な場所で選び取ること。また、その過程やかたちを他者にひらくこと。それらを通して、問いや想像が生まれる場をつくれたらと考えています」(きらかなこさん)
アートコンビ〈13番館〉とは?
それぞれが13日生まれという〈13番館〉のきらさんとヒロノさん。美術大学の在学中に知り合い、現在は生活を共にするなかで、各々の表現活動を行っています。
きらさんは先述の通り、暮らしのなかでの気づき、忘れたくないものなどを、さまざまな手法で作品に展開しています。2019年には“起源”や“故郷”をテーマにした展覧会「Roots Routes Travelers」(滋賀県大津市)への出展や、2020年には個展「この星のピッチ」を開催。2021年には静岡県熱海市内の各所にてアーティストが作品を制作・展示するイベント「ATAMI ART GRANT」へ出展するなど精力的な活動を行っています。近年は日記本の執筆・制作にも注力しているそう。
ヒロノさんは現在、ドローイング、日記本・短歌集の制作をメインとした活動を展開中。現在も続くイスラエルによるパレスチナ侵攻・ジェノサイドの開始から1年が経った2024年10月には、友人・知人への呼びかけや、SNSを介して「パレスチナについて考えた日」の日記を一般募集し、1冊の本にする企画を主催。71名の書き手による日記集『パレスチナについて考えた日の日記』が同年12月に発行されました。
そのような活動を行うふたりからなる〈13番館〉は、文学フリマなどへの出店をはじめ、植民地主義や家父長制、権威への抵抗を示すグッズの制作やデモ参加など、社会に対する違和感に声をあげ、活動を共にしています。

「女らしさ、男らしさ」といった観念や、「こうしたほうがいい、こうするべき」といったステレオタイプな価値観、社会通念が根強く残り、そうした枠組みに無意識に自身も当てはめようとしがちな今の社会では、本当の自分の気持ちに気づきにくかったり、思いを置き去りにされたり、表に出しづらかったりすることもあるはずです。
だからこそ、自分がおかれている状況を見つめ直し、自分にとっての「ひつようなかたち」を模索してみることが今必要なのかもしれません。その”かたち”を知るためのヒントが、〈13番館〉のふたりの表現から見えてくるかもしれません。
Information
展覧会「ひつようなかたち」
会期:2025年7月16日(水)〜7月20日(日)
時間:13時〜20時(最終日は18時まで)
会場:水性(東京都中野区新井1-14-14 1階 薬師あいロード内)
アクセス:中野駅北口より徒歩8分
入場料:無料
主催:きらかなこ
共催:ヒロノアユミ
助成:公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京[スタートアップ助成]
SNS:Instagram、X
Information
〈こここ〉公式LINE、友達募集中!
毎週水曜日に編集部おすすめの新着記事を厳選してお届けしています。
・新着記事を確認するのは大変!
・記事のおすすめはある?
・SNSでは、追いかけきれない!
・プッシュで通知がほしい!
という方におすすめです。
友達追加はこちらから!