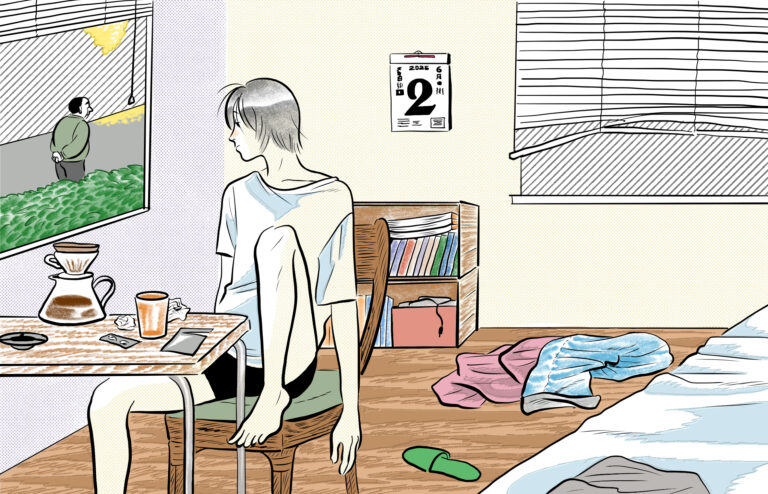ああ、どれもこれも、はやすぎる。「あらゆるものが、はやすぎる」をテーマにさまざまな方にエッセイを寄稿いただく連載です。今回は、NPO法人リベルテ代表の武捨和貴さんに綴っていただきました。(こここ編集部 垣花)
スマホの写真を見返すと、あどけない笑顔でまだ腰が引け恐々立ち上がったばかりの息子がこちらを見ている。この原稿を書いている今、彼は小学校2年。ニンテンドースイッチをしながら「であ!」とゲームの世界に入り込んでいる。彼にとってこの数年は身体も思考も趣味も日々変化が著しい。一方、自分は目に見える変化というのは少ない。
生物学者である福岡伸一さんは生物のありようについて、変化していこうとする細胞と抗う細胞のバランスで成り立つ「動的平衡」だと言っている。人間も1年後には身体を構成している細胞は全てが入れ替わってしまい、細胞としては別人らしい(!)。
それでも、無形の記憶や精神だけでなく有形である「わたし」という姿が変わらないのは、粒として存在する細胞「全体」の変わっていくものと変わらんとしようとするものの「抗い合い」のバランスで、「わたし」がいま、ここに現れているからなのだ。「わたし」は外的要因による変化だけではなく、自分の中の変化にも抗いながら、変わっていく。どちらも勝手に。
わが子は変化する。「大人」になろうとする細胞の方がまさっているから変化が僕から「見える」。僕の方は、「ここ」に留まろうとする細胞よりも「老い」という変化の勢いが増していく。子たちと僕とで、細胞の数や様子も、目に見える体の変化も、できることできないことや生活の様式も異なる。どこかで交差し合う日々の時間を経て、それぞれの生き方へ還る。いつまでも子や仕事を見守っていたいけど、そう思うと大事なのはやっぱり、その人が自分の身体で生きることなのだと思う。
自己紹介をすると、ぼくは今、長野県上田市でNPO法人の代表として地域福祉に関わっている。同じ職場で妻も相談支援員として働いている。妻、子4人と猫1匹で暮らしている。仕事の方は2025年現在、3つの事業所が4箇所の拠点に分かれて点在し、自分はそこの管理者でもある。
法人は13期目。一応、日本の障害福祉の制度で事業所を運営している。「アトリエ」と「食堂」と呼んでいるけど、生活介護と就労継続支援B型の多機能型を2事業、特定相談支援を1つという構成の福祉事業。また文化事業と今年から生涯学習事業の2つの事業も助成金、業務委託や支援を受け予算を確保しながら行っている。
小規模の法人なので/だから(?)事業も事業所も「部門」や「部署」として独立性が担保されている訳ではなく、影響し合う。けっこう、かなり。組織的にも取り組む事業的にも流動性が大きい。運営者として、いち支援者としても、組織や人の様子を見ていると能動的な変化もあれば、ただただ変化に受身になっていることもある。変化したくても変化できなかったり、その逆もあったり、変化していないように見えることが長く続いていてそれが変化だということもあったりする。
どうしようもない、どうもできない、というときは支援の現場でも運営でもある。そんなとき「忍耐力」が必要に感じる場面もあるけれど、耐え忍ぶことよりも、「できること」を見つけて停滞や保守的な停止に<小さく>抗うことが大事だと思っている。過去、不安でどうしようもないときにYouTubeにアップされていた清水ミチコさんと中川家兄の剛さんの泥棒コントを見てから寝るという夜を繰り返したことがあった。フフって笑って寝る。当時は気休めでも、あのくだらなさにどれだけ救われていただろう。
「どうしようもさ」に抗うための小さなことは、そんなことで良い気もする。例えば、人と話す、ということはその小さな抵抗として、停滞に拮抗しうる手段だと思う。しかし、その「人と話す」ということは案外難しい。
2013年、リベルテ初年度は8名の登録者だった。その中には何人かが週1日1時間の利用から始まった。ぼくたちリベルテでは利用する人をメンバーと呼ぶ。10年経って、現在は週4日、1日4時間サービス利用・通所する人もいる。人それぞれの生活や社会生活のペースがある。ああせいこうせいって、どんなに「社会的に正しい」とされても、本人の望まない、ついていけない正しさでは上手くいかないことが多かった。
そうりゃそうだ。「あなたは駄目だ」とさも正しいかのように社会に潜む恣意的な評価を、またリベルテのアトリエや食堂で再び繰り返しても上手くいくはずがない。どんなに同じペースで歩ける人が多くて、足の早いほうが目的地に直ぐに着くとしても、それはそれだ。1着2着よりも、自分が選んだということがとても大切。スタッフはメンバーと歩幅を合わせて仕事をしている。
リベルテは経営的にも事業者、福祉施設としても鈍行列車だ。各駅停車で乗り換えもあったけど、それでも徐々にメンバーも増えていきた。もちろん「働きたい」と願うメンバーもいる。リベルテで以前、哲学者の山森裕毅さんを招いた哲学カフェであるメンバーが「働く」の反対は「孤立」だと言っていた。ぼく自身、大学を中退し、親のスネをかじって京都に居座り通信教育でなんとか学士を取ったけど、学校に行かない、一人の時間はかなり堪えた。
事業を立ち上げた当時、目指したのは、こんな自分を雇ってくれた関孝之さんが立ち上げた風の工房やOIDEYOハウスのような場所だった。「障害」を「ハンデキャップ」から転換し、その人らしさの一つとして肯定し、行きたいときに行けて、アートを介し、手弁当で、人が集まり、地域と繋がっていく、そんな場所だった。今の福祉制度以前の「共同作業所」は「今、それぞれができること」を当事者も支援者も家族も、関わる人みんなで活動をする場所だった。
ぼくの興味関心はアートや表現活動だ。設立から10年、2023年10月「1の人100の言葉1000の時間」という名前の事業所を始めた。働くことが、孤立ではなく誰かとの関わりを生み出すものになればと、「食堂」として給食事業を開始。雇用保険適用となる週20時間を目指せると良いなと思ってそんな数字もメンバーと共有している。だけど、そこで大事なのは今、できることを積み重ねていく、見つめていくことだ。
福祉制度は3年で制度が見直される。障害福祉サービスでは「2年の期限、最長利用できるのが3年」というタームが設けられているものもある。それが悪いとは言わないし、具体的な目標設定が必要なこともあるだろう。だけど、みんながみんな、同じようにはいかない。支援の中で培われた施設内の関係性は「引継書」では引き継げない。
どうしたら事業所が軸ではなくて、「地域に生きる」人を軸に、ケアを福祉制度で生まれた関係や出会いを拡げていけるだろうか。人間は一人ひとりが違うのだから、障害のあり方も一人ひとり、生きている時代背景や地域環境、周囲の関係性、社会風土の中で、「あなた」と「わたし」の前に多様に現れる。こうすれば、こうなる。というような解ばかりではないこの世界に僕も子もメンバーも「あなた」もいる。
「どうすればいいだろう?」ということに出会うとき。目の前の大きな「社会」から成長や発達、解決と判断と結果と、数字や形を求められたとき。自分は自分でなくなるような、消え入ってしまうような感覚になることもあるかもしれない。それでも何か始めてみること、始めようとしたということ。猛スピードで走っている人は加速するその速さの中で風圧に顔をしかめながら、足を前にだしていること。抗いながら、今、できることがある。同じなんじゃないかと思う。今、動くこと、この先10年経って始まることもある。
文化事業で小さな公園づくりをした「路地」というアトリエがある。ガーデナーの和久井道夫さんとつくった。季節ごとに植栽した草木が景色を変える。そこに倉金伸光さんというメンバーが通っている。彼は中学卒業後、50歳を過ぎるまで自宅が主な生活の場だった。ある日、ぼくの息子に出会いそれまで書いてきた猫の絵から唐突にマッチョなクマ「くまきち」を描き始めた。アトリエにあったピラミッドの図版やおしゃれな雑誌のブロマイドを描いていたのに、突然、違う世界が表出した。笑顔が増え、「子は元気か」と声をかけスタッフの心配をする。それまでそうだったのかもしれないし、何かが解けたように感情が現れたのかもしれない。それは誰もわからない。本人も語らない。そういうこともあるのだ。
ある日、唐突に倉金さんから手紙をもらった「いつも元気でいてください。今日もせむくなりますね。元気でね。(原文ママ)」手紙なんて書く人じゃないと思ってたし、どちらかがいなくなる風なのが気になる。けど、いつか、手紙はどちらかの人生と交わるだろう。そのいつかまで、どうにもならないことに、例え小さくゆっくりだとしても、今、「わたし」という存在であることが現れていることを受け取り、自分も変わり、さながらの最中にいる。

Profile
![]()
-
武捨 和貴
特定非営利活動法人リベルテ代表理事/リベルテゲームの会副代表
1982年、長野県生まれ。
社会福祉法人かりがね福祉会「風の工房」に8年間勤務したのち、2013年に特定非営利活動法人リベルテを設立。現在は、就労継続支援B型と生活介護の多機能型事業所として、町中のアトリエをテーマにした「スタジオライト」と、食堂と公園をテーマにした「1の人100の言葉1000の時間」、さらに特定相談支援事業所「路地」を開設。これら3つの事業を、徒歩5分圏内に4拠点で運営している。
利用を希望する方や見学者、新任スタッフは、各施設を歩いて巡ることでリベルテの全体像に触れられると同時に、地域の町並みや生活風土、人と人との関係性にも触れることができる。
文化事業では、福祉施設と地域の境界を曖昧にする取り組み「路地の開き」を開始。2021年度は「公園づくり」、2022年度は仮装して街中を歩きながらドライフラワーを配る「パレード」、2023年度はメンバーの視点から街を読み返す「街歩き」を実施。2024年度には福祉施設を災害・有事における「避難所」と見立て、合宿形式で「避難訓練」を行った。これら一連の文化事業は、2022年度から2024年度にかけて信州アーツカウンシルの伴走支援を受けている。
2025年度は「障害のある人の生涯学習」をテーマに、LEARN by Creation NAGANO実行委員会と共催で事業を展開。「同心円状に関わり合う出会いと発見」を“学び”ととらえ、祭りと防災を掛け合わせた企画を進行中。
現在は上田市在住。妻と子ども、猫とともに3人と1匹で暮らしている。