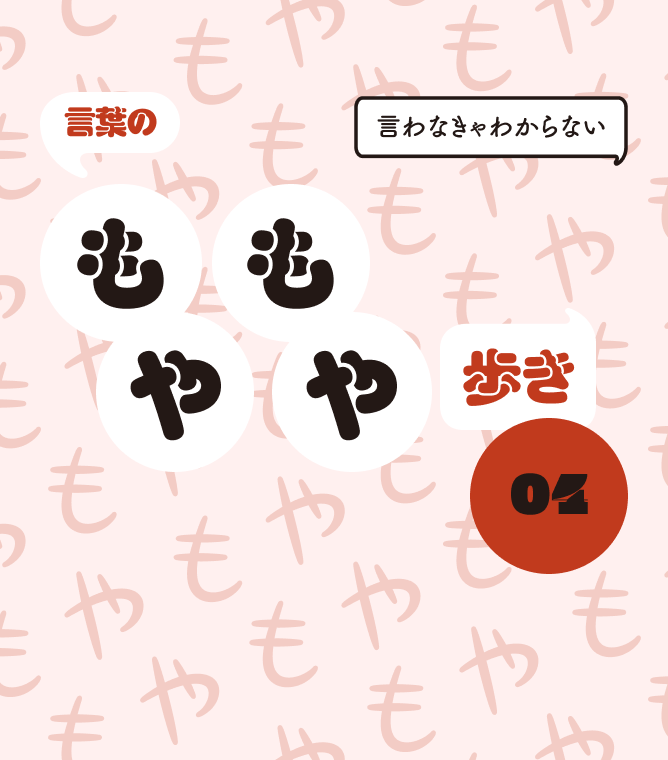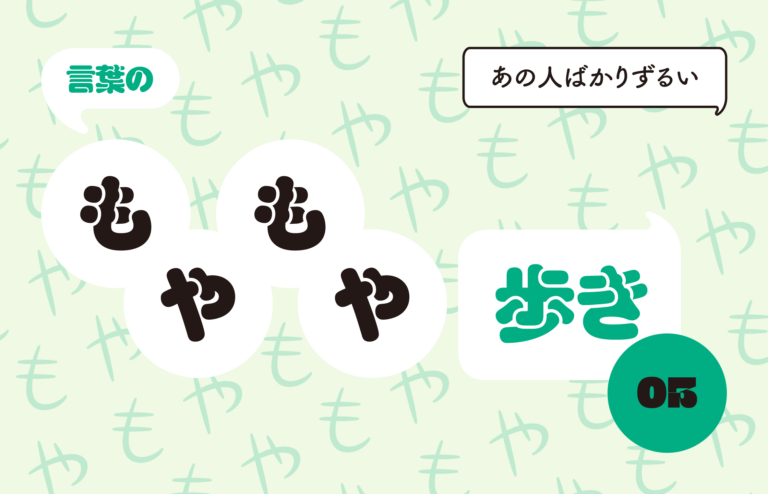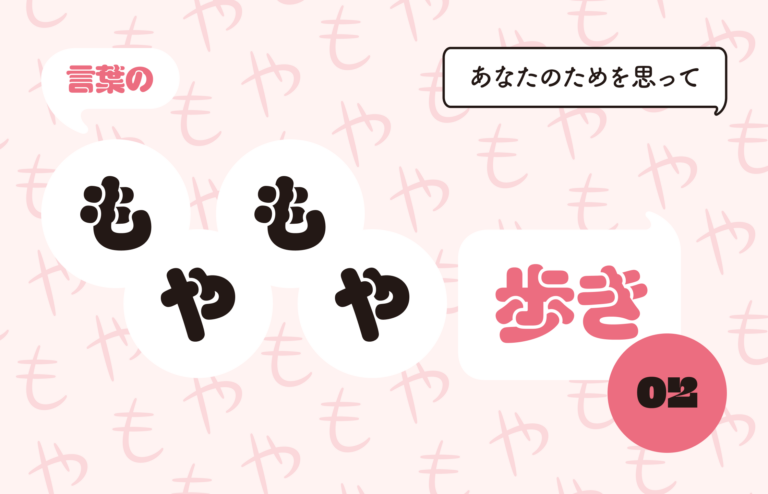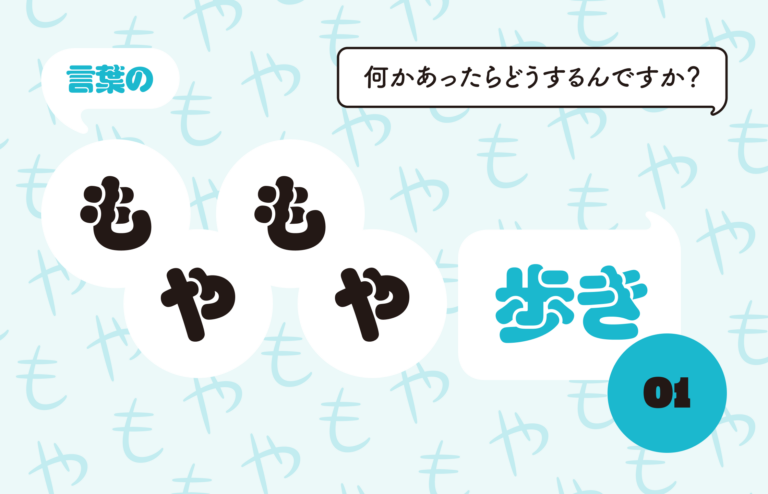言葉には誰かを感動させたり、人と人とをつないだりする力があります。一方で、言葉だけが暴走し、人を傷つける場面も増えているような気がします。「言葉にならないもの」や「言葉にできない状態」を、私たちはもう一度振り返ってもいいのかもしれません。
社会の中でときどき聞く、人々の幸せ(=福祉)に確実に影響を与えているだろう言葉をみんなで考えていく連載『言葉のもやもや歩き』。第4回のテーマは「言わなきゃわからない」です。
今回は、雑談の人として幅広く活動する桜林直子さん、児童養護施設をはじめさまざまな福祉事業所を運営する櫛田啓さん、難民・貧困・災害などをテーマに国内外を取材してきた安田菜津紀さんの3名にご寄稿をいただきました。
・桜林直子さん(雑談サービス「サクちゃん聞いて」主宰)
・櫛田啓さん(てらす峰夢 施設長/みねやま福祉会 理事長)
・安田菜津紀さん(フォトジャーナリスト/Dialogue for People 副代表理事)

「わからない」は怖いけれど 桜林直子
娘が小さい頃、泣いている彼女に「何がイヤだったのか、どうしたいのか教えてほしい」と何度も言った。泣いている最中は泣くことに忙しそうなので「泣き終わったら教えてね」と言うと、しばらくして「泣き終わったよ」と言いながらやってきて(かわいい)、「自分でやりたかったの」だとか「うまくできなくてイヤだったの」などと彼女なりに考えた理由を教えてくれた。泣いている間にわからなくなってしまったのか、理由が見つからないときは「おなかがすいてたのかもしれない」と言うこともあった。
言葉を多く持たない子どもに「言葉で説明しろ」というのは、いささかスパルタ気味だったと今では思うところもある。しかし、おかげで娘は自分の気持ちや気分を言葉で表す習慣がつき、わたしにいつも伝えてくれた。悪い癖ではない。自分で自分のことを知ろうと内側を覗き込み、言葉を見つけて外に出すことはいいことだ。気分が悪いときに近くの人にやつあたりしなくて済むし、どうしたいかわかっていた方が解決もスムーズだ。
結果的によかったと思ってはいるが、これは本当に彼女のためだったのだろうか、という疑問も残る。わたしの「相手をわかりたい」という気持ちに嘘はなく、悪いものは混ざっていないつもりだが、自分のわからなさを解消したくて、安心するために知ろうとしたとも言える。「わからない」は、怖いから。
気持ちにぴったりな言葉を探す作業は大切だが、頭の中や心の中にあるものと、言葉にして出すことの間には、本来ものすごい距離がある。知っている言葉に当てはめるだけではその距離は埋まらない。「悲しい」という言葉を使った途端、心の中では何色も混ざった複雑なマーブル状だった感情が、べたっと一色に塗られてしまう。言葉にすると伝えることはできるが、それらはすでに別ものなのだ。
「言わなきゃわからない」は確かにその通りだ。何も言わなくても汲んでくれというコミュニケーションは健全ではないし、わたしたちはエスパーでもない。
しかし、「わかりたい」という気持ちの奥には「わからない怖さを解消したい」という思いがあることも自覚したい。そして、どんなに言葉で説明されても、完全に伝わることはなく、「言っても完全にわかることはない」ということを前提に言葉を交換したい。どうせわからないのなら、せめて誤解のないように言葉を尽くしたい。「わからない」の怖さを受け入れ、「わからない」を味わう勇気を持ちたい。

本当の気持ちは、最後に⾔葉になった 櫛田啓
女の子は鏡を見てつぶやいた。
「私なんて全然可愛くない」
長い髪を二つに結んだ彼女が暮らしていたのは、家庭で生活することが難しい子どもたちが生活する児童養護施設だった。女の子は親から虐待を受け、5歳で施設にやってきた。人から愛される経験がなかった彼女は、自分を愛する方法がわからない。ある日、女の子は泣きながらこう⾔った。
「私なんて生まれてこなければよかった」
5歳の幼い子どもの口から出たあまりにも悲しい⾔葉に、施設の職員の胸は締めつけられた。それから職員は毎日のように女の子を抱きしめた。「大好きだよ」と⾔葉を添えて。
それでも女の子は毎日のように泣き、怒り、時にはパニックのような状態になった。「死ね」「お前なんか嫌いだ」と職員に暴⾔をぶつけることもある。いつまでこんな日々が続くのだろう……。そう感じながらも、職員は決して怒らなかった。なぜなら、その⾔葉や行動は、過去に体験した寂しさや恐怖や悲しみが自分の中で入り混じり、整理できずにあふれ出てしまったものだと知っていたから。彼女の本心ではない、と考えたのだ。
福祉の現場で働く職員は、目に見える行動や耳で聴く⾔葉だけで子どもの状態を判断しない。その背景にある「⾔葉にならない声」に耳を澄ませ、目には見えない困り事を感じ取ろうとする。時に暴⾔や反抗に見える行動も、実は「助けて」という叫びかもしれない。その声を受け止め、子どもたちの力を信じ、困った時はいつでも助けられるように側に居続けることこそが、福祉の仕事の大切な専門性なのだ。
女の子は笑っていても、どこか不安そうな目をすることがあった。他の子どもが大きな声を出すと怯えた表情を見せたり、夜になると部屋の隅に座って一点を見つめたりすることもあった。職員はその一つひとつの表情から、何に怯えているのか、どんな記憶が思い出されたのか、今どんな気持ちでいるのか、小さな変化を見逃さないよう感性を研ぎ澄ませる。毎日のように暴⾔をぶつけられながらも、職員はそうして彼女に寄り添い、抱きしめ続けた。
数年が経ち、女の子は今、たくさんの愛情に包まれながら里親家庭で生活している。施設を退所する日の朝、鏡の前で「ねえ、今日の髪型可愛い? この服どうかな?」と笑顔で問いかける女の子に、「最高に可愛いよ」と返した職員の目には涙が輝いていた。すると、彼女は泣いている職員を見つめて⾔った。
「今までいっぱい酷いこと⾔っちゃったけど、本当はとっても感謝してるよ。ありがとう」
その⾔葉に、職員の頬を大粒の涙が伝った。
「嬉しいよ」
言わなくても感じ取れる声がある。⾔わなきゃわからない⾔葉もある。
女の子の本当の気持ちは、最後に⾔葉になった。

「言わなくてもわかれよ」との狭間で 安田菜津紀
「言わなきゃわからない」の向こう側、というテーマを頂いたとき、ひねくれ者の私の頭にはすぐ、「言わなくてもわかれよ」という反対方向の圧力を指す言葉が浮かんでしまった。
念頭にあるのは電車内などで無断撮影した写真を、「迷惑外国人」といった文言付きで世界中に晒す行為だ。悪質なケースもあるかもしれないが、「公共」の概念や、社会で共有されている「暗黙のルール」はそれぞれ異なり、それを「知らない」という場合もあるだろう。「言わなくてもわかれよ」は、違ったカルチャーに身を置いてきた人の姿を“異物化”する。もちろん、単に「言えばいい」ということでもなく、怒鳴り散らしながら一方的に撮影することが問題であることは言うまでもない。
逆に「言わなきゃわからない」が、暴力的に外国ルーツの人々に向けられることもある。たとえば命の危険から逃れてきた人たちが直面する、難民認定のハードルの高さだ。
日本政府は、「あなた個人に迫害のおそれがあるという証拠を示せ」など、国際ガイドラインとはおよそかけ離れた独自の解釈をあてはめてきた。しかしどの点をどのように説明すればいいかなど、当事者が認定の仕組みを把握しきれるはずもない。私がインタビューしたアフリカ出身の男性は、不慣れな書類に書ける限りのことを書いて提出しようとしたものの、入管窓口で「ここダメ、これダメ」と日本語で言われるばかりだったという。彼が最初に覚えた日本語が「ダメ」だったのもそのためだ。
何がどう「ダメ」なのか、「言わなくてもわかれ」と投げかけておきながら、当の難民申請者にはハードルの高い説明責任を「言わなきゃわからない」と課す。そのくせ「言わなきゃわからない」と求めてきた側は、その説明を結局は受け止めようとしない。
入管の難民認定審査で不認定とされ、不服を申し立てた人の「二次審査」は、法務大臣に指名された難民審査参与員が担う。しかし審査件数に偏りがあり、ある参与員は2022年、単純計算すると一件あたりの審査時間が6分ほどではないか(*注)、と思われる大量のケースを担っていた。命を左右する判断であるにもかかわらず、だ。
そして今、「日本人ファースト」というスローガンのもと、デマも交えたヘイトスピーチが横行する。その矛先を向けられても、日本国籍がなければ、投票を通してそれに「NO」を示すことができない。今度は「言わせない」不条理だ。
「言わなくてもわかれよ」と「言わなきゃわからない」、そしてそもそも「言わせない」の狭間で、マイノリティや脆弱な立場にいる人たちが翻弄されている。その現状さえも「言わなければわからない」社会でいいのだろうか。
*注:全国難民弁護団連絡会議の声明(2023年5月29日)より

Profile
Profile
![]()
-
櫛田啓
てらす峰夢(児童養護施設)施設長
社会福祉士。2025年6月より、社会福祉法人みねやま福祉会 理事長。出身は京都府京丹後市峰山町。学生時代に「Jリーガー」を夢見てサッカーに明け暮れたのち、恩師の一言から「福祉」の道を志すことに。大阪や福岡での生活を経て、10年振りに帰郷し故郷の衰退を目の当たりにした時、自らの運命を受け止める覚悟を決める。現在は、子ども・大人・お年寄りという世代に関わらず、また、年齢や疾患、障がいの有無に関わらず、地域の中で人と人の支え合いを大切にする「ごちゃまぜ」の社会づくりを通じて、人々のこころ豊な暮らしの創造に貢献する。社会福祉の変革に取り組む職員の想いを社会に届けるイベント「社会福祉HERO’S TOKYO 2018」初代ベストヒーロー賞受賞。