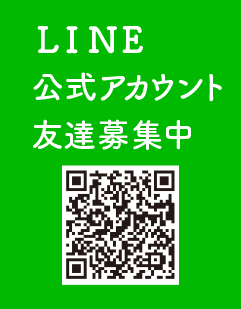ニュース&トピックス
『文化的処方のはじめの一歩』でアートと社会をつなぐ。実践に役立つガイドブックが3月17日より無料公開
書籍・アーカイブ紹介
- トップ
- ニュース&トピックス
- 『文化的処方のはじめの一歩』でアートと社会をつなぐ。実践に役立つガイドブックが3月17日より無料公開

アートや文化が、こころの処方箋になる。「文化的処方」のガイドブックが誕生
忙しさに追われる日々のなか、美術館に足を運んだり、地域のイベントで誰かと話したり、手を動かして何かをつくったりすることで心が安らいだ経験がある人も多いのではないでしょうか。文化や芸術が、健康でより良く生きるための助けになることがあります。
文化・芸術と暮らしをつなぎ直す「文化的処方」の実践をサポートするためのガイドブック『文化的処方のはじめの一歩』が2025年3月に、〈国立アートリサーチセンター〉(略称:NCAR、センター長:片岡真実)および東京藝術大学等によって制作されました。ウェブマガジン「ああともTODAY」にて公開され、無料でダウンロードすることができます。
ストレスにも孤独にも、認知症にも。アートと文化が持つ力
国立アートリサーチセンターは、アートの力を社会の中で活かしたいという思いから生まれた組織です。「アートをつなげる、深める、拡げる」をミッションに掲げ、全国の美術館や大学、研究機関などと連携しながら、アートを深く知るための情報発信や、作品を活用するアイデアの共有、アーティストへの支援など、幅広い活動を行っています。
その中で注目されているのが「文化的処方」という考え方。美術館に行くことや、絵を描くこと、音楽を楽しむことでストレスが軽減されたり、食欲が増進したりと、心や体の健康に良い影響を与えることが近年の研究で明らかになりました。認知症などの疾患や社会での孤独感といった医療や福祉の課題に役立つとされ、欧米をはじめとする多くの地域で実践が進められています。
国立アートリサーチセンターは、こうしたアートとケアの関係に注目し、「文化的処方」を社会の中で広めていこうとしています。東京藝術大学が拠点となり、大学、美術館、医療・福祉の組織や自治体など、42の産官学と連携する「共生社会をつくるアートコミュニケーション共創拠点(略称:ART共創拠点)」にも参加し、「文化的処方」を推進。
この取り組みのひとつとして、ガイドブック『文化的処方のはじめの一歩』が作られました。このガイドブックの発刊には、「多くの人が、アートの力を身近に感じられるように」という思いが込められています。誰にとってもアートや文化的活動がそばにある社会を目指す。そんな第一歩となるようなツールです。

「文化的処方」で何ができる?効果効能から、始め方まで解説
「文化的処方」は、欧米では「つながりをつくる処方/ Social Prescribing」や「クリエイティブ・ヘルス / Creative Health」として注目されており、日本でもその広がりが期待されています。
ガイドブックは、「あなたの『好き』が、誰かの『道しるべ』になる」とのステートメントから始まり、「文化的処方」の定義や意義を丁寧に解説したうえで、美術館・病院・市民団体・大学・個人店という多様な現場での5つのケーススタディを紹介しています。
それぞれの現場で、どのようにアートがケアの現場とつながっているのかを、写真を交えた事例紹介から具体的に知ることができます。

ケーススタディの1つとして、2021年のコロナ禍で東京都美術館がスタートしたシニア向け事業〈Creative Ageing ずっとび〉の中で企画された、オンラインプログラム「アート・コミュニケータと一緒に楽しむ おうちでゴッホ展」が取り上げられています。
認知症のある人とその家族を対象に、オンライン上でアート・コミュニケータ(愛称:とびラー)とともにゴッホの作品を鑑賞し、参加者同士がコミュニケーションを深めるプログラムです。年齢を重ねてもアートが身近にあり、生活を楽しむための手札の1つとしてあり続ける重要性が記されてます。

〈こここ〉でも、東京都美術館と東京藝術大学と市民が連携して行う、アートを介してコミュニティを育むソーシャルデザインプロジェクト「とびらプロジェクト」について取り上げ、“対話”を生むアート・コミュニケータ「とびラー」の役割を紹介しました。
また、街中でのケーススタディとして、三重県にある〈すみた酒店〉が、店の奥の座敷で実践してきた影絵劇の取り組みも掲載されています。酒屋を運営する夫婦が、近所の人や地元の中高生などを巻き込みながら繰り広げてきた影絵劇。あるとき、老人介護施設に入所する人が観劇し、介護職員も驚くような、感情豊かな反応が見られたという出来事が紹介されています。

さらに、ケーススタディの後には、「文化的処方を始めるにはどうしたらいいか」という手引きも掲載されています。「学ぶ」「つながる」「調べる」の3項目で、押さえておきたい用語やアートを通して人と人をつなげるステップ、リサーチのヒントを紹介し、生活の中での実践方法をわかりやすく解説。

「文化」「芸術」「アート」は特別な人のためのものと、どこか敷居が高く感じる人もいるかもしれません。しかし、アートは「自分に似合う服を選ぶときのワクワクや、きれいに並べられた料理を味わう心のような、日常の中にある創造的な喜び」であると本書の巻末に記されているように、小さな感動は身近にたくさんあるかもしれません。
『文化的処方のはじめの一歩』は、文化活動を広げたい人や、医療・福祉に新しい視点を取り入れたい方にとって、まさに“はじめの一歩”となる1冊です。気になる方は、ぜひ手に取ってみてください。
Information
『文化的処方のはじめの一歩』
内容:「文化的処方」の定義・意義、日本の美術館・病院・市民団体・大学・個人店での事例紹介
仕様:B5変型/36ページ/中綴じ
対象:アートやケアに関わる個人の方や地域でのつながりに関心のある市民団体、美術関係者や医療・福祉関係者
閲覧方法:ウェブマガジン「ああともTODAY」にて2025年3月17日(月)より公開
サイトURL: https://aatomo.jp/guidebook
PDF版URL:https://aatomo.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/bunka_print.pdf
お問い合わせ:
国立アートリサーチセンター ラーニンググループ
https://ncar.artmuseums.go.jp/inquiries/learning/
Information
〈こここ〉公式LINE、友達募集中!
毎週水曜日に編集部おすすめの新着記事を厳選してお届けしています。
・新着記事を確認するのは大変!
・記事のおすすめはある?
・SNSでは、追いかけきれない!
・プッシュで通知がほしい!
という方におすすめです。
友達追加はこちらから