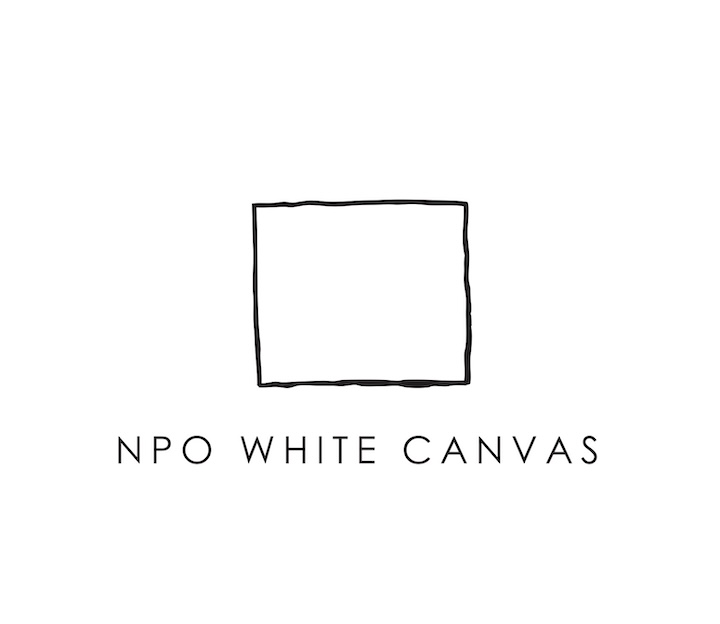こここなイッピン
ユメカワ・シリーズ〈WHITE CANVAS〉
福祉施設がつくるユニークなアイテムから、これからの働き方やものづくりを提案する商品まで、全国の福祉発プロダクトを編集部がセレクトして紹介する「こここなイッピン」。
滲んで、広がって、混ざり合う、美しい色彩の「ユメカワ・シリーズ」。そのベースとなる水彩画は、メンバーの心身の調和を図り、整える“アートセラピー”から生まれているのだとか!
“絵画療法”による水彩画を活用した、エモーショナルなペーパー・プロダクト

シャボン玉に揺らめくあの色を閉じ込めたような、淡く儚いグラデーション。滲んで、広がって、混ざり合う色たちは、いつか見た不思議な夢の世界のようで、情緒的で、やさしくて、美しい。
そんなエモーショナルなイッピン「ユメカワ・シリーズ」を制作するのは、2020年に長野県安曇野市に設立された〈NPO法人 WHITE CANVAS〉。生活介護事業所を利用するメンバーたちの心や体にアプローチする“絵画療法”として描かれた水彩画を、バッグや封筒に仕立てています。

アートセラピーから生まれた「ユメカワ・シリーズ」
自由な芸術・表現・ものづくりの場を目指す〈WHITE CANVAS〉。染織、刺繍、陶芸、造形、木工などに加え、色の世界に浸る療法的な水彩も行われています。
その水彩とは、湿らせた紙に専用の絵の具を置き、色の持つ動きを感じていく「コロー・メソッド」の技法のひとつを導入したもの。ふんわりと色が滲みつつも、滲み過ぎることはなく、絵筆の動きが、動きとして残っていくのだとか。
「まずは、15色ほどある絵の具の中からメンバーに好きな色を選んでもらい、自由に描いてもらうんです。あるメンバーさんは点々を描くのが好きで、色の一つひとつの広がりをじーっと眺めながらリラックスしています。そして、だんだんと色の散らばりが楽しくなって、最終的には感情がエキサイトしていくんですね。もう衝動が抑えられない! という感じで」
そう語るのは〈WHITE CANVAS〉の代表であり、オーストラリアのシエナアカデミーでコロー・メソッドを学んだ石岡享子さん。

コロー・メソッドとは、シュタイナー教育(※注)の流れを組み、色彩の働きによって心身の調和を図り、整えていくというアートセラピー。教育者のルドルフ・シュタイナーや、詩人・劇作家・小説家としても知られる自然科学者 ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテの「色彩論」を基盤に、画家のリアン・コロー・デボアが開発した絵画療法です。
1枚目の水彩では、メンバーの思いのままに色を乗せて感覚を刺激して発散し、2枚目の水彩では、スタッフがガイドをしながら昂った心身を落ち着かせ、深い呼吸を取り戻す状態にまでに持っていくのだといいます。
「点々を描くメンバーさんは、コロー・メソッドを終える頃には呼吸も穏やかになるようです。週に一度、そんな日を設けていることがご本人の良いリズムになっていると感じています」
(※注)ドイツを中心に活動した哲学者・教育者のルドルフ・シュタイナー(1861-1925)が提唱した、人智学に基づき、子どもの個性を尊重した教育思想。1919年にドイツで最初のシュタイナー学校が設立され、100年以上経った今も、世界60カ国以上で1000校以上が存在するとされている。

そうして描かれた水彩画の活用として制作されているのが「ユメカワ・シリーズ」。これまでにバッグ、封筒、ランタン、ポーチなど、さまざまなアイテムが生まれてきました。
シリーズのひとつ「ユメカワbag」には、じんわりと滲みが広がる障子紙が使われています。表面に蝋引きをし、裏面には不織布を貼り、ミシンで縁を縫って完成。素材が素材だけに強度はありませんが、ドライフラワーなどを入れて壁に飾ったり、LEDライトを中に入れて淡い灯りを楽しんだり、という使い方もオススメです。

そして、さまざまなサイズの封筒やポチ袋に展開された「ユメカワ封筒」。こちらに使われている紙は、某メーカーのお絵描き帳。障子紙より色が滲まず、描いたままの形を残したいメンバーに人気の素材です。
刻々と変化する空模様のように、一枚一枚に異なる情景が広がる「ユメカワ・シリーズ」。その淡くも深い色の連なりを眺めていると、不思議な没入感があります。制作者の心身を整えてきた水彩は、見手側の感情にも心地よい刺激を与え、作用するのかもしれません。
福祉のものづくりを“たて糸”に、地域とのつながりを“よこ糸”に
NPO法人として2020年に立ち上げられた〈WHITE CANVAS〉。代表の石岡さんは、美術大学の在学中に障害のある人のものづくりに出会い、福祉施設、保健センター、在日外国人のコミュニティなどにおける活動を重ねてきました。
大学卒業後はケニアに渡り、盲学校でのボランティアや、障害のある人の手仕事などに触れ、帰国後はデザインの仕事に従事。そして再び日本を離れて、障害のある人・ない人と共同生活を営むイギリスの「キャンプヒル」に参加するなど、国内外を行き来し、さまざまな実践を行ってきました。
そうしたなかで、社会とポジティブにつながれる「デザイン」や「アート」の力や可能性を実感した石岡さんは、自由な表現を引き出し、ものづくりを突き詰める事業所設立を計画。集まってきた仲間とともに〈WHITE CANVAS〉を立ち上げました。

現在は、アート活動を中心とする生活介護事業所「TIME WARP」と、絵画クラブやオイルマッサージサロンを中心に、地域の人々との出会いや交流を生み出す拠点「atelier WOOF」を運営しています。
事業名に冠された「WARP」は織物の“たて糸”を指し、「WOOF」は“よこ糸”を意味します。障害のある人のものづくりを主軸とする「TIME WARP」をたて糸と捉え、地域のものづくりが好きな人々が「atelier WOOF」を通じてよこ糸として関わり、いつしか大きな1枚の織物となっていく――。そんなイメージを思い描きながら、〈WHITE CANVAS〉は今後も多様な活動を行っていくといいます。
イベント情報
野焼きの焼き物づくり、土絵具をつくって絵を描くなど、ユニークなワークショップを度々行ってきた〈WHITE CANVAS〉が、2025年10月3日(金)・4日(土)の2日間、廃鉄をコークスで熱して叩く「ぺちゃんこにするワークショップ in 安曇野 2025年 秋」を開催!
鉄作家の小沢敦志さんを講師に迎え、食材の空き缶、壊れた農機具、譲り受けた自転車や工具など、さまざまな状態の鉄の廃材をコークスで熱し、ひたすら叩くというワークショップです。 鉄を叩き続けた先に見える景色とは? 参加ご希望の方はイベントページをチェックしてみてください。
Information
ユメカワ・シリーズ
ユメカワbag
サイズ:W26×H30cm
価格:909円+税
―
ユメカワ封筒
サイズ:商品による
価格:300円+税/2枚セット、500円+税/5枚セット
販売:GOODJOB! STORE
制作:NPO法人 WHITE CANVAS