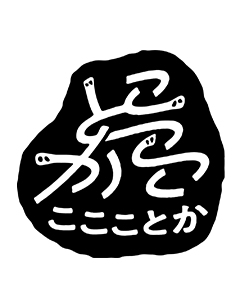こここなイッピン
手織り・手縫いのポーチ&バッグ〈ひょうたんカフェ〉
福祉施設がつくるユニークなアイテムから、これからの働き方やものづくりを提案する商品まで、全国の福祉発プロダクトを編集部がセレクトして紹介する「こここなイッピン」。
障害のある人とともに“織物”を中心とした活動を行う〈ひょうたんカフェ〉。メンバーが得意とする表現をすくい出し、個人名を冠した織り名をつけるなど、一人ひとりの個性を尊重したものづくりと、ユニークな事業内容をご紹介します。
メンバーの創造性が光る一点ものも! 多くのファンを持つ手織り・手縫いアイテム

織り機で丁寧に織った布で仕立てた木の葉型のポーチと、その横に置かれた写真を見て、……ハッ! とした方はご名答。そう、このポーチに使われている布地は、写真から得られた情報を、織り手の感性や視点のなかで再構築し、織られたものです。
「赤富士」の写真を大きく構成するのは、赤、青、紺の3色。しかし、織り重ねられた糸は30種類を超え、極めて複雑です。ミクロの目で見れば実際にこのような色彩で構成されているかもしれません。
世界一美しい猿といわれる「アカアシドゥクラングール」のフワフワとした毛並みを、毛足の長い糸で形象するアイデアの妙。「ハンミョウ」と呼ばれる昆虫のメタリックな体色の表現力。昆虫だけでなく、背景の色彩も組み込まれていることに気づいたでしょうか?
「なかじま織り」と名づけられたこの織りの色彩構成は、絵画の技法にも通じるものがあります。もはやこのポーチは“ひとつの絵画”といえるかもしれません。

メンバーの個性や好きなものを肯定し、世に放つ
この「リーフポーチ」を制作・販売しているのは、愛知県名古屋市中村区に拠点を構えるNPO法人〈ひょうたんカフェ〉。同法人が運営する生活介護事業所に通う中嶋さんは、写真やテーマをもとに独自の感性で色彩を再現していく「なかじま織り」を7年ほど前からスタートさせました。
そのきっかけをつくったのは、カラフルなさをり織りを得意とし、図鑑を眺めるのが大好きという、中嶋さんのパーソナリティをよく知るスタッフ。図鑑から好きなモチーフを選び、それをテーマに織ってみることを提案すると、爬虫類や魚類などを選んでは、糸棚から30~40種類もの糸を選び、織っていったといいます。その様子をスタッフの佐々木さんはこのように語ります。
「僕たちには見えてこない、中嶋くんならではの色彩感覚があるんです。僕が糸を選ぶならせいぜい15色くらい。でも、中嶋くんは水色だけでも10色くらい選んだりするんです。『この色が足りない!』って、ずっと糸棚を探していて。多いときは、ひとつの織物に50種類もの糸を使っています」
そんな中嶋さんならではの織りを広く提供できればと、なかじま織りの受注を開始。依頼者から写真やテーマを提示してもらい、中嶋さんが布地を織り、スタッフが指定の形に仕立てています。これまで、飼い猫や結婚式の写真、好きなアニメ作品といったテーマで注文があり、中嶋さんの感性で織られた布に「そうそう、この色!」と依頼者たちも満足気なのだとか。

現在〈ひょうたんカフェ〉には15人ほどの織り手・縫い手がおり、それぞれが個性の際だった表現を行っています。
5人組の某アイドルが好きな織り手は、5つのメンバーカラーで構成した「アイドル織り」を開発。また、毛織物産地として名高い尾州(愛知県尾張西部~岐阜県西濃エリア)の高級装飾糸を使い、織り手ならではの色彩感覚と間で織られた「るり織り」や、無地に織られた布にカラフルな刺し子を施していく「コウジステッチ」などがあり、それぞれに根強いファンがついています。
そのメンバーにしか生み出せない表現を、日々の何気ないやり取りのなかですくい上げることを大切にしているというスタッフ。そのつぶさな眼差しから生まれる支援と、「〜〜織り」とメンバーの名前や特徴を冠し、その人の個性や好きなものを肯定しながら世の中に放っていく事業のあり方が、メンバーの大きな自信につながっています。
豆腐屋さんスタイルの“引き売り”も⁉
〈ひょうたんカフェ〉が設立されたのは2006年。同事業所の副代表理事であり、〈NPO法人motif〉の理事長・井上愛さんは、福祉施設の職員として活動していた頃、障害のある人が手がけた「織り」の奔放な表現に出会い、感銘を受けたといいます。その後、手織り教室を3年間運営し、現在の代表理事・橋本思織さんとともに〈ひょうたんカフェ〉を立ち上げました。
事業所の取り組みとして導入したのが「手織り」。網代織り、千鳥織りなど、シンプルな織り方で取り組みやすく、糸の色を変えれば印象ががらりと変わり、大量生産も可能な「組織織り」が事業の中心となりました。淡々と織りながらも、クリエイティブな創作活動である手織りは、ものづくりが好きなメンバーたちにフィットしたといいます。

その後、もうひとつの活動としてスタートしたのが「手づくり豆腐」事業。国産大豆の豆乳を仕入れ、事業所内の工房で豆腐をつくり、「パ〜プ〜」とラッパを吹きながら、リアカーを引いてまち中で売り歩く活動が2008年に始まりました。
現在は国産大豆のおからを使ったドーナツづくりに舵を切り、事業所内のカフェにて販売。毎週木曜には、ドーナツ、パック入り豆腐、焼き菓子、雑貨などをリアカーに乗せ、まち中での引き売りも行っています。

そうした、メンバーとともに外へ出ていく活動や、評判のドーナツと、さまざまなグッズ展開で名が知られ、地域住民から愛される存在となった〈ひょうたんカフェ〉。
新しい図案の組織織りをいち早くオーダーする地元ファン、ポーチを大口発注する地域の民生委員、法要などの際に身につける輪袈裟を「るり織りで織ってほしい」とオーダーするお寺関係者も。そして、引き売りのラッパの音を楽しみにしている人も多くいるようです。
〈ひょうたんカフェ〉が目指してきたのは、障害のある人を中心として、地域のさまざまな人が出会い、交流し、お互いを認め合い、人とつながり合う喜びを感じられる“カフェ”のような場所。今では月に一度、事業所をひらく「オープンディ」も開催され、まさに多様な人が集まる場となっています。
さて、さまざまな紋様&カラーの組織織りアイテムをはじめ、なかじま織りといった各メンバーによるオリジナル品は、常時オーダーを受け付けているとのこと。ご興味のある方は公式サイトのメールフォームや電話にて問い合わせてみてはいかがでしょうか?
Information
手織り・手縫いのポーチ&バッグ
リーフポーチ
サイズ:W14×H10センチ
価格:1450円
–
スマートフォンショルダー
サイズ:約W13×H18.5×D2.5センチ
価格:4620円
–
カードケース
サイズ:W13×H8センチ
価格:1450円
–
PCケース
サイズ:W37×H25センチ
価格:4950円
製造:NPO法人ひょうたんカフェ
Information
〈ひょうたんカフェ〉のアイテムが〈ここことか〉#004 にて販売!
東大阪市の「近大まなびや通り」に所在する福祉発セレクトショップ〈ここことか〉にて、〈ひょうたんカフェ〉のアイテムを取り扱っています。
- 取扱期間:2025年9月8日(月)〜12月末
- オープン日時:基本的に月・水・金の11時〜18時(祝日など例外的にオープンする日もあるので、詳細は〈とか〉のInstagramをご覧ください)
- 住所:〒577-0811 大阪府東大阪市西上小阪14-14 〈とか〉店舗内
- 運営:〈とか〉、株式会社マガジンハウス〈こここ〉
詳細はこちらをご覧ください。
Profile
![]()
-
ひょうたんカフェ
特定非営利活動法人
〈特定非営利活動法人ひょうたんカフェ〉は、名古屋市中村区を拠点として活動しているNPO法人です。「障がいをもつ方々を中心として、地域のさまざまな人たちが出会い交流する中で、お互いを認め合い、人とつながりあう喜びを感じられる社会づくりに寄与する」ことを目的として平成18年に設立しました。設立以来、さまざまな活動を展開し、現在は障がいをもつ方々の日中活動及び就労の場としての「多機能型事業所デイセンターひょうたんカフェ」の福祉サービス事業の運営を通じて地域の社会資源としての役割を担いつつ、「障がいのある方々の力を社会に生かし、発信していく」という活動ミッションの遂行を目指して活動を行っています。