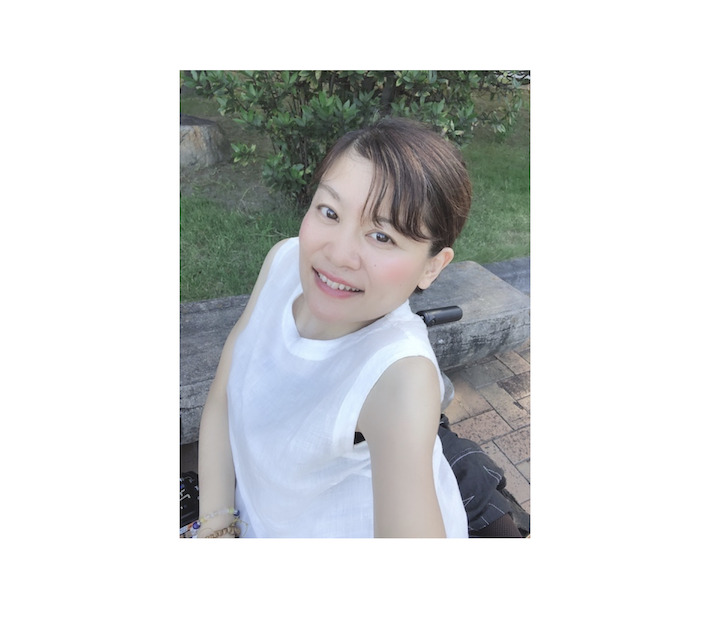踊ること、自分の身体のこと、それを誰かに見せること、その逡巡。キム・ウォニョンさん×森田かずよさん 森田かずよのクリエイションノート vol.06
- トップ
- 森田かずよのクリエイションノート
- 踊ること、自分の身体のこと、それを誰かに見せること、その逡巡。キム・ウォニョンさん×森田かずよさん
「身体は変えられないが社会は変えられる」
著作『希望ではなく欲望-閉じ込められていた世界を飛び出す』でそう語るのは、ダンサーで、作家や弁護士としても活動するキム・ウォニョンさん。
「やっぱりダンサーとしての私たちは『自分の身体で何ができるのか』っていうことを考えていくじゃないですか」
キム・ウォニョンさんの言葉を受けてそう話すのは、〈こここ〉の連載「森田かずよのクリエイションノート」を担当しているダンサーの森田かずよさん。
韓国と日本で、踊ることを軸に表現活動を行っているお二人。キム・ウォニョンさんが考える「いいダンサー」とはなにか。自身の身体を他者に見せることへの逡巡や「美しさ」へのまなざし。踊ることを真ん中に据えて、さまざまなテーマを語っていただきました。
いつからダンサーを志したのか?
森田かずよさん(以下、かずよ):ウォニョンさんとは、ダンスがきっかけで交流がはじまりましたよね。2018年には、まず日本財団主催の「サマースクール2018」で共に参加者として、そのあとも2回ほど韓国でお会いする機会がありました。
今回、お話するにあたって、3冊の著書を拝読しましたが、どれも素晴らしかったです。
ダンサーでありながら、哲学や映画、小説から引用して、自分の身体と身の回りで起こっていることをこれだけ造詣深く表現できる方というのは、なかなかいないと思います。私も、日々踊りながら感じたこと・考えていることを言葉にする難しさを実感しているからこそ驚きました。

かずよ:ウォニョンさんの著書『希望ではなく欲望-閉じ込められていた世界を飛び出す』の日本語版序文で、2021年秋に韓国最大の芸術大学(韓国芸術総合学校舞踊院)を受験したと書かれていましたよね。
私も18歳のときに芸術大学を志したのですが、障害があることを理由に入試を受けられなかった過去があって。今も日本の大学、とくに芸術を専門とする大学はまだ、障害のある人へ開かれていないように思います。
ウォニョンさんはなぜ芸術大学の扉を叩こうと思ったんですか?
キム・ウォニョンさん(以下、ウォニョン):38歳のとき、より真剣に、いろんな人とダンス創作をやってみたいと思うようになったんです。領域を限定せずより多くの人と協働してみたいなと。

ウォニョン:かずよさんも話していたように、韓国の芸術大学でも「障害者」の学生がなかなか受け入れてもらえない現状がまだまだあります。その問題へのアプローチとして挑戦した部分もあるんです。結果は落ちてしまいましたが。
あとは、振付や演出というまだ自分が学んだことのない分野の勉強をしてみたいという考えもありましたね。
かずよ:私の経験則だと、私たちのように障害のある人が振付や演出を学びたい場合、とにかく作品を作って実践を繰り返すしか方法がないように感じています。「ダンサー」として活動していく道はまだありますが、専門的に学べる大学へ行けないとなると、体系立った理論や方法論を学ぶ機会が限られてしまいますよね。
ウォニョン:かずよさんはこれまでどのように学んできたのですか?
かずよ:先ほどお話しましたが、18歳の時に芸術大学の入試を受けさせてもらえなかった経験もあり、演劇やダンスなどの実践を学ぶ大学を再度受験する勇気は私にはありませんでした。でも同じ時期にミュージカルスクールでジャズダンスやバレエのレッスンを受けはじめていて。近年、障害のある人がダンスを学ぶ場は増えていますが、その当時は、スクールには私以外に障害のある人はいませんでした。幸運なことに私を受け入れてくれたんです。なので少しずつ、自分の学びたい場所に行き、交渉して、自分の存在を受け入れてもらう。そういったことの繰り返しでしたね。
2019年から2021年までは、神戸大学の人間発達環境学研究科の修士課程で、障害のある人の表現や踊りについて研究していました。ただウォニョンさんの出身校であるソウル大学と同じく、芸術大学ではありません。
今年4月からは1年間、大阪大学の人文学研究科の研究生として哲学を学ぼうと思っています。自分の身体を語るために、哲学の知識が必要だと考えるようになって。進路を決めるにあたっては、ウォニョンさんの本をとても参考にしたんです。
ウォニョンさんはいつからダンサーを志していたんですか?
ウォニョン:自分の身体経験と社会との関係性を表現したいという考えは幼い頃から持っていました。
まずは台詞のある伝統的な演劇から入って、その後、ダンスを始めていきました。今思えば、なにかを演じることよりも身体で表現することに興味があったのですが、当時はそれをダンスと呼ぶことを知らなくて。ダンスや演劇などの特定のジャンルで表現するクリエイターとして生きたいと思っていた期間も長かったです。
ですが、20代頃の私がそれを韓国社会で実現させるのは難しかったように思います。ソウル大学に入学した2002年頃は障害者人権運動が重要なイシューとして注目されている時期でした。
当時の自分は、自身の身体経験を探求したり表現したりする活動では、「障害者である自分の責任を果たせないのではないか」と思っていたんです。社会から要求されるある種の役割があって、それに応えなければならないというプレッシャーが常にありました。
障害者のための制度や法律がほぼ皆無だった時代の韓国社会で(中略)障害者は人々から希望を持てと言われ、「希望のアイコン」のように語られたりもしました。けれど、一個人として持っている欲望を語ることはできませんでした。
『希望ではなく欲望: 閉じ込められていた世界を飛び出す』p5よりウォニョン:大学時代は「障害者人権連帯事業チーム」というサークルに所属していました。障害のある学生が教育を受ける権利を行使して適切な支援が受けられるよう、一人デモや署名活動などを通じて大学に呼びかけていたんです。支援センターの設置や車椅子リフトつきのシャトルバスの運行といった要望を一つずつ実現させていきました。
わたしは夢や希望より、今目の前にある階段や段差を取り除くことが必要だった。そのころ社会に飛び出していった重度障害者たちと同じく、わたしには選択の余地がなかった。
『希望ではなく欲望: 閉じ込められていた世界を飛び出す』p152-153よりウォニョン:大学卒業後、関心のあった社会学などの基礎学問の研究ではなくロースクールに進んだのも、演劇や表現活動との関連性を維持しながら生計を立てるための選択だったわけです。両親が経済的に厳しい状況にあったため、わたしが生計を支える必要がありました。
現在の韓国は、以前よりも障害者がダンスや演劇での表現活動をしやすい社会になってきています。だからこそ、これからは自分の能力やエネルギーをそこに集中して、より多くの表現をしていきたいと思っています。
「いいダンサー」とは?

かずよ:ダンサーとしての私たちは「自分の身体で何ができるのか」を考えていくじゃないですか。「障害のある人のダンス」というジャンルがあるわけでもない。私はバレエやタップダンスも踊りますが、それはジャンルに特化したプロダンサーになるためではなく「自分の身体を知るための手段」として様々なジャンルの踊りを選択しているところがあって。
あるジャンルで表現されているものを、自分の身体を使ってどう表せるのか、よく考えるんです。だからこそ他のダンサーが自らの身体でなにを感じ考えて創作をしているのか、すごく興味があります。
ウォニョン:私の場合、まず自分の身体の動きの中でも、社会の規範や人々の視線のせいで日常では見せられなかった動きに注目するんです。たとえば、床を這って動くことや、脚を見せることなどです。すると、自分自身はもちろんのこと、ダンスをするほかの人たちにとっても予想外の動きの質感(クオリティー)を発見することがあるんです。そういうときに自分の中で感じられる新たな気持ちや感覚もあって。
最近は、自分の身体の中に抑えこんでいた動きや深いところにある感覚を探ること自体に注目するのではなく、むしろバレエのようにシステムがきちんと整っているダンスの技術を、自分の身体に合わせて訓練すべきではないかと考えたりもします。それが「いいダンサー」になるうえで、今のわたしに必要なプロセスではないかと思うので。
──ウォニョンさんにとっての「いいダンサー」とはどういうものなのでしょうか?
ウォニョン:難しい質問ですね(笑)。
現時点の私が考える「いいダンサー」は、別の世界の他者とつながるために自分の身体をいつでも変形したり拡張したりできる人なのではないかと思います。
前提として、他者や異なる世界とつながるには当然、自分の身体を理解しておく必要があるとは思います。自分の身体をよく探求し、表現し、それを通じて世界と向き合うのも大事です。
ですが完全な自分自身を目指すだけではなくて、より大きな世界とつながって自分の動きを拡張する、もしくは変奏する、それができるのが「いいダンサー」の条件なのではないかと。ダンスの「技術」を習得することも、「自分」自身という枠を超え、より大きな世界とつながるための訓練の一つだと思います。
自分の身体を理解しておくことや自分の身体と向き合うことは、私がこれまでやってきた作業だともいえます。ダンスを通じて異なる世界や他者とどうやってつながっていくのか。それが、私が今模索しているテーマです。

ウォニョン:だからこそ「相互主観性」に興味があります。これは哲学者のフッサールが唱えた概念で、一人ひとりが持つ主観を持ち寄って共有しながら大きな主観にしていく、という考え方です。たとえば現在の状況なら、かずよさんと私の主観的経験が、この対談を通してつながっていますよね。私がかずよさんにただ共感するのでもなく、かずよさんが私と全く同じことを思っているのでもなく、こうして私たち二人が一緒にいるからこそ経験できる世界があると思うんです。
人と人とがつながる主観性のかたちがどこまで到達できるのか、ダンスを通してさまざまな方法で模索していきたい。以前、お互いに文章を書いて朗読し、相手がそれにあわせて踊るというワークショップをしたことがあります。今年の夏には、二人の人間の生み出す空間の変化をサウンドに変換してくれる服を着て、その音をお互いにイヤフォンで聞きながら一緒に動くというワークショップをやろうと思っています。(※注1)
注1:ワークショップを共にするメディアアーティストのソン・イェスルさんの作品リンクはこちら
こうした作業を通じて、「日本」在住の「障害者」、「韓国」在住の「非障害者」などといった属性だけでは表せない、これまで経験したことのない形での身体との出会いや主観の相互共有が経験できると思っています。自分以外の身体と自分が触れたときに生まれる新しい感覚を探し求めていくこと。これが、私が「いいダンサー」になるために必要だと思う作業の一例です。
かずよ:他者と踊るときに、なにを共通言語としていくかはすごく難しいですよね。あるジャンルのダンスなのか、ジャンルじゃないものなのか。私とウォニョンさんが踊るときは、なにがいいんでしょうね。
ウォニョン:そうですね、少なくともジャンルの問題ではないとは思います。
自分の身体を他者に見せること
かずよ:2022年8月のドイツのダンスフェスティバルTanzmesse(タンツメッセ)で、ウォニョンさんは「Becoming-dancer」というパフォーマンス作品を披露しましたよね。この作品にも、先程の考え方が色濃く反映されているかと思います。
ウォニョン:「Becoming-dancer」つまり「ダンサーになる」。現代舞踊やポストモダンダンスといった新しいジャンルのダンスが出てきています。でもそれは「障害者」の身体を反映していないダンスなのではないか。そんな考えから生まれた作品でした。
現代舞踊やポストモダン的なダンスを車椅子に乗っていてもできるものへ変換して、さらに、私と同い年の「非障害者」のダンサーができるダンスへ再変換して、一緒に踊ってみたんです。作中には即興的な表現もありましたし、車椅子を降りてフロアで動く場面は自分的にもチャレンジングで、学ぶことがたくさんありました。
かずよ:そう、ウォニョンさんが車椅子から降りているのを見てびっくりしました。
ウォニョン:恥ずかしかったです。
かずよ:それはどうしてですか?
ウォニョン:車椅子から降りた自分の身体を他者に見せることには抵抗がありました。演劇で舞台に上がるときも、車椅子から降りることだけは絶対にしませんでした。演出家が提案してきても断っていました。車椅子から降りて床を這ったり、自分の身体の輪郭や背の高さ、サイズ、かたちなどを他者に見せるのが嫌だったんです。
でもダンス公演を重ねるなかで徐々に、車椅子から降りることに挑戦しようと思えるようになりました。
かずよさんは踊るときに車椅子を使いますか?
かずよ:踊るときは車椅子を使わないです。私の場合は義足で似たようなことを感じたことがあります。
作品レパートリーのなかに、義足を外した踊りがあるんですけれど、それを初めて人前で披露するとき、とても怖かった。

かずよ:自分の身体の一部を取り去ってしまうという意味で、ウォニョンさんと、とても似ているシチュエーションだと思います。
私の場合は「恥ずかしい」よりも、外すことで「自分が障害者であることを周りに見せつけるだけになってしまうのではないか」という怖さが非常にありました。今思うと自分の姿そのものを「表現」だというところまで持っていく自信がなかったんです。

かずよ:ウォニョンさんは踊ることで、その「恥ずかしさ」とどう向き合っていったのですか?
ウォニョン:いまだに身体のかたちなどについては自信がなくて、恥ずかしくもあって、まだそこから抜け出せていません。
「Becoming-dancer」で、一緒に演じる「非障害者」の男性と並んで同じ動作をしながら床の上を移動する場面があるのですが、両者の身体の違いがとても露わになる瞬間なので、私自身、練習中も鏡を見ることに抵抗がありました。
自分が一番自分の身体に「この身体は変だ」と偏見の認識を持っている。自分のことなのに、障害への偏見があるんです、私は。
──「偏見がある」と自覚し、認めることはすごく難しいことのように思います。
ウォニョン:私の持っている偏見は、私が自分自身を抑圧してきた結果です。だから、何が問題なのか自分自身で考え、理解を深めたからこそ見えてきたんだと思います。まだそこから十分に自由になったわけではないですが。
最近は自分の感覚よりも観客の視線を信頼しています。昔は鏡に映った自分の姿を恥ずかしいと思いこむあまり、他の人はもっと酷い目で見ているんじゃないかと思っていましたが、最近は自分が思うのとは違うふうに観客は見てくれていると感じています。

かずよ:自分が日々見ている「身体」って、圧倒的に他者のもののほうが多くて、自分ではない身体を見ていますよね。だから自分で自分の身体を見ることは本当に難しいなって思うんです。
たとえば、私たちは鏡で自分の姿を確認しますけれど、鏡で見られる場所にも限りがある。自分の身体を認識する作業って、思っている以上にとても難しい。
私も「自分の身体」というものを、踊ることで把握していったと思うんですね。踊ることで、身体がどういうふうに動くのか、毎回発見があります。踊りながら自分自身を観察していくと、自分の予想を超えてくることもあって。踊りは、より自分の身体を知る術になりますね。
でも身体は日々変化しているし、まだまだ知らない部分が多くて。きっと、これからも踊りながら、知っていくと思います。
他者の身体が美しい、だから自分もそうだと信じられる
かずよ:ウォニョンさんの著書の中では、「障害者」のアイデンティティーや尊厳についても綴られていますよね。そこでのメッセージはとても強いものだったけど、今日のウォニョンさんの話からは、自分の身体に対する迷いが感じられるのが、ちょっと不思議な感じです。
ウォニョン:本で書いた私の意見はもちろん嘘ではないのですが、それは「最善の私」、ベストな私であり、最善の瞬間を集めたものですから。社会から「障害者」に与えられる烙印というのはやはり強大なので、本を書いていくうちにようやく、自分が「障害者」であると何気なく言えるようになり、人からそう思われることにも抵抗がなくなった、という認識はあります。ですが自分の身体を美学的に見ることはやっぱりちょっと難しくて、それは課題ですね、ここの部分はまだまだ。

かずよ:著作のなかでも「美しい」という言葉が何度か書かれていたし、「車椅子を1.8秒に1回のペースで漕ぐのがもっとも優雅だ」という表現もありましたよね。ウォニョンさんは美に対するこだわりのようなものが強いんだろうなと思っています。「美しさ」はウォニョンさんにとってどういうもので、どういうことを「美しい」と感じているんですか?
ウォニョン:私は弁護士としても働いていて、「障害者」の人権が尊重されることを重要視しています。ただ、ルールだけで障害者の人権を啓蒙するには限界があると思っていますし、「(自分には)障害があるけれども、“美しい”あの人と友達になることは可能なのか」というふうにもよく考えてしまいます。
著作のなかでは、「あなた」と一緒になりたい・つながりたいと思うことを「美しさ」と表現しました。セクシュアルな意味だけではなく、友情や親愛など、そこにはさまざまな意味があると思います。そういう感情を「美しさ」と表現して、広い意味で捉えていました。ですが、自分自身ステレオタイプな美しさに囚われている一面もあるので、これからも多様な美しさを見い出し、探っていきたいという気持ちもあります。
かずよさんにとって「美しさ」とは何ですか?
かずよ:私は「身体至上主義」みたいなところがあって、「自分の身体が美しい」とは、私は、今、大きな声では言えないですけれど、「人間の身体は美しい」と信じています。そして、いろんな人がそうあってほしいと思っています。自分が思ってるからですね。他者の身体を美しいと思うからこそ、自分の身体も美しいと信じられます。ただ、その美の基準は人それぞれで、多様であるべきだとも思います。
ウォニョン:そうですね。私もそう思います。
かずよ:ウォニョンさんが今後、どんなふうに踊っていくのか楽しみですね。どんな踊りをしていくんだろう。これから身体を使って、なにをしていきたいですか?

ウォニョン:先程の続きになりますが、障害の有無に関係なく他者とつながる方法を探求してみたいと思っています。他国のダンサーの作品を自分の身体で解釈してみたり。あとは、マイノリティの人たちと一緒にワークショップをやりたいなと。趣味としてですが、最近はクライミングもやってみたいと思っています。
個人的に思っているのはアジアの、たとえばインドネシアやモンゴルの「障害者アーティスト」との公演やワークショップを画策していて、かずよさんともぜひ一緒にできたらと思います。かずよさんは今後、どんなことをやっていくんですか?
かずよ:私は2年前から、大阪府茨木市で、障害のある人もない人含めた、市民参加のダンス公演のディレクションと振付を担当しています。今まで自分自身の振付はしていたけれど、他者へ振付することにも、挑戦しはじめました。障害の有無というよりも、様々な身体や考えを持つ人となにが出来るのか、協働のかたちを考えようとしているところです。ウォニョンさんの仰る、アジアの障害のある人とのワークショップもとても興味があります。やってみたい!いろんな人と踊っていきたいですね。

information
・『希望ではなく欲望-閉じ込められていた世界を飛び出す』(牧野美加訳、クオン、2022年)
・『サイボーグになる テクノロジーと障害、わたしたちの不完全さについて』 (牧野美加訳、岩波書店、2022年)
・『だれも私たちに「失格の烙印」を押すことはできない』(五十嵐真希訳、小学館、2022年)
Profile
![]()
-
キム・ウォニョン
ダンサー、作家
骨形成不全症により車椅子を使用する。社会学と法学を学び、弁護士として韓国の国家人権委員会などで働いた。現在はおもにダンサー、作家として活動している。これまでに「愛と友情における差別禁止及び権利救済に関する法律」、「人情闘争―芸術家編」、「Becoming-Dancer」などの公演でパフォーマーとしてステージに上がった。障害と身体、芸術、規範の関係に関心を持つ。著書に、日本でも翻訳出版された『希望ではなく欲望―閉じ込められていた世界を飛び出す』、『だれも私たちに「失格の烙印」を押すことはできない』、『サイボーグになる―テクノロジーと障害、わたしたちの不完全さについて』(キム・チョヨプとの共著)がある。
Profile
- ライター:遠藤ジョバンニ
-
1991年生まれ、ライター・エッセイスト。大学卒業後、社会福祉法人で支援員として勤務。その後、編集プロダクションのライター・業界新聞記者(農業)・企業広報職を経てフリーランスへ。好きな言葉は「いい塩梅」、最近気になっているテーマは「農福連携」。埼玉県在住。知的障害のある弟とともに育った「きょうだい児」でもある。
この記事の連載Series
連載:森田かずよのクリエイションノート
![]() vol. 122026.02.18義足をつけて踊り、歩けるわたしが電動車椅子を使う理由
vol. 122026.02.18義足をつけて踊り、歩けるわたしが電動車椅子を使う理由![]() vol. 112025.04.28「障害とダンス」の実践と研究をしてきたわたしの現在地
vol. 112025.04.28「障害とダンス」の実践と研究をしてきたわたしの現在地![]() vol. 102024.12.25テレビドラマ『パーセント』のスタッフ顔合わせで伝えたこと
vol. 102024.12.25テレビドラマ『パーセント』のスタッフ顔合わせで伝えたこと![]() vol. 092024.06.14滞在先で医療ケアが受けられる場所を探すこと
vol. 092024.06.14滞在先で医療ケアが受けられる場所を探すこと![]() vol. 082023.12.26「歩く」を解体して見えた景色
vol. 082023.12.26「歩く」を解体して見えた景色![]() vol. 072023.09.0416年活動してきた劇団が生み出した「障害演劇を作るための創作環境規約」にふれて
vol. 072023.09.0416年活動してきた劇団が生み出した「障害演劇を作るための創作環境規約」にふれて![]() vol. 052023.04.07わたしの義足とわたしの身体の関係
vol. 052023.04.07わたしの義足とわたしの身体の関係![]() vol. 042022.12.21「障害のあるアーティスト同士が出会う場」で私が聞きたかったこと
vol. 042022.12.21「障害のあるアーティスト同士が出会う場」で私が聞きたかったこと![]() vol. 032022.08.01障害のある俳優は「障害のある役」しか演じられないのか
vol. 032022.08.01障害のある俳優は「障害のある役」しか演じられないのか![]() vol. 022022.05.19私ではない身体が生み出したダンスを、私の身体はどのように解釈するのか
vol. 022022.05.19私ではない身体が生み出したダンスを、私の身体はどのように解釈するのか![]() vol. 012021.12.22ダンス創作を通して「わたし」と「あなた」が出会う
vol. 012021.12.22ダンス創作を通して「わたし」と「あなた」が出会う