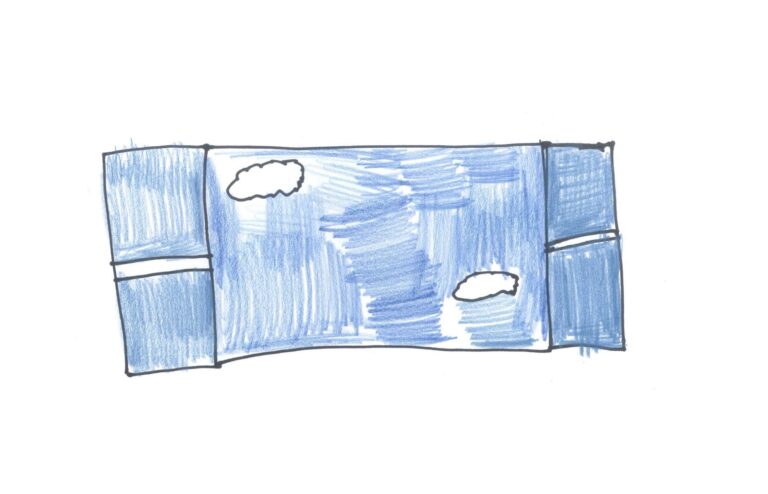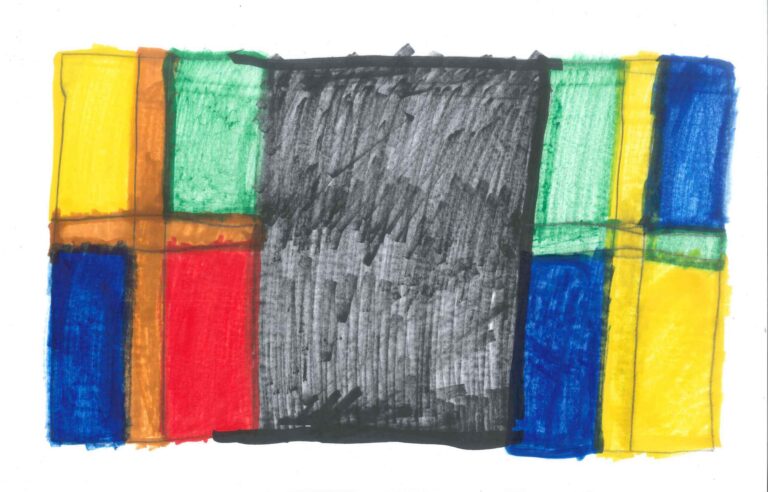「だれとも競争しなくていい場所」としての教室と美術館。オランダの大学院で感じたこと アムステルダムの窓から 〜アートを通して一人ひとりの物語に出会う旅〜|佐藤麻衣子(マイティ) vol.08
- トップ
- アムステルダムの窓から 〜アートを通して一人ひとりの物語に出会う旅〜|佐藤麻衣子(マイティ)
- 「だれとも競争しなくていい場所」としての教室と美術館。オランダの大学院で感じたこと
水戸芸術館現代美術センターの学芸員(教育普及担当)を経て、現在フリーランスのアートエデュケーターとして活動している、マイティこと佐藤麻衣子さん。2021年秋からオランダ・アムステルダムにわたり、美術館プログラムのリサーチなどを行っています。
この連載では、マイティさんが滞在中に感じた出来事や、訪ねた場所のエピソードなどを綴ってきました。今回のお話は、無事に引越し先の部屋も見つかり、大学院にも通い始めた、新しい生活での出来事です。
全8回にわたりお届けしてきた本連載も、いよいよ今回が最終回となります。連載は一旦終わりますが、マイティさんのアートを通した人々との出会いはこれからも続いていきます。(こここ編集部・岩中)
「アムステルダムの窓から」これまでの連載記事はこちらから
- Vol.1 美術の授業がきらいだったわたしが、アートの仕事をするようになるまで
- Vol.2 初めての海外生活で知った、美術館までの「距離」
- Vol. 3コロナ禍で失われた手触りを求めて。ロックダウンのオランダで、ワークショップを通してつながったもの
- Vol.4 アムステルダムでやっと手に入れた自分だけの自転車。運河をこえ、美術館やアトリエ目指して走らせる
- Vol.5 大きな収蔵庫と小さなギャラリー。ロッテルダムの2つのコレクション
- Vol.6 300台以上の緊急車両が、子どもや家族を乗せて動物園に向かう日。「キンダー・ベイスト・フェイスト」へ
- Vol.7 見つからない家とフェルメール作品の間で
新しい生活のはじまり
そよ風が吹いただけでも、どこか遠くに飛ばされそう。
わたしのメンタルは、極度の不安で綱わたりだった。春先から家探しをはじめて2ヶ月たつのに、一向に見つからない。「こんな思いをするくらいなら、日本に帰りたい」、帰国がちらつきはじめた。いっぽうで、わたしはアムステルダムの大学院を受験し、合格通知を手にしていた。「ミュージアムの勉強を海外でいつかしてみたい」、頭の片隅にずっとあった夢が、目と鼻の先で叶いそうだった。日本にもどり、落ち着いたころの自分を想像してみる。「あのとき、もう少しねばっていたら転居先が見つかって、大学院に行けたかもしれないのに」、頭をかかえている姿が脳裏をよぎる。目を閉じて、Y字路の前で迷う自分を想像した。はっきりとした根拠はないけれど、後悔してからでは遅い。わたしは、アパート探しを再開した。
考えられる策を出しつくし、これ以上成す術はないと思ったころ、幸運が舞いこんできた。家を貸したいという人から、メッセージが届いたのだ。「このラッキーを受けとめるために苦しんでたのかも」、としか表現できないほど、良心的な大家さんと出会い、ひと目見て「いいな」と思ったアパートを借りられることになった。「明日からは家を探さなくていいんだ」と実感すると、安堵と疲れが吹きだし、しばらくの間は人に会うのも、外へ出るのもしんどかった。そして、わたしは、オランダで5軒目の家に引っ越した。
9月からは、大学院に通う生活がはじまった。専攻はミュージアム&ヘリテージスタディーズで、同級生は18人。オランダ人が6割くらいで、他にはイタリア、ロシア、アメリカ、中国、インド出身の人がいる。日本人はわたし一人だけ。世代も多岐にわたり、数ヶ月前に大学を卒業した人から、社会人をしながら違うキャリアを目指す人までいる。なので、最初はだれが先生でだれが学生なのかわからなかった。「あのコロンビアの人、ほとんど授業に出てないなぁ」と、しばらく思っていたら、わたしたちの前で授業をはじめて驚いたことがある。
学校での一番のカルチャーショックは、エンドレスなディスカッションだ。先生が説明するたびに、天井に向けて人差し指を指す仕草が、どこからともなく視界に入ってくる。この合図は、発言したいという意思表示。「はい、マックス。次はイムケ、アリーチェね」と、先生は順番を示す。当てられた人が質問し、先生が回答すると、さらにその答えに対して質問したい人や意見を言いたい人が、こぞって指を立てる。まるで収穫期をむかえたアスパラガスのように、ニョキニョキと指が生えてくる。ときには、「えっ、そんなことまで言うの?!」と、耳を疑うような感情も要望も飛び交う。「このテキストを読んで、イライラしました」、「もっと早くこのトピックを習いたかったです」先生という存在に臆することなく、直球を投げかける。授業後に共有されたパワーポイントを見ると、スライドの最後までたどりついていない日がしばしば。それくらい、先生は一人ひとりの言葉に同じ熱量で応じている。先生は「教える人」というより、ディスカッションをまわす「ファシリテーター」と例えたほうが近いかもしれない。

どうしても追いつけないへだたり
いっぽうのわたしは、ひとけのない離れ小島から、キラキラした街をながめているようだ。大半の人が、ネイティブスピーカーではないはずなのに、英語をあやつっている。質問ひとつするにしても、当の質問から、なぜ自分は疑問に思うかまで、ペラペラペラ~と3文くらい、息つぎする間もなくつづける。日本の学校では、正反対のスタイルだった。「聞く」姿勢が基本だった。前を向いて先生の話を聞き、ノートを取っていれば、おのずとチャイムは鳴った。授業中にすすんで口をひらくのは、せいぜい一回あるかないか。それと同時に、人前で話すときは、周囲の反応が気になった。変なことを聞いていると思われたくないので、脳内で質問を吟味し、みずからゴーサインを出せたら、意を決して手をあげる。質問が終わると、過剰に研ぎ澄まされた自意識で疲れきっていた。だから、能動的に参加するだなんて、今まで受けてきた受け身のスタイルとは、方向性がちがいすぎる。それに、英語で意見を言うなんて、大勢の前でわざわざ間違いを披露しているようで、恥ずかしい。授業が終わるまで、なるべく目立たないようにしたい。それなのに、悲しいかな、机のならびは全員の顔が見えるコの字形……。発言できないわたしは、身の置きどころも隠しどころもなかった。
休憩時間になっても、授業が終わっても、クラスメイトの議論はどこまでもつづく。勝負がつかない卓球のラリーを永遠に見ているようで、気が遠くなる。「マイコももっと話しなよ。マイコの経験や日本のミュージアムについて知りたい」オランダでは小学校に入ったころから、話し合いをするのが日常で、発言しないと授業に参加していないと見なされるらしい。興味を持ってくれる気持ちはうれしいけど、ディスカッションに抵抗がない人に言われても、ハードルを乗り越えるための理由にはこれっぽっちもならない。英語で聞いて、理解して、追いつくのでいっぱいいっぱい。現実は、話さないんじゃなくて、話せない。質問したいと思ったら、話の展開が変わっているのが日常茶飯事。話さないからといって、なにも考えていないわけじゃない。できれば放っておいてほしい。無言の訴えが増えれば増えるほど、教室は居心地の悪い場所になっていく。
異なる文化のなかで、もがいていると、はるか昔に過ごした小学校の風景がよぎるようになった。とくに、小学1、2年生のときに同じクラスだったKくんの姿がクリアに浮かんできた。肥満症のKくんは、マラソン大会のたびに、どうしても最下位になってしまう。Kくんが校門からグラウンドに入ってくると、すでにゴールしているKくん以外の全員で、固唾をのんで見守った。それから、「がんばれー!」と、ありったけの声を出して、最後まで応援した。Kくんは、ときおり体操服の袖で涙をふきながら、みんなの前を通過し、ゴールテープを切る。わたしたちは拍手しながら、Kくんの頑張りと完走を祝福した。でも、Kくんは、みんなと同じように心の底から喜んでいたのだろうか? ほんとうは、どんなことを思っていたんだろう? 日本にいたときのわたしは、常に「みんな」側にいた。勉強した分に比例して成績は上がったし、日常生活に大きな困難をおぼえたことはなかった。それにひきかえ、今のわたしはどんなに時間をかけて努力を注いでも、まわりの人と同じようにはふるまえない、他の人たちに追いつけない。一緒に出発した同級生が、視界からどんどん遠ざかっていく。
だれとも比べられない場所
「怖がらずに質問してもいいんだ」忘れていた感覚を取り戻してくれたのは、クラスメイトのパシャとエマだった。丸一日あった歴史学の講義だったのに、「なんにも理解できなかった」と、自覚した瞬間、さめざめと泣いてしまった。帰り支度であわただしい教室で、10歳以上も年下のふたりが、目ざとくわたしを見つけると、そそくさと近づいてくる。理由を説明できなかったのに、ふたりは察して、交互に声をかけながら励ましてくれる。「わたしたちだって、授業を全部理解しているわけじゃないよ」、「わからなかったときは、クラスのグループチャットで聞いたらいいんだよ」新しい環境に慣れるのに精一杯で、だれかにたずねたり、助けを求めたりする選択肢が、すっかり抜け落ちていた。わたしはチューターの存在を思い出し、すぐさま面談の約束をとりつけた。
チューターとは、学校生活全般について相談できる先生で、学生一人ひとりに割りふられている。「あなたはずっと、競争社会のなかにいたのね」わたしが周囲に助けを求められなかった理由を、マニュエラはズバリ言い当てた。「この人ならわかってくれるかも」わらにもすがる思いで、今の気持ちをひとつ残らず吐き出した。ディスカッション中心の授業に戸惑っていること、先生やクラスメイトから比べられているような気がすること、大勢の前で英語を話すのが恥ずかしいこと。すると、マニュエラは「だれもあなたの発言をジャッジしないわ」と、断言した。今まで、教室は格闘技のリングのような場--完璧に仕上げてきたスキルを使って相手と戦い、観客からやじや声援を飛ばされる--だと思い込んでいた。でも、どうやら教室は、面前にさらされるわけでも、優劣をつけられるでもない安全な領域らしい。
この考えをダメ押しで裏づけてくれたのは、カリキュラムの責任者の先生、チラだった。わたしは、チラにも同様にアドバイスを求めた。チラは、「クラスはセーフスペースよ。何を話しても大丈夫。英語を苦手だと思う気持ちはわかる。でも、練習するのが語学上達の一番の近道なのよ」と、芯のとおった口調で答えた。「あなたはこれから一人のプロフェッショナルとして、職場で意見を求められるようになる。自分のアイデアを話さないといけなくなるのよ。そのときのために、授業で練習すればいい」

美術館がわたしにとって居心地のいい理由
オランダに来る前に、日本の美術館で体験した印象的なできごとがある。ひとつの作品を7人くらいで会話をしながら、時間をかけて見るプログラムを行っていたときのことだ。目の前の作品は、現代アーティストによって描かれた作品で、古典的な絵画のモチーフや技法が引用されている。「話したい人はどうぞ」、鑑賞がはじまったとたん、口火を切った人がいた。その人は、えんえんと話しつづけ、元ネタである古典絵画の知識をひとしきり披露した。まわりで聞いている人は、あいづちを打ったり、口をはさむ間もない。完全に独壇場だった。話はようやく終わったが、他の人たちは固まっている。全員がうつむき、黙ったままだ。わたしはいつもなら、作品の第一印象や直感を伝え、他の人が話しやすい雰囲気をつくる。それなのに、声がのどをつかえてしまった。展示パネルや美術の本にあるような、客観的な情報だけをシャワーのように浴びていると、自分の知識不足を実感させられる。「先生」みたいな人が目のまえにいると、個人的な感情や経験を話すなんて、ちっぽけで他愛もないと一蹴されそうで、ひるんでしまう。その後、会話はぽつぽつと芽生えたけど、深まらなかった。歯切れが悪いまま、わたしたちは作品をあとにした。
鑑賞をふりかえる時間になると、ふたたび、例の最初の人が切り出した。「実は、『わからない』と言うのが怖かったんです」その人は、意外な言葉を口にした。予習のため、前もって作品を見ていたけど、どうしてもあの作品だけは、何の印象も浮かんでこなかった。知っている物事を最初に話してしまえば、自分の不足している部分をだれにも気づかれず、やり過ごせる。知識を盾に、わからない自分を守ろうとした。「でも、いざ教科書的な話題を広げてしまうと、他の人がしゃべりづらくなるのがわかりました。みなさんと話しながら見られるせっかくの機会だったのに」と、同じ時間を過ごした人たちに、申し訳なさそうな表情をした。
だれかと一緒に作品を見るとき、「わからない」と伝えるだけでも、会話がはじまることがある。「よくわからないんだけど、あなたはどう感じた?」とたずねると、相手の言葉が基準となって、「なるほど」と同意できたり、「そうは思わないなぁ」と、真逆の考えが生まれたりする。他の人の感想が引き金になって、自分の感覚をキャッチできるのだ。「わからなさ」を共有すると、となりにいる人と、新たなかかわり合いがうまれてくる。だから、「美術の教養がないから」、「見ても理解できないから」と、作品鑑賞に引け目を感じる人たちには、「わからないこともシェアしてください」と、励まし伴走してきた。わたしは、美術館は安心できる空間だと、相手に伝えたかったのかもしれない。美術と出会い、「生きるのが楽しい」と思えた高校生のころから、ゆっくりと時間をかけて醸成されてきたものだった。

12月も中盤になると、学校はクリスマス休暇をむかえる。明日からは、毎日の課題からしばらく解放される。「打ち上げに行こう!」と、ミキが提案し、わたしたちは、いそいそと自転車を走らせた。暖房とおしゃべりの熱気で満ちたカフェ。ビールグラスからは、汗が吹き出している。大きなテーブルをかこみ、今年あった一番よかったできごとを、順々に答えはじめる。耳をそばだて、テーブルを見渡すと、急に一人ひとりのしぐさや表情、あいづちが、スローモーションのように目に映りはじめた。「今、全員の話が手にとるようにわかるかも」いつもと違う感触に気をとられていると、自分の話す番がやってきた。(みんなと出会えたこと、今日までなんとかやってこれたことは、すでに挙がっているトピックだしな……あ、そうだ!)「あなたたちのおかげで、英語が上達したよ」一番奥に座るパシャまで届くように大きな声で伝えると、「マイコ、泣くなよー」、「よかった」と、みんなが笑う。正面のディエルクが、わたしの肘をつかみ、ゆらした。わたしだけが取り残され、先に進んでいくように思えたクラスメイトたちは、ずっと隣にいた。
オランダらしい大きな窓からは、街のクリスマスイルミネーションがよく見える。テーブルに置かれたろうそくの灯は、クラスメイトをあたたかく照らしている。夜が一番長い日が近づいている。わたしは、やわらかな椅子に身をあずけた。

Profile
![]()
-
佐藤麻衣子(マイティ)
アートエデュケーター
水戸芸術館現代美術センターで教育普及担当の学芸員(アートエデュケーター)を経て、2021年よりフリーランスで活動。普段あまり美術館に来ない人、なかなか来られない人たちに向けたプログラムを企画。さまざまな人たちとの作品鑑賞の場づくり、学校見学の受け入れやワークショップなどを行ってきた。2021年11月からオランダで、障害のある人に向けたアートプログラムの調査を行っている。あだ名はマイティ。好きなものは星野源とビール。
写真:スズキアサコ
この記事の連載Series
連載:アムステルダムの窓から 〜アートを通して一人ひとりの物語に出会う旅〜|佐藤麻衣子(マイティ)
![]() vol. 072023.05.26見つからない家とフェルメール作品の間で
vol. 072023.05.26見つからない家とフェルメール作品の間で![]() vol. 062023.05.02300台以上の緊急車両が、子どもや家族を乗せて動物園に向かう日。「キンダー・ベイスト・フェイスト」へ
vol. 062023.05.02300台以上の緊急車両が、子どもや家族を乗せて動物園に向かう日。「キンダー・ベイスト・フェイスト」へ![]() vol. 052023.02.06大きな収蔵庫と小さなギャラリー。ロッテルダムの2つのコレクション
vol. 052023.02.06大きな収蔵庫と小さなギャラリー。ロッテルダムの2つのコレクション![]() vol. 042022.10.31アムステルダムでやっと手に入れた自分だけの自転車。運河をこえ、美術館やアトリエ目指して走らせる
vol. 042022.10.31アムステルダムでやっと手に入れた自分だけの自転車。運河をこえ、美術館やアトリエ目指して走らせる![]() vol. 032022.08.05コロナ禍で失われた手触りを求めて。ロックダウンのオランダで、ワークショップを通してつながったもの
vol. 032022.08.05コロナ禍で失われた手触りを求めて。ロックダウンのオランダで、ワークショップを通してつながったもの![]() vol. 022022.06.01初めての海外生活で知った、美術館までの「距離」
vol. 022022.06.01初めての海外生活で知った、美術館までの「距離」![]() vol. 012022.04.08美術の授業がきらいだったわたしが、アートの仕事をするようになるまで
vol. 012022.04.08美術の授業がきらいだったわたしが、アートの仕事をするようになるまで