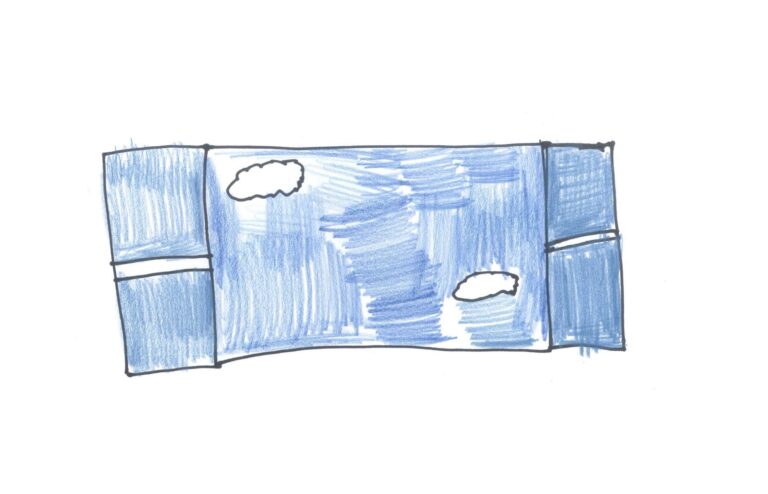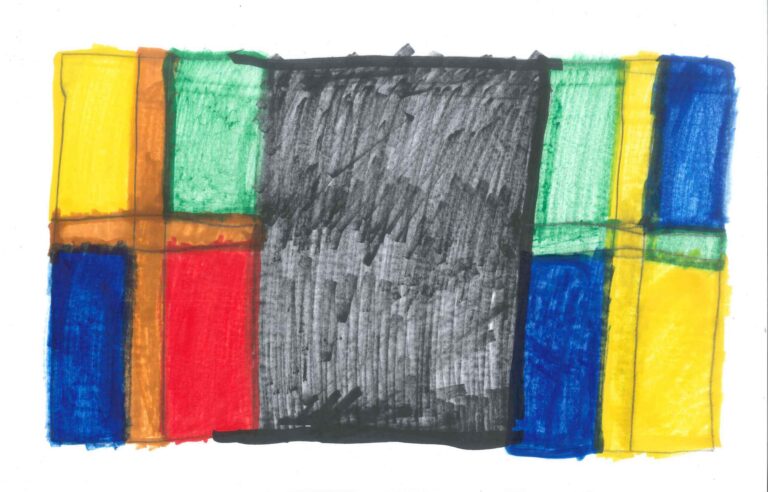コロナ禍で失われた手触りを求めて。ロックダウンのオランダで、ワークショップを通してつながったもの アムステルダムの窓から 〜アートを通して一人ひとりの物語に出会う旅〜|佐藤麻衣子(マイティ) vol.03
- トップ
- アムステルダムの窓から 〜アートを通して一人ひとりの物語に出会う旅〜|佐藤麻衣子(マイティ)
- コロナ禍で失われた手触りを求めて。ロックダウンのオランダで、ワークショップを通してつながったもの
水戸芸術館現代美術センターの学芸員(教育普及担当)を経て、現在フリーランスのアートエデュケーターとして活動している、マイティこと佐藤麻衣子さん。2021年秋からオランダ・アムステルダムにわたり、障害のある人に向けた美術のプログラムのリサーチなどを行っています。
この連載では、マイティさんがアムステルダム滞在中にたずねた施設やアトリエでの、さまざまなアート活動の中で見たこと、感じたこと、そして、そこに関わる人たちから聞いたストーリーなどを綴っていきます。
第3回となる今回は、ロックダウン中のオランダで、初めてワークショップを実施するまでのお話。コロナ禍の美術館で失われてしまったさまざまな感覚を取り戻すべく、試行錯誤を重ねた日々。マイティさんがワークショップを通してオランダで出会ったものとは、どんなものだったのでしょうか。(こここ編集部・岩中)
世界の美術館から消えてしまったもの
世界中の美術館が眠っている。
2020年3月、監視員も警備員も清掃員も姿を消した。SNSのグループができ、全国の学芸員たちが休館情報やオンラインプログラムをシェアし始めた。アメリカやヨーロッパではスタッフが解雇されているらしい。白く光る画面をただただ眺めていた。
オランダに来る前の日本でのこと。勤務していた美術館はコロナ禍で扉を閉めた。足を運んでもらうため、あの手この手でプログラムを考えていたのに、もうだれも来られなくなってしまった。「美術ができることを伝えなければ」休館対応の慌ただしいオフィスで、静かな使命感が芽生えていた。
仕事でもプライベートでもオンラインでのやりとりが始まる。外出する必要はないし、不安な気持ちを共有できる安心感は得られたけど、なにか足りないと引っかかっていた。
疑問の答えは突然、ポストにもたらされた。友達から届いた1通の手紙。開封するのが待ちどおしい。部屋に戻り封を開けると、友だちの子どもが貼ったシールの合間から友だちの文字が現れる。紙に触れながら、今ここにはない温度が伝わってきた。パソコンの画面越しでは、目の前にいる人のにおいや感触が欠けていた。マスクを外せず、できる限りの接触を避けるうちに、自分の感覚に頼ることを忘れていたのかもしれない。
カトラリーケースに入っている木のスプーンを思い出し、木工作家の髙山英樹さんに電話した。見えないウイルスに疑心暗鬼になる世界で、美術の可能性を手探りする日々が始まった。
手元にある”手触り”。いろんな場所から届く”気配”
わたしが使っている木のスプーンは、手づくりだ。
外に出られない日がやってくるなんて、だれも想像していなかったころに企画したワークショップでつくった。髙山さんが準備してくれたスプーン。といっても、削り出したばかりの無骨な木片なので、“スプーンらしき”形だ。これだ!と選んだ1本を手に取り、持ちやすさを探る。親指を大胆に動かし、荒いやすりで形を決めていく。白い粉がほうぼうに舞うころには、木の香りが天井まで漂っている。
ぬらした布で全体を拭きとり、表面を入念に指でなぞる。食べるときを想像する。口当たりがいいと思うところまで、細かいやすりで表面をなめらかにしていく。終わらせるタイミングは、自分の五感だけが知っている。オリーブオイルを塗り、布で磨きあげると、身体になじんだスプーンができあがる。他の人にはいびつに見えるかもしれないけど、自分だけのかたち。手に入れたころには空の色が変わっていた。
オンラインではできないことがある。手紙とスプーンが気づかせてくれた手応えに賭けてみよう。“スプーンらしき”木片とやすり、髙山さんからのメッセージを同封し、美術館のネットショップで販売した。
もうひとつ、やってみたことがある。
ワークショップユニット「BOB ho-ho」との企画は、予定していたワークショップの延期連絡がきっかけだった。ポストカード作品を郵便で集め、つなげて展示するプログラムを考えたという。そのころの美術館は、参加者を集めるワークショップはできなかったけど、人数制限をしながら再オープンしていた。
家で作品をつくって送ったら、展示に参加でき、それぞれのタイミングで見に行ける。今の状況にぴったりのアイデアだった。試作のカードを見せてもらうと、白い厚紙に赤と黒の模様が印刷されている。山が3つ連なった柄、L字の太い線、円や三角形、長方形が組み合わさった図柄など、7種類。ふちまでいっぱいに印刷された模様は、他のカードの模様とつながる。すべてのカードをつなげれば、1枚の大きな絵になる。
募集を始め、作品が舞い戻ってくる頃には季節がひとつ進んでいた。プリントされた模様を活用した絵もあれば、全く気に留めていない絵もあった。「7時に起こしてください」とメモが貼られたカードには「孫娘が書いた置き手紙が捨てられなくて」と、添えてあった。裏面の消印で、新しい地名を毎日憶えた。
すべての作品が壁の上でつながったとき、おのおのの場所で過ごす人たちの気配が伝わってきた。

ブルーな季節。オランダで初めてのワークショップ
2022年は、オランダのロックダウンとともに迎えた。年越しだけは若者がノーマスクでABBAを熱唱し、次から次へとシャンパンで乾杯している。築130年のアパートの窓から聞こえてくるムードとは対照的に、わたしは予期せぬ心配事と過ごす新年だった。研修先である「フィフス・シーズン」のディレクター、エスターがアートセラピーウォークを企画していて、ポストカードのワークショップをやってほしいと誘われていた。トラムの倉庫を改修した歩行者通路で、作品展示やワークショップを歩きながら楽しめるイベントだ。「北半球の人が最も落ち込みやすいといわれている1月中旬の1週間を、ポジティブにしたいの」とエスターは構想を語った。
でもいつの間にか、落ち込みやすい時期の一員にわたしも加わっていた。前年に日本から速達で送ってもらったカードは1ヶ月経っても届かない。展示する壁は発注と違う姿に仕上がっていた。
そして当日。わたしは一人で現場にいた。手伝ってくれるはずのスタッフは一向に来ない。カードと画材が置かれたテーブルの横に立ち、数秒で身の危険を感じた。屋根はあるけど入口から風が入ってくる。風邪をひきそうだし、忙しさのあまり新種の単語“オミクロン”を忘れていた。投げ出して帰りたくなった。
ロックダウン中といっても、近くのマーケットやスーパーは開いているので人通りはある。歩みを止め、青い壁の前でカードを眺めている人がいる。「もうどうにでもなれ」やけくそになりながら、手当たり次第に声をかけた。「参加してみませんか?」とワークショップの紹介をする。カードがつながっていることに気づくと「ドミノみたいね」「ラブリー!」と反応してくれる。
完成させると、描いたばかりの絵や言葉を説明してくれる。「ここなら模様がつながるかしら?」「このカードの隣に貼りたいわ」、日を追うごとに大きな絵は表情を変え、青い面が減っていく。

カードを通して生まれたことば
オランダに来て2ヶ月。人に会うのははばかられ、知り合いが増える気配はない。街を歩いている人はこんなにいるのに。アムステルダムで普通に生活する人と話してみたかった。「もしかして今、願いがかなってる?」ワークショップを武器に、歩いている人とやりとりできるのか。作品の前で誰かの話を聞くことが好きだった日本での日々を懐かしむ。このまま道行く人に話しかけてみよう。
壁にはひときわ目立つカードがあった。エメラルドグリーン色のふくらんだハートが、カードいっぱいに貼ってある。そのカードの上に、迷わずつなげた女性がいた。「愛の力は大きい」緑色の文字で書いてある。「どんな意味なの?」とたずねると、「姉を10年前にがんで亡くしたの。残された姪っ子が心配だったけど、愛情をいっぱい注いだらすごくいい子に育った」通りがかりの人から、家族の生き死にの話を聞くなんて思ってもみなかった。彼女の深い部分に触れたような気がして、いつの間にか涙がこぼれていた。「すごくいい言葉ですね」と、彼女の腕をさすりながら伝えると、「あなたはもう知っているでしょ? 愛の力を知っているから、これをしているのよ」
日曜の夕方は気が早い。歩く人は途絶え、外はすっかり暗くなっていた。頭の上ではイルミネーションが知らぬ間に光っていた。
青い壁の上で蛇行するカードは、オランダに暮らす人によって1枚の大きな絵になった。片付けに来たスタッフのアーシアが「来週はロックダウンが明けるみたいだよ」とわたしに告げた。

Profile
![]()
-
佐藤麻衣子(マイティ)
アートエデュケーター
水戸芸術館現代美術センターで教育普及担当の学芸員(アートエデュケーター)を経て、2021年よりフリーランスで活動。普段あまり美術館に来ない人、なかなか来られない人たちに向けたプログラムを企画。さまざまな人たちとの作品鑑賞の場づくり、学校見学の受け入れやワークショップなどを行ってきた。2021年11月からオランダで、障害のある人に向けたアートプログラムの調査を行っている。あだ名はマイティ。好きなものは星野源とビール。
写真:スズキアサコ
この記事の連載Series
連載:アムステルダムの窓から 〜アートを通して一人ひとりの物語に出会う旅〜|佐藤麻衣子(マイティ)
![]() vol. 082024.01.22「だれとも競争しなくていい場所」としての教室と美術館。オランダの大学院で感じたこと
vol. 082024.01.22「だれとも競争しなくていい場所」としての教室と美術館。オランダの大学院で感じたこと![]() vol. 072023.05.26見つからない家とフェルメール作品の間で
vol. 072023.05.26見つからない家とフェルメール作品の間で![]() vol. 062023.05.02300台以上の緊急車両が、子どもや家族を乗せて動物園に向かう日。「キンダー・ベイスト・フェイスト」へ
vol. 062023.05.02300台以上の緊急車両が、子どもや家族を乗せて動物園に向かう日。「キンダー・ベイスト・フェイスト」へ![]() vol. 052023.02.06大きな収蔵庫と小さなギャラリー。ロッテルダムの2つのコレクション
vol. 052023.02.06大きな収蔵庫と小さなギャラリー。ロッテルダムの2つのコレクション![]() vol. 042022.10.31アムステルダムでやっと手に入れた自分だけの自転車。運河をこえ、美術館やアトリエ目指して走らせる
vol. 042022.10.31アムステルダムでやっと手に入れた自分だけの自転車。運河をこえ、美術館やアトリエ目指して走らせる![]() vol. 022022.06.01初めての海外生活で知った、美術館までの「距離」
vol. 022022.06.01初めての海外生活で知った、美術館までの「距離」![]() vol. 012022.04.08美術の授業がきらいだったわたしが、アートの仕事をするようになるまで
vol. 012022.04.08美術の授業がきらいだったわたしが、アートの仕事をするようになるまで