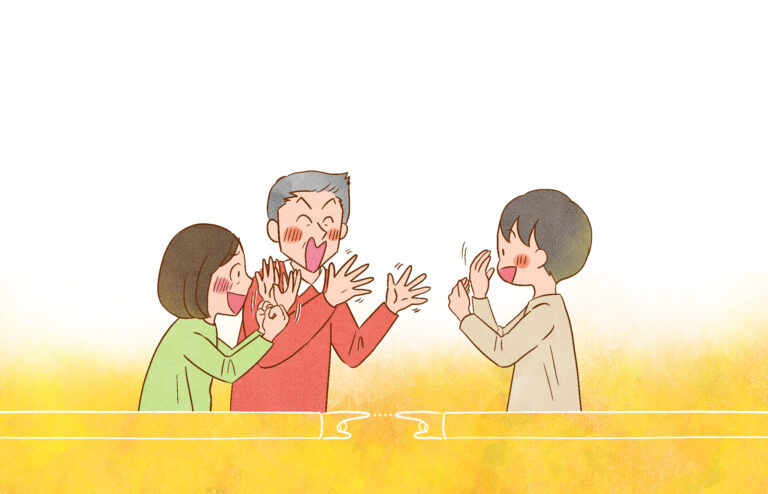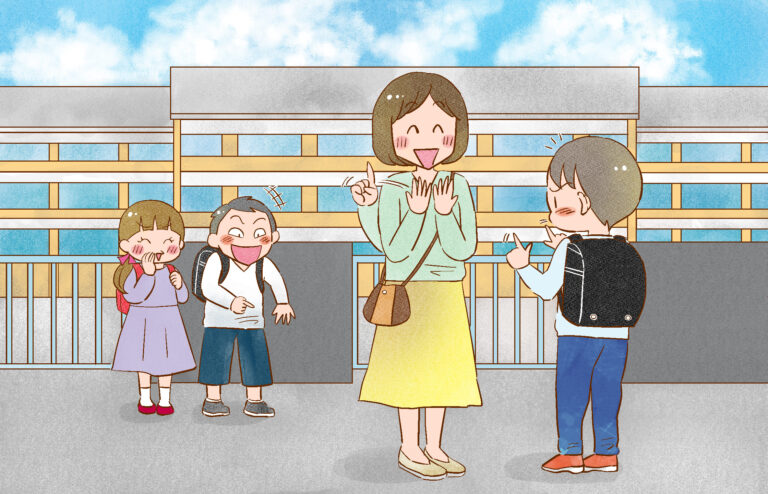わかりあいたいのに、うまくいかない。話したいと思いながら、機会がやってこない。身近だからこそ、上手に会話ができない。そんな人はいますか。
連載「いま話したい人がいる」は、ライター/エッセイストの五十嵐大さんによるエッセイです。
ぼくの両親は耳が聴こえない。父親は後天的に聴力を失い、母は生まれつき聴こえなかった。そんなふたりから生まれた子どもは、「コーダ(CODA、Children of Deaf Adults)」と呼ばれる。思春期に差し掛かるころ、ぼくは周囲の心無い言葉に傷つき、自分の環境に苛立ち、手話を使うことをやめた。それはつまり、親との共通言語を手放すということだった。30代になり、ぼくはそのことを後悔する。聴こえない両親とちゃんと向き合いたい。話したい。そうして再び、ぼくは手話を学び直そうとオンライン講座の戸を叩いた。>第1回「耳の聴こえない両親と、もう一度“話したい”」
コーダが「手話を勉強し直す」とはどういうことか
4月の第1週、いよいよ初回の手話講座を迎えた。
フリーランスになって数年が経つ。もはや曜日感覚なんてなくて、今日が平日なのか週末なのか、それとも祝日なのか、いちいち確認しないとわからないような人間になってしまった。季節の感覚すら薄れている。春夏があっという間に過ぎ、気づけば年末が目前まで迫っていた、なんてこともザラだ。
だから、4月に新しいことをはじめるというだけでワクワクしてしまう。4月は出会いの季節。今年、ぼくの生活に顔を覗かせたのは「手話」だ。これから週に1回、オンラインで手話を学んでいくことになる。
振り返ってみれば、大人になってから何度か手話を学習するチャンスは訪れていた。友人に誘われてなんとなく参加してみた社会人向けの手話サークル、突然思い立ち、書店で購入した手話の教本。でも、サークルは勉強というよりも、「趣味の延長」に近くてあまり本気度が感じられなかったし、教本だけでは「動きのある言語」である手話を理解することが容易ではなかった。なにより、ぼく自身に切実な想いがなかったのだ。なにがなんでも手話を身につけてやる、という想いが。
ただ、いまは違う。「聴こえない両親と、手話できちんと話したい」という明確な目標ができた。いまさら「手話を一から勉強します」と宣言するのは少し恥ずかしさもあったけれど、自分に発破をかけるつもりでツイートしてみた。すると何人もの人から応援され、励まされた。そのなかには、ぼくと同じコーダもいた。
コーダが手話を勉強し直す。それがどんな意味を持つのか。
「手話ができない、あまり上手ではない」と説明するとき、いつも小さな針で胸を突かれているような痛みを感じた。だって、それはつまり、「親子間でのコミュニケーションを放棄してきた」こととほぼ同義だったからだ。
誰からも責められたことはなかったけれど、それでも、ふとした瞬間に、誰かに責められているような気持ちがした。
あなたが手話を覚えなかったことで、両親は苦労したんじゃないの?
そんな風に責められたとしても、言い訳なんてできない。事実、そうだったと思うから。
でも、その過去も踏まえた上で、未来に目を向けている。
「手話を一から勉強します」という宣言は、「ぼくは両親が大切にしていた言語を放り投げてきました」との懺悔でもあり、「だからこそ、それを取り戻して、あらためて彼らと話したいと思っているんです」という希望でもある。ツイッター上でメッセージをくれたコーダたちには、それが伝わっていた。「自分のペースでゆっくりね。幼い頃に体に染み付いた手話は、きっとすぐに思い出せるよ」。その言葉がとてもうれしかった。
日本語は一切禁止……それで大丈夫?
ぼくが受講する手話講座では、ろう者が講師を務める。ここを選んだのも、それが決め手だった。常に手話を使って生きるろう者の元でなら、生きた手話が学べると思ったのだ。
時間になり、オンライン会議用のURLをクリックする。ぼく以外の参加者はもうひとり。手話を学ぶのはほぼ初めてという、Kさんだ。画面越し、お互いに会釈する。Kさんはやや緊張した面持ちだったが、それはぼくも同じだろう。でも、手話には顔の動きも重要である。滑らかに動かせるよう両手で大げさに顔をほぐし、時間になるのを待った。
講師は柔らかい笑顔が印象的な、とてもやさしそうな人だ。
初回はどんな内容なんだろう。緊張と期待とがないまぜになった状態で講師を見つめていると、最初に講座の注意点が説明された。それを見て、瞬間、固まってしまう。
――講座のなかでは、日本語の使用を禁止します。

手話を使って、手話を学ぶ。その際、音声日本語のみならず、テキストでの補足説明も基本的にはしてもらえない。ぼくらがふだん使っている日本語という言語を一切排除して、その時間は手話だけにどっぷり浸るというのだ。
要するに、英語話者しかいない環境で英語を学ぶようなものだ。新しい言語を学ぶという意味では、とても理想的な環境だとも言える。
数年前、「ダイアログ・イン・サイレンス」というイベントに参加したことがある。それは完全に音を遮断された空間で、アテンドと呼ばれる聴こえない人たちの案内に従い、音に頼らないコミュニケーションを体験するイベントだ。そこでは手話の使用も禁じられていて、使えるのはボディランゲージや表情、目線のみ。
そんな空間を通して、聴こえる参加者たちは、音以外でのコミュニケーションの難しさと面白さを知る。こちらの意図することが伝わらないともどかしいし、無音の状態で意思疎通ができるとこれ以上ないくらいうれしい。
そのときの体験を踏まえれば、たしかに音がなくてもコミュニケーションは取れると思う。けれど、今回は「手話を学ぶ」という明確な目的がある。「あの場面では意思疎通ができなかったね」と笑って終わらせるわけにはいかないのだ。言語を学ぶ場である以上、誤解やすれ違いは最小限にしておきたい。
このスタイルで手話を正しく学んでいけるのだろうか……。一緒に受けているKさんも同じことを考えていたようで、若干、戸惑っていた。
「コーダ」という手話単語を知って
日本語こそ使用禁止だったものの、それを補うために講師が取り出したのは「イラスト」だった。たとえば、「男性」という手話を教えるときには、男の人が描かれたイラストをホワイトボードに貼り付ける。なるほど、耳に頼らずに「視覚」を活用するということか。
それぞれの名字、性別、色、数字などの表現を順調に学んでいく。このあたりはほとんど知っているものばかり。日常会話で出てくる単語については、手話と距離を置いていたぼくの体にもしっかり染み込んでいるようだ。講師がイラストを提示するたび、「あ、これはできるぞ」と反射的に思った。その小さな積み重ねが、自信につながっていく。
講師が手を動かすたびに、幼い頃に見ていた両親の手の動きが重なる。これも知ってる、これも、これも。見失っていたはずの足跡を辿るように、一つひとつの手話を確かめていくと、忘れかけていた過去がまざまざと蘇ってくる。手話という言語には、両親との思い出が紐付いていた。
思い出というものは、映像、匂い、触感、味など、さまざまな要素で構築されるものだ。そのなかにはもちろん、「言葉」という要素も欠かせないものとして存在する。そして、ぼくにとってその「言葉」に当たるものの大部分は、やはり手話だった。ご飯を食べて美味しいと笑い合ったときのこと、喧嘩をして泣きながら怒りをぶつけたときのこと、ワガママを言って困らせてしまったときのこと。両親と過ごしたすべてのシーンに、手話が存在している。それほどまでに大切なものだったのに、どうしてぼくは手放してしまったのだろう。ほんの少しの後悔と、抱えきれないほどの懐かしさを覚えながら、ぼくは講師の手話を見つめていた。
話題が家族に移ったときのことだ。講師がぼくらに尋ねる。
――ふたりの両親はろう者? それとも聴者?
Kさんが先程教わったばかりの手話で説明する。
――私の両親は聴者です。
それに続いて、ぼくも手を動かした。
――ぼくの親は、ろう者です。父も母も、どちらも聴こえません。
申し込みの際、自分がコーダであることは伝えていた。でも、その情報がどこまで講師に共有されているのかはわからない。ぼくがコーダであると知って驚いただろうか。
講師は「なるほど」という表情を浮かべ、続けざまに手を動かした。右手を「C」の形にして、耳から口元へと動かす。
――あなたは、コーダなんだね。
それは「コーダ」という手話だった。知らなかった。自分の生い立ちを表す手話が存在するなんて、想像もしなかった。

――これが、コーダ?
――そう、コーダってこうやるの。覚えてね。
講師が見ている前で、何度か「コーダ」と手を動かしてみる。このときの感動は忘れられない。自分がコーダと呼ばれる存在だと知ったときの感動とはまったく種類の違う想いが、ぼくの胸に去来していた。
両親が使っている手話で、自分のアイデンティティの核となっているものを表現できる。まるで両親が生きる世界に、ぼくの居場所を見つけたような感覚だった。コーダという手話単語がある。つまりそれは、彼らの世界にコーダという概念が存在することとイコールだ。
手話によって、あらためて両親とつながる
ぼくは幼い頃、両親が生きる聴こえない世界には、自分の居場所がないと感じていた。ろう文化にとても近いところで生きているのに、ぼくはどう頑張ったって聴こえてしまう。耳を塞いでも、ぼくの聴力がゼロになることはない。
ぼくと両親は「違う世界を生きている人間なんだ」。その事実に打ちのめされそうになることが、たびたびあった。違うから、すれ違う。だったら、最初から同じだったら良かったのに。ぼくの耳も聴こえなければ、両親が苦労することもなかったかもしれない。気持ちや考えていることを、スムーズに共有できたかもしれない。考えても無駄なのに、「かもしれない」と思うことが多かった。
同時に、完全な聴者かと問われれば、それもしっくり来なかった。ろう者と聴者の狭間を漂うような感覚。どちらの世界のことをも知っているけれど、それはつまり、どちらの世界のことも中途半端ということだ。そんな不安定な存在をどう表現したらいいのか。子どもの頃はそれがわからず、だから両親の世界には、ぼくみたいな存在は他にいないのだと思っていたのだ。
でも、そうじゃなかった。「コーダ」という手話単語は、ぼくと両親をつなぐ光みたいなものだ。それを実感すると、手話の世界がより一層身近に感じられる気がした。
(つづく)
※記事中の登場人物については、プライバシー保護のため一部フィクションを織り交ぜて描写しています。

Profile
Profile
![]()
-
ミカヅキユミ
イラストレーター
新潟県在住。先天性の聴覚障害を持つ。2児(ともにコーダ)の母。幼いころから絵を描くことが好きで、美術系の学校を卒業後、一般企業に就職。イラスト制作の仕事に携わる。第一子妊娠&出産を機に、8年勤めた会社を退職。子どもが生まれてから育児絵日記をスタート。消しゴムはんこ作家として活動歴あり。オーダーや委託販売で経験を積む(現在は活動休止中)。現在はライブドアブログ「背中をポンポン」やSNSにて、聴こえない自分の日常や子どもたちとのエピソードをコミックエッセイで発信している。レタスクラブwebにて、コーダの子育てをテーマとしたコミックエッセイ「聴こえないわたし 母になる」連載中。