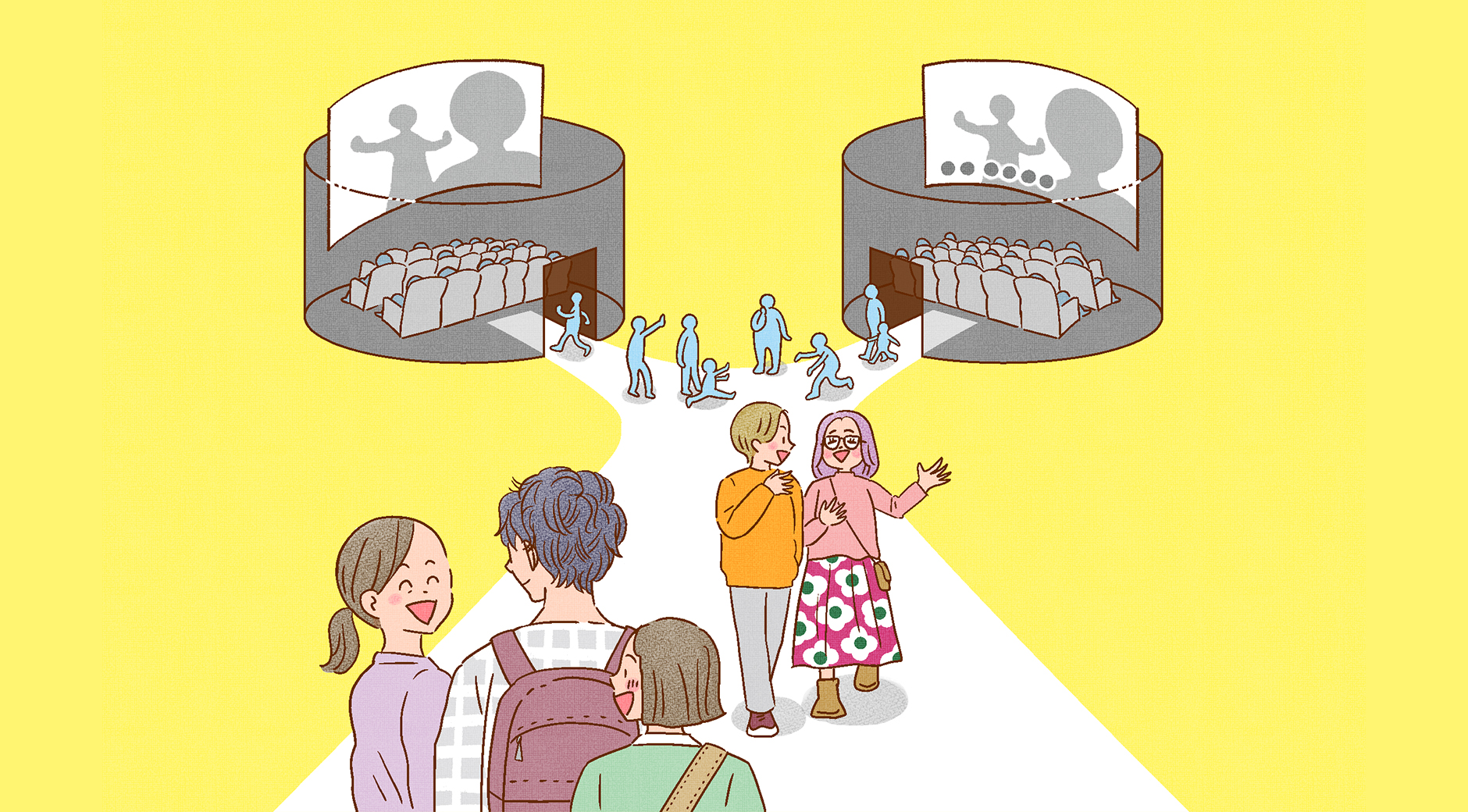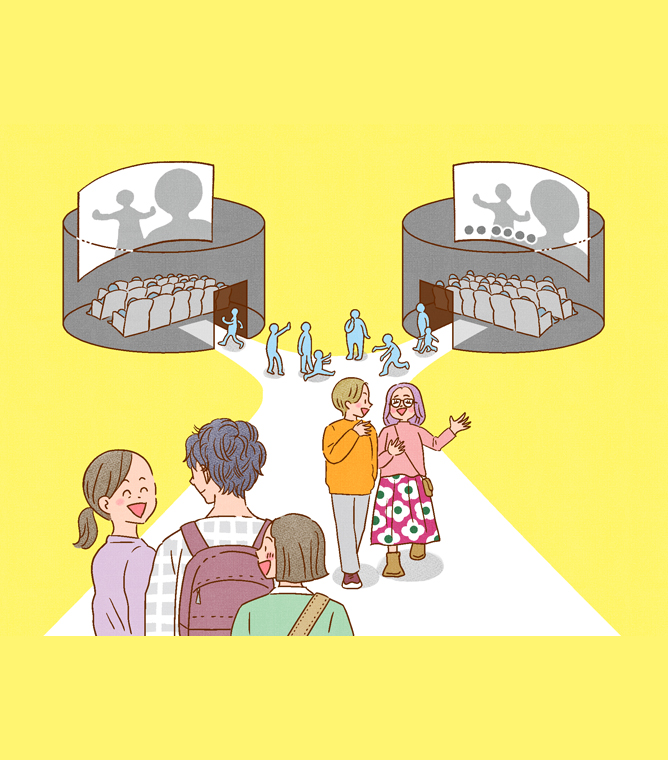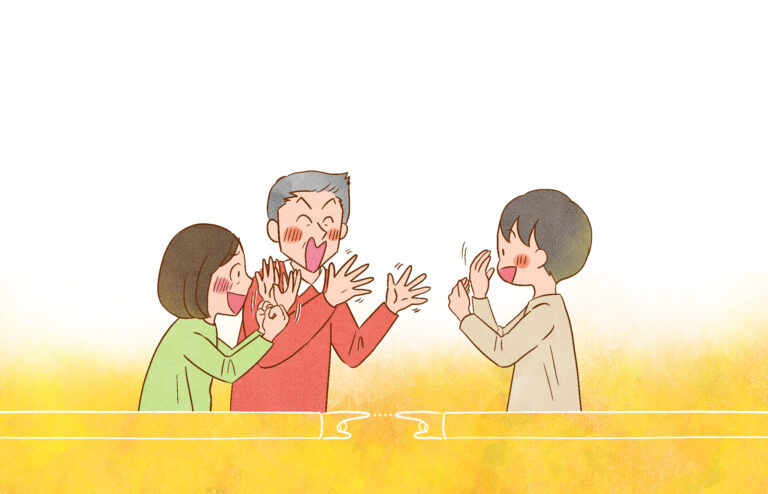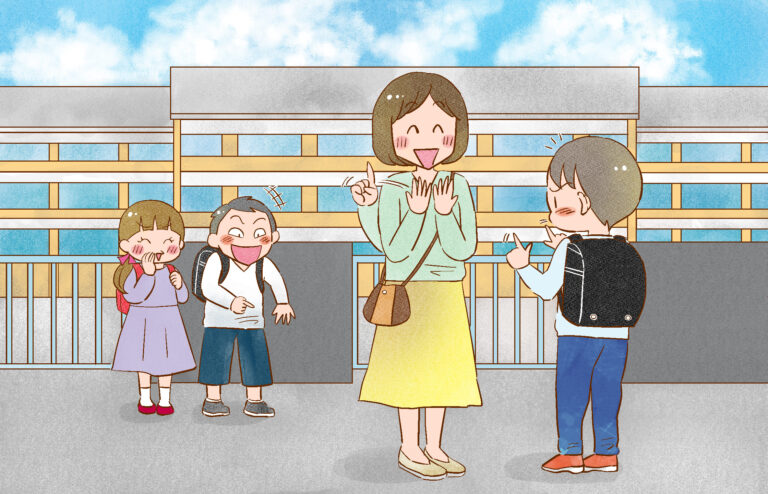わかりあいたいのに、うまくいかない。話したいと思いながら、機会がやってこない。身近だからこそ、上手に会話ができない。そんな人はいますか。連載「いま話したい人がいる」は、作家・五十嵐大さんによるエッセイです。前回から少し時間が経ち、その後の出来事から感じたことを綴っていただきました。
ぼくの両親は耳が聴こえない。そんなふたりのもとで育った子どもは、「コーダ(CODA、Children of Deaf Adults)」と呼ばれる。思春期に手話を使うことをやめたぼくは30代を迎え、両親とちゃんと向き合いたいと思うようになった。オンライン講座を通して、改めて両親との共通言語「手話」を学び直すことに。そしていよいよ「全国手話検定試験」に挑戦することになった。会場で手話がわからず困っている受験生を見つけ、一瞬躊躇するが、ぼくは「言語に対してリスペクトを持つ」という態度を選ぶことにした。そして手話検定5級・4級に合格。それから3年が経ち……。
>第4回「言語を尊重するということ」
エッセイが映画化されることになって
「五十嵐さんのエッセイを映画化したい、というお話が届いています」
担当編集者からのメッセージを確認したとき、移動中の電車内で思わず「え!」と大きな声を漏らしてしまった。2冊目のエッセイである『ろうの両親から生まれたぼくが聴こえる世界と聴こえない世界を行き来して考えた30のこと』を出版して、半年後のことだった。
ありがたいことに制作陣に恵まれ、丁寧に時間をかけて作られた映画は、『ぼくが生きてる、ふたつの世界』というタイトルで、2024年9月に公開された。自分の書いた本が映像になる嬉しさは他のものに例えようがないくらい特別なことで、脚本が上がってきたり、ロケ地について決まったりするたびに、ぼくは喜びを噛み締めた。なかでも最も感動したのは、制作陣の「当事者の存在を無視しない」という態度だった。作中に登場するろうの登場人物には実際にろう者俳優を起用し、手話演出やコーダ監修を配置し、現場でのコミュニケーションには手話通訳者が付けられ、そして、映画は通常版のみならず、バリアフリー字幕版も作られた。
そうして映画が公開されると、ぼくの両親は初日に映画館へ足を運んだ。たった一度ではなく、友人知人を誘って何度も観に行ってくれたそうだ。
ぼくが記憶している限り、母が映画館へ行ったことはなかったように思う。一方、父は無類の映画好きで、週末になると大量のビデオを借りてきては、テレビ画面の向こう側で繰り広げられる世界を見つめていた。そんな父の側で育ったからなのか、子どもの頃のぼくも映画に夢中になった。一番好きだったのは、『大長編ドラえもん』のシリーズだ。ふだんはダメダメなのび太くんが活躍するところも、ジャイアンが急にいい奴になるところも、ピンチのときにドラえもんがポンコツになるところも、すべてひっくるめて好きだった。そのうち、父と一緒にビデオショップに足を運んでは、さまざまな映画を借りては、流すようになった。
自室にはテレビとビデオデッキがあったけれど、ぼくはあえてリビングで、借りてきた映画を観た。父も母もそれに付き合ってくれて、エンドロールが流れると、ぼくは映画の良かったところやつまらなかったところを語った。そんなぼくを見て、ふたりは柔らかく笑っていた。
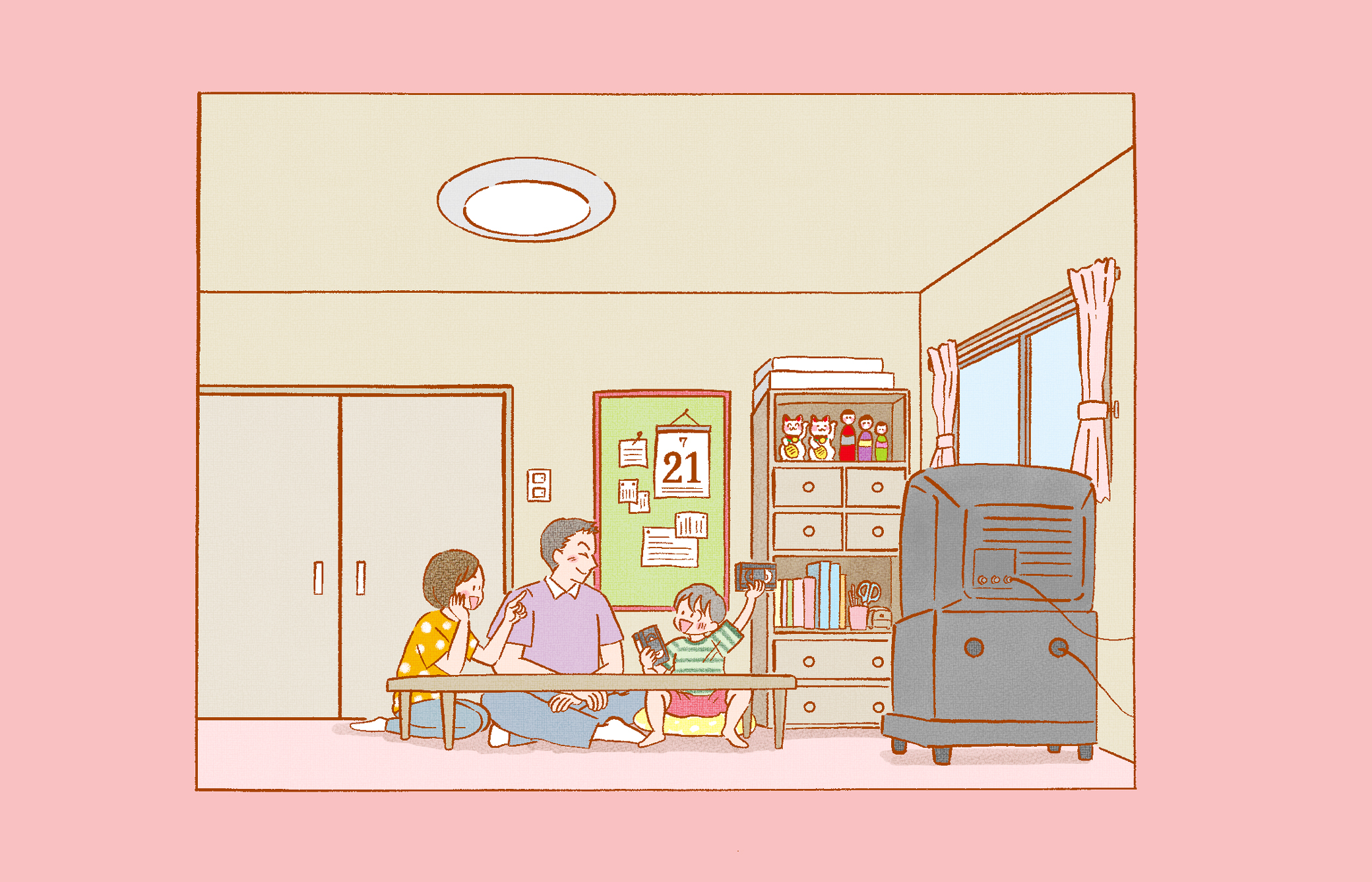
どうして字幕版の上映が少ないのか
映画『ぼくが生きてる、ふたつの世界』が公開されてからは、盆と正月が一緒に来るとはこのことか、と膝を打つような日々が続いた。なかには、「あの頃の五十嵐が抱えているもの、なんにも気付けなかったよ」とわざわざ謝罪の連絡をくれる旧友もいて、あなたはなにも悪くなかったよ、と思いながらも、胸の奥に広がる温かさに浸る日もあった。
しかしながら、残念なこともあった。せっかく作ってもらったバリアフリー字幕版の公開期間が短いことが、方々から耳に入ってきたからだ。
邦画に字幕が付けられること自体、いまだに一般的ではない。大好きなアニメの劇場版が公開されることになったものの、字幕版の上映がないことを知り、落ち込んでいるろう者の知人もいた。あるいは、字幕版自体は用意されているけれど、映画公開からわずか一週間、しかも平日の早朝の時間帯のみ、という出来事もあった。平日の朝から映画館に足を運べる人がどれくらいいるだろう。
聞くところによると、字幕版の上映の有無は、各映画館が判断しているらしい。その地域にはろう者がどれくらいいるのか、そのなかの何人が邦画を観に来るのか、つまりは字幕版を流すことでどれほどの収益につながるのかが判断材料ということだろうか。
でも、いやちょっと待ってくれよ、と思ってしまう。仮に、その地域に邦画を観にくるろう者が少なかったとして、原因はどこにあるのか。そもそも字幕版が上映されていなかったら、観に行くろう者が少ないのは当然だ。逆に言うならば、邦画に字幕が付けられることが一般的になっていれば、映画館に足を運ぶろう者はもっともっと多いのではないか。鶏が先か、卵が先かみたいに、字幕版がなかったことが原因なのかろう者の観客が少なかったことが原因なのか、本当のところはわからない。ただ、周りを見る限り、邦画を楽しみたいというろう者は必ず存在する。だから、彼らの存在を無視するのではなく、やはり字幕版を用意してもらいたい。
ぼくもその立場になってみるまではわからなかったのだけど、映像作品における原作者の立場はそれほど強くはない。全権限を握れるわけもなく、基本的には映像業界の専門スタッフたちを少し離れた場所から見守るような感じだ。ましてや、映画館に直接アプローチすることなんてできない。
だからこそ、字幕の件にはもどかしい思いを抱いた。せっかく制作陣が思いを込めて作ってくれた映画が、しかも、コーダとろうの親の関係を描いた映画が、当事者に観てもらえないなんて、こんなに悲しいことはあるだろうか。でも、自分にできることはほとんどない。どうしたらいいんだろう……。それならせめて、と、字幕版の上映期間の延長や復活を要望するツイートをしたところ、想像以上に拡散された。なかにはすでに映画を観たという聴者から「聴者にとっても字幕はありがたいです」といった声も寄せられた。
その結果、いくつかの映画館が賛同してくれ、字幕版の上映が小さくではあるものの広がっていくのを確認できた。この社会は捨てたもんじゃないのだ。
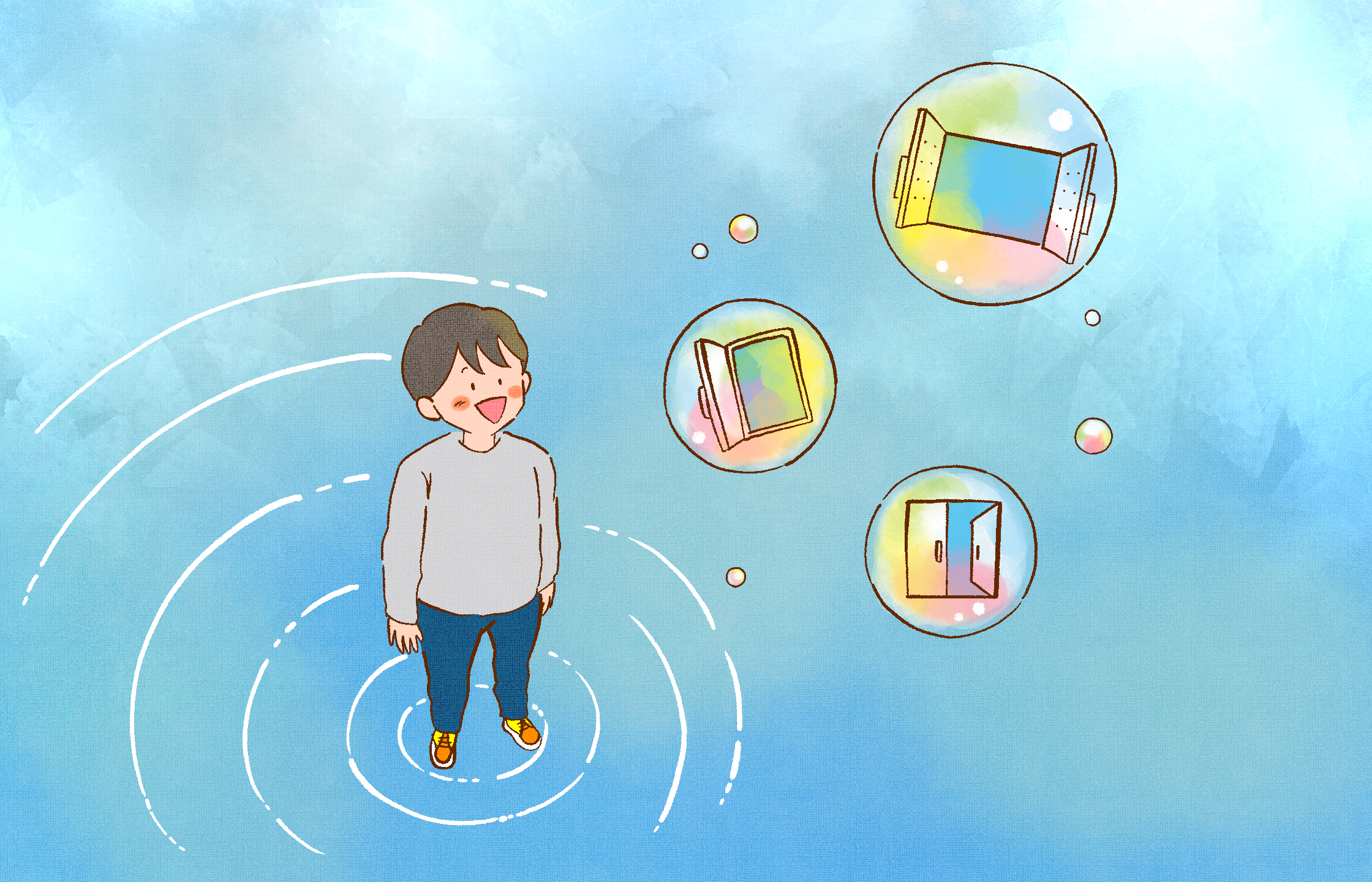
違う立場で、同じ物事を一緒に楽しめる未来へ
映画の公開から少し経った頃、ぼくは両親のもとを訪ねた。恐る恐るではあるものの、映画の感想を聞くためだった。原作はぼくの実体験をもとにしたエッセイだ。つまり、そこに書かれていることは、両親も同じように体験したことばかり。幼い頃、耳が聴こえない両親を恥ずかしいと感じたことも、周囲の人たちから差別されたことも、それによって生じた怒りを両親にぶつけてしまったことも、ありのままに綴った。そんなエッセイをほとんど原作そのままに映像化してもらったのだから、両親、特に母が必要以上に傷つくのではないかと不安だったのだ。
でも、杞憂だった。ふたりとも熱心に映画の感想を伝えてくれた。主演の吉沢亮さんの手話が見事だったことにはじまり、東京で苦労するぼく(というか、映画の主人公)が心配で仕方なかったこと、くも膜下出血で倒れた父が助かったときの安堵感、幼少期のぼくとの思い出……と、映画の内容と昔話を絡めては、お喋りが止まらない。怒涛の勢いで手を動かすふたりを見ていて、ちょっと疲れてしまうほどだった。
そうして気がつく。子どもの頃、こんな風にひとつの映画の感想を話し合ったことがあっただろうか、と。当時はテレビに字幕機能もなかったし、もちろん、借りてきた邦画に字幕がついていることも皆無だった。でも、幼かったぼくはそんなことを気にすることもなく、ただただ、自分が観たい作品ばかり借りてきては、なぜか両親も巻き込んでは一緒に観ていた。
あの頃、邦画にも字幕が付けられていたら、ぼくらは同じ作品を一緒に楽しむことができていたんだろうな。映画の感想を延々話している両親を見ながら、そんなことをぼんやり思った。
誰かと話すことの喜びのひとつは、特定の物事を共有できるということだ。たとえばそれが映画だった場合、どこのシーンで泣きそうになったとか、あの演技がよかったとか言い合って、感動をより深めていける。あるいは、互いに真逆の感想を持つこともあるかもしれない。でも、それもまたいい。相手の話を聞き、自分には気づけなかったことに気がつく。相手の観察眼の鋭さに感心したり、好みの違いに溜息を吐いたりすることだってあるだろう。いずれにしても、「共有」できるからこそ生まれる営みだ。
ところが、この社会には、ひとつの物事を取ってみても、それを享受できる人とできない人が存在する。邦画を字幕なしでも楽しめる聴者と、字幕を必要とするろう者。その違いを埋めていかなければ、両者が同じ映画の感動を共有することは難しくなってしまう。
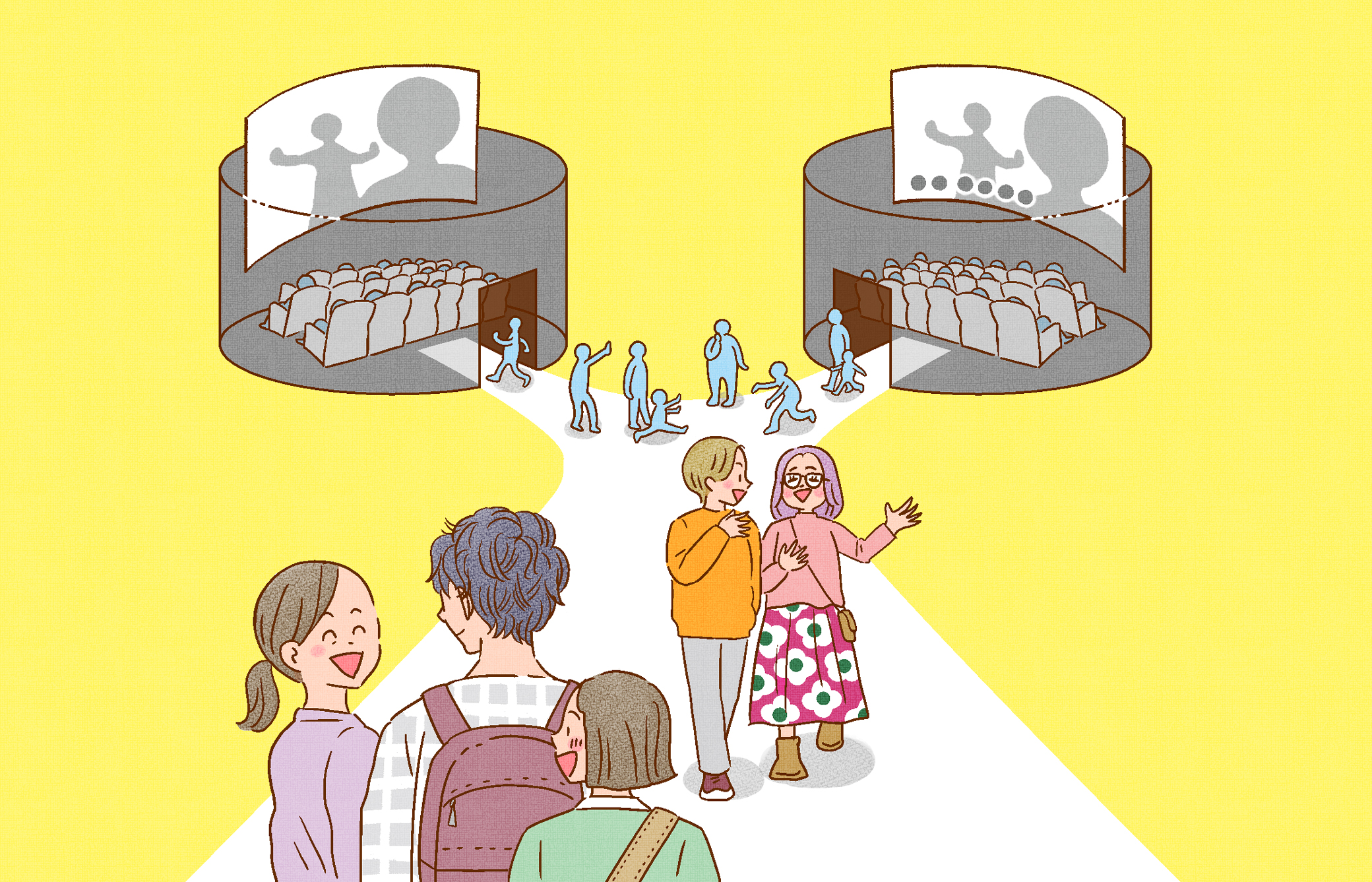
だからぼくは、これから先、邦画に字幕がつけられることが当たり前になってほしいと思う。「期間限定の特別上映」のような扱いではなく、字幕なし版が上映されるのと同じ感覚で字幕版が用意されている世の中であってほしい。
視覚優位な人のなかには、画面に字幕があると気が散ってしまって映画の内容が理解できなくなる人もいるらしい。そういう人は字幕なしのものを観て、ろう者は字幕版を楽しむ。キャストのセリフを一言一句逃したくないという聴者も字幕版を観ればいいし、今日は映像だけを追いかけたいと思うならば字幕なし版を選べばいい。
あらゆる場面で、そうやって選択肢を増やしていけば、取り残される人が減っていくと思う。その先にあるのは、誰もが同じ物事を共有し、話に花を咲かせられる未来なんじゃないだろうか。