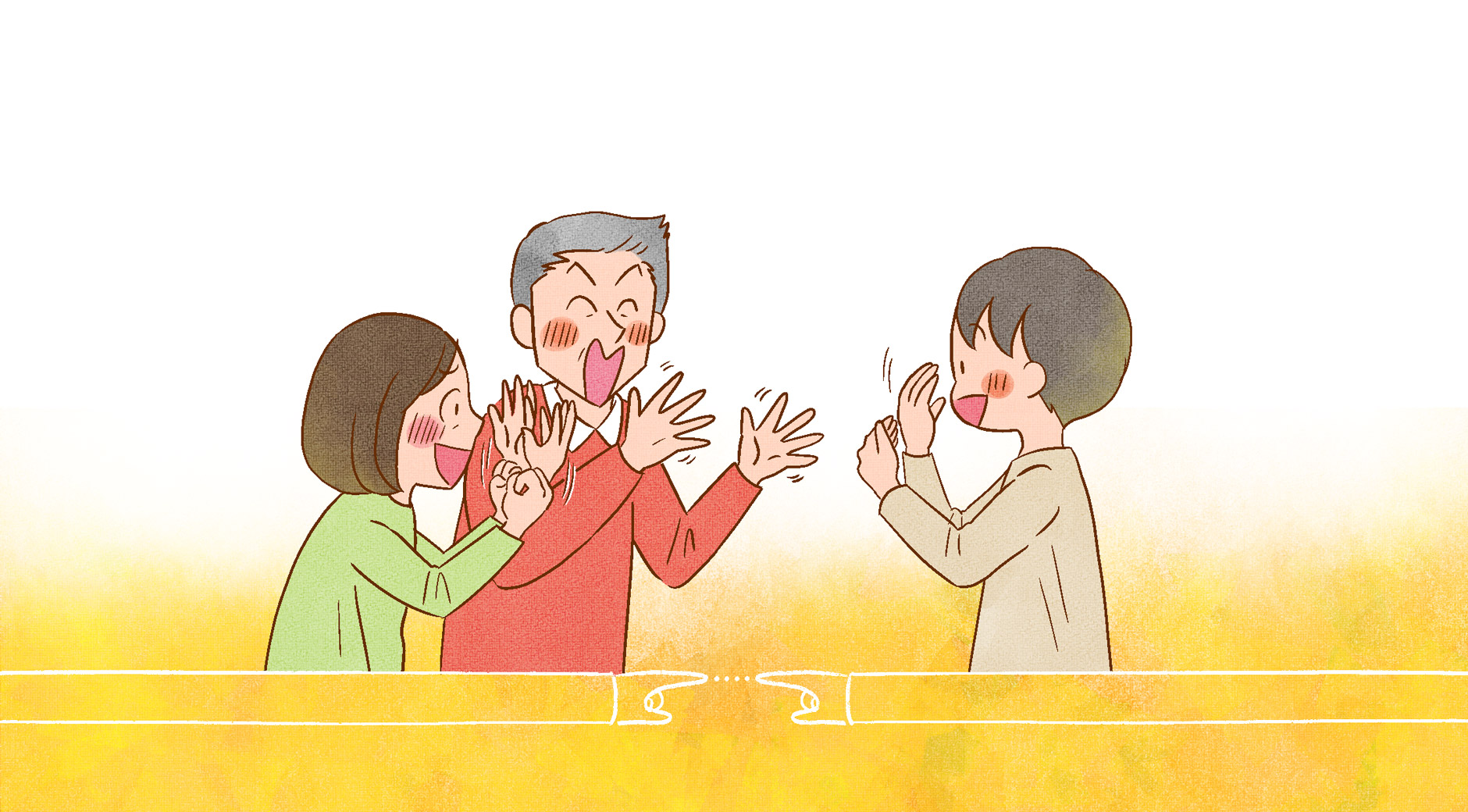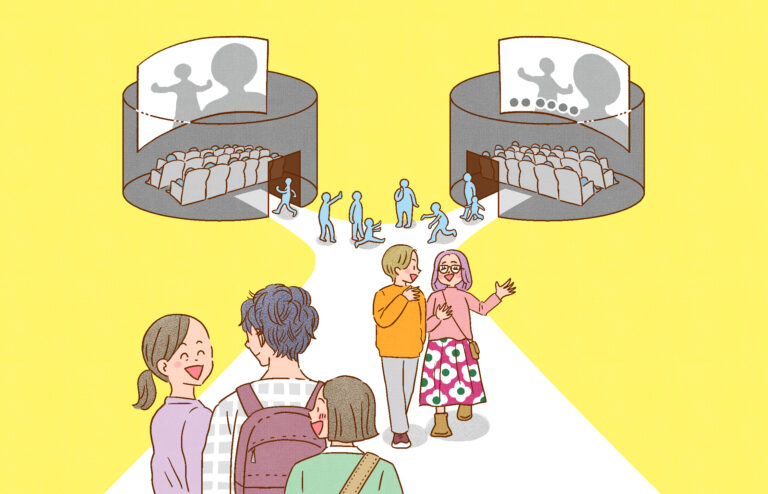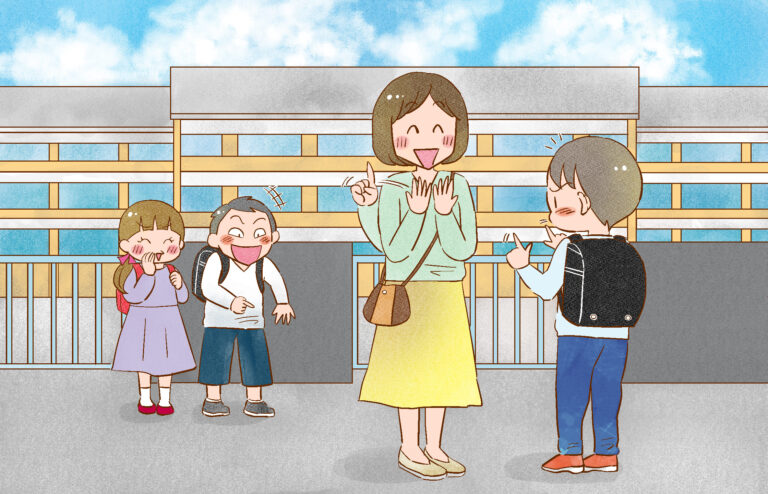わかりあいたいのに、うまくいかない。話したいと思いながら、機会がやってこない。身近だからこそ、上手に会話ができない。そんな人はいますか。連載「いま話したい人がいる」は、ライター/エッセイストの五十嵐大さんによるエッセイです。
ぼくの両親は耳が聴こえない。そんなふたりのもとで育った子どもは、「コーダ(CODA、Children of Deaf Adults)」と呼ばれる。思春期に手話を使うことをやめたぼくは30代を迎え、両親とちゃんと向き合いたいと思うようになった。オンライン講座を通して、改めて両親との共通言語「手話」を学び直すことに。開始から1カ月後。順調に進んでいたように思えた手話学習でつまずき、「言葉が通じない」苦しさを味わう。そこで初めて僕は、両親が聴こえないことで感じてきた苦しい状況に思いを馳せられたのだった。
>第3回「『マイノリティ』ってなんだろう?」
「全国手話検定試験」への挑戦
「手話検定って知ってる?」
手話を学び始めて、数カ月が過ぎた頃だった。コーダの知人に言われた。
「検定があるんだ」
「そうそう。もしよかったら腕試しのつもりで受けてみたらどうかなって思ったの」
「いや、ぼくには無理だし、落ちたらショックだから……」
調べてみるとすぐに見つかった。「全国手話検定試験」。それは手話学習者を対象とする検定で、その実力に応じて「5級/4級/3級/2級/準1級/1級」と6段階にレベル分けされる。一番下の5級を受験する上で、目安となる学習歴は「6カ月」だ。
手話学習は真剣にやってきた。ろう者の講師に教わるオンライン講座の他、件のコーダの知人が定期的に勉強会を開いてくれていて、空き時間には手話単語の教科書も読む習慣が身についた。でも、やはり不安だ。落ちてしまうのが怖い。
これが他の言語だったら、「今回は残念だったけど、まあ仕方ない。また次の機会に頑張ろう」とあっさり仕切り直せる気がするが、手話となるとそんな簡単に割り切れるとは思えなかった。
「そんなに深刻に考えなくてもいいんじゃない? 小さな目標を立てておいたほうが、手話の勉強も捗ると思うよ?」
「じゃあ、やってみようかな」
まずは5級から。でも、せっかくだし、その上も目指してみたい。
「どうせだし、4級も受けてみるよ。その分、しっかり勉強しないと」
「いいね、同じコーダとして応援するよ!」

5級は手話で日常的な挨拶や自己紹介ができること、手話が読み取れることが基準だ。それに加えて4級は1週間や1年など、時の経過を表す単語を理解しているかがポイントになる。学習歴の目安は1年。合格するかどうか、自信がない。
それでも挑戦することを決めたのは、きっと少しでも多くの証明が欲しかったのだと思う。一度は「捨てた手話」を、どこまで取り戻せているのか。第三者の目でしっかり評価してもらうことで、自分の現在地を確認したかったのだ。
申込みから数カ月、必死で勉強した。そして迎えた検定の日、新宿に設けられた試験会場へとぼくは向かった。
手話でのやりとりに戸惑う子を見て
会場が用意されたビルの入り口で、親子連れと出くわした。子どもは小学生くらいだろうか。どうやらその子が受験するらしく、親御さんは会場まで見送りに来たようだ。
会場には受験者しか入れないため、親御さんとその子はエレベーター前でお別れをする。
「頑張ってね! 大丈夫だから!」
そんな声が聴こえてきた。聴者の家庭なのだろう。どんな理由で手話を勉強しようと思ったのか訊いてみたくなったが、ぐっと堪え、ぼくとその子は同じエレベーターに乗り込んだ。
時間に余裕を持ってきたつもりだったものの、みんな考えることは同じみたいで、会場の入り口はすでに混雑していた。受験票を握りしめ、入場するための列に並ぶ。会場の運営スタッフは聴者とろう者が担当しているようで、前方では受験者と会場誘導を担当する男性が手話でやりとりしていた。
――受験票を見せてください。
――こちらです。
――ありがとうございます。あなたの席はあちらです。
――ありがとうございます。
一人ひとりの受験番号をチェックし、指定された席が会場内のどこにあるのかを伝える。これが会場誘導係のろう者の男性の役割のようだ。
いよいよ始まるのだなと思いながら順番を待っていると、列の動きが止まってしまう。先程、親御さんに見送られてきた小学生と男性とのコミュニケーションが、うまく成立していないようだった。

――あなたの席は、ここです。ここで試験を受けてください。
会場誘導係の男性は、何度も何度も繰り返し手を動かす。その手話はとてもわかり易く、幼い子でも理解できるように意識しているのが明白だった。
でも、その子はなにを指示されているのか掴めないようで、首をかしげている。
このままではどうしようもないだろうし、通訳してあげよう――。
身を乗り出そうとした瞬間、ギリギリのところで思い止まった。
いまぼくが、ここで音声日本語を用いて通訳してしまえば、ほんの数秒ですべては解決できるかもしれない。でも、手話を勉強し、その実力を試すこの場所で、音声日本語を頼ってはいけない。そう思った。
言語を学ぶ上で「リスペクト」を持ちたい
言語を学ぶ上で「大切なもの」とはなんだろうか。その言語に触れている時間、圧倒的な語彙数……。なにを大切だと捉えるのかは、もちろん人それぞれだ。
でも、ぼくはこう思う。
言語を学ぶ上で大切なのは、言語の背景にあるものを理解し、それを使って生きる人たちも含めてリスペクトすること。
勉強し始めれば壁にぶつかってしまうことがある。ハードルの高さに挫折を覚えたり、諦めたりすることだってあるし、それは仕方ない。ただし、決して雑に扱ってはならないと思う。
その言語を母語として使い、言語をベースに築き上げてきた独自の文化の中で生きている人たちがいる以上、触れるときも離れるときも、敬意を持ちたいと僕は思う。
どうしてそう考えるのか。それは手話がたしかな「言語」であるにも関わらず、尊重されてこなかった歴史があるからだ。そのことは手話を使うろう者たちを苦しめてきた。
振り返ると、ぼくの実家ではあまり手話が大事にされていなかったように思う。ぼくに手話を教えようとする両親に代わって、祖父母は「手話よりも音声言語を身に着けなさい」と教育した。実際に「手話を覚えたってしょうがないでしょう」と言われたこともあったし、それを証明するかのように、ぼくと両親以外は誰も手話ができなかった。
祖父母は明確な悪意を持っていたわけではないと思う。聴こえない両親にはやさしかったし、工夫をしながら同居していた。それでも、彼らが手話を言語として尊重していなかったのは、歴史的な偏見を知らず知らずのうちに内面化していたのかもしれない。
日本初のろう学校「京都盲唖院」が設立されてから1920年代の前半までは、ろう者の手話が教育現場でも用いられてきたそうだ。けれど、1925年に「日本聾口話普及会」が発足し、唇の動きを読み取り、発生練習をするという「口話」が推奨されるようになると、本来はろう者の第一言語である「手話」を一切認めないという運動が広がっていった。そのとき、関係者のひとりは手話を「手真似」と蔑んだ。その後、「手話も必要である」という論が提議されるようになったのは1960年代に入ってからのことだ(※注)。それだけを見ても、実に長い間、手話という言語が不当な扱いを受け、手話を使う人に対しても偏見の目が向けられてきたことがわかるだろう。
※注参考資料:『日本手話とろう教育』(クァク・ジョンナン/生活書院)
そんな時代を生きてきた祖父母は、手話への偏った価値観を持ってしまっていたのだと思う。
そしてぼく自身も、「手話なんて要らない」という思いに囚われていくようになった。結果、それを後悔し、大人になったいま必死で取り戻そうとしているのだけれど。
「通じ合えた」というよろこびが糧になる
では、この試験会場で「手話をリスペクトする」とはどういうことか。それは、僕にとって「困ったときも手話で試行錯誤する」ということだと考えた。
日本では少数言語に位置づけられ、蔑まれてきた歴史も持つ手話が、この試験会場では尊重されている。誰もが手話を賢明に学び、実力を試そうとやって来ている。そんな受験者たちを迎えるのももちろん、手話を使う人たち。ここでは手話が「公用語」になっている。
だからぼくは、目の前で困っている小学生に対して、ただ見守ることしかできなかった。
頑張れ、その人の手の動きと目線を見て、きっとわかるから――。
数分後、小学生はようやく「意味がわかった!」と表情を明るくし、会場誘導係の男性に向かって大きく頷いた。男性はホッとしたのか、「大丈夫?」と手を動かす。小学生は再度頷くと、駆け足で自分の席へと向かっていった。
――お待たせしてすみません。
男性は安堵しながらそう手を動かしたけれど、そのやりとりに対して怒っている人は誰もいなかった。きっとみんな、「伝わってよかった」「理解できてよかった」と胸を撫で下ろしていたに違いない。
ぼくはぼくで、小学生に通訳をしなくてよかった、と思っていた。
もしもあの場面でぼくが通訳をしていたら、音声日本語でサポートしていたら、小学生のなかには「やはり手話よりも音声日本語のほうが伝わるし、便利なんだ」という気持ちが芽生えてしまったかもしれない。
でも、時間をかけてでも手話のやりとりを理解した小学生の胸中には、おそらく「手話で通じ合えたよろこび」が生まれていると思う。今後、手話学習を続けていく上で、そのよろこびは大きな糧になるだろう。そしてそれは、ぼく自身にも言えることだ。
さて、肝心の試験はというと、これが実に散々だった。
筆記はほぼできたものの、面接試験では想像以上に緊張してしまい、手話単語がなかなか浮かばない。なにを訊かれているのかは理解できるのに、その回答を表現する力が足りていないのだ。
あああ、こう伝えたいのに、出てこない!
それでも知っている単語を組み合わせ、わからないこと、表現できないことは正直に話し、最後は笑顔で終わらせた。席を立つとき、面接官に対して「ありがとうございます。次はもっと頑張ります」と手話で伝えた。面接官は「お疲れさまでした」と笑ってくれた。最後の最後、そうやって通じ合えたことがうれしかった。
今回はいい経験になった。後はもう成るように成れ、だ。
最初に手話検定を勧められたとき、必要以上に深刻に捉えていたぼくは、もうどこにもいなかった。手話がリスペクトされている空間で、思い切り自分の手話を表現してきた。それだけでなんだか晴れ晴れとした気持ちで一杯だったのだ。
ダメだったら、またチャレンジしよう! 帰り道、素直にそう思った。
ところがその数カ月後、自宅に届いた試験結果を見てみると……、なんと「合格」していた。5級も4級も、どちらも合格だった。

自信を喪失していたぼくはコーダの知人にそれを伝えた。
「やっぱり! 五十嵐くんなら大丈夫だと思ってたんだよ!」
そして両親にはビデオ通話で結果を伝えた。
――手話検定の5級も4級も、どっちも合格したよ!
――すごいね! おめでとう!
――まだまだ下手くそだけど、これからも頑張るよ。
――下手なんかじゃないよ? 前と比べると随分と上達したし、唇を読まなくてもあなたの言いたいことがわかるようになってきてるもの。
これが通じ合うことのよろこびなのだ。この手話検定を通じて実感したよろこびは、一生忘れないと思う。この気持ちを大事に育て、ぼくはこれからも手話学習を続ける。
そして、あのとき出会った小学生も、いまのぼくと同じ気持ちでいてくれたらいいな、とぼんやり思った。
(つづく)

Information
ミステリー小説『エフィラは泳ぎ出せない』発売中
五十嵐大が初めてのミステリー小説を刊行しました。障害のある兄の自死をめぐり、主人公がその真相を探っていく物語。ひとが生きていく中で抱える痛みや苦み、そして喜びを、一歩一歩辿ります。
『エフィラは泳ぎ出せない』
- 著者:五十嵐大
- 出版社:東京創元社
- 判型:四六判仮フランス装
- ページ数:302ページ
- 初版:2022年8月31日
- ISBN:978-4-488-02019-4
Profile
Profile
![]()
-
ミカヅキユミ
イラストレーター
新潟県在住。先天性の聴覚障害を持つ。2児(ともにコーダ)の母。幼いころから絵を描くことが好きで、美術系の学校を卒業後、一般企業に就職。イラスト制作の仕事に携わる。第一子妊娠&出産を機に、8年勤めた会社を退職。子どもが生まれてから育児絵日記をスタート。消しゴムはんこ作家として活動歴あり。オーダーや委託販売で経験を積む(現在は活動休止中)。現在はライブドアブログ「背中をポンポン」やSNSにて、聴こえない自分の日常や子どもたちとのエピソードをコミックエッセイで発信している。レタスクラブwebにて、コーダの子育てをテーマとしたコミックエッセイ「聴こえないわたし 母になる」連載中。