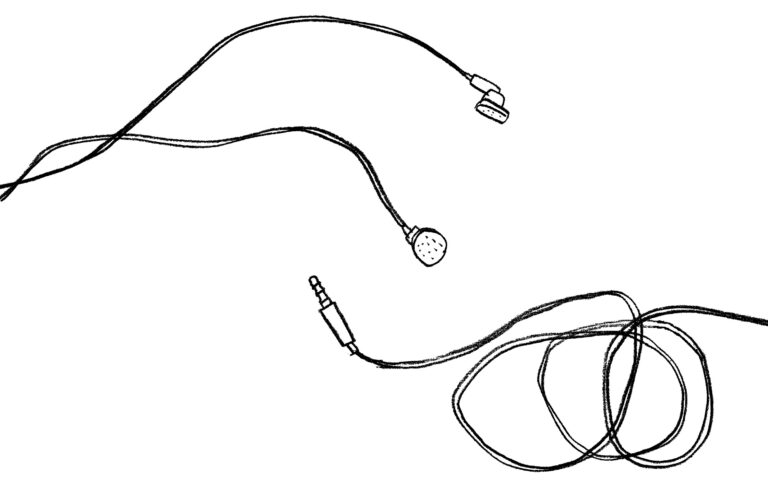社会福祉法人元理事長による性暴力とハラスメントについて考えた、「そばに居る者」としての記録 砕け散った瓦礫の中の一瞬の星座 -ケアと表現のメモランダム-|アサダワタル vol.09
- トップ
- 砕け散った瓦礫の中の一瞬の星座 -ケアと表現のメモランダム-|アサダワタル
- 社会福祉法人元理事長による性暴力とハラスメントについて考えた、「そばに居る者」としての記録
※この記事には性暴力やハラスメントに関する記述が含まれます。読む際にはご注意ください。
はじめに(編集部より)
本記事は、「ケア」と「表現」の交わる現場に関わってきた文化活動家・アサダワタルさんによるエッセイ連載の第9回目です。
アサダさんは、ユニークな方法で他者と関わることを「アート」と捉え、音楽や言葉を手立てに、全国の市街地、福祉施設、学校、復興団地などで文化活動を手掛けてきたアーティストです。特に障害福祉領域に関わる経験が豊富で、全国各地の福祉現場でアートプロジェクトやワークショップを実施されてきました。2019年からは、〈品川区立障害児者総合支援施設ぐるっぽ〉(東京都)にて、障害のある人とともに創作活動・地域活動を行うコミュニティ・アートディレクターも務められました。
本連載「砕け散った瓦礫の中の一瞬の星座 -ケアと表現のメモランダム-」では、アサダさんがこれまでにケアの現場で経験してきた出来事、育まれてきた表現、人々との関係性を振り返り、揺れや戸惑いも含めて、率直に感じたこと・考えたことを書いていただいています。ぜひ過去の連載記事もお読みください。
今回の記事では、アサダさんが現場で直面した「社会福祉法人元理事長による法人理事・職員への性暴力とハラスメント」について綴られています。
アサダさんは被害者と加害者双方と長年仕事をしてきた親しい立場にありました。アサダさんが当時どのように性暴力事件について知り、受け止め、煩悶し、対応し、対話し、行動し、現在どのように考えているのか。連載テーマに応じるかたちで率直に執筆いただきました。記事作成にあたっては、被害者である木村倫さん(仮名)や、登場される施設利用者・ご家族の確認・許可をいただき掲載しています。(本記事は執筆者による一人称のエッセイですので、より客観的・具体的な情報を知りたい場合は、「Dignity for All -社会福祉法人役員による性暴力・ハラスメント裁判の原告を支える会-」公式サイトをご照会ください)
〈こここ〉は社会に生きる一人ひとりの人権を大切にしたいと考えており、福祉の重要性と創造性を信じています。だからこそ、ある社会福祉法人の現場で起きた性暴力やハラスメントについて、構造的な問題について向き合い、読者とともに考える機会を持ちたいと思い、約3万字に渡る今回の記事を掲載することにしました。アサダさんが触れられているとおり、この問題には本連載のテーマである「ケア」と「表現」にも深く根ざしています。
重ねてにはなりますが、本記事では性暴力やハラスメントに関する記述が含まれます。被害者が勇気を持って告発した加害内容を矮小化することなく伝えるため、掲載する判断をしました。ただし、そうした記述を読むことで、フラッシュバックや二次受傷などが起こる方もいらっしゃるはずです。そのような可能性がある方はご注意ください。
それでは、以降、アサダワタルさんによる本編をお届けします。(こここ編集部)

これまでのことを思い返す
「ケアする人のケア」という言葉をご存知だろうか。
福祉現場で高齢者や障害のある人を介護・支援するスタッフや、在宅で家族を介護する人など広く「ケア従事者・支援者」に対して、必要な手を差し伸べ、心身のストレスを和らげる必要性のことだ。ケアの営みは、日々の利用者(メンバー)との関わりの中で見出す喜びややりがいがある一方で、ときにそのやりがいが過剰な「奉仕精神」にすり替えられる。高齢者介護の現場では、介護スタッフが利用者からハラスメントを受けるケースが後を絶たない。「職場の7割は女性」(※注1)と言われる福祉業界において、利用者の性格・生活歴から来る女性に対する固定観念や、スタッフの尊厳を低く見る傾向など、いろいろ原因は考えられる(※注2)。「奉仕して(されて)当たり前」「献身こそが美徳」ということだろうか。
この考えは、「利用者―支援者」の間にあるだけでなくて、「支援者―支援者」の間にも強く存在する。現場で働くスタッフの奉仕精神を、管理職や法人経営者が自覚的・無自覚的問わず当たり前のものとして勘定し、スタッフがどんどん疲弊していく事態だ。ここにも様々なタイプのハラスメントが発生する。とりわけ、「現場スタッフは圧倒的に女性が多いのに、ごく少数の管理職や経営者は男性が多い」というこの歪な組織構造が、この問題を加速させる。悲しいことだけど、僕も現場に入りながらこのことを日々実感してきた。そしてこう感じてきた。「支援者が“やられた”ときは、一体誰が救ってくれるのだろう?」と。
自分の尊厳が根っこから傷つけられても誰にも助けを求められないとき、私たちは、どのようにして「生き延びる」ことができるのか。比喩ではない。尊厳をいちじるしく傷つけられた人が孤立してしまえば、心身が蝕まれ、時には自ら命を落とすことだってあるのだから。私たちは、本当は気づいているはずだ。「誰にも助けを求められない」ことの原因に、そもそも「誰も助けに応じられない」という構造が存在することに。愕然とする。仲間が傷ついても何にも「ケア」できない自分に……。そんな無力さに打ちひしがれた人たちは多いのではないか。
今から3章にわたって書くことは、僕が働いてきた品川区立障害児者総合支援施設「ぐるっぽ」の指定管理者(2019年4月ー2022年9月)であった社会福祉法人グローと社会福祉法人愛成会で働く者の間で起きた、重大な性暴力・ハラスメントにまつわる、アサダ個人の視点からの記録だ。またこれは、言葉にしがたい事態の「そばに居る者」が、その起きてしまった出来事をそれでもなんとか言葉にしようともがくその態度の記録でもある。「本題」に行く前に、今回はまず昔のことから書かねばならない。僕の個人的な前史に、しばらくお付き合い願おう。
※注1 :令和3年度介護労働実態調査 事業所における介護労働実態調査 結果報告書(公益財団法人 介護労働安定センター)参照
※注2: 介護現場におけるハラスメントに関する調査研究 報告書(厚生労働省)参照
*
2008年、29歳のとき、「アート×障害福祉」というキャリアにつながる大きな契機が訪れた。滋賀県にある社会福祉法人グロー(2008年当初は滋賀県社会福祉事業団)との出会いだ。グローと言えば、障害のある人の作品とプロの現代美術作家のそれとを並列に扱う美術館「ボーダレス・アートミュージアムNO-MA」(近江八幡市)の運営で、アート界隈でも知られていた。出会いのきっかけは、僕が大阪で携わってきた障害のある人たちとのアート活動や、ヘルパーとして働いている経験(本連載Vol.3参照)に興味を持った職員からの1本のメールだった。JR大阪駅と直結したホテルグランビアの一階の喫茶店で、メールをくれた担当職員と共に訪れたのが当時50代になったばかりのグロー理事長 北岡賢剛氏。でも記憶では、そのとき北岡氏とはほとんど会話を交わしていない。確か彼は……、そう、ずっと携帯電話をいじっていたのだ。大きな身体に顎髭を携え、少し色黒な北岡氏の最初の印象は強面で無愛想。「この人、僕にはまったく興味を持ってなさそうだな。たまたま予定が空いたから部下と一緒に立ち会ったんだろう」。僕は心の中で生意気にもそう思っていた。しかし、なぜか不思議と気になる存在だった。ただ単に「感じ悪い人だなぁ」では終わらない、独特なオーラが彼を包んでいたのだ。
「日本のアール・ブリュットの立役者」。北岡氏の業績をインターネットで調べていたら、こう書かれた記事に辿り着いた。そう、アール・ブリュット。既存の美術教育を受けず、世間の影響も受けず、ただひたすら内側から湧いてくる衝動の赴くままに創作された芸術。その作り手の中には、障害のある人たちも多く含む。僕はこのようにして、そのアール・ブリュットを広め新しい障害福祉の扉を開こうとしている人たちの存在を知った。グローは滋賀県内の様々な障害福祉施設を運営する職員数600名を超える大法人だ。また、滋賀県内のみならず全国でも名が知られた社会福祉法人であり、また北岡氏はNO-MAの運営を始めとしたアール・ブリュット普及に限らず、そもそも障害福祉分野において先駆的な地域サービスを立ち上げてきた業界の著名人だった。その後、何度か職員と顔を合わせ、全国の知的障害者たちによる舞台芸術の事例を調査する仕事を皮切りに、グローに度々出入りするようになった。
北岡氏と再会したのは最初の出会いから約1年後の2009年。グローが運営する滋賀県湖南市の施設現場で打ち合わせをしていたときだ。障害者舞台芸術の全国調査が大詰めを迎え、担当職員と打ち合わせをしていた際に、突然内線が入った。職員が「アサダさん、北岡理事長がお呼びですので、会議室までどうぞ」と声をかけたのだ。襟を正して扉を開くと、そこには以前のごとく眉間に皺を寄せながら携帯電話をぐっと目に近づけて親指でひたすらボタンを弾いている北岡氏の姿があった。突如電話が鳴り「おお、〇〇くん。すまんなぁ。あの件だけどさぁ、そうそう……」と話し始める彼。さすがに手持ち無沙汰になり、どうしようか、一度退室しようかと目を泳がせていたとき、彼の机の上に一冊の本が置かれてあるのを見つけた。それは僕が当時大阪で企画した文化事業の年間報告書だった。他にも僕がこれまで手がけてきた様々なイベントのチラシもあり、この様子だと彼はついさっきまでこれらを読んでいたのだろう。ようやく電話が終わり、待ちぼうけ状態の僕を見て、彼は慌てて話しかけてきた。
「ごめんなさい! 呼んでおいて待たせちゃって。いやぁ、あなたがやっていること、すごく面白いね」
僕はその意外な反応に驚いた。その報告書は、アーティストが自宅の一部を開放し、展覧会やコンサートを各所で実施するイベントに関するもので、一見、福祉とは縁のなさそうなものだった。しかし、北岡氏は独特の嗅覚でこのようなことを言ってくれた。
「この自宅を開いて他人を招き入れる活動なんて、僕からみたら新しい“福祉”なんだよ。 地域にこういう拠点がたくさんあったら、障害者も高齢者も施設なんて通わなくても、もっと地域で助け合ってみんなで生きていけるんだよね」
そのとき、心が動いた。実は僕自身がこれはアート活動である一方で、「福祉」でもありえると、どこかで実感していたから。自宅の一室をアーティストが開放するイベントは、子育てや仕事をリタイヤしたシニア世代の活動にもヒントを与えるだろうし、空き部屋を活用して地域交流サロンにだって発展できる。そうすれば、地域のなかで困っている人同士が情報を交換し、それぞれの自宅が小さな「ケア」の拠点になってゆくだろう……。北岡氏は少ない情報から見事にこちらの狙いを当ててみせたのだ。「この人は僕の深い理解者になるかもしれない」と感じた瞬間だった。
このやりとりの後、彼は自らが生涯かけて尽力してきたアール・ブリュットの普及について、言葉は多くないが確かな熱意を持って語り出した。これからの福祉は、障害者のこととか、高齢者のことばっかりに興味を持っていてもだめ。そのためにはアートで感性を磨くことが必要。そうして感性を磨いた若い人こそが福祉にもっと関わるべき。「あなたのように」と。彼の主張はざっとそのようなものだった。そして、最後にこう言った。
「アサダくん、僕と友達になってよ」
*
この日から10年以上にわたって僕と北岡氏は深い信頼関係を築き、グローの事業パートナーとして広範な仕事を行うこととなる。本拠地である滋賀県内をはじめ、東京ほか全国各地、時に海外にまで及んだ。内容も多岐にわたる。あるときは、知的障害者とミュージシャンが共演する音楽祭を企画。またあるときは、アートによる障害者支援をテーマにシンポジウムを進行。パリやロンドンに出向き、日本のアール・ブリュット作品を海外に発信する事業にも参画した。グローが運営する「ボーダレスアート・ミュージアム NO-MA」の委員も務めた。北岡氏を筆頭に、グローで文化事業を司る企画事業部のスタッフとも親交を深め、酒も酌み交わした。
このような企画に関わるなか、僕は「もっと“現場”に関わりたい」と思うようになる。「現場」というのはもちろん、障害のある人たちが生活する施設のことだ。たまに行ってそこのメンバーたちとワークショップするのも楽しいし、取材をしにいくのも学びはある。でもやればやるほど、間接的な関わりだけでは見えてこない彼ら彼女らの「日常と地続きのアート」があるように思えてきた。そうなると、もっと「近く」に居なければ。
そう思っていた2016年ごろ、品川区が数年後に総合的な障害福祉施設を新設するという話を耳にする。グローは、他の法人と連携しながらその指定管理事業(※注3)にチャレンジしようとしていた。そのチームのなかに、後々僕が所属することになる社会福祉法人愛成会も含まれていた。ある時、僕は北岡氏に「品川の現場にすごく興味があります」と率直に伝えた。そしてしばらく時が経ち、コンペプランを具体的に練っていく段階で声がかかった。3本の柱からなるコンセプトはこうだ。障害福祉分野でありながら「医療」と連携し、地域に開かれた「食」の拠点を目指し、かつグローや愛成会が得意にしてきた「文化」も織り交ぜる。こうして、これまでの公立障害福祉施設では見られない、まったく「新しい福祉」を品川区から世界に羽ばたかせる……。
「もし、採択されたらアートディレクターとして働いてよ。」
北岡氏はこう話した。嬉しかった。ずっと抱いていた希望をこの現場で実現できそうだ。ただひとつ、条件があった。それは「愛成会の職員になること」だった。理由は二つ。一つ目は、「文化」の主対象となる成人サービス事業(特別支援学校を卒業した18歳以上を対象とした事業)を担当するのが愛成会だったということ(グローは相談支援事業の担当だった)。二つ目は、区役所とのコミュニケーションを円滑に行う上でも、指定管理事業者からさらに外注するより「中の人」になってもらう方が良いということ。これまでフリーランスの立場で仕事をしてきた僕にとって、この提案はそれなりに重い選択を迫った。しかも、慣れ親しんできたグローではなく、愛成会への所属。僕にとって愛成会は、東京の中野区にある社会福祉法人で、アール・ブリュットを発信し続けているグローの「相方のような存在」という認識だった。事実、北岡氏が愛成会の理事を兼任していたので、そう見えてきた面は大きい(後述するが、もちろん愛成会には固有の歴史があり、かつグローとは違う特徴を持ち合わせていた)。当時、北岡氏を介してしか愛成会の実態を知らなかった僕は、その法人の「中の人」になることに躊躇いがあったのだ。それでもこの仕事はやりたいと思った。だから僕は北岡氏の提案を受け入れた。そこからはひたすら品川事業の「文化」にまつわる青写真を描き、品川区に提案した。区役所の職員と何度もやりとりを重ねた。比較的、福祉に対して保守的な姿勢を取る品川区にとっては、これらは「新しすぎるチャレンジ」ゆえに受け入れられなかったものも多く、採択したうえで降りかかる課題も山積みだった。しかし、紆余曲折を経て、グローや愛成会を含むジョイントベンチャー「一般社団法人FreeUnity」が、地元の大法人に競り勝ち、採択決定。2019年から本格的に品川事業がスタートした。これが本連載でたびたび取り上げてきた、品川区立障害児者総合支援施設「ぐるっぽ」のはじまりだった。
※注3 「品川区における指定管理者制度の活用について」(品川区)参照
*
愛成会のことについて書く。2010年、グローと関わってしばらく経った31歳のとき、のちに愛成会でアール・ブリュット発信の中核を担う木村倫さん(仮名)と出会う。その年、滋賀県のNO-MAのような、障害のある人が生み出すアートの発信拠点を全国各地に創設するという、壮大なプロジェクトが立ち上がっていた。僕は事務局運営に携わり、そのとき同じく事務局スタッフとして共に働いたのが倫さんだった。活発そうな雰囲気を携えつつもどこか繊細で、人の話を丁寧にじっくり聞く人。これが、彼女に抱いた最初の印象だった。フリーランスとしていくつかの法人を渡り歩いてきた倫さんは、幼少期から絵を描くのが好きだった。また親族が福祉施設を運営していたこともあり、知的障害のある人たちとの関わりも持ってきた。彼ら彼女らの「ありのままでいる姿」に驚き、枠のない自由な創作にも心を打たれた。そんな経験から、「世の中にとって“ふつう”とは何か?」という問いを抱える10代を送る。アートに興味を持ちながらも、大学では社会福祉を専攻。その後、作り手の多くに障害のある人たちを含む、アール・ブリュットの存在に出会う。人がありのままに表現する衝動に魅せられ、非常勤スタッフとして愛成会に入職。北岡氏との出会いもあり、彼女の「福祉とアートを交差させる力」が発揮され始める。北岡氏はいつも、倫さんのことを「倫」と呼び、国内はもちろん海外にまで同行させていた。明らかに有望な若手を「育てている」という感覚があったのだろう。
倫さんと出会った2010年は、グローが主体となってパリで「アール・ブリュット ジャポネ」という大規模な展覧会が企画された。こうして、日本のアール・ブリュット、ならびに障害者による大胆な芸術表現が、海外から逆輸入される形で高い評価を受け始める。倫さんの独自の経験と見識はこの波に乗り、彼女は国内外で活躍するアール・ブリュット展のキュレーターとなった。僕はそんな彼女の活躍を、同世代の一人としてとても尊敬していた。各地で同席するたびに、互いに声を掛け合った。「ワタルさんとゆっくりお話ししたいので、またご飯食べにいきましょう!」「倫さんと何か面白いことがしたいです!」と親交を深める。僕らが会う時は、大体北岡氏も同席しているので、公の場ではお互い気を遣いながら、ミーティングの合間とか、帰り際とか、ほんの少しの立ち話だけど、「同じ空気」を共有できている感覚はあった。おそらく倫さんの側にも。当時は共に30代前半。まだキャリアとして若かったなかで、自分の名前を公にし、責任を持って企画を世に送り出す彼女の存在は、僕にとって数少ない同志であり、友人だった。
倫さんはさらにキャリアを積み重ね、いつしか愛成会の幹部(理事)にまでなる。品川事業の話が上がり始め、指定管理者採択に向けて本格的に動き出した2018年頃から、北岡氏のみならず、倫さんも含めたやりとりが始まった。2019年春に採択が決まり、前述した通り僕は特別任用スタッフとして愛成会と雇用契約を結ぶ。品川区立障害児者総合支援施設「ぐるっぽ」にて、主に成人の利用者を対象にプログラムを組み立てるアートディレクター職だ。このときから、法人理事である倫さんは僕の上司となった。しかし、彼女は今まで通り僕のことを「ワタルさん」と呼び、経営を司る幹部としての意見を言いながらも、対等に対話をする姿勢を崩さなかった。倫さんの第一印象である「人の話をじっくり聞く人」。それは時を経て互いの立場が変わっても不変で、むしろ一層、その印象は強くなった。
愛成会に入って、最初に実感したことがある。それは「強いリーダーが存在しない」ということだ。逆に言えばグローには、強すぎるほどのリーダーがいた。もちろん、北岡氏だ。「ぐるっぽ」で働くまで、愛成会よりグローとの関わりの方が強かった立場として、北岡氏の強力なリーダーシップを度々目の当たりにしてきた。グローにおいては、彼が「NO」と言えばあらゆることが「NO」になった。例えば、展覧会のチラシを作る際、デザイナーとの調整が最終段階であっても、突然、北岡氏のチェックが入り、振り出しに戻ることもあった。またトークイベントを企画する際に、彼と良好な関係ではないゲストを調整した際には、すぐにチェックが入った。自分で言うのもなんだが、彼は僕のことを気に入っていたので、ほとんど直接苦言を呈されることはなかった。しかし、スタッフを通じてやんわりと釘を刺されることが幾度とあった。僕は残念な気持ちを抱えながらも、時に反論し、時に譲歩し、また時には対立を避けて忖度した。納得できない気持ちを抱えながらも、「仕事だから」と割り切って……。グローの中で絶対的な存在である北岡氏の力は、法人を超え、時に理事を兼任する愛成会をはじめ、全国の仲間の法人に及んだ。北岡氏と近しい人の中で、彼が打ち出す福祉サービスや文化事業に面と向かって口出しをする人はまずいなかった。それほど彼は尊敬されていたし、一方で恐れられてもいた。確かに、強いリーダーシップがあってこそ、世界を飛び回る「アール・ブリュットの立役者」になれたわけだし、だからこそ厚生労働省の社会保障審議会障害者部会の委員や内閣府の障害者政策委員会の委員などを歴任し、官僚や政治家とまでパイプを築きながら、日本の障害福祉業界に大きな変化をもたらしてきたのだろう。僕自身も彼の推進力の渦中に居たわけだから、彼の飛び抜けた才能を認めざるを得ない。でも、あまりに突出して権力が集中していたことに対して、モヤモヤと感じることはあった。でもそれも、心の中のつぶやきに過ぎなかった。
そう、愛成会はそんなグローとは真逆だった。良く言えばとても平和で民主的。悪く言えば優柔不断で誰もはっきりとは決めない。着任当初は戸惑った。いろんなことを話し合っても、なかなか物事が前に進まない! でも、「誰も傷つかない」ことを大切にしているとも感じられた。現場には、そういった、平たく言えば「思いやり」とか「優しさ」のようなものがあった。利用者に対してはもちろんのこと、スタッフ同士の関係においても。また、女性のスタッフの活躍が目立った。もちろんグローの場合も、現場の支援職は女性が多い。しかし、管理職や主任やチーフ職など、主要なポストに就く人にも女性の存在があった。そこには、愛成会の歴史が関係する。愛成会は戦後まもなく、知的障害のある女性たちの施設として創設され、女性の生活の場・働く場を一貫して作り続けてきた。実際に法人本部がある中野区で運営する入所施設「メイプルガーデン」には、女性約60名が暮らし、法人理念の根底に「女性が安心して居られる場づくり」があるのだ。グローとはかなり異なる社風であり、そもそも初めての現場業務に日々翻弄されながら、僕は徐々に愛成会の一員としての立場を作り上げていった。
*
ここまで、お付き合いいただきありがとうございます。とにかく、僕は品川で「ぐるっぽ」を運営する二つの法人、グローと愛成会、そして法人の中核を担う北岡氏と倫さんととても近い関係にあった。その背景を伝えたかったので、できるだけ紙幅を取らせていただいた。続く章では、この現場のすぐそこ、その傍らであまりにも受け入れ難いハラスメントが起きていたことに触れる。近しい立場だったゆえに、「見えていたこと」、でも「見えていなかったこと」、そして「見えていたかもしれないのに見なかったことにしたこと」、について。

ちゃんと見ようとしなかったことについて書く
品川「ぐるっぽ」での新たな仕事は、生みの苦しみの連続だったけど、とても充実していた。きよしさんの指で覆われる景色(本連載 Vol.1)も、看板に描いた春日さんの大きな句点「。」(本連載 vol.2)も、華のようなかえでさんのダンス(本連載 vol.8)も、すべてこの品川の「ぐるっぽ」という現場でないと出会えない事柄だ。いろんなワークショップをやってきた。
とりわけ「体を奏でる」と書く「体奏ワークショップ」はとても人気があった。ダンスアーティストの新井英夫さんと板坂記代子さんに毎月来てもらって、決まった振り付けも音楽もない状態で、自由気ままに舞い踊った。新井さんたちはいつも素敵な小道具を用意してくれた。ある時は十数人のメンバーとスタッフが輪になって座り、等間隔に鈴を付けた長いゴム紐を両手で持ち上げながら波を描くように揺らし合う。左から右、右から左と、みんなで紐を動かす度に「チャリン〜リンリン〜」と音が鳴り、私たちの体が奏でるリズムが表出される。この輪に入れない人がいたら工夫する。
就労支援サービスを利用する翔太さん(仮名)は走ることが好き。でも仕事中はなかなかそれを叶えられない。だから広い会場を使ったこの体奏の時間では、できるだけ思う存分走ってもらうよう、スタッフも心掛けてきた。彼には鈴が付いたベルトを腰に巻いてもらった。するとゴム紐から奏でられるみんなのゆるやかな「チャリン〜リンリン〜」と、翔太さんの全力疾走によって奏でられる「チャンチャン!リン!リン!」が交響し、独特なグルーヴを生み出す。最初はスタッフが勧めていたが、ある時から翔太さん自らが進んで巻くようになった鈴付きの赤い皮ベルトは、彼にしか奏でられない楽器となった。
そう、こんな些細な行為であったとしても、それを日々積み重ねることで、「私たちはいま一緒にここに居る」という感覚が芽生えていったように思う。
*
品川区立障害児者総合支援施設「ぐるっぽ」がオープンした2019年は、指定管理者として施設運営を担う愛成会(本部:東京都中野区)やグロー(本部:滋賀県)など4つの社会福祉法人が定期的に集まり、施設の目指すべき姿を議論した。
僕は愛成会の特別雇用スタッフとなり、「文化×福祉」に関わるコンセプトづくりを担当。地域に開かれた施設運営について日々考え、品川区に提言し、一歩一歩実現させていった。僕の相談相手は、グロー理事長の北岡賢剛氏と、愛成会の理事の一人でアートディレクターの木村倫さん(仮名)の二人。そもそもこの現場に誘ってくれたのはグローの北岡氏であり、このあたりの経緯は先に触れた通りだ。
北岡氏は日本の「アール・ブリュット」の立役者であり、有力な福祉関係者はもとより、政治家や行政官僚、著名な芸能人ともパイプを持つ障害福祉業界の重鎮だった。また10年以上にわたって北岡氏と共に仕事をし、日本のアール・ブリュットを世界に発信するアートディレクター・キュレーターとして活躍してきたのが倫さんだった。
北岡氏と倫さん。この二人の上司とのやりとりを通じて、僕の戸惑いは日に日に増していった。まず背景には愛成会のガバナンスの問題があった。グローの理事長のみならず愛成会の理事も兼ねる北岡氏の権力は、僕が想像していた以上に浸透していて、その範囲は、愛成会の経営方針や予算、時に人事にまで及んだ。
2019年当時、理事長を含む理事7名のうち5名が男性であり2名が女性であったが、男性理事たちは総じて北岡氏に逆らえないイエスマンだった。「ぐるっぽ」は、中野区に根を張る愛成会にとって初めての区外の事業かつ指定管理者事業であったため、多くの理事が事業担当者として手厚く配置された。しかし、実際に愛成会の現場で実働する(他の法人をメインの職場としない)理事は、倫さんをはじめ多くはない。しかし、時折彼ら彼女らとミーティングをする際に感じてきたのは、明らかに倫さん(加えてもう一人の女性理事 ―彼女も現場勤務を兼ねる―)の立場が弱いということだ。
当時の愛成会は実質、遠方で弁護士を務める最高齢の理事長(男性)も含めて北岡氏の言うことには刃向かえなかったように見えた。僕はとても複雑な気持ちになった。なぜなら、まさに僕の愛成会の立場(特別雇用枠で他の多くのスタッフより雇用条件が良かった)は、北岡氏のその権力によって確保されたと感じたからだ。もちろん倫さんからも、僕の専門性を適確に精査した結果の正当な条件だと言ってもらえたが、どこか負い目があった。でも、そこは成果を出すしかないと割り切ったのだけど。
ともあれ、愛成会のガバナンスが適切かどうかは、疑わざるを得なかった。そう、北岡氏と倫さんはまったく対等ではなかったのだ。確かに倫さんが理事になったのは2015年からで、長年愛成会の理事を務め、かつ倫さんの活躍をサポートしてきた北岡氏は、彼女にとって上司としてあり続けたのだろう。だから、理事という同じ立場になったとしても、それ以前の上下関係が慣習的に残り続けることは容易に想像できる。でも、それだけではないと思った。彼と彼女の間の根っこに、もっと違うレベルの深い溝があるように思えたのだ。
組織のガバナンス云々といったが、もっとそれ以前の問題かもしれない。北岡氏は、会議中に倫さんの発言が終わった後、「まぁ倫の言う意見は置いておいて」とスルーして話を先に進めることが度々あった。また、時に「うん? そこまで言う必要ある?」と感じるほど、彼女の意見を強引に否定することもあった。そして、その直後に、僕に電話をかけてきて、以下のような発言をした。
「倫の言ってることは、ダメだと思うんだよ」
「彼女は何もわかってないんだ。君もそう思うだろ?」
そして、こう言われた。
「アサダくん、これからは品川のことは、僕にだけ相談すればいいよ」
一方の倫さんともよく電話で話した。彼女は決して北岡氏のことを悪く言わなかったが、しかし、こう言っていた。
「ワタルさん、私は、北岡さんのようなやり方ではない方法で、愛成会を変えたいんです」「誰もが否定されず自分らしく働ける組織にしたいんです」
倫さんの言っていることはとても正しいと思った。でも、一方で愛成会に僕を「送り込んだ」張本人である北岡氏からは「倫の言うことは聞かず、こちらに相談せよ」と言われる。これにはとても困った。僕は完全に板挟みになった。この状態が半年程続き、北岡氏からの電話の回数は日に日に増していった。
電話に出ると、また倫さんに対する不満を聞かされる。やや具体的な話になるが、北岡氏は、当時倫さんが部長を務めていた愛成会の文化セクションをなくそうと提案していた。社会貢献事業としての性格の強い文化事業は、財源を確保しにくい上に、品川事業が始まった今となっては、むしろ品川に文化事業のすべてを一元化させるべきだ、というのが彼の主張だった。グローで先駆的に文化事業を行なってきた彼が異様なまでにこのことにこだわる理由が僕にはよくわからなかった。
倫さんは中野区においても、商店街と密に連携したアール・ブリュット展に長年取り組んでいて、その素晴らしい成果は僕から見ても一目瞭然だった。文化セクションがすべて品川に統合されることは、中野区で仕事をしてきた倫さんにとって受け入れ難い提案なのは、容易に想像できた。あえて事の賛否を脇に置いたとしても、倫さんのいない宴席で、北岡氏が「みんなもそう思うだろ?」と言えば、ほとんどが「取り巻き」と化した愛成会理事や他法人の関係者も「そうですよね」と言わざるを得なかった。僕は、倫さんの思いをできる限り冷静に代弁した。でも、その場では理解してくれたように感じても、翌日また電話がかかってくる。「昨日のことだけどさ、やっぱりダメだと思うんだよ」と。倫さんからも北岡氏を説得する方法について度々相談されるようになった。正攻法で言っても跳ね返されるだけなので、どうロジックを組み立てるかを二人で膝を突き合わせて考えた。しかし一方で、僕はどこかでこう考えていたのだ。
「これはあなたたち“二人の問題”なんだから、僕を巻き込まないでくれよ……」
僕は段々憂鬱になり、これらのやりとりが半年ほど続いたあるとき、またもかかってきた北岡氏からの電話で、なかば感情的にこう言い放ってしまった。
「これ以上、僕を板挟みにしないでください!」
それ以降、さすがの彼も以前ほど彼女に関わる話をしてこなくなった。
僕はただ普通に働きたかった。自分のやるべき仕事をしたい、ただそれだけだった。でも、後になってわかった。その考えは過ちだったと。「ただ普通に」がそもそもどういう「構造」のもとで、誰の犠牲に基づいて成り立っているのか、「二人の問題」として切り捨てることが如何に深刻なことか、そこに想像力を働かせる余裕は当時の僕にはなかったのだ。
*
2019年に始まった品川での仕事が一年程経った2020年春、新型コロナウィルスが蔓延。2020年3月からは初の緊急事態宣言が発令された。基礎疾患があるメンバーもいるなか、彼ら彼女らの安全を守ることを最優先に、ダンスや音楽のワークショップも、みんなが働くレストランの運営も、地域住民との交流も自粛せざるを得なかった(※注4)。すべての会議がオンライン化されるにつれ、北岡氏と会う回数が徐々に減っていった。「コロナ鬱」という言葉も広がるなか、社会的に活躍し動き回っている人ほど、これまでの日常との落差が大きいのか、北岡氏もあまり体調が良くないように思えた。そんな中、2020年8月、北岡氏から突然こんなメールが届いた。
「周りがやかましくなってきたから、フェイスブックやめます」
以後、北岡氏との連絡が途端に取りづらくなる。メールが返ってこなくなったのだ。
一方で時期同じく2020年8月、スタッフ有志による「愛成会からハラスメントをなくす会」が立ち上がる。その数ヶ月前から、社内メールでは北岡氏などと業務上関わりの多かったスタッフを対象にしたハラスメントにまつわる内部調査が回覧されていた。
2020年10月11日、愛成会理事であり、品川区とのパイプ役を担う中山将勝氏(仮名)と電話で話す。北岡氏と連絡が取れない理由を聞くと、驚くべき返答があった。北岡氏と極めて近い関係にある中山氏の言い分は、まず倫さんが長年、北岡氏からセクシュアルハラスメントとパワーハラスメントを受けてきた“らしい”ということ。そして、愛成会でのハラスメント内部調査の結果報告も踏まえ、北岡氏の理事解任要求がなされ、北岡氏は自ら9月24日付けで理事を辞任しているということ。具体的には、理事会を牽制するチェック機構として設置されている「評議員会」(※注5)がこの事態を重く受け止め、ハラスメントに関わった理事(北岡氏)と、それを容認・黙認・同調してきた理事(中山氏を含む2名)に対して、理事の資質が問われる事案であると判断。「理事解任のための審議」を行うことを理事長に求めたのだった。
中山氏は「品川事業が忙しいのに参ったよ」といった感じで、「事実だったとしても、それは北岡さんと倫さんの“二人の問題”なんだから、法人運営の問題にまで広げないでほしい」と愚痴をこぼしていた。彼はそのことをこう喩えた。「坊主(北岡氏)憎ければ袈裟(自分)まで焼くのか」と。
なんとも言えない気持ちになった。もちろん以前から、倫さんは北岡氏との不調和について僕に話していた。でも、いつも根本的な理由は結局わからないままだった。動揺しながらも、この時は具体的な内容にまで踏み込んで聞けなかった。とにかく、何か倫さんに大変な出来事があったの“かも”しれないと思うだけで、胸が押し潰されそうになった。でも、まだ“かも”だった。その時点では、僕も中山氏の“らしい”と変わらなかった。だって、何が「真実」かなんて、わからないじゃないか……。
僕は北岡さんに何度も連絡をした。しかし、まったくの音信不通状態だった。あんなに連絡をよこしていたのに、それはないだろう!と憤りを感じた。そして、倫さんからの連絡を待った。彼女からはこの件で何か説明があるはずだと信じて。そして10月13日、倫さんから実際にLINEでメールをもらった。そのまま引用する。
「北岡さんのことを共有したいのです。ハラスメントのことです。ワタルさんはあまり聞きたくないかもしれませんが、状況を共有させていただけますと幸いです。(中略)私にとっては、かなり乱暴なやり方と理屈でがっかりする日々ですが、またワタルさんはワタルさんが受け止める理解で聞いてください。私は何も強要しませんし、どちらについてともいいませんので。私は私のできることをしていきます」
10月15日、倫さんとオンラインで話す。内容は、中山氏たちが、(中山氏たちに対する)理事解任要求を目的とした評議員会の実施を受け入れず、逆にそれら評議員たちを解任することで事態を収拾させようとしている事実だった。また中山氏は僕に電話で倫さんに対しても理事解任を検討していることを告げたのだ。えっ? どういうことなんだそれは……? 「坊主憎ければ袈裟まで焼くのか」という感情が、返す刀で評議員会の実施を拒み、そのまま倫さんに対する報復措置に出たということか。戸惑いながらも冷静さを保ち、中山氏の言い分と倫さんのそれとがまったく噛み合ってないことを伝えた。「ぐるっぽ」にとって重要な理事たちが仲間割れをしていることは今後の僕の仕事にも直接影響する事態だ。ここでも倫さんはあくまでハラスメントの具体的な内容には触れなかった。僕もそこは……、またしても聞けなかった。どう聞いていいのか、どこまで聞いていいのか、わからなかったのだ。
これを受け、10月19日、僕は彼女に以下のメールを送った。少し長いが引用する。
「(前略)アサダとしては、本件、中山さんのみからこの2ヶ月くらいの動きを比較的定点でうかがっており、また北岡さんとは一切連絡が取れない状況になり、倫さんとも本件に関しては触れ合うことがなかったため、私から聞くのではなく、時期が来たらきっと倫さんからも何かしらの共有があるだろうと思っていました。倫さんから先日話を伺った際に、まず事実として、中山さんのご説明と倫さんのご説明の両者に(現状認識の)相違がかなりあるということがわかりました。しごく当然なので、それ自体は疑問に思いません。そしてまず大前提としてあらゆるハラスメントはあってはならない、根絶しなければならないと思っていますし、自分もしている側にもいつなんどきならないか、あるいは無意識になっていないかなど常に自覚しないといけないと思っています。(中略)なので、北岡さんはもちろんのこと、中山さん、〇〇さんも「退任させられるかどうか」の前に、自らの考えをしっかり弁明する機会を設けるべしというのは同意見です。
そのうえで、少し踏み込んだことを話しますね。無礼をお許しください。実務経営的なことではありますが、品川の現場の立場からすると、やはり倫さんが今年に入ってから品川の現場にほぼお越しにならなくなり、(中略)いつのまにか、北岡さんー中山さんー△△さんが完全に品川担当理事的な体制をひいて、(品川と)中野を分断してしまったことについては、非常に残念に感じております。(後略)」
当時の僕の関心は、「ハラスメントはあってはならない」という前提に立っていたが、どこかで「自分の仕事がやりにくくなるのではないか」という打算的な考えに支配されていた。当時のメールを読み返せば、そのことは明らかだ。しかし、やはり知りたかった。本当に何があったのか……。倫さんはそれでもなお、こう繰り返していた。
「ワタルさんに同調してとも、味方になってくれということも求めません。ワタルさんの意思はワタルさんのものなので」
なんで? どうしてそこまで気を遣うの? だって大変な目に遭ったんでしょ?
だって、僕らは今でこそ上司と部下の関係だけど、それ以前から大切な同志であり、友人だよね?
確かに北岡さんは恩人だよ。でも、もし本当に何かとてつもなく痛ましいことがあったのなら……。
心の声が充満して、パンクしそうになる。
僕はいよいよ真実を知りたいと思った。怖いけど、知らなきゃいけないと思った。
10月29日、中野駅近くの喫茶店で倫さんと二人で話した。コロナ禍真っ只中の当時、福祉現場で働く私たちにとってオンラインでなく直接会うのは余程のことだった。でも、膝を付き合わせて話すべき内容だった。そこは画面越しでなくて。そして、聞いた。倫さんは泣きながらこれまであったすべての出来事を訥々と話してくれた。そして、犠牲者は倫さんだけではなかった。僕もよく知るグローの元職員である女性も、言葉にするのも躊躇われるほどのひどい性暴力とハラスメントを受けていた。僕は何も言えなかった。あまりのひどい内容に。そのことを長年ずっと抱え込んできた倫さんのその深い闇に。ただ黙って聞いた。そして確信した。「これが真実だ」と。
※注4:「空気」に言葉を与えること 言葉に頼らないこと ── コロナ禍における障害福祉現場の「自粛」をめぐっての一報告 ──(ウェブマガジン「教養と看護」)参照
※注5:評議員会は、法人運営の基本ルール・体制を決定するとともに、役員の選任・解任等を通じ、事後的に法人運営を監督する機関として位置付けられている。詳しくは社会福祉法人の経営組織(厚生労働省)参照
*
2020年11月13日。
社会福祉法人グローの理事長 北岡賢剛氏からセクハラ・パワハラを長年にわたって受けたとして、北岡氏も9月まで理事を務めていた愛成会の女性幹部である木村倫さん(仮名)とグローの元職員の鈴木朝子さん(仮名)が、北岡氏と社会福祉法人グローを相手取り、慰謝料など合計4069万円の損害賠償を求め、東京地方裁判所に提訴した。
ここからは訴状、僕が倫さんから直接聞いた話、彼女たちの記者会見、ならびに様々な報道内容から総合的に情報を補いながら書く。この連載はもとより「こここ」という媒体の性質上、あまり過激な描写で紙幅を取るのは相応しくないと考え、できるだけ簡潔かつ言葉を選んで書くが、それでも性暴力サバイバーの方などフラッシュバックの危険性がある方は、どうぞご自身の心身状態に十分留意した上で読み進めてほしい。またより詳細な実態を知りたい方は、「社会福祉法人役員による性暴力・ハラスメント裁判の原告を支える会」のホームページ(※注6)の「MEDIA」メニューに報道リンクを集めてあるので、そちらを各自あたっていただきたい。
※注6:「Dignity for All 社会福祉法人役員による性暴力・ハラスメント裁判の原告を支える会」参照
倫さんは、2008年以降、北岡氏によるパワハラ・セクハラを繰り返し受けてきた。北岡氏からの電話に3コール以内に出なければ罵倒され、気に入らないときは意図的に会議の場や業務から外され、タクシーに乗ればお尻の下に手を入れられた。上司と部下という関係を利用したハラスメントは日を追うごとに加速し、深夜にまで及ぶメールでの日常的なセクハラ発言、そして二人きりなった際に「好きだ」と言われ、無理矢理キスされたこともあったという。そして、2012年、飲み会で北岡氏に多量の酒を勧められ酷く酔った倫さんに衝撃的な出来事が起こる。目を醒ませば、北岡氏が滞在していたホテルの一室に上半身を裸にされ寝ていたのだ。下半身を覗かれた痕跡もあったが、たまたま生理用のショーツを穿いていたため、レイプは免れたという。一方、学生時代から障害のある人のアートに惹かれ、夢を抱いてグローに新卒入職した鈴木朝子さんは、採用の半年後から北岡氏からのハラスメントに悩まされることに。突然夜に携帯電話がなり北岡氏からホテルに来るよう誘われ、「好きです」「恋人気分でお願いします」といった内容のメールが何度も送られてくるように。2014年、グローでは出張先のホテルでよく行われてきた「部屋飲み」に来るよう誘われた朝子さんは、会の終わった後、一人だけ残るように指示される。北岡氏が彼女の今後のキャリアについて話しながら隣に座り、彼女の服をまくりながら胸や下半身に触れ、抱きついてきたという。覆い被さる北岡氏に対して布団にくるまりながら抵抗をしていたら、まもなくいびきが聞こえてきて、そこには全裸姿の北岡氏が寝ていた。このような凄惨な性的暴行をうけた二人は、現在まで長年PTSD(心的外傷後ストレス障害)の症状に苦しんできた。そして、周りの多くが北岡氏に逆らえないという事実を重々知っていたがゆえに、無理解や報復を恐れ、誰にも真実を打ち明けられなかったのだ。
10月に倫さんと中野の喫茶店で会って以来、僕はこれまでの北岡氏と過ごした様々な記憶を必死に手繰り寄せた。はっきりと言える。心当たりはあったのだ。北岡氏は倫さんや朝子さんに「男はいるのか?」と面白がって聞いていたのを何度も目撃してきたこと。中山氏など愛成会幹部もグローの幹部も、つまり北岡氏と付き合いが長い「取り巻き」たちはその様子を笑ってみていたこと。時には「セックスはしたのか?」といったストレートな発言もあったこと。僕は覚えている。見ていたのだ。でも、何も言えなかった。おそらく引き攣った表情で一緒になって笑い、その場をやり過ごしていたと思う。僕だって「空気」に抗えなかったんだ。倫さんや朝子さん、そして何かしらのハラスメントを受けてきたスタッフたちに、心から申し訳なく思う。
一連の報道でも度々紹介されるのが北岡氏のこの発言だ。
「振り子のように真面目なことをしたら不真面目なことをするのは自分の個性だ」
障害福祉政策で国の委員まで務め、全国に彼を崇拝する人たちが大勢いる絶対的な存在である北岡氏のなかで、「こんなに真面目に障害者のために頑張ってるんだから、これくらいいいよね!?」という気持ちがあった上での発言だと思う。また、日本のアール・ブリュットを牽引する貴重な職場だからこそ、「この仕事から外されたくない」という彼女たちの気持ちに付け込んで弄んだのだ。この発言に関しても、僕は本人の口から聞いたことがある。でもその言葉の裏で起きていた実態を知らなかった。こんなの、到底あり得ない。この原稿を書きながら今でもどこかで「おいおい北岡さん、嘘だろ!?」って思っている。でも、これは真実だと信じざるを得ない。そして、僕はちゃんと見てなかった。いや、「芽」はあったのに、見ようとしなかったのだ。
そしてこれは、「構造的な暴力」でもあるんだ。北岡氏の行為の卑劣さはもちろん個人の資質にも起因する。でも、それだけじゃない。誰も止めなかった、いや、止められなかったんだから。中山氏の「坊主(北岡氏)憎ければ袈裟(中山氏ら)まで焼くのか」という発言を思い出す。構造的な暴力において「なんで俺まで!?」という完全なミスリードを犯した中山氏らは、保身に回るあまり、本来救済されるべき倫さんに対して報復措置を取り、この場をやり過ごそうとした。
「誰にも助けを求められない」ことの原因に、そもそも「誰も助けに応じられない」という確固たる「構造」が存在すること。であれば、この構造を知り尽くした加害者がより行動をエスカレートさせるのは論理的帰結だ。そして、被害者の「声の上げられなさ」をいいことに、「ややこしいこと」にならないうちに、その被害者を(自主的であったにせよ)退職に追い込む。朝子さんはまさにそうしてグローを離れた。そして倫さんも、まさに理事解任に追い込まれそうになったではないか。彼女たちは口を揃えてこう言う。
「ただ普通に働きたかった」
「ただ普通に」。
つまるところ私たちの寄って立つ「日常」に、自明なことなど何一つないのかもしれない。

「個人」として引き受ける。「変化」のために
“「ただふつうに働きたかった」 日本の社会福祉を牽引してきた社会福祉法人役員による性暴力とパワーハラスメント被害を受けて、提訴します”
(第一回オンライン記者会見プレスリリースの見出しより引用)2020年11月16日。
社会福祉法人愛成会の理事 木村倫さん(仮名)と社会福祉法人グローの元職員の鈴木朝子さん(仮名)原告2名と原告代理人の笹本潤弁護士による第一回オンライン記者会見が開催された。その後、新聞、週刊誌、ウェブマガジン等による各種報道が加速した。記者会見に先立って11月14日、僕は自分の考えを当時連載していた医療系のウェブマガジンで表明。グロー理事長 北岡賢剛氏にまつわるこれまでの好意的な見解を自ら否定し、倫さん、朝子さんの活動に伴走することを公にした。
これら各種報道を耳にした現場(品川区立障害児者総合支援施設「ぐるっぽ」)には、これまで経験したことのない緊張感が漂い始めた。当然、メンバーやその家族から不安の声が多数聞こえてくる。メディアからの電話もかかってくる。現場の最前線に立つ支援スタッフたちは、これらの声、要請にどう応えればいいのか。しかし、中山将勝氏(仮名)をはじめとした愛成会の理事たちからはなかなか納得のいく説明がなされない。北岡氏と極めて関係が近く本人も「構造的なハラスメントに加担した」と報道で言及されてきた中山氏は、「係争中」を理由に「事実かどうかわからないから冷静に」という説明に終始した。一方、倫さんと共にハラスメントをなくそうと複数のスタッフに勤務実態を聞き取ってきたもう1人の女性理事は、涙で言葉を詰まらせながら「ハラスメントはあった」という前提に立った説明を行い、これまでと変わりなく支援業務に携わりながらも心中穏やかでないスタッフの現状を案じた。このように同じ法人の理事でもスタンスは真っ二つに分かれ、現場ではこのことを口にするのも憚れる空気が流れていく。愛成会だけではない。愛成会と同じく「ぐるっぽ」の指定管理者として同じ施設内で相談支援業務に携わるグローのスタッフとも、以前と比べぎこちなく接せざるを得なかった。
時期同じくして、「ぐるっぽ」は次期指定管理者の公募を控えていた。愛成会、グローを含む4つの法人が中心となってこの施設を運営する第1期は、2019年4月から2022年9月までの3年半。つまり2022年10月からは、このチームが継続運営するのか、はたまた別のチームが名乗りを上げ新たに参入するかのいずれかになる。その結果を決める重要な公募の〆切が間近に控えていたのだ。有難いことに、品川で新しい福祉を実現させるべく信頼関係を築いてきたメンバーやそのご家族からは、私たちのチームによる継続運営を望む声が多数あがっていた。そんな期待が膨らむ中での今回の提訴と報道は、メンバーやご家族にとってまさに晴天の霹靂だった。
あるメンバーのお母さんはこのようなことを言った。
「報道見ています。もし事実なら絶対いけないことです。でも、今回の件で、ぐるっぽから愛成会さんたちが居なくなってしまうのは残念すぎます。私たちはどうしたらいいんでしょう……?」
僕はなんて答えればいいのか、わからなかった。メンバーの家族の多くは、今回のハラスメント事案に関する僕の見解記事も読んでいた。「ぐるっぽ」の運営チームの一人である僕が「ハラスメントはあってはならない!」と意気込んで発信することは、組織を代表してハラスメントの事実を認め、表明した意見と受け止める人もいるだろう。そうなると、愛成会やグローの社会的信用は一層失われ、次期指定管理公募に多大な影響を及ぼすかもしれない。それでも、僕は「ハラスメントはあった」と認識し、だからこそ「個人の立場」から発信する責任を感じ、実際に声を上げ始めたわけだ。しかし、声を上げれば、現場の運営はより不穏になる。まるで「自分で進みながらも自分の裾を踏んでいる」ようだった。
一方で、法人関係者でありながら被害者に伴走する表明をした僕の元には、様々な人たちからメールが届くようになった。北岡氏だけでなく直属の上司からもパワハラを受けた元グロースタッフ、グローに関わりのあった行政職員や、北岡氏と近い関係にあった社会福祉法人の幹部、障害福祉とアートにまつわる研究者など。自ら受けた辛い経験を吐露してくれた人もいれば、「自分の立場では言えないことを代弁してくれた」と感謝を述べる内容もあった。
複雑だった。こうして打ち明けてくれたことで連帯できる兆しを喜びつつ、しかし、とても後ろめたかったからだ。「こんなに北岡氏と近かった僕が、どの面下げて正義を振りかざしてるんだ!」と。だから「代弁」なんかじゃない。でも、それでも、今からでもやれることがあるならやらねばならない。そう思っただけなのだ。
*
報道が始まった翌月の2020年12月中旬から、「ぐるっぽ」では大きな展覧会を開催する予定だった。障害のある人を作り手に含み、専門的な美術教育を受けず、あるがままの衝動によって生み出された独創的な表現を発信する「アール・ブリュット展 in 品川」。この展覧会に、どうしても出展してもらいたい人がいた。「ぐるっぽ」のメンバーである大上航(おおがみわたる)さんだ。僕は彼の家を度々訪ねた。そこで繰り広げられるのは「トイレ越しの交信」だ。この時期、彼は長期にわたってトイレに籠城していた。出展のために預かった絵画作品をコピーしたA4用紙をトイレの扉下の床わずか数ミリの隙間越しに手渡す。受け取った彼は何やらブツブツ言っている。しばらくしてから「マンボウ!」とタイトルが伝えられる。
「ありがとう! 航さん。これでキャプション(作品名を記載して貼る小さなパネル)を作れます!」
「うん、アサダちゃん!」
「じゃあ次はこれいきますね? いい?渡すよー」
「うん……トリ(鳥)!」
こんなトイレ越しのやりとりを作品の数だけ繰り返す。時折、トイレに持ち込んだカレンダーやチラシの裏紙に絵を描き、またiPadを使ってペイントした新作をほんの少し開けたドアの隙間越しに見せてくれた。1982年生まれの航さんはPUFFYやTOKIOなどの90年代Jポップやアイドルを好み、それら楽曲がiPadを通じてトイレ越しに聞こえてくる。それに合わせて「しーろーのパンダと〜♪」(PUFFY「アジアの純真」、1996年)と僕も合わせて歌っていたらなぜだかおもむろに停止し、一瞬で気配がなくなることも……。
「えっ……? 航さん! 大丈夫ですか?」
「……あ……あ…アサダちゃん!」
「良かった……。気絶したのかと思ったよ……。」
こんな会話を扉ごしに繰り返し、結局一度も姿を目にしない日もあったのだ。
生まれてからずっと品川区在住の航さんは、2020年の年始から「ぐるっぽ」に通い出した。地域活動支援センターでのアトリエ活動をはじめ、ショートステイ(短期入所)や生活介護サービスを利用。大きな画用紙に黒い油性ペンで、テレビや水族館などで目にした生き物の輪郭を描き、クレヨンやパステルで色を塗る。その独特な彩色のルールもさることながら、彼の絵をより際立たせるのは、文字の存在だ。描いた生き物の名前に加えて、支援スタッフなど彼にとってその時々に身近な人物の名前が書き綴られてゆく。集団はとても苦手なようで、いつも一人離れたところで誰に邪魔されることなく、自分のペースで机いっぱいにロール紙を広げ縦横無尽にモチーフを重ねる。こうして、存在しそうで存在し得ない眩い原色で彩られた独特のフォルムの生き物たちが、瑞々しく立ち現れていったのだ。
ところが2020年の夏から、航さんは「ぐるっぽ」に来られなくなった。心身共に安定しない日々が続いていると知って、その時から月に一度の自宅通いが始まった。支援現場のスタッフとして送迎以外の目的でメンバーの自宅に出向くのはイレギュラーなこと。だから、「展覧会の打ち合わせ」を理由に訪問したのだ。その理由の半分は本当だったけど、もう半分は業務とは言えない理由。なんと言うか、ただ彼と会いたかった。そして彼の母親である大上好江さんともお話したかったのだ。
航さんはハンガーストライキ状態になり、ほとんどご飯を食べず、牛乳とコーラだけを飲み、数日トイレに立て篭もっていた。時折、「痩せろー! 痩せろー!」とトイレから声が聞こえてくる。これ以上、凹みようがないほど十分痩せたお腹を覗き込むように叫び続け、トイレに座り続ける日々。こうなるともう誰にも事態を打開することはできなかった。たまたま僕が訪れた日に突如暴れ出し、テレビをなぎ倒し、ベランダから階下に物を投げようとすることもあった。両親に暴力を振るい出したのを止めに入ったとき、胸のあたりをゲンコツで何発も強く殴られた。その時の胸の痛みよりも、母・好江さんから発せられた「もうこの家には住めないかな……」という言葉の方が、生々しく思い出される。本人が「ここに住むの! 住むの!」と大声で訴えるのを、僕はなす術もなく、本人の暴れる手を静止しつつそのままただ抱きしめることしかできなかったのだ。
それでも、調子のいい日はあった。トイレから出て、父親と近所のスーパーまで散歩に出かけカラオケに行く。僕が来ることを知ってあらかじめ居間で待っていることも。そんな日は会話が止まらなかった。大量に保管された作品を一枚一枚めくりながら、航さんは「クリオネ!」「〇〇ちゃん!(大好きなスタッフの名前)」と解説してくれる。デザインのお仕事をされてきたお父さんが航さんの作品をモチーフにデザインしたイラストや、グッズ化されたハンカチなども見せてくれた。そのやりとりは、なんだかとても充実した眩い時間だった。ある時、好江さんに航さんの過去の作品を見せてもらいながら、彼が絵を描き始めたときの貴重なエピソードを聞かせてもらった。それは2012年頃、「部屋の壁」から始まったらしい。好江さんはこんな風に話してくれた。
「どうして描くようになったのかはわからないけど、あそこ(壁)に描くようになって、落ち着いたんですよね。」
とは言え、航さんの「波」はそう簡単にはおさまらなかった。それは十分わかっているが、それでもなお、彼にとって絵を描き続けることは、気分転換や趣味の範囲に留まらない、なんかもっと大きな意味があるように思えてならない。例えばそれは、自分をありのままに保つための大切な術だったり、周囲と濃密なコミュニケーションを取る切実な手立てだったんじゃないか。このような過程を経て、航さんを始めとする10組の作家との出展準備を終えた。そして、2020年12月17日から「アール・ブリュット展 まなざすかぞく」がスタートした。
この展覧会においても、ハラスメントにまつわる報道の影響は大きかった。関連するトークイベントの出演予定者からの辞退の申し出。密に連携してきた商店街の方々から、報道された内容について説明を求める声。当然のことだ。すぐに対応にあたる。「展覧会なんてやってる場合なの?」「踊ったり歌ったり、楽しんでていいの?」。僕のもとにはいつしかこんな内なる声が響きわたるように。怒りと戸惑いが入り混じる不穏な日々のなかで、いつしか僕は表現活動に対するモチベーションを失っていった。
そんななか、ある光景が僕を前に進めてくれた。
出展作品のなかでとりわけ大きな造形物。山梨県甲府市在住の20代、関根悠一郎さんが制作した「船」にまつわるエピソードだ。長さ3.1メートル、幅1.5メートル、深さ85センチもある手作りの木造船。幼い頃から絵を描くことも、オブジェをつくることも、庭を作り野菜を育てることも「当たり前にやってきた」という悠一郎さん。多彩な作風のなかでも「船」というモチーフが扱われることは多く、10代の間に数年かけて、実際に自分が乗れる船の制作を行った。しかし、その夢は当時、周囲から理解されることが少なかった。小学校高学年から幻聴と幻視が現れ、2010年にアスペルガー症候群、2013年に統合失調症と診断された彼は、独学で「病と向き合う方法」を編み出してゆく。17歳のときに「一旦完成」させたこの「船」は、彼の「生きることそのものが創作」といった態度が存分に表れている。
2020年12月15日。
開催二日前の作品搬入日に、「船」は山梨県甲府市の一軒家の庭から、この東京都品川区の「ぐるっぽ」の展示会場まで1日かけて運ばれてきた。幅がありすぎて当初搬入を予定していた通用口から入らなかったため、愛成会のスタッフ4名が後部から手で担ぎ、前部を台車に乗せてゴロゴロと「出航」させた。施設前の「元なぎさ通り」に一旦出て、ぐるっと逆側に回り込んで搬入可能なガラス戸を開け放って入れるという作戦。この「航海」が非常に美しかった。その名の通りかつては海岸線だったこの大通りも、いまとなってはビルが林立するオフィス街。たくさんの人が行き交う通りに突如として現れた大きな「船」。いい大人がそれを担いでよいしょよいしょと行進する様子は、まるでどこかの海村の儀式のようだった。通行人たちがとにかく不思議そうに眺め、時に笑いながら「わぁ!」と声をあげる。自然と僕らスタッフにも笑みが溢れてくる。なんだろう、このこそばゆいけど誇らしい感覚は。結構重いし、ちょっと恥ずかしいんだけど……すごく楽しい。いつも歩いているこの道が、渚に逆戻りしてまったく新しい光景として僕らを包み込む。残念ながらその光景はあっという間に過ぎ去り、「船」はついぞ搬入可能なガラス戸を開け放って展示会場に「着港」したのだけど。
ふと思った。
「いつ以来だろう? こんなに笑ったのは。」
大切にしないといけない日常が、守りたい居場所が確かにある。でもその日常を、その居場所の尊さを堂々と語るためには、そもそもそれらを成り立たせている土台の脆弱さに対して、目を逸らしてはいけなかったのだ。いままで僕はただ信じてきた。北岡賢剛氏を、彼や彼の周囲の人たちと僕も含めて一緒に作り上げてきた「福祉」や「アート」を。でもその「信じる」の裏で、誰かが著しく犠牲になっていたとしたら、「信じる」はそのまま「暴力」と化すだろう。活動が世間的に「良きこと」であればあるほど、思考は放棄される。その状態がいかに恐ろしいことか。そう、僕がこの事件の当事者であるならば、「良きこと」に安住していたことにこそ「当事者性」があるのだ。倫理的にはもちろんのこと、表現者として致命的だ。
多くの人たちが「良い」「正しい」と信じていることを、でも、どこかで「間違っているかもしれない」と気づくその芽を自ら摘み、ただ信じ続けるという態度は、いかに創造的でないか。つまるところ、木村倫さんや鈴木朝子さんたちに対する正義感や罪悪感としてのみでなく、自分自身の尊厳のためにも、ここは語らないといけないのだ。これは本質的には「アクティブ・バイスタンダー(※注7)」の問題ではないのかもしれない。自分に真っ向から正直に生きる人々―航さんや悠一郎さんやその他この連載で取り上げてきた多くの表現者たち―に出会ってきた僕の歴史の中で、結局は「“個人”としてどう生きたいか」に直結する問題なのだ。
※注7:アクティブ・バイスタンダーとは「行動する傍観者」のこと。ここでは、ハラスメントや暴力、差別が行われている場面で、被害を軽減するために第三者として自分ができる行動をする人を指す。
*
2021年1月19日。
僕は倫さんから依頼を受け、「愛成会とグローの性暴力とパワハラ被害者を支える会 #ただふつうに働きたかった」(現在は「Dignity for All -社会福祉法人役員による性暴力・ハラスメント裁判の原告を支える会- #ただふつうに働きたかった」)のホームページに掲載するメッセージを寄稿した。そこに書ききれなかった思いを改めてここに記したい。
僕は北岡賢剛氏のことを10年来、尊敬してきました。一緒に仕事をする機会も多く、彼から教わったことは数知れません。「ハラスメントをしても、その功績は否定されない」という論調をよく見受けます。つまり、「それはそれ、これはこれ」ということ。一方で、「功績があっても、だめなものはだめ」という意見もあります。しかし僕はそのどっちも違うと思うに至りました。ハラスメントそのものは「だめなものはだめ」なんです。その前提で聞いてほしいのですが、「功績があっても」ということわりが入った後にハラスメントが否定されているその順序に違和感があるんです。伝わりますか? むしろ問題は「“それ”があったとしても、“これ”は認められる」も「“これ”があったとしても、“それ”はだめ」も、「構造」の本質に触れていないということ。つまり時として「“それ”と“これ”とが絡まり合う構造のなかでさらなる功績も生まれ、その過程で時に誰かは排除され、尋常でない暴力が増幅されることがある」ということです。この「構造」こそ直視し、根絶しないといけない。この本質を掘らない限り、二次加害も、二次被害もなくならないのではないでしょうか。
まずは強く自覚しないといけない。この構造に気づけないでいることも、この構造に気づいているにも関わらず何も声をあげないことも、どっちももはや「加害者」になるということ。この記事を読んでいるあなたは自覚し続ける自信はありますか? 正直言えば、僕にはなかった。でも今は自覚し続けようと覚悟を決め、こうしてここに長々と文章を書いている。
裁判では、往々にして訴えていることが事実か/そうでないかに焦点があたります。確かに「事実かどうか」だけで言えば、周囲の人間は「係争中のため云々」「真偽が明確になってから」と言葉を濁せるのかもしれません。百歩譲ってだけど。しかし、被害を訴える「声」があがっていること自体に、「人」として向き合うべきではないでしょうか。僕は「構造」を前にして個人の力は無力だと思いたくない。たしかに個人の声のあげづらさは、まさに「構造」に起因する。だから「構造なんか気にせずみんな個人の立場から発言しろ!」などと安易に言いたいわけではないんです。でもね、いきなり公に向かって大声で叫べなくても、誰か身近な人にだけ、あの人この人だけには「本当はこう思っている」と伝えてみることや、言葉ではないかたち ー絵画でも写真でもダンスでも音楽でもー で表してみることや、あるいは言葉だったとしても様々な文体や独自のニュアンスで「私」という個人の向き合い方を細やかながら表現する回路は残されているのではないでしょうか。なんとか「構造」の網目から自身をすり抜けさせ、外の世界に出るその回路が。そしてさらに思うんです。こうしてこの連載でずっと綴ってきた表現にまつわる体験、つまり福祉現場でアートをやりながら個人の感性でさまざまに蔓延する「常識」という顔をした「構造」をズラし笑い飛ばしてきた経験が、まさに今こそ必要なのではないかと。そう、「別の回路」を発見するためにも。
この事件が報道された2020年11月のタイミングは、「ぐるっぽ」の次期指定管理者の公募期間中でもありました。そして、時期近く2021年1月14には「性暴力被害で理事長提訴の法人、引き続き指定管理者に 滋賀県、障害者施設の運営で」という見出しの記事(京都新聞)が出ました。この記事は、地域は違えども同じく公立(品川区立)の施設である「ぐるっぽ」の指定管理者としてとても目が離せないものでした。「ハラスメントの件で指定管理者が不採択になるくらいの制裁は受けなくてはならないのではないか」と思っている自分。しかしその一方で、「ここまで事業を頑張ってきて不採択になるのはあまりにも残念だ」という思いを持っている自分。滋賀県の記事を読んで思った。「なんだ、何もお咎めなしか。じゃあ品川ももしかして継続できるのかな……?」と。しかし、こう考える自分に対して強烈な違和感が襲ってきた。この違和感こそが「構造」に抗う芽であると思いました。社会ぐるみでなかったことにする。そのことにどう向き合うか。でも……、そこに仕事の継続はある。つまり未来がある……。これは本当にしんどい。「それはそれ、これはこれ」とは言えないだろうと憤りながらも、でも、やっぱりここは黙って「賢く」やるべきことなのか……。
いや。「中立」はあり得ない。「中立」はすなわち「現状に対する放置的容認」へとつながります。つまり「構造」への「加担者」となります。問題を掘れば掘るほど、様々なレベルで「当事者性」は増すのです。被害者を「応援する」ことは大事。でも誤解を恐れず言えばそれ以上に大切なのは、「“自分”がどう生きるか」という姿勢でこのことを引き取り、そして表現すること、だと思うのです。
*
―The world is a dangerous place, not because of those who do evil, but because of those who look on and do nothing. ―
―この世は危険なところだ。悪いことをする人がいるためではなく、それを見ながら、何もしない人がいるためだ。―
2021年1月23日。
倫さんからLINEを通じて送られてきたのは、アルバート・アインシュタインによるこの言葉だった。
「彼がこの言葉を言ったときからどのくらい時がたったでしょう。でも古い言葉と思えない鮮度に人間社会の本質を見ます。」
こう語る倫さんに僕が返したのはこの言葉だった。
―You must be the change you want to see in the world. ―
―あなたがこの世で見たいと願う変化に、あなた自身がなりなさい。―
これは僕自身がずっと大切にしてきた、マハトマ・ガンジーの言葉だ。この教えの通り生きてきたと胸を張れる自信はないが、少なくとも幾度となく助けられてきた。この世界に生きるなかで、何度も「構造」に引っ張られ、絡め取られ個人としての力が削ぎ落とされ何も言えなくなっていく状況を経験すること。それでも「私」という存在を通じて、「私」なりの方法で「この世で見たいと願う変化」を表現・体現してみること。そしてその変化を共有する仲間と出会い「一人じゃない」と実感し連帯していくこと。「そばに居る」と伝えるためにも、この言葉を倫さんと共有したかったのだ。倫さんはこう語った。
「変わらないか変わるか、対峙してみて、模索したいと思います。対峙しないで、このままの世界で生きて、終わりたくはないのです。(中略)私はここではない世界で生きてみたいと思っただけです。自分の人生が暗く悲しいものになったとしても、対峙してみて、結果をみたかったのです。暗く悲しい結果だったとしてもその方が自分としてスッキリします。生きているうちにしかあがけないので、先延ばしにせず、あがいたからには、あがける限りの力であがいてみようと思いました」
2021年1月14日に始まった、北岡氏による性暴力・ハラスメント裁判は、2023年5月、執筆時現在も継続中。2021年2月に「ぐるっぽ」の指定管理が不採択(※注8)になった愛成会ならびにグローなどによるチームは、2022年9月末で品川区から撤退した。僕は引き続き、倫さんとの対話を重ねながら、自分なりのやり方で「この世でみたい変化」になれるよう、活動を続けている。
※注8:次期指定管理が不採択に至った理由は様々に考えられるが、「ぐるっぽ」の運営を担ってきた愛成会と社会福祉法人グローが関わっているハラスメント問題(にまつわる係争事案)が結果に響いたことは、2021年2月22日、品川区議会厚生委員会における「(品川区立障害児者総合支援施設の)指定管理者の指定について」の報告および審査の際に、障害者施策推進担当課長より明言(「品川区議会議事録 厚生委員会_02/22 本文 2021-02-22」のうち発言「249」参照)があったことを付け加えておく。








性犯罪・性暴力に関わる相談窓口
Profile
![]()
-
アサダワタル
文化活動家
1979年生まれ。これまでにない不思議なやり方で他者と関わることを「アート」と捉え、音楽や言葉を手立てに、全国の市街地、福祉施設、学校、復興団地などで地域に根ざした文化活動を展開。2009年、自宅を他者にゆるやかに開くムーブメント「住み開き」を提唱し話題に。これまでkokoima(大阪堺)、カプカプ(神奈川横浜)、ハーモニー(東京世田谷)、熱海ふれあい作業所(静岡熱海)など様々な障害福祉現場に携わる。2019年より品川区立障害児者総合支援施設ぐるっぽにて、公立福祉施設としては稀有なアートディレクター職(社会福祉法人愛成会契約)として3年間勤務した後、2022年より近畿大学文芸学部文化デザイン学科特任講師に着任(2024年度より専任講師)。博士(学術)。著書に『住み開き増補版 』(ちくま文庫)、『想起の音楽』(水曜社)、『アール・ブリュット アート 日本』(編著、平凡社)など。2020年より東京芸術劇場社会共生事業企画委員。
この記事の連載Series
連載:砕け散った瓦礫の中の一瞬の星座 -ケアと表現のメモランダム-|アサダワタル
![]() vol. 102024.07.02最終回:「当事場」をつくる
vol. 102024.07.02最終回:「当事場」をつくる![]() vol. 082023.02.03どこにも向かわない「居場所」をどこまで続けられるか
vol. 082023.02.03どこにも向かわない「居場所」をどこまで続けられるか![]() vol. 072022.10.04「舟」に一緒に乗り込むこと。 ―ラジオと支援と高崎くんと [後編]
vol. 072022.10.04「舟」に一緒に乗り込むこと。 ―ラジオと支援と高崎くんと [後編]![]() vol. 062022.08.15粘る。いても、いなくても。 ―ラジオと支援と高崎くんと [中編]
vol. 062022.08.15粘る。いても、いなくても。 ―ラジオと支援と高崎くんと [中編]![]() vol. 052022.05.31生きてきた証は電波に乗って ―ラジオと支援と高崎くんと [前編]
vol. 052022.05.31生きてきた証は電波に乗って ―ラジオと支援と高崎くんと [前編]![]() vol. 042022.01.26「壁画」と「まなざし」
vol. 042022.01.26「壁画」と「まなざし」![]() vol. 032021.12.09この現場から、「考える」を耕す
vol. 032021.12.09この現場から、「考える」を耕す![]() vol. 022021.11.10句点「。」の行方
vol. 022021.11.10句点「。」の行方![]() vol. 012021.10.08指で覆われる景色
vol. 012021.10.08指で覆われる景色