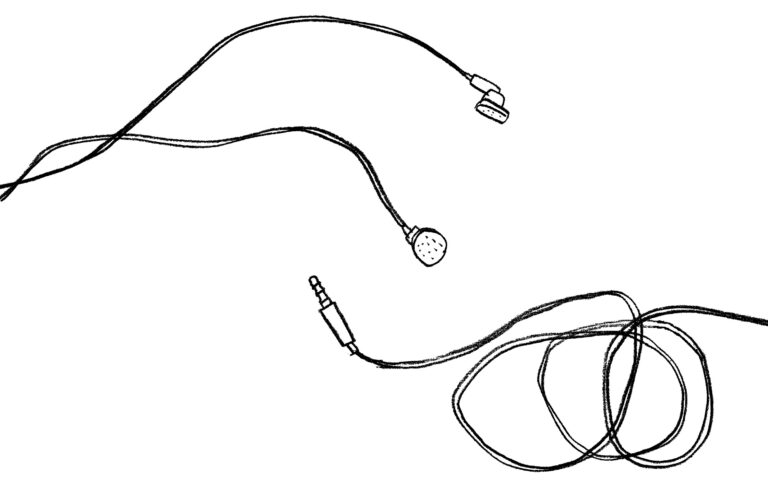この現場から、「考える」を耕す 砕け散った瓦礫の中の一瞬の星座 -ケアと表現のメモランダム-|アサダワタル vol.03
- トップ
- 砕け散った瓦礫の中の一瞬の星座 -ケアと表現のメモランダム-|アサダワタル
- この現場から、「考える」を耕す
10年以上に渡り、「ケア」と「表現」の交わる現場に関わってきた文化活動家・アサダワタルさんによるエッセイ連載。
アサダさんは、ユニークな方法で他者と関わることを「アート」と捉え、音楽や言葉を手立てに、全国の市街地、福祉施設、学校、復興団地などで文化活動を手掛けてきたアーティストです。特に障害福祉領域に関わる経験が豊富で、これまでに〈kokoima〉(大阪府)、〈カプカプ〉(神奈川県)、〈ハーモニー〉(東京都)などの福祉の現場でアートプロジェクトやワークショップを実施されてきました。2019年からは、〈品川区立障害児者総合支援施設ぐるっぽ〉(東京都)にて、障害のある人とともに創作活動・地域活動を行うコミュニティ・アートディレクターも務められています。
本連載「砕け散った瓦礫の中の一瞬の星座 -ケアと表現のメモランダム-」では、アサダさんがこれまでにケアの現場で経験してきた出来事、育まれてきた表現、人々との関係性を振り返り、揺れや戸惑いも含めて、率直に感じたこと・考えたことを綴っていただきます。(こここ編集部)
>vol.01 「指で覆われる景色」 >vol.02 「句点「。」の行方」
この現場から、「考える」を耕す
ちょっとだいぶ過去のことを。
「障害」をそのままに「表現」として捉えるという僕自身の原体験について。
2005年、26歳のとき。大阪で肢体に障害のある人たちと演劇をつくったことがはじまりだった。「脳性麻痺の当事者を役者とした演劇をやろう」。音楽活動の傍ら、当時勤めていたアートスペースに、知り合いが関わる福祉団体から声がかかった。その団体では、マキクニヒコさんというミュージシャンがホームヘルパーとして働いていた。その誘いに興味を持って、演劇プロジェクトの映像担当となった。稽古や打ち合わせなど創作のプロセスをビデオカメラで記録し、本番当日オープニングで上映しようということになったのだ。しかし、あるときマキさんから意外な提案があった。
「アサダくん、よかったらうちのメンバーたちの家に泊まって撮影せぇへん?」
僕は戸惑った。プライベートな領域にヘルパーでもない自分が、いくら演劇を面白くするためとはいえ乗り込んでいいものか。しかし、それはとても面白そうでもあった。理屈では躊躇しても、身体が「やりたい」と語りかけてきた。
「ぜひやらせてください。何か研修とか受けたほうがいいですか……?」
「ははは。いやいや、アサダくんが入浴や排泄の介助をするわけじゃないから、ただそこに居てカメラを回してくれるだけでええよ」
「なんか緊張しちゃいますね。わかりました。でも、ご本人として本当に大丈夫ですか?」
「大丈夫! ちゃんと話はつけてるし、平野さん、アサダくんが来ることすごく楽しみにしていたよ」
この演劇作品の中心人物である中年男性の平野さん(仮名)は、元消防士だった。つっかえつっかえ、吃りながら言葉を発し、いつも明るくユーモアに富み、周りの人の気持ちも明るくさせた。平野さんにはエビアレルギーがあり、かつて飲み会で間違ってエビを食べてしまいトイレに駆け込んだものの、吐瀉物を喉に詰まらせ意識喪失。そのまま発見が遅れたことで脳を損傷し、下半身不随に。発話にも障害が残った。以来、マキさんをはじめ複数のヘルパーが彼の一人暮らしをかわるがわる支えている。
介助を通じて生活に深く関わり、関係を深めてきたマキさんだからこそ、平野さんのその発話を「表現としてひらく」という着想と覚悟を得たのだろうと、演劇づくりを手伝いながら支援活動の深みを実感した。作品の中では、まるで「どもり自慢」をするかのように、平野さんたち脳性麻痺者の「言葉の訪れ」を待つことを周囲が楽しみ、いままさに発せられた僅かな言葉に全員でツッコミを入れる。最初は戸惑った。「こんなにネタにしていいのか?」と。でも当事者である彼ら彼女らから教わった。「いいんだよ。だってこれがありのままの私なのだから」と。
平野さんたち脳性麻痺当事者は、日頃からヘルパーを活用していることもあり、他者を家に招き入れることに実に慣れていた。ビデオカメラを回すことを躊躇していた僕の緊張もほぐしてくれた。僕自身も少しずつ彼らが話す言葉に耳が慣れ、会話も増えた。日常の些細な出来事をもとに、日常とほぼ地続きの演劇作品が生まれてゆく。会話が中心だが、時折歌も入る。マキさんが同僚の浜村不純さんと組んでいるバンド「コマイナーズ」が作詞作曲したものだ。代表的なのが「だんだんばたけ」だ。
“だんだんだんだんだんだんばたけ
だんだんだんだんだんだんばたけ
だんだんぼくらはめたもるほーぜ
だんだんぼくらはむとんちゃく
ぼくらを耕そう
ぼくらを差し出そう
だんだんだんだんだんだんばたけ
だんだんだんだんだんだんばたけ
だんだんぼくらはめたもるほーぜ
だんだんぼくらはぼくらでなくなる
世界がむくむく
果実はカラフル”
(「だんだんばたけ」 作詞:浜村不純 作曲:マキクニヒコ)
私たちを耕し、私たちを差し出す。そして、だんだん私たちは「私たち」ではなくなってゆく。
この歌詞は何を表しているのだろう。それは「私は私」として固執しながら自ずと引いていた境界線を崩し、もしかしたら「この人は私だったかもしれない」と、他者にもなりえる「ありえた私」を受け入れた先に、新たに産み落とされる境界なき「私たち」という動的な営み、ではないか。
「支援をする側」に知らないうちに立っていた「私」は、「支援をされる側」であるはずの「他者」から緊張をほぐされ、多くのことを教わった。演劇を通じて、ただ互いの個性や才能を突き合わせ、作品を高めてゆく。そこにはただ「その人」が存在するだけで「障害者」という属性はすぅーっと後退する。より正確に言えば、「障害」があることも含めてかたどられる「その人」が醸すコミュニケーションに魅了されることで、名付けられた種々の「障害」の名前だけで相手を見る感覚が薄らぐということかもしれない。って言うか、そもそも「障害」とは本当のところ何なんでしょうね。何だと思いますか?

もうひとつ、「問題行動」なのかもしれないが、「こだわり」とも言えるし、「美学」とも言えるし的な何かについての体験について。
2007年、28歳のとき。大阪でホームヘルパーのアルバイトを始めた。半年という短い期間ではあったが、重度の身体障害者の入浴介助や排泄介助、知的障害者の移動支援など、様々な経験をした。最初に担当したのは、特別支援学級に通う高校生・高山くん(仮名)の通学支援だった。
下校時、校門の前で高山くんを待ち伏せして、見つけたら声をかけ、一緒に駅まで歩く。その距離は僕の速度だと徒歩5分ほどだが、突然立ち止まったり、ふと電柱にそっと人差し指で触れ、映画『E.T.』のような交信を遂げた後に「にやっ」と笑ったかと思えば、おもむろに走り出し、いつもと違う方向に再び歩みをゆーっくりとゆるめたり……といった彼との不思議な逍遥において、「所要時間」という概念は無意味だった。
そうして地下鉄に乗り、自宅付近の駅に着くと必ず寄るところがあった。マクドナルド、あるいは、ミスタードーナツ。どちらに入るかは直前までわからない。マクドナルドなら、ポテトMサイズをみっつ。ミスタードーナツなら坦々麺と相場が決まっていた。ポテトなら、みっつを交互に食べる。だんだん、混ざってくる。僕はその様子をただただ眺めて食べ終わるのを待つ。坦々麺はやや介助が必要だった。なぜなら彼は手を箸代わりにして麺を掴んで食べるので、あたり一面汁まみれになるからだ。僕はトレイや机をペーパーナプキンで拭いて回った。いつもたむろしている女子高生グループが「またやっているわ」と言わんがごとく、チラチラこちらを見ている。時折コーヒーのお代わりを淹れにくる店員も怪訝そうな顔で「また机ふかなあかんやん」と言いたげ。でも、当の高山くんはそんな視線には一切気にかけず、ひたすら指と指の間にはさまった麺をジュルジュルと唇で引っ張り出すようにして胃の中に放り込んでいった。彼の表情は、それはもうとても幸せそうだった。
食べ終わったら再び歩き出した。大阪市内有数の寺町の坂道をゆっくりと連れ立って下ってゆく。高台から夕陽に向かって歩む彼の後ろ姿はなんだか風情があり、今日も赤く照らされた西の風景へと溶け込んでいった。彼はいまもう30歳近くか。変わらず元気にしているだろうか。

あれから十数年が経過し、ケアの現場により一層身を置くことが多くなった。とりわけ東京・品川の施設には、最初の2年間は朝から晩まで週4日、いまこうして書いている現在(2021年)も最低でも週2日は必ず行って、支援業務とアート企画の間のような仕事を他の支援スタッフと連携してやっている。先ほど綴った20代の頃の僕は、本業であるアートの仕事をやりつつ、あくまで別の仕事としてホームヘルパーをしていて、実感としてはつながっていたけど、仕事としては明確に分かれていた。30代になってから、いろんな福祉現場にゲスト講師として招いてもらうようになり、そこで音楽をしたり、お話をしたりすることはあった。でも、日々、一職員として現場に入ると全然違う。見える景色も、メンバーさんと分かち合う喜びも、様々な不条理による怒りや悲しみも。
個人的に大きな変化があったのは、「書けなくなった」ということだ。もちろん、多くの時間を現場に割いているので執筆時間が減ったというのもあるけど、それが言いたいのではない。いろいろ知りすぎて、感じすぎて、言葉が追いつかなくなったのだ。書いていいのかという躊躇いも増えてしまった。現場に入る前は、「これからは知らない世界をもっと体験できるから、より筆も進むはずだ」と思い込んでいた。しかし、逆だった。現場に居れば居るほど、書けなくなっていったのだ。もっと言えば、書かない方が「倫理的」なのではないか、と思うような引力が現場にはある。これは物書きとしては致命的だ。
そこを踏み越えるときに考えるのは、書くことによって生まれる「公共性」という話になるのだろうか。福祉の現場で起きていることを、言葉によってひらく。それはひとえに現場とその外側にある社会の間に「回路」を設けるということに尽きる。その回路は業務日誌からは生まれない(とても大事だけど)。ある意味、無理矢理誰かが外に向けて書かないといけない。しかしそんな使命まで与えられる現場はまずないので、個人の立場で引き取って、責任を持って書いて出す。
この連載などで、それをやっていこうと思う。基本的に誰も傷つけたくはない。僕個人の言葉に違和感を覚えたりする近しい人も居るかもしれない。でも、ひとまず書く。そして、こうやって考えている過程を、ときに躊躇いも含めて書く。なぜなら一緒に考えたいからだ。
そう。この「福祉」という現場から、「ケア」という行為を、「表現」というメガネを通じて、「考える」という営みを皆さんと一緒に耕したいから。
Profile
![]()
-
アサダワタル
文化活動家
1979年生まれ。これまでにない不思議なやり方で他者と関わることを「アート」と捉え、音楽や言葉を手立てに、全国の市街地、福祉施設、学校、復興団地などで地域に根ざした文化活動を展開。2009年、自宅を他者にゆるやかに開くムーブメント「住み開き」を提唱し話題に。これまでkokoima(大阪堺)、カプカプ(神奈川横浜)、ハーモニー(東京世田谷)、熱海ふれあい作業所(静岡熱海)など様々な障害福祉現場に携わる。2019年より品川区立障害児者総合支援施設ぐるっぽにて、公立福祉施設としては稀有なアートディレクター職(社会福祉法人愛成会契約)として3年間勤務した後、2022年より近畿大学文芸学部文化デザイン学科特任講師に着任(2024年度より専任講師)。博士(学術)。著書に『住み開き増補版 』(ちくま文庫)、『想起の音楽』(水曜社)、『アール・ブリュット アート 日本』(編著、平凡社)など。2020年より東京芸術劇場社会共生事業企画委員。
この記事の連載Series
連載:砕け散った瓦礫の中の一瞬の星座 -ケアと表現のメモランダム-|アサダワタル
![]() vol. 102024.07.02最終回:「当事場」をつくる
vol. 102024.07.02最終回:「当事場」をつくる![]() vol. 092023.07.06社会福祉法人元理事長による性暴力とハラスメントについて考えた、「そばに居る者」としての記録
vol. 092023.07.06社会福祉法人元理事長による性暴力とハラスメントについて考えた、「そばに居る者」としての記録![]() vol. 082023.02.03どこにも向かわない「居場所」をどこまで続けられるか
vol. 082023.02.03どこにも向かわない「居場所」をどこまで続けられるか![]() vol. 072022.10.04「舟」に一緒に乗り込むこと。 ―ラジオと支援と高崎くんと [後編]
vol. 072022.10.04「舟」に一緒に乗り込むこと。 ―ラジオと支援と高崎くんと [後編]![]() vol. 062022.08.15粘る。いても、いなくても。 ―ラジオと支援と高崎くんと [中編]
vol. 062022.08.15粘る。いても、いなくても。 ―ラジオと支援と高崎くんと [中編]![]() vol. 052022.05.31生きてきた証は電波に乗って ―ラジオと支援と高崎くんと [前編]
vol. 052022.05.31生きてきた証は電波に乗って ―ラジオと支援と高崎くんと [前編]![]() vol. 042022.01.26「壁画」と「まなざし」
vol. 042022.01.26「壁画」と「まなざし」![]() vol. 022021.11.10句点「。」の行方
vol. 022021.11.10句点「。」の行方![]() vol. 012021.10.08指で覆われる景色
vol. 012021.10.08指で覆われる景色