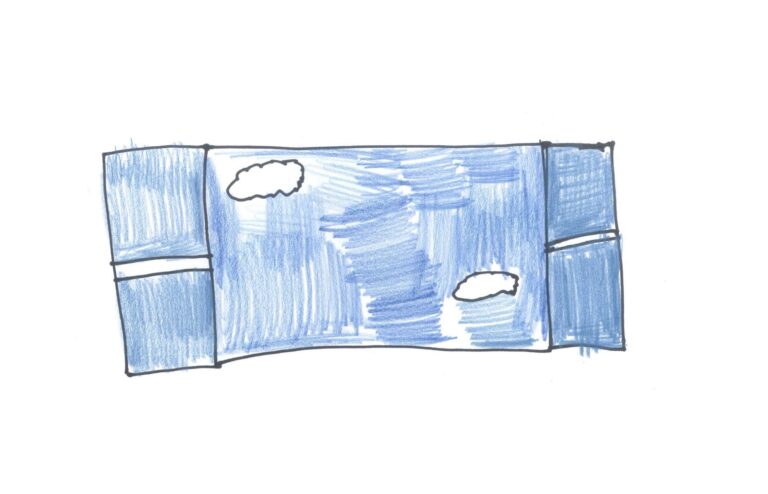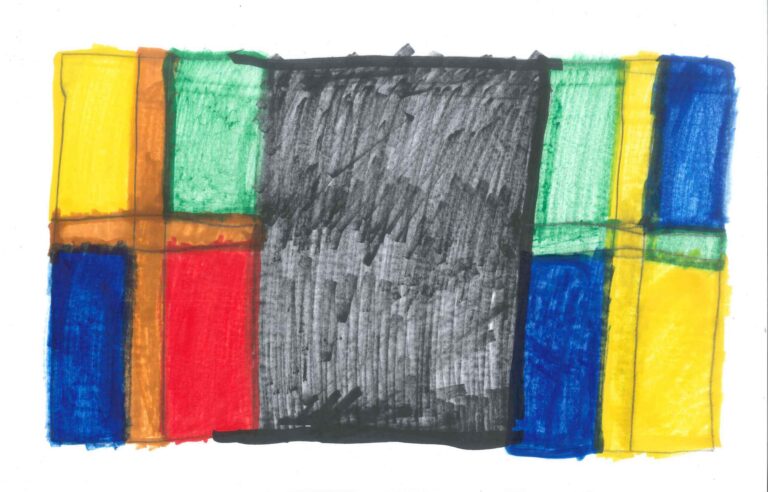アムステルダムでやっと手に入れた自分だけの自転車。運河をこえ、美術館やアトリエ目指して走らせる アムステルダムの窓から|佐藤麻衣子(マイティ) vol.04
- トップ
- アムステルダムの窓から|佐藤麻衣子(マイティ)
- アムステルダムでやっと手に入れた自分だけの自転車。運河をこえ、美術館やアトリエ目指して走らせる
水戸芸術館現代美術センターの学芸員(教育普及担当)を経て、現在フリーランスのアートエデュケーターとして活動している、マイティこと佐藤麻衣子さん。2021年秋からオランダ・アムステルダムにわたり、美術館プログラムのリサーチなどを行っています。
この連載では、マイティさんがアムステルダム滞在中に感じた日常の出来事や、訪ねた場所のエピソードなどを綴っていきます。
第4回となる今回は、自転車の街アムステルダムでついに自分の自転車を手に入れたこと、そして、その自転車で街をめぐったときのお話です。(こここ編集部・岩中)
「アムステルダムの窓から」これまでの連載記事はこちらから
- Vol.1 美術の授業がきらいだったわたしが、アートの仕事をするようになるまで
- Vol.2 初めての海外生活で知った、美術館までの「距離」
- Vol.3 コロナ禍で失われた手触りを求めて。ロックダウンのオランダで、ワークショップを通してつながったもの
自転車乗りが一番えらい街
自転車を手に入れた。地面にべったりと足が届くやつ。オレンジ色の車体はところどころへこみ、傷だらけで、ヒビの入ったサドルからは雨水がしみだす。「自転車見せてよ」モルドバ人の同僚に言われ、「見せるほどのものでも……」と、やりとりする様子を見ていた研修先のエスターが、「古いくらいがいいのよ。新しいと盗まれるから」と笑いながら諭した。
アムステルダムに来たのは、冬のはじまりだった。最初は歩くだけで緊張した。気ままに止められた自転車を避けながら、「白鳥さんが来たら、どう歩くのだろう?」と、全盲の友人のことをよく思い出していた。
横断歩道で立ち止まり、歩行者用の黄色いボタンを押すと、「タッッッ タッッッ タッッッ タッッッ」と、せっかちな音が鳴る。待ち時間のあいだに「左、左、左」と念仏のように唱える。「カタタタタタタタタターー」青になったことを知らせるリズムに急かされ、思わず右を向いてしまう。小さい頃に習った「右見てー、左見てー」の習慣が、長い時を経ても発揮されている。いかんいかん、オランダは左から車がやって来るのだ。気を取り直して左を向くと、わたしを目がけて自転車が猛スピードで突進してくる。ここは無理せず、通り過ぎるのを待つ。
オランダでは自転車乗りが王様だ。自転車専用道路を走る偉大なるお方には、歩行者もドライバーも決して逆らえない。歩行者用信号が青でもほぼ、いや、確実に止まってくれない。止まる気配すらない。くりかえすが、自転車乗りが王様なのだ。夕刻になると、家路を急ぐ車輪がびゅんびゅんと脇を通る。後方を照らす赤いライトが、すい星のごとく過ぎ去っていく。

飛び込んでみた自転車の海
3月になると、まわりの世界が動きだした。マスクの箱が積み重なり、安売りが始まった。レジの床に貼ってある1.5m刻みのテープは黒ずみ、はがれかけている。カーテンの隙間から刺すように入ってくる朝6時の光は、今日も晴れだと知らせてくれる。コロナウイルスも長くて暗い冬も、どこかに行ってしまった。
そんなとき、橋に立てかけられた自転車の写真を目にした。「身長155cmでも足がつきました」オランダで暮らす日本人が交流するインターネットの掲示板に、書き添えてあった。帰国のため、新たな引き取り手を探しているようだ。オランダには、見上げて話すくらい背の高い人が山のようにいる。そんな人たちでさえ足が届かない自転車を、サーカスのように乗りこなしているのを見ていて、自分に合ったものはないんじゃないかと諦めていた。でも、これなら大丈夫そう。新生活の相棒として迎えたくなった。先を越されまいと、すぐさま持ち主にメッセージを送ると、一番に見に行けることになった。
路面電車で待ち合わせ場所のカフェに行き、実物を目にすると、何人の手に渡ったか分からないくらい年季の入った自転車だった。サドルにまたがってみると、靴底がアスファルトを感じた。合格。その場で代金を支払い、今日からわたしがオーナーになった。
ということはつまり、自転車で帰ることを意味する。一刻も早く手に入れたいと思いつきで動いていたので、ルールを予習していなかった。時すでに遅し。「ゆっくり走れば大丈夫ですよね?」自分に言い聞かせるように前オーナーに確認し、自転車道に「えいっ」と飛び込んだ。
日中だったので、通行量はさいわい少ない。ペダルを踏むのは大丈夫、日本と一緒だ。交差点が見えてきた。前には自転車が止まっている。うしろにつける。右に見える信号には、赤い自転車マークが光っている。青に変わると、われ先にとスタートダッシュを見せる自転車乗りたち。一方、歩行者用信号は赤のまま。そっか、自転車と歩行者は動き出すタイミングが違うのか。ルールが飲み込めてきた。自転車のときは自転車用信号に注目すればいい。
ハンドサインや慣れない交差点にオロオロしながらも、近所にある広大な公園、フォンデルパークの脇を通り過ぎた。「家まであと少し」距離をつかんだ瞬間、「このままどこまでだって行けそう」今まで体験したことのない感覚が襲ってきた。うっすらと汗をかいた全身も、この自由さに同意している。自転車道には、前に進む自転車しかいない。歩く人も通行をさえぎる物もない。そして、オランダ特有の真っ平らな景色が、見渡す限り続いている。オランダ人から「移動には自転車が一番早いよ」と聞いたとき、さっぱり意味が分からなかった。でも、いざ使い始めると、信号以外わたしを止めるものは何もない。路面電車やバスのように、待ち時間や乗り換え時間がない。「だから自転車の国なんだ!」オランダに住む人のことが、ひとつ大きくわかったときだった。
映画の中で見たアムステルダム国立美術館へ
自転車の鍵を開けるのが一日のはじまりになると、自転車道を眺める余裕が出てきた。小さな子どもやお年寄り、電動車椅子や犬までもが共存している。2台が併走できる広さだから、早い人は左から追い抜いていく。まわりとの調和を気にせず、自分のペースで動ける。
通勤路には運河クルーズの出発地やビール工場がある。連なった大型バスのまわりでは、いくつもの国の言葉が飛び交う。自転車道と知らずに悠々と歩く観光客に、わたしはベルを鳴らし、あからさまに険しい表情を見せる。ハンドルを握ると、性格が変わってしまう。
今日はアムステルダム国立美術館を目指してみる。1885年にオープンした美術館には、約100万点の作品や資料が収蔵されており、レンブラントの《夜警》やフェルメールの《牛乳を注ぐ女》、ゴッホの《自画像》を見ることができる。コレクションのハイライトを集めた「名誉の間」は、観光客や学校見学で、いつもごった返している。外観はヨーロッパのお城のようなたたずまいだが、目を凝らすとすこし妙な作りだ。自転車道と歩道が建物を貫通している。
この美術館は、10年におよぶ大規模な改修工事を経て2013年に再オープンしたのだが、当初の予定から大幅に遅れた。理由のひとつに、自転車道の計画が市民に反対されたことがある。ドキュメンタリー映画『ようこそ、アムステルダム国立美術館へ』で、この騒動のようすを見ていたので、ミーハー気分が炸裂していた。自転車に乗ったままアーチをくぐると、ほてった顔がひんやりする。歩道には入館を待つ人が列をなし、ソプラノ歌手がチップを集めている。幾重にも重なる声をBGMに、もったいぶってペダルをこぐと、ミュージアム広場が視界に飛び込んできた。あざやかな青い芝生がまぶしい。
「10年後、アムステルダムの住民になって自転車で通るんだよ」映画館の椅子の上で、遠い異国の世界だと思っていたわたしに教えてあげたかった。

エリーのスタジオを訪ねる
アーティストのエリーのスタジオを訪れたのもその頃だった。大きな青いドアの前に到着すると、教会の鐘が10時を知らせた。中には、彼女の背丈を超えるスチール製の本棚が、動線に沿って奥まで置かれている。品ぞろえのよい本屋のように、村上春樹のタイトルが取りこぼすことなく詰まっている。「オランダ語訳は発売が遅いから、英語で読んでいるの」スタジオの天窓から光が差し込むと、白い空間がいっそう明るくなる。
エリーとの出会いは、アムステルダムにある社会的企業が運営するギャラリーだった。精神疾患のあるアーティストが約100名所属しており、作品の販売とレンタルをしている。地下には作品を保管する倉庫が、一階部分には展示スペースとオフィスがあり、入口付近には作品を立てかけたラックが置かれている。レコードショップでレコードを選ぶように、飾りたい作品を一点ずつ吟味できる。展覧会は月に1、2回開催され、展示替えをするたびに、オープンに合わせてパーティーが開かれる。所属アーティストやボランティアスタッフが集まるので、わたしも時々のぞきに行く。ここで出会う人と話をすると、精神的につらかった時期や働けなくなった理由がさらりと登場する。まるで、天気の話でもするかのように。
だから、エリーからもそんな話が出てくるのかなとぼんやり考えていた。エリーは作品を一つひとつ、ていねいに紹介してくれた。楽譜や詩集の上に描かれたドローイングだけでなく、素材として使っている麻の切れ端についても。

自転車に鍵をかけなかった日
ゆったりと流れる時間の中で、お腹が空いていることに気づき始めた。オランダ人は食事の時間に厳密だと聞いていたので、そろそろ出なければいけない時間だろう。
帰る前に、ずっと気になっていたことを切り出した。「あなたは精神的な問題を抱えているの?そう思えないのだけど」自分の声を耳で受け止めながら、「今の質問はまずかったな……」反射的に感じた。「なんておろかで野暮なことを聞いてしまったんだろう」後悔が覆いかぶさってくる。
エリーの目が、丸めがねから鋭くのぞく。「わたしたちが出会ったのが、あのギャラリーでなかったら、その質問をしていたかしら?」図星だった。取り繕おうとしても、言葉が散ってつながらない。「ごめんなさい」ただ言うしかなかった。
わたしをしっかり掴むような眼差しのまま、エリーは言葉を選ぶ。「謝る必要はないわ。攻めていないし、怒ってもいない。あなたは障害のある人の作品を取り扱うギャラリーってどう思う? 実を言うと、わたしは賛成できないの。だって、障害があるとかないとか関係なく、自分は自分でしょう?どんな作品をつくったって、どんな状況だって、自分でいること、『エリー』でいることが大事なんじゃないかな」
見送ろうとするエリーと一緒に、建物の出口まで歩く。見慣れた自転車が、微動だにせず青い扉の前できちんと待っていた。
中に運び入れたとき「鍵をかけなくて大丈夫よ。住民全員が知り合いだから」と言われ、わたしはいぶかしげだった。だって、アムステルダムで自転車が盗まれるのは、めずらしくないことだから。鍵だって、オートバイに使うような太くて頑丈なものが必要なくらい。慣れない海外暮らしで、なにかを無くしたくないといつもこわばっていた。
でも、今日は初めて相棒に鍵をかけなかった。「またね」自転車越しにエリーとハグをした。

Profile
![]()
-
佐藤麻衣子(マイティ)
アートエデュケーター
水戸芸術館現代美術センターで教育普及担当の学芸員(アートエデュケーター)を経て、2021年よりフリーランスで活動。普段あまり美術館に来ない人、なかなか来られない人たちに向けたプログラムを企画。さまざまな人たちとの作品鑑賞の場づくり、学校見学の受け入れやワークショップなどを行ってきた。2021年11月からオランダで、障害のある人に向けたアートプログラムの調査を行っている。あだ名はマイティ。好きなものは星野源とビール。
写真:スズキアサコ
この記事の連載Series
連載:アムステルダムの窓から|佐藤麻衣子(マイティ)
![]() vol. 082024.01.22「だれとも競争しなくていい場所」としての教室と美術館。オランダの大学院で感じたこと
vol. 082024.01.22「だれとも競争しなくていい場所」としての教室と美術館。オランダの大学院で感じたこと![]() vol. 072023.05.26見つからない家とフェルメール作品の間で
vol. 072023.05.26見つからない家とフェルメール作品の間で![]() vol. 062023.05.02300台以上の緊急車両が、子どもや家族を乗せて動物園に向かう日。「キンダー・ベイスト・フェイスト」へ
vol. 062023.05.02300台以上の緊急車両が、子どもや家族を乗せて動物園に向かう日。「キンダー・ベイスト・フェイスト」へ![]() vol. 052023.02.06大きな収蔵庫と小さなギャラリー。ロッテルダムの2つのコレクション
vol. 052023.02.06大きな収蔵庫と小さなギャラリー。ロッテルダムの2つのコレクション![]() vol. 032022.08.05コロナ禍で失われた手触りを求めて。ロックダウンのオランダで、ワークショップを通してつながったもの
vol. 032022.08.05コロナ禍で失われた手触りを求めて。ロックダウンのオランダで、ワークショップを通してつながったもの![]() vol. 022022.06.01初めての海外生活で知った、美術館までの「距離」
vol. 022022.06.01初めての海外生活で知った、美術館までの「距離」![]() vol. 012022.04.08美術の授業がきらいだったわたしが、アートの仕事をするようになるまで
vol. 012022.04.08美術の授業がきらいだったわたしが、アートの仕事をするようになるまで