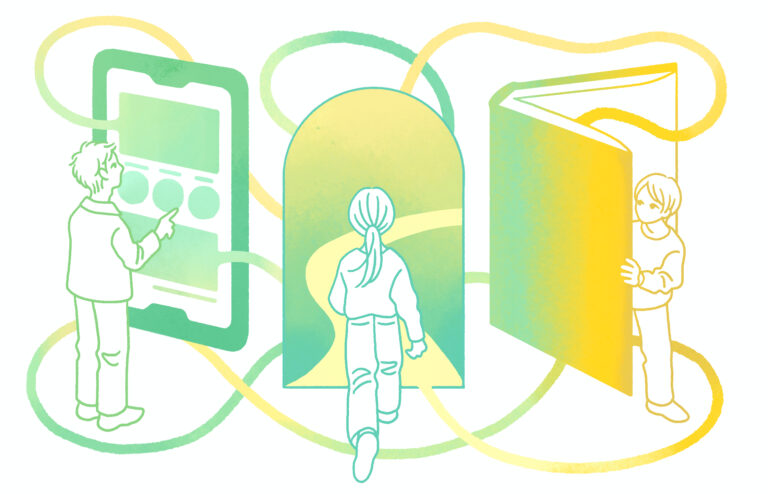いいチームってなんだろう? 多職種連携で「看取り」に取り組む特別養護老人ホーム「芦花ホーム」をたずねて “自分らしく生きる”を支えるしごと vol.30
Sponsored by 厚生労働省補助事業 令和7年度介護のしごと魅力発信等事業(情報発信事業)
- トップ
- “自分らしく生きる”を支えるしごと
- いいチームってなんだろう? 多職種連携で「看取り」に取り組む特別養護老人ホーム「芦花ホーム」をたずねて
どんな職場においても、自分と違う職種の人の業務のすべてを理解し、尊重することは難しい場面がある。エンジニアと営業職がお互いの業務の大変さを理解しきれないが故にぶつかってしまったり、厨房スタッフとホールスタッフがお互いに「自分のほうが大変だ」と思ってしまったり。チームの仲間を尊重して連携を取ることが大切とわかってはいても、それが実現できていない職場も多いだろう。
介護の業界でも同じことが言える。介護職員・看護師・医師・生活相談員・管理栄養士・ケアマネジャーなど、さまざまな職種の人が働く特別養護老人ホームでは、多職種間の連携が不可欠だ。特に利用者の最期を見送る「看取り」は、多職種が協力しあい、チーム一丸となって取り組むことが望ましい。しかし実際には、うまく連携を取れず、看取りの方針が曖昧なままケアが進んでしまう事業所も少なくないと聞く。
そんな中で、世田谷にある特別養護老人ホーム「芦花ホーム」は、かなり早い段階から看取りにおける多職種の連携を実践してきた。それを推し進めてきたのが、医師の石飛幸三さんだ。
石飛医師は令和6年に永眠されたが、その後の芦花ホームでは、いかに石飛医師の思いを継承し、多職種間でチームを築いてきたのか。現在の芦花ホームにおけるチームのあり方、介護のあり方について、主任である大里尚代さんにお話を伺った。
多職種の連携が難しいと言われている理由
京王線・芦花公園駅から徒歩7分。緑豊かな公園と高級マンションが共存する閑静な住宅街に、芦花ホームはある。

芦花ホームは平成7年に世田谷区によって設立され、令和3年に民営化された。大きな建物の中には居宅介護支援、訪問看護、デイ・ホーム、ホームヘルプサービスの各事業所が併設されている。
そんな芦花ホームには、現在、107名の利用者が暮らしている。それだけの人数が暮らしているとなると当然、「看取り」の時期を迎える方もいる。利用者の最期を見送る「看取り」は、特別養護老人ホームにとってとても大切なしごとだ。芦花ホームでは、看取り期を迎えた利用者に対し、さまざまな職種の職員がチームを組んでケアにあたる。
芦花ホームは1・2階のフロアと3・4階のフロアに分かれていて、ひとつのフロアに60人ほどの利用者が暮らし、30人ほどの職員がケアをしている。介護職員と看護師は居室担当者・利用者担当者が決まっており、利用者に変化があったときには、担当者が上長に報告し、医師や主任や係長が集まって今後の方針を検討する。そして、介護職員・看護師・医師・生活相談員・管理栄養士・ケアマネジャー・歯科衛生士・機能訓練指導員が協力しあい、方針に沿ってケアを進める。そのように、現在の芦花ホームでは「多職種連携」がうまく実践できている。

しかし、多職種間の連携がうまくできないことに悩んでいる事業所も少なくない。その理由について大里さんは、「介護業界には長い間、『介護職員と看護師がわかりあえない』という風潮がありました。介護保険制度の誕生前、医療の序列がそのまま現場に持ち運ばれていたことなどが原因で、現場において、介護職員がなかなか意見を言い出しづらい雰囲気があったんです」と話す。
遠慮なく意見を言い合える環境がなければ、チームとしての信頼関係を構築するのは難しいだろう。
大里さん:介護施設でいいチームを築くには、介護職員と看護師が対等に意見を言い合える環境が不可欠です。お互いの仕事に対してリスペクトがあると話しやすいし、連携も進めやすい。ここ最近は介護業界の風潮もだいぶ変わってきて、対等な環境も増えてきていると聞きますが、まだまだ意識は必要な段階だと思います。

石飛先生が来て、連携も看取りも変わった
芦花ホームは、職種が違っても対等に意見を言い合える、いわゆる「風通しのいい職場環境」が築けている。けれど、昔からそうだったわけではない。以前は多くの事業所と同じように「介護職員と看護師が対等に意見を言い合えない」課題を持っていたという。
そんな芦花ホームが変わったのには、医師の石飛幸三さんの存在があった。
石飛医師は「利用者を一番そばで見ているのは看護師じゃなくて介護職員だ」「介護職員は24時間365日、利用者を見ている。だから介護職員の言うことが正しい」と主張し、介護職員の意見を尊重した。そんな石飛医師に触発されて職員全体の意識も少しずつ変わっていき、介護職員も看護師も、お互いに率直な意見を言えるようになったという。大里さんが平成27年に芦花ホームに赴任したときは、すでに石飛医師による意識改革がおこなわれたあとだった。
大里さんは約4年間、石飛医師とともに働いた。石飛医師が亡くなったあとも、芦花ホームには多職種同士が対等に意見を言い合える文化は残った。
大里さん:石飛先生はすごく介護職員思いの先生で、いつも私たちに寄り添ってくれました。話し合いの場や看取りの家族面談でも、必ず「介護はどう思う?」って意見を聞いてくれるんです。私が意見を言うと、「君がそう言うんだったらそうしよう」と尊重してくれました。
大里さんは石飛医師に出会って初めて「医師に自分の意見を尊重してもらう」という経験をした。介護職員に意見を求め、素直に受け入れる医師は当時とてもめずらしかったのだという。このように、マネジャーや上司など、声の大きい人が率先して「立場に関係なくみんなが意見を言いやすい環境」を目指すことは、どんなチームにおいても必要なことなのだろう。
石飛医師が推し進めたのは、多職種間の連携だけではない。石飛医師は「その人らしく最期を迎えること」をモットーとし、芦花ホームの看取りの方針そのものを変えた。老衰に対して過度な延命治療などをおこなわない「平穏死」を提唱したのだ。病院で管に繋がれた状態で亡くなるのではなく、普段の暮らしの中で自然に最期を迎えることを理想とした。
大里さん:石飛先生が来る前は、利用者さんの最期が近づいてきたらすぐに病院に搬送していたそうです。あと、ごはんを食べられなくなった利用者さんに対して、腹部に小さな穴を開けてチューブを通し、胃に栄養を注入する「胃ろう」の処置をすることも多かったそう。けれど、石飛先生が来てからは、胃ろうをすることが減りました。
もともと胃ろうは、一時的に口から食べられなくなった患者のための処置で、延命のためのものではなかった。ほとんど動けない終末期の利用者に胃ろうで栄養を注入すると、逆流により誤嚥性肺炎や便秘を起こすこともある。石飛医師は「胃ろうは悪いことではない」としつつも、その人らしい自然な死を実現するために、できるだけ胃ろうをしない方針を取った。
医師として書籍を執筆したり講演をおこなったりと、メディアに出る機会も多かった石飛医師。気さくなべらんめぇ調で話し、職員に対して愛のある叱責をすることもあった。大里さんも一度、こっぴどく叱られたことがあるという。
大里さん:弱ってきた利用者さんに対して、治療したら延命できるかもしれないと思って、石飛先生に「病院に連れて行ってください」と言いに行ったんです。そしたら「病院に行くことによって苦しい思いをするのは利用者さんだ!」と叱られて、たしかにそうだなと思いました。でも、そんなふうに意見を言いに行ける先生は今までいなかったですね。

石飛医師が「その人らしく最期を迎えること」を理想に掲げたことで、大里さんの意識や行動も変化していった。チームとして進むべき方向性がはっきりと明示されれば、自分が取るべき行動もおのずとわかるようになるからだ。チームにとっての「理想」とは、迷いやすい山道における道標のように、メンバーを同じ方向に導いてくれる。介護施設に限らず、あらゆるチームにおいて、理想を持つことは道標のような意味を持つのだろう。
チーム内で意見が食い違ったときはとことん話し合う
看取り期に入ると褥瘡(じょくそう)もできやすくなるし、体位交換やお風呂など、一つひとつの介護を慎重におこなう必要がある。慎重になるがゆえ、チーム内で意見が食い違う場面も出てくる。たとえば、介護職員が「今だったらまだ車椅子に座れるんじゃないか」「お風呂に入れてあげたい」と思ったとしても、医師や看護師は「動かすと命に危険が及ぶ」と反対することがある。チーム内で十分な連携が取れていても、誰かの意見が採用されるということは、他の意見を持つ人の思いが叶わないということでもある。
大里さん自身も、「チームと自分の意見が噛み合わなくて、自分が望むケアができず後悔した経験があります」と話す。
だからこそ大里さんは、チーム内で意見がぶつかったときは、納得いくまで話し合うことを大切にしている。芦花ホームでは看取り期間に入った利用者一人ひとりについてミーティングを開くが、その際、大里さんは積極的に自分の意見を伝えるようにしているという。
チームの一人ひとりが、「その人らしく最期を迎えること」という理想を叶えるため、最善を尽くしている。しかし、同じ方向を向いていても、どうしても意見が食い違うこともある。そんなとき、意見を伝えずに諦めてしまっては、自分の中にずっとモヤモヤしたものが残るだろう。たとえ自分の意見が通らなかったとしても、納得いくまで話し合いができていれば、モヤモヤは残らないはずだ。
看取りにおいてチームがうまく連携を取るには、利用者をよく観察し、「この前はできていたことができなくなっている」などの小さな発見を共有することが重要だ。どんなに些細なことでも、共有するに越したことはない。スムーズな情報共有をおこなうために、芦花ホームでは「常日頃から職員同士が話しやすい環境を作っておく」ことを心がけている。
その甲斐あって、芦花ホームは職員同士の仲が良く、職種が違っても話しやすい雰囲気が醸成されている。しかし、まだ職場に慣れていない新人さんは、内心で「他職種の人には話しかけにくいな」と思っているかもしれない。大里さんは「介護職員と看護師、それぞれの上司が密にコミュニケーションを取っている姿を部下に見せることが大切」と話す。
大里さん:私は主任なので、みんなが話しやすい雰囲気を作るために、職種を問わず自分から声をかけるよう心がけています。しごとの話はもちろん、プライベートな話もしますし。新人さんには、私が看護師さんに接している様子を見て、「あ、こうやって接したらいいんだ」と学んでほしいですね。
良かったと思える看取り、後悔が残る看取り
大里さんは「一般的に特別養護老人ホームにおける看取りは、利用者が安心・安全・安楽であることが第一とされます」と話す。その上で、芦花ホームでは「最期までその人らしく生活できること」も重要視している。石飛先生が築いた文化が根付いているのだ。
大里さん:芦花ホームは、利用者さんにとってはおうちです。だから、最期まで普通の暮らしを送ることが理想。なるべくお風呂に入れてあげたいし、本人に食べる意思がありそうなら、何かしら口にできるような工夫をします。
また、大里さんは、看取り期に入った利用者の家族のことも気にかけている。医師から「そろそろお看取りの時期になります」と伝えられると、不安になる家族は多い。初めて家族を見送る人はなおさらだ。主任である大里さんは、不安になっているご家族に対して、「私は今までたくさんのお看取りを見てきましたが、苦しんで亡くなる方は見たことがありません。皆さん、苦しまずに静かに最期を迎えられています」と伝えている。
看取りにおいて、「最期までその人らしく」という芦花ホームの方針は大切だが、ご本人やご家族の意向ももちろん大切だ。芦花ホームでは、サービス利用時に「看取り」にまつわる方針をご本人やご家族に伝えたり、看取りが近くなると再度ご家族に説明をしたりしている。できるだけ、ご本人やご家族の意向を汲みたいからだ。
看取りは十人十色。大里さんの長いキャリアの中で、とても良かったと思える看取りもあれば、後悔が残る看取りもあるという。
大里さん:良かったと思えるのは、ご家族と職員数名とで利用者さんのベッドを囲んで、たくさんお話をしたお看取りです。娘さんも「昔のお母さんはこんなことがあって……」と笑いながら思い出話をされていました。そうやってみんなで和気あいあいと話している中で、利用者さんの呼吸が静かに止まったんです。娘さんが「お母さん、とっても幸せな最期だね」っておっしゃって。ご家族も職員も、涙は出てくるけど笑顔でした。
想像しただけで温かい気持ちになる。まさに「最期までその人らしく」を体現した、理想的な看取りだったのだろう。一方で、後悔の残る看取りとはどんなものだったのか。
大里さん:ご家族がいなくて独居で、誰も面会に来ない利用者さんがいたんです。そういう方が孤独な最期を迎えないよう、看取りの時期になると職員みんなで集まっていろいろな話をするんですね。だけど、一人、また一人と他の業務でその場を離れて、利用者さんが少しだけ一人になったタイミングがあって……次に見に行ったときには呼吸が止まっていました。本人が一人で逝くことを望んだのかもしれないけれど、後悔が残りますね。

大里さんは、「利用者さんが一人でいるときに呼吸が止まるのは絶対に嫌だ」と話す。何十年も生きてきた命の灯火を、たった一人で消させたくはないと。だから看取りの時期は絶対に誰かがそばにいるよう心がけているが、それでも稀に、一人で逝かせてしまうことがある。その後悔は、大里さんの中に残り続ける。
命が尽きるまでの最期の時間、大里さんは利用者とどのような話をするのか。
大里さん:入所されてから今までの思い出話をします。「あのとき、こんなこと言ってましたよね。覚えてますか~?」なんて言いながら。人って動けなくても話せなくても、耳は聞こえてるんです。だから、呼吸が止まるまで声はかけ続けますね。
職員がみんなで同じ方向を向くために
芦花ホームが看取りをする上で「最期までその人らしく」をモットーとしていることは、大里さんの話からとてもよく伝わってきた。これは石飛医師が伝えた価値観であり、大里さんはそれを継承している。
しかし一般的に、職員全員が同じ価値観を共有し、同じ方向を向くことは難しい。さまざまな職種の人が働いている職場では、立場によって見える景色も違うからなおさらだ。芦花ホームでは、大切にしている価値観をどのようにして職員全員に浸透させているのだろうか。
大里さん:浸透させるという意識でやっているわけではありませんが、とにかく思ったことははっきりと言葉にしています。「私はこうしていきたいです」という希望は特に、他職種の人にも遠慮なく言いますね。心の中で思っていても伝わりませんから。逆に相手の気持ちも言ってもらわなきゃわからないので、「どう思っていますか?」と率直に尋ねます。聞いたらみんな、遠慮なく意見を言ってくれますよ。
介護職員も看護師も医師もケアマネジャーも、芦花ホームの職員は率直に意見を交わすことで、「最期までその人らしく」という価値観を共有してきた。率直に意見を交わせるのは、信頼関係が構築できている証だろう。
では、新しく入ってきた人にその価値観を伝えるにはどうしたらいいのか。石飛医師がいた頃は、新人研修の際に直接自分の理念を伝えていたそうだ。現在は年に2回の「看取り研修」の際に、芦花ホームが大切にしている価値観を伝えているという。看取り研修は新人だけではなく、介護職員や看護師にとっても、大切なものを今一度みんなで振り返るいい機会になっている。
大里さん:新人さんに大切にしている価値観を伝えるには、自分の経験を話すことが一番だと思います。私が今までどんな気持ちで、どんなお看取りをしてきたのか。それを知ってもらうことが一番心に響くんじゃないかなと。だからこれからも、私が出会ってきた利用者さんについて、自分の言葉で伝えていきたいです。
大里さんは専門学校時代に特別養護老人ホームに見学に行った際、職員の方に「利用者さんはみんな家族みたいなものだから。ここで働いたら家族がたくさんできるよ」「特別養護老人ホームは365日24時間利用者さんと接する場所であり、本当の家族にはなれないけど家族に近い存在になれる」と言われたことで、介護の道に進んだ。妊娠中は、利用者から「あなたの子どもは私の孫」と言われたこともあった。
家族が大切かどうかは人によるが、その人らしい暮らしを願う相手のことを「家族」と呼ぶのなら、大里さんと利用者の関係はまさに「家族」と呼べるものだろう。そんな「家族」を、大里さんはもう何人も看取ってきた。泣き顔も笑顔もたくさん見て、たくさん見せてきた。その経験を胸に、これからも多くの人を看取っていく。チームで力を合わせて、最期までその人らしくいられることを願いながら。

読者アンケート実施中|抽選で〈ダブディビ・デザイン〉のアートハンカチ「Square world」をプレゼント
アンケートにお答えくださった方から抽選で5名様に、こここなイッピンでも紹介した〈ダブディビ・デザイン〉のアートハンカチ「Square world」をプレゼントいたします。
※当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
※色・柄は編集部がセレクトしたものをお送りします。
(申込期限:2026年2月28日/発送:2026年3月発送予定)
マガジンハウスの3メディアで「ケアするしごと」を特集!
〈こここ〉では連載「“自分らしく生きる”を支えるしごとー介護の世界をたずねてー」 や「ケアするしごと、はじめの一歩」を通して、さまざまな「ケアするしごと」を取り上げています。また、〈anan web〉や〈POPEYE web〉でもさまざまな記事を公開中! ぜひご覧ください。
【anan web】
・山崎怜奈さん、介護のしごとを初体験! 子どもと高齢者がともに過ごす「深川えんみち」へ
・移住して実現! 鞆の浦で“自分らしい介護”を届ける24歳の物語
・介護の仕事も自分らしく! 東京・三鷹で働く三者三様の働き方ケーススタディ
【POPEYE web】
Profile
Profile
![]()
-
大里尚代
介護主任
1978年東京都生まれ。1999年、東京福祉商経専門学校社会福祉士受験資格児童指導員学科卒。同年、世田谷区社会福祉事業団へ入職し、特別養護老人ホーム上北沢ホームで勤務。その後、世田谷区福祉人材育成センターなどの勤務を経て、2015年から特別養護老人ホーム芦花ホームにて勤務し、2016年から介護主任としてフロア業務に携わる。
この記事の連載Series
連載:“自分らしく生きる”を支えるしごと
![]() vol. 322026.01.14本から「介護にあるまなざし」に出会う。編集者、ダンサー、美術家、介護職員の選ぶ4冊
vol. 322026.01.14本から「介護にあるまなざし」に出会う。編集者、ダンサー、美術家、介護職員の選ぶ4冊![]() vol. 312025.12.26「助けて」という言葉が必要になる前に。社会福祉法人丹緑会特別養護老人ホーム栗林荘をたずねて
vol. 312025.12.26「助けて」という言葉が必要になる前に。社会福祉法人丹緑会特別養護老人ホーム栗林荘をたずねて![]() vol. 292025.12.10一人ひとりの「あたり前」を大切にできる環境とは?「あたり前の暮らしサポートセンター布施屋」をたずねて
vol. 292025.12.10一人ひとりの「あたり前」を大切にできる環境とは?「あたり前の暮らしサポートセンター布施屋」をたずねて![]() vol. 282025.12.05安心して歳を重ねられる地域とは? 社会福祉法人くらしのハーモニーをたずねて
vol. 282025.12.05安心して歳を重ねられる地域とは? 社会福祉法人くらしのハーモニーをたずねて![]() vol. 272025.11.18「ケア」を感じたマンガを教えてください。作家、社会学者、アーティスト、福祉施設長の選ぶ4作品
vol. 272025.11.18「ケア」を感じたマンガを教えてください。作家、社会学者、アーティスト、福祉施設長の選ぶ4作品![]() vol. 262025.11.10「安心できる住まい」はどう育まれる? 特別養護老人ホーム「美里ヒルズ」をたずねて
vol. 262025.11.10「安心できる住まい」はどう育まれる? 特別養護老人ホーム「美里ヒルズ」をたずねて![]() vol. 252025.03.06地域の「居場所」ってなんだろう? 佛子園「三草二木 西圓寺」をたずねて
vol. 252025.03.06地域の「居場所」ってなんだろう? 佛子園「三草二木 西圓寺」をたずねて![]() vol. 242025.02.27幅広く使われる「ケア」をどうとらえる? 向坂くじらさん、吉田真一さんと考える
vol. 242025.02.27幅広く使われる「ケア」をどうとらえる? 向坂くじらさん、吉田真一さんと考える![]() vol. 232025.01.30本から「介護にあるまなざし」に出会う。イラストレーター、哲学者、ジャーナリスト、介護福祉士の選ぶ4冊
vol. 232025.01.30本から「介護にあるまなざし」に出会う。イラストレーター、哲学者、ジャーナリスト、介護福祉士の選ぶ4冊![]() vol. 222025.01.23地域の歴史や文化とともに歩む福祉とは? ライフの学校「六郷キャンパス」をたずねて
vol. 222025.01.23地域の歴史や文化とともに歩む福祉とは? ライフの学校「六郷キャンパス」をたずねて![]() vol. 212025.01.20多世代が一緒に過ごすことで生まれる安心とは?「深川えんみち」をたずねて
vol. 212025.01.20多世代が一緒に過ごすことで生まれる安心とは?「深川えんみち」をたずねて![]() vol. 202025.01.10アーティストが滞在する福祉施設とは? 「デイサービス楽らく」をたずねて
vol. 202025.01.10アーティストが滞在する福祉施設とは? 「デイサービス楽らく」をたずねて![]() vol. 192024.12.18「助けて」と言い合える環境を育むには? 「みんなの家 タブノキ」をたずねて
vol. 192024.12.18「助けて」と言い合える環境を育むには? 「みんなの家 タブノキ」をたずねて![]() vol. 182024.12.13私もあなたも、主人公でいられるように。「DAYS BLG! はちおうじ」をたずねて
vol. 182024.12.13私もあなたも、主人公でいられるように。「DAYS BLG! はちおうじ」をたずねて![]() vol. 172024.12.12「ケア」を感じたマンガを教えてください。組織開発コンサルタント、俳優、福祉施設所長、介護福祉士の選ぶ4作品
vol. 172024.12.12「ケア」を感じたマンガを教えてください。組織開発コンサルタント、俳優、福祉施設所長、介護福祉士の選ぶ4作品![]() vol. 162024.11.08安心して歳を重ねられる町とは? 鞆の浦・さくらホームをたずねて
vol. 162024.11.08安心して歳を重ねられる町とは? 鞆の浦・さくらホームをたずねて![]() vol. 152024.03.12介護のしごとに興味をもったとき、はじめの一歩はどうすれば?
vol. 152024.03.12介護のしごとに興味をもったとき、はじめの一歩はどうすれば?![]() vol. 142024.02.27認知症を“体験”する「VR認知症」。イシヅカユウさんと体験して気づいたこと
vol. 142024.02.27認知症を“体験”する「VR認知症」。イシヅカユウさんと体験して気づいたこと![]() vol. 132024.02.22認知症のある方100人以上にインタビューをして気づいたこと。認知症未来共創ハブ代表・堀田聰子さん
vol. 132024.02.22認知症のある方100人以上にインタビューをして気づいたこと。認知症未来共創ハブ代表・堀田聰子さん![]() vol. 122024.02.20暮らしのなかで閉じる命をつないでいく 写真家/訪問看護師 尾山直子さん
vol. 122024.02.20暮らしのなかで閉じる命をつないでいく 写真家/訪問看護師 尾山直子さん![]() vol. 112024.02.19科学的な介護ってなんだろう? 福祉楽団「杜の家なりた」をたずねて
vol. 112024.02.19科学的な介護ってなんだろう? 福祉楽団「杜の家なりた」をたずねて![]() vol. 102024.02.08「老いと共に生きる」を映画から考える。編集者、映画作家、介護福祉士、福祉施設運営者の選ぶ5作品
vol. 102024.02.08「老いと共に生きる」を映画から考える。編集者、映画作家、介護福祉士、福祉施設運営者の選ぶ5作品![]() vol. 092023.12.20居場所ってなんだろう? 人が自然と集まる場所を目指す「52間の縁側」をたずねて
vol. 092023.12.20居場所ってなんだろう? 人が自然と集まる場所を目指す「52間の縁側」をたずねて![]() vol. 082023.12.13「ケア」を感じたマンガを教えてください。文学研究者、精神科医、看護師、介護福祉士、文筆家の選ぶ5作品
vol. 082023.12.13「ケア」を感じたマンガを教えてください。文学研究者、精神科医、看護師、介護福祉士、文筆家の選ぶ5作品![]() vol. 072023.12.06自然の循環に身を委ね、大地と共に生きる。「里・つむぎ八幡平」が実践する「半農・半介護」の暮らし
vol. 072023.12.06自然の循環に身を委ね、大地と共に生きる。「里・つむぎ八幡平」が実践する「半農・半介護」の暮らし![]() vol. 062023.11.29介護施設×学生シェアハウス「みそのっこ」が教えてくれる、「介護×場づくり」の可能性
vol. 062023.11.29介護施設×学生シェアハウス「みそのっこ」が教えてくれる、「介護×場づくり」の可能性![]() vol. 052023.11.10いくつになっても「働く」は楽しい。ばあちゃんたちの生きがいとビジネスの両立を目指す、株式会社うきはの宝をたずねて
vol. 052023.11.10いくつになっても「働く」は楽しい。ばあちゃんたちの生きがいとビジネスの両立を目指す、株式会社うきはの宝をたずねて![]() vol. 042023.11.07居心地の良い場所の条件ってなんだろう? 浦安にある高齢者向けの住まい「銀木犀」をたずねて
vol. 042023.11.07居心地の良い場所の条件ってなんだろう? 浦安にある高齢者向けの住まい「銀木犀」をたずねて![]() vol. 032023.10.31ケアってなんだろう? ナイチンゲール看護研究所・金井一薫さんをたずねて
vol. 032023.10.31ケアってなんだろう? ナイチンゲール看護研究所・金井一薫さんをたずねて![]() vol. 022023.10.30さまざまな命に囲まれて、心を動かして生きる。 園芸療法を行う「晴耕雨読舎」をたずねて
vol. 022023.10.30さまざまな命に囲まれて、心を動かして生きる。 園芸療法を行う「晴耕雨読舎」をたずねて![]() vol. 012023.10.11自分らしく生きるってなんだろう? 一人ひとりの人生に向き合う介護事業所「あおいけあ」をたずねて
vol. 012023.10.11自分らしく生きるってなんだろう? 一人ひとりの人生に向き合う介護事業所「あおいけあ」をたずねて