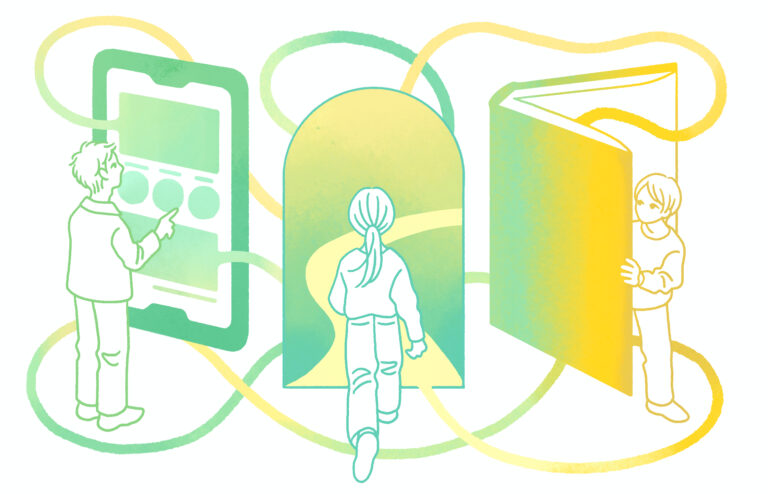「老いと共に生きる」を映画から考える。編集者、映画作家、介護福祉士、福祉施設運営者の選ぶ5作品 “自分らしく生きる”を支えるしごと vol.10
Sponsored by 厚生労働省補助事業 令和5年度介護のしごと魅力発信等事業(情報発信事業)
- トップ
- “自分らしく生きる”を支えるしごと
- 「老いと共に生きる」を映画から考える。編集者、映画作家、介護福祉士、福祉施設運営者の選ぶ5作品
“老い”という言葉から、みなさんは何を思い浮かべますか?
「誰もが年をとり、老いていく」とわかっていても、訪れていない自分の未来を想像することは難しいものです。高齢化の進む社会にあって、老いにまつわる情報はさまざまに飛び交っていますが、ネガティブな話題も少なくなく、うまく向き合えないと感じている人もいるかもしれません。
今回、編集部が目を向けたのは、私たちに身近な「映画」。古今東西の、さまざまな人生が映しだされた作品の中には、老いの可能性を広げてくれるヒントがあるのでは——そんな思いで、クリエイターや福祉関係者など5名に「老いと共に生きる」をテーマにした作品を選んでいただきました。
映画を推薦いただいた方
・伊藤ガビンさん/編集者
・久保田翠さん/福祉施設運営者
・多田智美さん/編集者
・牧原依里さん/映画作家
・矢尾眞理子さん/介護支援専門員
身近な家族のことだったり、いつかは訪れる自分の未来だったりと、さまざまな人生への重ね方ができる作品ばかりです。ぜひみなさんも観てみてください。
『グラン・トリノ』(原題『Gran Torino』)

【推薦】伊藤ガビンさん/編集者
『グラン・トリノ』は、クリント・イーストウッドが主演および監督を務めた作品です。朝鮮戦争従軍時の体験にトラウマを持ち、フォードの工場に50年務めた主人公ウォルト・コワルスキーは、息子たちにも孫たちにも嫌われています。
汚い言葉を使い、つばを吐きながらわが道を行く頑固じじいは、息子たちにとっては鬱陶しい“老害”そのものなのでしょうが、正しい行いを頑なに守る姿にグッときます。素晴らしい映画です。
なんですが、今回は映画の内容について深く触れたいわけではないんです。むしろこの映画が2008年に作られたこと。クリント・イーストウッドが78歳の時の作品であることに視線を向けたい。爺さんが爺さんを演じて、その爺さんが監督もしてて、その上ものすごく面白い作品になっている。たまらんです。
一年ほどまえから、Webに「はじめての老い」という原稿のシリーズを書いています。そのなかで気づいたことのひとつが、自分が老人に近づいてくると「どこまでも成長する人」というものに、なんだか希望を見出してしまうな、と。
芸術家は不思議な職業で、ごく稀にだけど死ぬまで傑作を作り続ける人がいます。坂本龍一さんとかね。映画監督でも、アレハンドロ・ホドロフスキーとか、最近では北野武さんとか。その年齢でまだこんな傑作が撮れるのか、とぷるぷるしてしまうんです。これって、10代の頃に同世代のスターが出てきたときに、なにかわけのわからん希望が湧いてきた感覚にとても似ていることに気づいた。今や、同年代どころか「もう俺の年齢から上の人ぜんぶ!」みたいな雑なことになってるのかもしれませんが、とにかくそうなんです。
年をとると未来に希望を抱けなくなるとよく聞きますが、凄い老人監督が撮る映画はちゃんと「老人になってからでないと撮れない」作品になっていて、それが傑作だったりすることもあって、最高なわけです。もっと見せてくれ!
『東京物語』

【推薦】久保田翠さん/福祉施設運営者
私は現在一人で暮らしている。夫は4年前に他界、重度知的障害のある長男たけしも様々な人々に支えられながら自立生活を始めた。そして長女も結婚して家を出た。家族から解放された今、改めて「孤独」について考えるようになった。
ある老夫婦が、東京に暮らす長男一家、長女一家、そして次男の未亡人を訪ねて上京する『東京物語』。この作品には「孤独」が通底していると私は思う。家族がいながら人は結局「ひとり」であり、孤独とともに生きていくのだということを語っている。いくら輝かしい功績があろうと死ぬときはひとり。一方で、孤独を知り、恐れないことがその後の人生を生きることにもつながるのだと、淡々と伝えているようにも思う。
そしてこの映画は1953年、終戦から8年後に公開されている。戦争の前と後、人々の生活や価値観が激変したとしても人は結局ひとり。そう思うと余計に、血縁を軸にした家族とではなく、人はさまざまな他者と緩く、淡々とつながればいいのだと感じさせてくれる。
そんな境地は、人生100年に迫る現代においても通じるものだったはずだ。むしろますます強くなっているかのように見える、連綿と続く家族神話(家族がなんとかする、家族だから頼っていい、などの呪いみたいなもの)は、小津安二郎が生きていたら「日本人の精神構造の衰退」とでも言われてしまうのだろうか。
『レナードの朝』(原題『Awakenings』)

【推薦】多田智美さん/編集者
ミュンヘンへ向かう機内で、約30年ぶりに『レナードの朝』を観た。原作は、脳神経科医で著作家のオリヴァー・サックスが綴った医療ノンフィクションだ。
舞台は、1969年のニューヨーク。主人公のレナードは、1920年代に流行した嗜眠性脳炎に罹患して以降約30年間、話すことも身を動かすこともできない半昏睡状態にあった。ある日、彼が過ごす慢性神経病患者専門の病棟に、もう一人の主人公、引っ込み思案の研究医セイヤーが着任するところから物語が展開する。
「慢性病なので、なにもしません。だから、ここは庭みたいなもの。水と栄養をやるだけだからね」。
着任したばかりのセイヤーを案内するスタッフの、自虐的にも聞こえるこのセリフが耳に残った。認知症高齢者の方が入居する施設を訪れたときのことを思い出したからだ。充実したプログラムがある一方で、一人ひとりの興味関心やこれまでの生き様は一度傍に置いておかれているように感じ、勝手に寂しくなったときの気持ちと重なったのだ。
映画内では、誰もが治療を諦めた環境のなか、セイヤーは患者の小さな小さな反応に目を向け、新薬を投与する。すると、レナードたちは、長い眠りから目を覚ましたかのように意識を回復。奇跡のような、ひと夏の出来事が繰り広げられる。
昏睡状態から目を覚ました人々の振る舞いはさまざまだ。自分の人生を取り戻すかのように、思い思いに好きなことをして過ごす患者たちからは、心から楽しい、嬉しいという感情が溢れ出ている。「こういう表情をどうしたら引き出せるだろう?」と試行錯誤するセイヤーの原動力は、私が日々挑む、プロセスも含めたメディアづくりに通じるものがあるのではないか。
一方、人生を謳歌すると同時に葛藤を抱くレナードの姿は、私たちに、生きる喜びとは? ケアとは? 人間の尊厳とは? とたくさんの問いも投げかけてくれる。『レナードの朝』には、答えのない「老い」というテーマと自分なりにつきあっていくヒントが散りばめられている、と思う。
『楽日』(原題『不散/Goodbye, Dragon Inn』)

【推薦】牧原依里さん/映画作家
『楽日』は台北に実在した古い映画館“福和大戲院”を舞台に、閉館する最後の一日を過ごす人たちの人間模様を描き出した作品だ。その映画館には、受付の女性、映画技師の男性、幽霊らしき女性や男性など様々な人たちが出てくる。そしてキン・フー監督の『血斗竜門の宿』(原題『龍門客棧/Dragon Inn』)が映し出されている巨大なスクリーンを前に、1,000席以上もありそうなただっ広い座席で映画を観ている、二人の老人。彼らはその映画に登場していた往年のスター俳優、シー・チュンとミャオ・ティエンだった。
上映後に二人は出会い、再会を喜ぶとともに「皆映画を見ないね」「誰も我々を覚えてない」と呟く。最後には受付の女性と、映画技師の男性が映画館から出ていく。とても静寂かつ饒舌な作品だ。
この作品を見るたびに、なんとも言えない感傷的な気持ちに陥る。本当に閉館する映画館を舞台にしているからなのか。実際にその作品に出ていた俳優だからなのか。自分でも理由がよくわからない。恐らく一人ひとりが積み重ねてきた時間が、この作品を通して実感させられるからなのだろう。
老俳優の台詞から、二人が生きてきた歴史に思いを馳せるなかで、その作品で起こった記憶と体験が観る人たちに受け継がれていく。映画の中で、映画の外で、老俳優たちが生きてきた時代を私たちは追体験する。そう、この古い映画館にいる若い二人のように。「老いと共に生きる」ということは「時間を生きる」ことであり、それは「歴史を生きる」ことでもある。その事実を直に体感させてくれる作品だ。
『おらおらでひとりいぐも』

【推薦】矢尾眞理子さん/介護支援専門員
本作は、75歳で一人暮らしをする主人公・桃子さんが、直面する孤独な日々に戸惑いながらも、自分らしく老いることを探索する作品です。
故郷を離れて、55年。桃子さんは、図書館で地球の歴史を読んだことをきっかけに、地球46億年の歴史の勉強に没頭しながら、自分自身の人生を振り返っていきます。就職、結婚、出産、子育て、夫婦関係、夫との死別、自分の生き方について。
一人暮らしで子どもや友人とも疎遠な桃子さんの対話相手は、彼女にしか見えない3人組「寂しさ1、2、3」です。家族にささげた時間を幸せに思いながらも、ひとりで生きてみたかった願いを捨てられず、本当に自分の人生を生きてきたのかと葛藤する桃子さんを、「寂しさ」たちは時に茶化し、問いかけ、共感していきます。時空を自由自在に操り、過去を捉えなおし、自分の感情を解放していく桃子さんが、夫の墓参りの道中に現れた過去の自分に「おらひとりでいぐも」(わたしはひとりでいく)と誓うように呟く姿は、観ていて清々しく感じました。
また、地球の歴史をひも解きながら、そこと一見かけ離れた自分の人生が、46億年の中に生まれた命のひとつの歴史にすぎないとも気づいた桃子さん。生まれてきた意味がわからずとも「生きている」ことを全うする、と決めたあと、図書館の司書から何度誘われても断っていた地域のサークル活動に「やってみようかしら」と一歩踏み出す場面は、思わず胸が熱くなりました。
映画全体の雰囲気はほっこりしていますが、老いがもたらす孤独もしっかり描かれている本作は、「早くお迎え来ないかな」と口にしながら、今を全うしようとする逞しさも持つ、介護現場で出会うお年寄りたちの顔を思い起こさせます。誰もが通る老いの道も、歩き方は人それぞれ自由。介護に携わるひとりとして、出会った方々がそう思える関係を築きたいと感じました。そして私自身の老いの道も、マイペースに歩いていこうと思える作品でした。
Information
紹介した映画作品について
・『グラン・トリノ』
デジタル配信中/Blu-ray 2,619円(税込)/DVD 1,572円(税込)
発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント
販売元:NBC ユニバーサル・エンターテイメント
・『東京物語』ニューデジタルリマスター
デジタル配信中/Blu-ray 5,170円(税込)/DVD 3,080円(税込)
発売元・販売元:松竹
・『レナードの朝』
デジタル配信中/Blu-ray 2,619円(税込)/DVD 1,551円(税込)
発売元・販売元:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
・『楽日』
予告編:YouTube
東京国際映画祭2022 舞台挨拶:YouTube
・『おらおらでひとりいぐも』
デジタル配信中
提供:アスミック・エース
Information
・anan webにて「介護の現場でかなえる、私らしい働き方」記事を公開中!リンクはこちら
・POPEYE webにて「福祉の現場を知りたくて。」記事を公開中!リンクはこちら
Profile
Profile
![]()
-
久保田翠
認定NPO法人クリエイティブサポートレッツ理事長
武蔵野美術大学で建築を学び、東京藝術大学大学院では環境デザインを専攻。卒業後、出身地の静岡県静岡市で、環境デザイン事務所を設立。
長女出産によって、仕事をセーブする必要に迫られ、設計事務所に所属。その後、設計事務所の浜松事務所所長として浜松に移住。
1996年長男たけしを出産。重度知的障害児のため、手術、入院、子育てに追われ、復帰ができず1999年に退職。
2000年、障害があってもたけしと家族が自由に、安心して居られる居場所づくりとしてクリエイティブサポートレッツを設立。2006年NPO法人化。2015年認定NPO法人化。アートNPOとして多様な人たちが共に生きる社会をアートを通して取り組む活動を開始。2008年個人のやりたいことをやりきる熱意を文化創造の柱とする「たけし文化センター」事業を開始し、2010年障害者の通所施設アルス・ノヴァ設立。
2011年から2014年「たけし文化センターINFOLOUNGE」、2014年から「のヴぁ公民館」を開所。独自の文化センターを展開。2016年から個人の存在自体を表現ととらえなおす「表現未満、」プロジェクト開始。障害者福祉施設に1泊2日滞在する「タイムトラベル100時間ツアー」「雑多な音楽の祭典~スタ☆タン!」をスタート。
2018年浜松市中心市街地にたけし文化センター連尺町建設し、3階建ての建物にアルス・ノヴァ、音楽スタジオと一般の人も利用できるシェアハウス、ゲストハウスが併設する。2019年から重度障害者の暮しを通して街を考える「たけしと生活研究会」をスタート。2020年ヘルパー事業所ULTRAに着手。2021年福祉から街づくりを考える「浜松ちまた会議」をスタート。
2022年中心市街地に誰もが利用できる私設私営の公民館「ちまた公民館」オープン。「表現未満、」をもとに、文化によるコミュニティづくりに取り組んでいる。
2017年度芸術選奨文部科学大臣新人賞、2022年静岡県文化奨励賞受賞。
Profile
![]()
-
多田智美
編集者/株式会社MUESUM代表/株式会社どく社共同代表
1980年生まれ。龍谷大学文学部哲学科教育心理学専攻卒業後、彩都IMI大学院スクール修了。2004年編集事務所・MUESUM設立(2014年に法人化、現在5名の編集者が在籍)、2021年に出版社・株式会社どく社設立。「出来事の創出からアーカイブまで」をテーマに、アートやデザイン、建築、福祉、地域にまつわるプロジェクトに携わり、紙やウェブの制作はもちろん、建築設計や企業理念構築、学びのプログラムづくりなど、多分野でのメディアづくりを手がける。共著に『小豆島にみる日本の未来のつくり方』(誠文堂新光社、2014)、『ローカルメディアの仕事術』(学芸出版社、2018)など。2024年1月末発行の『DIVERSITY IN THE ARTS PAPER 14』より編集を担当。
Profile
Profile
この記事の連載Series
連載:“自分らしく生きる”を支えるしごと
![]() vol. 152024.03.12介護のしごとに興味をもったとき、はじめの一歩はどうすれば?
vol. 152024.03.12介護のしごとに興味をもったとき、はじめの一歩はどうすれば?![]() vol. 142024.02.27認知症を“体験”する「VR認知症」。イシヅカユウさんと体験して気づいたこと
vol. 142024.02.27認知症を“体験”する「VR認知症」。イシヅカユウさんと体験して気づいたこと![]() vol. 132024.02.22認知症のある方100人以上にインタビューをして気づいたこと。認知症未来共創ハブ代表・堀田聰子さん
vol. 132024.02.22認知症のある方100人以上にインタビューをして気づいたこと。認知症未来共創ハブ代表・堀田聰子さん![]() vol. 122024.02.20暮らしのなかで閉じる命をつないでいく 写真家/訪問看護師 尾山直子さん
vol. 122024.02.20暮らしのなかで閉じる命をつないでいく 写真家/訪問看護師 尾山直子さん![]() vol. 112024.02.19科学的な介護ってなんだろう? 福祉楽団「杜の家なりた」をたずねて
vol. 112024.02.19科学的な介護ってなんだろう? 福祉楽団「杜の家なりた」をたずねて![]() vol. 092023.12.20居場所ってなんだろう? 人が自然と集まる場所を目指す「52間の縁側」をたずねて
vol. 092023.12.20居場所ってなんだろう? 人が自然と集まる場所を目指す「52間の縁側」をたずねて![]() vol. 082023.12.13「ケア」を感じたマンガを教えてください。文学研究者、精神科医、看護師、介護福祉士、文筆家の選ぶ5作品
vol. 082023.12.13「ケア」を感じたマンガを教えてください。文学研究者、精神科医、看護師、介護福祉士、文筆家の選ぶ5作品![]() vol. 072023.12.06自然の循環に身を委ね、大地と共に生きる。「里・つむぎ八幡平」が実践する「半農・半介護」の暮らし
vol. 072023.12.06自然の循環に身を委ね、大地と共に生きる。「里・つむぎ八幡平」が実践する「半農・半介護」の暮らし![]() vol. 062023.11.29介護施設×学生シェアハウス「みそのっこ」が教えてくれる、「介護×場づくり」の可能性
vol. 062023.11.29介護施設×学生シェアハウス「みそのっこ」が教えてくれる、「介護×場づくり」の可能性![]() vol. 052023.11.10いくつになっても「働く」は楽しい。ばあちゃんたちの生きがいとビジネスの両立を目指す、株式会社うきはの宝をたずねて
vol. 052023.11.10いくつになっても「働く」は楽しい。ばあちゃんたちの生きがいとビジネスの両立を目指す、株式会社うきはの宝をたずねて![]() vol. 042023.11.07居心地の良い場所の条件ってなんだろう? 浦安にある高齢者向けの住まい「銀木犀」をたずねて
vol. 042023.11.07居心地の良い場所の条件ってなんだろう? 浦安にある高齢者向けの住まい「銀木犀」をたずねて![]() vol. 032023.10.31ケアってなんだろう? ナイチンゲール看護研究所・金井一薫さんをたずねて
vol. 032023.10.31ケアってなんだろう? ナイチンゲール看護研究所・金井一薫さんをたずねて![]() vol. 022023.10.30さまざまな命に囲まれて、心を動かして生きる。 園芸療法を行う「晴耕雨読舎」をたずねて
vol. 022023.10.30さまざまな命に囲まれて、心を動かして生きる。 園芸療法を行う「晴耕雨読舎」をたずねて![]() vol. 012023.10.11自分らしく生きるってなんだろう? 一人ひとりの人生に向き合う介護事業所「あおいけあ」をたずねて
vol. 012023.10.11自分らしく生きるってなんだろう? 一人ひとりの人生に向き合う介護事業所「あおいけあ」をたずねて