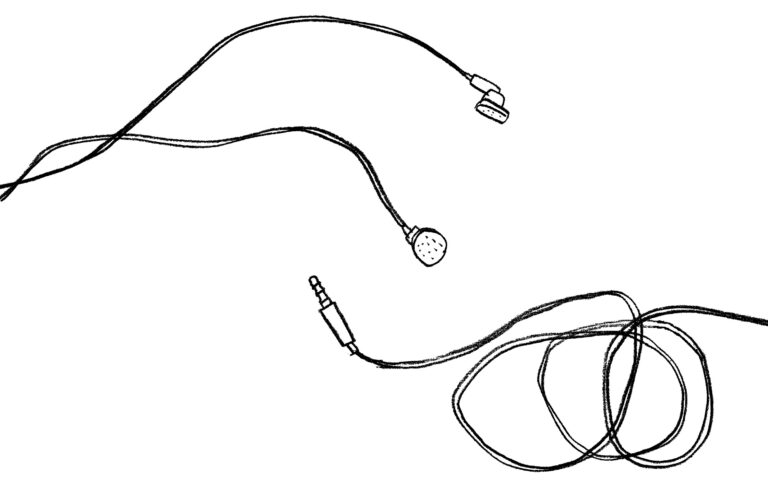10年以上に渡り、「ケア」と「表現」の交わる現場に関わってきた文化活動家・アサダワタルさんによるエッセイ連載を〈こここ〉でスタートします。
アサダさんは、ユニークな方法で他者と関わることを「アート」と捉え、音楽や言葉を手立てに、全国の市街地、福祉施設、学校、復興団地などで文化活動を手掛けてきたアーティストです。特に障害福祉領域に関わる経験が豊富で、これまでに〈kokoima〉(大阪府)、〈カプカプ〉(神奈川県)、〈ハーモニー〉(東京都)などの福祉の現場でアートプロジェクトやワークショップを実施されてきました。2019年からは、〈品川区立障害児者総合支援施設ぐるっぽ〉(東京都)にて、障害のある人とともに創作活動・地域活動を行うコミュニティ・アートディレクターも務められています。
本連載「砕け散った瓦礫の中の一瞬の星座 -ケアと表現のメモランダム-」では、アサダさんがこれまでにケアの現場で経験してきた出来事、育まれてきた表現、人々との関係性を振り返り、揺れや戸惑いも含めて、率直に感じたこと・考えたことを綴っていただきます。
テーマは、「いま、私たちは何をもって『共生』や『多様性』、それらを含む『正しさ』を考えていくべきか」ということ。簡単に答えの出ない問いですし、歩んでいく方向は何度も揺れるかもしれません。それでも、悩み、立ち止まり、言葉にしてみる試行を諦めない。そんな、アサダさんによる「ケアと表現のメモランダム(覚え書き)」を読者の皆さんと共有していただきます。(こここ編集部・中田)
指で覆われる景色
うららかな春日和。狭い歩道を行き交う自転車を避けながら、解けた靴紐を急いで結び直し、先々へと進む一群を小走りで追いかける。
「はーい。ちょっとギリギリだから次の青信号を待ちましょうか!」
なんとか先頭に追いついた僕は、そう声をかけながら最後尾を確認し、信号の切り替わりとともにゆっくりと横断歩道を渡り始めた。今日は数名の「メンバー」と、インスタントカメラを持って、近所の公園に繰り出す日。遊具が充実した品川区内でも指折りの公園では、春休み中の子どもたちが賑やかに走り回り、その様子を遠目で見守る母親同士が世間話に花を咲かせていた。
「とっちゃだめですかぁ?」
手を上げながら質問してきたのは、メンバーの一人 きよしさん(仮名)だ。スタッフからカメラを受け取った彼は、使い方の説明を聞く間もなく、「バシャッ!」とシャッターボタンをすかさず押している。
「きよしさん、お待たせしました! じゃあ始めましょう! 公園のなかで気になった風景を自由に撮ってくださいねー!」
僕の声かけが終わる間もなく、きよしさんのカメラから「ウィーンジリジリ……」とぶっきらぼうな機械音が鳴り、感熱紙にモノクロでプリントされた写真が出てくる。しかし、きよしさんをはじめ写真そのものに関心を寄せるメンバーは少ない。兎に角にも早くシャッターを切りたいのだろうか。そして、彼が撮る写真はいつも灰色にふわぁっとぼやけている。初めてその写真を観たときは「カメラの不調か?」と思ったがそうではなかった。原因は指だった。そう。彼の太く丸っこい中指と薬指がレンズの大半を覆っているのだ。
きよしさんの口癖は「マァックゥー!」である。独特な発音だがマクドナルドのことだ。特にチーズバーガーが好きらしい。でもスタッフが「一番好きなメニューはなんですか?」と質問すると「コーラ!」と堂々と答える日もある。大阪出身の僕は、日々楽しく「ボケ」倒すメンバーに対して細かい「ツッコミ」を怠らないよう、自分に課している。
「きよしさん。コーラやったら別にマックでなくてもどこにでもあるやん!」
「マックゥ行きたい! だめですかぁ?」
「さっき給食食べたばかりじゃないですか。今日は何食べました?」
「にく!」
「いやいや!今日はさかなですやん! さかな! あはははは。」
笑いの絶えないやりとりを日々重ね、彼はすっかりムードメイカーだ。しかし、きよしさんは肥満体質でもあり、医師からカロリー制限の指示が出ている。「マクドナルドに行けるのは2週間に1度」という具体的なルールもある。彼の頭のなかがどれほどマックにまつわる想念で満たされているか、実際のところわからない。なぜなら、「言葉」がきよしさんにとって最適なコミュニケーションであるとも限らないからだ。これは彼だけでなく多くの知的障害を伴う人たちに共通する点だと僕は考えている。とはいえ、「マァックゥー!」が最頻出ワードなのは間違いなく、スタッフはその一言を手がかり、足がかりにして、彼とさまざまな言葉を紡ぎ、日々コミュニケーションを深めてきた。
きよしさんの撮った写真を改めて眺める。そこにあるのは、ふくよかな中指と薬指によって強制的にフィルターをかけられた灰色の前景と微かな光を得て浮かび上がる残景だ。感熱紙にモノクロで印刷されるカメラの特性もあいまって、まるで抽象画のような様相を帯びていた。「きよしさん、指はこっち!」とスタッフが笑いながら叫んでも、まったく気に留めず確実に世界を遮る。もしかしたらこれって、きよしさんが独自の表現スタイルを生み出している、とも言えるのではないか……。
そんな妄想とも批評とも付かぬ思索を巡らせるのが僕の特性であり、ある意味ではその思索こそが僕の仕事なわけだが、それは後述する。
公園から施設に戻り、僕とスタッフ数名は、写真家の加藤甫(はじめ)さんと振り返りをした。甫さんはメンバーの日中活動の講師として、毎月「カメラワークショップ」を担当してくれている。ダウン症の息子さんがいる甫さんは、かねてから「知的障害のある人とカメラを通じて何か面白いコミュニケーションができないか」と僕に言っていた。その言葉がずっと気になっていた僕は、この福祉施設がオープンすると同時に声をかけたのだ。
僕は、きよしさんの写真が面白いと思いながらも、本人はあまり撮った写真に関心を示していないように感じ、甫さんと意見を交わし合った。
「きよしさんは、シャッターボタンを押すことの方に興味があって、写真そのものはそんなに関心ないんじゃないですかね……?」
すると甫さんからは意外な答えが返ってきた。
「きよしさんは、きっと撮ることを通じてアサダさんや他の皆さんとの反応を楽しんでいるんだと思いますよ。指でレンズを隠しちゃう彼を見て、スタッフがみんな『ああ! ゆびゆび!』とか言って笑うじゃないですか。あのリアクションがきっと嬉しいんじゃないかな」
なるほど。そういう見方があったか。
甫さんは続けてこう言った。
「きよしさんって、印刷された写真をすぐにカメラからちぎって引き離そうとするでしょ。確かにアサダさんの言う通り、撮った写真はあまり見てないかも。でも、誰かにあげたいからこそ、早くちぎっちゃうんだと思うんですよ」
このやりとりにハッとさせられた。まさに「木を見て森を見ず」。
「マァックゥー!」もそうだ。あの声を受け止め、スタッフが声を返すことでこそやりとりが生まれ、「マァックゥー!」は「マック」として認知され、翻ってきよしさんならではの独特なあの「マァックゥー!」として共感を得る。たとえ誰も反応しなくても、彼はあの指隠し撮影を続けるかもしれない。しかし、それではコミュニケーションにはならない。プリントされた写真を渡すことまで含めて、きよしさんが楽しんでいたと捉えるならば。 そう、きよしさんは写真を通じて「関係」をつくっているのだ。そう考えてもなお「写真そのものに関心はない」という言い方はできるだろうか……。
思索は深まる。そしてこう思い至る。
「そこで起きているコミュニケーションという現象そのものが、きよしさんにとっての“カメラ”であり“写真”なのだ」と。

事務連絡的背景共有。
ここまでの話は、東京都内にある品川区立障害者福祉施設「ぐるっぽ」でのこと。2019年に品川区の新しい障害福祉政策の一環として区長肝煎りでオープンしたこの施設は、公立でありながら民間法人に運営を委託する形(「指定管理者制度」と言います)でさまざまなニーズに沿った福祉サービスを展開してきた。
民間法人のうち、知的障害のある成人の支援を担うのが、社会福祉法人愛成会だ。他にも、障害のある人のニーズを受け止める「相談支援」という窓口事業を担う社会福祉法人グローや、発達障害のある児童の支援を担う法人、メンタルクリニックを運営する法人などが、地上6階、地下1階、全7フロアーにわたる大きな施設をそれぞれの専門性に則って日々運営している。僕は、成人支援を担う愛成会の契約スタッフとして勤務し、支援プログラムの企画運営を担っている。肩書きは「アートディレクター」。知的障害のある成人のメンバーたちと、絵画、造形、音楽、写真、ダンス、工作、園芸など日々、さまざまなアート活動を行ない、福祉以外の分野の人や、地域の人との接点をつくるのが仕事だ。
障害のある人が通う施設で、なぜそれほどまでアート活動を重視するのか。そしてなぜわざわざアートディレクターという専門職まで配置するのか。
それには愛成会やグローたちが取り組んできた「障害者によるアート活動」という長い歴史の蓄積があった。知的障害のある人や精神障害のある人のなかには、その個性的な行動やコミュニケーションが、時に「アート」として結実し、社会的に評価される人たちが存在する。驚くほどの解像度で日常を描いた細密画、独自の色使いと筆致で見るものを圧倒する具象画、気の遠くなるような小さな土粒を丁寧に積み重ねてゆく陶芸など。それらはときにフランス語で「アール・ブリュット(生の芸術)」と呼ばれ、ときに英語で「アウトサイダーアート」などと形容されてきた。とりわけ愛成会やグローは日本のアール・ブリュット発信のトップランナー的な存在だ。
障害のある人への支援は、その人たちができないことを支援するはもちろんのこと、すでに持っている可能性を発見し、それらを地域活動や就労の機会として社会に橋渡しをしてゆくこともとても大切。そのための最適な手立てとしてアートを重視し、日中支援のテーマのひとつとして「アート活動の充実」を掲げているのが、この「ぐるっぽ」という施設の特徴なのだ。
一方、個人的背景として、僕自身がアーティストでもある。
これまで神奈川や静岡、大阪や東京などさまざまな施設現場で、知的障害のある人、精神障害のある人たちと長らくアーティストという立場で関わってきた。障害のある人だけでなく、ときに路上生活をしている人たちと活動し、ときに東日本大震災で被災した高齢の方々と、ときに暴力の被害経験がある女性たちと、ときに過疎化が進む地域の小学生と。実に多様な背景を持った人たちと、音楽をはじめとしたさまざまなアート活動を行なってきた。
アートだからこそできる、人と人との出会い方、つながり方、個性の尊重、尊厳の回復、社会参加があると、身をもって感じてきた。とはいえ、何もかも上手くいくことなんてなく、戸惑うことも多々ありながら。
だからこうして、現場での経験を通して思ったことを、ときにはっきり、ときに揺れながら、この場を借りて素直に書いていきたいと思っている。
― ― ― ― ―
冒頭のきよしさんのことを改めて。
カメラワークショップで撮影される彼の写真に指がかからないようにすることはできるかもしれない。でも、その必要性が本当にあるのかどうかから、少々思索したい。
たとえば「写真はこうやって撮ります」という方法を伝えたり、あるいは何か道具を使ってできるように支援し、しかしそれでも本人が「指覆い」を続けるとする。そのとき、「この現場において、『写真の一般的な撮り方』という社会的規範が本当に必要か」と、立ち止まって考えられるのが、「創作(アート)」を通じて体感できる本質的な美的・感性的価値だと、僕は思っている。
「矯正」や「訓練」をしない道を見出すため、社会的な良し悪しの判断を宙吊りにし、そこに現れたものをその人の「表現」と捉えていく。そういった活動の積み重ねが、支援スタッフの「内なる規範」をも揺るがすとき、「この社会に生きる」ということを批判的に省みる機会・装置としてカメラワークショップのような「現場」が機能するのであって、それは広い意味での「福祉」(幸せについて追求する場!)に通ずるのではないか。
「本人がどうしたいか」という意思確認は、支援スタッフのスキルとして問われるが(専門的には「意思決定支援」と言う)、コミュニケーションが成立しているかどうかは常に悩みながらの日々というのが、正直な現場感覚だと思う。本人が“本当に”どうしたいかは、結局のところはっきりとはわからないことが多い。そのなかで、仮“説”的に「こうなのではないか…?」という選択を日々積み重ね、利用者と支援者は関係性を築き上げ、いつしかコミュニケーションの型のようなものを生み出してゆく。しかしその「型」ですら本来は仮“設”的なのであり、それをそのまま続けるのがいいと支援スタッフも思っていないことが多い。それは間違いなく言える。
創作活動のプロセスには、自由さの担保のために、細やかな意思決定の連続が存在する。たとえば、メンバーの「それを今やりたい(のではないか)」は、次の制作段階の前条件や制約(「ここに今穴を開けてしまうとあとで紐を通しにくくなる」など)にもなるので、慎重に考えつつも、しかし前には進めなければならない。その過程で、本人が本当に「そうしたかった」のかどうかの判断を難しくさせる身体的・コミュニケーション的な特性、いうならば「くせ」のようなものが発揮された形で生まれた作品は、「そうするしかなかった!」(指でレンズが隠れた!)をどう「表現」として読み替えるかという支援スタッフのセンスも問われてくるだろう。
しかし、そのセンスも一方的に「これでいいじゃん!」と押し付けて評価するのではなく、障害のあるメンバーも支援スタッフもともに面白がる状況を生み出すことがとっても大切だと思う。
本人の特性的行為を、創作を通じて見える場所に引き出し、起きてしまった一見ヘンテコな、非合理な出来事に対する受け止め方を無限に広げてみること。「支援される/支援する」という枠を超えて、いまこの場で起きているこの出来事を「味わう」ということ。こうしてようやく、「福祉」に感性的・美的な価値観が導入されるのではないか。
僕はなにも障害福祉の創作現場を描写して、能天気かつロマンチックな話をしたいわけじゃない。この「感性的なまなざし」こそが、支援現場を外に開き、障害のある人と日頃接しない人々がコミュニケーションに参加できる重要な契機となると、本気で思っているのだ。でも、そう簡単に福祉は変わらない。でも、変わってきてもいる。これから、そんなことをつらつら書いていきたい。
Profile
![]()
-
アサダワタル
文化活動家
1979年生まれ。これまでにない不思議なやり方で他者と関わることを「アート」と捉え、音楽や言葉を手立てに、全国の市街地、福祉施設、学校、復興団地などで地域に根ざした文化活動を展開。2009年、自宅を他者にゆるやかに開くムーブメント「住み開き」を提唱し話題に。これまでkokoima(大阪堺)、カプカプ(神奈川横浜)、ハーモニー(東京世田谷)、熱海ふれあい作業所(静岡熱海)など様々な障害福祉現場に携わる。2019年より品川区立障害児者総合支援施設ぐるっぽにて、公立福祉施設としては稀有なアートディレクター職(社会福祉法人愛成会契約)として3年間勤務した後、2022年より近畿大学文芸学部文化デザイン学科特任講師に着任(2024年度より専任講師)。博士(学術)。著書に『住み開き増補版 』(ちくま文庫)、『想起の音楽』(水曜社)、『アール・ブリュット アート 日本』(編著、平凡社)など。2020年より東京芸術劇場社会共生事業企画委員。
この記事の連載Series
連載:砕け散った瓦礫の中の一瞬の星座|アサダワタル
![]() vol. 102024.07.02最終回:「当事場」をつくる
vol. 102024.07.02最終回:「当事場」をつくる![]() vol. 092023.07.06社会福祉法人元理事長による性暴力とハラスメントについて考えた、「そばに居る者」としての記録
vol. 092023.07.06社会福祉法人元理事長による性暴力とハラスメントについて考えた、「そばに居る者」としての記録![]() vol. 082023.02.03どこにも向かわない「居場所」をどこまで続けられるか
vol. 082023.02.03どこにも向かわない「居場所」をどこまで続けられるか![]() vol. 072022.10.04「舟」に一緒に乗り込むこと。 ―ラジオと支援と高崎くんと [後編]
vol. 072022.10.04「舟」に一緒に乗り込むこと。 ―ラジオと支援と高崎くんと [後編]![]() vol. 062022.08.15粘る。いても、いなくても。 ―ラジオと支援と高崎くんと [中編]
vol. 062022.08.15粘る。いても、いなくても。 ―ラジオと支援と高崎くんと [中編]![]() vol. 052022.05.31生きてきた証は電波に乗って ―ラジオと支援と高崎くんと [前編]
vol. 052022.05.31生きてきた証は電波に乗って ―ラジオと支援と高崎くんと [前編]![]() vol. 042022.01.26「壁画」と「まなざし」
vol. 042022.01.26「壁画」と「まなざし」![]() vol. 032021.12.09この現場から、「考える」を耕す
vol. 032021.12.09この現場から、「考える」を耕す![]() vol. 022021.11.10句点「。」の行方
vol. 022021.11.10句点「。」の行方