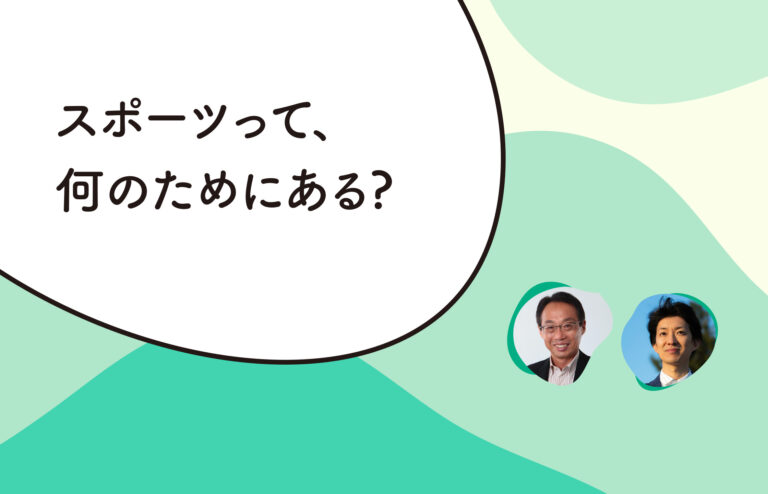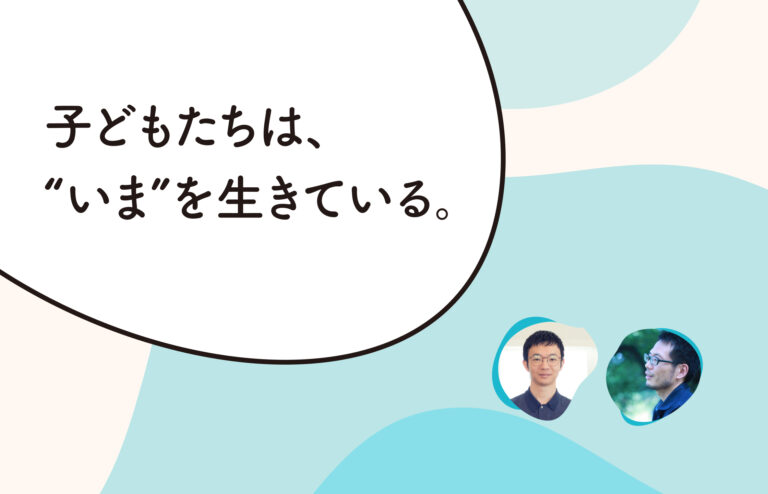福祉施設が学びあいの拠点になることで育まれるものとは?ライフの学校・田中伸弥さん こここインタビュー vol.05
2020年4月、宮城県仙台市に<ライフの学校>と名づけられた学校が開校した。
建物の前に広がる庭には、地域で暮らす人の家々に眠っていた道具や置物、街なかから集めた石などがにぎやかに並ぶ。

キャンパス内では、地域の子どもたちを対象にした福祉の授業体験や、高齢者や障害のある方との「お話会」といったさまざまなプログラムが、毎日のように開催されている。




ここは、社会福祉法人が運営する福祉施設だ。
2021年9月時点において、特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、相談支援センターからなる「萩の風キャンパス」、居宅介護支援センター、訪問ヘルパーステーションからなる「上飯田キャンパス」、障害や難病のある方の就労支援の場「沖野キャンパス」がここにはある。 どちらも日々のケアの中から「ライフ(LIFE)=命や暮らし、生きること」についての学びを多くの人々と分かちあうことをコンセプトに掲げている。
施設を利用する人々(ライフの学校では利用者という言葉は使わず「パートナー」と呼ぶ)や、そのケアに関わる人々の人生が豊かであるためには、福祉施設を地域に“ひらいて”いく必要があると思います。
ライフの学校の理事長を務める田中伸弥さんは語る。地域にひらかれた福祉を実現するためにはなにが必要なのか。そして、そのひらかれた場を通じてなにが生まれているのか。田中さんに、これまでの取り組みについてのお話を伺った。

死ぬことや生きることについて考える機会が少なすぎる
田中さんが「福祉をひらく」という想いに至ったきっかけは、病に倒れた母の看取りを20代で経験したことだった。
病院での入院生活で、母の望みを満足に叶えてあげられなかったことに大きな悔いが残り、「尊厳ある看取りの実践から、自分と同じような後悔をする人を少なくしたい」という想いから、特別養護老人ホームで働きはじめる。
しかし実際に現場に立ってみると、施設にいる期間が長期化している利用者ほど、社会との接点が限られてしまうことを痛感する。
施設に一旦入居してしまうと利用者の暮らしは地域社会から見えづらく、亡くなればほかの利用者にも知らされることなく、ひっそりと裏口から運ばれてしまう現実もあった。
田中さんはそこで、福祉施設を“閉ざされた”ものではなく、施設の利用者やその家族、スタッフと地域住民がお互いに支えあう場へと変えていく必要性を感じる。施設を地域にひらくことで、利用者に地域住民との接点が生まれるのはもちろん、地域そのものに命や暮らし、生きることについての経験値が蓄積していくはずだと考えた。
日々のケアのなかには多くの学びがあります。福祉の現場に携わるほとんどの看護・介護職は、仕事を通じて「ケアをする」側である自分たちがむしろ「ケアされている」と感じるような経験をしたことがあると思います。
そういった感覚を得られる機会が専門職の人たちだけに限定されてしまうのはもったいないと思ったんです。
それに、福祉に携わっていない方にとっては、死ぬことや生きることについて日常的に考える機会自体がそもそもとても少ない。むしろどこか死というものに対してネガティブなイメージがあって、見て見ぬ振りをしてしまうこともあるんじゃないかと。
だからこそ、死ぬことや生きることについて考えられるきっかけが、日常生活のなかにもっと点在していた方がいいのではないかと田中さんは言う。
福祉施設がその拠点として地域に存在することが大切ではないかと思い、地域にひらいていこうと考えました。
「学び」というとその場ですぐになにかを得られるようなイメージを抱く方もいるかもしれないけれど、もっとじわじわとでもいいと思っているんです。
生きていると、学生時代に先生に言われたことをふとした瞬間に思い出して「ああ、あれはこういうことだったのか」って突然わかることがあるじゃないですか。
言われたその瞬間にはよくわからなくても、時差で効いてくること。そういう体験が人生のなかにもっと散りばめられてほしい、そのための場が福祉施設で実現できたらと思いました。
コンセプトを共有するため、スタッフと話し合いを重ねた
その理想が「ライフの学校」として具現化されるまでには、とても長い道のりがあった。施設で大切にしたいケアのあり方として、田中さんはいつもスタッフに1枚の写真を見せているという。
ホスピスでベッドに横たわる年配の男性の隣に、その方が警察官時代にを共にしたという愛馬が顔を寄せている写真だ。
スタッフにはいつも「これがウチの法人で大切にしたい風景だよ」と話しています。ホスピスに馬を連れてくることがリスクのない行為かと言ったら、そうではない。
けれど、病院のスタッフたちが、目の前の人の最後の希望に寄り添った結果こういう瞬間が生まれた。それがまさにケアの本質的な部分だと思ったんです。
2016年、田中さんは特別養護老人ホームの施設長に就任。試行錯誤を重ねる最中、相模原障害者施設殺傷事件が起きる。福祉業界には当然、大きな衝撃が走った。
事件を受けて、国からもセキュリティをより強化するため、監視カメラや電子錠などへの補助金が示されました。このことから防犯体制を強化する施設も増えた。
これは、施設を地域に対して“閉じていく”という方針と変わりありません。あの事件は一般の人々のみならず、福祉に携わる人たちも「閉じていくこと」、「セキュリティを強化していくこと」の正当性を認めざるをえない状況にあった。本当にこれでいいのだろうかと強い葛藤もありました。
自問自答を続けていた田中さんだったが、同じ頃、特別養護老人ホームと地域とを隔てていた壁を取り払い、施設にある営みを可視化し、地域との関係をより築いていこうとするプロジェクトを決行した神奈川県の施設「ミノワホーム」の存在を知る。
同施設を経営する馬場拓也さんの取材記事を読み、すぐ会いに行き話を聞いた。また、新潟県長岡市で郊外にあった大規模の特別養護老人ホームをサテライト化し、利用者がこれまで培ってきた暮らしを社会として支えていく取り組みをおこなった「こぶし園」にも訪れた。
それらの施設での視察を通じ、田中さんは、やはり地域にはひらかれた福祉施設があるべきだと確信する。
まず、スタッフとは何度も話し合いを重ねました。現場で一緒に働いてきたこともあり、「田中さんがやりたいことはなんとなくわかる」とは言ってくれるのだけれど、コンセプトをきちんと言語化して、共有できるようにする必要があると思ったんです。
そのために、社会の広告社さんにも入っていただいて、法人名の変更を含むリブランディングについて考えていきました。
話し合いのなかで、学びを分かちあうための『学校』というキーワードが出てきたとき、スタッフからは反対の声も挙がったという。
スタッフや施設のパートナーのなかには、不登校の経験者や、画一的な教育から取りこぼされてしまった記憶を持つ人たちもいた。「学校というイメージに拒否感を覚える人もいるかもしれない」という意見に、田中さんは大いに頷いた。
スタッフもみんな真剣に考えてくれているんだな、とそのとき感じました。ネガティブな意見が出るのはある程度、予測はしていました。
以前、福祉楽団の理事長飯田大輔さんからイヴァン・イリイチの『脱学校の社会』という本を薦められて読んでいました。
これを課題図書としてスタッフが読み、自分たちがいま作ろうとしている『学校』は「教えられ、学ばされる」という一方向性の関係ではなく、「自ら学ぶ」という自律的行為、すなわち学習者が内発的に動機づけられた行動を取り戻すための、暮らしを通じて学びあう拠点であるという認識が固まってきました。
そこでようやく『ライフの学校』という名前が決まったんです。

土地の歴史を知ることは、人の歴史を知ることだ

コンセプトや新しい法人名が決まったあとは、地域住民を巻き込みながらワークショップを複数回開催し、具体的に施設をどのように変えていきたいか、「学校」としてどんなプログラムがあったら参加したいかという意見を集めていった。
田中さんはその土地に長く暮らしている人が多く集まる町内会のイベントなどにも積極的に参加し、住民との関係を地道に積み上げていったという。そうした関係性づくりも功を奏し、ワークショップには、地元の小中高生をはじめとする多くの人が集まった。
さらに並行して、施設の改修も一つひとつ進めていった。最初にとりかかったのは、特別養護老人ホームを地域から隔てる生垣を取り払い、庭をひらくという「ライフの庭」プロジェクトだ。横浜に拠点を置く建築設計事務所のtomito architectureと協働しつつ、田中さんは地域の歴史を知るためのフィールドワークをおこなった。
tomito architectureはプロジェクトを進めていく上で、地域をとにかく地道にリサーチし、土地の文脈を読み解いていくというアプローチをとるんです。そのやり方にはケアの「アセスメント」に通じるものを感じました。
庭の改修プロジェクトの過程で、tomitoと一緒にライフの学校の周辺地域のフィールドワークをしようということになったんですが、地域について初めて知ることの多さには私自身も驚かされました。
都会から来た若い建築家の人たちが熱心に土地の歴史を知ろうとしているというのは地域の人にとってもうれしかったようで、市民センターの館長が「この本あげっからさ」とか言って貴重な資料をくれたりするんですよ。
こっちはここに10年いるけど一度ももらったことないぞっていうようなものを(笑)。
リサーチを進めるなかで、地域一帯が50年ほど前から住宅地として整備され、一時は多くの家が建てられたものの、近年では住民の高齢化もあり、庭の植物などが管理されなくなってきているという現状を知る。
そういった庭の植物をはじめ、地域住民が大切にしていた古道具や置物などを「ライフの庭」に引っ越しさせるというアイデアが生まれ、改修は着々と進んでいった。
建築家としてのtomitoの視点も交えつつ、土地の歴史を知れたのは、本当におもしろい経験でした。土地の歴史を学ぶことで、その「人」自身の「解像度」があがりました。
パートナーは、地域の話をするときに昔の地名を使うんですよね。だから、パートナーたちの話が前よりずっとわかるようにもなった。土地の歴史を知ることは人の歴史を知ることでもあるんだと、そのとき強く思いました。

そのようにして、「ライフの庭」は地域にひらかれた場となっていった。同時に、地域の誰もが自由に訪れて利用することができる図書館や駄菓子屋も施設内に開設され、2020年春、ライフの学校は無事に開校を迎えた。



集客よりも、「続ける」ことを重視する
開校から約1年半。ライフの学校では現在、地域の子どもたちが福祉の仕事を体験できるプログラムや、施設内で暮らすパートナーの人生を「聞き書き」を通じて振り返る「ライフストーリー学」といったプログラムを日常的に開催している。
これらのプログラムはワークショップで出たアイデアを下敷きにしつつ、「運営企画室」に所属する、スタッフたちによって考えられているという。
いまは全職員中24人、だいたい2割のスタッフが運営企画室を兼任してプログラムを考えてくれています。
こうして取材などで注目していただけるようになると、おもしろいイベント、集客できるようなイベントをやろうという話になることもあるんですが、それよりも地道に日々のプログラムを「続ける」ことを重視しようというのは全員に伝えています。
来てくれる人数を増やしていくのも大切ですが、「目の前にいるひとりの人」を大事にしたいというのが私たちの共通認識なので。

さまざまなプログラムが継続的に運営されていくことで、日々の現場のケアにも変化が生まれているという。パートナーのキャリアやこれまでの人生について話を伺う「ライフストーリー学」はその筆頭だ。
たとえば、あるパートナーのライフストーリー学では、聞き書きを通じてその方がすごく好きだったラーメン屋さんのラーメンがあるというのがわかったんです。すごいな、そんなところまで掘り下げるのかと私も内心びっくりしたんですが(笑)。
その方が終末期に「ラーメンを食べたい」というリクエストをしてくれたのですが、スタッフが悩みながらも応えようとして、亡くなる前に大好きだったそのお店のラーメンを食べてもらえたんです。
介護報酬の加点の仕組みなどによって、介護施設ってどうしてもケアが均質化・マニュアル化してしまいがちで、本当に相手のことを考えられているだろうか、と悩むスタッフも多いのは事実です。
でも、目の間にいる人に向き合って悩みながらも応える経験をするとスタッフにも自信が生まれ、周りのスタッフもその姿勢に影響されて伸びていくのを感じます。

介護の仕事において、目の前の相手のことをすこしでも知ろうと学び続ける姿勢は重要だ。その一方で、自分のキャパシティを知ることも大切だと、田中さんは繰り返しスタッフに伝えているという。
なんでも「できます」と引き受けた結果キャパオーバーになっちゃうのってやさしい人にありがちなんです。自分の身の丈を知らずにあれもこれもしたいと思って抱えすぎたらだめだよってスタッフにはよく言いますね。
現場では、目の前の人に関わること、その人のことを精いっぱい考えることがなによりも楽しいという気持ちは私にもよくわかるんですが、自分がいまはできないことまでしてあげたいと考えすぎるとしんどくなってきてしまうので、その線引きはきちんとしないといけない。
対話は本当に「面倒くさい」けれど
スタッフや地域住民、そして施設で暮らすパートナーと誠実かつ地道な対話を積み重ねてきた田中さんだが、それでも、地域や人との地道な関わりは「面倒なこと」も多いと言う。
いや、本当に面倒なことも多いです。地域の人たちの関係って複雑で「あの人が来るなら俺は行かない」「なんでこっちから声をかけないんだ」みたいなことも普通にありますよね(笑)。
ただ、目の前の人に向き合い続けるということは、その「面倒さ」を蔑ろにしないことだと田中さんは思っている。
もちろん、すべての面倒を1人で引き受けるべきだとは思わない。法人としてはICTも進めていて、『ケアコラボ』という記録ツールを利用するなど、効率化できるものはどんどん効率化すべきと思っています。
それによって生まれた時間を、きちんと人と向き合うための時間にしたいと思っているんです。
たとえば、庭の草刈りも面倒だけれど欠かせないことのひとつです。庭を舗装してしまえばそんなことはしなくてよくなるんだけど、そうしたら地域の方と立ち話をする機会が失われてしまう。
現に、私もさっきまで草刈りをしてたんですが、数時間のあいだに4人の人が庭まで来て話しかけてくれたんです。「精が出るねえ」ってちっちゃい飴をくれたり、コロナのことを話したり。そういう時間は大事にしたいと思っています。
日常生活のなかで関わる人の数が多いと、いざというときに頼れる相手の選択肢も増える。あまねく人とつながれる環境があることにはそういった意義もあると田中さんは言う。
新型コロナウイルス流行の影響で地域住民との新たな出会いの機会は以前より減ってはいるものの、最近、ライフの庭を通るルートに散歩コースを変えてくれたという人や、庭のほうを眺めながら歩道を通っていく人もいるという。
庭の近くを歩いている方には「よかったら通ってください」って声をかけるんですが、「いやいや」って遠慮されることもあります。
でも、そもそも庭の生垣を取り払わなければ、そういう方がいることも見えていなかったはず。
ということは、いままで10年間、私たちも地域から見えていなかったということだと思うんです。だから、それも“時差”かもしれないけど、今後生まれてくるものがあったらいいなと思いますね。
たまに、フラ~っと入ってきた子どもが庭の石を平均台にして遊んだりしているのを見ると、そんな使い方もあったのかとうれしく思います。
子どもは最初からそうやって自由に遊べるんですけど、大人はある程度のガイドがないと躊躇してしまうというのもだんだんわかってきた。だから、またパートナーや地域の人の声を聞きつつ改修は進めていきたいと思っています。

インタビューの最後に、“地域にひらかれた”場の理想的なあり方について田中さんに尋ねてみると、「『えっ、誰あの人?』と思うような人がごく自然にそこに『居られる』環境ですかね」という答えが返ってきた。
当然だがそれは、ただ闇雲にすべてをオープンにするということではない。特に、看取りに際してはパートナー本人と家族の希望を尊重し、プライバシーにも配慮している。
命を軽視したいわけでも、「こんな死に方もありますよ」と死をデコレーションして見せたいわけでは決してないんです。どんな環境で看取られたいかというのはもちろん、パートナーのご意向を第一に考え、ご家族の意向も尊重します。
ライフの学校では、亡くなった方をスタッフや他のパートナーたちが見送る光景が、庭を通して地域住民から見えることもある。「『あ、誰か亡くなったんだな』というのが第三者にわかるだけでも意味はある」と田中さんは言う。看取りをひらくことも、生や死について考えるひとつのきっかけを生むはずだと考えている。
これから高齢者がどんどん寿命で亡くなり、多死社会が来るということをみなさんやっぱりまだ実感されていないと思う。
うちくらいの規模の施設ですら、本当にたくさんの方を看取っています。それがまったく見えない状態になっている社会って、私はあまり健全じゃないと思うんです。
ここ最近も看取りが続いているんですが、パートナーの方がそれぞれに生ききるのをお手伝いできたんじゃないかと思えることは多いです。
ライフストーリー学の発表が終わったその夜に亡くなったり、ご家族がみんな集まって記念撮影をしたそのあとに亡くなったり……。
そういう話って美化されて伝わりがちだと思うんですが、目の前でそれがリアルに起きているというのをもっと伝えたい。暮らしのなかでもうすこしだけ死に触れるためにはどうしていけばいいのか、私にもまだはっきりとした答えは見つかっていないんですが、これからもいろいろな人の意見を聞きつつ考えていきたいです。
「どうすればいいのか私にもわからない」「いろいろな人の声を聞きながら考えていく」。取材のなかで、田中さんは何度もそんな言葉を口にした。それはまさに、ライフの学校が掲げる「学びあい」や「支えあい」という言葉の日常的な実践であるように思えた。
「最近ひさびさに読み返したメイヤロフの言葉に、ライフの学校の方針とリンクしているのを感じました」。取材後、そんな添え書きとともに田中さんが教えてくれた哲学者ミルトン・メイヤロフの著書『ケアの本質』には、こんな一節がある。
「“場の中にいる”と感じるときには、そこには経験についてのある濃度というべきものが存在している。(中略)ケアというものは、使って使いきれる程度の一定量しかないというものではないからである。
むしろケアとは、それを実践することによって絶えず新しくなり、発展していくのである。またこの豊富さというのは、私たちと補充関係にある他者へのケアをとおして、この他者が成長していくことにも示される。存在がその深みを増してくるのである。
つまりこれは、私たちが興味をもっているものについて深く研究すればするほど、その対象が貧弱になるどころか、より豊饒であることがわかるのと同様である」
(『ケアの本質 生きることの意味』 p.153 ミルトン・メイヤロフ著、田村真・向野宣之訳 ゆみる出版)
絶えず実践されるケアを通して、他者が存在の深みを増していく。そして、その変化は「場」そのものにも経験として蓄積される。ライフの学校は、変化してゆく他者に根気強く関わり続け、それに伴って「場」も変化し続けることを日々実践している。その積み重ねのなかに地域にひらかれた福祉があるのだろう、と感じさせられた。




Information
社会福祉法人ライフの学校サポーター(寄付)募集中
サポーター(寄付)に関する詳細はこちら
Profile
Profile
- ライター:生湯葉シホ
-
1992年生まれ、東京在住。フリーランスのライター/エッセイストとして、おもにWebで文章を書いています。Twitter:@chiffon_06
この記事の連載Series
連載:こここインタビュー
![]() vol. 322025.03.18言葉を超えて誰もがつながる「身体表現」の魅力とは? 福祉を起点に広がるパフォーミングアーツ、生きづらさを変える可能性
vol. 322025.03.18言葉を超えて誰もがつながる「身体表現」の魅力とは? 福祉を起点に広がるパフォーミングアーツ、生きづらさを変える可能性![]() vol. 312024.10.09なぜ自分に価値があるか確認したくなるんだろう? 勅使川原真衣さんと新澤克憲さんによる「評価」を巡る対話
vol. 312024.10.09なぜ自分に価値があるか確認したくなるんだろう? 勅使川原真衣さんと新澤克憲さんによる「評価」を巡る対話![]() vol. 302024.09.13大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 写真家/訪問看護師 尾山直子さんをたずねて
vol. 302024.09.13大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 写真家/訪問看護師 尾山直子さんをたずねて![]() vol. 292024.09.07地域に根ざす園から、子どもも大人も混ざった“絶景“を生み出せたら。〈学校法人thanka〉が新ステートメント「手を繋ぎにいく」に込めた願い
vol. 292024.09.07地域に根ざす園から、子どもも大人も混ざった“絶景“を生み出せたら。〈学校法人thanka〉が新ステートメント「手を繋ぎにいく」に込めた願い![]() vol. 282024.08.30大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 株式会社Blanket 秋本可愛さんをたずねて
vol. 282024.08.30大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 株式会社Blanket 秋本可愛さんをたずねて![]() vol. 272024.07.25気軽な買い物体験から、「未来が良くなる」手応えを。〈フェリシモ〉の新カタログ『GO! PEACE!』制作の裏側
vol. 272024.07.25気軽な買い物体験から、「未来が良くなる」手応えを。〈フェリシモ〉の新カタログ『GO! PEACE!』制作の裏側![]() vol. 262024.04.30蓋された「小さな自分」の声に耳を傾けて。ケアを促す料理レッスンの場、就労支援の場──山口祐加さん×鞍田愛希子さん
vol. 262024.04.30蓋された「小さな自分」の声に耳を傾けて。ケアを促す料理レッスンの場、就労支援の場──山口祐加さん×鞍田愛希子さん![]() vol. 252024.04.10「インクルーシブ」は誰のための言葉? 老舗メーカー〈ジャクエツ〉×医師・紅谷浩之さんの、子どもに“遊びと友だち“を返す遊具
vol. 252024.04.10「インクルーシブ」は誰のための言葉? 老舗メーカー〈ジャクエツ〉×医師・紅谷浩之さんの、子どもに“遊びと友だち“を返す遊具![]() vol. 242024.03.29文化施設のウェブアクセシビリティを向上する。障害当事者との「建設的な対話」に必要なこととは?──伊敷政英さん×森司さん
vol. 242024.03.29文化施設のウェブアクセシビリティを向上する。障害当事者との「建設的な対話」に必要なこととは?──伊敷政英さん×森司さん![]() vol. 232024.03.27だれもが文化でつながるために。クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョーが見据えるこれからの文化施設のあり方とは。
vol. 232024.03.27だれもが文化でつながるために。クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョーが見据えるこれからの文化施設のあり方とは。![]() vol. 222023.12.22人のためってなんだろう? 他者にコントロールされない「LOVOT」から、“人間らしさ“を考える──伊藤亜紗さん×林要さん
vol. 222023.12.22人のためってなんだろう? 他者にコントロールされない「LOVOT」から、“人間らしさ“を考える──伊藤亜紗さん×林要さん![]() vol. 212023.11.08保育料ゼロを実現し、子育てを“みん営化”する。 学童保育施設〈fork toyama〉岡山史興さん
vol. 212023.11.08保育料ゼロを実現し、子育てを“みん営化”する。 学童保育施設〈fork toyama〉岡山史興さん![]() vol. 202023.05.29ともだちってなんだろう? 答えを出す必要はないけれど。新澤克憲さんとテンギョー・クラさんの対話から考える
vol. 202023.05.29ともだちってなんだろう? 答えを出す必要はないけれど。新澤克憲さんとテンギョー・クラさんの対話から考える![]() vol. 192023.05.23歌人・岡本真帆さん×西淡路希望の家・金武啓子さん対談。「感動」の発見、どう他者と分かち合いますか?
vol. 192023.05.23歌人・岡本真帆さん×西淡路希望の家・金武啓子さん対談。「感動」の発見、どう他者と分かち合いますか?![]() vol. 182023.03.20“みる”から始める、アーティストと支援現場のつなぎ役。日常の関係性を変える「TURN LAND プログラム」の挑戦
vol. 182023.03.20“みる”から始める、アーティストと支援現場のつなぎ役。日常の関係性を変える「TURN LAND プログラム」の挑戦![]() vol. 172023.03.15アート活動で、「できる/できない」を揺さぶる。日常の価値を言葉に変えるコーディネーターの役割
vol. 172023.03.15アート活動で、「できる/できない」を揺さぶる。日常の価値を言葉に変えるコーディネーターの役割![]() vol. 162023.03.03唯一の答えを探しすぎていないか? 下地ローレンス吉孝さん×なみちえさんと“わかりやすさ”について考える
vol. 162023.03.03唯一の答えを探しすぎていないか? 下地ローレンス吉孝さん×なみちえさんと“わかりやすさ”について考える![]() vol. 152023.02.15“わたし”と“あなた”それぞれの複雑さを大切にするには?──なみちえさん×下地ローレンス吉孝さんと共に考える
vol. 152023.02.15“わたし”と“あなた”それぞれの複雑さを大切にするには?──なみちえさん×下地ローレンス吉孝さんと共に考える![]() vol. 142022.12.23出会いを広げながら、協働を生む「メディア」を目指して──〈こここ〉シーズン2を振り返る
vol. 142022.12.23出会いを広げながら、協働を生む「メディア」を目指して──〈こここ〉シーズン2を振り返る![]() vol. 132022.12.19働くことも、映画祭も「みんなが心地よい」を目指して。GOOD NEWSとTHEATRE for ALLのインクルーシブな場づくり
vol. 132022.12.19働くことも、映画祭も「みんなが心地よい」を目指して。GOOD NEWSとTHEATRE for ALLのインクルーシブな場づくり![]() vol. 122022.10.14バリアフリーの映画祭を通して、「その人のまま」でいられる社会に。作家・川内有緒さん×THEATRE for ALL・金森香さん
vol. 122022.10.14バリアフリーの映画祭を通して、「その人のまま」でいられる社会に。作家・川内有緒さん×THEATRE for ALL・金森香さん![]() vol. 112022.09.13スポーツの可能性って何だろう? 「プロスポーツ」「ゆるスポーツ」から考える──岡田武史さん×澤田智洋さん
vol. 112022.09.13スポーツの可能性って何だろう? 「プロスポーツ」「ゆるスポーツ」から考える──岡田武史さん×澤田智洋さん![]() vol. 102022.03.31まだみぬ「表現」との出会いを、誰もが体験できる社会へ。障害のある人の芸術・文化活動を支える窓口が全国に
vol. 102022.03.31まだみぬ「表現」との出会いを、誰もが体験できる社会へ。障害のある人の芸術・文化活動を支える窓口が全国に![]() vol. 092022.02.09コロナ禍で「消される」声に、どう耳を傾ける? 次の社会をつくる言葉と対話のあり方──荒井裕樹さん×青山誠さん
vol. 092022.02.09コロナ禍で「消される」声に、どう耳を傾ける? 次の社会をつくる言葉と対話のあり方──荒井裕樹さん×青山誠さん![]() vol. 082021.12.24福祉をたずねて1年。編集部は何に出会い、悩んできた?──〈こここ〉振り返り座談会
vol. 082021.12.24福祉をたずねて1年。編集部は何に出会い、悩んできた?──〈こここ〉振り返り座談会![]() vol. 072021.11.24コロナ禍を経て新たな表現の協働へ ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[後編]
vol. 072021.11.24コロナ禍を経て新たな表現の協働へ ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[後編]![]() vol. 062021.11.24アートプロジェクトは福祉の現場で何を生み出す? ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[前編]
vol. 062021.11.24アートプロジェクトは福祉の現場で何を生み出す? ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[前編]![]() vol. 042021.06.03VR認知症を体験して気づいた、わからない世界へ手を伸ばし続ける大切さ。シルバーウッド 下河原忠道さん
vol. 042021.06.03VR認知症を体験して気づいた、わからない世界へ手を伸ばし続ける大切さ。シルバーウッド 下河原忠道さん![]() vol. 032021.04.15まだ名付けられていない感覚に出会う「遊び」の可能性とは? インタープリター 和田夏実さん
vol. 032021.04.15まだ名付けられていない感覚に出会う「遊び」の可能性とは? インタープリター 和田夏実さん![]() vol. 022021.04.15「助けて」とお互いに言い合えるのが、成熟した社会。ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ代表 志村季世恵さん
vol. 022021.04.15「助けて」とお互いに言い合えるのが、成熟した社会。ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ代表 志村季世恵さん![]() vol. 012021.04.15「お笑い」や「演劇」は他者の世界に寄り添うヒントをくれる。りんたろー。さん×菅原直樹さんが語る「介護の話」
vol. 012021.04.15「お笑い」や「演劇」は他者の世界に寄り添うヒントをくれる。りんたろー。さん×菅原直樹さんが語る「介護の話」