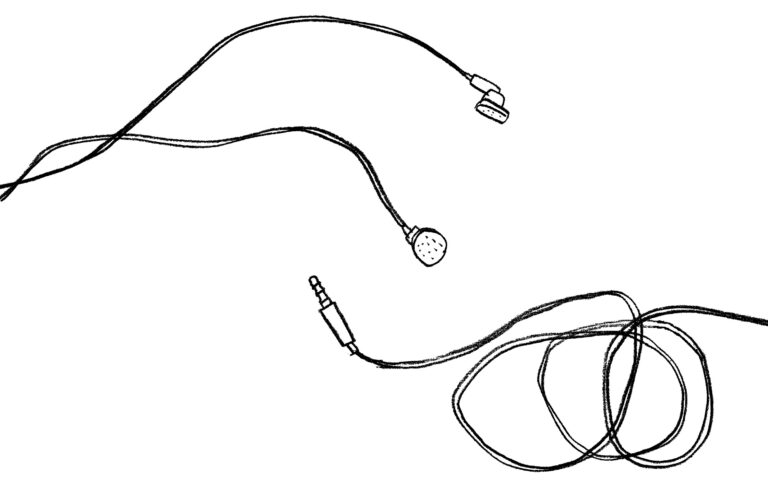本連載は、ユニークな方法で他者と関わることを「アート」と捉え、音楽や言葉を手立てに、全国の市街地、福祉施設、学校、復興団地などで文化活動を手掛けてきた文化活動家・アサダワタルさんによるエッセイシリーズです。アサダさんがこれまでにケアの現場で経験してきた出来事、育まれてきた表現、人々との関係性を振り返り、揺れや戸惑いも含めて、率直に感じたこと・考えたことを綴っていただきます。
最終回となるVol.10は、昨年7月に公開し、大きな反響を呼んだVol.09 「社会福祉法人元理事長による性暴力とハラスメントについて考えた、『そばに居る者』としての記録」を執筆する上で考えたこと、そしてアサダさんによる「当事場」という考え方に触れます。(こここ編集部・中田)
「事件」と「福祉」はどうつながるか?
“アサダさん、返信が遅れて申し訳ありません。本企画、編集部で相談する中で、「社会福祉法人で起きた性加害事件を主題に連載を展開することは、読者を『福祉』から遠ざけることにならないか?」という意見が出て悩んでいました。「福祉に関わりのある人にとって大事な事件ではあるが、〈こここ〉の読者は福祉業界の人に限らない。『福祉』の入口手前にいる人達にどういう意図を持って届けるべきか」という問いに、うまく答えられずにいたからです”
社会福祉法人で起きた性加害事件のことについて書こうと思った僕は、〈こここ〉編集長の中田一会さんに相談した。
以前より友人だった彼女は品川の現場「ぐるっぽ」にも遊びに来てくれたし、「福祉と表現をめぐるウェブマガジンの創刊準備をしているので、実現したら何か書いてほしい」と言ってくれていたのだ。当初は、一人ひとりのメンバーとの関わりや、そこでの表現活動に焦点を絞ったエッセイ“のみ”になると思っていた。その後、身近で起きた事件のことを知り、むしろそのことを主題に添えた企画書を彼女に手渡した。そのあとにもらったのが、冒頭の中田さんからのメールだ(※内容は一部要約している)。
もっともだと思う。僕も説明できないと思った。当時は。福祉現場から生まれる表現の豊かさと、ハラスメント事件はなんのつながりもない、まったく別のテーマだと思っていたからだ。〈こここ〉の創刊趣旨には以下のことが書かれている。
“「社会」に関係のない人がいないように、「福祉」に関係のない人もいません。この世界に生きる“わたしたち”みんなに関わること、それが福祉だと〈こここ〉は考えています。 でも多くの人にとって、まだまだ福祉は身近なものではないのかもしれません。だから〈こここ〉では、「クリエイティブな福祉」の活動をたずね、「福祉に宿るクリエイティビティ」をたずねることで、読者と一緒に旅をしてみたいのです。ーー「こここについて」より“
そう。「福祉」はまだまだ身近なものではないのかもしれない。高齢者福祉に関しては、家族が介護サービスを受ける経験などを通じて身近なこともあるだろう。しかし、僕が最も関わってきた障害者福祉に関しては、日頃触れ合う機会はぐっと減るのではないだろうか。
僕にとってもそうだった。障害当事者でもなく、その家族でもなく、支援の専門職でも福祉の研究者でもない。でも、間違いなく言えることは、「出会ってしまった」ということ。
音楽や演劇などの表現活動を通じて肢体に障害のある人たちと出会い、ホームヘルパーとしても働いた20代。「アール・ブリュット」という言葉に出会い、自閉症やダウン症の当事者、統合失調症の当事者による、ありえないほど自由な発想とこだわりが凝縮されたアートに触れた30代。
福祉畑でなくアート畑の自分だからこそ持ち得る視点から、現場で起きていることを観察し、行動し、「福祉って面白いよ、福祉ってとってもクリエイティブだよ」と「福祉の外」の人たちに伝える。福祉を広げる、開く。そういった「場づくり」をするのが僕の仕事だ。
それは時に生活介護や地域活動支援センターなど福祉サービスの運営という形を取るし、時にこうして文章を書いて発表することもある。でもやっていることは一緒。「福祉」を手繰り寄せる「場」を創ることなのだった。だからこそ、このウェブマガジンの趣旨に賛同し、ぐるっぽのメンバーたちが綺羅星のごとく展開する小さな表現に溢れた日常を綴ることは、これまで福祉に縁がなかっただろう〈こここ〉読者に対するささやかな提案になると思った。と同時に、それらを書くことは、これまでの世間一般に流通している「福祉」や「支援」というイメージに対する違和感への僕なりの挑戦でもあった。
福祉における「非対称性」と「当事者性」の課題
違和感の起源は、「福祉=いいことをしている」、「福祉=弱者を救っている」という固定観念からだ。一見何も問題がないように見えるこの考えの下で、「いいことをしている」は気づかないうちに「いいことをしてあげている」に変換されることがある。その変換の先では、「支援する/される」「強い人/弱い人」や、「普通の人/そうでない人」「マジョリティ/マイノリティ」という強固な非対称性が自然と培われてゆく。
この非対称性を前提に、社会制度として弱者を支えるための「福祉業」は生まれた。福祉が生業として成立するのはそれ自体悪い事ではなく、むしろ多くの人々の困りごとに寄り添う上で無くてはならないことだ。そもそも歴史的には、家庭でのみ担われてきたケア領域が様々な社会運動を経て「みんなのこと」として認識され、政治を動かし、人々の常識を変え、福祉サービスを充実させてきた。先人たちの積み重ねに対する多大な敬意は払っても払いきれないほどだ。
その功績を強調した上で、でも、「そもそもなぜその非対称性が存在するの?」という問いを、私たちは何度でも引っ張り出さないといけない。この非対称性の自明さに対するツッコミは、障害福祉現場においては「そもそもこの社会において、“障害”とはいかにして“発生”するのか?」という問いへとパラフレーズできる。僕はその問いに深いレベルで答えようとする支援実践が必要だと思うし、その「答え方」として現場にアート・表現活動を導入することが有効だと思ってきた。
きよしさんの指で覆われる景色(Vol.1)も、看板に描いた春日さんの大きな句点「。」(Vol.2)も、勝山直斗さんの「壁画」(Vol.4)も、高崎史嗣くんの「ラジオ」(Vol.5-7)も、華のようなかえでさんのダンス(Vol.8)も、翔太さんの鈴付きベルトで奏でられる「チャンチャン!リン!リン!」(Vol.9)も、大上航さんが描く作品を介した「トイレ越しの交信」(Vol.9)も、関根悠一郎さんの「船」(Vol.9)も。これらの数々の「表現」は、支援の対象になるのみならず、むしろ支援スタッフに対して「あっ、私はこれでいいのかな?」とか「何がこの世の“ふつう”なんだろう?」といった問いをもたらす。
そこにいる障害当事者一人ひとりの個性を支援することは、できることを増やす支援のみではなく、すでにあること、存在することを愛でる支援だと言えるだろう。でも、さらに大事なのは「支援のその先」で起こる、支援スタッフをはじめとした周囲に変化が起きることなのではないか。
この社会に生きるうえで、「当事者性」と言われるレンズがセルフィーモードのごとく反転し、「こちら」を写し出す。これは「当事者」のことが“わかる”という意味ではない。ましてや「自分にもそういった障害特性に通ずるものがある」といった安易な越境を求めるものでもないのだ。言うならば「自分が寄って立つこの世界の土台は果たして自明なのか?」と問うことを通じて、この私自身を掘り下げ、時に掘り崩していくような「当事者性」に出会うということだ。
答えのないゲームを共にすることで「自分も変えられてしまう」という体験を覚悟せず、メンバーさんにだけ変化を求める(仮に「その人のためにやっている!」という強い気持ちがあったとしても)思考であるなら、それは一方的で、不均衡で、凝り固まった支援観なのではないかと、Vol.4で書いた。そして、熱海のFM局から電波に乗せて黙々と自らを表現した高崎史嗣くんが求めていたのは「支援者」ではなくて「同志」だったのではないかと、Vol.7で書いた。言葉を変えながらも、ずっと同じことを考え、綴ってきたつもりだ。
それでも現実問題として支援スタッフが「当事者性」を手渡され、「同志」になるのは簡単ではない。理由のひとつに、堅牢な非対称構造の下、身体的、精神的、そして経済的にも極めて厳しい環境でなんとか福祉を支えているなか、「当事者性」を受け取るための思索の時間、つまり現場で起きているコミュニケーションそのものを味わい、自らの価値観を醗酵させてゆく時間が圧倒的に足りないのだ。それほどまでに現場は余裕がなく、疲弊している。こんなふうに言語化する時間なんて容易には作り得ない。
一緒に働いてきた仲間たちを尊敬しながら、僕は僕なりの立場を生かして、いまこうして“書かせて”もらっている。改めて、最も伝えたいことを書く。それは、「当事者性」は「人」にのみ宿るのではなく、「場」にも宿ると考えることができないだろうか?という問題提起だ。
人に着目した「当事者性」、場を主にする「当事場」
「者」という文字が入っている「当事者性」という言葉は、障害を始め多くの場合は社会で“問題”とされる何かを抱えている「人」に置かれる言葉であることは、疑う余地はないだろう。「当事者」という言葉があってこそ「当事者性」という言葉があるのだから、あまりにも当たり前でトートロジー(同語反復)と感じるかもしれない。「当事者性」は「人」に宿るのだとしたら、当事者主権という発想の下では非当事者による代弁不可能性という課題は必ず生まれる。「非当事者のあなたが口を挟むな!」「あなたは当事者じゃないからわからないでしょ?」と言ったように。でも、「当事者性」を「人」のみに対応させない考え方がもしあり得たらどうだろうか。
「当事者というのは、“事に当たる人”って書くでしょ。その“事”を精神障害とすると、それに“当たっている人”というのは本人だけじゃなくて、医者も看護師も親も子供も、それぞれみんながその“事”に当たっているんです」
これは、Vol.7で取り上げた、精神障害当事者として静岡県内でピアサポートをしている竹内晃さんの発言だ。ピア(当事者同士で)支援するなかで、彼は「事に当たる人」としての当事者の範囲を広げてみせた。まさに当事者である彼が提案するからこそ、この言葉は実に刺さるし、僕自身も「語ってもいいんだ!」という救われる気持ちになれた。でも、竹内さんのこのメッセージは、それを受け取る側の倫理観が問われると思う。つまり、当事者性の定義を広げて受け止めることは、時に自分の都合の良い足場を確保することや、こうして書いたり語ることで当事者性を身勝手に強化させる危険性もあるからだ。
でも、再度こう考え直す。私たちはその「当事者になり得なさ」を深く受け止めた先に、もっとふさわしいやり方で「当事者性」を感受し、熟考し、他者と対話をするための「場」を創る行動へと移すべきなのではないか。僕はその「場」のことを「当事場(とうじば)」と名付ける。
この連載で綴ってきた「表現」の数々は、支援スタッフをはじめとした様々な「非当事者」に、“私”自身を掘り下げ、時に掘り崩す機会を感受する「当事場」となる。
当事場は一種の変換回路であり、障害当事者としての当事者性を直接受け取る場ではなく、かれらが紡ぎ出すその表現に注目することで、「別の当事者性」を生成する。障害当事者であることと、その表現を生み出した当事者であることは確かにつながっているし、もちろん同一人物から滲み出るものだけど、それらを別の当事者性と捉えることで、支援スタッフの内にも「支援者という当事者性」とは異なる当事者性が生成される。

左側に立つのは、「強い当事者性」を持つ人で、例としては「知的障害の当事者」などを指す。障害当事者である以外も、さまざまな属性を持つが、「強い当事者性」が全面にくることで他の属性は見えにくくなり、「支援される人」と定義される。右側に立つのは、「強い当事者性と向き合う属性」を持つ人で、例としては福祉施設などの「支援スタッフ」などを指す。この人も様々な属性を本来は持つが、「強い当事者性と向き合う属性」が全面にくることで「支援する人」として定義される。
本モデルでは、お互いが様々な属性を持つ存在であるということは見えにくくなり、「支援される人 ⇔ 支援する人」の単純な構造に陥り、非対称的な関係が生まれやすくなる。
(原案:アサダワタル/描画:くぼやままさこ)

左側に立つのは、「強い当事者性(知的障害の当事者など)」を持つ人で、自分の様々な属性のうちの一つを「当事場」に投げ入れている。右側に立つのは「強い当事者性と向き合う属性(支援スタッフとしてなど)」を持つ人で、同じく自分の持つ様々な属性のうちの一つを「当事場」に投げ入れている。
「障害当事者」と呼ばれてきた人の個々の属性は、時に“こだわり”や“生活行為”として現れ、それらはときに“表現”や“作品”として「当事場」に浮かび上がる。このとき、従来「支援者」という属性でのみ関わってきた人も、興味関心や特技、私的背景を「当事場」に持ち出すことになり、混ざり合っていく。そこでようやく、「強い当事者性」や「強い当事者性と向き合う属性」は、その人を構成する一つの要素として前面にくることなく後退する。
(原案:アサダワタル/描画:くぼやままさこ)
そういった場こそが当事場であり、当事者の持つ当事者性を相対化し、その中にも複数の当事者性が重層的に存在しているという想像力を育む。
そのようにして、当事者と非当事者の間で、各々において複数の当事者性が生成されるプロセスを通じて、徐々に徐々にでも同じ地平に立ち、互いの当事者性を分かち合う状況が展開される。「自閉症の当事者」や「統合失調症の当事者」といった一見名付けられた言葉に対する当事者性ではなく、未だ名付けられてないし、名付けられないことを担保しつつづける余白の領域にこそ、各々の当事者性を共有する入会地、つまり「当事場」を創造しえるのではないか?
「障害をありのままに受け容れる」とはよく使われる言葉だ。「その人そのものと出会う」とも。僕もあまり深く考えることなくこれまで使ってきた気がする。でも、実は「ありのまま」も「その人そのもの」も実は存在しないのではないか。だって人はそもそも重層的に生きているからだ。全体を見渡し、まるごと感知することなどできっこない。
そう、個々人ですらそうなのだから、ましてや「みんな」なんてものも存在しえない。だから、福祉は「みんなの問題」というのも実は正確ではなくて、大事なのは、個々人の差異を孕む一様ではない当事者性を前提にして、その当事者性の一面がふと顔を出す瞬間での、誰かと誰かのその一面同士のフュージョンのパターンが無限にあることを知った上で、「ありのまま」も「みんな」も成立し得ると再認識することなのではないか。
「強い当事者性」だけに囚われないために
さて、冒頭の中田さんからの問いにそろそろ答えなくてはならない。つまり、「福祉」の入り口にいる人たちに対して、なぜあの事件までもを語る必要があるのか、という問いに。
答えは、障害当事者と、支援スタッフも含む非当事者の間に「当事場」を生み出そうとする創意工夫(クリエイティビティ)の積み重ねは、身近な人の間で起きたハラスメント・性被害・傷つきに対してどういった「当事者性」を持ち得るのかという問いに深いレベルで貢献しうるからだ。
被害当事者、加害当事者、両者を取り巻く関係者(あるいは傍観者)、そして各々の立場で行動する支援者の存在。しかし、Vol.9で何度も繰り返してきた「構造(的暴力)」をつぶさに見れば、各々の立場は決して完全に分離されてなくて、そこにグラデーションが存在することを知るだろう。
その上で「あなただって加害者(の一員)になり得るんだよ」と諭されることや、「自分も被害者になっていたかもしれない」と想像すること、ましてやその先でいよいよ声を上げることは、一体どれほどの障壁があることだろう。しかし、違うのだ。僕は違うと思う。「被害者」としてのその人や、「加害者」としてのその人の、その「当事者性」に自分を重ね合わせることを目指すよりも、私が私として、あなたがあなたとして「どう生きたいか」という「当事者性」があって、そこにこそ問いかけるべきではないか。
誤解を恐れず言えば、僕が木村倫さんと共に闘いたいと思ったのは、自分だって構造的に「加害者」だったじゃないかという負い目や、「支援者」としてサポートしたいという気持ちよりも、まず倫さんの「どう生きたいか」というその「当事者性」に圧倒されたからだ。Vol.9でも掲載した2021年1月23日に倫さんからもらったこのLINEメッセージを再び引用する。
“変わらないか変わるか、対峙してみて、模索したいと思います。対峙しないで、このままの世界で生きて、終わりたくはないのです。(中略)私はここではない世界で生きてみたいと思っただけです。自分の人生が暗く悲しいものになったとしても、対峙してみて、結果をみたかったのです。暗く悲しい結果だったとしてもその方が自分としてスッキリします。生きているうちにしかあがけないので、先延ばしにせず、あがいたからには、あがける限りの力であがいてみようと思いました”
強く思う。これを自らのこととして引き受けなければ、僕は「福祉」から、「ぐるっぽ」のメンバーをはじめこの連載で紹介してきたかれらから一体何を学んできたというのか。
急いで断りを入れるが「みんな倫さんのように行動しよう!声をあげよう!」と拙速に言いたいわけではない。そのメッセージを強要すること自体が時に暴力になってしまう。より大事なのは、ある「当事者」とされる人の「その当事者性」が「別の当事者性」へと変換され、それを受け取る者の「当事者性」を引き出し、互いが響きあう「場」なのではないか。
倫さんは「被害当事者」である前に、「木村倫さん」として“様々に”生きてきた。本来一人の人間の中に重層的に存在する当事者性に向き合うためには、強い当事者性のみに囚われてはいけない。そして、強い当事者性が個人という「人」にのみ帰すると捉えることは、その強い当事者性が発生しているという「構造(的暴力)」の存在をたちまち見過ごしてしまうだろう。障害は人に属さず社会の中でこそ生まれるという「障害の社会モデル」はそのことを根っこから確認する考え方であるのは言うまでもない。だからこそ、「場」を見るのだ。そして、僕らは、当事者性を相対化しながら自らの当事者性と照らし合わすその営みを発生させる「場」をこそなんとか拵えるのだ。そう、「当事場」を。
だからこの連載では、障害福祉の現場で生まれていった一つひとつの表現を描写し、立ち止まり、考え、そこから同じ地平線上で性加害事件についても綴った。この連載を通じて、読者のみなさんと当事場をじっくり紡ぎあうことを、切に願っています。
Information
本連載が書籍化されました!
2025年7月、本連載に加筆・修正を加えた書籍『当事場をつくる』が晶文社より発売されました。詳しくは〈こここ〉のニュースをご覧ください。
『当事場をつくる――ケアと表現が交わるところ』
- アサダワタル 著
- 四六判並製 264頁
- 定価:2,200円(本体2,000円)
- サイト:晶文社
Profile
![]()
-
アサダワタル
文化活動家
1979年生まれ。これまでにない不思議なやり方で他者と関わることを「アート」と捉え、音楽や言葉を手立てに、全国の市街地、福祉施設、学校、復興団地などで地域に根ざした文化活動を展開。2009年、自宅を他者にゆるやかに開くムーブメント「住み開き」を提唱し話題に。これまでkokoima(大阪堺)、カプカプ(神奈川横浜)、ハーモニー(東京世田谷)、熱海ふれあい作業所(静岡熱海)など様々な障害福祉現場に携わる。2019年より品川区立障害児者総合支援施設ぐるっぽにて、公立福祉施設としては稀有なアートディレクター職(社会福祉法人愛成会契約)として3年間勤務した後、2022年より近畿大学文芸学部文化デザイン学科特任講師に着任(2024年度より専任講師)。博士(学術)。著書に『住み開き増補版 』(ちくま文庫)、『想起の音楽』(水曜社)、『アール・ブリュット アート 日本』(編著、平凡社)など。2020年より東京芸術劇場社会共生事業企画委員。
この記事の連載Series
連載:砕け散った瓦礫の中の一瞬の星座|アサダワタル
![]() vol. 092023.07.06社会福祉法人元理事長による性暴力とハラスメントについて考えた、「そばに居る者」としての記録
vol. 092023.07.06社会福祉法人元理事長による性暴力とハラスメントについて考えた、「そばに居る者」としての記録![]() vol. 082023.02.03どこにも向かわない「居場所」をどこまで続けられるか
vol. 082023.02.03どこにも向かわない「居場所」をどこまで続けられるか![]() vol. 072022.10.04「舟」に一緒に乗り込むこと。 ―ラジオと支援と高崎くんと [後編]
vol. 072022.10.04「舟」に一緒に乗り込むこと。 ―ラジオと支援と高崎くんと [後編]![]() vol. 062022.08.15粘る。いても、いなくても。 ―ラジオと支援と高崎くんと [中編]
vol. 062022.08.15粘る。いても、いなくても。 ―ラジオと支援と高崎くんと [中編]![]() vol. 052022.05.31生きてきた証は電波に乗って ―ラジオと支援と高崎くんと [前編]
vol. 052022.05.31生きてきた証は電波に乗って ―ラジオと支援と高崎くんと [前編]![]() vol. 042022.01.26「壁画」と「まなざし」
vol. 042022.01.26「壁画」と「まなざし」![]() vol. 032021.12.09この現場から、「考える」を耕す
vol. 032021.12.09この現場から、「考える」を耕す![]() vol. 022021.11.10句点「。」の行方
vol. 022021.11.10句点「。」の行方![]() vol. 012021.10.08指で覆われる景色
vol. 012021.10.08指で覆われる景色