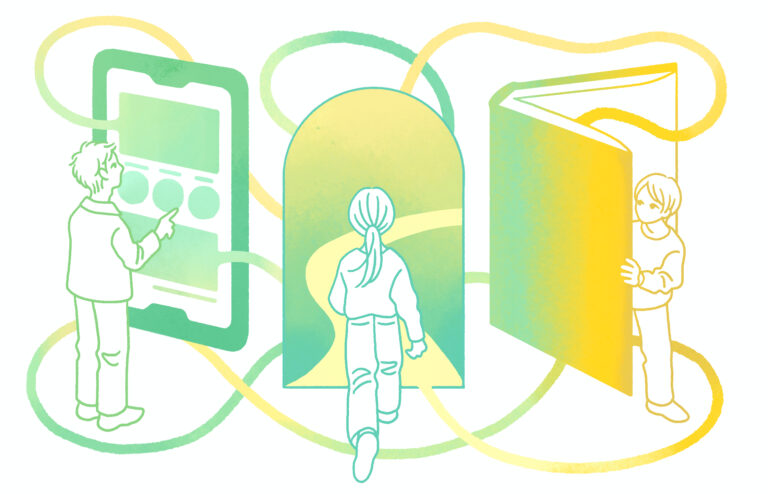ケアはしがらみも、めんどうくささもある? 竹端寛さん、羽田知世さん、石川裕子さんによる鼎談 “自分らしく生きる”を支えるしごと vol.33
Sponsored by 厚生労働省補助事業 令和7年度介護のしごと魅力発信等事業(情報発信事業)
- トップ
- “自分らしく生きる”を支えるしごと
- ケアはしがらみも、めんどうくささもある? 竹端寛さん、羽田知世さん、石川裕子さんによる鼎談
「ケア」という言葉を聞いて、なにを連想するでしょうか?
政治学者ジョアン・C・トロントは、2024年3月に邦訳された著書『ケアリング・デモクラシー──市場、平等、正義』(勁草書房)において、ケアにおける複雑なプロセスを5つに分類しています。
①関心を向けること(Caring about)
②配慮すること(Caring for)
③ケアを与えること(Care giving)
④ケアを受け取ること(Care receiving)
⑤共にケアすること(Caring with)
誰かを支えること、自分をいたわること、専門職による援助、制度としての支え――ここ数年、幅広い意味で使われるようになった「ケア」という言葉。
それぞれの生活を支えるケアはどのように実践されているのでしょうか。そもそも「ケア」とはいったいなんなのでしょう。
この問いを手に、福祉社会学者の竹端寛さん、広島県福山市で介護・福祉事業を展開する「鞆の浦(とものうら)・さくらホーム」の羽田知世さん、石川裕子さんの3名にお話を伺いました。
竹端寛さんは、福祉と社会の関係を問い直す社会福祉学を専門とし、兵庫県立大学環境人間学部の教授を務めています。著書である『ケアしケアされ、生きていく』(ちくまプリマー新書)では、ケア中心の社会を取り戻すべく「他人に迷惑をかける」ことの重要性を説きました。
そして羽田知世さん、石川裕子さんが勤める「鞆の浦・さくらホーム(以下、さくらホーム)」は、瀬戸内海に面する小さな港町・鞆の浦で、高齢者介護事業や放課後等デイサービス、就労継続支援B型事業所などを展開。2024年にこここ編集部も足を運び、鞆の浦で暮らす人々と利用者、さくらホームのスタッフが一体となって地域密着型のケアを実践する姿を目の当たりにしました。
【訪問記:「安心して歳を重ねられる町とは? 鞆の浦・さくらホームをたずねて」の記事を読む】
立場や役割が異なる3人とともに、「ケア」の輪郭を探っていきます。
無駄、余計、非合理のなかにケアが宿る
—— まずは、今回のテーマや「ケア」という言葉を聞いたとき、なにを考えたのか、連想したのか教えてください。
羽田知世さん(以下、羽田):私は取材が決まって、「ケア」という言葉を頭に置きながら日々を過ごしたり映画を観たりしていました。そこで思ったのは、生まれた環境で人生の一部が決まることと、人との出会いが人生を大きく変えたり救いになったりすることだったんです。そこからさくらホームのあり方、利用者さんとの関わり方についても考えが巡って。
さくらホームでは、「そこまでする必要ある?」「そこまでやらなくてもいいんじゃないか」というところまで利用者さんと関わることが頻繁にあるんですよ。
でも、ここ最近経営にも携わるようになって難しさを感じていて。経営の立場になるとどうしても線引きというか、効率や一定の範囲を超える関わり方の見直しを考えてしまう自分がいるんです……。ただ、効率優先でケアの範囲を切り分けてしまうと重要な部分が抜け落ちてしまう可能性もある。そのバランスの難しさを実感しているところです。
石川裕子さん(以下、石川):ともちゃん(羽田さん)の話を聞きながら話したいなと思ったことがあるんですけど、いいですか?
—— ぜひ、お願いします。
石川:去年から関わり始めた、おじいさんがいるんですけど。咽頭がんを患っていて、それまでは福山市内の病院に入院していて、鞆の浦に帰って来られるタイミングでさくらホームを利用することになったんですね。その方は入院中は真面目に治療を続けていたんですけど、自宅に戻ると、さくらホームのスタッフへの拒否反応がありました。この間お家にお伺いしたら、ウイスキーのリポビタンD割りなのか、リポビタンDのウイスキー割りなのかわからないけど、お酒をたしなまれていて(笑)。
彼の最近のブームは、たまたま再会した幼馴染と2人でコメダ珈琲のモーニングに行くこと。一度私がモーニングをご一緒したときは何のメニューが好きか、食パンはバター派かジャム派か、どうのこうのってずっと2人で話をしてるんです。「(おじいさんの)お姉さんの家でエッチなビデオを見るときはちゃんとイヤホンして聞いてるぞ!」という話までするようになって(笑)。
なんか、病気を患いながらも友達や姉弟・周りの人たちと一緒にいれることって、とっても豊かだよなって。周りの人を緩やかに巻き込んで、その人のことをみんなで一緒に考える。その人にとって大事な人たちと一緒にケアしていきたいって私は思っているんです。
竹端寛さん(以下:竹端):今の石川さんの話、めっちゃおもろいなあ。誰かをケアするとき、その人の背景や、これまでどんな生き方だったのかっていう生き様の総体があって、それを知ることで配慮や気遣いできる範囲が全然変わってきはりますよね。
僕でいうと、娘のケアをするときって「今、目の前で泣いている」だけじゃなくて、付属情報がめちゃくちゃ大事なんです。「なんで泣いてるのか」を考え直すと、「そういえば昨日寝るのが遅かったな」とか「今日の朝、ぶつくさ言ってあんまりご飯食べてへんかった」とか、忘れ物して先生に怒られたとか、いろんな物語が背景にあるなかで、不機嫌になって泣いている。
石川さんの話も同じで、そのおじいさんの物語を切らずに語ってくれはった。それだけでめっちゃ想像が広がるし、その人をありありと理解するうえで大切なディティールが詰まっているなと。だけど、そうしたディティールって、効率化や合理化という仕組みのなかでは、無駄なもの・余計なノイズだとバッサリ切られてしまう可能性が高くて。だからもしかしたら、無駄だと思われるもの、余計なもの、非合理なものも含めて関わることが、ケア的な営みなのではと思いましたね。
自己責任じゃない。緩やかなにつながる、みんなの責任
—— それぞれの話を踏まえて、ここからは聞いてみたい・話したいと思ったことを共有いただければと思います。
竹端:僕、いいですか。ぜひ羽田さん、石川さんに聞いてみたいんやけど。
—— お願いします。
竹端:まず、ケアって日々同じことを繰り返す反復行動の側面があると思うんですよ。でも、同じことの繰り返しは変化を求める人にとって、馬鹿にされてしまう傾向があると。それから、アメリカの社会学者であるアミタイ・エツィオーニは、弁護士や医師は「完全専門職(Full professions)」で、看護師や教師・ソーシャルワーカーは「半専門職(Semi-professions)」だと言っていて。
—— 完全専門職はたとえ組織に属していても、専門職の知識の範囲で行為に関する決定は専門職自身が行える。つまり、完全専門職は組織から独立できて、専門職として成立できる。一方で半専門職は、知識よりもコミュニケーションに従事する特徴があって、完全専門職に比べると容易に組織構造に統合されうる、という話ですよね。
竹端:はい。AIが発達した現代においては、相手の話を最後までじっくり聞くとか、どこにいくのかわからない話を聞き続けることのほうが大切で、人間にしかできないことになってくると僕は思うんです。2人はそういうことができている気がしていて、もとからそうでしたか?
羽田:私は、さくらホームに入職するまで、作業療法士として病院で働いていて。30歳のときに介護スタッフとして入職したんですけど、当時は竹端さんが反復行動の話をされていたように、正直「この仕事、私がやることなのかな」と思っていましたね。自分の仕事に誇りを持てなくて、友達と話すときも介護の仕事をしていることは伏せてるくらいで。
でも、それが変わってきたのは、石川さんとの出会いが大きいです。さっきのおじいさんの話もそうだけど、彼女はとにかく楽しそうに利用者さんのことを語るんですよ(笑)。その姿を見て「あ、介護ってこんなに面白く人を見られる仕事なんだ」と思って。「80代の男性」をケアするのと、「エロビデオが楽しみなおじいさん」をケアするのとでは自分の捉え方が変わってくる。そこから誇りをもてるようになりましたね。
石川:私は大学を卒業したあと、介護老人保健施設で相談員を5年していたんですけど、サービスの調整や交渉に手が取られてしまって、目の前にいる人をまったく見れていなかったですね。なんとか調整はできているけど、目の前の人はあんまり幸せそうじゃなかったり、満足していない様子だったりして。
このままだと自信をもって「ソーシャルワーカー」だと名乗れないなって思ったから、仕事を一旦離れて、社会福祉協議会の人に2週間ついて動いてみたんです。そこで、どうサービスを調整するかじゃなくて、その人にとっての大事な人をつないだら、その人が自然と変わるということを体感して。そこからですね。
竹端:うんうん。
石川:さくらホームでは、家族、友達、時には町内会長さんや民生委員の方も、その人(利用者)のことを一緒に悩むメンバーとして緩やかにつながれるようにしていて。だから、利用者さん個人が抱えている悩みや問題、置かれている状況に対して、「自己責任」とはあんまり言われないんですよ。さくらホームも含めて、みんなの責任。悩んでいる人がいたらみんなで解決したり、最後にどこで死にたいかをみんなで考えたり。その人ごとに、一緒に悩めるメンバーをつくっている感じで、「この人のためにどうできるか」を考え続けていますね。
専門性をもったケアと、ごちゃまぜのケア
竹端:そう思うとおふたりは、作業療法士や相談員という役割における専門性を一旦手放したってことになるのでしょうか。やっぱり「これが自分の専門だ」となると、責任や権限の範囲が生まれるじゃないですか。範囲内のことはやってもいいけど、範囲外のことは他の人に渡す、みたいな。でも、さくらホームは範囲どうこうとは真逆の世界のように感じています。
羽田:子どものとき、近所にすごく怖い犬がいる家があったんですよ。で、その家の前を通るときはいつも近所の大人が一緒についてきてくれたんです。そうやって、困っているから助けてもらうという環境が当たり前だったのに、病院で専門職として働くなかで、ケアする人・される人って無意識のうちに上下関係を考えてしまうようになって。だからさくらホームに入職した当初、スタッフと利用者という分け方じゃなくて、子どものときのように「困っているからみんなで助け合う」っていうごちゃまぜの状況に慣れるのに時間がかかったんです。
竹端:大学や病院である意味、専門職としての「区切り」を知ったからこそ、戻ってきたときに「なんやこのごちゃまぜな場所は!」ってなったんや。
羽田:そうですね。
石川:でも、それこそAIの話じゃないですけど……もしかしたらAIでもケアプランやアセスメントは作れるかもしれない。けど、そんなことをしてしまったら私たちがいる意味がなくなると私は思っていて。さくらホームは、とにかく目の前のその人に対して向き合うことを大切にしているから、制度・施設という枠組みに収まる感じではなくなりつつあるかもしれないですね。
竹端:うんうん。なんというか、めっちゃはみ出してるよね。本来、介護サービスの枠組みや施設としての範囲が設けられているから、そこに人を当てはめるとどうしても区切らざるを得なくなってしまう。対して、物事も人も、連続体なんだよね。その人が生きてきた人生もそうだし、地域との関係性、周りの人とのつながりも、本当は全部つながっている。さくらホームは、そうしたごちゃまぜのなかでケアをしているのかもしれませんね。
羽田:竹端さんの話を聞いてドキッとしたことがあります。経営に携わるようになると、サービスや施設としてできることと、利用者さんのことを分けて考えようとしてしまうんですよね。たとえば、スタッフの給与をあげたいと思うと、効率よく働いてもらうことの優先度がどうしても高くなってしまうし、でもそれだとさくらホームの良さがなくなるし……このあたりは石川さんともよく議論しているんですけど。
――もしかしたら、経営者、現場、研究者と、それぞれの立場によって、できる「ケア」も託したいものも異なってくるのかなと感じていて。石川さんはどうですか?
石川:私はやっぱり、介護保険や施設の枠組みに収まらないところを大事にしたいですね。その人にとっての大事な人たちを巻き込むこともそうだし、いろんな人たちと一緒に関わる生き方もありだよねというのを大事にしたい。地域のなかでケアを共有して、日々積み重ねていく、みたいな。私と、目の前のあなたのケアだけじゃなくて、もっと広げていきたい。町、会社、一緒に働いている人、近所の人、みんなでケアできたらいいなと。
多面的な役割を一人ひとりが担っているから
竹端:さくらホームではその人を知り、その人の生き様に関わり、その人の生き様の一ページとしてケアをしている。その人が中心だから、その人が暮らしている鞆の浦という町のことも考える。そうなると、誰々さんの親戚のなんとかさんとか、前にここの工場で働いてたなんとかさんとかっていうような物語性が必然的に結びついてくる。たぶん、それがめっちゃ面白いところで。
病院でも介護施設でも、個人の場所性から切り離されてしまうことってあると思うんですよ。場所性から切り離されてしまうと、その人の生き様からも切り離されてしまう。観光客が来る賑やかな日もあれば、静かな日もあって、魚が新鮮で海の香りもして、みたいな町の文脈も含めて、全部セットでのケアなんだよね。
――「ケア」の要素として、人と人の関係だけではなく、環境や場所性も大切になるというのは興味深いです。ちなみに、竹端さん自身は「ケア」という言葉に何を託しているのでしょうか。
竹端:『ケアする私の「しんどい」は、どこからくるのか: 見えないケア責任を語る言葉を紡ぐために』(勁草書房)では、「感覚的活動」という概念がキーワードになっていて、センシェントアクティビティ(Sentient activity、以下、SA)と言われています。そしてこの二つの言葉をひっくり返したらアクティブセンシビリティ(Active Sensibility)、「能動的な配慮・心配り」になるのですが、この「能動的な配慮」という言葉を思い出していました。
――イギリスの社会学者ジェニファー・メイソンが提唱した概念ですね。著者のひとりである平山さんが紹介していたメイソンの主張も印象的でした。
「ケア労働といえば、たとえば、ごはんをつくって食べさせる、といった目に見える作業だけが取り上げられがちです。しかし、そうした作業をただこなすだけでは、誰かのケアには必ずしもなりません。目に見える作業が誰かのケア、つまり、その人の生存や生活を支えるものになるためには、その作業が行われる前にも、それが行われている最中にも、さまざまな感知や思考(=SA)が行われている」(『ケアする私の「しんどい」は、どこからくるのか: 見えないケア責任を語る言葉を紡ぐために』(勁草書房)より)
竹端:そうです。それを踏まえると、石川さんはまさに「能動的な配慮」の達人なのでは。
恥ずかしながら、ケアのことを理屈っぽく語る僕自身は、なかなかそれが実践出来ないのです! それまでの自分は身軽で根無し草的に生きてきていたけど、今は娘がいて、根を張ってこの地域で暮らしていて、娘の友達とかいろんな関係性がある。そのなかで、どうやったら僕も「能動的配慮」がさらりとできるようになれるのか(笑)。
さくらホームは、能動的な気遣いをお互いにするから、困ったときは身内だけじゃなくて地域の人にも助けてもらうみたいな関係性がある。それってケアとして大事なことだし、みなさんがどんなふうに実践してきたのか、もっと知りたいです。
羽田:仕事と暮らしを切り離さないで済んでいることが大きいような気がしますね。さくらホームに携わってくれている人の半数以上が、鞆の浦の町民なんですよ。鞆の浦で生まれ育った住民であり、生活者であり、専門職であり、多面的な役割を一人ひとりが担っている。たとえば、町の中で子育てしているお父さんがさくらホームの作業療法士で、近所のおじちゃんおばちゃんが利用者として来る、みたいなことも起こり得るんです。利用者としてだけじゃない、その人のことも知っている。それがケアに活きているというか。
石川:なんか、全部つながっている。いろんな線が、多面的につながっている感じがあって。
羽田:でもさ、「絆」とか「つながり」とか、そんな綺麗な言葉じゃなさそうじゃない?なんか、こう、もっと……しがらみ?
石川:あ~。
竹端:そうか。うっとうしいもの、バカバカしいものも含めた、その人の物語なんだ。
石川:そう! そうかも!
竹端:ごちゃまぜのなかには、いやらしい話だとか、愚かな話も当然だけどある。めんどうくさいとか、うっとうしい、しつこい、くさい、やらしいとか、そういう負の感情も含めて、愛おしさがあるのかもしれへんね。「それでもなんか、あの人憎みきれんよな」みたいな。
羽田:そうですね。めんどうだけど、愛おしい(笑)。
ジタバタしながら、危機を抱える「町」をまなざす
――ここまでお話を聞いてきて、さくらホームがウェブサイトに掲げている「ケアする心を、まちの文化に」という言葉と実践がしっかり結びついているのだなと感じています。
竹端:気になっているのが、鞆の浦は町内の人だけじゃなくて、町外の人や移住者も受け入れてくれる場所なんですか?
羽田:いや、以前はそうでもなかったですね。むかしから、住民一人ひとりに役割があるんですよ。たとえば、お祭りで若頭をやったりとか。自分のポジションがあって、それをまっとうするみたいな。で、以前は町内の人以外はお祭りにも参加できないし、お神輿にも触れなかった。
石川:女性もだめだったよね。
羽田:でも今、ものすごい勢いで人が減ってきているから、「この町は、どうなるんだろう」っていう危機感みたいなものがみんなに生まれてきて。徐々に町外の人や、移住者も受け入れるようになっていますね。
竹端:いつぐらいから? 10年前ぐらい?
石川:緩やかになってきたのは、それぐらいですね。
竹端:なんとなく、ケアの文脈が変わってきているような気がしていて。昔は「この町の中だけで支え合うんや」「この町のことは、この町だけで考えるんや」と思っていた。でも、そうも言ってられへんくなったときに、町外の人やわざわざ移住してくれる人もウェルカムしながら、どうやっていこうって試行錯誤している。
羽田:10年前くらいから住んでいる人の顔がより濃く見えるようになった。と思うし、協力し合う感じが進んできていますね。危機感がみんなの共通認識としてあるから、自分たちで手を取り合って、なんとかこの町を残していこう、良さを残していこうっていうふうになっている気がします。
竹端:オープンダイアローグでは、「急性期こそ窓が開いている」って言われてますよね。
――フィンランドにある病院の精神科で生まれ、実践されてきたケアの手法ですね。患者、その家族や関係者、専門家たちが集まって対話する。「本人のことは本人のいないところでは決めない」「答えのない不確かな状況に耐える」など対話のための最低限のルールも印象的です。
竹端:ええ。精神疾患のある方も、急性期状態のときにはいろいろな表現方法で、窓が開いているのよ。関われる状態になっている。
石川:ああ、わかる。わかります。
竹端:窓が開いているってことは、対話の可能性があるということ。地元の人だけでなんとか歯を食いしばっていた時代もありつつ、状況が変わってきたから、窓を開けざるをえなくなって、町外の人も女性も受け入れる体制に変わってきたのでしょうね。さくらホームは、これまで目の前の人にとっての解決方法を常に探ってきた経験があるから、鞆の浦という町全体の危機に対しても、同じようにジタバタしながらどうにかできる方法を探しているように見えますね。利用者も、町へのアプローチも、正解はない。きっと石川さんは、ジタバタするプロなんやろうね。
石川:あはは(笑)。
竹端:ぜひ「ジタバタするプロ」に伺いたいのですが、どうやったら対象者と一緒にジタバタできるのですか? 戸惑っちゃったり、テンパったりはない?
石川:なんで、か……なんでかはわからないけど、私が先に諦めないようにしようとだけは思ってますね。先に限界を決めない。でも、たとえば一緒にいるスタッフが「辛い」って言ったときは、全員にわかってもらおうとしないで、何人かでもわかってくれるスタッフからチームにするようにしているかな。排除はしたくないから、グラデーションをつけるのは意識しているかも。
竹端:いいですね。目の前の利用者さんだけじゃなくて、同僚同士もケアする。ケアし合うチームになるための試み。
羽田:今まで、さくらホームは利用者さんを真ん中に置いたケアをしていたんですよね。どちらかというとスタッフは奉仕していこうみたいな。でもこれからは、スタッフ同士もケアし、ケアされることも考えていて。スタッフ一人ひとり、自分を大切にしながら働いてもらいたい。
竹端:スタッフのなかでのケアへの向き合い方、働き方の希望も含めて、チームとして切らない。
羽田:そうそう。そうです。
竹端:いや〜いいな。うん、めっちゃいい。さくらホームに行きたくなってきた。今度、ぜひ遊びに行かせてください。(その後、本当に日程調整して遊びに伺うことになりました(笑))

読者アンケート実施中|抽選で〈ダブディビ・デザイン〉のアートハンカチ「Square world」をプレゼント
アンケートにお答えくださった方から抽選で5名様に、こここなイッピンでも紹介した〈ダブディビ・デザイン〉のアートハンカチ「Square world」をプレゼントいたします。
※当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
※色・柄は編集部がセレクトしたものをお送りします。
(申込期限:2026年2月28日/発送:2026年3月発送予定)
マガジンハウスの3メディアで「ケアするしごと」を特集!
〈こここ〉では連載「“自分らしく生きる”を支えるしごとー介護の世界をたずねてー」 や「ケアするしごと、はじめの一歩」を通して、さまざまな「ケアするしごと」を取り上げています。また、〈anan web〉や〈POPEYE web〉でもさまざまな記事を公開中! ぜひご覧ください。
【anan web】
・山崎怜奈さん、介護のしごとを初体験! 子どもと高齢者がともに過ごす「深川えんみち」へ
・移住して実現! 鞆の浦で“自分らしい介護”を届ける24歳の物語
・介護の仕事も自分らしく! 東京・三鷹で働く三者三様の働き方ケーススタディ
【POPEYE web】
Profile
Profile
Profile
- ライター:田邊なつほ
-
建築業界の営業に従事し、ライターに転身。介護・福祉業界の採用支援を行う企業の業務委託ライターを勤め、イベントレポートやインタビュー記事の執筆を行う。編集プロダクションで編集者も経験。福祉・介護、ビジネス、アパレルなど幅広いジャンルの取材・執筆、コンテンツ制作が得意。
この記事の連載Series
連載:“自分らしく生きる”を支えるしごと
![]() vol. 322026.01.14本から「介護にあるまなざし」に出会う。編集者、ダンサー、美術家、介護職員の選ぶ4冊
vol. 322026.01.14本から「介護にあるまなざし」に出会う。編集者、ダンサー、美術家、介護職員の選ぶ4冊![]() vol. 312025.12.26「助けて」という言葉が必要になる前に。社会福祉法人丹緑会特別養護老人ホーム栗林荘をたずねて
vol. 312025.12.26「助けて」という言葉が必要になる前に。社会福祉法人丹緑会特別養護老人ホーム栗林荘をたずねて![]() vol. 302025.12.17いいチームってなんだろう? 多職種連携で「看取り」に取り組む特別養護老人ホーム「芦花ホーム」をたずねて
vol. 302025.12.17いいチームってなんだろう? 多職種連携で「看取り」に取り組む特別養護老人ホーム「芦花ホーム」をたずねて![]() vol. 292025.12.10一人ひとりの「あたり前」を大切にできる環境とは?「あたり前の暮らしサポートセンター布施屋」をたずねて
vol. 292025.12.10一人ひとりの「あたり前」を大切にできる環境とは?「あたり前の暮らしサポートセンター布施屋」をたずねて![]() vol. 282025.12.05安心して歳を重ねられる地域とは? 社会福祉法人くらしのハーモニーをたずねて
vol. 282025.12.05安心して歳を重ねられる地域とは? 社会福祉法人くらしのハーモニーをたずねて![]() vol. 272025.11.18「ケア」を感じたマンガを教えてください。作家、社会学者、アーティスト、福祉施設長の選ぶ4作品
vol. 272025.11.18「ケア」を感じたマンガを教えてください。作家、社会学者、アーティスト、福祉施設長の選ぶ4作品![]() vol. 262025.11.10「安心できる住まい」はどう育まれる? 特別養護老人ホーム「美里ヒルズ」をたずねて
vol. 262025.11.10「安心できる住まい」はどう育まれる? 特別養護老人ホーム「美里ヒルズ」をたずねて![]() vol. 252025.03.06地域の「居場所」ってなんだろう? 佛子園「三草二木 西圓寺」をたずねて
vol. 252025.03.06地域の「居場所」ってなんだろう? 佛子園「三草二木 西圓寺」をたずねて![]() vol. 242025.02.27幅広く使われる「ケア」をどうとらえる? 向坂くじらさん、吉田真一さんと考える
vol. 242025.02.27幅広く使われる「ケア」をどうとらえる? 向坂くじらさん、吉田真一さんと考える![]() vol. 232025.01.30本から「介護にあるまなざし」に出会う。イラストレーター、哲学者、ジャーナリスト、介護福祉士の選ぶ4冊
vol. 232025.01.30本から「介護にあるまなざし」に出会う。イラストレーター、哲学者、ジャーナリスト、介護福祉士の選ぶ4冊![]() vol. 222025.01.23地域の歴史や文化とともに歩む福祉とは? ライフの学校「六郷キャンパス」をたずねて
vol. 222025.01.23地域の歴史や文化とともに歩む福祉とは? ライフの学校「六郷キャンパス」をたずねて![]() vol. 212025.01.20多世代が一緒に過ごすことで生まれる安心とは?「深川えんみち」をたずねて
vol. 212025.01.20多世代が一緒に過ごすことで生まれる安心とは?「深川えんみち」をたずねて![]() vol. 202025.01.10アーティストが滞在する福祉施設とは? 「デイサービス楽らく」をたずねて
vol. 202025.01.10アーティストが滞在する福祉施設とは? 「デイサービス楽らく」をたずねて![]() vol. 192024.12.18「助けて」と言い合える環境を育むには? 「みんなの家 タブノキ」をたずねて
vol. 192024.12.18「助けて」と言い合える環境を育むには? 「みんなの家 タブノキ」をたずねて![]() vol. 182024.12.13私もあなたも、主人公でいられるように。「DAYS BLG! はちおうじ」をたずねて
vol. 182024.12.13私もあなたも、主人公でいられるように。「DAYS BLG! はちおうじ」をたずねて![]() vol. 172024.12.12「ケア」を感じたマンガを教えてください。組織開発コンサルタント、俳優、福祉施設所長、介護福祉士の選ぶ4作品
vol. 172024.12.12「ケア」を感じたマンガを教えてください。組織開発コンサルタント、俳優、福祉施設所長、介護福祉士の選ぶ4作品![]() vol. 162024.11.08安心して歳を重ねられる町とは? 鞆の浦・さくらホームをたずねて
vol. 162024.11.08安心して歳を重ねられる町とは? 鞆の浦・さくらホームをたずねて![]() vol. 152024.03.12介護のしごとに興味をもったとき、はじめの一歩はどうすれば?
vol. 152024.03.12介護のしごとに興味をもったとき、はじめの一歩はどうすれば?![]() vol. 142024.02.27認知症を“体験”する「VR認知症」。イシヅカユウさんと体験して気づいたこと
vol. 142024.02.27認知症を“体験”する「VR認知症」。イシヅカユウさんと体験して気づいたこと![]() vol. 132024.02.22認知症のある方100人以上にインタビューをして気づいたこと。認知症未来共創ハブ代表・堀田聰子さん
vol. 132024.02.22認知症のある方100人以上にインタビューをして気づいたこと。認知症未来共創ハブ代表・堀田聰子さん![]() vol. 122024.02.20暮らしのなかで閉じる命をつないでいく 写真家/訪問看護師 尾山直子さん
vol. 122024.02.20暮らしのなかで閉じる命をつないでいく 写真家/訪問看護師 尾山直子さん![]() vol. 112024.02.19科学的な介護ってなんだろう? 福祉楽団「杜の家なりた」をたずねて
vol. 112024.02.19科学的な介護ってなんだろう? 福祉楽団「杜の家なりた」をたずねて![]() vol. 102024.02.08「老いと共に生きる」を映画から考える。編集者、映画作家、介護福祉士、福祉施設運営者の選ぶ5作品
vol. 102024.02.08「老いと共に生きる」を映画から考える。編集者、映画作家、介護福祉士、福祉施設運営者の選ぶ5作品![]() vol. 092023.12.20居場所ってなんだろう? 人が自然と集まる場所を目指す「52間の縁側」をたずねて
vol. 092023.12.20居場所ってなんだろう? 人が自然と集まる場所を目指す「52間の縁側」をたずねて![]() vol. 082023.12.13「ケア」を感じたマンガを教えてください。文学研究者、精神科医、看護師、介護福祉士、文筆家の選ぶ5作品
vol. 082023.12.13「ケア」を感じたマンガを教えてください。文学研究者、精神科医、看護師、介護福祉士、文筆家の選ぶ5作品![]() vol. 072023.12.06自然の循環に身を委ね、大地と共に生きる。「里・つむぎ八幡平」が実践する「半農・半介護」の暮らし
vol. 072023.12.06自然の循環に身を委ね、大地と共に生きる。「里・つむぎ八幡平」が実践する「半農・半介護」の暮らし![]() vol. 062023.11.29介護施設×学生シェアハウス「みそのっこ」が教えてくれる、「介護×場づくり」の可能性
vol. 062023.11.29介護施設×学生シェアハウス「みそのっこ」が教えてくれる、「介護×場づくり」の可能性![]() vol. 052023.11.10いくつになっても「働く」は楽しい。ばあちゃんたちの生きがいとビジネスの両立を目指す、株式会社うきはの宝をたずねて
vol. 052023.11.10いくつになっても「働く」は楽しい。ばあちゃんたちの生きがいとビジネスの両立を目指す、株式会社うきはの宝をたずねて![]() vol. 042023.11.07居心地の良い場所の条件ってなんだろう? 浦安にある高齢者向けの住まい「銀木犀」をたずねて
vol. 042023.11.07居心地の良い場所の条件ってなんだろう? 浦安にある高齢者向けの住まい「銀木犀」をたずねて![]() vol. 032023.10.31ケアってなんだろう? ナイチンゲール看護研究所・金井一薫さんをたずねて
vol. 032023.10.31ケアってなんだろう? ナイチンゲール看護研究所・金井一薫さんをたずねて![]() vol. 022023.10.30さまざまな命に囲まれて、心を動かして生きる。 園芸療法を行う「晴耕雨読舎」をたずねて
vol. 022023.10.30さまざまな命に囲まれて、心を動かして生きる。 園芸療法を行う「晴耕雨読舎」をたずねて![]() vol. 012023.10.11自分らしく生きるってなんだろう? 一人ひとりの人生に向き合う介護事業所「あおいけあ」をたずねて
vol. 012023.10.11自分らしく生きるってなんだろう? 一人ひとりの人生に向き合う介護事業所「あおいけあ」をたずねて