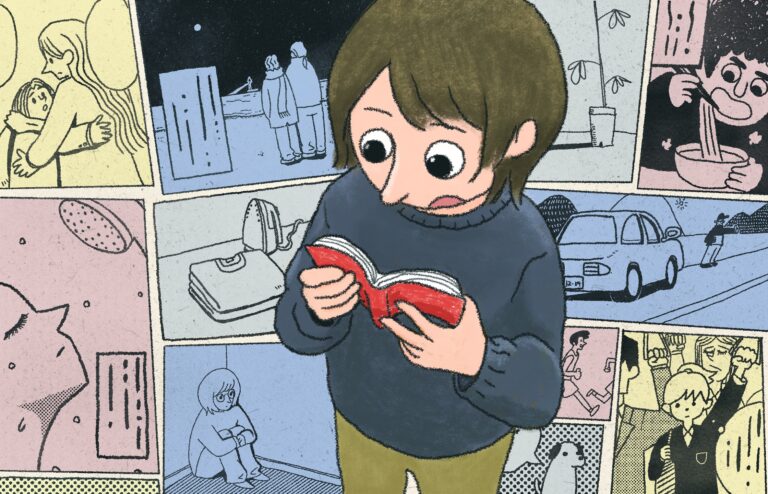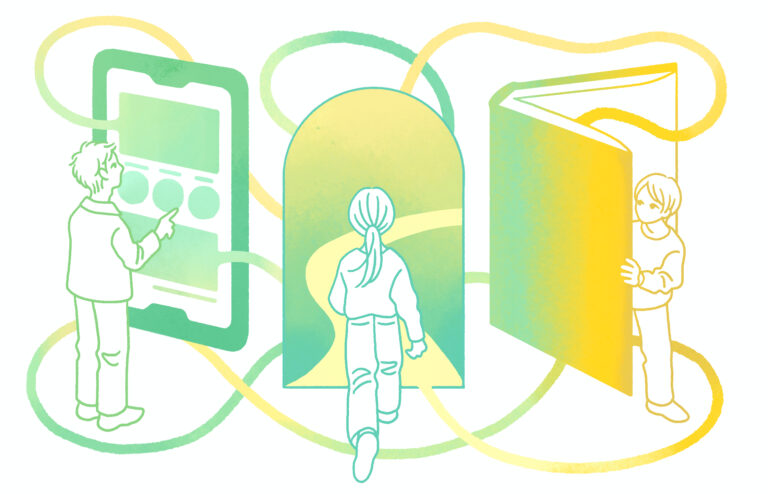「安心できる住まい」はどう育まれる? 特別養護老人ホーム「美里ヒルズ」をたずねて “自分らしく生きる”を支えるしごと vol.26
Sponsored by 厚生労働省補助事業 令和7年度介護のしごと魅力発信等事業(情報発信事業)
- トップ
- “自分らしく生きる”を支えるしごと
- 「安心できる住まい」はどう育まれる? 特別養護老人ホーム「美里ヒルズ」をたずねて
「父が施設に入ることになるかも」
友人からそう聞いたとき、とっさに言葉が出なかった。
施設に入ると、暮らしは大きく変わるんだろう。住み慣れた家を離れ、初めて会う人たちと集団で過ごしたり、施設のスケジュールに沿って動いたりすることに、ストレスを感じるかもしれない。そんな場所で安心できる暮らしを保つのは、簡単ではないはずだーー。言葉が見つからなかったのは、そう思い込んでいたからかもしれない。
だから三重県津市にある「特別養護老人ホーム 美里ヒルズ」の話を聞いたとき、私は半信半疑だった。
美里ヒルズでは「特養を施設ではなく住まいに」という思いのもと、「ユニットケア」を実践しているという。
ユニットケアとは、介護施設において入居者を10人程度の小規模グループ(ユニット)に分け、家庭的な環境の中できめ細かなケアを提供する方法のこと。起床や食事などの時間を一律にせず、一人ひとりの生活リズムや個性が尊重される。
70人が入居する施設で、本当にそんな個別ケアが実現できるのだろうか? 入居者が安心して過ごせる環境は、どう育まれているのだろう? そんな疑問を携えて美里ヒルズを訪れてみると、そこには私が思い描いていた介護施設とは違う光景があった。
「自分の家族を入居させたい」と思えるように
クネクネとした山道を車で登っていく。山道を抜けるとポツポツと民家が現れ、しばらくして丘の上にある今回の取材先に到着した。
人口約3,000人の美里町(三重県津市)に、「特別養護老人ホーム 美里ヒルズ」はある。緑に囲まれた、平屋の大きな建物。ベージュの洋瓦の屋根に、採光用なのだろうか、煙突のような小さな塔がちょこんと立っているのが親しみを感じさせる。

出迎えてくれたのは、施設長の世古口正臣さんだ。「安心できる住まい」がどんな工夫のもとにつくられているのかを教えてもらうべく、私は施設を案内してもらうことにした。

歩き出すと、入り口付近のお菓子売り場で、スナックを買いにきていた入居者に遭遇した。この男性は、美里ヒルズで働く職員のご家族だという。ここでは、自分の家族を入居させる職員も多いそうだ。
「自分の家族を入居させたい施設になっているかどうかは、大切な基準です」と世古口さんはいう。

美里ヒルズの入居者は70人。7つに分かれたユニットは、10の個室と共用のリビング、対面キッチン、デッキテラス、トイレで構成される。

ユニットの入り口は、まるで自宅の玄関のように飾り付けされていた。可愛らしいポストがあったり、味のある木製の靴箱があったり。住宅メーカーに依頼してつけたという門扉まで。


「おじゃまします〜」と言いながら玄関を通っていく看護師さんを横目に、世古口さんはこう話す。
「おじゃまします」と言いましょうと定めているわけではないし、接遇マナー研修などもしていないんですよ。玄関を作ることで、職員の振る舞いも変わっていくのだと思います。

そういえば、職員がみんな私服を着ている。聞けばユニフォームはなく、清潔感のある服装であれば自由だという。
ジャージやポロシャツを制服にすると、お出かけした際に、いかにも「入居者と職員」に見えてしまうでしょう。あとは看護師が一般的に使用するワゴンのような道具もありません。施設っぽさをイメージするものはなるべく使わないようにしています。
世古口さんが言う「施設っぽさ」とは、集団を管理する場所を連想させるものだ。制服や業務用の道具ひとつが、「ここは生活の場ではない」という印象を作ってしまう。美里ヒルズを入居者にとっての「住まい」にするため、施設や病院をイメージするものはなるべく使わないようにしているそうだ。
待ち遠しくなるような食卓を
各ユニットごとの共用スペースであるリビングには、大小さまざまなダイニングテーブルが5つほど置かれている。ウトウトとしている人、ソファでテレビを見ている人、ひとりでお茶を飲んでいる人。それぞれが思い思いに過ごしていた。



玄関や共用スペースの装飾とレイアウトは、各ユニットの担当者が決められた予算のなかで作り上げたものだ。
最初にリビングを作ってもらっています。各ユニット共通の決まりごととして定めたのは、ダイニングテーブルを複数配置すること、生きた草花を一つは置くこと。装飾の選定基準は、自分の家にも置きたいかどうかです。
温かみのあるオレンジ色の照明や、対面キッチンで作業する職員の姿。そして、たくさんの雑貨や植物で彩られた景色に、なんだか知り合いの家に遊びにきたかのような気持ちになる。
キッチン前のカウンターには、ポットなどの家電製品や入居者それぞれの食器などが並ぶ。「怪我のリスクがあるものは手の届かないところに」という常識とは真逆の光景だ。
入居者さんやその家族が、好きなタイミングで飲んだり食べたりできるようにしているんです。美里ヒルズでは、各ユニットにスタッフが常駐し目を配っていて、入居者さんが自由に過ごせることを優先しています。

世古口さんはキッチンに目をやり、こう続ける。
ここでお味噌汁を作り、ご飯を炊いています。車椅子を使う利用者さんからも調理するスタッフの姿が見えるし、おいしそうなご飯の香りが届くようにしているんです。
美里ヒルズでは入居者70人のうち9割が普通食で、咀嚼や嚥下がしやすいソフト食やムース食をとる人は1割だという。
食事のケアは“食べさせ方の技術”だと思われがちですが、待ち遠しくなるような食卓をどう演出するかも含めてケアだと考えています。職員がワゴンで食事をテーブルに運び、「今日はどれぐらい食べますか?」などと聞きながら配膳したり、入居者自身に盛り付けをやってもらったりして、自然と意欲がわくような環境づくりをしているんです。

介護は”お世話する仕事”ではない
入居者一人ひとりを尊重するケアを支えるのは、「24時間暮らしの支援シート(24シート)」だ。このシートには、各入居者の起床から就寝までの生活リズム、好みの過ごし方、必要な支援の内容とタイミングなどが詳細に記録されている。
たとえば、6時に起きて早めの朝食をとりたい人もいれば、8時半まで寝ていたい人もいる。入浴も午前中を好む人もいれば、夕方が落ち着く人もいる。24シートを活用することで、ケアする側の業務スケジュールではなく、一人ひとりの生活習慣や希望に沿ったケアが実現できる。

世古口さんは「介護は“お世話する仕事”だと思われがちで、『誰にでもできる』と言われることがあるのですが、それは違うんです」と指摘する。
たとえば排泄の介助。オムツを替える作業自体は、やり方を覚えればできる作業かもしれません。でも私たちがやっているのは、尿意がない方、排泄の感覚がわからなくなった方を、どのタイミングでトイレへお連れすれば気持ちよく排泄できるかを見極めることなんです。日々の排泄記録をデータ化し、その日の食事や水分摂取量、体調、様子を観察して、適切なタイミングでトイレに誘導します。できるだけ最期までトイレでの排泄を諦めずにすむように、専門的な技術をもってケアにあたっているんです。
世古口さんは、言葉に力を込めて続ける。
オムツを受け入れている方も、本当はいろいろなことを諦めているはずです。私は、美里ヒルズを「自分らしい暮らし」を諦めなくていい場所にしたい。恥ずかしい思いをさせないこと、尊厳を守ること。それが私たちの仕事だと思っています。
美里ヒルズの入居者の要介護度は、全国の特別養護老人ホームの平均と同等だが、テープ留めのオムツを使用するのは70人中3人のみ。9割が普通のパンツで過ごし、トイレで排泄しているという。

一人ひとり異なる生活サイクルに合わせて個別にケアをするのは、とても大変なことのように思える。職員の負担にはならないのだろうか? そう尋ねると、「手間をかけた方が、結果的に職員も楽なんです」と世古口さんは話す。
時間を決めて一斉にケアする方が、実は大変なんです。「時間内に作業を終えられるかな」「遅番のスタッフに交代するまでにこれを終わらせなきゃ」などと焦ってスタッフに余裕がなくなると、それが入居者にも伝わるし、イレギュラーなお願いにも応えられない。すると、特に認知症のある方は混乱してしまい、職員を困らせるような行動をとる。悪循環なんです。
逆に、一人ひとりの生活リズムを把握すれば、職員の1日の動きも見えてくる。たとえば、Aさんは朝7時に起きて8時に朝食、Bさんは9時起床で10時に朝食、というように個々のペースを理解していれば、「今、誰に何をすべきか」が明確になる。時間に追われながら全員を一斉に動かすより、一人ひとりのペースに沿う方が業務が分散し、職員にとっても無理のない流れができるのだ。
さらに美里ヒルズでは職員をユニットごとに固定し、担当する入居者の数を限定しているため、想定外の出来事にも柔軟に対応できる体制なのだという。
職員が働きやすい環境と、入居者が安心して暮らせる環境は、実はイコールなんです。職員の都合を優先し、効率重視になったり入居者をコントロールしようとしたりしてしまうと、入居者にとっては不自由で居心地の悪い場所になる。入居者が穏やかに過ごせる場所を作れば、それが結果的に職員にとっても働きやすい環境になるんです。



若い世代が「働き続けたい」と思える環境に
美里ヒルズでは20〜30代の職員が6割以上を占める。「ここで働きたい」と片道1時間以上かけて通勤する人もいるそうだ。
子育て世代は夜勤免除で、小学校入学までの時短勤務制度を設けるなど、若い人たちが「介護の現場で働き続けたい」と思える環境を目指していると世古口さんは語る。
私たちは、入社4年目の畔地真央さんにも話を聞かせてもらうことにした。
両親が介護職だった彼女は、小学生の時から「自分も介護の仕事をするのだと思っていた」という。高校3年生のとき、求人で美里ヒルズを知り、ユニットケアに興味を持って就職を決めた。
畔地さん:最初はユニットケアのことはよくわからなかったんです。でも先輩たちの姿を見ていて、入居者さんと会話する時間をしっかりとっていると思いました。友達も同じ介護の仕事をしていて、他の現場の話を聞くことがあるんですけど、やっぱり美里ヒルズは違うなって感じます。
畔地さんが見た先輩たちは、一人ひとりと丁寧に関わることを大切にしていた。日々会話を重ね、その日の調子や体調の変化を知り、その人らしい過ごし方を支える。それが彼女が最初に肌で感じた、美里ヒルズでのユニットケアの実践だった。

日々のケアの中で、畔地さんが常に意識しているのは「職員主導にならないこと」だ。
畔地さん:「自分たちのペースで動いちゃいけない」っていうことは、常に頭に入れています。働き続けるうちに、入居者さん一人ひとりのペースで日々を過ごしてもらうことが一番大事なんだな、とわかるようになりました。
昨年、3年間過ごしたユニット「花の街2丁目」から、「色彩の街」へと異動になった畔地さん。一人ひとりの生活サイクルが異なるため、まずは各入居者を知ることから始めなければならない。
畔地さん:最初は覚えることがいっぱいで大変でした。でも24シートがあるので、それを見て一人ひとりのペースや好み、1日の流れをつかむことができました。
働く中で、彼女の心に残った出来事がある。
ある入居者の看取りをしたときのこと。最期のとき、畔地さんが手を握ると、その人はギュッと握り返してくれた。
畔地さん:言葉はなくても、何かが伝わった気がして。この仕事をしていてよかったなと心から思いました。
取材中、「面接みたいで緊張する〜!」と茶目っけたっぷりに私たちを和ませてくれた彼女だったが、最後にそう、静かに語ってくれた。
一人ひとりに向き合い、その人のペースを大切にする。そうした「理想の介護」を実践できているからこそ、畔地さんのように真っ直ぐに、仕事への誇りや喜びを感じられるのかもしれない。


「私は幸福や」。夢を叶えた入居者の声
入居者の「自分らしい暮らし」を支える取り組みの一つに、「夢プランプロジェクト」がある。
美里ヒルズでは「介護サービスの計画書」であるケアプランに、入居者の「夢」を記載しているのだ。
「体が思うように動かなくなったり認知症になったりしてから、諦めてきたことがたくさんあるはずです。それを美里ヒルズで叶えられたらいいなって。入居者の夢を実現するために他職種とも連携して、ケアプランの一番大事なポイントとして共有しています」
「夢プラン」の内容はさまざまだ。
いつもベッドで音楽を聞いている入居者の夢は「ビートルズを聴きたい」。そのほか、「ナゴヤドームに野球観戦に行きたい」「伊勢神宮にお参りに行きたい」「家族とお墓参りに行きたい」など、一人ひとりの思いが反映されている。
世古口さん:入居者さんとご家族のお出かけでは、私たちはご家族のサポート役。入居者の夢を叶えることに加えて、ご家族の「やってあげられた」という満足感にもつながるんです。
夫と一緒に美里ヒルズに入居した、若林ふみ子さんという女性がいる。
ある日、ふみ子さんの夫・八(わかつ)さんが「ヤマノカミさんに会いに行かなあかん」と言ったそうだ。「ヤマノカミ」がなんのことか、最初は誰もわからなかった。職員が詳しく聞いてみると、五穀豊穣・無病息災を祈る神事で祀られる「山の神様」であることがわかった。若林さん夫妻がかつて暮らしていた地域で、長年大切にしてきた場所だ。
山の神様は山の中にあり、平坦な道のりではなかったが、職員とご家族が一緒になって、若林さん夫妻の願いを叶えることにした。
2025年5月3日。細い山道を抜け、少し開けた場所に出ると、そこに山の神様の石碑があった。前日の雨で地面はぬかるんでいたが、家族が車椅子を押して石碑の近くまで進む。
山の神様の前で、八さんとふみ子さんは何も言わず、静かに手を合わせていたそうだ。最後に、息子夫妻とともに、山の神様の前で写真を撮影した。
取材当日、その日のことを思い返しながら、ふみ子さんはかわいらしい笑顔を浮かべた。
私は嬉しい、幸福やと思いました。

美里ヒルズには、入居者が最期まで”自分らしく暮らす”ことを諦めずに済むように、一人ひとりの声に耳を傾け、寄り添い続ける人たちがいた。安心して過ごせる「住まい」は、そうした人たちによる日々の積み重ねの中で育まれていた。
今なら、「父が施設に入ることになるかも」と打ち明けてくれた友人に、なんて声をかけるだろう。やっぱりうまい言葉は浮かんでこないけれど、今日見た景色を伝えることはできそうだ。そんなことを考えながら、私は帰路についた。

読者アンケート実施中|抽選で〈ダブディビ・デザイン〉のアートハンカチ「Square world」をプレゼント
アンケートにお答えくださった方から抽選で5名様に、こここなイッピンでも紹介した〈ダブディビ・デザイン〉のアートハンカチ「Square world」をプレゼントいたします。
※当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
※色・柄は編集部がセレクトしたものをお送りします。
(申込期限:2026年2月28日/発送:2026年3月発送予定)
マガジンハウスの3メディアで「ケアするしごと」を特集!
〈こここ〉では連載「“自分らしく生きる”を支えるしごとー介護の世界をたずねてー」 や「ケアするしごと、はじめの一歩」を通して、さまざまな「ケアするしごと」を取り上げています。また、〈anan web〉や〈POPEYE web〉でもさまざまな記事を公開中! ぜひご覧ください。
【anan web】
・山崎怜奈さん、介護のしごとを初体験! 子どもと高齢者がともに過ごす「深川えんみち」へ
・移住して実現! 鞆の浦で“自分らしい介護”を届ける24歳の物語 ・介護の仕事も自分らしく! 東京・三鷹で働く三者三様の働き方ケーススタディ
【POPEYE web】
Profile
Profile
- ライター:白石かりん
-
1989年生まれ、さいたま市在住。大学や一般企業で働いたのち、2020年にフリーライターへ転身。機能不全家庭で育った経験から、「福祉」や「家族」といったテーマに関心を寄せ、取材・執筆をする。夫と猫と3人暮らし。
この記事の連載Series
連載:“自分らしく生きる”を支えるしごと
![]() vol. 322026.01.14本から「介護にあるまなざし」に出会う。編集者、ダンサー、美術家、介護職員の選ぶ4冊
vol. 322026.01.14本から「介護にあるまなざし」に出会う。編集者、ダンサー、美術家、介護職員の選ぶ4冊![]() vol. 312025.12.26「助けて」という言葉が必要になる前に。社会福祉法人丹緑会特別養護老人ホーム栗林荘をたずねて
vol. 312025.12.26「助けて」という言葉が必要になる前に。社会福祉法人丹緑会特別養護老人ホーム栗林荘をたずねて![]() vol. 302025.12.17いいチームってなんだろう? 多職種連携で「看取り」に取り組む特別養護老人ホーム「芦花ホーム」をたずねて
vol. 302025.12.17いいチームってなんだろう? 多職種連携で「看取り」に取り組む特別養護老人ホーム「芦花ホーム」をたずねて![]() vol. 292025.12.10一人ひとりの「あたり前」を大切にできる環境とは?「あたり前の暮らしサポートセンター布施屋」をたずねて
vol. 292025.12.10一人ひとりの「あたり前」を大切にできる環境とは?「あたり前の暮らしサポートセンター布施屋」をたずねて![]() vol. 282025.12.05安心して歳を重ねられる地域とは? 社会福祉法人くらしのハーモニーをたずねて
vol. 282025.12.05安心して歳を重ねられる地域とは? 社会福祉法人くらしのハーモニーをたずねて![]() vol. 272025.11.18「ケア」を感じたマンガを教えてください。作家、社会学者、アーティスト、福祉施設長の選ぶ4作品
vol. 272025.11.18「ケア」を感じたマンガを教えてください。作家、社会学者、アーティスト、福祉施設長の選ぶ4作品![]() vol. 252025.03.06地域の「居場所」ってなんだろう? 佛子園「三草二木 西圓寺」をたずねて
vol. 252025.03.06地域の「居場所」ってなんだろう? 佛子園「三草二木 西圓寺」をたずねて![]() vol. 242025.02.27幅広く使われる「ケア」をどうとらえる? 向坂くじらさん、吉田真一さんと考える
vol. 242025.02.27幅広く使われる「ケア」をどうとらえる? 向坂くじらさん、吉田真一さんと考える![]() vol. 232025.01.30本から「介護にあるまなざし」に出会う。イラストレーター、哲学者、ジャーナリスト、介護福祉士の選ぶ4冊
vol. 232025.01.30本から「介護にあるまなざし」に出会う。イラストレーター、哲学者、ジャーナリスト、介護福祉士の選ぶ4冊![]() vol. 222025.01.23地域の歴史や文化とともに歩む福祉とは? ライフの学校「六郷キャンパス」をたずねて
vol. 222025.01.23地域の歴史や文化とともに歩む福祉とは? ライフの学校「六郷キャンパス」をたずねて![]() vol. 212025.01.20多世代が一緒に過ごすことで生まれる安心とは?「深川えんみち」をたずねて
vol. 212025.01.20多世代が一緒に過ごすことで生まれる安心とは?「深川えんみち」をたずねて![]() vol. 202025.01.10アーティストが滞在する福祉施設とは? 「デイサービス楽らく」をたずねて
vol. 202025.01.10アーティストが滞在する福祉施設とは? 「デイサービス楽らく」をたずねて![]() vol. 192024.12.18「助けて」と言い合える環境を育むには? 「みんなの家 タブノキ」をたずねて
vol. 192024.12.18「助けて」と言い合える環境を育むには? 「みんなの家 タブノキ」をたずねて![]() vol. 182024.12.13私もあなたも、主人公でいられるように。「DAYS BLG! はちおうじ」をたずねて
vol. 182024.12.13私もあなたも、主人公でいられるように。「DAYS BLG! はちおうじ」をたずねて![]() vol. 172024.12.12「ケア」を感じたマンガを教えてください。組織開発コンサルタント、俳優、福祉施設所長、介護福祉士の選ぶ4作品
vol. 172024.12.12「ケア」を感じたマンガを教えてください。組織開発コンサルタント、俳優、福祉施設所長、介護福祉士の選ぶ4作品![]() vol. 162024.11.08安心して歳を重ねられる町とは? 鞆の浦・さくらホームをたずねて
vol. 162024.11.08安心して歳を重ねられる町とは? 鞆の浦・さくらホームをたずねて![]() vol. 152024.03.12介護のしごとに興味をもったとき、はじめの一歩はどうすれば?
vol. 152024.03.12介護のしごとに興味をもったとき、はじめの一歩はどうすれば?![]() vol. 142024.02.27認知症を“体験”する「VR認知症」。イシヅカユウさんと体験して気づいたこと
vol. 142024.02.27認知症を“体験”する「VR認知症」。イシヅカユウさんと体験して気づいたこと![]() vol. 132024.02.22認知症のある方100人以上にインタビューをして気づいたこと。認知症未来共創ハブ代表・堀田聰子さん
vol. 132024.02.22認知症のある方100人以上にインタビューをして気づいたこと。認知症未来共創ハブ代表・堀田聰子さん![]() vol. 122024.02.20暮らしのなかで閉じる命をつないでいく 写真家/訪問看護師 尾山直子さん
vol. 122024.02.20暮らしのなかで閉じる命をつないでいく 写真家/訪問看護師 尾山直子さん![]() vol. 112024.02.19科学的な介護ってなんだろう? 福祉楽団「杜の家なりた」をたずねて
vol. 112024.02.19科学的な介護ってなんだろう? 福祉楽団「杜の家なりた」をたずねて![]() vol. 102024.02.08「老いと共に生きる」を映画から考える。編集者、映画作家、介護福祉士、福祉施設運営者の選ぶ5作品
vol. 102024.02.08「老いと共に生きる」を映画から考える。編集者、映画作家、介護福祉士、福祉施設運営者の選ぶ5作品![]() vol. 092023.12.20居場所ってなんだろう? 人が自然と集まる場所を目指す「52間の縁側」をたずねて
vol. 092023.12.20居場所ってなんだろう? 人が自然と集まる場所を目指す「52間の縁側」をたずねて![]() vol. 082023.12.13「ケア」を感じたマンガを教えてください。文学研究者、精神科医、看護師、介護福祉士、文筆家の選ぶ5作品
vol. 082023.12.13「ケア」を感じたマンガを教えてください。文学研究者、精神科医、看護師、介護福祉士、文筆家の選ぶ5作品![]() vol. 072023.12.06自然の循環に身を委ね、大地と共に生きる。「里・つむぎ八幡平」が実践する「半農・半介護」の暮らし
vol. 072023.12.06自然の循環に身を委ね、大地と共に生きる。「里・つむぎ八幡平」が実践する「半農・半介護」の暮らし![]() vol. 062023.11.29介護施設×学生シェアハウス「みそのっこ」が教えてくれる、「介護×場づくり」の可能性
vol. 062023.11.29介護施設×学生シェアハウス「みそのっこ」が教えてくれる、「介護×場づくり」の可能性![]() vol. 052023.11.10いくつになっても「働く」は楽しい。ばあちゃんたちの生きがいとビジネスの両立を目指す、株式会社うきはの宝をたずねて
vol. 052023.11.10いくつになっても「働く」は楽しい。ばあちゃんたちの生きがいとビジネスの両立を目指す、株式会社うきはの宝をたずねて![]() vol. 042023.11.07居心地の良い場所の条件ってなんだろう? 浦安にある高齢者向けの住まい「銀木犀」をたずねて
vol. 042023.11.07居心地の良い場所の条件ってなんだろう? 浦安にある高齢者向けの住まい「銀木犀」をたずねて![]() vol. 032023.10.31ケアってなんだろう? ナイチンゲール看護研究所・金井一薫さんをたずねて
vol. 032023.10.31ケアってなんだろう? ナイチンゲール看護研究所・金井一薫さんをたずねて![]() vol. 022023.10.30さまざまな命に囲まれて、心を動かして生きる。 園芸療法を行う「晴耕雨読舎」をたずねて
vol. 022023.10.30さまざまな命に囲まれて、心を動かして生きる。 園芸療法を行う「晴耕雨読舎」をたずねて![]() vol. 012023.10.11自分らしく生きるってなんだろう? 一人ひとりの人生に向き合う介護事業所「あおいけあ」をたずねて
vol. 012023.10.11自分らしく生きるってなんだろう? 一人ひとりの人生に向き合う介護事業所「あおいけあ」をたずねて