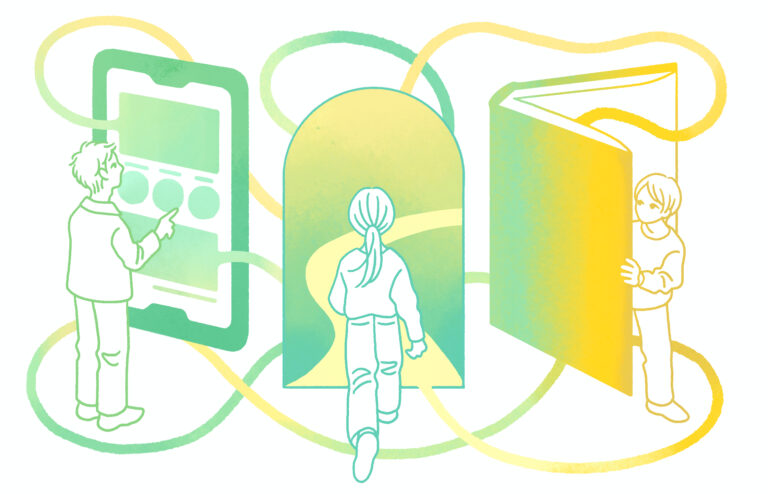暮らしのなかで閉じる命をつないでいく 写真家/訪問看護師 尾山直子さん “自分らしく生きる”を支えるしごと vol.12
Sponsored by 厚生労働省補助事業 令和5年度介護のしごと魅力発信等事業(情報発信事業)
- トップ
- “自分らしく生きる”を支えるしごと
- 暮らしのなかで閉じる命をつないでいく 写真家/訪問看護師 尾山直子さん
東京・世田谷にある桜新町アーバンクリニックで訪問看護師として働く尾山直子さんは、写真家としても活動している。看護師としてのキャリアは20年ほど。働きながら写真を学び、2021年には初の個展『ぐるり。』を開催。写真と文で構成した展覧会は、地元世田谷をはじめ軽井沢、神戸、名古屋など各地に巡回した。
尾山さんは、なぜ看護師をしながら写真を撮るのだろうか。背景の一つには多くの看取りの経験がある。その人にとって最良の過ごし方や別れのかたちを考える尾山さんが、写真を通して伝えたいこととは。
看護の仕事を続けながら、30代で入学した美大
ヘルメットを被り、世田谷のまちを自転車で颯爽と駆け抜ける。リュック一つで訪問先の家々を回るのが尾山さんの日常だ。1日に訪問するのは4件ほど。自転車で片道20分を超える距離を移動することもある。

写真を本格的に始めたのは2014年。桜新町アーバンクリニック在宅医療部の5周年記念誌で、旅先で写真を撮ることが趣味だった尾山さんが撮影担当になった。実際に撮影をはじめると写真が遺影として使われ、ご家族に感謝を伝えられることが多かった。
その様子を見ていた事務長から「訪問看護の仕事のなかで、家族写真の撮影をやってみては?」と提案され、仕事にするならきちんと勉強したい、と写真コースのある大学に入学。働きながら学べる京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)の通信教育学部を選んだ。

写真表現で気づいた「違い」
以前からアートが好きで芸術祭や美術館に出かけることはあったものの本格的に学ぶことは初めて。ましてや自分が作品をつくる側になるとは思ってもみなかった。カリキュラムには写真専門の科目以外にも、哲学や民俗学といった教養科目もあり、あらゆる角度から芸術を学んだ。
この仕事をしていると「生きること」「死ぬこと」「人間とは何か」といった問いにどうしても向き合わざるを得ないんです。そのことに別の視点からアプローチできることが新鮮でした。言葉にならないことを別のかたちで表現する、その手段を知ることができました。

卒業制作のタイトルは「終わりのない対話」。複数の患者と話した死生観についての会話をテキストと写真で表現した。訪問看護の仕事は、慢性期(病気の進行はあるものの病状は比較的安定していて穏やかな時期)の疾患のケアと終末期における看取りが大半を占める。
多くの人を看取ってきた尾山さんにとって「死は暮らしの延長線上にあるもの」。在宅医療の現場では暮らしのなかで死を迎えるが、その直前にあるものは必ずしも悲しみやつらさばかりではない。思うように体が動かせないことや病気の痛みや苦しみがある一方で、日常生活には些細な喜びやユーモアもある。
だが、制作した作品を学生の仲間や先生方に見せると、思った以上に作品の受け止め方に自分とのギャップがあることに気づいた。死は特別な出来事、突然訪れるセンセーショナルなものとしてとらえられている、そちらのほうがマジョリティかもしれないと。
死は、人間の営みのなかに当たり前につながれてきたものという感覚があったので、人によってこれだけとらえ方が違うのか、ということを目の当たりにしました。
日常と切り離された「死」
70年前には8割を超えていた在宅での死は高度経済成長期とともに減っていき、いまや病院や施設で最期を迎える人が8割強(※)を占める現代日本。日常と切り離された老いや死に「どう向き合えばいいかわからない」という卒業制作を通して得た反応は、その後の展覧会『ぐるり。』につながっていく。


会場には、在宅医療を受けていた「えいすけさん」の亡くなる1週間前の写真や、えいすけさん本人が残した短いテキストが展示された。写真は展覧会を目的に撮影したものではない。えいすけさんを担当した看護師の悩みが撮影のきっかけとなった。
わたしは彼女のケアへの想いに共感していたのですが、「多職種のケアチーム内にうまく伝わらない」という悩みを抱えていました。言葉ではなく写真なら伝わるかもしれない、とえいすけさんとご家族に許可をもらい撮影をはじめました。
尾山さんがカメラでとらえたのは、えいすけさんが亡くなる1週間ほど前の日常生活だ。えいすけさんが好んで着る下着。頭だけ廊下に出してすやすやと寝る姿。布団からはみ出た足。目を閉じる時間が多くなっても、スタッフが帰る間際に必ず合わせられる手。
そのなかに介助されながら水を飲む姿がある。頭をそっと持ち上げて口にスプーンを運ぶのはスタッフではなく息子さん。いつもそばで見ていることの多かった息子さんが「自分にも何かできることはないですか?」と声をかけてくれたときにお願いしたものだった。

このときの2人を見て、息子さんがえいすけさんを支えるだけではなく、親が「人がどのように老いて命を閉じていくか」を伝え、それを子どもが受け取っているようにも感じたのです。
2人の間にある「循環」のようなもの。それが『ぐるり。』というタイトルにつながった。かつては当たり前のように家庭で伝承された終末期のケアや死が病院に移行した現代で「安全に水を飲むといったケアの技術を家族に伝えることも、看護の仕事の一つかもしれません。小さいことを積み重ねていくことで、地域のなかで死を受け入れられる営みが戻るのではないかなと思ったりします」と尾山さんは加えた。

※厚生労働省「厚生統計要覧(令和4年度)」及び「在宅医療の最近の動向」を参照。後者によると、1951年には在宅死の割合は8割を超え、病院死の割合は1割に満たない。それが1971年には逆転し、2005年に78.4%になるまで病院死の割合が増え続ける。ただし2005年以後は「在宅療養支援診療所」(2006年)の制度がつくられるなど、徐々に在宅医療を選択する人が増えている。
訪問看護師という仕事
尾山さんが現在の職場で働くようになったのは2012年。0歳から100歳までみることのできる看護師になりたい、と総合病院と子ども病院に勤めたあと、いまの在宅医療の現場に移った。病院の仕事と大きく違うと感じたのは、心電図をつけずに人が亡くなること。命が終わったことを医療行為なしに判断するのは、病院医療と在宅医療の大きな違いの一つだという。
病院と在宅医療は文化が違います。病院は治療するための場所で、入院中は睡眠や食事の時間も決められ、飲食などの制限もある。それは治療を効果的に行うことを目的にしているからです。
病院がルールを決めているのに対し、在宅医療では患者さん自身がルールのようなところがあって、医療はその人の人生をサポートするための脇役になります。


いつも手に「ワンカップ」を持っていた100歳を超えるおじいさんを担当していた尾山さん。「人間は動物だから、いつか死ぬのが当たり前なんだ」が口癖だった。ただ、お酒やタバコといった健康の妨げになるようなものであっても「それを止める権利はわたしたちにはなくて」と話す。
在宅医療での目的は「疾患の治療」ではなく「生活の質の向上」だからだ。病気や臓器といった「部分」だけでなく、人や生活「全体」を支えていく。

そこで重要なのはケアされる本人の意思や希望。そのためにアセスメントをしたり、ヒアリングシートを用意したりするだけではなく、訪問を重ねるなかで関係性をつくり、引き出していく。
どんな医療やケアを望むか、最後の時間をどう過ごしたいか。その背景にある思いをケアの従事者や家族など周囲の人たちと繰り返し話し合うことは「ACP(アドバンスケア・プランニング/人生会議)」と言われ、在宅医療では訪問看護師の役割も大きい。


尾山さんも制作にかかわった、在宅療養のためのガイドブック『LIFE これからのこと 在宅療養・ACP(アドバンス・ケア・プランニング)ガイドブック』(世田谷区保健福祉政策部、2021年)では、周りの訪問看護師たちが普段、患者さんにする質問を参考につくったページがある。
そこには、住んだことのある土地やこれまでの仕事・行きたい場所・やりたいこと・好きな食べ物・趣味などの質問が並べられている。
それまでどのような人生を歩んでこられたか、何を大事にされているか、どんな生活を送っているのかを知り、その人がその人のまま、最期まで過ごせるようにすることが訪問看護師の重要な仕事かなと思っています。
わたしたちはあくまで看護の面から支えることしかできないけれど、チームで共有してその人にとって一番良い方法を常に考えています。
訪問看護師だけではなく、医師・ケアマネジャー・訪問看護スタッフ・薬剤師・リハビリ専門職など多様な職種の担当者が情報を共有し、家族と相談しながらチームとなってケアを進めていくことも在宅医療ならではだ。それによって、薬の量や回数を減らすなどして、在宅療養で可能なシンプルなかたちを模索していく。

いつか順番が来るもの
いま、尾山さんは『人のさいご』という新しい本の制作を担当している。人が自然にいのちを閉じていくときに起きる自然な変化について書かれたものだ。
一人暮らしの方で、自分はこの先どうなるのかを軽やかに質問されたことがあるんです。「死んだらどこにいくと思う? 尾山さん、知ってるんでしょう?」って。旅立つ前の体の変化などについてほかの方からも同じような質問を受けることがたびたびあるのですが、家族向けのパンフレットはあっても本人のために言葉を選んで書かれたものはなかなかなくて。
「誰に」語るかによって、伝え方が変わりますよね。『人のさいご』は、命が閉じていく過程に起きる自分の変化を前もって知っておくための本です。
家で死ぬことが当たり前だった時代と比較すると、現代は死や老いへの恐怖はより大きいのかもしれない。自分の命がどう閉じられていくのか。その知識に触れることで恐さは減り、「生」の選択肢も増えていく。あらためて、尾山さんの考える死とはどのようなものかをたずねた。
早いか遅いかわからないけれど、いつか順番が来るものという感じでしょうか。
「両親も夫も、きょうだいもお友だちもみんな亡くなって、もうそろそろわたしもあちらに行きたい。でも順番だからしょうがないわよね」と、あっけらかんと話す方も多くいて、これまで出会ってきた患者さんたちに受け止め方を教えてもらいました。
写真を通じて「大きいものの陰に隠れて見えないもの、はみ出ている何かに光を当てられたら」という尾山さんの写真からは、一見だれも気づかないような人生の痕跡が見える。小さな気づきから千差万別なケアを創造する訪問看護師という仕事は、どんな「生」も肯定し、その人の「生きること」を一緒につくっているようにも見える。
そうして日常から切り離されてきた人生最後の点を、少しずつ線や面にして、それぞれの暮らしや地域につなげ直そうとしているのかもしれない。

Information
・anan webにて「介護の現場でかなえる、私らしい働き方」記事を公開中!リンクはこちら
・POPEYE webにて「福祉の現場を知りたくて。」記事を公開中!リンクはこちら
Profile
![]()
-
尾山直子
看護師/写真家
1984年埼玉県生まれ。看護師/写真家。「桜新町アーバンクリニック」在宅医療部にて訪問看護師、広報として勤務。高校で農業を学んだのち看護師の道に進み、複数の病院勤務を経て2012年より現職。訪問看護師の勤務の傍ら、2020年京都造形芸術大学美術科写真コースを卒業し、現在同大学大学院に在籍。かつて暮らしのなかにあった看取りの文化を現代に再構築するための取り組みや、老いた人との対話や死生観・看取りの意味を模索し、写真を通じた作品制作を行っている。2021年よりデザインリサーチャーの神野真実と共同で写真展「ぐるり。」を開催し、各地を巡回。
- ライター:佐藤恵美
-
編集者、ライター。2009年よりアート・デザイン関連の本やウェブを中心に、編集と執筆の仕事をしている。美術館、編集事務所、アートセンター等を経て、現在フリーランス。
この記事の連載Series
連載:“自分らしく生きる”を支えるしごと
![]() vol. 332026.02.13ケアはしがらみも、めんどうくささもある? 竹端寛さん、羽田知世さん、石川裕子さんによる鼎談
vol. 332026.02.13ケアはしがらみも、めんどうくささもある? 竹端寛さん、羽田知世さん、石川裕子さんによる鼎談![]() vol. 322026.01.14本から「介護にあるまなざし」に出会う。編集者、ダンサー、美術家、介護職員の選ぶ4冊
vol. 322026.01.14本から「介護にあるまなざし」に出会う。編集者、ダンサー、美術家、介護職員の選ぶ4冊![]() vol. 312025.12.26「助けて」という言葉が必要になる前に。社会福祉法人丹緑会特別養護老人ホーム栗林荘をたずねて
vol. 312025.12.26「助けて」という言葉が必要になる前に。社会福祉法人丹緑会特別養護老人ホーム栗林荘をたずねて![]() vol. 302025.12.17いいチームってなんだろう? 多職種連携で「看取り」に取り組む特別養護老人ホーム「芦花ホーム」をたずねて
vol. 302025.12.17いいチームってなんだろう? 多職種連携で「看取り」に取り組む特別養護老人ホーム「芦花ホーム」をたずねて![]() vol. 292025.12.10一人ひとりの“あたり前”を大切にできる環境とは?「あたり前の暮らしサポートセンター布施屋」をたずねて
vol. 292025.12.10一人ひとりの“あたり前”を大切にできる環境とは?「あたり前の暮らしサポートセンター布施屋」をたずねて![]() vol. 282025.12.05安心して歳を重ねられる地域とは? 社会福祉法人くらしのハーモニーをたずねて
vol. 282025.12.05安心して歳を重ねられる地域とは? 社会福祉法人くらしのハーモニーをたずねて![]() vol. 272025.11.18「ケア」を感じたマンガを教えてください。作家、社会学者、アーティスト、福祉施設長の選ぶ4作品
vol. 272025.11.18「ケア」を感じたマンガを教えてください。作家、社会学者、アーティスト、福祉施設長の選ぶ4作品![]() vol. 262025.11.10「安心できる住まい」はどう育まれる? 特別養護老人ホーム「美里ヒルズ」をたずねて
vol. 262025.11.10「安心できる住まい」はどう育まれる? 特別養護老人ホーム「美里ヒルズ」をたずねて![]() vol. 252025.03.06地域の「居場所」ってなんだろう? 佛子園「三草二木 西圓寺」をたずねて
vol. 252025.03.06地域の「居場所」ってなんだろう? 佛子園「三草二木 西圓寺」をたずねて![]() vol. 242025.02.27幅広く使われる「ケア」をどうとらえる? 向坂くじらさん、吉田真一さんと考える
vol. 242025.02.27幅広く使われる「ケア」をどうとらえる? 向坂くじらさん、吉田真一さんと考える![]() vol. 232025.01.30本から「介護にあるまなざし」に出会う。イラストレーター、哲学者、ジャーナリスト、介護福祉士の選ぶ4冊
vol. 232025.01.30本から「介護にあるまなざし」に出会う。イラストレーター、哲学者、ジャーナリスト、介護福祉士の選ぶ4冊![]() vol. 222025.01.23地域の歴史や文化とともに歩む福祉とは? ライフの学校「六郷キャンパス」をたずねて
vol. 222025.01.23地域の歴史や文化とともに歩む福祉とは? ライフの学校「六郷キャンパス」をたずねて![]() vol. 212025.01.20多世代が一緒に過ごすことで生まれる安心とは?「深川えんみち」をたずねて
vol. 212025.01.20多世代が一緒に過ごすことで生まれる安心とは?「深川えんみち」をたずねて![]() vol. 202025.01.10アーティストが滞在する福祉施設とは? 「デイサービス楽らく」をたずねて
vol. 202025.01.10アーティストが滞在する福祉施設とは? 「デイサービス楽らく」をたずねて![]() vol. 192024.12.18「助けて」と言い合える環境を育むには? 「みんなの家 タブノキ」をたずねて
vol. 192024.12.18「助けて」と言い合える環境を育むには? 「みんなの家 タブノキ」をたずねて![]() vol. 182024.12.13私もあなたも、主人公でいられるように。「DAYS BLG! はちおうじ」をたずねて
vol. 182024.12.13私もあなたも、主人公でいられるように。「DAYS BLG! はちおうじ」をたずねて![]() vol. 172024.12.12「ケア」を感じたマンガを教えてください。組織開発コンサルタント、俳優、福祉施設所長、介護福祉士の選ぶ4作品
vol. 172024.12.12「ケア」を感じたマンガを教えてください。組織開発コンサルタント、俳優、福祉施設所長、介護福祉士の選ぶ4作品![]() vol. 162024.11.08安心して歳を重ねられる町とは? 鞆の浦・さくらホームをたずねて
vol. 162024.11.08安心して歳を重ねられる町とは? 鞆の浦・さくらホームをたずねて![]() vol. 152024.03.12介護のしごとに興味をもったとき、はじめの一歩はどうすれば?
vol. 152024.03.12介護のしごとに興味をもったとき、はじめの一歩はどうすれば?![]() vol. 142024.02.27認知症を“体験”する「VR認知症」。イシヅカユウさんと体験して気づいたこと
vol. 142024.02.27認知症を“体験”する「VR認知症」。イシヅカユウさんと体験して気づいたこと![]() vol. 132024.02.22認知症のある方100人以上にインタビューをして気づいたこと。認知症未来共創ハブ代表・堀田聰子さん
vol. 132024.02.22認知症のある方100人以上にインタビューをして気づいたこと。認知症未来共創ハブ代表・堀田聰子さん![]() vol. 112024.02.19科学的な介護ってなんだろう? 福祉楽団「杜の家なりた」をたずねて
vol. 112024.02.19科学的な介護ってなんだろう? 福祉楽団「杜の家なりた」をたずねて![]() vol. 102024.02.08「老いと共に生きる」を映画から考える。編集者、映画作家、介護福祉士、福祉施設運営者の選ぶ5作品
vol. 102024.02.08「老いと共に生きる」を映画から考える。編集者、映画作家、介護福祉士、福祉施設運営者の選ぶ5作品![]() vol. 092023.12.20居場所ってなんだろう? 人が自然と集まる場所を目指す「52間の縁側」をたずねて
vol. 092023.12.20居場所ってなんだろう? 人が自然と集まる場所を目指す「52間の縁側」をたずねて![]() vol. 082023.12.13「ケア」を感じたマンガを教えてください。文学研究者、精神科医、看護師、介護福祉士、文筆家の選ぶ5作品
vol. 082023.12.13「ケア」を感じたマンガを教えてください。文学研究者、精神科医、看護師、介護福祉士、文筆家の選ぶ5作品![]() vol. 072023.12.06自然の循環に身を委ね、大地と共に生きる。「里・つむぎ八幡平」が実践する「半農・半介護」の暮らし
vol. 072023.12.06自然の循環に身を委ね、大地と共に生きる。「里・つむぎ八幡平」が実践する「半農・半介護」の暮らし![]() vol. 062023.11.29介護施設×学生シェアハウス「みそのっこ」が教えてくれる、「介護×場づくり」の可能性
vol. 062023.11.29介護施設×学生シェアハウス「みそのっこ」が教えてくれる、「介護×場づくり」の可能性![]() vol. 052023.11.10いくつになっても「働く」は楽しい。ばあちゃんたちの生きがいとビジネスの両立を目指す、株式会社うきはの宝をたずねて
vol. 052023.11.10いくつになっても「働く」は楽しい。ばあちゃんたちの生きがいとビジネスの両立を目指す、株式会社うきはの宝をたずねて![]() vol. 042023.11.07居心地の良い場所の条件ってなんだろう? 浦安にある高齢者向けの住まい「銀木犀」をたずねて
vol. 042023.11.07居心地の良い場所の条件ってなんだろう? 浦安にある高齢者向けの住まい「銀木犀」をたずねて![]() vol. 032023.10.31ケアってなんだろう? ナイチンゲール看護研究所・金井一薫さんをたずねて
vol. 032023.10.31ケアってなんだろう? ナイチンゲール看護研究所・金井一薫さんをたずねて![]() vol. 022023.10.30さまざまな命に囲まれて、心を動かして生きる。 園芸療法を行う「晴耕雨読舎」をたずねて
vol. 022023.10.30さまざまな命に囲まれて、心を動かして生きる。 園芸療法を行う「晴耕雨読舎」をたずねて![]() vol. 012023.10.11自分らしく生きるってなんだろう? 一人ひとりの人生に向き合う介護事業所「あおいけあ」をたずねて
vol. 012023.10.11自分らしく生きるってなんだろう? 一人ひとりの人生に向き合う介護事業所「あおいけあ」をたずねて