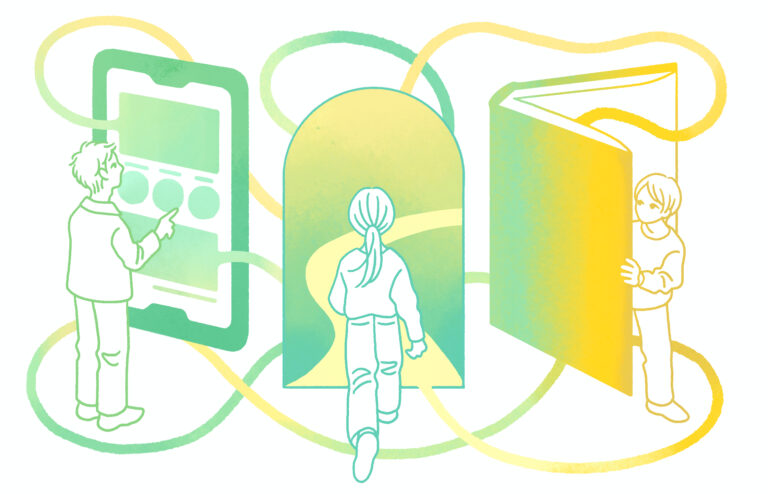アーティストが滞在する福祉施設とは? 「デイサービス楽らく」をたずねて “自分らしく生きる”を支えるしごと vol.20
Sponsored by 厚生労働省補助事業 令和6年度介護のしごと魅力発信等事業(情報発信事業)
- トップ
- “自分らしく生きる”を支えるしごと
- アーティストが滞在する福祉施設とは? 「デイサービス楽らく」をたずねて
福祉施設に、アーティストが宿泊して活動する試みがあると聞いて、少し驚いた。日常生活を支援する場である福祉施設と非日常を扱うことが多いアートとの接点がどのようなものになるのか? 想像が及ばなかったからだ。
「クロスプレイ東松山」は、埼玉県東松山市にある高齢者福祉施設「デイサービス楽らく(以下、楽らく)」にアーティストが滞在し、リサーチや作品制作を通して文化的な交流を重ねるプロジェクトである。
2022年より、アートを通じた“よりクリエイティブなケアの実践”の場として、高齢者福祉施設が文化施設の機能と役割を持つというコンセプトのもとにスタートし、現在までに14名のアーティストが滞在、その成果発表となるイベントなども行われてきた。
プロジェクトを立ち上げたのは、同施設を運営する「医療法人社団保順会」とアートにまつわるプロデュースやマネジメントを行う専門家のコレクティブ「一般社団法人ベンチ」。
アートと福祉が交わることで、どのような関係性が育まれるのか? 楽らくを訪ね、施設長の武田奈都子さんと職員の山木麻紀子さん、また滞在経験のあるアーティストの竹中香子さんに、それぞれどんな影響を受けたのか、話を聞いた。
モットーは「らくに たのしく その人らしく」
埼玉県東松山市、東武鉄道・森林公園駅から徒歩だと30分。楽らくは昔ながらの広いお庭や畑も多い、静かな場所にあった。施設長の武田奈都子さんに出迎えられ、スリッパに履き替えて中へ。

入口からまっすぐ進んで扉を開けると、利用者が食事や入浴などで使用するメインの空間がある。手前右手には、ギャラリーのようにも使用できる多目的空間。さらにその奥に、アーティストが滞在利用できるワンルームのお部屋があった。

楽らくは、2007年より「らくに たのしく その人らしく」をモットーに、 “寄り添うケア ”を大切にしたサービスを続けている。
施設は当初、市内の別の場所にあった。移転して新施設を建築することが決まり2022年6月に新たな施設が完成。現在、定員30名の楽らくでは、曜日によって異なる方々が日々、入浴や食事、余暇などの時間を過ごしている。
訪れた午後は、昼食が終わって歌や工作など、レクリエーションの時間が始まるところだった。
武田さんの案内で中を見学させていただく。

案内いただいたのはお風呂場。午前中は、入浴サービスを受ける人が多いそうだ。要介護度や心身の特性によって、必要な介助が異なり、ときには一般的な浴槽と小型介助浴槽を使って入浴介助を行う。

楽らくの利用者は、女性が8割を占める。男女構成は各デイサービスによってまちまちだそうだが、こちらはレクリエーションの多さからか、女性に特に人気のようだ。おしゃべりをしている人も多く、施設内も明るい雰囲気だった。

ケアとアートが交差する「クロスプレイ東松山」
楽らくで展開されているのが、ケアとアートを結びつけるプロジェクト「クロスプレイ東松山」だ。参加するのは、美術・音楽・演劇・ダンス・写真・文学等の活動をしているアーティスト(表現者)で、高齢者・介護・福祉に興味がある方たち。20日以上30日以内の滞在を行い、楽らくにあるスペースをアトリエやスタジオとして利用しながら、福祉や介護などを題材にした作品のリサーチを行うことができる。
「クロスプレイ東松山」では、アーティストの関わり方が二種類ある。事務局からアーティストに依頼し、滞在・交流しながら、施設内や外部の場所等で作品制作や上演・展示等のアウトプットを目指すアソシエイトアーティストと、滞在を希望するアーティストを公募し、レジデンススペースを提供する公募アーティストだ。
2022年7月より、アソシエイトアーティストとして振付家・演出家・ダンサーの白神ももこさんの滞在を皮切りに、現在までダンサーや写真家や文筆家など、13名のアーティストが訪問・滞在し、活動を行ってきた。
アートを媒介にすると、ケアを取り巻く関係性が変わる
クロスプレイ東松山の取り組みは、なぜ生まれたのだろう。その背景には、楽らく施設長の武田さんの経験と想いがある。
武田さんは、芸術系の大学に進学して舞踊を学び、その後もダンスカンパニーやアートフェスティバル事務局のマネージャー職に就いていた。そんな彼女が福祉に携わることになったきっかけは、母親が立ち上げた、デイサービス楽らくの仕事を手伝うようになったことだった。
当時は介護の資格を持たないまま、デイサービス利用者の髪を乾かしたり、お茶を出したりと、施設内で過ごしていた。その中で、アートと介護の親和性を感じるようになっていったという。

武田奈都子さん(以下、武田):良い介護のために必要なのは豊かな想像力だな、って。認知症の症状があったり、必要なサポートが人それぞれ異なるからこそ、どんなケアが必要かを考えるのは、すごくクリエイティブだと思ったんです。
その後、福祉の勉強を重ね、医療法人社団保順会の理事となった武田さんは、本格的にアートと介護をつなぐ試みに着手する。
もともと楽らくでは手先が器用な職員が多くいたこともあって、工作や手芸なども積極的に行っていた。そこで、まずは美術関連のアーティストに来てもらって、美術関係のワークショップをしてもらった。
武田:通常だと、介護職は何かを「与える人」で、利用者は何かを「与えられる人」という関係性になりがちですが、アーティストが来ると「みんな表現者だよね」と、フラットな関係性になる瞬間を見ることがあって。「アートを媒介とすることで、介護する人/される人という構造ではない時間が生まれるといいな」と思ったんです。
ただ1日限りのワークショップを行うだけだと、どうしてもアーティスト側が先生のようになってしまう。職員もその場を任せて違う仕事をしたりと、当事者性を持ちづらい状況でもあった。もっと日常の時間にアーティストがいるという環境を作りたいと思ったとき、思い浮かんだのがアーティストが施設に滞在するアーティスト・イン・レジデンスの仕組みだった。
武田:アーティストが日常の時間に入ることで、よりフラットな関係性が生まれるんじゃないかって。社会福祉を学んだ中で、やっぱりアートが必要だって思ったそのエッセンスをここで体現したいという思いが強くありました。
武田さんは社会福祉士の資格を取り、2022年6月に移転新築した施設では施設長に就任。設計を担当した建築家と相談しながら、現在の楽らくが完成した。



アーティストが圧倒される介護の現場
「クロスプレイ東松山」は、武田さんの想いをベースに、現場職員や利用者をはじめ、多くの人の協力で成り立つプロジェクトだ。初めての試みには試行錯誤がつきものだが、ここでも当初の想定とは違う産みの苦しみがあった。
武田:職員の多くは、普段アーティストと接する機会がないですし、施設は自分たちの空間であるという意識も強い。だから当初はすごく怖さというか、警戒心も強かったと思いますし、今も多少はあると思う。けれど、一定期間を過ごす中で、「アーティストも特別な存在ではなくて普通の人間なんだ」と、少しずつ存在に慣れてきたり、関わり方を模索してくれているように思います。

それよりも武田さんが驚いたのは、アーティスト側の受け止め方だった。
武田:プロジェクトが始まって、「これはもう、えらいこと頼んじゃったな」と。
アーティストにとっては、通常自分たちが与えられる創作の現場は、それ用にしつらえられていることが多いんです。だけどここはそうではない。いくら福祉に興味があっても、運営中の高齢者福祉施設で、介護の世界を見るだけで、みなさん圧倒されていて。
その現場で「アートとはそもそも何か? 自分は何ができるのか?」っていうことに向き合うことになる。プロジェクトに参加して、自分の表現の仕方や作品への向き合い方が変わるとか、自分の創作活動をあらためて考えるきっかけになっている人が多い気がします。
「クロスプレイ東松山」では、公募アーティストは成果として何かを提出する必要はなく、レジデンス滞在中こうしなければならない、という義務もない。役割がない一人のアーティストが、きっちりとスケジュールやルーティンがあり、慌ただしい時間を過ごすデイサービスの現場に入っていく。その過程で悩む人も多いそうだ。

アーティストの滞在期間はさまざまだが、滞在中に具体的な作品ができあがるということはほとんどない。例えば、民話の採集を目的に滞在した仁禮洋志(にれい・ひろし)さんは、普段は写真で作品を発表しているが、楽らくでの経験から、朗読という全く違った形のパフォーマンスをすることになった。多くのアーティストが、楽らく滞在を経て、新しい表現を模索している。

また、デイサービス利用者とアーティストの間に入る重要な役割を果たすのが、楽らくの職員だ。忙しく動き回る職員のみなさんと、いかに関係性を築き、協力してもらえるかがプロジェクトの鍵にもなる。
アーティストを迎える戸惑いと変化
クロスプレイ東松山の取り組みを、現場の職員の方はどのように感じているのだろうか。お話を伺ったのは、職員の山木麻紀子さん。医療法人社団保順会との関わりが9年目、前職も福祉系で障害者支援施設にいたという筋金入りのケア・プロフェッショナルだ。
「この仕事は奥が深く、まだまだ初心者」と謙虚な山木さんだが、現在は楽らくの相談員として、主に利用者家族やケアマネジャーとの調整などの顧客対応や介護保険の請求関連の業務を担いつつ、職員の様子を見ながらフォローに回る立場として、毎日現場を行き来している。

利用者にとって心地いいと思える瞬間を大切にしたい、と話す山木さんは「クロスプレイ東松山」についてはどのように感じているのだろうか?
山木麻紀子さん(以下、山木):アーティストが楽らくに入ることで、利用者も今までされなかった質問をされるなど、脳が活性化されたり、すごく刺激があっていいですよね。どうしても独居の方だとお話する相手が少ないこともあるから。家族にクロスプレイのことをなんらかの形でお伝えしてくれてる方もいて、写真展や舞台などがあったときは、連れてきてくださることもあります。
ただ、現場の職員として、受け入れるときには、プロジェクトの趣旨は理解しているものの、難しく感じることもある。
山木:デイサービスの役割は入浴と食事、服薬のような、基本的な生活という部分で。朝も来たらすぐ血圧測って、入浴にご案内して、という感じで慌ただしいんです。
アーティストが短いスパンで来られたときは、お名前を覚えた頃にもう次の方がいらっしゃって、という状況で、なかなか職員がアーティストと交流するような時間を取りづらいのが実情です。

また、当初は職員側がアーティストとどのように関わっていけばよいか?アーティスト側の自由度が高い故に、接し方も難しかったそう。
山木:アーティストが目指しているものを、私たちが具体的にイメージできなくて。例えば「こういうものを作ります」と明確にわかれば、それに向かってアドバイスもできたのかなと思うんですけど、当初戸惑いはありました。
その点はクロスプレイの事務局とも話し合いました。「みなさん介護の現場を初めて見る方もいらっしゃって、実際に利用者と関わらないと具体的なイメージは出てこないし、想定とは違う何かを見つけていいアウトプットになっていく」という話を聞いて、「なるほど」と理解しました。アーティストもきっとすごく悩んだり苦労されたりしてるんだろうなって思います。
また、山木さんは、アーティストから当たり前の日常業務に対して問いかけられることで、職員側も刺激を受け、あらためて仕事内容を工夫するなどの変化も起きていると語る。

山木:私たちの仕事のことを「素晴らしいお仕事ですね」って言ってくださるアーティストも多くて。介護のお仕事について、いろんな方に広く伝えてくれたらいいなという気持ちもあります。私たち職員も、日々のなかで彩りが感じられたらいいですよね。


俳優・竹中香子さんが陥ったアイデンティティの混乱
一方、アーティストはどのように感じていたのだろうか? 公募アーティストとして参加した俳優の竹中香子さんにも話を伺った。
フランスで俳優国家資格を取得し、通訳やプロデューサーとしても活躍している竹中さん。そもそも竹中さんが、介護の仕事に意識が向いたのは、父親の看取りやコロナ禍などを契機にいったん帰国していた時期だった。
竹中香子さん(以下、竹中):父親が自宅介護で、複数人の介護職が入って長年ケアしていただきました。危篤になってから死を迎えるまでの1週間も、毎日通って寄り添ってくださって、おかげで私も大きな喪失感をおぼえることなく、なだらかに父の死を受け入れることができました。また、父が暮らしていた家に「たくさん食べるときはむせないようにこうする」などのメモがたくさん残されていたり、手すりが見えやすいように黒いテープが貼ってあったり、ありとあらゆる工夫の跡にも衝撃を受けたんです。
普段、映画も作っているので、映像やそこから集めた記憶で何か作品にすることも考えて、既に文章に介護職の方々と過ごした最期の一週間、どういうことが起きたかなども細かく書いていました。
そうして介護職のあり方に関心を寄せていたところ、以前から関係性があった武田さんが主催するクロスプレイ東松山で、公募アーティストを募集していることを竹中さんは知る。日本で活動の場を求めていた竹中さんにとって、介護の現場は興味関心にちょうど重なるものだった。
竹中:応募したときは、施設の利用者のためにワークショップだったり、何か楽しいことを提案するクリエイターみたいなことを求められてるんだと思っていたんです。実は全くそうじゃなかったんですが。

クロスプレイ東松山に参加する公募アーティストは、滞在後のアウトプットとして具体的な作品づくりを求められるわけではない。竹中さんは、その自由度ゆえに、逆にアイデンティティ・クライシスに陥ってしまったという。
竹中:直接介護に関連する作品を作っているならまだしも、やるべきこともなく、その場にただいるのは、「この人は経済的なことを気にせずになんとなく過ごしている、生活に余裕がある人なのだ」と職員の方からは見えてしまうのかな、と。
芸術の場では、自分の思想や問題提起をするときに、「嫌われても何か社会にその問いを投げかけたい」という思いでやってるのに、福祉の現場では、「とにかく嫌われたくない」と思ったことに、自分でも驚きました。
竹中さんが陥った「ここにただ突っ立っているのはつらすぎる」という状況を動かしたのは、自分が役割を持ち、働いて役に立つと決めたことだった。レジデンス滞在の後半2週間、竹中さんは職員の「実習生」の名札をつけて、エプロン姿になって利用者や職員と関わることにしたのだ。
竹中:エプロンや名札が本当に衣装みたいな感じで、それを着ることによって、声の大きさや歩く速度、姿勢など全てが変わって。役を演じるようにここでどう振る舞えばいいかが明確になって、すごく楽になりました。

入浴介助で気づいた「溶け合う」ような人間関係
竹中さんは、実習生として、楽らくの仕事に関わることで、作品づくりに繋がる大きな気づきを得ることになった。入浴介助の仕事を手伝うなかで、コミュニケーションやそれに伴う感覚の異なりをあらためて実感したという。
竹中:ヨーロッパにいるときは、強固な「自分」を見つけるために、私と他者を隔てる自分の輪郭をつくろうとみんなが努力しているのをひしひしと感じてきました。私もその中で活動してきたのですが、入浴介助のお手伝いでお風呂場に入ったときに、その意識がすごく邪魔だって思ったんですよね。
お風呂ってセンシティブなところだから、最初は躊躇していたんですが、職員さんと一緒に手伝っているうちに、どこまでが自分で、どこまでが他人かもわからないから、見たり見られたり、触ってもらっても怖くない。溶け合ってるみたいな感覚になって。
竹中さんは人間関係がこのような「溶け合う」感覚になることを体感し、その中に自分がいるということに、泣けるほど感動し、その経験をもとに作品を構成することにした。
不確実性を楽しみ、他人を想像して演技する作品『ケアと演技』
演技とは、自己表現の道具ではなく、「その役を想像して、この人はそのときどうだったんだろう?」と、他者を想像するメカニズムがある、と竹中さんは話す。その部分に目を向けると、介護職の仕事と重なるものがあると指摘する。
竹中:いい俳優さんもそうですし、介護職のみなさんもそうだったのですが、「不確実性に身を開いている」態度だったんですよね。
一度、入浴介助のとき、利用者が途中で粗相しちゃって全部清掃し直しで、それまでの細かい計画が全部壊れちゃったんですけど、それでも職員の方々は、「毎日同じことやってるのに何が起きるかわかんないんだよ、だから楽しいのよ」と言っていて。管理やコントロールではなく、不確実を楽しんでくれているその態度は、すごく利用者も安心するだろうし、それは「いい演技」 とも結びつくんじゃないかと。

滞在中に感じたことをパフォーマンスにしたいと思った竹中さんは、滞在後に作品を創作。不確実な要素を掘り下げるため、竹中さん自身が体験談として演技をするのではなく、別の俳優が演じる試みが行われた。

武田さんも作品を観て、竹中さんが滞在中に真摯にケアと向き合ったことを感じとって心を動かされたそう。2025年3月には、竹中さんが創作した作品を介護職員の方への研修の一環として見ていただき、ディスカッションを行う予定だ。
また、竹中さんは現在、『ケアと演技』の発展版の企画として、家庭でのケアを担う方々を一般公募し、彼/彼女たちの物語を電話を通して観客に届けるインスタレーション作品『サテライト・コール・シアター』という新たな企画に取り組んでいる。
介護する・される人の、フラットな関係性を目指して
「クロスプレイ東松山」は、竹中さんのような演劇のアウトプットだけでなく、美術や短歌、写真の発表など、さまざまなかたちで、アーティストと楽らくの職員、利用者のみなさんにも影響を与えるプロジェクトとして進められている。
2024年度は新たに2名の公募アーティストを選定し、プロジェクトが進んでいく予定で、前述の竹中さんも今度はアソシエイトアーティストとして、再度楽らくに滞在することが決まっているそう。
継続にあたっては、より開かれた施設づくりのため、地域の文化施設と連携するほか、アーティストの選考過程を職員と共有し、選考後は自己紹介を行う機会を設けるなど、アーティストと職員が関わるきっかけとなるための、新たな工夫も検討されている。
今後「クロスプレイ東松山」が目指すビジョンはどのようなものだろうか?

武田:想定していた以上に時間がかかるプロジェクトだなって実感はしていますね。でも、そこで諦めちゃいけない。私は「アートの持つ力は大きい」って確信があるんです。たとえ高齢になって認知症になったり、できなくなることが増えていったりしたとしても、豊かな時間を作り出すことは、いろんな人の関わりでできるんじゃないかなって。
介護する人/される人という上下関係のような立場でなく、お互いに助け合うフラットな関係性も、今作っている過程にあって、今後も長い目で見続けていかないと難しいことだとは思っています。
小さな出来事の積み重ねで、福祉とアートが交差する未来に
武田さんは、「アーティストの滞在で、毎日すごくドラマチックなことが、起きるわけではないけれど、よく考えればこれはアーティストがいるから起こった、という小さなカケラのような出来事が散りばめられています」と話してくれた。そうした積み重ねが、福祉とアートが交差するあたらしい未来につながっているのではないか。
高齢介護の現場は人生の終わりが近づいた人が集まる場でもある。老いを自分ごととして考えることで、この世にどう存在するか、生きる意味といった哲学的な思考につながる深い洞察が起こり、新たな視点を持ち得るフィールドとなっていく。そういった意味で、介護の世界とアートの世界は、全く違うようでいて、どちらも不確実性が強く、クリエイティブな領域が多分にある。
ケアとアートが交わることで、育まれるものとはなにか?
「クロスプレイ東松山」では、決められた枠の中で、工夫をしつつも毎日を過ごす介護職員や楽らく利用者が、アーティストのさまざまな試みに触れ、新たな視点を得ていた。一方、アーティストの竹中さんは福祉の世界に身を委ねたとき、規則化された環境の中に「溶け合う人間性」を見つけ、役割を演じることで安心感を得ることに気づいた。「クロスプレイ東松山」は、ケアとアートが出会い、一度お互いの枠組みが外れた後にできあがる、新たな関係性の発生装置なのかもしれない。

Information
『ケアと演技』 デイサービス楽らく公演
日時:
2025年3月29日 13:30〜(デイサービス楽らく職員限定公演・一般公開なし)
2025年4月12日/13日 両日とも11:00〜/15:00〜
場所:医療法人保順会 デイサービス楽らく(埼玉県東松山市下唐子1574-1)
料金:一般 前売・当日 3,000円/東松山市及び比企郡在住割引 2,000円
共同主催:医療法人社団保順会、一般社団法人ハイドロブラスト、一般社団法人ベンチ
詳細はこちら
Profile
![]()
-
デイサービス楽らく
人が人としてかけがえのない人生を豊かに過ごすためには、Cure(治療)のための医療だけでなく、Care(介護、福祉)のちから、そして何より自己実現のためのCulture(文化)が必要という理念をもつ医療法人社団保順会が運営するデイサービス。
埼玉県のへそと言われる、東松山市唐子(からこ)地区に2007年に開所し「らくに たのしく その人らしく」をモットーに、年齢を重ねることで生じる病気や障害等により介護や手助けが必要になっても、住み慣れた地域での暮らしを豊かにし続ける場として、専門性のあるスタッフが“寄り添うケア”を大切にしたサービスを続けている。2022年6月に、行為としての介助を提供するだけでなく、アートを通じた“よりクリエティブなケアの実践”の場として、アーティスト・イン・レジデンスを併設した施設を移転新築し、ケア×アート「クロスプレイ東松山」を実施している。
Profile
![]()
-
武田奈都子
デイサービス楽らく施設長
社会福祉士。(医)保順会常務理事。玉川大学芸術学部、英国ラバンセンターにて舞踊を学ぶ。大学卒業後、パフォーマンスシアター水と油制作、フリーランスのアートマネージャー、フェスティバル/トーキョー実行委員会事務局を経て、2012年(医)保順会の理事就任。‘22年より現職。
「クロスプレイ東松山」を通して、ケアとアートが交わる場の創出・実践に取り組んでいる。
Profile
![]()
-
山木 麻紀子
デイサービス楽らく相談員
デイサービス楽らく相談員。介護福祉士・介護支援専門員。障害者福祉施設勤務を経て、2016年(医)保順会入職 介護職員として勤務した後、‘22年6月より現職。利用者様に1日一笑いをモットーに日々業務にあたる。
Profile
![]()
-
竹中香子
俳優・プロデューサー
一般社団法人ハイドロブラスト プロデューサー・俳優・演劇教育。2011 年に渡仏。日本人としてはじめてフランスの国立高等演劇学校の俳優セクションに合格し、2016年、フランス俳優国家資格を取得。パリを拠点に、フランス国公立劇場を中心に多数の舞台に出演。2017年より、日本での活動も再開。俳優活動のほか、創作現場におけるハラスメント問題に関するレクチャーやワークショップを行う。2021年、フランス演劇教育者国家資格を取得。主な出演作に、市原佐都子作・演出『妖精の問題』『Madama Butterfly』。太田信吾との共同企画、映画『現代版 城崎にて』では、プロデュース、脚本、主演を担当し、ゆうばり国際ファンタスティック映画祭2022 にて優秀芸術賞を受賞。2024年初戯曲を執筆し、YAU CENTERにて『ケアと演技』を上演。太田信吾との共同演出作品『最後の芸者たち』は、Festival d’Automne Paris 2024のプログラムとしてパリで上演される。初の長編映画プロデュース、太田信吾監督作品『沼影市民プール』が、全国公開を控える。「演技を、自己表現のためでなく、他者を想像するためのツールとして扱うこと」をモットーに、アートプロジェクトの企画を行う。
この記事の連載Series
連載:“自分らしく生きる”を支えるしごと
![]() vol. 322026.01.14本から「介護にあるまなざし」に出会う。編集者、ダンサー、美術家、介護職員の選ぶ4冊
vol. 322026.01.14本から「介護にあるまなざし」に出会う。編集者、ダンサー、美術家、介護職員の選ぶ4冊![]() vol. 312025.12.26「助けて」という言葉が必要になる前に。社会福祉法人丹緑会特別養護老人ホーム栗林荘をたずねて
vol. 312025.12.26「助けて」という言葉が必要になる前に。社会福祉法人丹緑会特別養護老人ホーム栗林荘をたずねて![]() vol. 302025.12.17いいチームってなんだろう? 多職種連携で「看取り」に取り組む特別養護老人ホーム「芦花ホーム」をたずねて
vol. 302025.12.17いいチームってなんだろう? 多職種連携で「看取り」に取り組む特別養護老人ホーム「芦花ホーム」をたずねて![]() vol. 292025.12.10一人ひとりの「あたり前」を大切にできる環境とは?「あたり前の暮らしサポートセンター布施屋」をたずねて
vol. 292025.12.10一人ひとりの「あたり前」を大切にできる環境とは?「あたり前の暮らしサポートセンター布施屋」をたずねて![]() vol. 282025.12.05安心して歳を重ねられる地域とは? 社会福祉法人くらしのハーモニーをたずねて
vol. 282025.12.05安心して歳を重ねられる地域とは? 社会福祉法人くらしのハーモニーをたずねて![]() vol. 272025.11.18「ケア」を感じたマンガを教えてください。作家、社会学者、アーティスト、福祉施設長の選ぶ4作品
vol. 272025.11.18「ケア」を感じたマンガを教えてください。作家、社会学者、アーティスト、福祉施設長の選ぶ4作品![]() vol. 262025.11.10「安心できる住まい」はどう育まれる? 特別養護老人ホーム「美里ヒルズ」をたずねて
vol. 262025.11.10「安心できる住まい」はどう育まれる? 特別養護老人ホーム「美里ヒルズ」をたずねて![]() vol. 252025.03.06地域の「居場所」ってなんだろう? 佛子園「三草二木 西圓寺」をたずねて
vol. 252025.03.06地域の「居場所」ってなんだろう? 佛子園「三草二木 西圓寺」をたずねて![]() vol. 242025.02.27幅広く使われる「ケア」をどうとらえる? 向坂くじらさん、吉田真一さんと考える
vol. 242025.02.27幅広く使われる「ケア」をどうとらえる? 向坂くじらさん、吉田真一さんと考える![]() vol. 232025.01.30本から「介護にあるまなざし」に出会う。イラストレーター、哲学者、ジャーナリスト、介護福祉士の選ぶ4冊
vol. 232025.01.30本から「介護にあるまなざし」に出会う。イラストレーター、哲学者、ジャーナリスト、介護福祉士の選ぶ4冊![]() vol. 222025.01.23地域の歴史や文化とともに歩む福祉とは? ライフの学校「六郷キャンパス」をたずねて
vol. 222025.01.23地域の歴史や文化とともに歩む福祉とは? ライフの学校「六郷キャンパス」をたずねて![]() vol. 212025.01.20多世代が一緒に過ごすことで生まれる安心とは?「深川えんみち」をたずねて
vol. 212025.01.20多世代が一緒に過ごすことで生まれる安心とは?「深川えんみち」をたずねて![]() vol. 192024.12.18「助けて」と言い合える環境を育むには? 「みんなの家 タブノキ」をたずねて
vol. 192024.12.18「助けて」と言い合える環境を育むには? 「みんなの家 タブノキ」をたずねて![]() vol. 182024.12.13私もあなたも、主人公でいられるように。「DAYS BLG! はちおうじ」をたずねて
vol. 182024.12.13私もあなたも、主人公でいられるように。「DAYS BLG! はちおうじ」をたずねて![]() vol. 172024.12.12「ケア」を感じたマンガを教えてください。組織開発コンサルタント、俳優、福祉施設所長、介護福祉士の選ぶ4作品
vol. 172024.12.12「ケア」を感じたマンガを教えてください。組織開発コンサルタント、俳優、福祉施設所長、介護福祉士の選ぶ4作品![]() vol. 162024.11.08安心して歳を重ねられる町とは? 鞆の浦・さくらホームをたずねて
vol. 162024.11.08安心して歳を重ねられる町とは? 鞆の浦・さくらホームをたずねて![]() vol. 152024.03.12介護のしごとに興味をもったとき、はじめの一歩はどうすれば?
vol. 152024.03.12介護のしごとに興味をもったとき、はじめの一歩はどうすれば?![]() vol. 142024.02.27認知症を“体験”する「VR認知症」。イシヅカユウさんと体験して気づいたこと
vol. 142024.02.27認知症を“体験”する「VR認知症」。イシヅカユウさんと体験して気づいたこと![]() vol. 132024.02.22認知症のある方100人以上にインタビューをして気づいたこと。認知症未来共創ハブ代表・堀田聰子さん
vol. 132024.02.22認知症のある方100人以上にインタビューをして気づいたこと。認知症未来共創ハブ代表・堀田聰子さん![]() vol. 122024.02.20暮らしのなかで閉じる命をつないでいく 写真家/訪問看護師 尾山直子さん
vol. 122024.02.20暮らしのなかで閉じる命をつないでいく 写真家/訪問看護師 尾山直子さん![]() vol. 112024.02.19科学的な介護ってなんだろう? 福祉楽団「杜の家なりた」をたずねて
vol. 112024.02.19科学的な介護ってなんだろう? 福祉楽団「杜の家なりた」をたずねて![]() vol. 102024.02.08「老いと共に生きる」を映画から考える。編集者、映画作家、介護福祉士、福祉施設運営者の選ぶ5作品
vol. 102024.02.08「老いと共に生きる」を映画から考える。編集者、映画作家、介護福祉士、福祉施設運営者の選ぶ5作品![]() vol. 092023.12.20居場所ってなんだろう? 人が自然と集まる場所を目指す「52間の縁側」をたずねて
vol. 092023.12.20居場所ってなんだろう? 人が自然と集まる場所を目指す「52間の縁側」をたずねて![]() vol. 082023.12.13「ケア」を感じたマンガを教えてください。文学研究者、精神科医、看護師、介護福祉士、文筆家の選ぶ5作品
vol. 082023.12.13「ケア」を感じたマンガを教えてください。文学研究者、精神科医、看護師、介護福祉士、文筆家の選ぶ5作品![]() vol. 072023.12.06自然の循環に身を委ね、大地と共に生きる。「里・つむぎ八幡平」が実践する「半農・半介護」の暮らし
vol. 072023.12.06自然の循環に身を委ね、大地と共に生きる。「里・つむぎ八幡平」が実践する「半農・半介護」の暮らし![]() vol. 062023.11.29介護施設×学生シェアハウス「みそのっこ」が教えてくれる、「介護×場づくり」の可能性
vol. 062023.11.29介護施設×学生シェアハウス「みそのっこ」が教えてくれる、「介護×場づくり」の可能性![]() vol. 052023.11.10いくつになっても「働く」は楽しい。ばあちゃんたちの生きがいとビジネスの両立を目指す、株式会社うきはの宝をたずねて
vol. 052023.11.10いくつになっても「働く」は楽しい。ばあちゃんたちの生きがいとビジネスの両立を目指す、株式会社うきはの宝をたずねて![]() vol. 042023.11.07居心地の良い場所の条件ってなんだろう? 浦安にある高齢者向けの住まい「銀木犀」をたずねて
vol. 042023.11.07居心地の良い場所の条件ってなんだろう? 浦安にある高齢者向けの住まい「銀木犀」をたずねて![]() vol. 032023.10.31ケアってなんだろう? ナイチンゲール看護研究所・金井一薫さんをたずねて
vol. 032023.10.31ケアってなんだろう? ナイチンゲール看護研究所・金井一薫さんをたずねて![]() vol. 022023.10.30さまざまな命に囲まれて、心を動かして生きる。 園芸療法を行う「晴耕雨読舎」をたずねて
vol. 022023.10.30さまざまな命に囲まれて、心を動かして生きる。 園芸療法を行う「晴耕雨読舎」をたずねて![]() vol. 012023.10.11自分らしく生きるってなんだろう? 一人ひとりの人生に向き合う介護事業所「あおいけあ」をたずねて
vol. 012023.10.11自分らしく生きるってなんだろう? 一人ひとりの人生に向き合う介護事業所「あおいけあ」をたずねて