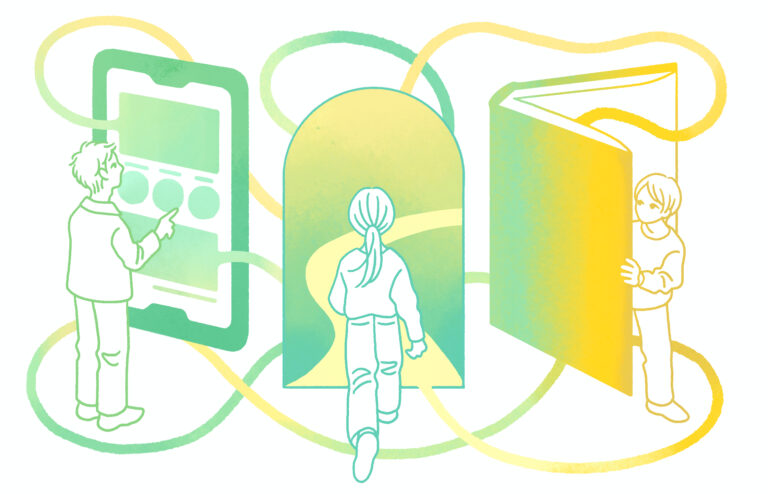「助けて」と言い合える環境を育むには? 「みんなの家 タブノキ」をたずねて “自分らしく生きる”を支えるしごと vol.19
Sponsored by 厚生労働省補助事業 令和6年度介護のしごと魅力発信等事業(情報発信事業)
- トップ
- “自分らしく生きる”を支えるしごと
- 「助けて」と言い合える環境を育むには? 「みんなの家 タブノキ」をたずねて
日々の暮らしをひとりで、あるいは家族だけで、営んでいくことはできない。介護や子育てといったケアは1対1で向き合っていると息が詰まるし、そうでなくても、孤独を感じることもあれば、困りごとが生じることもある。
そんなときに、できれば近所に、ちょっと「助けてほしい」「手伝ってほしい」と伝え合える関係性があったなら。そう願ってはいても、家の内と外には壁も距離もあって、家族以外の他者に頼るのはなかなか難しい。
自分が暮らす地域で、お互いに「助けて」と頼り合える関係性は、どうやって育めるのだろう?
今回訪ねる長野県小諸市の「みんなの家 タブノキ」は、「ともに暮らしやすい地域をつくる」ことを願いとして掲げている。高齢者と障害のある子どもたちが通う共生型のデイサービス施設でありながら、地域にひらかれたみんなの家。そこはどんな場所で、どんな関係性が育まれているのか。
好奇心と問いを携えて、東京から新幹線に乗り込み、長野・佐久平駅に降り立った。
「用事」を真ん中に、木陰に集うように暮らす
澄んだ空の下、きりりと聳(そび)え立つ山々に囲まれた田んぼ道を行く。車を降りると、肌に触れる風が冷たい。「みんなの家 タブノキ」の看板を見つけて寄っていくと、軒先で数人が柿を干している。


「冷えてきたから中に入りましょう」と作業を切り上げて「○○さん、ありがとね〜」と一人ひとりに声をかけているのが、株式会社タブノキ代表の深山直樹(みやま・なおき)さん。挨拶もそこそこに、さっそく施設を案内をしてもらうことに。

建物は、大工のいとこを中心にDIYで改装したという築50年ほどの民家。「まだまだ改装中で、たぶんずっと完成はしない。サグラダファミリア状態なんですよ」と深山さんは笑う。


離れの倉庫には、廃材と工具が並び、頻繁に修理や家具づくりをしているそう。積まれた薪は、頼まれて別荘地の木を切って持ち帰り、割ったものだ。

もともと田んぼだった土地を借り、水路を掘って耕した畑。そこには大豆が植えられていて、蔵には育てた大豆で春に仕込んだ手前味噌が貯蔵されていた。


タブノキでは、こうした暮らしの中で生まれる作業を「用事」と呼び、利用者とスタッフ、地域の人たちと垣根なく、ともに取り組んでいる。
利用者さんたちのほとんどが認知症の状態にある方々ですが、もともと長年、農業や土木をされていて、力があったり手先が器用だったりするんですね。ちゃんと体が覚えているので、僕らが学び、助けられることも多いんですよ。
家の中におじゃますると、陽の当たる廊下で、おばあさんたちがご近所からのいただきものだという乾燥した「あおばつ(青豆)」の皮をむいていた。

薪ストーブを囲むあたたかなリビングでは、利用者のお年寄りたちが、子どもたちと戯れたり、おしゃべりに花を咲かせたり、寝息を立てたり、食器を洗う姿も。


利用者とスタッフの境界線が溶け出し、季節ごと、毎日の「用事」を真ん中に、できる人ができることをして、同じ屋根の下に集う。“施設”でそれぞれが過ごしている、というよりは、“家”でともに暮らしている。この光景の源には、深山さんが「タブノキ」の名前に込めた想いがある。
福祉の仕事ってどうしても、利用者さんとスタッフ、される側/する側の間に境界線が生まれてしまう。そこに違和感があって。僕らの理想の施設のイメージは、1本の大きな木。タブノキは土に広く根を張り数百年生きる木なんですね。時間をかけて暮らしを積み重ねて、地域の人が集える木陰のような居場所をつくりたい。今はまだか弱いですけど……。
そう話す深山さんの手元には、この土地に根を生やしはじめた小さなタブノキの芽があった。

諦めても弱くても、どうあっても許されていい
深山さんがこの土地、長野に「みんなの家 タブノキ」の種を植えたのは、2020年の春のこと。なぜはじめたのか。その問いに答えるように、深山さんは幼少時代、仕事での挫折、そこから得た気づきを語ってくれた。
生まれは東京の府中で、一人っ子なんですけど、あんまり家に居場所がなくて。父は統合失調症、母も精神的な状態がよくなくて仲が悪かった。家庭の中で、守られたい存在なのに「助けて」と言えない。近所のおばあちゃんの家で、いとこと遊んでいるときだけ気が安らいだんです。家庭以外の居場所があったから、なんとかやっていけたんですよね。
年上のいとこに付いて参加した「野外教育クラブ」が長野との縁。7歳から15歳までの8年間、年に2回のペースで野外活動に訪れていた深山さんは、大人になって、長野と出会い直したという。
大学を卒業しても仕事をせず、モラトリアム期間に槍ヶ岳の山小屋でアルバイトをしていたんです。その時に、どう考えても自分の居場所は長野だよなと思ってはいました。東京で少し働いたけど、やっぱり水が合わなくて。ホームに帰ってきたつもりで、長野に引っ越してきたんです。

長野では、“生きづらさ”を抱えていた自分を何度も救ってくれた音楽に夢中になっていたが、結婚を機に手に職をつけようと林業に従事することに。
音楽は、唯一無二の音を鳴らそうと気負って人に頼れず、うまくいかずに投げ出したところがあって。林業も、まったく向いていなかった。仕事ができずに怒鳴られて、さらには仕事中に指を切断しちゃって。がんばったらできるんじゃないかと思っていたけど、がんばってもできないことがあるんだと気づきました。はっきりとした挫折を味わって、もう無理だなって諦めたというか、自分の弱さを認めることができたんです。
できないことはできない。そう諦め、弱さを受容した深山さんはそこから、できることを探り、福祉の仕事に足を踏み入れた。親戚のおばさんと妻が福祉職に就いていて従事する人が身近にいたことに加え、父の看取りに後押しされた。
ハローワークの職業訓練場に2年通って介護の資格を取ったんですけど、その間に父が他界したんです。父は仕事で挫折をして心を病んでしまい、世間から見たら“降りていく人生”だったのかもしれませんが、ぼくは最期がどんな状態であっても父の人生には価値がある、と思えたんですね。
福祉の仕事に対する覚悟を決めたものの、深山さんは実際の介護現場を目の当たりにして打ちのめされる。
介護施設での実習は、決められた時間割に沿った流れ作業で、お年寄りたちが囚われの身であるかのように見えたんです。ここで自分にできることはあるんだろうかと、また挫折感を味わいましたね。
それでも「ごく楽介護の会」という勉強会で知った、自分たちのやり方で介護の現場を切り拓く先人たちの姿に一筋の希望を抱き、職に就いた。ところが、勤めた宅ろう所では、介護をお年寄りへの“おもてなし”と捉え、サービスとしての画一的なケアが行われ、どうもがいてもその歯車にしかなれなかった。
決められた時間割通りにできない利用者さんと、一緒にそのレールを外れて寄り添おうとすると、許されずに排除されていってしまう。流れに乗ることを諦めても、弱くても、人はどういう状態であっても許されてもいいはずなのに。
レールに乗れない人たちは、幸せに暮らせないんだろうか? 流れに乗って楽しめる人はそれでいいけど、どうにもならない人たちが、暮らしやすさを手に入れる選択肢があってもいいんじゃないか。そうした想いが降り積もって限界が来て爆発して、自分で始めることにしました。

時間割を手放し、徹底的に管理をしない
こうして深山さんは自分で介護施設を運営していくことを決意した。とはいえ、その時点で「金なし、人脈なし、実績なし、ない、ない、ない、の三拍子だった」と振り返る。そこで、同じ長野で会社を営む先輩経営者に助けを求めた。
相談したら、「あなたがやろうとしていることはおもしろいけど、今のあなたには、お金も人脈も実績も何もない。まずはそこをひっくり返すことからじゃないですか」と言われ、親身にいろいろ教えてくださって。事業計画を書いて、商工会議所に行って、毎日Twitterをつぶやいて……と、教えてもらったことをぜんぶ実行していったら、1年後の開業日には、お金も人も経験値もぜんぶある、ある、あるにひっくり返っていたんです。
ひとり“生きづらさ”を抱えて「助けて」と言えなかった深山さんは、自分の弱さを認め、ありたい姿を見つけ、タブノキを立ち上げる頃には「助けて」と声を上げられるようになっていた。
そんな深山さんを起点に、タブノキでは「助けて」と「ありがとう」が循環する。一方的に“もてなす”のではなく、“ともに暮らす”。その中で、畑仕事や洗濯物などの用事を「助けてほしい」と伝え、やってもらったら「ありがとう」を返す。


こうしたタブノキのあり方の根底にあるのが、「時間割を手放し、徹底的に管理をしない」という姿勢だ。
分刻みのスケジュールで、お年寄りから用事を取り上げ、自分に心の余裕がない状態で接する日々が暮らしとは思えないんですよね。上から管理する一方的な関係はいやだ。だから、時間割は絶対につくりません。できないことはできないし、やりたくないことはやらない。それでいいんです。タブノキでは、管理しないことを徹底しています。

実際にリビングを見渡してみると、おやつを食べている人もいれば、ベッドで横になっている人もいる。画一的な時間割りではなく、それぞれのペースで時が動いている。中には外へ出て行く人も。
うちは鍵もつけてないし、外に行く人も止めません。もちろん、気づけば一緒に行きますが。よく近所の農家のおばちゃんが、あの人が出て行ったよって知らせに来てくれるんですよ。

いわゆる「全員参加」のレクリエーションはないけれど、参加したい人たちだけで、カラオケや温泉に行くこともあるという。この日も紅葉狩りに行っている人たちがいた。
用事も行事もやりたくない人はやらなくていい。ただそこにいるだけでいいんです。やりたくないことをやらないだけで、時間と心に余白が生まれるので、やりたいことが立ち上がってくることもあるんですよね。

やりたくないことをやらない。つまり、徹底的に管理をしない。これが、集う人たちが互いに「助けて」と伝え合える、タブノキがタブノキであることを支える根っこなのだ。
スタッフと利用者、仕事と暮らし。溶け出す境界線
「みんなの家 タブノキ」を一言で冠するのは難しいけれど、福祉施設の区分としては、要介護の高齢者の「通所介護」と、障害のある子どもたちの「放課後等デイサービス」を合わせた「共生型」の事業所になる。でも、ここに集うのは認知症の状態にあるお年寄りや障害のある子どもたちだけではない。

介護を必要としない高齢者、スタッフや近所の子どもたち、時に赤ちゃんもやって来る。タブノキでは、0〜3歳の赤ちゃんを連れてきた親御さんに昼食と1000円を渡す「赤ちゃんボランティア」を実施。毎週水曜は誰でも晩ごはんを食べられる「みんなの食堂」も開いている。
さらに、「みんなの家 タブノキ」の少し先には看取りや緊急避難ができるシェアハウス「あっちの家」があり、ここで寝泊まりしている人たちもいる。

スタッフなのか、要介護の利用者なのか、それとも地域の人なのか、一体誰の子どもなのか、その境界線は混ざり合っていて曖昧で、一見しただけではわからない。
深山さんの思想、タブノキのあり方に吸い寄せられて集まるスタッフもどこかユニークで、なんだか人間らしい。空き家から集まる古物を販売するギャラリーを土蔵で開く予定の青年。二日酔いで子どもを連れて来て休んでいたママ。利用者として見学に来てそのまま働くことになった夫婦──。
バーを経営する看護師の石田祐樹さんもその一人。朝5時までバーに立ち、週に3回タブノキで働いている。

石田:高校の同級生の紹介でタブノキで働き始めたんですが、毎日が新鮮でめちゃくちゃおもしろいです。ここでは、看護師として患者さんをケアするという仕事の領域を超えていける。職種とか肩書きではなく、一人の人として関わっていけるというか……。みんなで豆を撒いて味噌を仕込んだり、子どもたちとおやつをつくったり。料理とか作物を育てるとか日本の季節の用事とか、今まであまりやってこなかったことを歳上のスタッフやおじいちゃんおばあちゃんに教えてもらうこともよくあって、ありがたいです。
出勤時間以外はほとんど何も決まってなくて、自由にやらせてもらっています。おれは事務作業はあんまりできないんで、ゴミ捨てとか掃除を積極的にやるようにしていて。働いている、というよりは暮らしを一緒にやりに来ている感じ。ずっと仕事が嫌いだったけど、深山さんの考え方も、ここで働くことも好きですね。
ぶつかり合って、ともに生きている。関係性は完結しない
5年目を迎えた2024年の秋。「ゼロベースからやっと『タブノキ1.0』のフェーズにいる」と話す深山さんは、「課題が山積み」だと言葉を続ける。
深山:管理しないっていうのは本当に難しくて。なぜかみなさん、ここにいると社会性の仮面が1枚、また1枚と剥がれていくんですよね。なんていうか、喜怒哀楽がぜんぶむき出し。異なる価値観の人たちが隣にいて、怒りや哀しみを出していくと、衝突や摩擦が起きて、関係性にひずみが生まれる。タブノキにルールがないから、毎回それぞれのYES or NOをぶつけ合って進むしかないんですよね。トラブルがない日がないんで、正直しんどいです(笑)。

その日も利用者さんの怒鳴り声が響き、慣れない取材チームはビクッとしたけれど、タブノキでは日常茶飯事なのだとか。たしかに筆者も、家族に対しては恥じらいも遠慮もなく、怒りや哀しみが溢れ出てしまうことがある。でもそれは、関係性が修復できるという安心と信頼がベースにあるからだとも思う。
深山:5年目にして、利用者さんもスタッフも、ここに集う人たちの距離が縮まって、関係性が広がり深まっているのかもしれません。その過程ではぶつかり合うことも必然なのかなって。なので近くに物件を見つけて、衝突が起きたときに物理的に離れる”逃げ場”を用意しようと思っているんです。
何度ぶつかり合っても、少し距離を置いて、そこからまた手を伸ばし、関係を結び直せるように。

深山:タブノキに集う人たちは、家族でも友だちでもないけど、他人じゃない。人と人との間にある関係性は常に揺れ動いていて、一定じゃないんですよね。建物だけじゃなく、関係性も完結することはない、サグラダファミリア状態です。次から次へと課題は出てくるので、タブノキでの場づくりも関係づくりも、永遠につづくんだと思います。
僕らが掲げる「ともに暮らしやすい地域をつくる」って、ゴールではなく“願い”なんですよ。目標地点に向かってがんばるのではなく、今この瞬間がどれだけの濃さを持っているかを大切にしたい。課題が解決しきることはないし、しんどいことも多いけど、生きてる!って思えています。自分を抑え込むのではなく、解放して、助け合ってみんなとともに生きている。僕は、そう思える社会で暮らしていきたいんですよね。

「みんなの家 タブノキ」は、深山さんとそこに集う人たちのそれぞれの居場所であり、願いだった。やり方やかたちは違っても、こうありたいという願いをベースに、同じ場所に集い、時に助け合い、時にぶつかり合って離れてまた集って、関係性を結び直しながら、安心して暮らせる居場所をつくっていけたら──。
そんな想いを胸に灯しながら、お裾分けいただいた小さなりんごを両手に、自分が暮らす家へ帰った。
Information
〈こここ〉では連載「“自分らしく生きる”を支えるしごとー介護の世界をたずねてー」 を通して、さまざまな「ケアするしごと」を取り上げています。また、〈anan web〉や〈POPEYE web〉でもさまざまな記事を公開中! ぜひご覧ください。
【anan web】
・介護の現場1/ 都会で? 里山で? フルタイム? スキマ時間? 選択肢もたくさん。自分を表現できる現場で働く、新しい介護のカタチ。
・介護の現場2/ローカルな暮らし×介護を体現する[くろまめさん]で、幅広い交流を楽しみながら働く
・介護の現場3/自分の強みを活かしながら介護に関わるキーパーソンの働き方に密着!
【POPEYE web】
Profile
![]()
-
株式会社タブノキ
2020年4月より「みんなの家タブノキ」を始業。
長野県小諸市にて、古民家をセルフリノベーションし、赤ちゃんからお年寄りまで、障害の有無に関わらず誰もが過ごす事ができる居場所として運営を続けている。
新型コロナウイルス第一波と同時に始業したため、全国的に施設が外部との交流を次々遮断していく中、地域に開き続けることを選択肢の一つとして提案し賛否を呼び注目を集める。
現在 通常規模通所介護、共生型放課後等デイサービス、共生型生活介護を「みんなの家タブノキ」で行い、斜め向かいに誰でも泊まれる古民家ハウス「シェアハウスあっちの家」を構え定期巡回随時対応型訪問介護サービスで対応している。
この他、地域支援事業や「みんなの店タブノキ」として古物商、特殊伐採請負など行っている。
Profile
この記事の連載Series
連載:“自分らしく生きる”を支えるしごと
![]() vol. 322026.01.14本から「介護にあるまなざし」に出会う。編集者、ダンサー、美術家、介護職員の選ぶ4冊
vol. 322026.01.14本から「介護にあるまなざし」に出会う。編集者、ダンサー、美術家、介護職員の選ぶ4冊![]() vol. 312025.12.26「助けて」という言葉が必要になる前に。社会福祉法人丹緑会特別養護老人ホーム栗林荘をたずねて
vol. 312025.12.26「助けて」という言葉が必要になる前に。社会福祉法人丹緑会特別養護老人ホーム栗林荘をたずねて![]() vol. 302025.12.17いいチームってなんだろう? 多職種連携で「看取り」に取り組む特別養護老人ホーム「芦花ホーム」をたずねて
vol. 302025.12.17いいチームってなんだろう? 多職種連携で「看取り」に取り組む特別養護老人ホーム「芦花ホーム」をたずねて![]() vol. 292025.12.10一人ひとりの「あたり前」を大切にできる環境とは?「あたり前の暮らしサポートセンター布施屋」をたずねて
vol. 292025.12.10一人ひとりの「あたり前」を大切にできる環境とは?「あたり前の暮らしサポートセンター布施屋」をたずねて![]() vol. 282025.12.05安心して歳を重ねられる地域とは? 社会福祉法人くらしのハーモニーをたずねて
vol. 282025.12.05安心して歳を重ねられる地域とは? 社会福祉法人くらしのハーモニーをたずねて![]() vol. 272025.11.18「ケア」を感じたマンガを教えてください。作家、社会学者、アーティスト、福祉施設長の選ぶ4作品
vol. 272025.11.18「ケア」を感じたマンガを教えてください。作家、社会学者、アーティスト、福祉施設長の選ぶ4作品![]() vol. 262025.11.10「安心できる住まい」はどう育まれる? 特別養護老人ホーム「美里ヒルズ」をたずねて
vol. 262025.11.10「安心できる住まい」はどう育まれる? 特別養護老人ホーム「美里ヒルズ」をたずねて![]() vol. 252025.03.06地域の「居場所」ってなんだろう? 佛子園「三草二木 西圓寺」をたずねて
vol. 252025.03.06地域の「居場所」ってなんだろう? 佛子園「三草二木 西圓寺」をたずねて![]() vol. 242025.02.27幅広く使われる「ケア」をどうとらえる? 向坂くじらさん、吉田真一さんと考える
vol. 242025.02.27幅広く使われる「ケア」をどうとらえる? 向坂くじらさん、吉田真一さんと考える![]() vol. 232025.01.30本から「介護にあるまなざし」に出会う。イラストレーター、哲学者、ジャーナリスト、介護福祉士の選ぶ4冊
vol. 232025.01.30本から「介護にあるまなざし」に出会う。イラストレーター、哲学者、ジャーナリスト、介護福祉士の選ぶ4冊![]() vol. 222025.01.23地域の歴史や文化とともに歩む福祉とは? ライフの学校「六郷キャンパス」をたずねて
vol. 222025.01.23地域の歴史や文化とともに歩む福祉とは? ライフの学校「六郷キャンパス」をたずねて![]() vol. 212025.01.20多世代が一緒に過ごすことで生まれる安心とは?「深川えんみち」をたずねて
vol. 212025.01.20多世代が一緒に過ごすことで生まれる安心とは?「深川えんみち」をたずねて![]() vol. 202025.01.10アーティストが滞在する福祉施設とは? 「デイサービス楽らく」をたずねて
vol. 202025.01.10アーティストが滞在する福祉施設とは? 「デイサービス楽らく」をたずねて![]() vol. 182024.12.13私もあなたも、主人公でいられるように。「DAYS BLG! はちおうじ」をたずねて
vol. 182024.12.13私もあなたも、主人公でいられるように。「DAYS BLG! はちおうじ」をたずねて![]() vol. 172024.12.12「ケア」を感じたマンガを教えてください。組織開発コンサルタント、俳優、福祉施設所長、介護福祉士の選ぶ4作品
vol. 172024.12.12「ケア」を感じたマンガを教えてください。組織開発コンサルタント、俳優、福祉施設所長、介護福祉士の選ぶ4作品![]() vol. 162024.11.08安心して歳を重ねられる町とは? 鞆の浦・さくらホームをたずねて
vol. 162024.11.08安心して歳を重ねられる町とは? 鞆の浦・さくらホームをたずねて![]() vol. 152024.03.12介護のしごとに興味をもったとき、はじめの一歩はどうすれば?
vol. 152024.03.12介護のしごとに興味をもったとき、はじめの一歩はどうすれば?![]() vol. 142024.02.27認知症を“体験”する「VR認知症」。イシヅカユウさんと体験して気づいたこと
vol. 142024.02.27認知症を“体験”する「VR認知症」。イシヅカユウさんと体験して気づいたこと![]() vol. 132024.02.22認知症のある方100人以上にインタビューをして気づいたこと。認知症未来共創ハブ代表・堀田聰子さん
vol. 132024.02.22認知症のある方100人以上にインタビューをして気づいたこと。認知症未来共創ハブ代表・堀田聰子さん![]() vol. 122024.02.20暮らしのなかで閉じる命をつないでいく 写真家/訪問看護師 尾山直子さん
vol. 122024.02.20暮らしのなかで閉じる命をつないでいく 写真家/訪問看護師 尾山直子さん![]() vol. 112024.02.19科学的な介護ってなんだろう? 福祉楽団「杜の家なりた」をたずねて
vol. 112024.02.19科学的な介護ってなんだろう? 福祉楽団「杜の家なりた」をたずねて![]() vol. 102024.02.08「老いと共に生きる」を映画から考える。編集者、映画作家、介護福祉士、福祉施設運営者の選ぶ5作品
vol. 102024.02.08「老いと共に生きる」を映画から考える。編集者、映画作家、介護福祉士、福祉施設運営者の選ぶ5作品![]() vol. 092023.12.20居場所ってなんだろう? 人が自然と集まる場所を目指す「52間の縁側」をたずねて
vol. 092023.12.20居場所ってなんだろう? 人が自然と集まる場所を目指す「52間の縁側」をたずねて![]() vol. 082023.12.13「ケア」を感じたマンガを教えてください。文学研究者、精神科医、看護師、介護福祉士、文筆家の選ぶ5作品
vol. 082023.12.13「ケア」を感じたマンガを教えてください。文学研究者、精神科医、看護師、介護福祉士、文筆家の選ぶ5作品![]() vol. 072023.12.06自然の循環に身を委ね、大地と共に生きる。「里・つむぎ八幡平」が実践する「半農・半介護」の暮らし
vol. 072023.12.06自然の循環に身を委ね、大地と共に生きる。「里・つむぎ八幡平」が実践する「半農・半介護」の暮らし![]() vol. 062023.11.29介護施設×学生シェアハウス「みそのっこ」が教えてくれる、「介護×場づくり」の可能性
vol. 062023.11.29介護施設×学生シェアハウス「みそのっこ」が教えてくれる、「介護×場づくり」の可能性![]() vol. 052023.11.10いくつになっても「働く」は楽しい。ばあちゃんたちの生きがいとビジネスの両立を目指す、株式会社うきはの宝をたずねて
vol. 052023.11.10いくつになっても「働く」は楽しい。ばあちゃんたちの生きがいとビジネスの両立を目指す、株式会社うきはの宝をたずねて![]() vol. 042023.11.07居心地の良い場所の条件ってなんだろう? 浦安にある高齢者向けの住まい「銀木犀」をたずねて
vol. 042023.11.07居心地の良い場所の条件ってなんだろう? 浦安にある高齢者向けの住まい「銀木犀」をたずねて![]() vol. 032023.10.31ケアってなんだろう? ナイチンゲール看護研究所・金井一薫さんをたずねて
vol. 032023.10.31ケアってなんだろう? ナイチンゲール看護研究所・金井一薫さんをたずねて![]() vol. 022023.10.30さまざまな命に囲まれて、心を動かして生きる。 園芸療法を行う「晴耕雨読舎」をたずねて
vol. 022023.10.30さまざまな命に囲まれて、心を動かして生きる。 園芸療法を行う「晴耕雨読舎」をたずねて![]() vol. 012023.10.11自分らしく生きるってなんだろう? 一人ひとりの人生に向き合う介護事業所「あおいけあ」をたずねて
vol. 012023.10.11自分らしく生きるってなんだろう? 一人ひとりの人生に向き合う介護事業所「あおいけあ」をたずねて