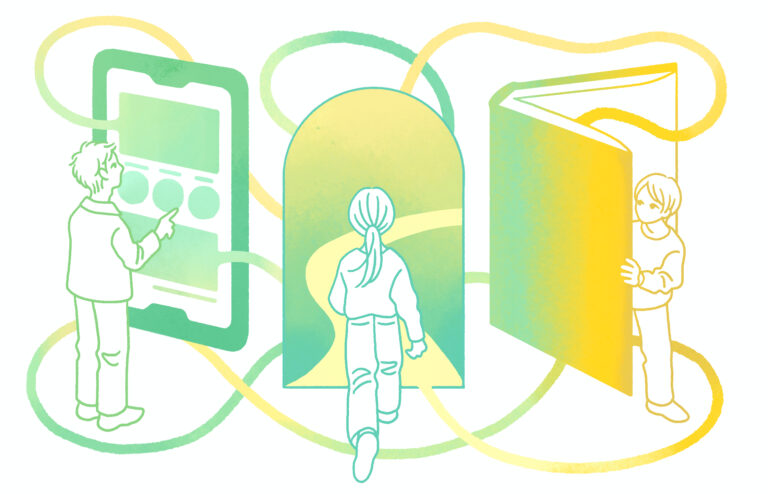科学的な介護ってなんだろう? 福祉楽団「杜の家なりた」をたずねて “自分らしく生きる”を支えるしごと vol.11
Sponsored by 厚生労働省補助事業 令和5年度介護のしごと魅力発信等事業(情報発信事業)
- トップ
- “自分らしく生きる”を支えるしごと
- 科学的な介護ってなんだろう? 福祉楽団「杜の家なりた」をたずねて
「介護の仕事って、“やさしさ”や“思いやり”といった情緒的なイメージで語られることが多いんです。でも、それだけでは良い介護は実現できません」
そう話すのは、社会福祉法人 福祉楽団の代表・飯田大輔さん。福祉楽団は、千葉県と埼玉県を中心に、高齢者介護や子ども支援、障害者支援や農林業など、多分野にわたる福祉サービスを展開している法人だ。
飯田さんの言葉を聞いて思わずハッとした。私自身が介護に対してまさに「人のため」とか「個性を尊重する」というイメージばかりを抱いていたからだ。
福祉楽団では、介護の実践に際して「科学的な介護」という言葉をとても大事にしている。「科学」とは、私たちが持つ介護のイメージとはずいぶんとかけ離れているように思えるが、一体どういうことなのだろう?
そんな問いをたずさえて、福祉楽団が運営する「杜の家なりた」の特別養護老人ホームをたずねた。
介護はやさしさだけじゃない?
都心から電車に揺られ1時間半。千葉県成田市は下方(シタカタ)ののどかな風景の中に「杜の家なりた」は建っている。エントランスをくぐり、ぐるりと館内を見回すと、壁一面の窓から太陽の光がやわらかく差し込んでいた。


今から20年以上前、農学部出身の飯田さんが福祉の世界に足を踏み入れたのは、偶然のきっかけからだった。福祉施設の立ち上げを計画していた母親が道半ばでたおれ、飯田さんが事業を引き継ぐことになったのだ。日本社会事業大学で福祉をイチから学ぶなかで、介護が「やさしさ」や「思いやり」という情緒的な言葉ばかりで語られることに違和感を抱くようになったという。
そんな折、現在ナイチンゲール看護研究所の所長を務める金井一薫さんの授業を受けたことが転機となり、「科学的な介護」が飯田さんの活動の指針となった。
飯田さんが20年にわたり実践してきた「科学的な介護」とは、一体どのようなものなのだろうか。

たとえば高熱を出してまったく食欲がない時、好物だからといってカツ丼を声かけしながらやさしく口に運ばれたとしたらどう思いますか? きっと、それは良い介護とは言えないですよね。
飯田さんはそんな例をもとに話を始めた。
たしかにそうだ。どれだけやさしくされたって、高熱の時に消化に悪いものを食べれば、むしろ体調は悪くなるにちがいない。これが「介護はやさしさだけじゃない」という所以である。
介護には、「やさしさ」だけではなくて生理学の知識が必須なんです、と飯田さんは続けた。
なぜ発熱しているのか、その時に消化管はどうなっていて、にじみ出る汗はどういう組成なのか。「発熱」を解剖生理学に基づいて理解していれば、浸透圧や温度を配慮した水分補給が必要だということが分かる。すると、スポーツドリンクの他に「お茶と梅干し」という選択肢が生まれる。その結果、利用者の方々の好みや気分に合わせた選択ができるのだ。
人間の身体の仕組みを理解して、根拠をもって利用者の生活を整えていく。それが私たちが実践する“科学的な介護”です。

もしも「やさしさ」や「熱意」だけで介護を行なったとしたら、介護が誤った方向に導かれても気づくことができない。それはむしろ利用者の苦痛を生んでしまう。
基本的な原理をふまえているからこそ、一人ひとりに合わせた介護の創意工夫とアイデアの幅が広がり、「その人らしさ」を尊重しながら、よい方向に導くことができる。介護の仕事のクリエイティブな側面はここにあるのだろう。
飯田さんは、こうした介護の目的を、ナイチンゲールの言葉を借りて、利用者の「生命力の消耗を最小にする」ことだととらえている。「生命力」とは、人間に備わっている、回復へ向かおうとする自然な力のことだ。
介護は「Care(ケア)」であり「Cure(治療)」ではない。相手が持つ可能性が十分に発揮されるように生活を整えること。そのために、解剖生理学の知識をベースに介護を実践すること。これが「科学的な介護」の考え方なのだ。

科学ではとらえきれない側面とどう向き合うか
「科学的な介護」が、生理学の知識をベースにして利用者の生活を整えることだということは分かった。一方で、人間には科学ではとらえきれない側面もある。
さらに、介護の現場において目の前の状況はつねにリアルで動的であり、ペーパーテストをじっくり読み解けば良いというものではない。「科学的な介護」を実践するためにはどのような能力が求められるのだろう。
飯田さんに問いかけると、こんな言葉が返ってきた。
まずは、一人の人間を「生物体」と「生活体」の2つの側面からとらえること。その上で利用者の最善を考えることが重要です。
「生物体」とは、解剖生理学に基づいた原理原則としての側面。人は誰しも同じ身体の構造を持っているということ。一方で「生活体」とは、一人ひとりの生活スタイルや趣味嗜好としての側面。人はみな異なる個性を持っているということ。

介護の現場では、この2つの側面のせめぎ合いが起こる。体調がすぐれないとき、お腹をこわすリスクがあったとしても、どうしてもキンキンに冷えたアイスコーヒーが飲みたい夏だってあるかもしれない。
もちろん本人の意向は無視できません。じゃあどうするかと言えば、共同的に意思決定していくプロセスが必要です。いま冷たいものを飲んだら、ちょっとお腹が痛くなっちゃうかもしれないですよとか、ぬるめのお茶やポカリもありますよとか。しっかりと説明をして、やり取りをすることが大事なんです。
そして、その意思決定のプロセスで求められるのが「観察」の能力であると飯田さんは言う。介護の現場において、利用者からの積極的な情報提供がむずかしい場合もある。そのため、介護する側が主体的に観察する必要があるのだ。

19世紀のイギリスの看護師であり統計学者でもあったフロレンス・ナイチンゲールは、『看護覚え書(Notes on Nursing)』の中で「観察」の難しさについてこう述べている。
(観察に基づいて)真実を述べるということは、一般に人びとが想像しているよりもはるかに難しいことである。それは《単純な》観察不足によるばあいがあり、また想像力のからみあった《複雑な》観察不足によるばあいがある。
『看護覚え書(Notes on Nursing)』現代社、改訂第7版、P180目の前で起きている出来事に対して、「こうに違いない」と思い込んでしまうことは私たちでもよくあることだ。どんなに生理学の知識があったとしても、自分の「ものの見方・考え方」を絶対化して介護にあたることには危険性が伴う。ではどうすれば良いのか。重要なのは、日々の介護行為に「問いを立てる」ことだと飯田さんは言う。
「こうだ!」と決めつけるのではなく「なぜ?」と問いを立てて思考することが必要です。介護職に就く人は広い視野を持たないと、目の前の相手の可能性を狭めてしまうことがあるからです。

また、「観察」の身につけ方について、飯田さんはこう続ける。
観察はすぐできるようになるものではありません。失敗を繰り返しながら、一人前の介護職員に成長する。知識を学び、思考と実践を繰り返すことが経験になるんです。素人には見えないものが見えて、聞こえない声が聞こえる。これが介護のプロなんです。
科学の特徴は「再現性」だ。とはいえ、どんなに原理原則があったとしても、目の前の状況はいつでも「一回目」である。だからこそ、問いをやめず、相手の最善を考え続けること。可能性をつねに開いておくこと。そのプロセスこそが、「科学的な介護」の本質なのではないだろうか。
「どうしても餅を食べたい」と言われたら?
杜の家なりたには、20-30代のフレッシュな職員が多い。しかも、福祉楽団に新卒で入社する約半数が福祉を学んでいない人だという。「科学的な介護」はどのように教えられ、現場でどのように実践されているのだろうか。
入社5年目の奥住比沙子さんは、学生の頃に抱いていた「人が安心できる場をつくりたい」という思いが福祉楽団の理念と共鳴し、入社を選んだという。とはいえ、介護の分野はまったくはじめてだったそう。
入社後に2ヶ月間行われる研修では、基礎的な生理学の知識を学び、とにかく「根拠を持ってケアをしてください」と言われて育ちました。仕事を続けるなかで、利用者さんの小さな変化に気づける観察力や、その人にベストなケアを考える力が、介護職の専門性なのかなと思うようになりました。

まさに、飯田さんから聞いた話と通ずる部分がある。奥住さんからは、実際に施設内で起きた具体的なエピソードを教えてもらった。
たとえば、車椅子に乗っている方が手すりにつかまってトイレの便器に座りかえる場面で、最近手すりをつかむのがなんだか難しそうだという変化に気づいたとします。そこにはいろんな理由が考えられるんですね。腕の筋力が低下してつかむ力が弱くなっているかもしれないし、視力の低下で手すりの位置がわからなくなっている可能性もある。
そのとき、その方の日々の生活を観察するなかで、ものを見分けるのが難しい場面が増えていたら「見えづらさ」が原因である可能性が高い。するとアプローチが変わってきます。この場合は、白地の手すりに目印となる赤いテープを貼って「赤いところを目印につかんでもらえますか?」と促したらうまくいくかもしれません。
安易に職員が動かしてあげるのは、本来的じゃないと思うんです。もちろんサポートはしますが、あくまでその方が自分で行うことが重要。その方の生活を朝から晩までずっと観察するなかで、他の行動にヒントが見つかるんです。

また、飯田さんが言っていたような「生物体」と「生活体」の2つの側面のせめぎ合いが生じることもあったという。
以前、飲み込む力が低下している方が、どうしても餅を食べたいとおっしゃったことがありました。「餅をつまらせて死ぬならそれでもいい!」と、その利用者さんは驚くほど餅を食べることに対する熱意がすごくて。
日頃の食事の様子を踏まえて、介護職員やリハビリ職員・看護師そして本人も含めて餅を食べる環境について相談しました。覚醒状態の良い時間を選び、水分を摂ってから餅を食べてもらうようにしたんです。
すると、部屋に閉じこもりがちだったその方は餅を食べるためにリビングに出てきて他の方とコミュニケーションを取るようになったり、低栄養で低すぎた体重が増えたり! 結果的に生物体として良い変化をもたらしたと考えています。

日々私たちは「この人にとっていいケアってなんだろう?」と考えながら観察しています。考えたケアが一発であたることなんてあまりないです。
「あれ? うまくいかないな」となったり、「そうきたか!」と想定外のことがおこったり、「これでいいのかな」と悩んだり。この思考過程がケアワーカーのクリエイティブな側面であり、おもしろいところです。
奥住さんの話を聴きながら感じたのは、奥住さんにしか見えないものや聞こえない音がたしかにあるということ。それは利用者に誠実に向き合い、試行錯誤を重ねることで育まれてきた能力にちがいない。「科学的な介護」の実践は、ひとりひとりの職員の創造性が発揮されることによって成り立つものなのだろう。
自然の力を活かし、日々の暮らしを空間から整える
「科学的な介護」の考え方は、杜の家なりたの環境設計にも取り入れられている。人間に備わっている回復力をうながすための工夫を探るべく、マネージャーの田中秀明さんに施設を案内してもらった。


施設を歩いていて、まず印象的なのが「窓」の数と大きさである。館内のいたるところに日差しがたっぷりと差し込んでいる。私たちもよく知るように、太陽光は布団を干せば殺菌してくれるし、日光浴をすれば心身の調子を整えてくれる。太陽の力を借りることで、室内を清浄に保ち、利用者の回復をうながしているのだ。


そして、利用者の個室を含め、ほとんどの窓の上部には換気窓がついている。「基本的には一日中換気しています」と田中さんが言うように、室内の空気は冷やされることなく循環し、つねに新鮮に保たれている。

さらに、排泄物や汚物を運ぶための通路が屋外に設置されているため、一度も室内を通ることなく処理場まで運ぶことができる。利用者が生活のなかで呼吸する空気はかぎりなく清浄だ。

ダイニングスペースへ向かうと、ほのかにご飯の香りがただよってきた。ちょうど昼食の時間のようだ。杜の家なりたでは、キッチンとダイニングの間に仕切りがない。その意図を田中さんはこう話す。
食事の時間になればご飯の匂いがする。調理や配膳の音も聞こえてくるし、誰が何をどのように盛り付けているかが目に見える。これってふつうの日常ですよね。

「ふつうの日常」を演出する工夫は、照明にも表れている。リビングとダイニングスペースに吊るされたペンダントライトは暖色で、夜になると少しだけ暗い。病院のように蛍光灯の光が昼も夜も変わらず点いているのではなく、夜には夜を感じられるようになっている。
特養の利用者にとって、この空間は「暮らし」の場に他ならない。健康だから日常の生活が送れるのではなく、日常の生活を送れる環境が整っているからこそ健康に向かっていく。
そしてその環境は、手の込んだ人工的なものに頼らずとも、自然の力やうつろいを最大限に活かすことによって整えることができるのだ。「科学的な介護」に基づく環境設計には、そんな逆転の発想があるように思える。


ひとりひとりがもつ音を、ともに奏でるために
取材を終え、杜の家なりたをあとにする。たった数時間の取材にも関わらず、介護に対するイメージがすっかり変わってしまったように感じた。

「福祉楽団」という名前は、オーケストラに由来しているそうだ。福祉楽団のリクルート用の冊子で、飯田さんは、音楽家のダニエル・バレンボイムと批評家のエドワード・サイードの対談からこんな言葉を引用している。
民主的な社会に暮らす方法を学びたいのならば、オーケストラで演奏するのがよいだろう。オーケストラで演奏すれば、自分が先導するときと追従するときがわかるようになるからだ。他の人たちのために場所を残しながら、同時にまた自分自身の場所を主張することはいっこうにかまわない。
(『バレンボイム/サイード 音楽と社会』みすず書房、P236)「科学的な介護」の実践は、まず「相手の音をよく聴く」ことから始まる。飯田さんも言っていたように、介護のプロは利用者ひとりひとりが持つ音を聴き分ける耳を持っているのだ。そこで聴こえた音をもとに、介護する側は自身の音をチューニングしながら、利用者の持つ音を最大限引き出していく。そうした意味で、介護の仕事は音のセッションにも似ているように思える。
相手が秘める音の可能性に関心を向け、ともに奏でようと試みる、きわめて創造的な行為ということだ。

バレンボイムは本の中で、良いオーケストラの条件は「ひとりひとりの演奏者が、自分自身もそこに創造的に参画しているという感覚」を持つことだと述べている。これは、ナイチンゲールが『看護覚え書』で書いている「art of nursing(看護/介護の芸術性)」にも通じる考え方だろう。
音楽は指揮者がつくり出すものではない。音はオーケストラのひとりひとりの音楽家によってつくり出されるものだ。他の演奏者の思いをはかりつつ、追従したり、主張したり、互いに応じあうなかで曲を作ってゆく。そして、そこにこそ「おもしろさ」が宿るのではないだろうか。

このプロセスは、介護や音楽の領域をこえ、普遍的な人間関係にまで広がっていくはずだ。それはより良い社会をつくるための実践にほかならない。なぜなら、社会はそれぞれに異なる物語を生きる「わたし」と「あなた」の無数の関係によって成り立っているのだから。
福祉楽団の楽団員たちが奏でる音楽は、これからどんな調べを響かせるのだろう。帰り道、車窓に映る夕日に染まった街並みを眺めながら、そんなことを想像した。
Information
・”ケアするしごと”バー開催決定!「福祉楽団」奥住比沙子さんをゲストに迎え2024年12月13日(金)開催。詳細や申込はこちら
・anan webにて「介護の現場でかなえる、私らしい働き方」記事を公開中!リンクはこちら
・POPEYE webにて「福祉の現場を知りたくて。」記事を公開中!リンクはこちら
Profile
Profile
- ライター:椋本湧也
-
1994年、東京生まれ、京都在住。都内の出版社と家具メーカーでの仕事を経て、現在京都で出版社の立ち上げ準備中。書籍の編集や執筆、個人出版なども行う。著作に『26歳計画』『それでも変わらないもの』『日常をうたう〈8月15日の日記集〉』。
この記事の連載Series
連載:“自分らしく生きる”を支えるしごと
![]() vol. 322026.01.14本から「介護にあるまなざし」に出会う。編集者、ダンサー、美術家、介護職員の選ぶ4冊
vol. 322026.01.14本から「介護にあるまなざし」に出会う。編集者、ダンサー、美術家、介護職員の選ぶ4冊![]() vol. 312025.12.26「助けて」という言葉が必要になる前に。社会福祉法人丹緑会特別養護老人ホーム栗林荘をたずねて
vol. 312025.12.26「助けて」という言葉が必要になる前に。社会福祉法人丹緑会特別養護老人ホーム栗林荘をたずねて![]() vol. 302025.12.17いいチームってなんだろう? 多職種連携で「看取り」に取り組む特別養護老人ホーム「芦花ホーム」をたずねて
vol. 302025.12.17いいチームってなんだろう? 多職種連携で「看取り」に取り組む特別養護老人ホーム「芦花ホーム」をたずねて![]() vol. 292025.12.10一人ひとりの「あたり前」を大切にできる環境とは?「あたり前の暮らしサポートセンター布施屋」をたずねて
vol. 292025.12.10一人ひとりの「あたり前」を大切にできる環境とは?「あたり前の暮らしサポートセンター布施屋」をたずねて![]() vol. 282025.12.05安心して歳を重ねられる地域とは? 社会福祉法人くらしのハーモニーをたずねて
vol. 282025.12.05安心して歳を重ねられる地域とは? 社会福祉法人くらしのハーモニーをたずねて![]() vol. 272025.11.18「ケア」を感じたマンガを教えてください。作家、社会学者、アーティスト、福祉施設長の選ぶ4作品
vol. 272025.11.18「ケア」を感じたマンガを教えてください。作家、社会学者、アーティスト、福祉施設長の選ぶ4作品![]() vol. 262025.11.10「安心できる住まい」はどう育まれる? 特別養護老人ホーム「美里ヒルズ」をたずねて
vol. 262025.11.10「安心できる住まい」はどう育まれる? 特別養護老人ホーム「美里ヒルズ」をたずねて![]() vol. 252025.03.06地域の「居場所」ってなんだろう? 佛子園「三草二木 西圓寺」をたずねて
vol. 252025.03.06地域の「居場所」ってなんだろう? 佛子園「三草二木 西圓寺」をたずねて![]() vol. 242025.02.27幅広く使われる「ケア」をどうとらえる? 向坂くじらさん、吉田真一さんと考える
vol. 242025.02.27幅広く使われる「ケア」をどうとらえる? 向坂くじらさん、吉田真一さんと考える![]() vol. 232025.01.30本から「介護にあるまなざし」に出会う。イラストレーター、哲学者、ジャーナリスト、介護福祉士の選ぶ4冊
vol. 232025.01.30本から「介護にあるまなざし」に出会う。イラストレーター、哲学者、ジャーナリスト、介護福祉士の選ぶ4冊![]() vol. 222025.01.23地域の歴史や文化とともに歩む福祉とは? ライフの学校「六郷キャンパス」をたずねて
vol. 222025.01.23地域の歴史や文化とともに歩む福祉とは? ライフの学校「六郷キャンパス」をたずねて![]() vol. 212025.01.20多世代が一緒に過ごすことで生まれる安心とは?「深川えんみち」をたずねて
vol. 212025.01.20多世代が一緒に過ごすことで生まれる安心とは?「深川えんみち」をたずねて![]() vol. 202025.01.10アーティストが滞在する福祉施設とは? 「デイサービス楽らく」をたずねて
vol. 202025.01.10アーティストが滞在する福祉施設とは? 「デイサービス楽らく」をたずねて![]() vol. 192024.12.18「助けて」と言い合える環境を育むには? 「みんなの家 タブノキ」をたずねて
vol. 192024.12.18「助けて」と言い合える環境を育むには? 「みんなの家 タブノキ」をたずねて![]() vol. 182024.12.13私もあなたも、主人公でいられるように。「DAYS BLG! はちおうじ」をたずねて
vol. 182024.12.13私もあなたも、主人公でいられるように。「DAYS BLG! はちおうじ」をたずねて![]() vol. 172024.12.12「ケア」を感じたマンガを教えてください。組織開発コンサルタント、俳優、福祉施設所長、介護福祉士の選ぶ4作品
vol. 172024.12.12「ケア」を感じたマンガを教えてください。組織開発コンサルタント、俳優、福祉施設所長、介護福祉士の選ぶ4作品![]() vol. 162024.11.08安心して歳を重ねられる町とは? 鞆の浦・さくらホームをたずねて
vol. 162024.11.08安心して歳を重ねられる町とは? 鞆の浦・さくらホームをたずねて![]() vol. 152024.03.12介護のしごとに興味をもったとき、はじめの一歩はどうすれば?
vol. 152024.03.12介護のしごとに興味をもったとき、はじめの一歩はどうすれば?![]() vol. 142024.02.27認知症を“体験”する「VR認知症」。イシヅカユウさんと体験して気づいたこと
vol. 142024.02.27認知症を“体験”する「VR認知症」。イシヅカユウさんと体験して気づいたこと![]() vol. 132024.02.22認知症のある方100人以上にインタビューをして気づいたこと。認知症未来共創ハブ代表・堀田聰子さん
vol. 132024.02.22認知症のある方100人以上にインタビューをして気づいたこと。認知症未来共創ハブ代表・堀田聰子さん![]() vol. 122024.02.20暮らしのなかで閉じる命をつないでいく 写真家/訪問看護師 尾山直子さん
vol. 122024.02.20暮らしのなかで閉じる命をつないでいく 写真家/訪問看護師 尾山直子さん![]() vol. 102024.02.08「老いと共に生きる」を映画から考える。編集者、映画作家、介護福祉士、福祉施設運営者の選ぶ5作品
vol. 102024.02.08「老いと共に生きる」を映画から考える。編集者、映画作家、介護福祉士、福祉施設運営者の選ぶ5作品![]() vol. 092023.12.20居場所ってなんだろう? 人が自然と集まる場所を目指す「52間の縁側」をたずねて
vol. 092023.12.20居場所ってなんだろう? 人が自然と集まる場所を目指す「52間の縁側」をたずねて![]() vol. 082023.12.13「ケア」を感じたマンガを教えてください。文学研究者、精神科医、看護師、介護福祉士、文筆家の選ぶ5作品
vol. 082023.12.13「ケア」を感じたマンガを教えてください。文学研究者、精神科医、看護師、介護福祉士、文筆家の選ぶ5作品![]() vol. 072023.12.06自然の循環に身を委ね、大地と共に生きる。「里・つむぎ八幡平」が実践する「半農・半介護」の暮らし
vol. 072023.12.06自然の循環に身を委ね、大地と共に生きる。「里・つむぎ八幡平」が実践する「半農・半介護」の暮らし![]() vol. 062023.11.29介護施設×学生シェアハウス「みそのっこ」が教えてくれる、「介護×場づくり」の可能性
vol. 062023.11.29介護施設×学生シェアハウス「みそのっこ」が教えてくれる、「介護×場づくり」の可能性![]() vol. 052023.11.10いくつになっても「働く」は楽しい。ばあちゃんたちの生きがいとビジネスの両立を目指す、株式会社うきはの宝をたずねて
vol. 052023.11.10いくつになっても「働く」は楽しい。ばあちゃんたちの生きがいとビジネスの両立を目指す、株式会社うきはの宝をたずねて![]() vol. 042023.11.07居心地の良い場所の条件ってなんだろう? 浦安にある高齢者向けの住まい「銀木犀」をたずねて
vol. 042023.11.07居心地の良い場所の条件ってなんだろう? 浦安にある高齢者向けの住まい「銀木犀」をたずねて![]() vol. 032023.10.31ケアってなんだろう? ナイチンゲール看護研究所・金井一薫さんをたずねて
vol. 032023.10.31ケアってなんだろう? ナイチンゲール看護研究所・金井一薫さんをたずねて![]() vol. 022023.10.30さまざまな命に囲まれて、心を動かして生きる。 園芸療法を行う「晴耕雨読舎」をたずねて
vol. 022023.10.30さまざまな命に囲まれて、心を動かして生きる。 園芸療法を行う「晴耕雨読舎」をたずねて![]() vol. 012023.10.11自分らしく生きるってなんだろう? 一人ひとりの人生に向き合う介護事業所「あおいけあ」をたずねて
vol. 012023.10.11自分らしく生きるってなんだろう? 一人ひとりの人生に向き合う介護事業所「あおいけあ」をたずねて