記事一覧

vol.322025.03.18言葉を超えて誰もがつながる「身体表現」の魅力とは? 福祉を起点に広がるパフォーミングアーツ、生きづらさを変える可能性

vol.312024.10.09なぜ自分に価値があるか確認したくなるんだろう? 勅使川原真衣さんと新澤克憲さんによる「評価」を巡る対話
私たちはなぜこれほどまでに評価に振り回されてしまうのだろう?そもそも「評価」って何なのだろう?むやみに評価したりされない環境をつくるにはどうすればいいだろう?勅使川原真衣さんと新澤克憲さんと共に考えました。

vol.302024.09.13大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 写真家/訪問看護師 尾山直子さんをたずねて
いのちの終わりに向かっていく大切な人の変化と、どう向き合っていけばいいのか。本人の気持ちを尊重しながら、残された時間をともに穏やかに過ごすためには、何ができるのか。訪問看護師・写真家の尾山直子さんに伺いました。

vol.292024.09.07地域に根ざす園から、子どもも大人も混ざった“絶景“を生み出せたら。〈学校法人thanka〉が新ステートメント「手を繋ぎにいく」に込めた願い
思い思いに遊ぶ子どもたちが、テラスや園庭、部屋に散っている「のだのこども園」。50年近い歴史があり、地域の要請にあわせて拡大を続けてきた「野田北部幼稚園」。隣り合う2園を運営する〈学校法人加藤学園〉は、2025年に〈学校法人thanka〉へ法人名やロゴサインを刷新、大きな転機を迎えようとしている。学校法人が、乳幼児の保育や障害福祉までを担うようになった背景には何があるのか? 新たなステートメント「手を繋ぎにいく」を掲げ、地域でどのような存在を目指そうとしているのか? 過去の理念や教育目標を引き継ぎながら、リブランディングに試行錯誤してきた理事長の加藤裕希さん、そのパートナーとして並走してきたデザイナー/アートディレクターの小田雄太さんにお話を伺った。

vol.282024.08.30大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 株式会社Blanket 秋本可愛さんをたずねて
大切な人の変化に戸惑ったとき、自分はいったいどう向き合っていけばいいのだろう? そして誰を、どんなタイミングで頼ればいいのだろう?株式会社Blanket秋本可愛さんに話を伺いました。

vol.272024.07.25気軽な買い物体験から、「未来が良くなる」手応えを。〈フェリシモ〉の新カタログ『GO! PEACE!』制作の裏側
大手通販の〈フェリシモ〉が、2023年、原点回帰とも呼べるカタログ『GO! PEACE!』を制作。「みんなで『うれしい未来』をつくるカタログ」をテーマに、お買い物を通じて気軽に他の誰かをしあわせにできるような商品を集め、世の中に提案しています。事業活動をしながら社会文化活動を進めてきたトップランナーは今何を考えているのか、兵庫県神戸市の本社を訪ねました。

vol.262024.04.30蓋された「小さな自分」の声に耳を傾けて。ケアを促す料理レッスンの場、就労支援の場──山口祐加さん×鞍田愛希子さん
“ちゃんと”働かなくては。“きちんと”料理をしなきゃ。日常的に私たちを取り巻く呪いや罪悪感に対して、どうケアをしていけばいいのか、自炊料理家の山口祐加さんと、障害のある方々の就労支援をする一般社団法人Atelier Michauxの鞍田愛希子さんに対談いただきました。場所は福祉施設「ムジナの庭」(東京都小金井市)にて。

vol.252024.04.10「インクルーシブ」は誰のための言葉? 老舗メーカー〈ジャクエツ〉×医師・紅谷浩之さんの、子どもに“遊びと友だち“を返す遊具
“インクルーシブ”という言葉が注目されるなか、創業100年を超える遊具メーカー〈ジャクエツ〉は2022年、さまざまな特性のある子どもたちが一緒に遊べる遊具シリーズ「RESILIENCE PLAYGROUND」を発売。この遊具がどのように生まれたのか、JAKUETS本社工場をたずね、デザイナーである田嶋宏行さんと、遊具を監修した、〈医療法人社団オレンジ〉理事長で医師の紅谷浩之さんにお話を伺いました。

vol.242024.03.29文化施設のウェブアクセシビリティを向上する。障害当事者との「建設的な対話」に必要なこととは?──伊敷政英さん×森司さん
キーワードは、異なる特性を持つ人どうしが一つのプロジェクト進める際に欠かせない「建設的な対話」。障害者専門のクラウドソーシングサービス「サニーバンク」のアドバイザーとしてプロジェクトに伴走してきた、先天性の視覚障害当事者でもある伊敷政英さんと、CWT・森司さんによる対談をお届けします。

vol.232024.03.27だれもが文化でつながるために。クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョーが見据えるこれからの文化施設のあり方とは。
だれもが文化施設やアートプログラムと出会えるように、芸術文化へのアクセシビリティ向上に取り組むプロジェクト「Creative Well-being Tokyo /クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョー」(以下「CWT」)。このプロジェクトを統括する、公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京 事業部事業調整課長の森司(もり・つかさ)さんに、この取り組みの背景や意義について話を伺った。

vol.222023.12.22人のためってなんだろう? 他者にコントロールされない「LOVOT」から、“人間らしさ“を考える──伊藤亜紗さん×林要さん
最近よく聞く「利他」って、一体どういうこと? そんな疑問を携えて実現した、空気を読まないのに愛されるロボット「LOVOT」の開発者〈GROOVE X株式会社〉代表取締役社長の林要さんと、〈東京工業大学・未来の人類研究センター〉で「利他学」を立ち上げた伊藤亜紗さんの対談。2人の著書『「利他」とは何か』『温かいテクノロジー』も参照しながら、私たちが誰かと共に生きるとき大事にしたい視点を一緒に考えました。

vol.212023.11.08保育料ゼロを実現し、子育てを“みん営化”する。 学童保育施設〈fork toyama〉岡山史興さん

vol.202023.05.29ともだちってなんだろう? 答えを出す必要はないけれど。新澤克憲さんとテンギョー・クラさんの対話から考える
ともだちってなんだろう? そんな問いを真ん中に置いて、”ふしぎな声が聞こえたり、譲れない確信があったり、気持ちがふさぎ込んだり。様々な心の不調や日々の生活に苦労している人たちの集いの場”「ハーモニー」の新澤克憲さんと、さまざまな地域を転々としながら暮らすヴァガボンドのテンギョー・クラさんに対話いただきました。

vol.192023.05.23歌人・岡本真帆さん×西淡路希望の家・金武啓子さん対談。「感動」の発見、どう他者と分かち合いますか?
20〜30代を中心に広がりを見せている「短歌」。注目される歌人「まほぴ」こと、岡本真帆さんは、ふとした日常の一コマや感情の移ろいを言葉にしたり、誰かの「思い」に共感したりすることをどう捉えているのでしょうか。障害のある人の表現を、驚きある雑貨や作品にする大阪市東淀川区の生活介護事業所〈西淡路希望の家〉を共に訪ね、美術スタッフの金武啓子さんと対談いただきました。

vol.182023.03.20“みる”から始める、アーティストと支援現場のつなぎ役。日常の関係性を変える「TURN LAND プログラム」の挑戦
異分野の協働プロジェクトの現場には、そのあいだをつなぎ、活動の意義を言葉にする存在が鍵となる。2022年に再始動した「TURN LAND プログラム」(主催:〈東京都〉〈公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京〉〈一般社団法人 谷中のおかって〉)で実際に「コーディネーター」を務める加藤未礼さん、竹丸草子さん、富塚絵美さんの3人にお集まりいただき、その育成のポイント、スタートしたばかりのプログラムの意義について伺いました(後編)。

vol.172023.03.15アート活動で、「できる/できない」を揺さぶる。日常の価値を言葉に変えるコーディネーターの役割
合理的な行動が重視されたり、経済的な生産性が求められたりする社会のなかで、これまでになく注目の集まる「アート」。どうすれば人が「よりよく生きる」ことができるかを考え、価値観そのものを見つめ直そうとするその活動の意義について、コミュニケーションデザイナーの加藤未礼さん、プロジェクトプランナーとして多くのワークショップを営む竹丸草子さん、アーティストでありアートディレクターとしても活動する富塚絵美さんにお話いただきました(前編)。3人は、福祉事業所やコミュニティがアートプロジェクトを日常的に生む“拠点”となることを目指す、「TURN LAND プログラム」(主催:〈東京都〉〈公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京〉〈一般社団法人 谷中のおかって〉)のコーディネーターを務めています。

vol.162023.03.03唯一の答えを探しすぎていないか? 下地ローレンス吉孝さん×なみちえさんと“わかりやすさ”について考える
人の複雑さや多面性、そして流動性を、私たちはどうすれば尊重することができるのだろうか? 『「ハーフ」ってなんだろう?――あなたと考えたいイメージと現実』(平凡社)の著者である下地ローレンス吉孝さんとアーティストのなみちえさんのお二人に対談いただいた。

vol.152023.02.15“わたし”と“あなた”それぞれの複雑さを大切にするには?──なみちえさん×下地ローレンス吉孝さんと共に考える
人の複雑さや多面性、そして流動性を、私たちはどうすれば尊重することができるのだろうか? アーティストのなみちえさんと『「ハーフ」ってなんだろう?――あなたと考えたいイメージと現実』(平凡社)の著者である下地ローレンス吉孝さんのお二人に対談いただいた。

vol.142022.12.23出会いを広げながら、協働を生む「メディア」を目指して──〈こここ〉シーズン2を振り返る
「個と個で一緒にできること」を合言葉に、さまざまな福祉施設や専門家、クリエイティブなアイテム、活動などをたずねるウェブマガジン〈こここ〉。2021年4月の創刊から1年8カ月が経つなかで、撒いた種の育ちを少しずつ実感した“シーズン2”の取材や記事について、編集部が座談会という形で振り返りました。

vol.132022.12.19働くことも、映画祭も「みんなが心地よい」を目指して。GOOD NEWSとTHEATRE for ALLのインクルーシブな場づくり
森や小川などの自然が溢れる複合施設GOOD NEWS。カフェやギャラリーが集まるその一角で開催された「まるっとみんなで映画祭 2022 in NASU」を振り返りながら、主催するTHEATRE for ALLの統括ディレクター・金森香さんと、GOOD NEWS FACTORYでサービス管理責任者を務める小宅泰恵さんが対談しました。劇場での体験づくりと就労支援という、異なる環境で活動する二人が、多様な人々が同じ空間を共有することについて言葉を交わしていきます。

vol.122022.10.14バリアフリーの映画祭を通して、「その人のまま」でいられる社会に。作家・川内有緒さん×THEATRE for ALL・金森香さん
動画配信サービス「THEATRE for ALL」で開催されている「まるっとみんなで映画祭 2022」。11月5日から始まる那須でのリアル上映会を前に、長編映画『目の見えない白鳥さん、アートを見にいく』(2023年に劇場公開)の共同監督・川内有緒さんと、映画祭を運営する株式会社precog・金森香さんが対談しました。「作家」と「場のつくり手」それぞれの立場から、作品の伝え方の試行錯誤や、鑑賞の“選択肢”が生む豊かさについて話を交わしています。

vol.112022.09.13スポーツの可能性って何だろう? 「プロスポーツ」「ゆるスポーツ」から考える──岡田武史さん×澤田智洋さん
「え、すごい。岡田さんが一番ですね!」モニター越しにそう盛り上がったのは、元サッカー日本代表監督の岡田武史さん、〈世界ゆるスポーツ協会〉代表の澤田智洋さん、そして〈こここ〉編集部メンバー。プレイしているのは、オンライン会議ツール上で行う「ARゆるスポーツ」だ。立場もキャリアも異なりながら、「スポーツ」を起点に人と人をつなごうとするお二人に対談いただき、今この時代におけるスポーツの可能性についてじっくりと語ってもらった。

vol.102022.03.31まだみぬ「表現」との出会いを、誰もが体験できる社会へ。障害のある人の芸術・文化活動を支える窓口が全国に
意思や感情を誰かに伝える「表現」という行為は、人の営みの根底にある。伸びやかな表現ができる状況に身を置くことで、私たちはいきいきとした状態でいることができる。「誰もがよりよく生きられる社会のために、多様な人の表現活動を支えたい」。そんな願いを持ち、全国に支援のネットワークを形成している『障害者芸術文化活動普及支援事業』について、〈厚生労働省〉と連携事務局の方々にお話を聞いた。
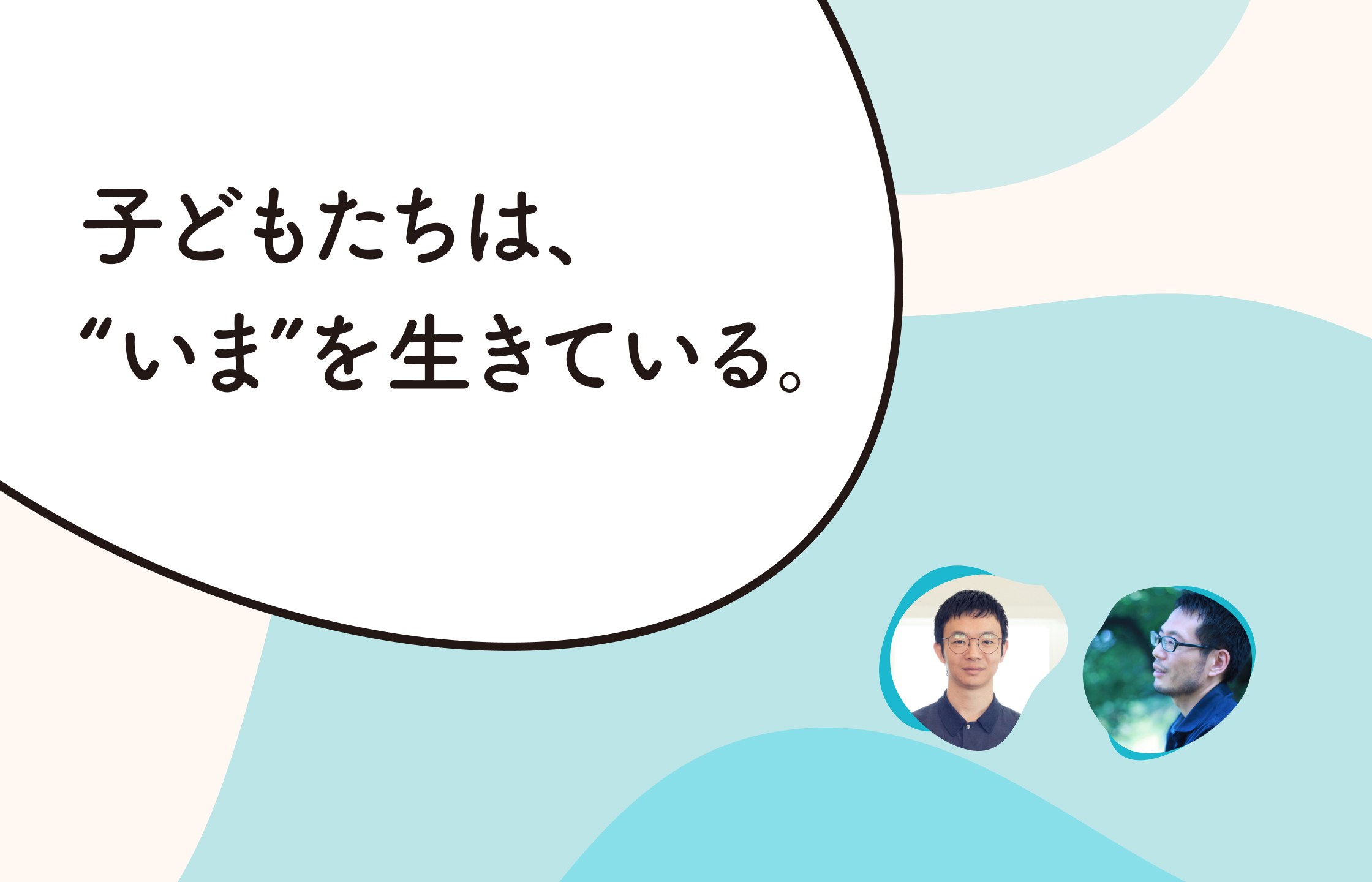
vol.092022.02.09コロナ禍で「消される」声に、どう耳を傾ける? 次の社会をつくる言葉と対話のあり方──荒井裕樹さん×青山誠さん
「私たちの社会は、みんなで支え合う生態系として成り立っているはずです。でも、このコロナ禍で『社会のために』と我慢を強いられてきたのは、結局弱い立場の人ばかりでした。」そう話すのは、『まとまらない言葉を生きる』の著者、荒井裕樹さん。荒井さんにとってコロナ禍で起きた急激な環境の変化は、当たり前に使っていた言葉を「それってそもそも何のことだっけ?」と問い直す連続だったと言います。そして、荒井さんと同じことを「保育」という現場で抱えてきたのが〈上町しぜんの国保育園〉の青山誠さんでした。お二人に対話していただくことで、この社会で今起きている変化や、ほころびが浮かび上がってくるのではないか。胸の中に抱く想いを共有していただきながら、私たちも一緒に考えていくことにしました。

vol.082021.12.24福祉をたずねて1年。編集部は何に出会い、悩んできた?──〈こここ〉振り返り座談会
2021年に創刊した、福祉をたずねるクリエイティブマガジン〈こここ〉。「個と個で一緒にできること」を合言葉に、さまざまな福祉施設、専門家、福祉にまつわるアイテム、活動などをたずね始めておよそ1年(メディアが世に公開されてからは8カ月)が経とうとしています。今も日々夢中で企画に向き合うなか、公開した記事数は早くも150以上に。そこで「印象深かった取材や企画を一度振り返ってみようか」と、年の瀬が迫る2021年12月某日、座談会を行うことにしました。

vol.072021.11.24コロナ禍を経て新たな表現の協働へ ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[後編]
小茂根福祉園で《風くらげ》《みーらいらい》といった表現活動を生み出した大西さんは、利用者さんによる新たな「ダンス」を開発。その名も《「お」ダンス》。その活動を広げていこうとした矢先、コロナ禍に見舞われます。

vol.062021.11.24アートプロジェクトは福祉の現場で何を生み出す? ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[前編]
「アーティストと私たち小茂根福祉園で、どんな関わりが育めるんだろう?」戸惑いを抱きながらも、アーティストを迎え入れ、6年という時間をかけて関係を築き、ともに表現を生み出していった福祉施設があります。

vol.052021.10.18福祉施設が学びあいの拠点になることで育まれるものとは?ライフの学校・田中伸弥さん
「施設を利用する人々(ライフの学校では利用者という言葉は使わず『パートナー』と呼ぶ)や、そのケアに関わる人々の人生が豊かであるためには、福祉施設を地域に“ひらいて”いく必要があると思います」「ライフの学校」の理事長を務める田中伸弥さんは語る。地域にひらかれた福祉を実現するためにはなにが必要なのか。そして、そのひらかれた場を通じてなにが生まれているのか。田中さんに、これまでの取り組みについてのお話を伺った。

vol.042021.06.03VR認知症を体験して気づいた、わからない世界へ手を伸ばし続ける大切さ。シルバーウッド 下河原忠道さん
既に持つ知識を基準に他者をラベリングして、わかったつもりになってしまうことがある。どうすれば知識を学ぶだけではこぼれおちてしまう「なにか」を大切にできるのだろう?

vol.032021.04.15まだ名付けられていない感覚に出会う「遊び」の可能性とは? インタープリター 和田夏実さん
現代を生きる私たちは、すでに「わかりやすく」「便利な」言語コミュニケーションに慣れきってしまっている。巷にあふれるコピーから気軽に送れるメッセージサービスまで、「言葉」を軸にした営みの数々。そのなかで、人が生まれながらに持つ感覚をどうすれば大切にできるのだろう。

vol.022021.04.15「助けて」とお互いに言い合えるのが、成熟した社会。ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ代表 志村季世恵さん
自分自身がいま困っていることを抱え込むんじゃなくシェアできるのが大人であって、本来の意味での成熟なんだろうな、と。だから、助け合うことに対して「お互いさま」と思えるのが成熟した個人・成熟した社会なんですよね。

vol.012021.04.15「お笑い」や「演劇」は他者の世界に寄り添うヒントをくれる。りんたろー。さん×菅原直樹さんが語る「介護の話」
介護の現場で8年間働いた経験を持つ、お笑いコンビ『EXIT』のりんたろー。さんと劇団『OiBokkeShi』代表の菅原直樹さん。お二人に介護経験のなかで感じてきたこと、介護とお笑い、演劇の関わりについて語っていただきました。

