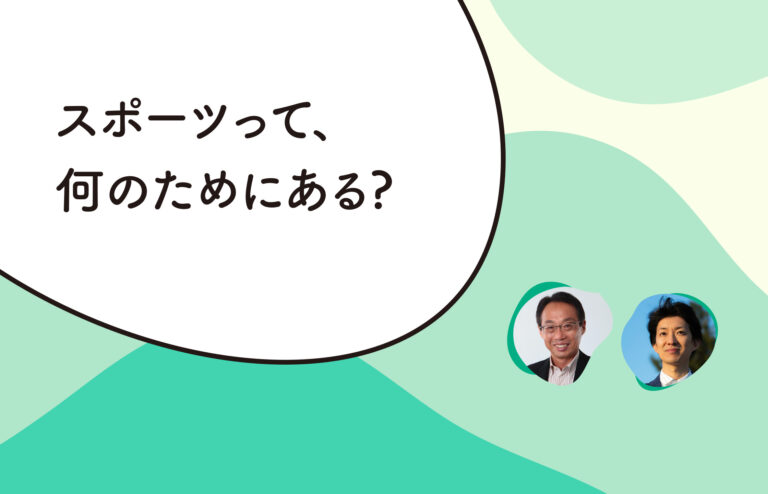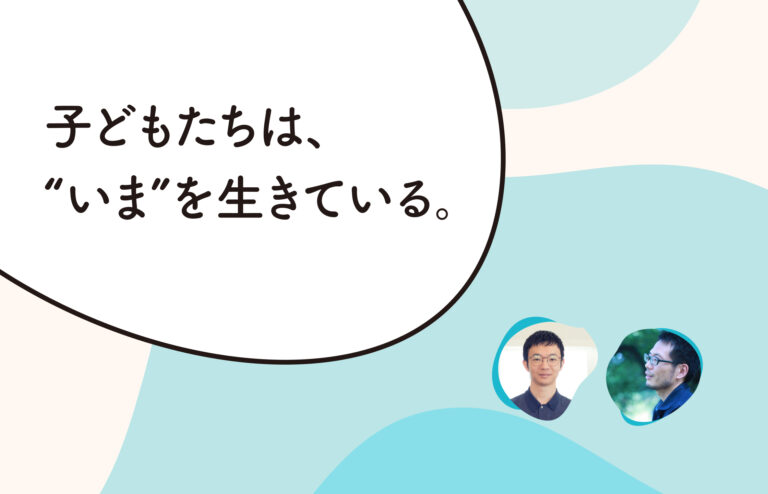まだ名付けられていない感覚に出会う「遊び」の可能性とは? インタープリター 和田夏実さん こここインタビュー vol.03
たとえば、まだ「言葉」を持たない子どもと接するとき。大人はさまざまな「言葉以外」のもの——表情、まなざし、声の響き、手や体全体のしぐさ——から、相手の個性や感情などを読み取っていく。
そこで気づくのは、世界を共有するための手段が本来、とても多様であることだ。だから、大人は子どもに対して「早く言葉を覚えてほしいな」などと思う傍らで、成長しても「今の豊かな表現を失ってほしくない」などと考えたりする。
だが、現代を生きる私たちは、すでに「わかりやすく」「便利な」言語コミュニケーションに慣れきってしまっている。巷にあふれるコピーから気軽に送れるメッセージサービスまで、「言葉」を軸にした営みの数々。そのなかで、人が生まれながらに持つ感覚をどうすれば大切にできるのだろう。
一人ひとりの異なる背景に思いを寄せることが、難しくなっている今、私は「遊び」を通じたコミュニケーションから、その人らしさに触れたいと思うんです。
そう話してくれたのは、インタープリター(解釈者)として活躍する和田夏実さんだ。和田さんはデザインやテクノロジーを活用し、さまざまな身体性の方々との協働から、それぞれの「感覚」に潜む可能性について模索している。
人が本来持つ感覚を研ぎ澄ませ、新たな形で他者に共有できれば、世界はより豊かになるのではないか。そう考える和田さんと共に、それぞれの感覚を発見することや一人ひとりの意識、身体の違いについて思いを巡らせました。
違うもの同士の境界をまぜ合わせてく“解釈者”として
ろう者のご両親のもと、「手話を第一言語に育った」という和田さん。さまざまな身体性を持つ方々と一緒に、多くの研究プロジェクトやメディアアート作品を手掛けてきた。 たとえば、手話表現を拡張させた『Visual Creole(ビジュアル・クレオール)』。伝えたいことを手で表現し、目で理解してもらうための視覚言語作成・習得ツールになっている。
『an image of』(企画制作:南雲麻衣+和田夏実、筧康明)は記憶と想像力をテーマにした実験映像作品だ。

また、誰でも手に入れられるコミュニケーションゲームの制作も和田さんが携わる活動の一つだ。例を挙げると、「つながる」という会話手法を楽しめる『LINKAGE』(制作:たばたはやと+magnet)。盲ろう者が主に使うコミュニケーション方法「触手話」の感覚から育まれたゲームだ。
視覚・聴覚、触覚など人の感覚を問い直し、新たな共有方法を育んでいる和田さんは、自らの肩書きを「インタープリター」と名乗っている。多岐に渡る活動を貫く言葉として、“通訳者”や“翻訳者”ではなく、あえて“解釈者”を選んだ。
私がやりたいのは、そもそも違うもの同士の境界をまぜ合わせてくことです。さまざまな身体性を持つ方々と一緒に、メディアとメディアの間、感覚と感覚の間に入り込んで、幅を持たせたインタープリート(解釈)をしていく。“解釈者”という余白感のある言葉が、自分のスタンスを示す意味で、とてもしっくりきています。

感覚を追求した先に「まだ見ぬ世界」が潜む
幼い頃から、「知らない世界に出会いたい」と好奇心が旺盛だった和田さん。その興味が感覚を通じた「境界の混ぜ合わせ」に向いたのは、手話を扱う両親からの影響が大きかった。たとえば、自分がいる部屋を星空に見立て、そこに手を重ねて5本の指を自由に泳がせる“星空の遊泳”などの遊びをよくやっていたという。

頭のなかにあるイメージを視覚的に映し出していった経験は、そのまま「音声言語に限らないコミュニケーション方法」の豊かさを信じる、原点となっている。
ろう者も聴者も、さまざまな言語を持つ人が世界中からうちにホームステイに訪れていたことも、原体験の一つになっています。お互いに使う言語が異なる場合でも、互いの国の文化を「踊りはこうで、焚き火があって、周りに人がいて……」と、手を使いながら視覚的に伝え合っていました。
だからか、逆に「音声言語」を起点にした声や文字だけで語り合うことを、もったいない行為のように感じてしまったんです。手話に限らず、表現の特性や表せる範囲の差によって、もっと気軽にメディアを選択できたらいいのにと思っていました。

そんな和田さんが大学で出会ったのが、メディアアートだ。たとえば、アーティストの三上晴子さんが手掛けたインスタレーション作品『欲望のコード』。既存の音声言語に頼らず、ほかの感覚を研ぎ澄ましていくことで新たな感覚世界を発見でき、それを他者とも共有していける可能性を感じたという。
また、先端のメディア表現やテクノロジーのなかだけでなく、ビジュアル・コミュニケーションの歴史を辿る過程でも、自分が「この感覚知っているかも」と思える表現に出会うことがありました。
1920年代にオットー・ノイラートらが開発した視覚記号の「アイソタイプ」は、言葉は違えど私の家で行なわれていた、ホームステイに来ていた方々とのコミュニケーションに近い。同じように、手をフォークに、刷毛を髪の毛に見立てるブルーノ・ムナーリの観察手法も、幼い頃やっていた父との手話遊びにつながるものだと感じたんです。

実際にメディアアートの研究を進めて気づいたのは、「人の感覚」を探求したプロジェクトや製品が想像以上に少ないことだった。特に不足していると感じたのは、マイノリティに関わる研究だ。仮にあっても、障害者がいわゆる健常者の世界に近づくことをゴールにした「マイナスをゼロに戻す」ような事例が多かった。
でも、私はマイノリティと呼ばれる方々の感覚に、まだ見えていない世界が潜んでいるという感覚がありました。まだ誰も踏んでいない、真っ白な雪の積もる大地が広がっているはず。そこを一つずつ探索してみたいと感じたんです。
もしそれを共有できたら、一人ひとりの世界をより豊かにするための表現や、多様性を持ちながらもみんなで楽しむための方法が見つかるかもしれない。そのためにも、従来の“足りない”を補うアプローチだけではなく、今ある状態をさらに深めていく研究をしたいと思いました。
美しさのありかを、「揺らぎながら」一緒に探る

手話表現にとどまらず、人の感覚の探求に強い興味を抱く和田さんは、視覚や聴覚に障害のあるクリエイターと一緒に、新たな感覚共有のあり方を探っている。最終的なアウトプットの形は、プロジェクトのパートナーとなるクリエイター「個人」の感覚・感性を信じ、一緒に時間を過ごすなかで、模索するという。
最初は単純に遊びに行ったり、買い物したりしながら、「この感覚って素敵だな」と思えるポイントを探っていくんです。たとえば全盲のゲームクリエイター野澤幸男くんとは、お店にあるアクセサリーから彼が一番良いと思うものを選んでもらう……なんてことをしていました。
すると彼は見た目じゃなく、触って感じた形のおもしろさでイヤリングを選んでくれる。その瞬間にふたりの間だけで取り決めされた「隠れた価値」が生まれる。そのあり方が、セクシーで美しいなと私は思うんです。
自分にとって新しい感覚に出会う方法は他にもたくさんあって、町のなかで目に入るものをどんどん名付けてみる実験をしてみたり、すれ違う人の髪型だけに注目して、ひたすら髪型の種類を集めていくようなことを繰り返したり。
一緒に時間を過ごし、その人の暮らしを知るなかで、原石を日々発見し集めていくイメージです。そのなかから、「これを磨いていこう」と一緒に選んだときが、実際のプロジェクトのスタートになります。

どのプロジェクトも「これで完成」と思える状態に至ることはなく、試作とテストを延々と何年も繰り返している。その意味で、明確なゴールから逆算していく制作過程と、原石を一緒に磨きながらの作品づくりは「まったく別物」だと和田さんは語る。
「誰かの頭のなかに出来あがっている創造性」をそのまま具現化していくことにも、もちろん美しさは宿ります。ただ、私たちがやっているのは、個人がもともと持つ「原石そのもの」を外に出して共有し、時間をかけて一緒に磨いていくこと。
一人が決めた美しさに従うのではなく、どこに美しさがあるのか、その場で揺らぎながら一緒に探っていきたいと思っているんです。実際、やってみては作り直すサイクルを重ねるなかで、角ばっていた原石がだんだん丸くなり、磨かれた美しい宝石になっていく感覚があります。
このとき大事なのは、できるだけその人の感覚に委ね、委ねた自分を信じること。そのために、必要以上に想像しないことを心がけています。
もちろん、目の見える私たちが、「目の見えない方ってこうなんじゃないかな……」と配慮することは大切なプロセスだと思います。でも一方で、そこでの想像が的を射たことって、私の経験ではあまりなくて。
「他者への想像は、良くも悪くもノイズになる」前提を持ってインタープリートしていくことが、新たな感覚を発見するためにはとても大事じゃないかなと思っています。

さらに和田さんは、原石を磨く手段として、ここでも音や触り心地などなるべく「言葉以外」のメディアを使うことを意識している。言葉は誰もが扱えるからこそ、解釈の幅も実は広い。それを単純にやり取りするだけでは、新しい感覚には辿り着けないと和田さんは考える。
私が言葉に対して持つイメージは「からっぽの箱」なんです。たとえば、“切ない”という言葉の箱があったとして、そのなかに実際入っている感情のかけらは人それぞれ違うと思うんですね。
言葉だけで会話をすると、互いのその箱をただ渡し合うだけになってしまう気がしていて。そうではなく、どの箱に入れるものかはよくわからないけれど、その断片をお互いに触り合いながら、「これは確かかも」と思える場所を見つけられるといいなと思っているんです。
“遊び”から他者の内側にある宇宙に出会う
和田さんにとって、感覚の探究と共有を模索するなかでたどり着いたもう一つの形がコミュニケーションゲーム開発だ。
冒頭で紹介したLINKAGE、顔や手や体でお互いの頭のなかを伝え合う『Shape it!』(制作:異言語Lab.)、カードを通じて個人のフェティシズムなどが見えてくる『Qua|ia(クオリア)』(制作:mmm + LOUD AIR)などがすでに発表されている。前述のようなプロセスを経て開発したものもあれば、思わぬ「遊び」から生まれたものもあるという。
Qua|iaは、ある展示会用の資料をつくっていたときにたまたま、モデルさんの写真で“肘”だけがフォーカスされた瞬間があったんです。それが、なぜだかわからないけど良かったんですよ。
試しにいろんな人が「なぜか惹かれる」写真を集めてポストカードをつくってみると、やっぱりよくて。たとえうまく言語化ができなくても、それぞれがなぜかいいと思うものってあるんですね。そうした感覚に触れ合う一つの方法として、カードゲームという形にしていきました。

寄せられた写真やエピソードから“その人らしさ”を感じていく過程は、閉じていた心の扉を開けてしまうような不思議な感覚があった。個人の嗜好といった「うまく言語化できない」感覚には、人が人を知るためのきっかけが現れやすい。和田さんは、これまでにもさまざまな試みを行なっていた。
一時期よく、「なまえのない遊び」という実験をしていました。子どもの頃やっていた、名付けるほどでもない小さな遊びをいろんな人に聞いていくんです。すると、「家の前に電柱が3本あって、1本目と2本目の間は海だから渡れなくて……って決めて歩いてたんだよね」なんて話が出てくる。
その遊びをしている子どもの頃を想像すると、どんな相手でも「ええ!かわいい」ってすぐ好きになれちゃうんですね(笑)。

「なまえのない遊び」を聞くと、普段は共有される機会のない、それぞれの遊びの文化に出会う。和田さんはそこに可能性や魅力を感じるという。
身体性の違いによって、それぞれ特有の感覚があります。遊びの文化も違うんですね。
目の見えない友人は、部屋のなかでボールを投げ、跳ね返り方やぶつかる音の響きから空間の広さを想像していたことを。また、肢体不自由で先天的に手のない方に話を聞くと、牛乳パックに腕を差し込んで腕をのばして遊んでいたことを教えてくれました。
何千何万とあったはずの遊びから思い出されるものには、今の自分を形成している何かがある。昔と今とがぎゅっと接続されることで、その人の内側に広がる宇宙に近づける気がするんです。
小さなことから、新たな関係性の構築は始まる

実は「願わくは子どものように遊んでいたい」って考えている人って多いと思うんです。でも社会通念のなかでは関係性やルールが固定化され、それぞれ異なる背景を持っていることにまで思いを寄せながらコミュニケーションを取ることが、難しくなっている。
そんな状況下で人と人とが楽しく共にいるために、ズラしをうみ、その人らしさに出会うという意味で「遊ぶこと」に価値があるんじゃないかと思うんですね。遊びであれば、誰もが簡単にゴールを設定でき、かつ勝ち負けの矢印をちょっとしたルール変更で180°変えてしまうこともできます。
硬直した前提をちょっと“ズラす”ことで、相手の意外な一面をのぞき見る。そのとき和田さんが大切にしたいのは、まだ名付けられていない感覚を伴う遊びだ。言葉の利便性に頼り過ぎてしまうと、ズレたことでせっかく見えた片鱗も、再び厳密な定義に埋もれかねない。
もちろん、短歌や詩など余白がある言葉もたくさんあります。ただ、世界にはまだまだ私たちが知らない感覚が眠っている。
それぞれの身体が持つ感覚をヒントにすれば、一人ひとりが大事にしているものを「大事にしたまま」つながれる、新しいコミュニケーションができるかもしれません。そんな誰も見たことのない景色に、私は出会いたいと思っています。

「言葉」の外にある感覚に目を向け、関係性を楽しく“ズラす”。そのためにできることは、日常のなかでもたくさんあるという。今日は片仮名メインでコミュニケーションのトーンを変えてみる、逆の手で箸を使って違う身体の使い方をしてみる、あるいは近しい人と毎日1回ハグをしてみる——ほんの小さなことから、新たな関係性の構築は始まると和田さんは語る。
そこには「誰が対象だから尊い」といった上下の関係は一切ありません。ともに日々を過ごす人、隣に今いる人、電車で出会った人……すべての人たちのなかに見えない宇宙が広がっている。
私自身、家族のことすら「全然知らないんだな」ってしょっちゅう気づかされます。一緒に遊びながら、たまにそこに触れることができたら、すごくいいなと私は思うんです。

Profile
![]()
-
和田夏実
インタープリター
1993年生まれ。ろう者の両親のもとで手話を第一言語として育ち,大学進学時にあらためて手で表現することの可能性に惹かれる。視覚身体言語の研究、様々な身体性の方々との協働から感覚がもつメディアの可能性について模索している。近年は、LOUD AIRと共同で感覚を探るカードゲーム”Qua|ia”(2018)やたばたはやと+magnetとして触手話をもとにした繋がるコミュニケーションゲーム”LINKAGE”、”たっちまっち”(2019)など、ことばと感覚の翻訳方法を探るゲームやプロジェクトを展開。アーティスト南雲麻衣とプログラマー児玉英之とともにSignedとして視覚身体言語を研究・表現する実験、美術館でワークショップなどを行う。2016年手話通訳士資格取得。2017-2018年ICC インターコミュニケーションセンター emergencies!033 “tacit crelole / 結んでひらいて”。
- ライター:佐々木 将史
-
1983年生まれ。編集者。保育・幼児教育の出版社に10年勤め、’17に滋賀へ移住。保育・福祉をベースに、さまざまな領域での情報発信、広報、経営者の専属編集業などを行う。個人向けのインタビューサービス「このひより」の共同代表。保育士で4児(双子×双子)の父。2021年8月よりこここ編集部に参画、以降は執筆ではなく主に企画・編集側を担当。
この記事の連載Series
連載:こここインタビュー
![]() vol. 322025.03.18言葉を超えて誰もがつながる「身体表現」の魅力とは? 福祉を起点に広がるパフォーミングアーツ、生きづらさを変える可能性
vol. 322025.03.18言葉を超えて誰もがつながる「身体表現」の魅力とは? 福祉を起点に広がるパフォーミングアーツ、生きづらさを変える可能性![]() vol. 312024.10.09なぜ自分に価値があるか確認したくなるんだろう? 勅使川原真衣さんと新澤克憲さんによる「評価」を巡る対話
vol. 312024.10.09なぜ自分に価値があるか確認したくなるんだろう? 勅使川原真衣さんと新澤克憲さんによる「評価」を巡る対話![]() vol. 302024.09.13大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 写真家/訪問看護師 尾山直子さんをたずねて
vol. 302024.09.13大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 写真家/訪問看護師 尾山直子さんをたずねて![]() vol. 292024.09.07地域に根ざす園から、子どもも大人も混ざった“絶景“を生み出せたら。〈学校法人thanka〉が新ステートメント「手を繋ぎにいく」に込めた願い
vol. 292024.09.07地域に根ざす園から、子どもも大人も混ざった“絶景“を生み出せたら。〈学校法人thanka〉が新ステートメント「手を繋ぎにいく」に込めた願い![]() vol. 282024.08.30大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 株式会社Blanket 秋本可愛さんをたずねて
vol. 282024.08.30大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 株式会社Blanket 秋本可愛さんをたずねて![]() vol. 272024.07.25気軽な買い物体験から、「未来が良くなる」手応えを。〈フェリシモ〉の新カタログ『GO! PEACE!』制作の裏側
vol. 272024.07.25気軽な買い物体験から、「未来が良くなる」手応えを。〈フェリシモ〉の新カタログ『GO! PEACE!』制作の裏側![]() vol. 262024.04.30蓋された「小さな自分」の声に耳を傾けて。ケアを促す料理レッスンの場、就労支援の場──山口祐加さん×鞍田愛希子さん
vol. 262024.04.30蓋された「小さな自分」の声に耳を傾けて。ケアを促す料理レッスンの場、就労支援の場──山口祐加さん×鞍田愛希子さん![]() vol. 252024.04.10「インクルーシブ」は誰のための言葉? 老舗メーカー〈ジャクエツ〉×医師・紅谷浩之さんの、子どもに“遊びと友だち“を返す遊具
vol. 252024.04.10「インクルーシブ」は誰のための言葉? 老舗メーカー〈ジャクエツ〉×医師・紅谷浩之さんの、子どもに“遊びと友だち“を返す遊具![]() vol. 242024.03.29文化施設のウェブアクセシビリティを向上する。障害当事者との「建設的な対話」に必要なこととは?──伊敷政英さん×森司さん
vol. 242024.03.29文化施設のウェブアクセシビリティを向上する。障害当事者との「建設的な対話」に必要なこととは?──伊敷政英さん×森司さん![]() vol. 232024.03.27だれもが文化でつながるために。クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョーが見据えるこれからの文化施設のあり方とは。
vol. 232024.03.27だれもが文化でつながるために。クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョーが見据えるこれからの文化施設のあり方とは。![]() vol. 222023.12.22人のためってなんだろう? 他者にコントロールされない「LOVOT」から、“人間らしさ“を考える──伊藤亜紗さん×林要さん
vol. 222023.12.22人のためってなんだろう? 他者にコントロールされない「LOVOT」から、“人間らしさ“を考える──伊藤亜紗さん×林要さん![]() vol. 212023.11.08保育料ゼロを実現し、子育てを“みん営化”する。 学童保育施設〈fork toyama〉岡山史興さん
vol. 212023.11.08保育料ゼロを実現し、子育てを“みん営化”する。 学童保育施設〈fork toyama〉岡山史興さん![]() vol. 202023.05.29ともだちってなんだろう? 答えを出す必要はないけれど。新澤克憲さんとテンギョー・クラさんの対話から考える
vol. 202023.05.29ともだちってなんだろう? 答えを出す必要はないけれど。新澤克憲さんとテンギョー・クラさんの対話から考える![]() vol. 192023.05.23歌人・岡本真帆さん×西淡路希望の家・金武啓子さん対談。「感動」の発見、どう他者と分かち合いますか?
vol. 192023.05.23歌人・岡本真帆さん×西淡路希望の家・金武啓子さん対談。「感動」の発見、どう他者と分かち合いますか?![]() vol. 182023.03.20“みる”から始める、アーティストと支援現場のつなぎ役。日常の関係性を変える「TURN LAND プログラム」の挑戦
vol. 182023.03.20“みる”から始める、アーティストと支援現場のつなぎ役。日常の関係性を変える「TURN LAND プログラム」の挑戦![]() vol. 172023.03.15アート活動で、「できる/できない」を揺さぶる。日常の価値を言葉に変えるコーディネーターの役割
vol. 172023.03.15アート活動で、「できる/できない」を揺さぶる。日常の価値を言葉に変えるコーディネーターの役割![]() vol. 162023.03.03唯一の答えを探しすぎていないか? 下地ローレンス吉孝さん×なみちえさんと“わかりやすさ”について考える
vol. 162023.03.03唯一の答えを探しすぎていないか? 下地ローレンス吉孝さん×なみちえさんと“わかりやすさ”について考える![]() vol. 152023.02.15“わたし”と“あなた”それぞれの複雑さを大切にするには?──なみちえさん×下地ローレンス吉孝さんと共に考える
vol. 152023.02.15“わたし”と“あなた”それぞれの複雑さを大切にするには?──なみちえさん×下地ローレンス吉孝さんと共に考える![]() vol. 142022.12.23出会いを広げながら、協働を生む「メディア」を目指して──〈こここ〉シーズン2を振り返る
vol. 142022.12.23出会いを広げながら、協働を生む「メディア」を目指して──〈こここ〉シーズン2を振り返る![]() vol. 132022.12.19働くことも、映画祭も「みんなが心地よい」を目指して。GOOD NEWSとTHEATRE for ALLのインクルーシブな場づくり
vol. 132022.12.19働くことも、映画祭も「みんなが心地よい」を目指して。GOOD NEWSとTHEATRE for ALLのインクルーシブな場づくり![]() vol. 122022.10.14バリアフリーの映画祭を通して、「その人のまま」でいられる社会に。作家・川内有緒さん×THEATRE for ALL・金森香さん
vol. 122022.10.14バリアフリーの映画祭を通して、「その人のまま」でいられる社会に。作家・川内有緒さん×THEATRE for ALL・金森香さん![]() vol. 112022.09.13スポーツの可能性って何だろう? 「プロスポーツ」「ゆるスポーツ」から考える──岡田武史さん×澤田智洋さん
vol. 112022.09.13スポーツの可能性って何だろう? 「プロスポーツ」「ゆるスポーツ」から考える──岡田武史さん×澤田智洋さん![]() vol. 102022.03.31まだみぬ「表現」との出会いを、誰もが体験できる社会へ。障害のある人の芸術・文化活動を支える窓口が全国に
vol. 102022.03.31まだみぬ「表現」との出会いを、誰もが体験できる社会へ。障害のある人の芸術・文化活動を支える窓口が全国に![]() vol. 092022.02.09コロナ禍で「消される」声に、どう耳を傾ける? 次の社会をつくる言葉と対話のあり方──荒井裕樹さん×青山誠さん
vol. 092022.02.09コロナ禍で「消される」声に、どう耳を傾ける? 次の社会をつくる言葉と対話のあり方──荒井裕樹さん×青山誠さん![]() vol. 082021.12.24福祉をたずねて1年。編集部は何に出会い、悩んできた?──〈こここ〉振り返り座談会
vol. 082021.12.24福祉をたずねて1年。編集部は何に出会い、悩んできた?──〈こここ〉振り返り座談会![]() vol. 072021.11.24コロナ禍を経て新たな表現の協働へ ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[後編]
vol. 072021.11.24コロナ禍を経て新たな表現の協働へ ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[後編]![]() vol. 062021.11.24アートプロジェクトは福祉の現場で何を生み出す? ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[前編]
vol. 062021.11.24アートプロジェクトは福祉の現場で何を生み出す? ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[前編]![]() vol. 052021.10.18福祉施設が学びあいの拠点になることで育まれるものとは?ライフの学校・田中伸弥さん
vol. 052021.10.18福祉施設が学びあいの拠点になることで育まれるものとは?ライフの学校・田中伸弥さん![]() vol. 042021.06.03VR認知症を体験して気づいた、わからない世界へ手を伸ばし続ける大切さ。シルバーウッド 下河原忠道さん
vol. 042021.06.03VR認知症を体験して気づいた、わからない世界へ手を伸ばし続ける大切さ。シルバーウッド 下河原忠道さん![]() vol. 022021.04.15「助けて」とお互いに言い合えるのが、成熟した社会。ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ代表 志村季世恵さん
vol. 022021.04.15「助けて」とお互いに言い合えるのが、成熟した社会。ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ代表 志村季世恵さん![]() vol. 012021.04.15「お笑い」や「演劇」は他者の世界に寄り添うヒントをくれる。りんたろー。さん×菅原直樹さんが語る「介護の話」
vol. 012021.04.15「お笑い」や「演劇」は他者の世界に寄り添うヒントをくれる。りんたろー。さん×菅原直樹さんが語る「介護の話」