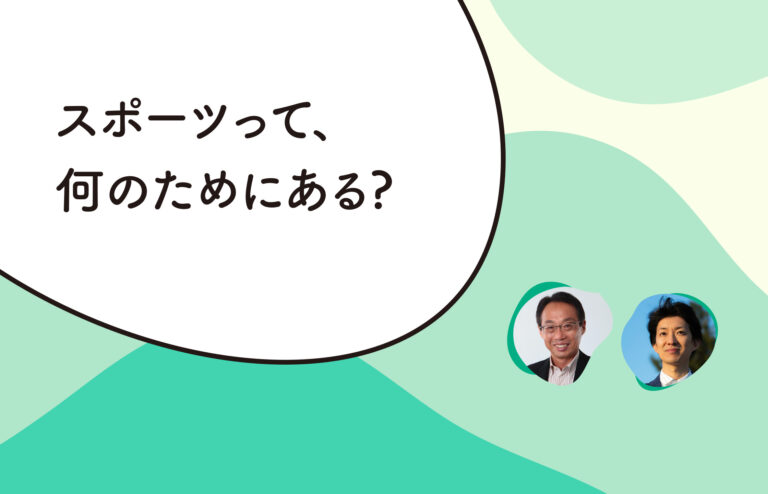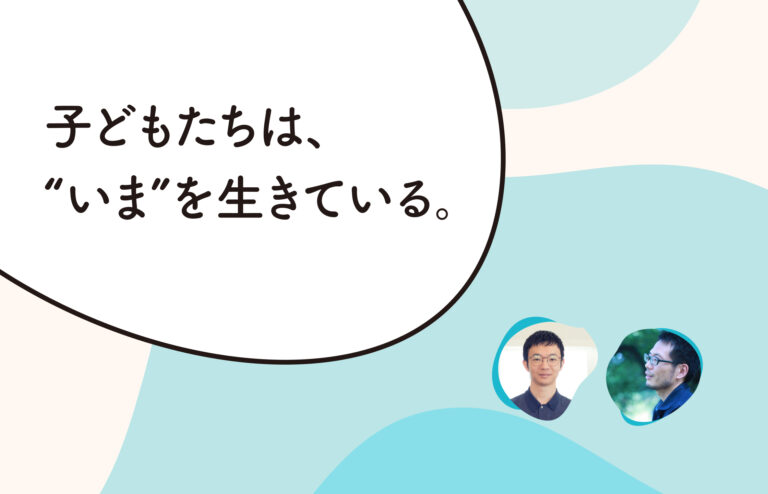VR認知症を体験して気づいた、わからない世界へ手を伸ばし続ける大切さ。シルバーウッド 下河原忠道さん こここインタビュー vol.04
他者が見ている世界と、自分が見ている世界は違う。だからこそ日々出会う人とのコミュニケーションにおいて、それぞれの行動や語る言葉の背景にあるものを想像するのは大切だと思う。
しかし「常日頃から実践できているか」と問われると自信が持てない。知識を得ることで、他者の背景にあるものをより解像度高く考えることはできる。一方で、既に持つ知識を基準に他者をラベリングして、わかったつもりになってしまうこともある。どうすれば知識を学ぶだけではこぼれおちてしまう「なにか」を大切にできるのだろうか。
そんな悩みについて考えるヒントを与えてくれたのが、サービス付き高齢者向け住宅「銀木犀」を運営する株式会社シルバーウッドの取り組み「VR Angle Shift」だ。
コンセプトは「あなたのAngle“視点” をShift“転換” する」。VRを活用した一人称「体験」を通じて、他者の視点が体感できるコンテンツを企業内研修などに向けて展開している。コンテンツは、さまざまな領域の当事者、専門家にヒアリングを実施し作成されており、複数のプログラムがある。
取材チームは、実際にVR Angle Shiftのプログラムを体験し、同社代表取締役 下河原忠道さんに他者の視点を疑似体験することの意義、社会から見えづらいものを可視化することの重要性について話を伺った。
認知症の中核症状の一つをVRで疑似体験する
インタビューに先立ち体験したのは「VR認知症」だ。銀木犀に入居する高齢者との関わりをもとに制作されたこのプログラムは、2016年からVR Angle Shiftの第一弾として展開されている。
取材チームは、2021年の3月から4月にかけて行われた個人向けのオンライン体験会に参加し、後日、同社オフィスでVR機材を装着し体験した。


視聴したのは『私をどうするのですか?』と題された認知症の中核症状の一つ視空間失認を疑似体験できるプログラムだ。
プログラムが再生されると、足がすくんでしまった。自分がビルの屋上に立ち、柵が一切ない状態で、はるか下の地面を見下ろしていたからだ。

「なぜこんな場所に立たされているんだろう?」
当然の疑問を浮かべるが、「落ちてしまうかもしれない」という恐怖でほとんど何も考えられない。
すると隣から「大丈夫ですよ」と声が聞こえてくる。声がする方向に目を向けてみると、スタッフらしき人が微笑んでいる。反対側には「さあ、足を出してみましょう」と、これもまた笑顔で語りかけてくるスタッフらしき人。
自分は今、ビルから落ちてしまうかもしれない状況で、恐怖にさらされている。なのになぜ、この人たちは笑っているのだろう……? それだけではなく、なぜ一歩踏み出すことを勧めてくるのだろう……。
混乱が続くなかで場面は変わり、車の前で自分が立っている光景に映像が切り替わる。ここではじめて、自分がいたのはビルの屋上ではなく、車の中だったと気づく。隣にいたスタッフは私の手を取り、開いたドアから降りるように促して「ほら、大丈夫だったでしょ?」と笑いかけてくるのだ。
このプログラムの視聴時間は約2分。決して長くはない時間だが「認知症がある方の中には、距離感が正しく認識できなくなる症状を持つ方もいるのだ」という衝撃はその後も頭から離れなかった。
オンライン体験会では、120分で三つのプログラム視聴し、一つの視聴ごとに参加者同士が「自分が何を感じたのか、どう思ったのか」を共有する時間が設けられている。
「なぜこんな目に遭っているのだろう」「この人たちにビルから落とされるかもしれない」……。多くの人が一人称の視点で感じたことを語る。
ファシリテーターから「あなただったらどう接してほしいですか」と問いが共有されると「大丈夫?ではなく、まずはどうしましたか?と聞いてほしい」「パニック状態なので、一旦落ち着くまで待ってほしい」といった気づきが共有されていく。
プログラム視聴の前後では、認知症の種類や中核症状、行動・心理症状の説明も行われる。知識、体験、自分や他の参加者が感じたことを行き来しながら、認知症のある当事者を取り巻く環境や問題について考えることができた。
「他者や社会との関係のなかに障害があること」を体感する

プログラム視聴後、下河原さんにお話を伺った。サービス付き高齢者向け住宅などを運営する企業がなぜVRを活用した取り組みをはじめるに至ったのか。きっかけは下河原さん自身が持っていたVR技術への興味だったという。
ゲーム用のVR機器「Oculus」(オキュラス)や、仮想空間で自由にお絵かきができるGoogleの「Tilt Brush」(チルトブラシ)などを使ってみると、とてもおもしろかったんです。
VRの技術を活用して、誰かに成りかわり、別人の視点を体験できる。これは人類がかつて味わったことのない感覚ではないかと。
VR技術を活用してなにかできないか。そう考え、クリエイターたちと試行錯誤を重ねるなかで、下河原さんはある小説に出会う。
主人公の一人称視点で物語が進んでいく小説でした。読み進めていくと、主人公と社会との接点でズレが発生しているとわかり、どんどん違和感を覚えるようになって。最終的には主人公に認知症があるとわかるんです。
VRを活用すれば、この小説を読んでいたときのように、認知症のある一人の当事者が見ている世界を、第三者が追体験できるのではないか。小説から着想を得て、VR認知症のプログラムを検討しはじめました。

VR認知症のホームページには「自分が認知症を経験したことがないから、認知症のある方への想像がしにくく、『もう何もわからなくなってしまった人』 といったネガティブな感情につながってしまうのではないか。そんな想いから、認知症がある方たちの世界を一人称体験する『VR認知症』が生まれました」と記載されている。
下河原さんは、認知症のある人と大きくカテゴライズして「一方的に『支援が必要な人』とラベリングしたり、固定された役割のみを押し付けることに違和感があった」のだという。
認知症の症状があることで、障害が生まれているのは事実です。でもそれは当事者個人の責任ではない。あくまで社会との間に障害が発生しており、社会全体の問題です。
他者の視点をVRで体験してもらうことによって「あくまで他者や社会との関係のなかに障害があること」を体感し、理解する手助けになるはずだと思ったんです。
同じプログラムを見ても感じることは人それぞれ

VR Angle Shiftのコンセプトは「他人事で見ていたことも“一人称”で体験するとちがって見えるはず」だ。それは、銀木犀の運営で大切にしていることに通ずるものがあるという。
銀木犀のスタッフには、自分が当事者だったらどう思うかの視点を大切にしてほしいと伝えています。誰しも小学生のときに「自分がされて嫌なことはしない」と言われたことはあると思うんです。
でも介護の世界では、安全を確保する、リスクを避けるという理由で「自分がされて嫌なこと」をついやってしまう。リスクばかり見ていると、目の前の大切にすべきことが見えなくなりやすいからこそ、自分がその立場だったらどう思うかの視点は大切だと思うんです。
VR Angle Shiftでも、他者の視点を一人称で「体験」することで、机の上で知識を「学ぶ」だけでは意識しづらい感情や感覚にも立ち止まれる。
プログラムを見たあとに参加者同士でそれぞれが感じたことを共有する時間を設けることで、共通で感じたことだけではなく、差異にも触れられる。
同じプログラムを見ても、感じることは人それぞれです。他者をわかったつもりにならないことの大切さを再認識してもらう機会になればうれしいですね。

他者の視点を想像し、実際に自分だったらどう思うかを語ること。言葉にするとシンプルだが実践するのは簡単ではない。
オンライン体験会で、ファシリテーターから「一人称でどう感じたかを共有してください」という説明があったとき、つい第三者視点で俯瞰的に状況を語ろうとする自分がいた。
「あの場面では、介護を担当するスタッフは周囲の状況を丁寧に説明するべきだった」というように。あるいは、限られた情報や知識のみで自分の思いを語ると、間違ったことを言ってしまうのではないかと不安になり、当たり障りのない言葉ばかり探してしまうこともある。
そもそも情報過多の時代において、自分の頭で想像し、自分の言葉で語る機会が少なくなっているのかもしれません。ネットで検索すれば、さまざまな情報にたどり着けますが、それは他の誰かが導き出した答えや解釈であり、自分自身の答えや解釈ではないんですよね。
だからこそ、自分で体験し、想像し、拙くてもまずは自分の言葉で語ることが大事だと思うんです。
福祉や介護におけるさまざまな側面を見える化していく

「拙くても自分の言葉で語る」。それは、自分が見えていない世界に手を伸ばし続けるために大切な行為だ。
異なる世界が見えている他者と接する上で、自分には見えていないものが常に存在することを忘れず、そこへ手を伸ばす「想像力」が鍵になるのかもしれない。そう下河原さんに伝えると、社会から見えづらいものを見える化することの重要性を教えてくれた。
福祉や介護の現場に携わっていない人にとって、日常的に見える部分は限られています。限られているからこそ、画一的なイメージから誤解が生まれてしまったり、関心が持てなくなってしまったりする。
僕は福祉や介護への関心を地域社会が取り戻していくことが、重要だと考えていて。そのためにできることの一つが「見える化」だと思うんです。
見える化は必要だが、それはやみくもに情報発信することではないと、下河原さんは続ける。
単一の面だけではなく、さまざまな側面を見える化していくことが大事です。たとえば従来の福祉や介護業界の「車椅子のおばあちゃんの横でスタッフがにっこり笑っている」イメージだけではなく、クリエイティブな人たちが関わって最先端の可能性を生み出しているなど。
「かっこいい福祉」の姿を見せていくことも、日本社会の無関心を打破するためには必要かもしれない。一方で、福祉や介護の領域には、きれいごとだけではなく、ドロドロしている部分も課題もたくさんあります。どれも置き去りにせず、さまざまな側面を共有して共に考えていけるといいですよね。

人間と人間で向き合うことや、それを支える仕組みが福祉と呼べるのかもしれない
福祉や介護におけるさまざまな側面を見える化していく。そのために、そもそも自分が「福祉」をどう定義しているのかを考えることは重要だ。下河原さんが考える「福祉」について伺った。
先日「ああ、これは福祉的な関わりだな」と思う出来事がありました。
銀木犀を建築する際に関わってくれた内装業者さんのお子さんの話です。その方は宅配便を扱う運送会社でドライバーとして働いていて、毎日同じ地域をぐるぐると回っているんですね。銀木犀については、親から話を聞いてコンセプトなどを知っていたそうです。
その方がある日、配送担当地域で暮らす一人暮らしの高齢者と知り合いました。「家族から『福祉施設に入ってはどうか』と言われるけれど、施設は行動が管理されるから怖いのよ」となにげなく話をしてくれたそうです。
するとドライバーのその人は銀木犀を紹介してくれた。「あそこなら鍵もかかっていないし、自分の生活を続けられるんですよ」と。
銀木犀を紹介してくれたことはもちろんありがたいのですが、一番うれしかったのはそこではなくて。ドライバーの仕事は荷物を運ぶことで、一人暮らしの高齢者の相談に乗ることではない。でも、目の前にいる人の暮らしにとって何がいいのかを考えて行動した。すごく福祉的な関わりだと思ってうれしくなったんです。

「私の仕事や役割はこれだから」と割り切り、その範囲で人と関わる。それは必要なことだ。しかし、その考えが行き過ぎてしまうと見えなくなってしまうものがある。
福祉は、固定化された役割や範囲を疑って人間と人間で向き合う行為の積み重ねであり、それを支える仕組みなのではないか。下河原さんの話を受けて感じたことを取材チームが伝えると「ドライバーさんのような一歩を地域の人それぞれがたくさん体験し、情報が共有されていくことで福祉の土壌が培われていくのではないかと僕は思っているんです」と応えてくれた。
福祉は特別な人のためのものではなく「みんなが参加するもの」
そもそも福祉とは、みんなが参加するものだと思っています。
福祉的なマインドを持ったカリスマが、社会のためになることを考えてどんどん実行していく。それも大切なのかもしれませんが、僕は一人ひとりが少しずつでいいから、福祉を理解して行動していくことがそれ以上に必要だと思うんです。
そうした下河原さんの思いは、銀木犀の運営スタンスにも如実に表れている。
銀木犀の施設内には「駄菓子屋」が設けられ、「店主」は入居者が務める。新型コロナウイルスの影響で活動を中止しているものの、コロナ前には地域の子どもたちが連日集い、思い思いの時を過ごしながら高齢者と関わっていた。

「子どもたちはただ駄菓子を買って騒いでいるだけなんだけど、一方では思いきり、福祉的な関わりを経験してくれているんですよね。『店主』を務める入居者の方も、子どもたちを見守ってくれたりする」と下河原さんは目を細める。
福祉を、自分とは関係のない「特別な人のためのもの」ととらえている人が多いのかもしれません。でも福祉の芽は案外身近な場所に生まれているものだと思います。
暮らしている地域でよく見かける人に声をかけてみる。そうした偶発性を大切にして、行動してみることで、福祉を自分ごと化できるようになるのではないでしょうか。

Information
・「VR Angle Shift まずは体験してみる~オンライン事前体験会開催」(研修開催またはVRのレンタルをご検討いただいている方を対象)詳細はこちら
Profile
![]()
-
下河原忠道
株式会社シルバーウッド代表取締役
2000年に株式会社シルバーウッドを設立。独自に開発した薄板軽量形鋼造「スチールパネル工法」の構造大臣認定を国土交通省より取得し、全国での構造躯体販売事業を展開。2011年にサービス付き高齢者向け住宅「銀木犀」開設、現在12棟の高齢者住宅を直轄運営。2017年「VR認知症体験会」開始。当事者との共同開発によって実現したVRを活用した認知症の一人称体験、2020年までに7万人の参加者が体験。2018年からVRの体験テーマを医療・看護教育への応用、LGBT、発達障害、管理職がワーキングマザーファザーを理解するためのプログラム等に広げ展開している。2021年より八重山諸島にて訪問介護看護事業を開始。一般財団法人サービス付き高齢者向け住宅協会理事のほか、高齢者住まい事業者団体連合会幹事を務める。
Profile
![]()
-
株式会社シルバーウッド
高齢者だからとか、認知症だからとか関係なく、人として自由な生活を送れる住まい環境を目指して、千葉・東京・神奈川に「銀木犀」というサービス付き高齢者向け住宅10棟とグループホーム2棟を運営。2017年からVRで認知症の症状を本人視点で体験する事を通して認知症に対する正しい理解に繋げる「VR認知症体験」を開始。今ではVRの体験テーマをLGBT、発達障害、ワーキングマザーファザー、ハラスメント、異文化コミュニケーション等に広げ、多様性の理解に繋げるプログラムを展開している。高齢者だからとか、認知症だからとか関係なく、人として自由な生活を送れる住まい環境を目指して、千葉・東京・神奈川に「銀木犀」というサービス付き高齢者向け住宅10棟とグループホーム2棟を運営。2017年からVRで認知症の症状を本人視点で体験する事を通して認知症に対する正しい理解に繋げる「VR認知症体験」を開始。今ではVRの体験テーマをLGBT、発達障害、ワーキングマザーファザー、ハラスメント、異文化コミュニケーション等に広げ、多様性の理解に繋げるプログラムを展開している。
- ライター:多田慎介
-
1983年、石川県金沢市生まれ。大学中退後に求人広告代理店へ入社し、転職サイトなどを扱う法人営業職や営業マネジャー職を経験。編集プロダクション勤務を経て、2015年よりフリーランスとして活動。働き方やキャリア、企業の採用コンテンツ、教育などをテーマに取材・執筆中。著書に『「目的思考」で学びが変わる―千代田区立麹町中学校長・工藤勇一の挑戦』(ウェッジ)。
この記事の連載Series
連載:こここインタビュー
![]() vol. 322025.03.18言葉を超えて誰もがつながる「身体表現」の魅力とは? 福祉を起点に広がるパフォーミングアーツ、生きづらさを変える可能性
vol. 322025.03.18言葉を超えて誰もがつながる「身体表現」の魅力とは? 福祉を起点に広がるパフォーミングアーツ、生きづらさを変える可能性![]() vol. 312024.10.09なぜ自分に価値があるか確認したくなるんだろう? 勅使川原真衣さんと新澤克憲さんによる「評価」を巡る対話
vol. 312024.10.09なぜ自分に価値があるか確認したくなるんだろう? 勅使川原真衣さんと新澤克憲さんによる「評価」を巡る対話![]() vol. 302024.09.13大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 写真家/訪問看護師 尾山直子さんをたずねて
vol. 302024.09.13大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 写真家/訪問看護師 尾山直子さんをたずねて![]() vol. 292024.09.07地域に根ざす園から、子どもも大人も混ざった“絶景“を生み出せたら。〈学校法人thanka〉が新ステートメント「手を繋ぎにいく」に込めた願い
vol. 292024.09.07地域に根ざす園から、子どもも大人も混ざった“絶景“を生み出せたら。〈学校法人thanka〉が新ステートメント「手を繋ぎにいく」に込めた願い![]() vol. 282024.08.30大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 株式会社Blanket 秋本可愛さんをたずねて
vol. 282024.08.30大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 株式会社Blanket 秋本可愛さんをたずねて![]() vol. 272024.07.25気軽な買い物体験から、「未来が良くなる」手応えを。〈フェリシモ〉の新カタログ『GO! PEACE!』制作の裏側
vol. 272024.07.25気軽な買い物体験から、「未来が良くなる」手応えを。〈フェリシモ〉の新カタログ『GO! PEACE!』制作の裏側![]() vol. 262024.04.30蓋された「小さな自分」の声に耳を傾けて。ケアを促す料理レッスンの場、就労支援の場──山口祐加さん×鞍田愛希子さん
vol. 262024.04.30蓋された「小さな自分」の声に耳を傾けて。ケアを促す料理レッスンの場、就労支援の場──山口祐加さん×鞍田愛希子さん![]() vol. 252024.04.10「インクルーシブ」は誰のための言葉? 老舗メーカー〈ジャクエツ〉×医師・紅谷浩之さんの、子どもに“遊びと友だち“を返す遊具
vol. 252024.04.10「インクルーシブ」は誰のための言葉? 老舗メーカー〈ジャクエツ〉×医師・紅谷浩之さんの、子どもに“遊びと友だち“を返す遊具![]() vol. 242024.03.29文化施設のウェブアクセシビリティを向上する。障害当事者との「建設的な対話」に必要なこととは?──伊敷政英さん×森司さん
vol. 242024.03.29文化施設のウェブアクセシビリティを向上する。障害当事者との「建設的な対話」に必要なこととは?──伊敷政英さん×森司さん![]() vol. 232024.03.27だれもが文化でつながるために。クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョーが見据えるこれからの文化施設のあり方とは。
vol. 232024.03.27だれもが文化でつながるために。クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョーが見据えるこれからの文化施設のあり方とは。![]() vol. 222023.12.22人のためってなんだろう? 他者にコントロールされない「LOVOT」から、“人間らしさ“を考える──伊藤亜紗さん×林要さん
vol. 222023.12.22人のためってなんだろう? 他者にコントロールされない「LOVOT」から、“人間らしさ“を考える──伊藤亜紗さん×林要さん![]() vol. 212023.11.08保育料ゼロを実現し、子育てを“みん営化”する。 学童保育施設〈fork toyama〉岡山史興さん
vol. 212023.11.08保育料ゼロを実現し、子育てを“みん営化”する。 学童保育施設〈fork toyama〉岡山史興さん![]() vol. 202023.05.29ともだちってなんだろう? 答えを出す必要はないけれど。新澤克憲さんとテンギョー・クラさんの対話から考える
vol. 202023.05.29ともだちってなんだろう? 答えを出す必要はないけれど。新澤克憲さんとテンギョー・クラさんの対話から考える![]() vol. 192023.05.23歌人・岡本真帆さん×西淡路希望の家・金武啓子さん対談。「感動」の発見、どう他者と分かち合いますか?
vol. 192023.05.23歌人・岡本真帆さん×西淡路希望の家・金武啓子さん対談。「感動」の発見、どう他者と分かち合いますか?![]() vol. 182023.03.20“みる”から始める、アーティストと支援現場のつなぎ役。日常の関係性を変える「TURN LAND プログラム」の挑戦
vol. 182023.03.20“みる”から始める、アーティストと支援現場のつなぎ役。日常の関係性を変える「TURN LAND プログラム」の挑戦![]() vol. 172023.03.15アート活動で、「できる/できない」を揺さぶる。日常の価値を言葉に変えるコーディネーターの役割
vol. 172023.03.15アート活動で、「できる/できない」を揺さぶる。日常の価値を言葉に変えるコーディネーターの役割![]() vol. 162023.03.03唯一の答えを探しすぎていないか? 下地ローレンス吉孝さん×なみちえさんと“わかりやすさ”について考える
vol. 162023.03.03唯一の答えを探しすぎていないか? 下地ローレンス吉孝さん×なみちえさんと“わかりやすさ”について考える![]() vol. 152023.02.15“わたし”と“あなた”それぞれの複雑さを大切にするには?──なみちえさん×下地ローレンス吉孝さんと共に考える
vol. 152023.02.15“わたし”と“あなた”それぞれの複雑さを大切にするには?──なみちえさん×下地ローレンス吉孝さんと共に考える![]() vol. 142022.12.23出会いを広げながら、協働を生む「メディア」を目指して──〈こここ〉シーズン2を振り返る
vol. 142022.12.23出会いを広げながら、協働を生む「メディア」を目指して──〈こここ〉シーズン2を振り返る![]() vol. 132022.12.19働くことも、映画祭も「みんなが心地よい」を目指して。GOOD NEWSとTHEATRE for ALLのインクルーシブな場づくり
vol. 132022.12.19働くことも、映画祭も「みんなが心地よい」を目指して。GOOD NEWSとTHEATRE for ALLのインクルーシブな場づくり![]() vol. 122022.10.14バリアフリーの映画祭を通して、「その人のまま」でいられる社会に。作家・川内有緒さん×THEATRE for ALL・金森香さん
vol. 122022.10.14バリアフリーの映画祭を通して、「その人のまま」でいられる社会に。作家・川内有緒さん×THEATRE for ALL・金森香さん![]() vol. 112022.09.13スポーツの可能性って何だろう? 「プロスポーツ」「ゆるスポーツ」から考える──岡田武史さん×澤田智洋さん
vol. 112022.09.13スポーツの可能性って何だろう? 「プロスポーツ」「ゆるスポーツ」から考える──岡田武史さん×澤田智洋さん![]() vol. 102022.03.31まだみぬ「表現」との出会いを、誰もが体験できる社会へ。障害のある人の芸術・文化活動を支える窓口が全国に
vol. 102022.03.31まだみぬ「表現」との出会いを、誰もが体験できる社会へ。障害のある人の芸術・文化活動を支える窓口が全国に![]() vol. 092022.02.09コロナ禍で「消される」声に、どう耳を傾ける? 次の社会をつくる言葉と対話のあり方──荒井裕樹さん×青山誠さん
vol. 092022.02.09コロナ禍で「消される」声に、どう耳を傾ける? 次の社会をつくる言葉と対話のあり方──荒井裕樹さん×青山誠さん![]() vol. 082021.12.24福祉をたずねて1年。編集部は何に出会い、悩んできた?──〈こここ〉振り返り座談会
vol. 082021.12.24福祉をたずねて1年。編集部は何に出会い、悩んできた?──〈こここ〉振り返り座談会![]() vol. 072021.11.24コロナ禍を経て新たな表現の協働へ ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[後編]
vol. 072021.11.24コロナ禍を経て新たな表現の協働へ ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[後編]![]() vol. 062021.11.24アートプロジェクトは福祉の現場で何を生み出す? ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[前編]
vol. 062021.11.24アートプロジェクトは福祉の現場で何を生み出す? ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[前編]![]() vol. 052021.10.18福祉施設が学びあいの拠点になることで育まれるものとは?ライフの学校・田中伸弥さん
vol. 052021.10.18福祉施設が学びあいの拠点になることで育まれるものとは?ライフの学校・田中伸弥さん![]() vol. 032021.04.15まだ名付けられていない感覚に出会う「遊び」の可能性とは? インタープリター 和田夏実さん
vol. 032021.04.15まだ名付けられていない感覚に出会う「遊び」の可能性とは? インタープリター 和田夏実さん![]() vol. 022021.04.15「助けて」とお互いに言い合えるのが、成熟した社会。ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ代表 志村季世恵さん
vol. 022021.04.15「助けて」とお互いに言い合えるのが、成熟した社会。ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ代表 志村季世恵さん![]() vol. 012021.04.15「お笑い」や「演劇」は他者の世界に寄り添うヒントをくれる。りんたろー。さん×菅原直樹さんが語る「介護の話」
vol. 012021.04.15「お笑い」や「演劇」は他者の世界に寄り添うヒントをくれる。りんたろー。さん×菅原直樹さんが語る「介護の話」