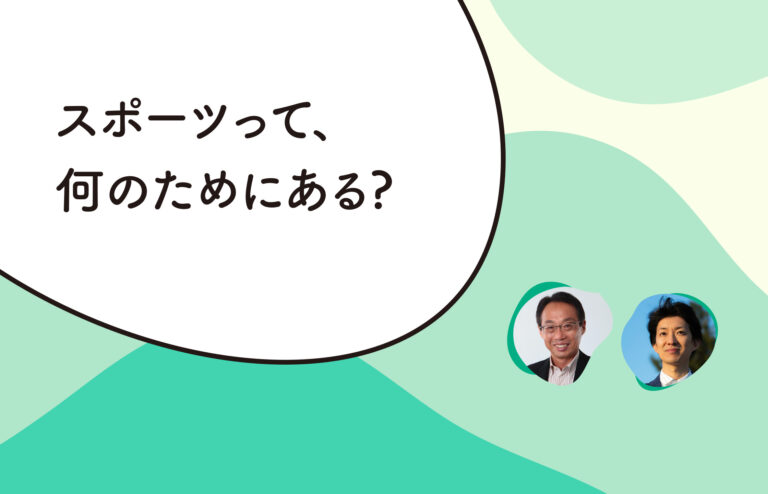コロナ禍で「消される」声に、どう耳を傾ける? 次の社会をつくる言葉と対話のあり方──荒井裕樹さん×青山誠さん こここインタビュー vol.09
私たちの社会は、みんなで支え合う生態系として成り立っているはずです。でも、このコロナ禍で「社会のために」と我慢を強いられてきたのは、結局弱い立場の人ばかりでした。
そう話すのは、2021年5月に出版された『まとまらない言葉を生きる』の著者、荒井裕樹さん。障害者文化論、日本近代文学を専門とし、主にマイノリティの自己表現について研究をされています。
大学教員でもある荒井さんにとって、コロナ禍で起きた急激な環境の変化は、当たり前に使っていた言葉を「それってそもそも何のことだっけ?」と問い直す連続だったと言います。例えば、リアルに顔を合わせられない学生たちにとっての、「友達」が示す言葉の意味。関わる人によってイメージする状態が全く異なる、「安全」という言葉の意味──。
そんな荒井さんと同じような疑問を、「保育」という現場で抱えてきたのが〈上町しぜんの国保育園〉の青山誠さんでした。「子どもの心に寄り添う保育」を掲げる同園の園長であり、さまざまなメディアで執筆などを行う保育者としても知られています。
保育園ってそもそも誰の、何のための場所なのか。根底を揺るがされるような状況に何度も出会いながら、僕は子どもたちの言葉が「大人によってまとめられようとしている」ことにすごく危機感を感じてきました。
でも、それはコロナのためというわけじゃない。むしろ日常的に抱えていたものが、コロナ禍で表面化しただけのように思うんです。
お二人に対話していただくことで、この社会で今起きている変化や、ほころびが浮かび上がってくるのではないか。
「『言葉が壊れてきた』と思う」──そんな一節からはじまる荒井さんの著書を真ん中に置き、それぞれが胸の中に抱く想いを共有していただきながら、私たちも一緒に考えていくことにしました。
コロナ禍で、以前から起きていた問題がはっきり突きつけられた
──青山さんは、荒井さんの『まとまらない言葉を生きる』をすでに読まれていたそうですね。
青山誠さん(以下、青山) はい。うちの保育園の栄養士さんが、「この本、知ってる?」と教えてくれたんです。それで興味を持って、手に取りました。
荒井裕樹さん(以下、荒井) ありがとうございます。書いているときは正直、「この本、本当に売れるのかな?」とも思っていました。私が日々モヤモヤと感じている疑問を、ただ書き連ねているようなものですから。

荒井 でも、ひとつだけ自信があったのは、「私が出会ってきた人たちは面白いんだ」ということでした。
その方々が生きてきたなかで、言葉がどういう風に使われてきたのかに目を向けていくと、そこに宿る力のようなものに胸打たれる瞬間がたくさんあった。それを伝えられる本にしたかったんです。
青山 僕はコロナ禍で保育者や子どもたちと一緒に過ごしながら、以前からわかっていた問題をより明確に、くっきりと突きつけられ、思わぬかたちで自分自身もその当事者になる経験をしてきました。荒井さんの本を読んで、この1年半ほどの間にリアルに感じてきたことを、なぞってもらえているような気がしたんです。
『まとまらない言葉を生きる』という書名、それから帯にも書かれていた「誰の人生も要約させない」という言葉──。中でも僕がとても印象深かったのは、悪意と善意の話を「人を遠ざける」という観点からされていたところでした。
コロナ禍では、さまざまな立場の人をひとつに“まとめようとする力”がものすごくはたらいてきたと思うんですが、まとめようとする側は意外と善意の顔をして近づいてくる。むしろ何かを強引にまとめてしまっていることにすら、気づいていない場合も多いですよね。本を読みながら、その事実をあらためて噛み締めていました。
「地域」じゃない。「隣近所」だ。
当時、「地域」という言葉を疑ったこともなかったぼくは、この言葉にガツンと頭を叩かれたような思いがした。
自分の「隣近所」を守ろうとする時、人は驚くほど保守的になったり、攻撃的になったりする。障害者運動の歴史を調べていると、そう感じることが多い。(中略)
人を遠ざけるのは「悪意」ばかりじゃない。「何かあったら大変です」「困るのはあなたじゃないですか」といった「善意」が人を遠ざけることもある。横田さんたちは、そうした「善意の顔をした差別」を鋭く告発してきた。
こんなことを書いているぼくにも、こうした保守性や攻撃性は、きっとある。子育てをしていると、「隣近所」で起こる変化に過敏になっている自分がいる。この過敏さは、どこかで誰かを傷つけていないだろうか?
※『まとまらない言葉を生きる』第五話の、『「地域」で生きたいわけじゃない』より引用。「横田さん」とは、障害者運動家の横田弘さんのこと
「みんなのために」が人の言葉をかき消していく
──コロナ禍の保育園で、青山さんが“まとめようとする力”を感じたのはどんな出来事からですか?
青山 例えば、保育者たちに対する国や自治体の姿勢でしょうか。未知のウイルスが来ていても、園については一方的に「社会のインフラなので閉めません」と言い切られた。けれど、そもそも保育園という場をつくっているのも「人」ですよね。そこで働く一人ひとりに目を向けることなく、「インフラ」という一言で済まされてしまうことに対して大きな疑問を感じていました。
また、うちの園がある区で、PCRの一斉検査を介護職や保育従事者に導入する話が持ち上がったこともありました。そうすると、職員はコロナ陽性になると行動履歴の提出を求められ、社会を支える場所で働いているというだけで「自分は安全です」と証明し続けなければならなくなる。
僕はそのグロテスクさに耐えられなくて、反対の声を上げました。個人に対するケアや配慮もなしに、なぜそんな扱いをされなきゃいけないんだろうって。

青山 さまざまな事情から一斉検査は実施されませんでしたが、発表された当初、マスコミやSNSではそれが英断のようにもてはやされました。「みんなの安全のために」というまとめられ方をされることへの違和感、怒りがありました。
荒井 結局、「みんなのために」という名目で我慢を強いられるのは弱い人たちであって、「みんな」が均等に重荷を負うわけではないんですよね。コロナ禍では医療や介護、保育、学校などの現場に、特に重い負担がのしかかってしまった。
本来、私たちの社会は生態系として成り立っていて、消費者は生産者でもあり、生産者は消費者でもあるわけです。支える/支えられる関係は複雑に絡み合って、入れ替わりながら動いている。子どもを預かってくれている人たちも、家に帰れば別の子どもたちのお父さん・お母さんであったりします。そうした支え合いのいちばん基盤になる場所が、保育園や学校、高齢者のためのケア施設などですよね。
2020年の春、その基盤の一つである学校が突然、真っ先に止められたわけです。事前に何の議論も説明もなく。この生態系のことをよく知らない人たちが実は社会の上に立ち、全体の舵を取っているんだと感じて、本当にショックでした。

青山 あらゆることを想定して、できる限り幅広い層に同じ軸を適用しようとする人たちと、現場で個々の具体的状況を見る人の違いもあったのだと思います。もちろん行政の方たちも、実は「よくわからないまま上からやらされている」だけのことも多い。話せばわかり合えることもたくさんあって、ある意味気の毒でした。
荒井 僕がすごく辛かったのは、まさにその「上」に立っている人たちのコミュニケーションなんです。誠意ある言葉で説明をせず、不機嫌さをあらわにして「察しろ」と迫るようなシーンを、何度も目にしました。
誰もが不安な気持ちを持っていたあの時期は、本来それを共有しながら、安心感を分かち合っていかなければいけなかったはずです。にもかかわらず、トップにいる人たちは、威圧的なコミュニケーションで社会を動かそうとした。社会にとって、これはすごく不幸なことだったと思います。
青山 威圧的なコミュニケーションの発端になっているのも、人の不安なのだと思います。はじめは誰かひとりが抱いたものが、匿名で、「市民の方からの声」となって行政に寄せられることで、いつしか公然化されたルールになり、荒井さんの本にもあったように「人を黙らせる」ようになる(第十四話の『「黙らせ合い」の連鎖を断つ』)。それに反したり逸脱したりした場合、非難されてもいいものと認識されてしまうんです。
コロナ禍でいちばん辛かったのが、そうした半ば匿名化したルールや、大人たちの「子どものためを思って」という大義名分の下で、子どもたち個別の事情が無視されること。「自分はこうしたい」という一人ひとりの想いや言葉が消されていくことでした。
奪われ続けている「子ども心地」
荒井 自分自身で声を上げることが難しい子どもや若者たちの動向が、社会防衛的な観点から語られてしまうのは怖いですよね。
青山 本当にそうです。その声って、大人がちゃんと耳を傾けないと聞こえてこないんですね。僕たちは保育者や教育者として、この基本にもう一度立ち返る必要があると、最近よく考えていて。
そんなことを職員たちと話しているなかで、「子どもたちの靴を国会議事堂の前に並べよう」というアイデアが出たことがありました。
荒井 それは抗議の意味で、ですか?
青山 実行するには至りませんでしたけど。抗議というよりは、子どもがここにいるよって伝えたくて。
子どもたちの靴って、実際に手に取ってみるとすごく小さいじゃないですか。そういう実感をもって社会のことを考えてほしい。子どもたちの存在を感じながら、話をしてもらいたいと僕は思うんです。

荒井 最初の緊急事態宣言の頃、公園で遊んでいる子どもがいると、学校に苦情がいく状況がありました。子どもは辛かっただろうと思うのですが、そもそも子どもたちってコロナに関係なく、ずっとそんな視線に晒されてきたのかもしれないとも感じます。
はしゃぎ声は騒音扱いされるし、公園でのボール遊びは迷惑がられる。子どもという存在は「基本は迷惑だけど、一定の範囲内なら受け入れる」といった扱いをされてきたのではないでしょうか。
青山 まさに、子どもたちはコロナの影響があろうがなかろうが、そういった立場に立たされ続けていると思うんです。僕は「いきいきした個人と、いきいきした集団は両立できる」と考えて保育をしているのですが、社会に目を向けると、全体のムードをつくる人、どちらかといえばネガティブな意見を発する人の声の強さが勝ってしまう現状があって。
僕たちのような自由な保育をしていると、周りの大人から「そんな教育をしていたら社会に通用しない」とか「わがままな子に育ったらどうするんだ」などと言われることがあります。

青山 ただ、わがままで何がいけないのって。人生の根っこを耕すこの時期に、「あるがままにふるまえること」ってとても大事です。それにきちんと子どもの姿を見ていれば、子どもたちがありったけのことをやったって、別にたいしたことないんです。そこまで大人が困ることは起きないし、仮に迷惑かけたってなんだっていうのでしょうか。保育者として、それは本当に日々感じていて。
荒井 なるほど……そうかもしれない。
青山 荒井さんの本に、「生きた心地」について書かれた章がありましたよね。子どもにも、子どもなりの“生きた心地”」があるはずです。「子ども心地」と言っていいかもしれません。
でも、今は何でも触れてはいけないし、汚れてはいけない。危険だから木登りもだめ、泥あそびもだめ。大人が「あなたの将来を思って」なんて言って、それを全部奪ってしまっているんです。
本当は子どもだろうと大人だろうと関係なく、誰もがその人の“いま”の人生を生きているはず。なのに、すべてが未来への担保のように扱われてしまっている現状があります。コロナ禍で、それがさらに強くなってきているのを感じるからこそ、僕らは対話をしていかなければいけないと思っています。
「刻まれたおでんは、おでんじゃないよな」
どうやら、特養の食事で出てきたおでんが刻まれていたようで、それが納得できなかったらしい。
普段は天下国家を論じる人の人間味あふれる一面を垣間見た気がして思わず吹き出しそうになったけど、でも、確かに真理を突いた言葉でもある。
「美味しいものを美味しく食べたい」というのは、本当にささやかな欲求だ。「生きた心地がする」というのは、まさに、こうした欲求が得られた時の感覚なのだろう。
でも、世間は時に、こうした感覚にさえ規制をかける。
自分でできないのだから。
万が一のことが心配だから。
他人様のお世話になっているのだから。
だから、「おでん」を刻まれるのは仕方がない。
──という具合に。
そして、多くの人は、こうした時に「諦めてくれる人」のことを「思慮深い」とか「わがままでない」と評価しがちだ。
(中略)でも、おでんがどうでもいいとされたら、その次は何が「どうでもいい」とされるのだろう。きっと、おでんに続く何かが「どうでもいい」とされてしまうはずだ。
※『まとまらない言葉を生きる』第十二話の、『「生きた心地」が削られる』より引用。発言者は、障害者運動家の花田春兆さん
話し合いは、何かを決めることだけが目的じゃない
──大人も子どもも、それぞれの“いま”を大切にしながら関わり合い、共に生きていくために、わたしたちはどんなことを意識すればよいのでしょうか。
荒井 それについては、今日はぜひ、青山さんにうかがいたいことがあったんです。私も事前に著書を拝見したのですが、保育の現場で、子どもたちが主体となって話し合う「ミーティング」をされていますよね。
私はいま、話し合うという行為に「結論」や「成果」が過剰に求められているような気がしています。でも、本来その営みには「みんなで同じ場に居る」とか「話したり話さなかったりすることを認めてもらう(ことで安心感を得る)」といった役割もあると思うんです。青山さんたちが実践されていることには、そうした存在感の確かめ合いのようなものを感じたのですが、いかがでしょうか。

青山 おっしゃる通りです。「ミーティング」と呼んでいますが、実際は会議ではなく「寄り合い」みたいなイメージなんですね
そこでは結論を必要としないし、お腹がすいたらもうやめよう、となることもある。シンプルに、「あなたはどう思う?」とその子自身に聞いていくことを繰り返しています。
荒井 特に子どもにとっては、そういうことのほうが大事ではないかと思うんです。でも、大人の立場からは誤解も多そうな気がして。
子どもたちが主役となって話し合いをする。そのこと自体が「子どもだけで結論を出させる」とか「意思決定できるようにする」とか、そんな文脈で受け取られがちなんじゃないかなと気になりました。
青山 合意形成が目的だと思われている方は保育者にも結構いらっしゃいますね。僕らがやっているのは、対話を通じて一人ひとりの存在を、くっきりさせることなんです。この視点が教育の現場で抜けるから、大人が集団をまとめるために使われるような「話し合い」になってしまうのではないでしょうか。
荒井 もしかすると「子ども中心」という言葉だけでは、うまく伝わらないのかもしれませんね。そもそも、子どもを「大人未満の存在」として見ることをやめないと変わらない気がします。
先ほどの話にもあったように、大人はつい子どもたちが生きている“いま”を、大人になる準備期間と考えてしまいがちです。でも本来、子どもたちは常に「子ども時間の本番」を生きている。青山さんのお話を聞きながら、「話し合いは結論を出しましょう」「大人がやることを子どもなりにやってみてごらん」みたいな方向に話が流れてしまうのも、やはりそこに原因があるように感じました。

青山 私たちは、「子ども中心」をもう少し紐解いて、「子どもの心に寄り添う」としています。子どもを大人未満の存在としてみなさないというのには賛成ですが、一方で、ではそのまま対等になりうるのか?という問題があるからです。
多くの場合、そのような意味での対等には、結果を見るとやはり大人が強者の位置に立って、大人のやりたいように子どもに対してふるまっていることが多くあります。でも、子どもが小さければ小さいほど、自分の意志を言語では表しません。いわば、大人と子どもとでは表している「言葉」が違うんです。
だから、子どもと大人とで対話的に関わるというときに、まずは大人のほうで子どもの「言葉」を聞き取れなければ、その関係は成り立たないと思っています。ただ口頭で「どう思う?」と聞くだけではなく、身体が溶け合うようなかかわりがないと本音がなかなか出てこない。表情の変化やちょっとしたしぐさを、こちらが「聞く」姿勢が必要です。
大人はどうしても、言語でのコミュニケーションに頼ってしまうのですが、“いま”を生きている子どもたちと関わるには、自分もその場に身をひたして、子どもたちの声に耳を澄まさなければいけないと思っています。
荒井 それはきっと、ミーティング以外の場面もですよね。青山さんは、「耳を澄ませる」ときにどういうことを意識されていますか?
青山 言葉をかける前の、近づき方でしょうか。急に「どうしたの?」と話しかけるのではなく、はじめはその子の視線に入らないように近づいて、まずはその子が見ている世界を、横で一緒に見るところからはじめる。
話しかけてもいいし、話さなくてもいいんです。傍にいるところから始めて、必要に応じて言葉を使っていく、という順番が大切だと僕は考えています。
「それは違う」と言葉にできる関係をつくる
──今回の対談では、まさに「言葉」そのものへの向き合い方もお聞きしたいと思っていました。言語によるコミュニケーションで、コロナ禍以外にお二人が感じた課題はありますか?
荒井 いろいろな世代の子どもと接する機会があるのですが、何というか、男の子たちの中に「女性には何でも頼みごとをしてよい」「女性というのは頼みごとを聞いてくれる存在だ」という価値観が、いつの間にかインストールされてしまうように感じることがあって、モヤモヤしています。大人社会の様子を見て、影響を受けるのでしょう。
なので、私たち夫婦はパートナーに対して何か頼みごとをするとき、パートナー間だからこそ、意識的に「きちんとお願いする言葉」を使うようにしています。ただ、この話を他の人とすると「家族の中でそんなに気を遣っていて疲れないの?」と言われることがあるんですよね。私はそれにもモヤモヤしてしまうんです。
私が大事にしたいのは「相手からぞんざいな言葉を使われない安心感」なのに、それに対して「相手に対してぞんざいな言葉を使ってもいい安心感」が対置されている。後者は「力」の上下関係を前提にした安心感ですよね。こうしたものが求められてしまうのは何なのか……。
青山 それはでも、まだまだあるかもしれませんね。
荒井 私自身、振り返ってみると、「相手に対してぞんざいな言葉を使ってもいい安心感」がまかり通る文化圏の中で生きてきたように思います。でもそれは、正直、自分自身もしんどかった。次の世代には引き継ぎたくないんです。
青山 僕もやはり言葉づかいはすごく大切だと思っています。保育の世界に入ったとき、一番最初に指導されたのがまさに自分の言葉づかいでした。師匠にあたる人に毎日、毎時間なにかしら怒られていましたね。
例えばあるとき、集まった子どもたちに「今日、なんでここに集まったか知ってる?」と軽く聞いたことがありました。すると、「あなたが集めたんでしょう。なんで子どもにそんな質問をするの?」と。
荒井 ああ、なるほど。
青山 集まってもらった意図を、自分からちゃんと言いなさいというわけです。そうやって、言葉を通じて身体を正されるような経験を何度もしました。
荒井さんは学校の現場で、学生さんへの言葉がけでどのようなことを気をつけていらっしゃいますか?
荒井 僕の場合、普段かかわりがあるのは大学生なのですが、本当に人間って十人十色で、「100人いたら100通りの答えがある」と実感しています。その中で、教員が個別のコミュニケーションや対応を一切間違えないのは、おそらく不可能なんです。
例えば、相手にどんな言葉をかけ、どんな呼び方をしたらよいのか。そうしたことは、本人のアイデンティティやお互いの関係性の組み合わせで決まっていくものなので、膨大な数の「それぞれの適切さ」が存在することになります。となると、汎用的な正解を求めることももちろん大事ですが、万が一こちらが相手の意志に反するコミュニケーションをとってしまったときに、学生が「こうしてください」とか「それはやめてください」などと言える制度や関係をつくっていくことも重要になってくるわけです。
ただ、先生という存在は「対応を間違えてはいけない」前提で見られることも多いので、難しさもありますね。人を追い込まないための、発想の転換が必要かもしれないと感じています。

荒井 また、私たちはいよいよこれから、「アフターコロナ」の社会について考えなければいけなくなります。今のままだと「コロナ以前の日常に戻そう」という空気感が強くはたらきそうですが、そこでつまづく人も必ず出てくると思うんです。
今日お話したような、実はさまざまな課題のあったコロナ前の社会に戻すのではなく、私たちは別の日常を目指さなければいけない。学生たちと接していると特にそう強く感じるのですが、青山さんはいかがですか?
青山 僕も同じことを感じています。コロナ禍で、例えば長時間労働による家庭や園の負担など、これまで表には見えていなかった実情も浮き彫りになりました。「その社会に戻っていいの?」という視点を持ちながら、僕たちはこれから表面化した課題について、徹底的に対話を重ねていくべきだと思っています。
Profile
Profile
![]()
-
荒井裕樹
二松學舍大学文学部 准教授
1980年東京都生まれ。専門は障害者文化論、日本近現代文学。東京大学大学院人文社会系研究科修了。博士(文学)。マイノリティの自己表現をテーマに研究を続ける。『障害者差別を問いなおす』(ちくま新書)、『まとまらない言葉を生きる』(柏書房)など多数。朝日新聞にてコラム「生きていく言葉」を連載中(隔週水曜日)。
- ライター:大島悠
-
ライター。普段は企業の情報資産を言語化・利活用する仕事をしている。「言葉」というものの深淵をのぞきこみつつ、おそるおそる対峙する日々。
この記事の連載Series
連載:こここインタビュー
![]() vol. 322025.03.18言葉を超えて誰もがつながる「身体表現」の魅力とは? 福祉を起点に広がるパフォーミングアーツ、生きづらさを変える可能性
vol. 322025.03.18言葉を超えて誰もがつながる「身体表現」の魅力とは? 福祉を起点に広がるパフォーミングアーツ、生きづらさを変える可能性![]() vol. 312024.10.09なぜ自分に価値があるか確認したくなるんだろう? 勅使川原真衣さんと新澤克憲さんによる「評価」を巡る対話
vol. 312024.10.09なぜ自分に価値があるか確認したくなるんだろう? 勅使川原真衣さんと新澤克憲さんによる「評価」を巡る対話![]() vol. 302024.09.13大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 写真家/訪問看護師 尾山直子さんをたずねて
vol. 302024.09.13大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 写真家/訪問看護師 尾山直子さんをたずねて![]() vol. 292024.09.07地域に根ざす園から、子どもも大人も混ざった“絶景“を生み出せたら。〈学校法人thanka〉が新ステートメント「手を繋ぎにいく」に込めた願い
vol. 292024.09.07地域に根ざす園から、子どもも大人も混ざった“絶景“を生み出せたら。〈学校法人thanka〉が新ステートメント「手を繋ぎにいく」に込めた願い![]() vol. 282024.08.30大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 株式会社Blanket 秋本可愛さんをたずねて
vol. 282024.08.30大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 株式会社Blanket 秋本可愛さんをたずねて![]() vol. 272024.07.25気軽な買い物体験から、「未来が良くなる」手応えを。〈フェリシモ〉の新カタログ『GO! PEACE!』制作の裏側
vol. 272024.07.25気軽な買い物体験から、「未来が良くなる」手応えを。〈フェリシモ〉の新カタログ『GO! PEACE!』制作の裏側![]() vol. 262024.04.30蓋された「小さな自分」の声に耳を傾けて。ケアを促す料理レッスンの場、就労支援の場──山口祐加さん×鞍田愛希子さん
vol. 262024.04.30蓋された「小さな自分」の声に耳を傾けて。ケアを促す料理レッスンの場、就労支援の場──山口祐加さん×鞍田愛希子さん![]() vol. 252024.04.10「インクルーシブ」は誰のための言葉? 老舗メーカー〈ジャクエツ〉×医師・紅谷浩之さんの、子どもに“遊びと友だち“を返す遊具
vol. 252024.04.10「インクルーシブ」は誰のための言葉? 老舗メーカー〈ジャクエツ〉×医師・紅谷浩之さんの、子どもに“遊びと友だち“を返す遊具![]() vol. 242024.03.29文化施設のウェブアクセシビリティを向上する。障害当事者との「建設的な対話」に必要なこととは?──伊敷政英さん×森司さん
vol. 242024.03.29文化施設のウェブアクセシビリティを向上する。障害当事者との「建設的な対話」に必要なこととは?──伊敷政英さん×森司さん![]() vol. 232024.03.27だれもが文化でつながるために。クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョーが見据えるこれからの文化施設のあり方とは。
vol. 232024.03.27だれもが文化でつながるために。クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョーが見据えるこれからの文化施設のあり方とは。![]() vol. 222023.12.22人のためってなんだろう? 他者にコントロールされない「LOVOT」から、“人間らしさ“を考える──伊藤亜紗さん×林要さん
vol. 222023.12.22人のためってなんだろう? 他者にコントロールされない「LOVOT」から、“人間らしさ“を考える──伊藤亜紗さん×林要さん![]() vol. 212023.11.08保育料ゼロを実現し、子育てを“みん営化”する。 学童保育施設〈fork toyama〉岡山史興さん
vol. 212023.11.08保育料ゼロを実現し、子育てを“みん営化”する。 学童保育施設〈fork toyama〉岡山史興さん![]() vol. 202023.05.29ともだちってなんだろう? 答えを出す必要はないけれど。新澤克憲さんとテンギョー・クラさんの対話から考える
vol. 202023.05.29ともだちってなんだろう? 答えを出す必要はないけれど。新澤克憲さんとテンギョー・クラさんの対話から考える![]() vol. 192023.05.23歌人・岡本真帆さん×西淡路希望の家・金武啓子さん対談。「感動」の発見、どう他者と分かち合いますか?
vol. 192023.05.23歌人・岡本真帆さん×西淡路希望の家・金武啓子さん対談。「感動」の発見、どう他者と分かち合いますか?![]() vol. 182023.03.20“みる”から始める、アーティストと支援現場のつなぎ役。日常の関係性を変える「TURN LAND プログラム」の挑戦
vol. 182023.03.20“みる”から始める、アーティストと支援現場のつなぎ役。日常の関係性を変える「TURN LAND プログラム」の挑戦![]() vol. 172023.03.15アート活動で、「できる/できない」を揺さぶる。日常の価値を言葉に変えるコーディネーターの役割
vol. 172023.03.15アート活動で、「できる/できない」を揺さぶる。日常の価値を言葉に変えるコーディネーターの役割![]() vol. 162023.03.03唯一の答えを探しすぎていないか? 下地ローレンス吉孝さん×なみちえさんと“わかりやすさ”について考える
vol. 162023.03.03唯一の答えを探しすぎていないか? 下地ローレンス吉孝さん×なみちえさんと“わかりやすさ”について考える![]() vol. 152023.02.15“わたし”と“あなた”それぞれの複雑さを大切にするには?──なみちえさん×下地ローレンス吉孝さんと共に考える
vol. 152023.02.15“わたし”と“あなた”それぞれの複雑さを大切にするには?──なみちえさん×下地ローレンス吉孝さんと共に考える![]() vol. 142022.12.23出会いを広げながら、協働を生む「メディア」を目指して──〈こここ〉シーズン2を振り返る
vol. 142022.12.23出会いを広げながら、協働を生む「メディア」を目指して──〈こここ〉シーズン2を振り返る![]() vol. 132022.12.19働くことも、映画祭も「みんなが心地よい」を目指して。GOOD NEWSとTHEATRE for ALLのインクルーシブな場づくり
vol. 132022.12.19働くことも、映画祭も「みんなが心地よい」を目指して。GOOD NEWSとTHEATRE for ALLのインクルーシブな場づくり![]() vol. 122022.10.14バリアフリーの映画祭を通して、「その人のまま」でいられる社会に。作家・川内有緒さん×THEATRE for ALL・金森香さん
vol. 122022.10.14バリアフリーの映画祭を通して、「その人のまま」でいられる社会に。作家・川内有緒さん×THEATRE for ALL・金森香さん![]() vol. 112022.09.13スポーツの可能性って何だろう? 「プロスポーツ」「ゆるスポーツ」から考える──岡田武史さん×澤田智洋さん
vol. 112022.09.13スポーツの可能性って何だろう? 「プロスポーツ」「ゆるスポーツ」から考える──岡田武史さん×澤田智洋さん![]() vol. 102022.03.31まだみぬ「表現」との出会いを、誰もが体験できる社会へ。障害のある人の芸術・文化活動を支える窓口が全国に
vol. 102022.03.31まだみぬ「表現」との出会いを、誰もが体験できる社会へ。障害のある人の芸術・文化活動を支える窓口が全国に![]() vol. 082021.12.24福祉をたずねて1年。編集部は何に出会い、悩んできた?──〈こここ〉振り返り座談会
vol. 082021.12.24福祉をたずねて1年。編集部は何に出会い、悩んできた?──〈こここ〉振り返り座談会![]() vol. 072021.11.24コロナ禍を経て新たな表現の協働へ ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[後編]
vol. 072021.11.24コロナ禍を経て新たな表現の協働へ ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[後編]![]() vol. 062021.11.24アートプロジェクトは福祉の現場で何を生み出す? ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[前編]
vol. 062021.11.24アートプロジェクトは福祉の現場で何を生み出す? ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[前編]![]() vol. 052021.10.18福祉施設が学びあいの拠点になることで育まれるものとは?ライフの学校・田中伸弥さん
vol. 052021.10.18福祉施設が学びあいの拠点になることで育まれるものとは?ライフの学校・田中伸弥さん![]() vol. 042021.06.03VR認知症を体験して気づいた、わからない世界へ手を伸ばし続ける大切さ。シルバーウッド 下河原忠道さん
vol. 042021.06.03VR認知症を体験して気づいた、わからない世界へ手を伸ばし続ける大切さ。シルバーウッド 下河原忠道さん![]() vol. 032021.04.15まだ名付けられていない感覚に出会う「遊び」の可能性とは? インタープリター 和田夏実さん
vol. 032021.04.15まだ名付けられていない感覚に出会う「遊び」の可能性とは? インタープリター 和田夏実さん![]() vol. 022021.04.15「助けて」とお互いに言い合えるのが、成熟した社会。ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ代表 志村季世恵さん
vol. 022021.04.15「助けて」とお互いに言い合えるのが、成熟した社会。ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ代表 志村季世恵さん![]() vol. 012021.04.15「お笑い」や「演劇」は他者の世界に寄り添うヒントをくれる。りんたろー。さん×菅原直樹さんが語る「介護の話」
vol. 012021.04.15「お笑い」や「演劇」は他者の世界に寄り添うヒントをくれる。りんたろー。さん×菅原直樹さんが語る「介護の話」