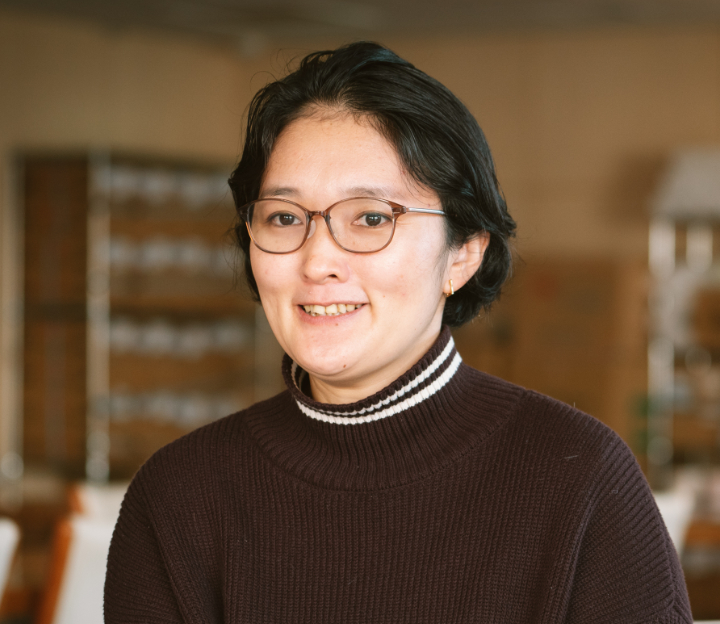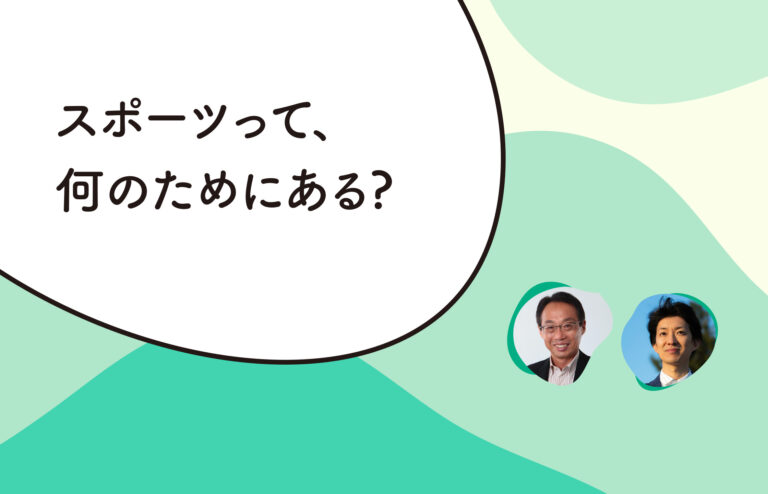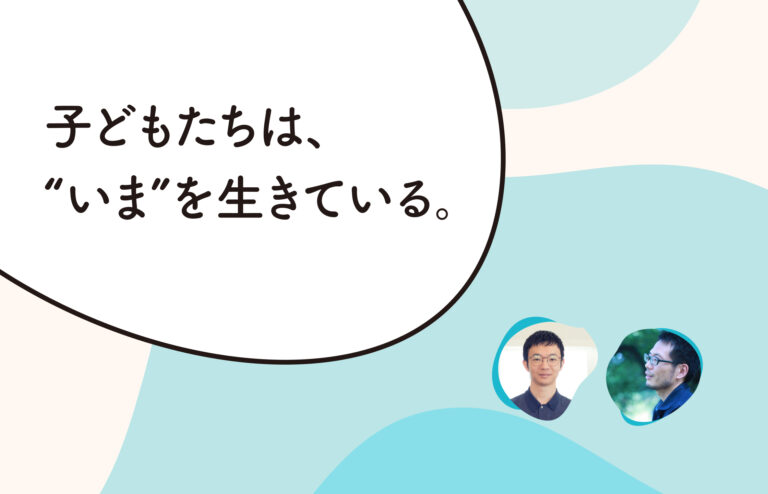アート活動で、「できる/できない」を揺さぶる。日常の価値を言葉に変えるコーディネーターの役割 こここインタビュー vol.17
私たちが暮らしている社会では、多くの場面で合理的な行動が重視されたり、経済的な生産性が求められたりしています。近年、多様な生き方や働き方を認め合う兆しも随所に見えていますが、すでに出来上がっている価値観やシステムを転換していくには、多大なエネルギーが必要なもの。その狭間で、今もさまざまな生きづらさを抱えている人は少なくありません。
そんな時流のなか、これまでになく「アート」に注目が集まっています。多くの人が「よりよく生きる」状況をつくるためにも、拙速に正解をもとめることから離れ、まずは一人ひとりが感じ、考えるプロセスが大切ではないか……そう考える人が増えている兆しを感じます。
アートを通じて個々の視点に立ち戻り、草の根から価値観そのものを見つめ直す道のりに、社会は立っているのかもしれません。
今回、そうした変化についてお話しいただいたのは、コミュニケーションデザイナーの加藤未礼さん、プロジェクトプランナーとして多くのワークショップを営む竹丸草子さん、アーティストでありアートディレクターとしても活動する富塚絵美さん。3人は、福祉事業所やコミュニティがアートプロジェクトを日常的に生む“拠点”となることを目指す、「TURN LAND プログラム」(主催:〈東京都〉〈公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京〉〈一般社団法人 谷中のおかって〉)のコーディネーターを務めています。
福祉現場とアート活動のあいだをつなぐ立場から紡ぎ出される言葉には、社会の転換のきっかけとなるような、大切な「問い」が散りばめられていました。
根源的なところから、生きる価値につながる「何か」をすくいあげたい
近年盛り上がりを見せる、福祉現場でのアート活動。〈こここ〉でもこれまで、各地のアートプロジェクトに関わる記事を公開したり、実際にいくつかの福祉施設で創作の場を訪れたりしてきました。そもそも福祉の現場に、アートの手法や考え方を持ち込むことには、どんな意味があるのでしょうか。
東京都板橋区の知的障害のある人の福祉施設〈小茂根福祉園〉で商品プロデュースに携わったことをきっかけに、各所で福祉職員向けのアート活動のためのワークショップなどを開催している加藤さんは、障害のある人の表現活動や展覧会が今盛り上がる背景には、「可能性を形にできる」ことへの切実な思いがあるのではと話してくれました。
加藤 今の社会構造の中では、障害のある方たちは学校でも、福祉事業所・施設でも、「できる/できない」の評価軸に晒されていることがよくあります。例えば手先が器用な人などは、一般企業の障害者雇用や、就労継続支援事業所で“仕事(福祉的就労)”につける。一方で、それができないために、ご自身も親御さんも「社会の中に入れてもらえない」という思いを抱かれている方も多くいるんです。
仕事を目的としない生活介護施設でも、生活支援の延長線上にあるモノづくりが、商品化につながることはよくあります。これまでの評価軸自体を「何をもってできるのか」「できないのか」と問い直したり、社会に存在を示したりするために、何かを形にすることには大きな意義があるのだと思います。

加藤さんの発言に、これまで幼稚園や小学校でのアーティストワークショップのコーディネートや、ファシリテーションを多数手がけた竹丸さんも同意します。最近は研究者として活動する竹丸さんもまた、教育現場における「できる/できない」の評価軸の強さを幾度となく感じてきました。
竹丸 世の中の一般的な基準で評価されてしまう子どもたちの中には、表現活動を通じて、それまでの「できる/できない」の軸をガラッと転換させることがあるんです。例えば学校でも事業所でも、ずっと「勉強ができない」「作業ができない」とされていた子が、アートに出会った途端に「すごい」と言われたり。周囲の見方が変わると、親御さんも本当に嬉しいんですよ。

進学の折には成績や身体条件で、就職の際には学歴やコミュニケーション能力で、その後も実績や経験で「できる/できない」と人々が振り分けられる現代社会。そうした価値観は、福祉の現場に携わる人々の意識にまで染み渡っているようです。
ですが、アートプロジェクトを通じてひとたび基準が“ひっくり返る”と、物ごとの多様な捉え方が生まれていきます。
加藤 仕事ができて自立できること、経済的な生産性が高いことだけを「生きる価値」だとする基準でいては、そこに当てはまらない人は生きる資格がないみたいな話になってしまう。それこそ、津久井やまゆり園事件の犯人が抱いていた優生思想につながる話ですよね。
でも、表現活動を長年やってきた、全国のさまざまな現場は、もっと根源的な「生きる価値」そのものを発信していると私は感じてきました。「できる/できない」という基準以外のところから、すくいあげたい何かがあるのだと思います。

アートが引き出す「多様な見方」を、いかに伝えるか
富塚 介護の現場に足を運ぶなかで、私も「高齢者が生きる価値を問われないためにも、アートが必要だ」と思うことがあります。どんな立場でも生きる価値があるはずなのに、労働力として見なされなくなる生活に、高齢者自身も適応できずにいる状況があるからです。
今まで社会に合わせてきた時間感覚や価値観もあるなかで、突然「多様だよ、自由だよ、好きにしていいよ」と言われても、困る人はたくさんいる。その発想の転換が必要なときに、アーティストという存在が効力を発揮します。
そう話してくれたのは、東京藝術大学大学院を卒業後に〈谷中のおかって〉を仲間と立ち上げ、アーティストでありながらアートディレクターとしても活躍している富塚さん。
社会にある既成概念を壊したり、変えたりする可能性に挑んでいるアーティストは、過去に自身が内面化した枠組みから離れ、個に立ち戻ることで新しい視座を得ようと、行動・創造の実践を積み重ねています。最初から「自由」を獲得していたわけではありません。だからこそ、戸惑う高齢者の心情を、理解しやすいのではといいます。
富塚 勇気がいるけど、本来自分が見せたいものは見せていいし、会いたい人がいるなら「会いたい」って言っていい。そうやって「ちょっとくらい迷惑をかけて生きていいんだよ」って背中を押す役は、アーティストがピッタリだなと思います。多くのアーティストは、そういうことに何度も悩みながら、それでも自分の気持ちを大事にしたほうがよかった、という経験をしてきているので。

竹丸 アーティストの役割は、私が見てきた現場で言えば「引き出す」イメージかもしれません。創作活動のなかで、アーティストとずっとやりとりをしている人が、自分でもよくわからないけれど「何か出てきた!」となる瞬間があるんですね。
それはアーティストが、人の心の奥をずっと見ていてくれているから。「もうちょっとない?」「ほらあった!」って、ぎゅーっと内面を引き出してくれる感じがしています。
富塚 本人の無意識下にあるものに焦点を当てる感じでしょうか。面白いですね。それをみんなで目撃してしまうと、内面を引き出されたその人に詳しくなった気持ちになる気がします。
そうやって人の内面に向かうアーティストもいるし、みんなが共有できるような体験をつくって、そこに人を巻き込んでいくアーティストもいる。アプローチの仕方はそれぞれですね。

異分野との協働の場で、新たな発見や気づきにより生き生きとする人の姿を、筆者もなんども目にし、その光景の美しさに魅了されてきました。
とはいえ、福祉職員とアーティストでは優先順位や時間の使い方、常識、言葉も違うなか、どのように協働しているのでしょうか。プロジェクトを走らせる過程では、課題もありそうです。
富塚 職員さんのなかから、「なぜ福祉施設でアートプログラムをやるのか」と疑問が出てきたときには説明の難しさを感じます。「利用者のため」という範囲を超えた関わりができるのがアートプログラムの大きな魅力なのですが、前のめりでやろうとされる方がいても、組織として引き受けることが難しい場合もあるんです。
また、どうしてもアーティストが“音楽や図画工作の先生”以上のイメージになっていかないことも課題です。限られたワークショップの時間だけでは、一時の楽しみとしてある以上の展開に、なかなか踏み込んでいけません。
竹丸 わかります。私が関わっているような特別支援学校だと、子どもを守るためにも、外から来る人を警戒してしまう傾向があるんです。そこに配慮しながら進めていくのは大変で、担当者までは顔が見えていても、その先の管理職の方がアートプログラムを理解されないことは実際にありますね。そこさえ突破すれば、すっと広がる手応えはあるのですが。

加藤 私の場合は福祉事業所などの職員さん向けにワークショップやセミナーをしているので、まさに今お話いただいた職員さんの悩みを聴きながら、一緒に乗り越える方法を考えてきた感じです。例えば、富塚さんが以前〈小茂根福祉園〉のワークショップで行っていた、アルミホイルをくしゃくしゃにしたりするような活動は、日常では“問題行動”に映ることもある。それをできるだけ多様な見方で、「その人にとっての表現ではないか」と解釈していければと思っています。
ただ、職員さんたちが広げる難しさはやはり感じていて。職員さんが自ら意義を感じて動けるようにサポートをしてきていても、自分たちの施設に戻ったときに、温度感が伝えづらくて孤軍奮闘してしまう人が多いのは、一つの大きな課題ですね。
生まれる価値を言語化し、共有していく「コーディネーター」の意義
3人が異口同音に「既に持っている価値観の転換」「関わる人の内面の変化」を語るアートプロジェクトの実践。一方で、アートといえば絵画や彫刻といった「技術的・美的に秀でたものをつくること」だと、狭義的に考える人もまだまだ多く存在しています。アートが持つ、「その人らしく生きる」ための力になる表現行為のプロセスに目を向けてもらうこともまた、プロジェクトを円滑にすすめるために欠かせないようです。
加藤 当事者の方がいつもたくさん描いている絵を、親御さんが稚拙だと考え、捨ててしまっているケースはよくあります。そうした表現行為に職員さんが光を当てようとしても、「外に出したら恥ずかしい」という気持ちになる方はまだまだ多いんです。
そこに対して、職員がどう説明をするのかが問われるのですが、実際には時間がかかりますよね。〈小茂根福祉園〉の『KOMONEST』も、商品としてさまざまなところで取り扱いがされ、外の人が「いいね」と言ってくれてはじめて、親御さんも「あ、いいんだな」となった過程がありました。

富塚 「芸術」というとどうしても、何か大きなもの、立派なもの、あるいは金属がぐにゃりと曲がっていて驚きのあるような作品などを期待するものですが、集中力が続かなかったり身体的な力が弱かったりする人には扱えない素材も多い。アーティストと障害のある参加者が、扱いやすい素材、例えば薄い紙で創作活動をしたとき、出来上がるものはただのくしゃっとした紙に見えるんですね。だから、持って帰ったらすぐに捨てられてしまう。
でも、つくった人にとっては、それが自分のアイデンティティを表現する大切な紙になっているわけです。アーティストとどこか抽象的な次元で心を通わせた、その時間自体が特別なものになっている。ですから、ワークショップをやっている側が言葉を尽くして、「これはすごい変化の末に出来上がった“作品”なんですよ」と、保護者や周りの人に価値を共有していかなくてはと思います。
せっかく創作行為を通じて内面が豊かに変わっていくきっかけを得たとしても、その人の日常のなかで、表現が歓迎される機会がなければ、活動をやめてしまうかもしれません。逆に表現活動のプロセスを見守れる人が、その「意味」を周囲に伝える努力があれば、内面だけでなく生き方そのものが変容していく可能性もあります。
竹丸 近親者だけでなく、もう少し遠い社会にまでプロジェクトで生まれている価値を伝えるのは、アーティストでもなく、施設職員でもない、私たちのようなプログラムをコーディネートする人の大切な役割だと思っています。職員さんたちもすごく想いを持っていて、社会に伝えたいことがある。そうしたことをキャッチして、きちんと外に出す人が必要なんです。
私は福祉施設で、現場の職員さんや評価の専門家も入ってもらって、ボトムアップで自分たちの感じている価値や想いを言葉にしていく活動をしています。自分たちで新しい評価軸をつくっていきたいなと。
富塚 社会的・公的な広がりを持てるまで、プロジェクトの価値を踏み込んで言語化する必要がありますよね。そこにはやはり、チーム戦でやっていかなければ実現できないこともあるので、「TURN LAND プログラム」のように運営を支える仕組みができたことは、すごく重要だと感じています。

新たな活動のなかで、互いに理解が及んでいないことがあれば、丁寧に説明をする。まだ言語化されていない価値が生まれていれば、外部の知恵も借りながら言葉をつむいで社会に発信し、価値を相対化していく。異分野間の協働の取り組みを、円滑かつ豊かなものに育てていくには、コミュニケーションのあいだをつなぐ存在が欠かせないようです。
そうして発信される内容こそ、個々の生き方や社会が変容するきっかけになってくれるでしょう。3人が関わる「TURN LAND プログラム」では、どの現場にもそれを担うコーディネーターがいて、福祉施設やコミュニティのアート活動に並走しています。後編(2023年3月20日公開)では、これまであまり光が当たってこなかったその役割の実際と、プログラムの内容について伺っていきます。
Information
TURN LAND プログラム
かつての「TURN」プロジェクト(“違い”を超えた出会いで表現を生み出すことを目指し、2015年から7年間開催されたアートプロジェクト)の後継事業として、2022年度に始動したプログラム。福祉事業所・施設や社会的支援を行う団体などがアートプロジェクトを日常的に展開する“拠点”となることを目指す「TURN LAND」「プレLAND」事業、コーディネーターの育成や知見の共有を目指す「TURN LAND オンラインサロン」「TURN LAND ミーティング」事業を核に活動中。
Profile
Profile
Profile
- ライター:友川綾子
-
gallery ayatsumugi ディレクター。アートマーケットとアートプロジェクトの経験から、アートの価値やアーティストとはなにかを探求する人。主にアートプロジェクト文脈で活躍するアーティストの展覧会を企画・記録集の編纂により、日本の美を世界に届ける。ほか、アートやカルチャー系媒体での編集・執筆、アートプロジェクトの広報業務などを担う。これまでドヤ街として知られる寿町(横浜)でのアートプロジェクト、フェスティバル・ボム(韓国・ソウル)、NPO法人スローレーベルが手がけるヨコハマ・パラトリエンナーレなどに携わる。著書『世界の現代アートを旅する』。プロセスワーク・コーチ。
この記事の連載Series
連載:こここインタビュー
![]() vol. 322025.03.18言葉を超えて誰もがつながる「身体表現」の魅力とは? 福祉を起点に広がるパフォーミングアーツ、生きづらさを変える可能性
vol. 322025.03.18言葉を超えて誰もがつながる「身体表現」の魅力とは? 福祉を起点に広がるパフォーミングアーツ、生きづらさを変える可能性![]() vol. 312024.10.09なぜ自分に価値があるか確認したくなるんだろう? 勅使川原真衣さんと新澤克憲さんによる「評価」を巡る対話
vol. 312024.10.09なぜ自分に価値があるか確認したくなるんだろう? 勅使川原真衣さんと新澤克憲さんによる「評価」を巡る対話![]() vol. 302024.09.13大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 写真家/訪問看護師 尾山直子さんをたずねて
vol. 302024.09.13大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 写真家/訪問看護師 尾山直子さんをたずねて![]() vol. 292024.09.07地域に根ざす園から、子どもも大人も混ざった“絶景“を生み出せたら。〈学校法人thanka〉が新ステートメント「手を繋ぎにいく」に込めた願い
vol. 292024.09.07地域に根ざす園から、子どもも大人も混ざった“絶景“を生み出せたら。〈学校法人thanka〉が新ステートメント「手を繋ぎにいく」に込めた願い![]() vol. 282024.08.30大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 株式会社Blanket 秋本可愛さんをたずねて
vol. 282024.08.30大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 株式会社Blanket 秋本可愛さんをたずねて![]() vol. 272024.07.25気軽な買い物体験から、「未来が良くなる」手応えを。〈フェリシモ〉の新カタログ『GO! PEACE!』制作の裏側
vol. 272024.07.25気軽な買い物体験から、「未来が良くなる」手応えを。〈フェリシモ〉の新カタログ『GO! PEACE!』制作の裏側![]() vol. 262024.04.30蓋された「小さな自分」の声に耳を傾けて。ケアを促す料理レッスンの場、就労支援の場──山口祐加さん×鞍田愛希子さん
vol. 262024.04.30蓋された「小さな自分」の声に耳を傾けて。ケアを促す料理レッスンの場、就労支援の場──山口祐加さん×鞍田愛希子さん![]() vol. 252024.04.10「インクルーシブ」は誰のための言葉? 老舗メーカー〈ジャクエツ〉×医師・紅谷浩之さんの、子どもに“遊びと友だち“を返す遊具
vol. 252024.04.10「インクルーシブ」は誰のための言葉? 老舗メーカー〈ジャクエツ〉×医師・紅谷浩之さんの、子どもに“遊びと友だち“を返す遊具![]() vol. 242024.03.29文化施設のウェブアクセシビリティを向上する。障害当事者との「建設的な対話」に必要なこととは?──伊敷政英さん×森司さん
vol. 242024.03.29文化施設のウェブアクセシビリティを向上する。障害当事者との「建設的な対話」に必要なこととは?──伊敷政英さん×森司さん![]() vol. 232024.03.27だれもが文化でつながるために。クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョーが見据えるこれからの文化施設のあり方とは。
vol. 232024.03.27だれもが文化でつながるために。クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョーが見据えるこれからの文化施設のあり方とは。![]() vol. 222023.12.22人のためってなんだろう? 他者にコントロールされない「LOVOT」から、“人間らしさ“を考える──伊藤亜紗さん×林要さん
vol. 222023.12.22人のためってなんだろう? 他者にコントロールされない「LOVOT」から、“人間らしさ“を考える──伊藤亜紗さん×林要さん![]() vol. 212023.11.08保育料ゼロを実現し、子育てを“みん営化”する。 学童保育施設〈fork toyama〉岡山史興さん
vol. 212023.11.08保育料ゼロを実現し、子育てを“みん営化”する。 学童保育施設〈fork toyama〉岡山史興さん![]() vol. 202023.05.29ともだちってなんだろう? 答えを出す必要はないけれど。新澤克憲さんとテンギョー・クラさんの対話から考える
vol. 202023.05.29ともだちってなんだろう? 答えを出す必要はないけれど。新澤克憲さんとテンギョー・クラさんの対話から考える![]() vol. 192023.05.23歌人・岡本真帆さん×西淡路希望の家・金武啓子さん対談。「感動」の発見、どう他者と分かち合いますか?
vol. 192023.05.23歌人・岡本真帆さん×西淡路希望の家・金武啓子さん対談。「感動」の発見、どう他者と分かち合いますか?![]() vol. 182023.03.20“みる”から始める、アーティストと支援現場のつなぎ役。日常の関係性を変える「TURN LAND プログラム」の挑戦
vol. 182023.03.20“みる”から始める、アーティストと支援現場のつなぎ役。日常の関係性を変える「TURN LAND プログラム」の挑戦![]() vol. 162023.03.03唯一の答えを探しすぎていないか? 下地ローレンス吉孝さん×なみちえさんと“わかりやすさ”について考える
vol. 162023.03.03唯一の答えを探しすぎていないか? 下地ローレンス吉孝さん×なみちえさんと“わかりやすさ”について考える![]() vol. 152023.02.15“わたし”と“あなた”それぞれの複雑さを大切にするには?──なみちえさん×下地ローレンス吉孝さんと共に考える
vol. 152023.02.15“わたし”と“あなた”それぞれの複雑さを大切にするには?──なみちえさん×下地ローレンス吉孝さんと共に考える![]() vol. 142022.12.23出会いを広げながら、協働を生む「メディア」を目指して──〈こここ〉シーズン2を振り返る
vol. 142022.12.23出会いを広げながら、協働を生む「メディア」を目指して──〈こここ〉シーズン2を振り返る![]() vol. 132022.12.19働くことも、映画祭も「みんなが心地よい」を目指して。GOOD NEWSとTHEATRE for ALLのインクルーシブな場づくり
vol. 132022.12.19働くことも、映画祭も「みんなが心地よい」を目指して。GOOD NEWSとTHEATRE for ALLのインクルーシブな場づくり![]() vol. 122022.10.14バリアフリーの映画祭を通して、「その人のまま」でいられる社会に。作家・川内有緒さん×THEATRE for ALL・金森香さん
vol. 122022.10.14バリアフリーの映画祭を通して、「その人のまま」でいられる社会に。作家・川内有緒さん×THEATRE for ALL・金森香さん![]() vol. 112022.09.13スポーツの可能性って何だろう? 「プロスポーツ」「ゆるスポーツ」から考える──岡田武史さん×澤田智洋さん
vol. 112022.09.13スポーツの可能性って何だろう? 「プロスポーツ」「ゆるスポーツ」から考える──岡田武史さん×澤田智洋さん![]() vol. 102022.03.31まだみぬ「表現」との出会いを、誰もが体験できる社会へ。障害のある人の芸術・文化活動を支える窓口が全国に
vol. 102022.03.31まだみぬ「表現」との出会いを、誰もが体験できる社会へ。障害のある人の芸術・文化活動を支える窓口が全国に![]() vol. 092022.02.09コロナ禍で「消される」声に、どう耳を傾ける? 次の社会をつくる言葉と対話のあり方──荒井裕樹さん×青山誠さん
vol. 092022.02.09コロナ禍で「消される」声に、どう耳を傾ける? 次の社会をつくる言葉と対話のあり方──荒井裕樹さん×青山誠さん![]() vol. 082021.12.24福祉をたずねて1年。編集部は何に出会い、悩んできた?──〈こここ〉振り返り座談会
vol. 082021.12.24福祉をたずねて1年。編集部は何に出会い、悩んできた?──〈こここ〉振り返り座談会![]() vol. 072021.11.24コロナ禍を経て新たな表現の協働へ ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[後編]
vol. 072021.11.24コロナ禍を経て新たな表現の協働へ ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[後編]![]() vol. 062021.11.24アートプロジェクトは福祉の現場で何を生み出す? ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[前編]
vol. 062021.11.24アートプロジェクトは福祉の現場で何を生み出す? ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[前編]![]() vol. 052021.10.18福祉施設が学びあいの拠点になることで育まれるものとは?ライフの学校・田中伸弥さん
vol. 052021.10.18福祉施設が学びあいの拠点になることで育まれるものとは?ライフの学校・田中伸弥さん![]() vol. 042021.06.03VR認知症を体験して気づいた、わからない世界へ手を伸ばし続ける大切さ。シルバーウッド 下河原忠道さん
vol. 042021.06.03VR認知症を体験して気づいた、わからない世界へ手を伸ばし続ける大切さ。シルバーウッド 下河原忠道さん![]() vol. 032021.04.15まだ名付けられていない感覚に出会う「遊び」の可能性とは? インタープリター 和田夏実さん
vol. 032021.04.15まだ名付けられていない感覚に出会う「遊び」の可能性とは? インタープリター 和田夏実さん![]() vol. 022021.04.15「助けて」とお互いに言い合えるのが、成熟した社会。ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ代表 志村季世恵さん
vol. 022021.04.15「助けて」とお互いに言い合えるのが、成熟した社会。ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ代表 志村季世恵さん![]() vol. 012021.04.15「お笑い」や「演劇」は他者の世界に寄り添うヒントをくれる。りんたろー。さん×菅原直樹さんが語る「介護の話」
vol. 012021.04.15「お笑い」や「演劇」は他者の世界に寄り添うヒントをくれる。りんたろー。さん×菅原直樹さんが語る「介護の話」