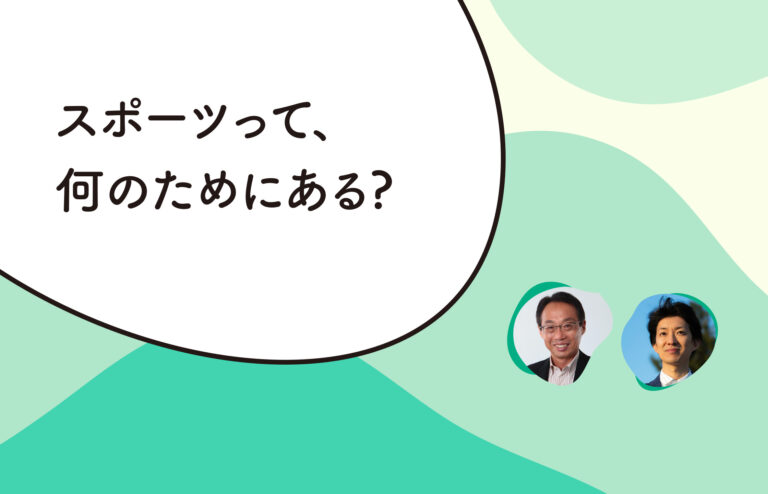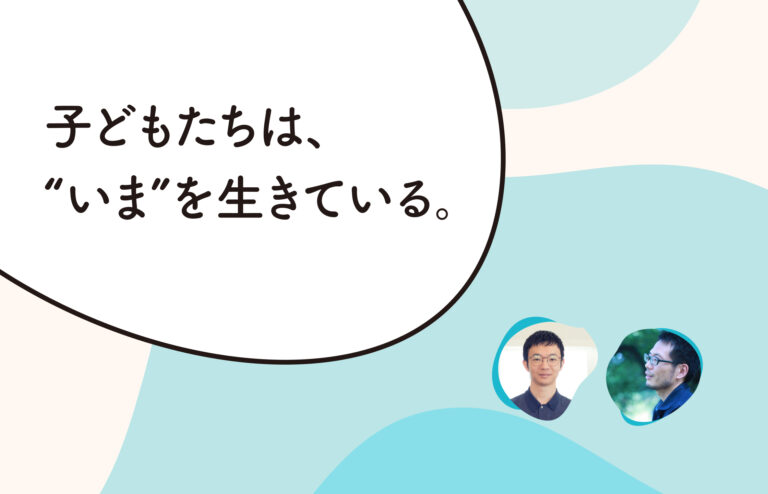文化施設のウェブアクセシビリティを向上する。障害当事者との「建設的な対話」に必要なこととは?──伊敷政英さん×森司さん こここインタビュー vol.24
美術館や劇場・ホールを訪れるとき、みなさんは事前にどんな情報を調べるだろう。
展覧会や公演の内容はもちろん、開館日や駅からのルート、人によっては車椅子用のスロープや鑑賞サポートの有無を調べることもある。さらに、その情報を目ではなく耳で探す人もいる。一人一人の身体的・心理的な特性によって、必要な情報や調べ方はじつに多様だ。しかし、多様な人たちが必要とする情報を十分に伝えられていない現状がある。
「だれもが文化につながる」ことを目指すプロジェクト「Creative Well-being Tokyo /クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョー」(以下「CWT」)は、さまざまな特性を持つ障害当事者と意見を交わしながら、都立美術館・博物館のウェブサイトのアクセシビリティ向上に取り組んでいる。この取り組みは、CWTにとってどのような意義を持ち、どのようなプロセスで進行しているのだろうか。
今回、CWTの進行役を務める森司さんと対談したのは、障害者専門のクラウドソーシングサービス「サニーバンク」のアドバイザーとして本プロジェクトに伴走してきた、先天性の視覚障害当事者である伊敷政英(いしき・まさひで)さん。
異なる特性を持つ人どうしが一つのプロジェクト進める際に欠かせない「建設的な対話」をキーワードに、これまでの取り組みを二人の視点から振り返った。
ウェブサイトは文化施設の入口
文化施設における「アクセシビリティ」には、さまざまな側面がある。作品の字幕や音声ガイダンスから、館内の段差やエレベーターの有無、そしてウェブサイトの情報まで。
CWTが発足して最初に行った仕事は、こうした多岐にわたるアクセシビリティを3つの段階に整理することだった。利用者に情報を届ける「情報サポート」、都立文化施設で作品を楽しむための「鑑賞サポート」、そして障害当事者がプログラムに主体的に参画するための「参画サポート」。この区分けにより、それぞれの文化施設が共通の認識のもとでアクセシビリティ向上に取り組みはじめている。
そのうち、CWTがまず着手したのは「情報サポート」。都立文化施設のウェブアクセシビリティを向上することだった。
森さん(以下「森」):文化施設に足を運んでもらうためには、まず「そもそも」の情報を伝える必要があります。今回の取り組みは、ウェブサイトをただ改修するというものではなく、そこを入口に鑑賞サポートや参画サポートへと連動していくものです。

とはいえ、「誰もが使いやすいサイト」を作ろうとしても、文化施設のウェブ担当者の知識だけでは限界がある。そこで、CWTは障害当事者と意見を交わしながら進行する方向に舵を切った。
森:従来のホームページは自分たちが言いたいことだけを載せていました。でも、さまざまなペルソナを持つ人たちにユーザー目線でチェックしてもらわないと、今回のプロジェクトは進められないと思ったんです。
こうした背景のもとでCWTに伴走することになったのが、伊敷さんがアドバイザーを務める「サニーバンク」。働く意思やスキルはあるが、既存の枠組みの中で仕事を得るのがむずかしい障害当事者(通称「ワーカー」)と企業をマッチングするサービスを提供している。

CWTとサニーバンクが伴走をはじめて半年。都立文化施設のウェブサイトのアクセシビリティチェックの目処が一通り立った今、伊敷さんは現状をどう捉えているのだろうか。
伊敷さん(以下「伊敷」):いろんな文化施設で、障害のある人も楽しめるようなイベントやプログラムが企画されています。その情報は各施設のウェブサイトに載ってはいるのですが、なかなかたどり着けない奥の方にあったり、説明文がわずかに書いてあるだけだったり、アクセシブルとは言いがたいのが現状です。それらの情報をどうやって当事者に伝えていくか。それができないと、まず文化施設に来てもらうことが難しいですよね。

近年、さまざまな特性の人が文化施設を楽しめる機会は少しずつ増えてきている。目の見える人と見えない人が言葉を交わしながら作品を鑑賞する「対話型鑑賞」や、弱視の人がスマホやタブレット端末の「拡大鏡」の機能を使って鑑賞する方法など、可能性はこれからも広がっていくだろう。
しかし、そもそもの情報を得ることができなければ文化施設での体験は始まらない。まずは文化施設の「入口」となるウェブサイトのアクセシビリティを整えることが、CWTの取り組みの出発点となるのだ。
「固まる」から気づきが生まれる
ここからは、ウェブアクセシビリティ向上の取り組みをどのようなプロセスで進めているのか具体的に見ていこう。
サニーバンクが提供しているウェブアクセシビリティ診断の中には、「障害当事者によるレビュー」を重視したメニューがある。
ひとつは、異なる特性を持つワーカーさんがそれぞれ普段使用している環境でウェブサイトをチェックしてレポートし、それらを報告書としてまとめる方法。もうひとつは「合同レビュー」の形で実施するもので、クライアントの担当者と数名のワーカーさんがオンラインで集まり、主要なページに対して意見を交わす方法だ。
今回のプロジェクトでは、対象となる9つの都立文化施設等が、それぞれ2回ずつ、計18回のオンライン合同レビューを行っている。

診断ではなく合同レビューを採用した理由を森さんはこう話す。
森:文字のレポートよりも、当事者の声を聞く方が学びが多いんです。普段はユーザーが「不自由だな」と感じたとしても、その声はこちらまで届きませんよね。なのでユーザーの意見を聞き、気づきを得る機会をつくることが重要だと考えました。
実際にオンライン合同レビューを行う中で、「フォトジェニックな写真を配置すれば良い」と思い込んでいたウェブサイトの写真についてこんな気づきがあったそうだ。
森:ウェブサイトをつくるときって写真を多用するじゃないですか。でも、スクリーンリーダーを使用している人にとって写真は情報にならないわけです。だから代替テキストで写真を過不足なく説明する必要が出てくるのですが、これが非常にむずかしい。これまであたりまえだと思っていた部分をどう情報保障するか考えたときに、固まってしまうんですね。

伊敷さんは、このように「固まる」ことをむしろポジティブなきっかけとしてとらえている。
伊敷:でも、「固まる」ってすごく重要だと思いますよ。今までは固まりすらしなかったんですから。「固まる」のは大事な一歩です。
オンライン合同レビューを行う際、伊敷さんは事前にワーカーさんには事前に見ておいてほしいページをある程度伝えておく。そのとき重要なのが、ワーカーさん自身が実際にその施設へ行く視点でチェックしてもらうことだという。
伊敷:視覚障害のあるワーカーさんであれば、やっぱり最寄り駅からの詳しい道案内が必要です。Googleマップでは不十分なんですね。言葉と図だけではなく、写真もほしい。説明の仕方も、点字ブロックはあるか、途中の目印は何か、などいろんなリクエストが出てきます。
ウェブアクセシビリティを向上することは、障害のない人にとってもメリットがあると伊敷さんは続ける。
伊敷:たとえば、地方から東京へ旅行に来た人が美術館に行こうとすると、土地勘がないのでGoogleマップだけではたどり着けない場合があります。そのとき、丁寧に作ったルート案内が役立つんです。

ウェブアクセシビリティは、障害者のためだけに特別に取り組まなければいけないことではない。World Wide Web(www)を考案した「ウェブの父」と呼ばれるティム・バーナーズ=リーも言うように*、ウェブの本質とは「誰でも情報にアクセスできる」ことであり、ウェブアクセシビリティを考える際に忘れてはいけない前提である。
※「The power of the Web is in its universality.Access by everyone regardless of disability is an essential aspect.(ウェブの力はその普遍性にあります。 障がいに関係なく誰もがアクセスできることはひとつの本質的な側面です。)」
とはいえ、障害には個別性やグラデーションがあるため、膨大な視点とニーズが出てくるはずだ。合同レビューで挙げられたリクエストに、施設側はどのように対応していくのだろうか。
森:ウェブアクセシビリティは最初から100%にできるものではありません。まず何をどこまでやるか・やらないかを覚えて、どのように維持していくかを学んでいくプロセスが必要になります。できるところから確実にしていくしかないと思っています。
二人のセッションで印象的だったのが、「固まる」という表現だ。「固まる」というのは、これまであたりまえだと思っていた流れが一度止まること。そこには新たなあたりまえが生まれるチャンスがある。
では森さんが「固まる」ことができたのはなぜか。それは、異なる特性を持つ相手の言葉に耳を傾けたからだった。
建設的な対話に必要なこととは?
今回のプロジェクトの重要なキーワードの一つが「建設的な対話」である。建設的な対話とは、意思決定をする際に、お互いが意見を交わしながら双方が歩み寄るプロセスのこと。合理的配慮を提供する上でも欠かせない要素だ。
言葉にするのは簡単だが、いわば世界の前提が異なる人どうしが意思決定をする場面にはいつでも困難がつきまとう。今回のプロジェクトは、伊敷さん、サニーバンクのワーカーさん、文化施設の担当者など、障害者と健常者が入り混じって進んでいく。具体的に、建設的な対話はどのように進められているのだろうか。
伊敷さんは美術館でのこんな記憶から話を始めた。
伊敷:私は弱視でしたが、当時は、iPadのカメラアプリを使って拡大すれば作品が見えることもあって、そういう時は鑑賞を楽しむことができました。ただ、施設が認めてくれない場合もあるんです。iPadを作品に向けた瞬間に監視員さんに「写真を撮らないでください」と言われて泣く泣く諦めたり、一度は許可されたものの「他のお客様からクレームがありました」と言われて使いづらくなったり。私は私で周りの状況がわからないし、監視員さんは監視員さんで私のことがわからないので、コミュニケーションが生まれないんですよ。

目の前の状況を先入観によって判断し、誰かが楽しむ可能性の芽を摘んでしまう。多くの場合、それは無自覚に行われていることだ。だからこそ、双方に歩み寄ることが大事だと森さんは話す。
森:「できること」を前提にしすぎている側面が大きいですよね。建設的な対話というのは、要するにインクルーシブな環境をつくるということ。属人的にできるようになったものを、少しずつ組織化していくプロセスを経るしかないと思っています。そして肝心なのは、アクセシビリティの取り組みは、障害のある人に対して「良いことをしている」わけではないということです。
伊敷:そうですね。やっぱり「あたりまえ」なんです。
アクセシビリティは、よく障害者への「特別」な対応だと思われがちだ。しかし、その考え方は「健常者が障害者のためにやってあげる」という一方的な構図に基づくものである。であり、そこに本当の意味での双方向の対話は生まれ得ないだろう。あらゆる人が情報にアクセスできることは「あたりまえ」であり、これまで損なわれていた尊厳を回復するための取り組みであるという前提を忘れてはいけないのだ。
では、オンライン合同レビューにおいて「建設的な対話」をうながすために、サニーバンクではどのようなことを意識しているのだろうか。
伊敷:サニーバンクのサービスは、ビジネスという側面だけでなく、多様な人の意見を聞く機会を世の中に提供するという側面もあります。ただ否定的に指摘するのではなく、「ここはすごくわかりやすいけど、こっちはもうちょっと改善してほしい」「こういう改善の方向性だと嬉しい」という話ができる場にしたいと思っています。

サニーバンクでは、合同レビューの際にウェブサイトの「良い点」も挙げるようにワーカーさんに伝えるのだそう。否定ではなく批評の視点こそが「建設的な対話」を促進させるのだろう。
今回、CWTの合同レビューで特に高評価を得たのが、2023年にウェブサイトをリニューアルした東京都庭園美術館のカレンダーだ。カレンダーはプログラムのタイトルや展示期間に加え、開館日や閉館日、場合によっては一部施設のみ開館など、様々な情報を記載する必要があり、デザインが難しいのだという。
伊敷:東京都庭園美術館ウェブサイトのカレンダーは、スクリーンリーダーで読んでも基本的な情報をある程度把握できます。シンプルにまとまっているんですね。また、目で見たときにノイズにならないように、かつスクリーンリーダーにも対応するため、「見えないけど読み上げる」という隠しテキストが入っています。このテキストの入れ方が絶妙で、冗長になりすぎず、それでいて読み上げにも違和感がありません。このような隠しテキストは視覚的には表示されないので、運用時に見逃されてしまうことも多く、実装するのはハードルが高いです。
オンライン合同レビューでは、「休館日の情報が色だけで伝えられていてスクリーンリーダーでは理解できなかった」「通常のタイル型のデザインのほうがわかりやすい」などの意見もあり、課題が全くないわけではないのですが、視覚的な情報とスクリーンリーダーで聴いたときの情報のバランスをうまくとっていて、かつそのバランスが運用しても崩れないように設計されているのはすごいと思います。美術館と制作会社さんがコミュニケーションを積み重ねてたどり着いたデザインなんだろうと思います。

東京都庭園美術館には、さらに素晴らしい点があると伊敷さんは続ける。
伊敷:東京都庭園美術館は古い建物(旧朝香宮邸)をそのまま美術館にしているため段差が多い。それでも美術館としてやっていくということで、ウェブサイトに「車椅子の方はスロープなどの対応をするので事前に連絡をください」と書いてあるんです。これをウェブサイトに書けるところはなかなかないし、ここまでやってくれるんだったら行ってみたいと思いますね。
これまで、各館2回ずつの合同レビューをしてきた中で、伊敷さんはある手ごたえを感じていると話す。
伊敷:1回目の合同レビューでは、もしかしたら「何を言われるんだろう」と不安を感じている方もいらしたかもしれません。そもそも障害のある人とあまり話したことがない人もいらっしゃいます。でも、2回目になると、逆にみなさんの方から向かってきてくれるんです。1回だけだと「いろいろ言われてつらい2時間だったな」と思うかもしれないけど、そこで何か一つでも気づきを得られたら「もっとこうなんじゃないか、あれもあるんじゃないか」とどんどんアイデアが湧いてくる。それは素晴らしいことですよね。
森:人って不思議なもので、続けていると見えるものが変わってくるんですよね。それが「誰もが使いやすいサイト」につながっていく。気づいて、目が養われて、改善のレベルが上がるプロセスは、非常にクリエイティブなことだと思っています。

言葉を持つことで視点が変わる
各文化施設でのオンライン合同レビューが一通り完了したあとは、どのようなフェーズに入っていくのだろうか。
これまでのプロセスを経て、森さんは「言葉を持つこと」の重要性を実感しているという。
森:「ウェブアクセシビリティ」や「建設的な対話」という言葉に出会うことで、ウェブサイトを見る視点や考え方が少しずつ変わってきました。このプロジェクトは、言葉を持って、対話をすることから始まるのだと改めて思います。
CWTのプロジェクトの中間タームは2025年。今回のウェブアクセシビリティを皮切りに、全体的な取り組みのレベルを一気に上げていく必要性も認識している。
森:様々な特性を持つ人たちにとって、文化施設が身近な存在になるためにどうしたらいいか。ここからは、もう一歩先のレベルの発想でサイトをつくったり、情報を提供する必要があると思っています。鑑賞サポートやプログラムの開発を含め、CWTの取り組み全体が繋がっていかなければいけません。


他方で、ここまでプロジェクトに伴走してきた伊敷さんは、今後の課題をこう分析する。
伊敷:各館ごとにウェブサイト運用の体制が異なったり、リニューアルの時期がバラバラですよね。扱っているコンテンツも違いますし、それぞれのサイトに特性があります。その違いを受け止めながら、どうしたら有意義なサポートができるかというのは、私たちの頑張りどころだと思っています。
それぞれが異なる特徴を持つ文化施設の間で、どうしたら相乗効果が生まれるか。9つの施設が同じタイミングで一気に取り組みを行ってきた背景には、文化施設同士のコミュニケーションを加速させるねらいもあると森さんは言う。
森:施設間でコミュニケーションを取る場面で、アクセシビリティについての会話が交わされることで、全体的な機運が作られていくと考えています。ここからはウェブアクセシビリティについての共通のガイドラインを用意するフェーズに入る予定です。
伊敷さんも、具体的なレベルでのネットワークを築くことで、合理的配慮の質が向上するのではないかと考えている。
伊敷:改善した点はもちろん、要望はされたけれど見送ったものなど、各館ごとに様々な判断や経験があると思うんです。それらを蓄積して、横断的に共有したり検索できる機会があるといいなと思います。
ウェブアクセシビリティの取り組みにおいて、「やらなくてもいい理由」を見つけるのは簡単だ。しかし、CWTが掲げる「だれもが文化につながる」状態を実現するには、アクセシビリティを「やるか/やらないか」ではなく、「どうやるか/どこまでやるか」という視点にレベルを引き上げる必要がある。
森さんも言うように、CWTの勝負どころはアクセシビリティの意識をいかに日常的な業務に組み込んでいけるかだろう。そのためには施設どうしのネットワークがカギになるはずだ。各文化施設のアクセシビリティチェックが完了したいま、「特別」を「あたりまえ」に変えられるかどうかは、CWTの次の一歩にかかっている。

ウェブアクセシビリティはコミュニケーションのデザイン
最後に、今後の展望を二人の視点から伺った。
CWTの取り組みを高く評価する伊敷さんは、アクセシビリティの向上によって新たな鑑賞体験が生まれる可能性を予感している。
伊敷:やっぱり文化施設の体験って楽しいんですよね。たとえば「対話型鑑賞」では、同じ作品を見ているはずなのに全然違う意見が出てきます。これがすごく面白くて、あっという間に時間が過ぎるんです。また、先日東京都美術館で開催していた「上野アーティストプロジェクト2023 いのちをうつすー菌類、植物、動物、人間」(会期:2023年11月16日~2024年1月8日)という展覧会では、一部のバード・カービング(野鳥彫刻)を触ることができたんです。虫をくわえている姿や飛んでいる姿に触れることができたり、鳴き声も聴けてとても楽しかったです。文化施設に多様な特性を持つ人が来るようになると、新しい企画のアイデアや鑑賞の仕方が生まれてくるのではないかと思います。

森:アクセシビリティの取り組みは、コミュニケーションのデザインであり、デバイスを使った可能性のクリエイションだと思います。だから、文化事業としてもっと果敢にやっていいと考えています。ただ同時に、むずかしさを思い知らされながら取り組んでいるというのも正直なところ。やはり当事者の方と対話を重ね、学びながらやっていくしかないんです。
義務感からクリエイティブへ──。アクセシビリティに新たな視点を見出す人が増えれば、プログラムの開発や鑑賞の仕方にも相乗効果が生まれるはずだ。
森:さまざまな特性を持つ人たちに期待されたいんです。縁遠いところだと思われるのではなく、期待されて、その期待に応えられる文化施設でありたい。それは文化施設が社会に参加していく姿勢の表れだと思うんです。
森さんはこう言葉を締めくくった。
森:ウェブアクセシビリティは息の長い取り組みです。一喜一憂しすぎず、歩みを止めることなく進んでいけたらと思っています。
森さんと伊敷さんの対談を聞きながら感じていたのは、新たなクリエイションは異なる者どうしの出会いから生まれるということだ。前回の取材時に森さんが言っていた「伴走すると新しい世界に行ける」という言葉は、これまでプロジェクトの最前線を走ってきた森さんの実感から生まれた表現なのだろう。
自分とは異なる特性を持つ人と出会ったとき、一度立ち止まって、相手の言葉に耳を傾けてみる。そして対話を重ねながら、同じ方角に向かって走り始めた先にこそ、まだ見ぬ景色は広がっているはずだ。CWTにおけるこの双方向のプロセスは、都立文化施設と障害当事者による「共創」の機会にほかならない。
Information
クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョー
Profile
![]()
-
伊敷政英
Cocktails代表、アクセシビリティコンサルタント、視覚障害当事者
1977年東京都生まれ。先天性の視覚障害があり、2020年からはほぼ全盲の状態が続いている。2001年頃よりウェブアクセシビリティに関心を持ち、2003年よりコンサルタントとして企業や自治体・省庁などのウェブサイトにおけるアクセシビリティ改善業務に従事。2010年に個人事業としてCocktailzでの活動をスタート。障害者専門のクラウドソーシングサービス サニーバンクでアドバイザーも務めている。
Profile
![]()
-
森司
公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京事業部事業調整課長、女子美術大学特別招聘教授
1960年愛知県生まれ。水戸芸術館で学芸員を務めた後、公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京事業推進室事業調整課長に就任。2009年より「東京アートポイント計画」を担い、ディレクターとしてNPOなどとの協働によるまちなかでのアートプロジェクトの企画運営を行う。2011~2020年まで「東京都による芸術文化を活用する被災地支援事業(Art Support Tohoku-Tokyo)」のディレクター、 2015~2021年まで東京2020公認文化オリンピアード事業「東京キャラバン」「TURN」のプロジェクトディレクターを務めた。現在「クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョー」を主導し、財団としてのアクセシビリティの向上等にあたっている。
- ライター:椋本湧也
-
1994年、東京生まれ、京都在住。都内の出版社と家具メーカーでの仕事を経て、現在京都で出版社の立ち上げ準備中。書籍の編集や執筆、個人出版なども行う。著作に『26歳計画』『それでも変わらないもの』『日常をうたう〈8月15日の日記集〉』。
この記事の連載Series
連載:こここインタビュー
![]() vol. 322025.03.18言葉を超えて誰もがつながる「身体表現」の魅力とは? 福祉を起点に広がるパフォーミングアーツ、生きづらさを変える可能性
vol. 322025.03.18言葉を超えて誰もがつながる「身体表現」の魅力とは? 福祉を起点に広がるパフォーミングアーツ、生きづらさを変える可能性![]() vol. 312024.10.09なぜ自分に価値があるか確認したくなるんだろう? 勅使川原真衣さんと新澤克憲さんによる「評価」を巡る対話
vol. 312024.10.09なぜ自分に価値があるか確認したくなるんだろう? 勅使川原真衣さんと新澤克憲さんによる「評価」を巡る対話![]() vol. 302024.09.13大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 写真家/訪問看護師 尾山直子さんをたずねて
vol. 302024.09.13大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 写真家/訪問看護師 尾山直子さんをたずねて![]() vol. 292024.09.07地域に根ざす園から、子どもも大人も混ざった“絶景“を生み出せたら。〈学校法人thanka〉が新ステートメント「手を繋ぎにいく」に込めた願い
vol. 292024.09.07地域に根ざす園から、子どもも大人も混ざった“絶景“を生み出せたら。〈学校法人thanka〉が新ステートメント「手を繋ぎにいく」に込めた願い![]() vol. 282024.08.30大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 株式会社Blanket 秋本可愛さんをたずねて
vol. 282024.08.30大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 株式会社Blanket 秋本可愛さんをたずねて![]() vol. 272024.07.25気軽な買い物体験から、「未来が良くなる」手応えを。〈フェリシモ〉の新カタログ『GO! PEACE!』制作の裏側
vol. 272024.07.25気軽な買い物体験から、「未来が良くなる」手応えを。〈フェリシモ〉の新カタログ『GO! PEACE!』制作の裏側![]() vol. 262024.04.30蓋された「小さな自分」の声に耳を傾けて。ケアを促す料理レッスンの場、就労支援の場──山口祐加さん×鞍田愛希子さん
vol. 262024.04.30蓋された「小さな自分」の声に耳を傾けて。ケアを促す料理レッスンの場、就労支援の場──山口祐加さん×鞍田愛希子さん![]() vol. 252024.04.10「インクルーシブ」は誰のための言葉? 老舗メーカー〈ジャクエツ〉×医師・紅谷浩之さんの、子どもに“遊びと友だち“を返す遊具
vol. 252024.04.10「インクルーシブ」は誰のための言葉? 老舗メーカー〈ジャクエツ〉×医師・紅谷浩之さんの、子どもに“遊びと友だち“を返す遊具![]() vol. 232024.03.27だれもが文化でつながるために。クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョーが見据えるこれからの文化施設のあり方とは。
vol. 232024.03.27だれもが文化でつながるために。クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョーが見据えるこれからの文化施設のあり方とは。![]() vol. 222023.12.22人のためってなんだろう? 他者にコントロールされない「LOVOT」から、“人間らしさ“を考える──伊藤亜紗さん×林要さん
vol. 222023.12.22人のためってなんだろう? 他者にコントロールされない「LOVOT」から、“人間らしさ“を考える──伊藤亜紗さん×林要さん![]() vol. 212023.11.08保育料ゼロを実現し、子育てを“みん営化”する。 学童保育施設〈fork toyama〉岡山史興さん
vol. 212023.11.08保育料ゼロを実現し、子育てを“みん営化”する。 学童保育施設〈fork toyama〉岡山史興さん![]() vol. 202023.05.29ともだちってなんだろう? 答えを出す必要はないけれど。新澤克憲さんとテンギョー・クラさんの対話から考える
vol. 202023.05.29ともだちってなんだろう? 答えを出す必要はないけれど。新澤克憲さんとテンギョー・クラさんの対話から考える![]() vol. 192023.05.23歌人・岡本真帆さん×西淡路希望の家・金武啓子さん対談。「感動」の発見、どう他者と分かち合いますか?
vol. 192023.05.23歌人・岡本真帆さん×西淡路希望の家・金武啓子さん対談。「感動」の発見、どう他者と分かち合いますか?![]() vol. 182023.03.20“みる”から始める、アーティストと支援現場のつなぎ役。日常の関係性を変える「TURN LAND プログラム」の挑戦
vol. 182023.03.20“みる”から始める、アーティストと支援現場のつなぎ役。日常の関係性を変える「TURN LAND プログラム」の挑戦![]() vol. 172023.03.15アート活動で、「できる/できない」を揺さぶる。日常の価値を言葉に変えるコーディネーターの役割
vol. 172023.03.15アート活動で、「できる/できない」を揺さぶる。日常の価値を言葉に変えるコーディネーターの役割![]() vol. 162023.03.03唯一の答えを探しすぎていないか? 下地ローレンス吉孝さん×なみちえさんと“わかりやすさ”について考える
vol. 162023.03.03唯一の答えを探しすぎていないか? 下地ローレンス吉孝さん×なみちえさんと“わかりやすさ”について考える![]() vol. 152023.02.15“わたし”と“あなた”それぞれの複雑さを大切にするには?──なみちえさん×下地ローレンス吉孝さんと共に考える
vol. 152023.02.15“わたし”と“あなた”それぞれの複雑さを大切にするには?──なみちえさん×下地ローレンス吉孝さんと共に考える![]() vol. 142022.12.23出会いを広げながら、協働を生む「メディア」を目指して──〈こここ〉シーズン2を振り返る
vol. 142022.12.23出会いを広げながら、協働を生む「メディア」を目指して──〈こここ〉シーズン2を振り返る![]() vol. 132022.12.19働くことも、映画祭も「みんなが心地よい」を目指して。GOOD NEWSとTHEATRE for ALLのインクルーシブな場づくり
vol. 132022.12.19働くことも、映画祭も「みんなが心地よい」を目指して。GOOD NEWSとTHEATRE for ALLのインクルーシブな場づくり![]() vol. 122022.10.14バリアフリーの映画祭を通して、「その人のまま」でいられる社会に。作家・川内有緒さん×THEATRE for ALL・金森香さん
vol. 122022.10.14バリアフリーの映画祭を通して、「その人のまま」でいられる社会に。作家・川内有緒さん×THEATRE for ALL・金森香さん![]() vol. 112022.09.13スポーツの可能性って何だろう? 「プロスポーツ」「ゆるスポーツ」から考える──岡田武史さん×澤田智洋さん
vol. 112022.09.13スポーツの可能性って何だろう? 「プロスポーツ」「ゆるスポーツ」から考える──岡田武史さん×澤田智洋さん![]() vol. 102022.03.31まだみぬ「表現」との出会いを、誰もが体験できる社会へ。障害のある人の芸術・文化活動を支える窓口が全国に
vol. 102022.03.31まだみぬ「表現」との出会いを、誰もが体験できる社会へ。障害のある人の芸術・文化活動を支える窓口が全国に![]() vol. 092022.02.09コロナ禍で「消される」声に、どう耳を傾ける? 次の社会をつくる言葉と対話のあり方──荒井裕樹さん×青山誠さん
vol. 092022.02.09コロナ禍で「消される」声に、どう耳を傾ける? 次の社会をつくる言葉と対話のあり方──荒井裕樹さん×青山誠さん![]() vol. 082021.12.24福祉をたずねて1年。編集部は何に出会い、悩んできた?──〈こここ〉振り返り座談会
vol. 082021.12.24福祉をたずねて1年。編集部は何に出会い、悩んできた?──〈こここ〉振り返り座談会![]() vol. 072021.11.24コロナ禍を経て新たな表現の協働へ ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[後編]
vol. 072021.11.24コロナ禍を経て新たな表現の協働へ ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[後編]![]() vol. 062021.11.24アートプロジェクトは福祉の現場で何を生み出す? ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[前編]
vol. 062021.11.24アートプロジェクトは福祉の現場で何を生み出す? ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[前編]![]() vol. 052021.10.18福祉施設が学びあいの拠点になることで育まれるものとは?ライフの学校・田中伸弥さん
vol. 052021.10.18福祉施設が学びあいの拠点になることで育まれるものとは?ライフの学校・田中伸弥さん![]() vol. 042021.06.03VR認知症を体験して気づいた、わからない世界へ手を伸ばし続ける大切さ。シルバーウッド 下河原忠道さん
vol. 042021.06.03VR認知症を体験して気づいた、わからない世界へ手を伸ばし続ける大切さ。シルバーウッド 下河原忠道さん![]() vol. 032021.04.15まだ名付けられていない感覚に出会う「遊び」の可能性とは? インタープリター 和田夏実さん
vol. 032021.04.15まだ名付けられていない感覚に出会う「遊び」の可能性とは? インタープリター 和田夏実さん![]() vol. 022021.04.15「助けて」とお互いに言い合えるのが、成熟した社会。ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ代表 志村季世恵さん
vol. 022021.04.15「助けて」とお互いに言い合えるのが、成熟した社会。ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ代表 志村季世恵さん![]() vol. 012021.04.15「お笑い」や「演劇」は他者の世界に寄り添うヒントをくれる。りんたろー。さん×菅原直樹さんが語る「介護の話」
vol. 012021.04.15「お笑い」や「演劇」は他者の世界に寄り添うヒントをくれる。りんたろー。さん×菅原直樹さんが語る「介護の話」