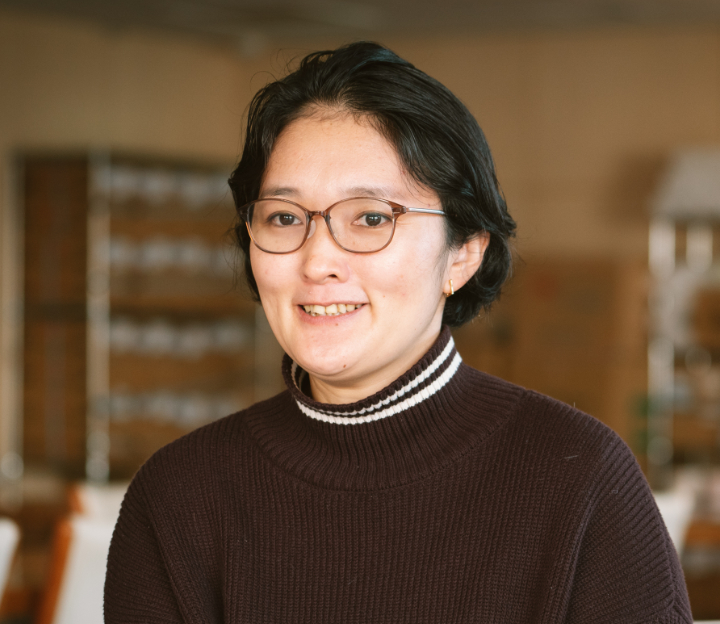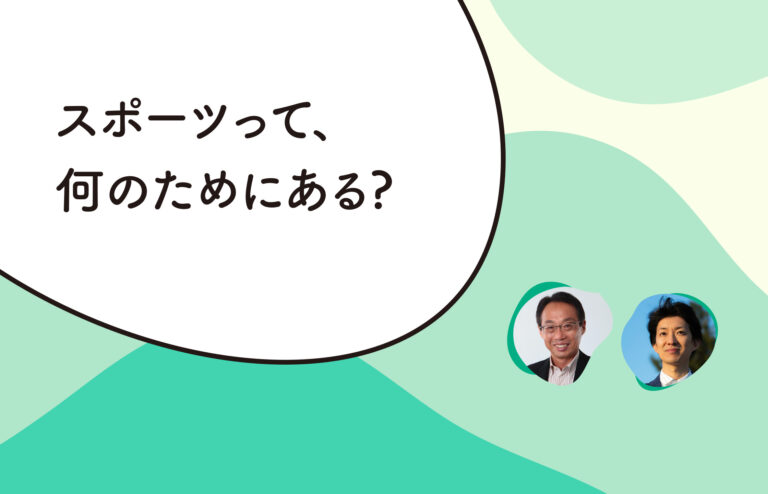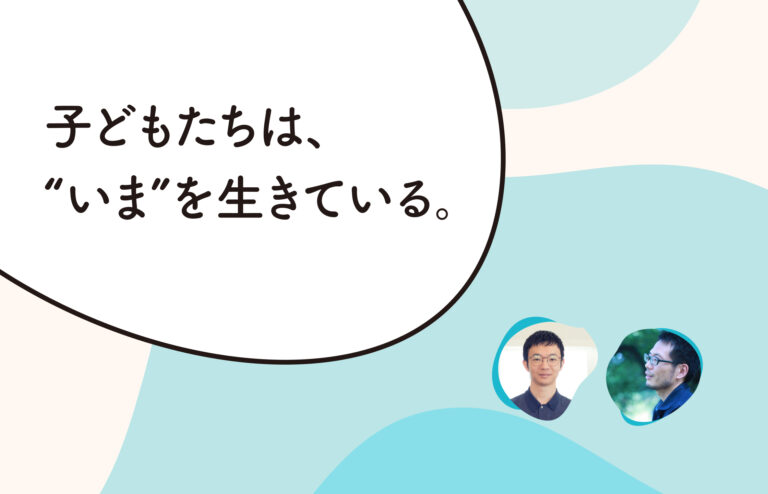“みる”から始める、アーティストと支援現場のつなぎ役。日常の関係性を変える「TURN LAND プログラム」の挑戦 こここインタビュー vol.18
「ずっと『できない』とされていた子の見方が、ガラリと変わる。アートにはそんな、周囲の価値観を変化させる力があります」
異分野の協働プロジェクトの現場で、互いの“違い”に創発されて新たな意味が見出され、より多様な価値観が許容されるようになる。そんな実践を重ねてきた、コミュニケーションデザイナーの加藤未礼さん、プロジェクトプランナーの竹丸草子さん、アーティスト/アートディレクターの富塚絵美さんの前回のお話からは、社会的にインパクトを生むためにも、分野同士のあいだをつなぎ意義を言葉にする存在——「コーディネーター」の関わりが鍵となることが明らかになってきました。
とはいえ、一般にこうした人材の役割は理解されづらく、必要な職能についても、さまざまな分野で試行錯誤しながら作り上げている段階です。2022年に再始動した「TURN LAND プログラム」(主催:〈東京都〉〈公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京〉〈一般社団法人 谷中のおかって〉)では、福祉施設や文化活動を行う団体との連携のなかで、そうしたコーディネーターの育成に力を入れているといいますが、まだまだ、言語化されていない部分もあるでしょう。
今回も引き続き、「TURN LAND プログラム」でコーディネーターを務める3人に、コーディネーターとは何か、そしてどんな風に育てていきたいかお話を伺いました。模索が続く本プログラムの意義とともに、彼女たちが今現在感じていることを深掘りしていきます。

事務担当? 調整役? 翻訳者? 「コーディネーター」とは何か
そもそも、アートプロジェクトになぜコーディネーターは必要なのでしょうか。前編での、プロジェクトの価値を内外に伝える役目についても、もし言語化が得意な事業所職員やアーティストがいれば、2者だけでやれなくないともいえます。まずはあえて独立した第三者が必要な理由について、コーディネーター研究をしている竹丸さんを筆頭に紐解いていただきました。
竹丸 まず一般的に、コーディネーターは人をつないだり調整したりする存在と理解されていますね。その上で、事務作業やマネジメントも担う場合が多いです。
もちろんそこも大事ですが、私はコーディネーターを、場を「みる」ことができる人だと思っています。ジャッジメントをせずに、ただ場が成立するように見守る存在ですね。
富塚 コーディネーターは点数をつける役ではありませんからね。ディレクターではないので、方向づけることもしない。
竹丸 そう。起きていることの判断は職員さんだったり、アーティストだったりができるのですが、そこで齟齬が生じる場合もある。そのとき、プロジェクトの場が壊れてしまってはダメなので、あいだにひゅっと入るのがコーディネーターの役割なんです。

竹丸 なぜコーディネーターの必要性が疑問視されるかというと、そうした現場での“黒子”としての役割が、外からは見えづらいからじゃないでしょうか。実際には、福祉の専門性、アートの専門性をそれぞれ理解しながら場を上手に支えているのですが、いざという時の「ひゅっと」がさりげなさすぎて、誰も気がつかない(笑)。
富塚 竹丸さんが今おっしゃった「みる」って大事ですよね。「見る」「診る」「観る」……いろんな漢字がありますから。
竹丸 全部があてはまるかもしれません。障害のある人も、その方に関わるアーティストもみていますし、職員さんもみている。「普段だったらこの人はこうなると調子が悪くなる」と職員さんが止めるようなときに、アーティストは「この人はただ楽しいだけかもしれない」と考えるかもしれない。それらを含めた全ての状況を、コーディネーターは「みる」必要があります。
仮にそれぞれのジャッジメントの方向が食い違っていたとしても、その場がよい状態に成立し続ける方法を考える。そんなバランサーとしての役割は、2者では担うことのできないものでしょう。
加藤 例えばある職員さんが、「他の職員さんのこれまでの判断」や「親御さんの通常行動」とは異なる関わり方をしようとしても、気を遣って言い出せないことがあるんです。失敗すれば自傷行為や他害につながったりする心配もあるので、簡単には提案できないんですね。
でも、そうしたリスクにもちろん配慮しながらも、アーティストは「こうかもね」って言える立場にある。これまでにない関わり方で可能性を引き出せるのは、アートプロジェクトならではの良さかもしれません。

富塚 そう、だからこそ、どんなアーティストでもいいわけではないんですよね。「これ以上は絶対に利用者に負荷はかけられない」となった際は、ストップもできるアーティストを選ぶ必要がある。そのとき、一緒に「じゃあどうしようか」と考えられるような関係をコーディネーターが築いておくことが重要かなと思います。
竹丸 アーティストが「ちょっとアプローチを変えてみよう」と仕掛けたことで、ごろっと場が変わるのを、私はこれまでに何度もみてきました。でも、そうした普段と違う提案って、みんなが安心・安全な場じゃないと出てこないんです。コーディネーターがそのための信頼関係をつくっていてはじめて、アーティストが自由に発言できるのではないかと思います。
例えば、2者間で判断の齟齬が生まれたとき、どちらかが譲ったり、考えを言い出せずに留めてしまったりしがちなものです。ただ、中立的な第三者として「あいだ」でクッションになってくれるコーディネーターになら、それぞれの想いを留めずに共有しやすいでしょう。そうしたやり取りのなかで、今までの判断にない新たな可能性を探っていけることが、アートプロジェクトの難しさであり、醍醐味かもしれません。
前例や慣習に則った関係性から、怖がらずに一歩踏み出せるようになる。アートを通じてそんな可能性をコーディネーターが生み出しうることを、3人の話は示しているのではないでしょうか。
地域に“拠点”を生みながら、福祉とアートのつなぎ手を育成する「TURN LAND プログラム」
2022年に新たな形で動き出した「TURN LAND プログラム」は、かつての「TURN」プロジェクト(“違い”を超えた出会いで表現を生み出すことを目指し、2015年から7年間開催されたアートプロジェクト)を引き継ぎ、さまざまな福祉施設や社会的支援を行う団体と連携しながら、現在は11のプログラムを展開しています。
その中核となる事業「TURN LAND」では、年間を通じて福祉事業者や団体が、アーティストと日常的にプログラムを実施し、地域に文化をひらく“拠点”として活動。また、「TURN LAND」実施の準備段階で、アーティストやコーディネーターと現場にあったプロジェクトを構想する「プレLAND」事業も実施し、今後に向けたリサーチや打ち合わせを進めています。


並行して、プログラムに参加するコーディネーターや、施設職員などに向けた研修事業も開始。ゲストに参加アーティストを迎え、施設職員や参加団体のスタッフがアートプロジェクト運営を学び合う「TURN LAND オンラインサロン」はこれまでに5回、地域の方々も交えた活動報告会「TURN LAND ミーティング」も2回実施されました。


初年度とはいえ、着実に企画を進める「TURN LAND」「プレLAND」ですが、先ほどの3人の話にあったように、異分野間での協働プロジェクトを予定調和に終わらせないためには、コーディネーターの育成こそ重要な意味を持ちます。
実際に本プログラムでは、どんなコーディネーターを育てようとしているのでしょうか。また、どんな人がコーディネーター向きだといえるのでしょうか。
富塚 ファシリテーターとしての能力は必要です。竹丸さんがおっしゃったように、現場をみながら柔軟に対応できること。また、いろいろな人のニーズを把握して、整理しながら、プロジェクトとしてデザインをしていけることも求められますね。
そして、アートやアーティストを怖がらないのも大事(笑)。現場をみていると、アーティストに気を遣いすぎているなと感じることが多くて。もっと普通にコミュニケーションをしてもらえたら、と思うときがあります。
竹丸 コミュニケーションでいえば、何があっても笑い飛ばせることも大切ですよね。一方で、そうやってコーディネーターに必要な能力の話をしだすと、多種多様な能力を身につけたすごい人が理想となってしまうんですが、私は「個人の人生や経験をそのまま持ってきていい」と思っているんです。実はそれが、場を「みる」力になる。
決して平均化しようとか、「これができたらコーディネーター」というのではない。いろいろなコーディネーターがいることが大事だと思うんですよね。

富塚 一人で全てを担おうと思わない人がいいのかもしれませんね。実際に「TURN LAND プログラム」は、チームでなければできないことをしているから。その点を理解できることは大事ですね。
加藤 タフで、対話力があって、場の空気を読める……人間的な力が求められるポジションですが、その人の強みやその人らしさを生かして、その人それぞれの在り方で基本はいいと思っています。私はその手前の部分で、コーディネーターをはじめ現場の自由をできる限り担保するために、全体設計をきちっとしておくことも重要だと感じました。事務局の役割、施設の役割をみんながきちんと理解できて、その中で複数のコーディネーターが動けるような体制があるといいなって思います。
障害者福祉に高齢者福祉、児童福祉はもちろん、映画館などでの地域コミュニティを含む、たくさんの現場とつながっている「TURN LAND プログラム」。これからコーディネーターとして育っていきたいと考える人は、福祉施設に関わった体験が全くなくても、すでに何らかの経験値や想いを持っていることでしょう。
まずはすでにある良さを生かしながら、不足している知識や経験を補っていく。それができれば、より3人の語るコーディネーター像に向けても成長できるはずです。

アートが生み出す「関係性の再構築」を、社会に広げていくには
有機的に異分野間の「あいだ」をつなげることができるコーディネーターが増えていくと、社会にはどんなインパクトがでるのでしょうか。今回のお話の舞台である福祉とアートの場以外でも、広く社会で活かせる可能性がまだまだありそうです。
最後に3人それぞれから、現場での実感をふまえた言葉をいただきました。
竹丸 アート活動をご一緒するなかで、私が関わっている福祉施設の職員さんがあるとき、「自信がついた」と言ったことがありました。利用者さんの表現を地域の方々にも楽しんでいただく、知っていただくといっても、今までは「もしかしたら何か問題が起きるかも」とどこかで思ってしまっていたそうなんですね。最初は信じていても、どこかで自信をなくしてしまうんですよ。
だから、アーティストが入ることで、職員さんと利用者さんの関係が再構築されることには意味があって。普段の「支援をする/される」関係が、アートというわからないことに「一緒に飛び込む」仲間になったりするからです。横並びの関係になれる、時には福祉職員さんが利用者さんから教えてもらうような関係性が生まれるのは、本当にウェルビーイングだなと思うんですよ。
富塚 アーティストが入ることで、人の見方を変えていける可能性は本当にたくさんあります。例えばここ〈はぁとぴあ原宿〉で、給食を食べる前に必ず皿の底をみる利用者さんがいたんですね。それをアーティストが面白がって、「またみた!なんでみるんだろう?」って言ったことで、初めて職員さんもそのことに気がついたんです。
どっちでもいいことのように思えますが、たぶんプログラムのない日常でも、その人がお皿の底をみているのに職員さんは気づくようになるはずです。そんな積み重ねが、どんな忙しい現場でも、ちょっとほのぼのする時間を増やすことにつながるのではないかなと。
その可能性は福祉に限らず、きっとどの分野にもあって、私はどんな業種の現場にも入っていきたいと思っています。社会のいろいろな現場に呼ばれていくと、発言の自由のなさや、想像力さえも限られてしまうことを目にする機会があちこちにありますから。

加藤 このコロナ禍でさまざまな現場が守りに入ってしまっているので、そこにアーティストがポンっと入っていくだけでは、うまくいかない可能性もあります。だからこそ、そこにコーディネーターがいて、価値を言語化したり、「あいだ」を調整したりする意義は大きいと思います。
福祉は本来、全ての生きる人に関係のあること。でも、今は少し価値観が凝り固まっていて、その担い手も自分たちの価値にあまり気がついていないことが多いんです。そんなとき、最初は訳がわからなくてもアーティストが入ってくることで、いろいろな視座が持てるようになる。想像力を失ってしまったままだと、福祉に関わる仕事はできませんからね。
私たちの固定された価値観をほぐしてくれ、想像力を喚起してくれるアーティストとの出会い。人と人との関係性を、再構築させてくれるアートプロジェクト。それが成立する場を創出してくれるコーディネーターが存在することで、新たな価値を獲得する実践がひろがり、社会にも共有されていきます。
異なる立場の「あいだ」をつなぐ役割の大切さが、世に広く認められるよう、社会も変わっていけたらいいなと感じます。
Information
TURN LAND プログラム
Profile
Profile
Profile
- ライター:友川綾子
-
gallery ayatsumugi ディレクター。アートマーケットとアートプロジェクトの経験から、アートの価値やアーティストとはなにかを探求する人。主にアートプロジェクト文脈で活躍するアーティストの展覧会を企画・記録集の編纂により、日本の美を世界に届ける。ほか、アートやカルチャー系媒体での編集・執筆、アートプロジェクトの広報業務などを担う。これまでドヤ街として知られる寿町(横浜)でのアートプロジェクト、フェスティバル・ボム(韓国・ソウル)、NPO法人スローレーベルが手がけるヨコハマ・パラトリエンナーレなどに携わる。著書『世界の現代アートを旅する』。プロセスワーク・コーチ。
この記事の連載Series
連載:こここインタビュー
![]() vol. 272024.07.25気軽な買い物体験から、「未来が良くなる」手応えを。〈フェリシモ〉の新カタログ『GO! PEACE!』制作の裏側
vol. 272024.07.25気軽な買い物体験から、「未来が良くなる」手応えを。〈フェリシモ〉の新カタログ『GO! PEACE!』制作の裏側![]() vol. 262024.04.30蓋された「小さな自分」の声に耳を傾けて。ケアを促す料理レッスンの場、就労支援の場──山口祐加さん×鞍田愛希子さん
vol. 262024.04.30蓋された「小さな自分」の声に耳を傾けて。ケアを促す料理レッスンの場、就労支援の場──山口祐加さん×鞍田愛希子さん![]() vol. 252024.04.10「インクルーシブ」は誰のための言葉? 老舗メーカー〈ジャクエツ〉×医師・紅谷浩之さんの、子どもに“遊びと友だち“を返す遊具
vol. 252024.04.10「インクルーシブ」は誰のための言葉? 老舗メーカー〈ジャクエツ〉×医師・紅谷浩之さんの、子どもに“遊びと友だち“を返す遊具![]() vol. 242024.03.29文化施設のウェブアクセシビリティを向上する。障害当事者との「建設的な対話」に必要なこととは?──伊敷政英さん×森司さん
vol. 242024.03.29文化施設のウェブアクセシビリティを向上する。障害当事者との「建設的な対話」に必要なこととは?──伊敷政英さん×森司さん![]() vol. 232024.03.27だれもが文化でつながるために。クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョーが見据えるこれからの文化施設のあり方とは。
vol. 232024.03.27だれもが文化でつながるために。クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョーが見据えるこれからの文化施設のあり方とは。![]() vol. 222023.12.22人のためってなんだろう? 他者にコントロールされない「LOVOT」から、“人間らしさ“を考える──伊藤亜紗さん×林要さん
vol. 222023.12.22人のためってなんだろう? 他者にコントロールされない「LOVOT」から、“人間らしさ“を考える──伊藤亜紗さん×林要さん![]() vol. 212023.11.08保育料ゼロを実現し、子育てを“みん営化”する。 学童保育施設〈fork toyama〉岡山史興さん
vol. 212023.11.08保育料ゼロを実現し、子育てを“みん営化”する。 学童保育施設〈fork toyama〉岡山史興さん![]() vol. 202023.05.29ともだちってなんだろう? 答えを出す必要はないけれど。新澤克憲さんとテンギョー・クラさんの対話から考える
vol. 202023.05.29ともだちってなんだろう? 答えを出す必要はないけれど。新澤克憲さんとテンギョー・クラさんの対話から考える![]() vol. 192023.05.23歌人・岡本真帆さん×西淡路希望の家・金武啓子さん対談。「感動」の発見、どう他者と分かち合いますか?
vol. 192023.05.23歌人・岡本真帆さん×西淡路希望の家・金武啓子さん対談。「感動」の発見、どう他者と分かち合いますか?![]() vol. 172023.03.15アート活動で、「できる/できない」を揺さぶる。日常の価値を言葉に変えるコーディネーターの役割
vol. 172023.03.15アート活動で、「できる/できない」を揺さぶる。日常の価値を言葉に変えるコーディネーターの役割![]() vol. 162023.03.03唯一の答えを探しすぎていないか? 下地ローレンス吉孝さん×なみちえさんと“わかりやすさ”について考える
vol. 162023.03.03唯一の答えを探しすぎていないか? 下地ローレンス吉孝さん×なみちえさんと“わかりやすさ”について考える![]() vol. 152023.02.15“わたし”と“あなた”それぞれの複雑さを大切にするには?──なみちえさん×下地ローレンス吉孝さんと共に考える
vol. 152023.02.15“わたし”と“あなた”それぞれの複雑さを大切にするには?──なみちえさん×下地ローレンス吉孝さんと共に考える![]() vol. 142022.12.23出会いを広げながら、協働を生む「メディア」を目指して──〈こここ〉シーズン2を振り返る
vol. 142022.12.23出会いを広げながら、協働を生む「メディア」を目指して──〈こここ〉シーズン2を振り返る![]() vol. 132022.12.19働くことも、映画祭も「みんなが心地よい」を目指して。GOOD NEWSとTHEATRE for ALLのインクルーシブな場づくり
vol. 132022.12.19働くことも、映画祭も「みんなが心地よい」を目指して。GOOD NEWSとTHEATRE for ALLのインクルーシブな場づくり![]() vol. 122022.10.14バリアフリーの映画祭を通して、「その人のまま」でいられる社会に。作家・川内有緒さん×THEATRE for ALL・金森香さん
vol. 122022.10.14バリアフリーの映画祭を通して、「その人のまま」でいられる社会に。作家・川内有緒さん×THEATRE for ALL・金森香さん![]() vol. 112022.09.13スポーツの可能性って何だろう? 「プロスポーツ」「ゆるスポーツ」から考える──岡田武史さん×澤田智洋さん
vol. 112022.09.13スポーツの可能性って何だろう? 「プロスポーツ」「ゆるスポーツ」から考える──岡田武史さん×澤田智洋さん![]() vol. 102022.03.31まだみぬ「表現」との出会いを、誰もが体験できる社会へ。障害のある人の芸術・文化活動を支える窓口が全国に
vol. 102022.03.31まだみぬ「表現」との出会いを、誰もが体験できる社会へ。障害のある人の芸術・文化活動を支える窓口が全国に![]() vol. 092022.02.09コロナ禍で「消される」声に、どう耳を傾ける? 次の社会をつくる言葉と対話のあり方──荒井裕樹さん×青山誠さん
vol. 092022.02.09コロナ禍で「消される」声に、どう耳を傾ける? 次の社会をつくる言葉と対話のあり方──荒井裕樹さん×青山誠さん![]() vol. 082021.12.24福祉をたずねて1年。編集部は何に出会い、悩んできた?──〈こここ〉振り返り座談会
vol. 082021.12.24福祉をたずねて1年。編集部は何に出会い、悩んできた?──〈こここ〉振り返り座談会![]() vol. 072021.11.24コロナ禍を経て新たな表現の協働へ ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[後編]
vol. 072021.11.24コロナ禍を経て新たな表現の協働へ ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[後編]![]() vol. 062021.11.24アートプロジェクトは福祉の現場で何を生み出す? ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[前編]
vol. 062021.11.24アートプロジェクトは福祉の現場で何を生み出す? ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[前編]![]() vol. 052021.10.18福祉施設が学びあいの拠点になることで育まれるものとは?ライフの学校・田中伸弥さん
vol. 052021.10.18福祉施設が学びあいの拠点になることで育まれるものとは?ライフの学校・田中伸弥さん![]() vol. 042021.06.03VR認知症を体験して気づいた、わからない世界へ手を伸ばし続ける大切さ。シルバーウッド 下河原忠道さん
vol. 042021.06.03VR認知症を体験して気づいた、わからない世界へ手を伸ばし続ける大切さ。シルバーウッド 下河原忠道さん![]() vol. 032021.04.15まだ名付けられていない感覚に出会う「遊び」の可能性とは? インタープリター 和田夏実さん
vol. 032021.04.15まだ名付けられていない感覚に出会う「遊び」の可能性とは? インタープリター 和田夏実さん![]() vol. 022021.04.15「助けて」とお互いに言い合えるのが、成熟した社会。ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ代表 志村季世恵さん
vol. 022021.04.15「助けて」とお互いに言い合えるのが、成熟した社会。ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ代表 志村季世恵さん![]() vol. 012021.04.15「お笑い」や「演劇」は他者の世界に寄り添うヒントをくれる。りんたろー。さん×菅原直樹さんが語る「介護の話」
vol. 012021.04.15「お笑い」や「演劇」は他者の世界に寄り添うヒントをくれる。りんたろー。さん×菅原直樹さんが語る「介護の話」