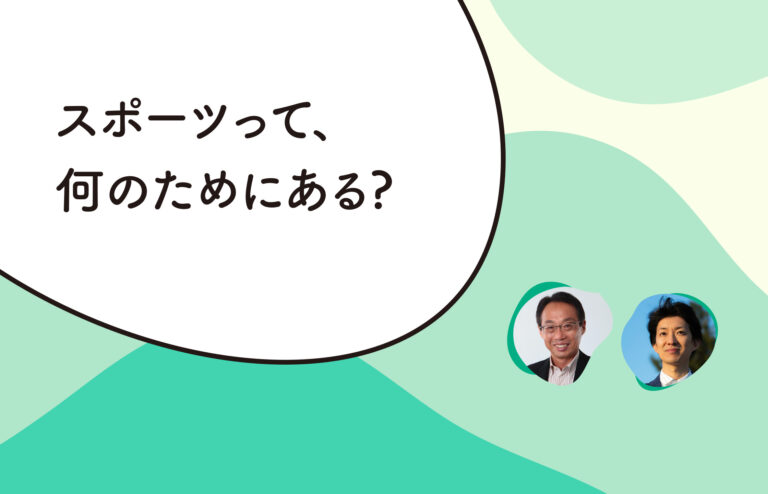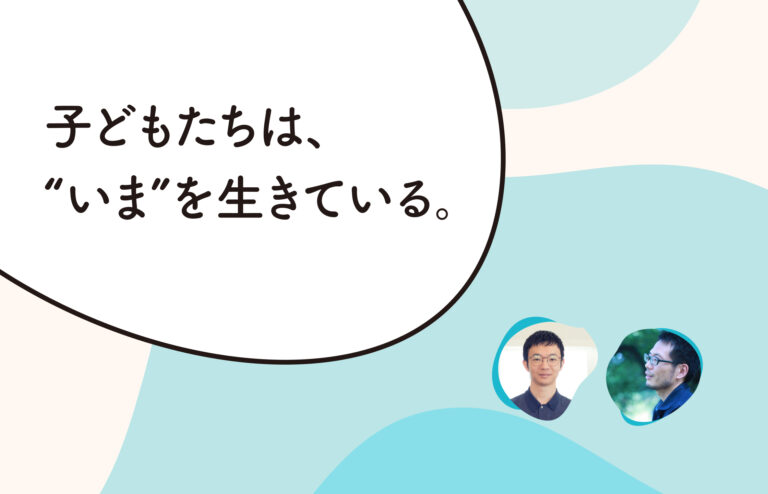「助けて」とお互いに言い合えるのが、成熟した社会。ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ代表 志村季世恵さん こここインタビュー vol.02
「気づかないうちに失礼なことを言っていないだろうか」
聴覚障害のある知人と話すとき、ふと不安になり、どこか恐る恐る言葉を交わしてしまったことがある。聴覚障害という領域の当事者ではない自分が無邪気に質問することで、知人のことを無自覚に傷つけているのではないかと。
「自分自身が知らないこと、すぐに当事者になれないことには触れるべきではない」と言う人がいるが、それでいいとは思えない。
他者を傷つけてしまうことへの不安はある。でも私は、まだ知らない・わからないからという理由で、自分とは違う特徴や文化を持つ人たちとのコミュニケーションに消極的になってしまうことは、あまりにも寂しいことだと思う。
視覚障害者・聴覚障害者がアテンド(案内人)を務め、見えない世界・音のない世界を案内してくれるソーシャル・エンターテインメント施設「対話の森」は、多様な人々が出会い、じっくりと対話をすることができる場だ。
「対話の森」のプログラムの背景にどのような思いがあるのかを知ることで、異なる文化を持つ人たちとのコミュニケーションのあり方や対話を考えるヒントが得られるのではないか。
そんな思いから、一般社団法人ダイアローグ・ジャパン・ソサエティの代表理事として「対話の森」のプログラムをつくってきた志村季世恵さんに、お話を伺った。

対話の森は「障害者と健常者が出会う場」ではなく、「個人と個人が出会う場」
私は今回、見えない世界を探検する「ダイアログ・イン・ザ・ダーク(以下、ダーク)」、そして音のない世界を探検する「ダイアログ・イン・サイレンス(以下、サイレンス)」の双方を実際に体験する機会を得た。


「ダーク」、「サイレンス」のふたつのプログラムの体験を終え、なによりも印象的だったのは、アテンドの“場をつくる”力の強さだった。今回、「ダーク」で見えない世界を案内してくれたハチさんと「サイレンス」で音のない世界を案内してくれたにゃんこさんは、それぞれにまったく違ったアプローチで参加者を場に巻き込んでいた。


インタビューの最初にそう伝えると、志村さんは「私はたぶん日本ではいちばん多くプログラムを体験しているはずだけど、それでも一度として同じような体験をしたことってないんです。1000回入ったら1000回とも違う。そして楽しい」と微笑む。

アテンドの個性が本当に出るんですよね。「サイレンス」には、にゃんこのような若いアテンドもいれば、70代のアテンドもいます。生きてきた時代やそれぞれの暮らしのなかで得てきた経験が違うと、同じプログラムを案内しても全然違った内容になるんですよ。味のあるアテンドばかりで、全員をおすすめしたいです。
志村さんは「対話の森」を障害者のサポートのための場ではなく、人と人とが対等に出会うことを楽しめる場にしたい、と語る。しかし、アテンドを務めるスタッフの過去の経験を聞くと、視覚障害者、聴覚障害者であるという面ばかりがクローズアップされ、“かわいそうな人”、“助けを必要としている人”とラベリングされることもあったという。
ダイアログのアテンドになる前の話ですが、学校の講演に招かれたとき、もしくはインタビューを受けたとき、最初から決めつけるように「あなたの困っていることはなんですか?」と聞かれることがあったようです。
そう言われると、自分は困っている人というレッテルを貼られているのかなと感じると。障害者=困っている人。もしかしたら自分の人生そのものまで、困っていると思われているのではないか? と感じたそうです。
見えないことや、聞こえないことで不便はあっても、それが全てではない。健常者であったとしても困りごとはあるし、悩みもある。あなたも私も同じ一人の人です。楽しいこと、幸せなこともたくさんあります。そして見えないからこそ、聞こえないからこそ、培った豊かな感性も持っています。
ダイアログでは、多様な人たちが活躍しています。「対話の森」では、それをリアルに感じてほしいんです。
視覚障害者、聴覚障害者であるという面に限らず、個人として出会える場。それを実現する手段として「ソーシャル・エンターテインメント」であることが対話の森においても大切にされている。
”見えない人”・”聞こえない人”と”健常者の自分”が出会う場、ではなく、もっとニュートラルに個人と個人が出会う場にしたかったんです。子どもの頃って、近所の名前も知らない子と会って遊んだりしていたじゃないですか? プログラムのなかで体験する遊びを通じて、そのような場をつくれたらいいなと思っています。
遊びの場だからこそ、プログラムやそこでの出会いを純粋に楽しみにやってくるリピーターも多い。「心を整えたいときに来ると決めている」という人や、毎回違った友達を連れ、対話の森を何度も訪れる人もいるという。

対話の森を何度も訪れたくなる、という気持ちはたしかによくわかる。プログラムを体験する約100分で、アテンドスタッフはもちろん同じ回を共にした参加者とも、じっくりと腰を据えて“対話した”という感覚が残るからだ。自分の場合、特に「ダーク」は、誰のことも見えず誰からも見られない空間で人と対話をすることの心地よさを強く感じた。
対話の森のホームページには、“この場で生まれていく「対話」が展示物です”という言葉が掲げられている。志村さんにとって「対話」とは、「相手と自分との思いの交換であり、ただ自分の思いをぶつけるだけではなく、ふたつの思いが混ざりあったときに生まれるもの」だという。
でも効率やはやさが求められる生き方のなかでは、対話の練習がしづらいですよね。たとえば親子でニュースを見て話をする時間があったとしても、「怖い事件ね、あなたも気をつけなさい」で終わってしまったりする。
「このニュースに私はこう思ったけれど、あなたは?」と、お互いに感じたことを伝え合うのが対話の起点だと思うのですが、いまはどうしても、コミュニケーションにも効率やはやさが求められてしまっている気がします。
お互いの発言に耳を傾け、理解する時間をゆっくり味わえる。効率や生産性のような指標から離れた場で、それらを体験できたのは、たしかに心地良かった。
視覚障害者がトレーニングを重ね「ダーク」のアテンドになって一番に驚くのが、晴眼者(視覚に障害のない人)は暗闇のなかでは歩く速度が驚くほどゆっくりになることだと言います。
その際、アテンドは急かすことなくその人のスピードに合わせて待ちます。やがて環境に慣れてくると暗闇の中にある様々なものを発見し、それを参加者同士で共有したりするのです。時には互いに協力し助け合う場面も。そのうちに対話が自然と生まれてきます。そんな流れをゆっくり待つ。それはプログラムの醍醐味のひとつかもしれません。
「サイレンス」も同じで、ジェスチャーや表情を通じたコミュニケーションがきちんと伝わるまで、アテンドは急かしたりせず待ちます。だからこそ、相手がなにかに気づいたり伝え合えたときに一緒になって喜べるんですね。
じつは、海外のプログラムはもうすこしスピード感があります。理由は海外の人は私たち日本人のようにシャイではなく、人と関わることに慣れているからです。また障害者と関わることの経験も多いです。日本はどうしても日常のコミュニケーションにスピードを求められてしまったり、文化の違う人に出会う機会も少ないという背景があるので、ここは大切にしようと思っています。
「助けて」と言えるようになると、他者を助けられるようになる
自分自身も「サイレンス」の空間に入ったばかりのとき、ジェスチャーへの理解が遅いせいでまわりを待たせているのではないか、迷惑をかけているのではないかという焦りを強く感じていたことを思い出す。
アテンドのにゃんこさんやほかの参加者が「大丈夫!」という表情やジェスチャーを何度もしてくれたおかげで、ようやく待たせることへの申し訳なさが薄まってきたのだった。
それを話すと、「『迷惑をかけてはいけない』とか『空気を読まなきゃ』って思ってしまうんでしょうね。『ダーク』で伝えたいことのひとつとして、『助けて』って言えるようになってほしい、という思いもあるんです」と志村さん。
日本人は人に助けを求めるのが苦手です。なんでも自分で解決しようとしてしまうのだけど、その姿勢こそが自分を追い込んで、孤独をつくっていくんですよね。私は自立って、なんでもできる自分でいられることではなく、「お互いさま」と思えることだと思っています。
自分自身がいま困っていることを抱え込むんじゃなくシェアできるのが大人であって、本来の意味での成熟なんだろうな、と。だから、助け合うことに対して「お互いさま」と思えるのが成熟した個人・成熟した社会なんですよね。
暗闇のなかって「みんなどこ?」とか「わからない」「助けて」って言いやすいんです。「助けて」って誰かが言う。そうしたら「助けるよ」と誰かの体が動く。だから、対話のひとつ前の段階として、声をかけ合うのが大切だということを、ダークの場で実感してもらえればいいなと思います。

その言葉に納得すると同時に、では自分が「助ける」側になるときはどうだろう、と考えてみる。街なかで白杖を持った方が立ち止まっているのを見かけたり、「いま手を貸してほしいのかもしれない」と感じる人に出会ったりしたとき、声をかけることが迷惑にはならないだろうか……とためらってしまうことがある。
声をかけることへの恐れをどう乗り越えればいいのか。そう尋ねると、志村さんは「めげない自分になること」と微笑んだ。
手助けが必要そうな人に声をかけて「大丈夫です」って断られちゃうことはたしかにありますよね。そういうときってショックだと思います。
でも、困っている人が仮に1万人いるとして、あなたに「大丈夫」って言ったのはそのうちの1人だけなんですよ。だから、その1人を頭のなかで1万人に変えてしまわないことが大事なんじゃないかな。
私は自分自身、子育てしていたときに本当にいろんな人たちが電車のなかや街なかで声をかけてくれて、そのおかげで孤独を感じずにいられたという経験があります。だから私も「大丈夫」って断られることはあるけれど、それでも毎回困っていそうな人がいたら声をかけることにしています。
声をかけるのが怖いと過剰に感じてしまうってことは、「助けて」と自分から言うのも苦手だったりしませんか? そう志村さんに聞かれ、思わず頷く。
なにか困ったことがあったとき、今度は「私のこと助けて」「困っているんです」ってまわりに言ってみてください。自分が「助けて」と伝えてまわりに助けてもらう経験をしていくと、“自分は助ける側でも助けられる側でもある”という両軸を持てるようになってくるんです、面白いことに。
“助けられる側”の当事者性を持つことが、他者を助けること、声をかけることへのためらわなさにつながっていくのだと志村さんは言った。
対話の「種」を、自分の家や職場に持ち帰ること

他者を助け、他者に助けられること。そして、他者の語りやそれらの理解にスピードを求めず、じっくりと向き合うこと。対話の森の参加者が体験したことをプログラム以外の場でも持続させていくためには、「持ち帰ってもらうこと」がなにより大切だと志村さんは言う。
「サイレンス」の場合、最後の部屋でアテンドから対話の“種”を渡されるシーンがありますよね。あの“種”を、ご自身の家庭や職場、社会まで持ち帰っていただくことが私たちの願いです。社会がいまより豊かになるためには、人同士の関わり、対話が必要だと思うんです。
志村さん自身も、自分とは異なる文化や身体的特徴を持ったアテンドやスタッフたちと働く上で、お互いを知り合う時間をいちばん大切に考えているという。
当たり前のことだけれど、相手に興味を持つということを大切にしています。たとえば「サイレンス」のアテンドであれば、どうしてこの人はこんなに表情豊かなんだろう? とか、どうしてこんなに美しい手の動きができるんだろう? と。
「どのようにしていまのあなたがいるのか」を知りたいんです。見えない文化や聞こえない文化について教えてください、という姿勢でいます。もちろんそれは、実際に知りたいから。
いきなり「あなたの聴力のレベルは?」「どのくらい見えていないの?」と聞いて相手を知ろうとするのではなく、一緒に時間を過ごすうちにだんだんそれに気づいていくのが理想的なんじゃないかと思います。
それが対話であって、人と知り合うということなのかなと。誰かと友達になりたいときってそうじゃないですか。それは職場においても、ほかの場においても同じなのかなと思います。
対話の森のなかで、アテンドを務めるスタッフはそれぞれに違う魅力を持ったすばらしいリーダーであり、パフォーマーだった。けれど、彼らの振る舞いや見えない空間・音のない空間をその領域の当事者ではない私が無邪気に楽しむのは、異なる文化に対しての一方的な消費や搾取になりえないだろうか──。最後に、取材チームが感じていた疑問を尋ねてみると、志村さんは力強く言った。
消費しないというのは、続けていく、終わらせない、ということです。対話の森の体験を通じてなにかを感じていただけたなら、それを忘れずにこの社会に活かそうと思ってもらいたい。毎回心が動くことを蔑ろにしなければ、「消費」は絶対にしないですよ。だからこそこの“種”を持ち帰って、続けていってください。

Information
・志村季世恵さん著書『エールは消えない -いのちをめぐる5つの物語』(婦人之友社)
・「ダイアログ・イン・サイレンス」は2024年1月13日〜2月25日まで開催中。
・歳を重ねることについて考えながら、 生き方について対話する体験型エンターテイメント、「ダイアログ・ウィズ・タイム」2024年春開催予定。
Profile
- ライター:生湯葉シホ
-
1992年生まれ、東京在住。フリーランスのライター/エッセイストとして、おもにWebで文章を書いています。Twitter:@chiffon_06
この記事の連載Series
連載:こここインタビュー
![]() vol. 322025.03.18言葉を超えて誰もがつながる「身体表現」の魅力とは? 福祉を起点に広がるパフォーミングアーツ、生きづらさを変える可能性
vol. 322025.03.18言葉を超えて誰もがつながる「身体表現」の魅力とは? 福祉を起点に広がるパフォーミングアーツ、生きづらさを変える可能性![]() vol. 312024.10.09なぜ自分に価値があるか確認したくなるんだろう? 勅使川原真衣さんと新澤克憲さんによる「評価」を巡る対話
vol. 312024.10.09なぜ自分に価値があるか確認したくなるんだろう? 勅使川原真衣さんと新澤克憲さんによる「評価」を巡る対話![]() vol. 302024.09.13大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 写真家/訪問看護師 尾山直子さんをたずねて
vol. 302024.09.13大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 写真家/訪問看護師 尾山直子さんをたずねて![]() vol. 292024.09.07地域に根ざす園から、子どもも大人も混ざった“絶景“を生み出せたら。〈学校法人thanka〉が新ステートメント「手を繋ぎにいく」に込めた願い
vol. 292024.09.07地域に根ざす園から、子どもも大人も混ざった“絶景“を生み出せたら。〈学校法人thanka〉が新ステートメント「手を繋ぎにいく」に込めた願い![]() vol. 282024.08.30大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 株式会社Blanket 秋本可愛さんをたずねて
vol. 282024.08.30大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 株式会社Blanket 秋本可愛さんをたずねて![]() vol. 272024.07.25気軽な買い物体験から、「未来が良くなる」手応えを。〈フェリシモ〉の新カタログ『GO! PEACE!』制作の裏側
vol. 272024.07.25気軽な買い物体験から、「未来が良くなる」手応えを。〈フェリシモ〉の新カタログ『GO! PEACE!』制作の裏側![]() vol. 262024.04.30蓋された「小さな自分」の声に耳を傾けて。ケアを促す料理レッスンの場、就労支援の場──山口祐加さん×鞍田愛希子さん
vol. 262024.04.30蓋された「小さな自分」の声に耳を傾けて。ケアを促す料理レッスンの場、就労支援の場──山口祐加さん×鞍田愛希子さん![]() vol. 252024.04.10「インクルーシブ」は誰のための言葉? 老舗メーカー〈ジャクエツ〉×医師・紅谷浩之さんの、子どもに“遊びと友だち“を返す遊具
vol. 252024.04.10「インクルーシブ」は誰のための言葉? 老舗メーカー〈ジャクエツ〉×医師・紅谷浩之さんの、子どもに“遊びと友だち“を返す遊具![]() vol. 242024.03.29文化施設のウェブアクセシビリティを向上する。障害当事者との「建設的な対話」に必要なこととは?──伊敷政英さん×森司さん
vol. 242024.03.29文化施設のウェブアクセシビリティを向上する。障害当事者との「建設的な対話」に必要なこととは?──伊敷政英さん×森司さん![]() vol. 232024.03.27だれもが文化でつながるために。クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョーが見据えるこれからの文化施設のあり方とは。
vol. 232024.03.27だれもが文化でつながるために。クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョーが見据えるこれからの文化施設のあり方とは。![]() vol. 222023.12.22人のためってなんだろう? 他者にコントロールされない「LOVOT」から、“人間らしさ“を考える──伊藤亜紗さん×林要さん
vol. 222023.12.22人のためってなんだろう? 他者にコントロールされない「LOVOT」から、“人間らしさ“を考える──伊藤亜紗さん×林要さん![]() vol. 212023.11.08保育料ゼロを実現し、子育てを“みん営化”する。 学童保育施設〈fork toyama〉岡山史興さん
vol. 212023.11.08保育料ゼロを実現し、子育てを“みん営化”する。 学童保育施設〈fork toyama〉岡山史興さん![]() vol. 202023.05.29ともだちってなんだろう? 答えを出す必要はないけれど。新澤克憲さんとテンギョー・クラさんの対話から考える
vol. 202023.05.29ともだちってなんだろう? 答えを出す必要はないけれど。新澤克憲さんとテンギョー・クラさんの対話から考える![]() vol. 192023.05.23歌人・岡本真帆さん×西淡路希望の家・金武啓子さん対談。「感動」の発見、どう他者と分かち合いますか?
vol. 192023.05.23歌人・岡本真帆さん×西淡路希望の家・金武啓子さん対談。「感動」の発見、どう他者と分かち合いますか?![]() vol. 182023.03.20“みる”から始める、アーティストと支援現場のつなぎ役。日常の関係性を変える「TURN LAND プログラム」の挑戦
vol. 182023.03.20“みる”から始める、アーティストと支援現場のつなぎ役。日常の関係性を変える「TURN LAND プログラム」の挑戦![]() vol. 172023.03.15アート活動で、「できる/できない」を揺さぶる。日常の価値を言葉に変えるコーディネーターの役割
vol. 172023.03.15アート活動で、「できる/できない」を揺さぶる。日常の価値を言葉に変えるコーディネーターの役割![]() vol. 162023.03.03唯一の答えを探しすぎていないか? 下地ローレンス吉孝さん×なみちえさんと“わかりやすさ”について考える
vol. 162023.03.03唯一の答えを探しすぎていないか? 下地ローレンス吉孝さん×なみちえさんと“わかりやすさ”について考える![]() vol. 152023.02.15“わたし”と“あなた”それぞれの複雑さを大切にするには?──なみちえさん×下地ローレンス吉孝さんと共に考える
vol. 152023.02.15“わたし”と“あなた”それぞれの複雑さを大切にするには?──なみちえさん×下地ローレンス吉孝さんと共に考える![]() vol. 142022.12.23出会いを広げながら、協働を生む「メディア」を目指して──〈こここ〉シーズン2を振り返る
vol. 142022.12.23出会いを広げながら、協働を生む「メディア」を目指して──〈こここ〉シーズン2を振り返る![]() vol. 132022.12.19働くことも、映画祭も「みんなが心地よい」を目指して。GOOD NEWSとTHEATRE for ALLのインクルーシブな場づくり
vol. 132022.12.19働くことも、映画祭も「みんなが心地よい」を目指して。GOOD NEWSとTHEATRE for ALLのインクルーシブな場づくり![]() vol. 122022.10.14バリアフリーの映画祭を通して、「その人のまま」でいられる社会に。作家・川内有緒さん×THEATRE for ALL・金森香さん
vol. 122022.10.14バリアフリーの映画祭を通して、「その人のまま」でいられる社会に。作家・川内有緒さん×THEATRE for ALL・金森香さん![]() vol. 112022.09.13スポーツの可能性って何だろう? 「プロスポーツ」「ゆるスポーツ」から考える──岡田武史さん×澤田智洋さん
vol. 112022.09.13スポーツの可能性って何だろう? 「プロスポーツ」「ゆるスポーツ」から考える──岡田武史さん×澤田智洋さん![]() vol. 102022.03.31まだみぬ「表現」との出会いを、誰もが体験できる社会へ。障害のある人の芸術・文化活動を支える窓口が全国に
vol. 102022.03.31まだみぬ「表現」との出会いを、誰もが体験できる社会へ。障害のある人の芸術・文化活動を支える窓口が全国に![]() vol. 092022.02.09コロナ禍で「消される」声に、どう耳を傾ける? 次の社会をつくる言葉と対話のあり方──荒井裕樹さん×青山誠さん
vol. 092022.02.09コロナ禍で「消される」声に、どう耳を傾ける? 次の社会をつくる言葉と対話のあり方──荒井裕樹さん×青山誠さん![]() vol. 082021.12.24福祉をたずねて1年。編集部は何に出会い、悩んできた?──〈こここ〉振り返り座談会
vol. 082021.12.24福祉をたずねて1年。編集部は何に出会い、悩んできた?──〈こここ〉振り返り座談会![]() vol. 072021.11.24コロナ禍を経て新たな表現の協働へ ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[後編]
vol. 072021.11.24コロナ禍を経て新たな表現の協働へ ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[後編]![]() vol. 062021.11.24アートプロジェクトは福祉の現場で何を生み出す? ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[前編]
vol. 062021.11.24アートプロジェクトは福祉の現場で何を生み出す? ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[前編]![]() vol. 052021.10.18福祉施設が学びあいの拠点になることで育まれるものとは?ライフの学校・田中伸弥さん
vol. 052021.10.18福祉施設が学びあいの拠点になることで育まれるものとは?ライフの学校・田中伸弥さん![]() vol. 042021.06.03VR認知症を体験して気づいた、わからない世界へ手を伸ばし続ける大切さ。シルバーウッド 下河原忠道さん
vol. 042021.06.03VR認知症を体験して気づいた、わからない世界へ手を伸ばし続ける大切さ。シルバーウッド 下河原忠道さん![]() vol. 032021.04.15まだ名付けられていない感覚に出会う「遊び」の可能性とは? インタープリター 和田夏実さん
vol. 032021.04.15まだ名付けられていない感覚に出会う「遊び」の可能性とは? インタープリター 和田夏実さん![]() vol. 012021.04.15「お笑い」や「演劇」は他者の世界に寄り添うヒントをくれる。りんたろー。さん×菅原直樹さんが語る「介護の話」
vol. 012021.04.15「お笑い」や「演劇」は他者の世界に寄り添うヒントをくれる。りんたろー。さん×菅原直樹さんが語る「介護の話」