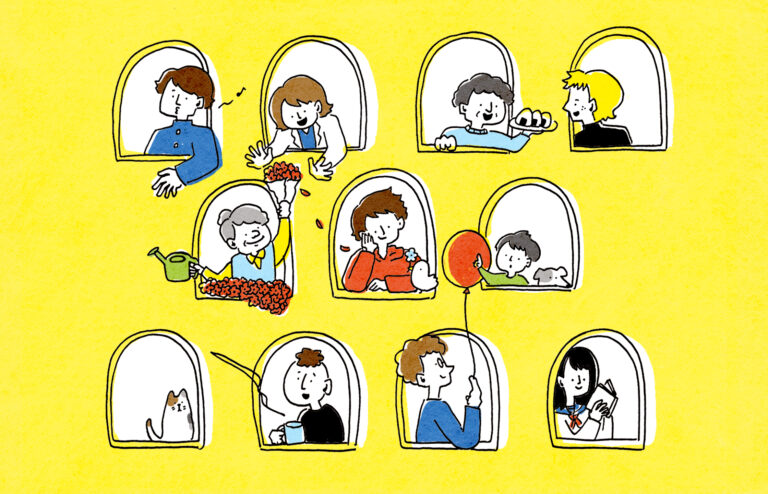偏見がない人はいない。川内有緒さん×木ノ戸昌幸さん『わたしの偏見とどう向き合っていく?』イベントレポート こここスタディ vol.05
いま、「あなたの中には差別意識や偏見がありますか?」と聞かれたら、あなたはどんなふうに答えるだろうか。即座に「たぶんない」と答える人もいるかもしれないし、すこし考えてから、「ないように努力している」と言う人もいるかもしれない。
ではそれが、「よく知らない人と話してみて、自分が抱いていた偏見に気づいたことはありますか?」という質問や、「軽い気持ちで口に出したことが、差別的な発言だったとあとから知ったことはありますか?」という質問だった場合はどうだろう。おそらく、「ない」と言い切れる人はほとんどいないのではないだろうか。
そんな、自分自身の内側にある「偏見」や「差別意識」との向き合い方について考えるトークイベント、「わたしの偏見とどう向き合っていく?」(SPBS TOYOSU主催)が2021年10月23日に開催された。
出演者は、昨年、著書『目の見えない白鳥さんとアートを見にいく』を上梓したノンフィクション作家の川内有緒さんと、京都にあるNPO法人「スウィング」理事長の木ノ戸昌幸さん。「偏見」や「差別意識」をめぐる対話を通じて、身近な人、そして自分自身の中にある偏見との向き合い方のヒントが提示された。オンラインで実施されたイベントの様子をレポートする。
「自分には偏見や差別意識がある」という自覚からまず始める
偏見や差別は、相手に対する敵意や嫌悪感から引き起こされるもの──と考えている人も少なくないかもしれない。しかし、必ずしもそうであるとは限らない。木ノ戸さんがイベントの冒頭で語った、ある“違和感”についてのエピソードは、私たちがいかに自分のしている差別に気づきにくいかを象徴している。
木ノ戸さんが運営するNPO法人「スウィング」がおこなっている活動のひとつに、バスの交通網が複雑に発達した京都市内で、路線バスの乗り継ぎ・行き方情報を“人力”で案内する「京都人力交通案内 『アナタの行き先、教えます。』」がある。
この活動がメディアで取り上げられる際、しばしばフォーカスされるのが障害のある特定のメンバーだけであることに、木ノ戸さんは違和感を覚えるという。
木ノ戸昌幸さん(以下、木ノ戸):京都人力交通案内って、基本的にQさん、XLさんと僕の3人でやっている活動なんですね。もっと言えばいつも同行してくれるフォトグラファーもいて、協働しながら続けているんです。
でも、この活動を新聞などのメディアで取り上げていただくとき、注目されるのは障害のあるQさんとXLさんばっかり。これに限らず、スウィングの活動がメディアで取り上げられるときって、「障害者」とか「障害のある人」って言葉がいちばん大きなメッセージとして伝えられがちなんです。
みなさんとても丁寧に取材してくださるんですよ。でもこれって、言ってしまえば差別だなって感じるんです。

川内さんも、自身の著書『目の見えない白鳥さんとアートを見にいく』の中で、京都人力交通案内の活動を紹介している。原稿を確認してもらう際、まさにその点を木ノ戸さんから指摘され、はっとしたことがあったという。
川内有緒さん(以下、川内):原稿を書き終えたときに木ノ戸さんから「この活動は3人でやっているんです」と聞いて、ああそうか、と思ったんです。
どうして無意識のうちに木ノ戸さんを省いていたんだろう、と考えてみると、自分の中に、障害者と呼ばれる人をフィーチャーしたいという一種の差別意識があったのかもしれないなと……。
もしかして私も知らず知らずのうちにそういうところに注目していたのかな、と気づかされてびっくりしました。
そういうものって、日常のあらゆるところに潜んでいる。差別意識や偏見を持っている側は、本当にそれに気づかずに生きているということなんですよね。

木ノ戸さんは、前述の京都人力交通案内がメディアに取り上げられるときのような違和感を、「やのに感」と呼ぶ。
個人の実績や活動内容以上に、社会的なラベリングやカテゴライズに注目が集まるとき、そこには「障害者やのにすごい」「女性やのにすごい」「外国人やのにすごい」……といった偏見があるのではないか、と指摘する。
川内:「美しすぎる〇〇」のような表現もそうですよね。そこには、「この分野の仕事に就いている人が美しいなんて珍しい」という偏見が隠れているんじゃないかと感じます。
差別意識や偏見は、それほどまでに日常の端々に潜んでいる。しかし、本当に問題なのは差別をしてしまうことそれ自体ではなく、「自分は差別をしていない」「自分には偏見なんてない」と思い込んでしまうことだと木ノ戸さんは言う。
木ノ戸:差別意識や偏見は、大なり小なり誰しも持っているはず。だから、偏見をもつことや差別をすることがやばいんじゃなく、自分はそういう意識を持っていないはず、と思うことがやばいんですよね。
中でも特に気づきにくいのが、やさしさや気遣いのような“善意”に覆われた差別だ。差別をしている側にも“正しさ”がある分、それが相手を傷つけ排他することにつながっても、自覚を持ちにくい。
川内:たとえば、(視覚障害者である)白鳥さんが美術館に行くと、「触察ツール」という手で触って作品を感じられるツールを勧められることがあるんです。
もちろんそれを使って作品を味わうこともあるけれど、『あ、いいです』と断るときもある。そうすると、「親切で言ってあげたのに」みたいな言葉をかけられたりすることがあるんですって。
……でも、そういうふうに善意で言ってしまう人の気持ちもなんとなくわかるんです。目が見えないんだから、触って楽しめばいいじゃない、と。白鳥さんに「そう言われるのもけっこう大変なんだよね」と聞いたとき、自分もこれまでに多々同じようなことをしていたかもしれないな、という気づきがありました。
「見ないことにする」のは、「差別していない」ことではない
自分の無自覚なひと言が相手を傷つけ差別することにつながってしまう可能性を思うと、「障害のある人に声をかけるのはやめておこう」と考える人もいるかもしれない。しかし、それは違うのではないかと木ノ戸さんは言う。
木ノ戸:自分のその行動が間違っているかどうかって、実際に自分で動いてみるまではわからないんですよね。「声をかけていいんだろうか」と逡巡しているだけでは、自分がただ固定化されて、わからないままで終わってしまう。
だからまずは、正解がわからなくても動くことが大事なんだと思います。もし動いた結果それが間違っていたなら、間違いを自覚し、自分の行動をそこからまたアジャストしていけばいい。
人のことってやっぱり基本的にはわからないんだけど、私たちはなぜか「きっとわかるはずだ」と思ってしまうふしがすごく強い。その思い込みから離れたほうが楽になれるんじゃないかな、と思います。
さらに、「障害者」という言葉の表記を「障がい者」にすべきか、あるいは他の表現に言い換えたほうがいいのかという議論にも、似た問題が潜んでいると木ノ戸さんは指摘する。
木ノ戸:「障害者」という言葉に勝手にネガティブなイメージを持たせているのは社会の見方であって、言葉そのものに問題があるわけではない。
むしろ、「障害者」という言葉をただの言葉として伝えていけるようにすることのほうがずっと大事だと思います、それはすごく時間のかかることかもしれませんけど。ただ単に表記を変えても、それは表面的な問題の解決にしかならない。すごく短絡的な手段で嫌だなと思います。
木ノ戸さんの話を受け、「なかったことにする」「見ないようにする」ことと「差別しない」ことがイコールになってしまうのは恐ろしい、と川内さんは語る。
川内:自分の中に本当は存在している偏見に蓋をして、口に出していないのだからOK、としてしまうと、言葉だけが上滑りする社会になってしまうと思います。
口に出さないことで偏見がなくなるわけじゃないし、むしろ逆かもしれない。もっともっと、自分の抱えている偏見について対話をしたほうがいいのかもしれないとも思えてきます。
私が『目の見えない白鳥さんとアートを見にいく』を書いていたときも、考えていたのはそのことでした。自分が差別的な意識を持っているかもしれない、ということを、もっと包み隠さずに書いていくべきだと思っていたんです。
社会の「セーフゾーン」を拡大していくために

川内さんの著書『目の見えない白鳥さんとアートを見にいく』の中では、アート鑑賞を趣味とする全盲の白鳥建二さんが、ほかの鑑賞者の“言葉”を通して作品を味わい、楽しむ様子が綴られている。
白鳥さんがそのようなアート鑑賞のしかたを“違和感”としてさまざまな場所に振りまいたことで、全国の美術館や美術鑑賞者の姿勢も少しずつ変化してきたのを感じる、と川内さんは言う。
川内:白鳥さんはたぶん最初、多くの人にとって“何をしているかよくわからない人”だったと思うんです。「言葉でアートを鑑賞するって何?」という違和感を、日本中の美術館にまき散らしたはず。でも、それによっていまは、言葉でアートを見ることが美術関係者の中で徐々に広まってきているのを感じます。
木ノ戸さんも著書『まともがゆれる ―常識をやめる「スウィング」の実験』の中で書かれていましたけど、白鳥さんも、「ギリギリアウト」のようなこと……つまり、最初は社会の中で「アウト」とされていたようなことを、時間をかけて「セーフ」にしてきた人だと思うんです。
ともすれば現代って、「セーフ」の領域がどんどん狭くなっていってしまうような社会。私が子どもだった頃と比べても、随分不自由になってきたな、よくなったところってあるんだろうか、と思ってしまうことも多いです。
「セーフ」を拡大するために、みんなもっとアウトに足を踏み入れていったほうがいいんじゃないかと感じます。

木ノ戸さんは、川内さんの意見に賛同した上で、「理想的な社会を作るべきだ」という思い込みがかえってセーフゾーンを狭めていくケースもあるのではないか、と指摘する。
木ノ戸:社会をよくしていこうと考えるのはもちろんすごく大切だと思うんですけど、別によくならんでもいい、と思うのも大事なのかなと……。
自分の中でそれは、「よくしていこう」という希望と矛盾するものではないんですね。よくしていこうと思いすぎると、アウトがどんどん増えていくというパラドックスに陥ってしまうこともあると思うんです。
たとえばスウィングの中ではいま、「自由」をより拡大していくための装置として、かえってルールという制限を設けてみる、というのを試しているんです。
スウィングの中ではもともと自由に昼寝をしていいことになっているんですが、仕事をする場という意識が強い人は、眠くても寝ちゃいけないとどうしても思ってしまう。それで、そういう人も眠いなら寝られるようにと思って「昼寝」の時間を作ってみたら、当たり前だけどみんな寝るんですね。
反対に、そんなルールなんてなくても自由を謳歌できる人は、特に寝ない。もちろん、ルールを守ってもらうことが目的ではなく、昼寝していい顔をする人が増えることが目的なので、それでいいんです。
つまり、使い方には慎重になる必要がありますが、ルールというものはときに自由を拡大する装置にもなるのではないか、と思うんです。人ってある程度の枠組みがないと、実はなかなか自由になれないのではないかと。
川内:ああ、それはとてもわかります。白鳥さんとアートを見にいくときにも、「アート作品」というひとつの枠組みがあることが、かえってコミュニケーションを自由にしているなと思うことは多いです。
たとえば、白鳥さんのことをよく知らない人に、作品なしで「なんでも自由に話していいですよ」と言っても、最初はきっとお互いに戸惑ったり変な気遣いが生まれてしまったりするんじゃないかと思うんですよね。
でも、「作品についてなんでも自由に喋ってください」というのは、制約がひとつある分すごく気楽なんですよ。相手を否定せず、それでいて自分の考えを自由に話せる場が、作品があることによって生まれているなとよく感じます。
今日の自分が完璧であると思わなくてもいい
イベント参加者から寄せられた「差別」や「偏見」をめぐる質問に、川内さん・木ノ戸さんの二人が回答する一幕もあった。
最初に寄せられたのは、「自分自身が抱えている偏見や差別意識に気づいたとき、それを受けて行動を変えていけばいいと頭ではわかっていても、自分を許すことができなくなってしまう人もいるように感じる。自分の差別的な行動・言動を率直に受け止めて次のアクションにつなげていくためにはどうすればよいか」という質問。
木ノ戸さんはこの問いに対し、人はそんなに正しくない、どうしても間違ってしまうときはあるという点を強調しながらも、「真摯に謝る」ことを勧めた。
木ノ戸:自分の間違いをすぐに認めて、とにかく謝ることですよね。誰かを傷つけてしまったことに対しては何の言い訳もできないから、すぐには難しいとしても、真摯に謝って、自分の態度を改めるしかない。間違っていた自分に気づいたときにはショックを受けるかもしれないけれど、それは別にだめなことではないと思います。
川内さんは、「あまり自分を理想化せず、今日の自分が完璧であると思わなくてもいいのではないか」と語りかける。
川内:私も、すこし前にトークイベントに参加したときに「ブラック企業」という言葉をなんの気なしに使ったら、友人でもある共演者の方から「ブラック企業という言葉は人種差別的な表現だから、闇企業という言い方にして」と指摘を受けたんです。それではっとして、もうその表現は使わないと思いました。
間違いに気づけた瞬間って、これから自分が変わることができるかもしれない分岐点ですよね。だから『自分を許せない』という気持ちになってしまうかもしれないけれど、変われるかもしれないというのはむしろ、素晴らしいことだと思います。
自分を変えていくことは、一生、死の直前まで続く戦いなのかもしれない。だから、今日はだめでも、明日は違う自分になっているはずだということを考え続けていけばいいんじゃないでしょうか。
さらにもう1件、「身の回りの人の発言に『それは差別的では?』と感じたとき、そのモヤモヤを言語化したり、やめてほしいと伝えることがなかなかできない。そういうときにどんなことができるか」という質問も寄せられた。
木ノ戸さんは、「必ずしも、モヤモヤを整った言葉にする必要はない」と答える。
木ノ戸:自分の思いが言葉らしい言葉になるまでには時間がかかることもあるし、言語化には得意不得意もある。モヤモヤした、というのを必ずしも整った言葉にする必要はなくて、まずは「モヤモヤしている」ということをそのまま口に出すことから始めたらいいんじゃないかなと思います。
川内:実は私も最近、家族でよく行くあるレストランで、店員さんが女性蔑視的な発言をしているのを聞いて気分が悪かったというのを夫に聞いて。
私はそれを直接的には聞かなかったんですけど、もしも次回同じことが起きたら、店員さんにどう言葉をかけようかとずっと考えていたんです。絶対に何か言いたいけれど、どの言葉もしっくりこないと思っていたので、いま木ノ戸さんからそれを聞けてよかったです。
整った言葉でなくても、まずは自分の感じたモヤモヤを話すところから会話は始まる、と思ったらすこしスッキリしました。
木ノ戸:本当に、44歳になってこんなにアワアワするかなと思うくらい(笑)、そういう場面ではいまだに自分もアワアワしてしまいます。
でも、アワアワしている状態をまず見せるというのが大事で。それを見せたら、相手からはおそらくリアクションがありますよね。
人間が関係していくというのはそういうことだと思うので、格好悪くてもいいから、思っていることをまず表明するのが、自分を大事にすることなのかなと感じます。
イベントでは、自身が経験したことや過去のコミュニケーションの反省点にも目を向けながら、自分の偏見や差別意識というテーマを終始「見えないこと」にせず言葉を尽くす川内さん・木ノ戸さんの姿勢が印象的だった。
このレポートをいま読んでいる人が、「どうやら自分は大丈夫そうだ」とホッとするよりも、普段は心の内に隠していたり、自分でもまだ自覚できていなかったりする偏見と向き合おうという気持ちになっていたら嬉しいと思う。自分自身の気持ちや過去の言動・行動に向き合うことが苦しくなったときには、「今日の自分が完璧であると思わなくていい」という川内さんの言葉、そして「間違っていた自分にショックを受けるのはだめなことではない」という木ノ戸さんの言葉を思い返したい。
Profile
![]()
-
川内有緒
ノンフィクション作家
1972年東京都生まれ。 映画監督を目指して日本大学芸術学部へ進学したものの、あっさりとその道を断念。 行き当たりばったりに渡米したあと、中南米のカルチャーに魅せられ、米国ジョージタウン大学で中南米地域研究学修士号を取得。米国企業、日本のシンクタンク、仏のユネスコ本部などに勤務し、国際協力分野で12年間働く。2010年以降は東京を拠点に評伝、旅行記、エッセイなどの執筆を行う。 『バウルを探して 地球の片隅に伝わる秘密の歌』(幻冬舎)で、新田次郎文学賞、『空をゆく巨人』(集英社)で開高健ノンフィクション賞を受賞。著書に『パリでメシを食う。』『パリの国連で夢を食う。』(以上幻冬舎文庫)、『晴れたら空に骨まいて』(講談社文庫)、『バウルを探して〈完全版〉』(三輪舎)など。 白鳥建二さんを追ったドキュメンタリー映画『白い鳥』の共同監督。現在は子育てをしながら、執筆や旅を続け、小さなギャラリー「山小屋」(東京・恵比寿)を家族で運営する。趣味は美術鑑賞とD.I.Y。「生まれ変わったら冒険家になりたい」が口癖。
(プロフィール写真撮影:鍵岡竜門)
Profile
![]()
-
木ノ戸昌幸
株式会社NPO 代表取締役
1977年生まれ・愛媛県出身。株式会社NPO代表取締役、元NPO法人スウィング理事長、フリーペーパー『Swinging』編集長、スウィング公共図書館CEO。引きこもり支援NPO、演劇、遺跡発掘、福祉施設勤務等の活動・職を経て、2006年、京都・上賀茂に<スウィング>を設立。仕事を「人や社会に働きかけること」と定義し、清掃活動「ゴミコロリ」、芸術創作活動「オレたちひょうげん族」、京都人力交通案内「アナタの行き先、教えます。」等の活動をプロデュース。ギリギリアウトを狙った創造的実践や発信を通して窮屈な社会の規定値を拡張したいと願う。単著に『まともがゆれる ―常識をやめる「スウィング」の実験』(2019/朝日出版社)。
(プロフィール写真撮影:Numata Ryohei)
- ライター:生湯葉シホ
-
1992年生まれ、東京在住。フリーランスのライター/エッセイストとして、おもにWebで文章を書いています。Twitter:@chiffon_06
この記事の連載Series
連載:こここスタディ
![]() vol. 222024.07.17「創造性」って何だろう? ブルーノ・ムナーリを辿りながら──デザイナー、アーティスト、教育者の随想
vol. 222024.07.17「創造性」って何だろう? ブルーノ・ムナーリを辿りながら──デザイナー、アーティスト、教育者の随想![]() vol. 212024.03.30「個人の心の問題」の多くは環境や政治の問題でもある〜「あなたのため」というバウンダリーの侵害〜
vol. 212024.03.30「個人の心の問題」の多くは環境や政治の問題でもある〜「あなたのため」というバウンダリーの侵害〜![]() vol. 202024.03.26自分と他者を区別する境界線「バウンダリー」とは?ソーシャルワーカー鴻巣麻里香さんによる解説
vol. 202024.03.26自分と他者を区別する境界線「バウンダリー」とは?ソーシャルワーカー鴻巣麻里香さんによる解説![]() vol. 192024.02.01「昔好きだった作品」の表現に戸惑ってしまったら? フィクションが与える2つの影響──文学研究者・小川公代さん
vol. 192024.02.01「昔好きだった作品」の表現に戸惑ってしまったら? フィクションが与える2つの影響──文学研究者・小川公代さん![]() vol. 182023.12.15「合理的配慮」は「ずるい」「わがまま」なのか? インクルージョン研究者 野口晃菜さんによる解説
vol. 182023.12.15「合理的配慮」は「ずるい」「わがまま」なのか? インクルージョン研究者 野口晃菜さんによる解説![]() vol. 172023.04.21“できる/できない”の社会を「ヨコへの発達」で問い直す。社会福祉の父・糸賀一雄を、垂髪あかりさんが研究する理由
vol. 172023.04.21“できる/できない”の社会を「ヨコへの発達」で問い直す。社会福祉の父・糸賀一雄を、垂髪あかりさんが研究する理由![]() vol. 162023.02.08「やさしい日本語」ってなに? 言語学者・庵功雄さんに聞くコミュニケーションの本質
vol. 162023.02.08「やさしい日本語」ってなに? 言語学者・庵功雄さんに聞くコミュニケーションの本質![]() vol. 152023.01.27人を見た目で判断することって全部「差別」になるの? 社会学者 西倉実季さんと、“ルッキズム”について考える
vol. 152023.01.27人を見た目で判断することって全部「差別」になるの? 社会学者 西倉実季さんと、“ルッキズム”について考える![]() vol. 142023.01.16自分の気持ちを話さない自由がある。NPO法人ぷるすあるはと一緒に考えた“きもち”との付き合い方
vol. 142023.01.16自分の気持ちを話さない自由がある。NPO法人ぷるすあるはと一緒に考えた“きもち”との付き合い方![]() vol. 132022.12.14“障害”ってそもそも何だろう? 困難の原因を「社会モデル」から考える──バリアフリー研究者・星加良司さん
vol. 132022.12.14“障害”ってそもそも何だろう? 困難の原因を「社会モデル」から考える──バリアフリー研究者・星加良司さん![]() vol. 122022.11.29「ちゃんとしなきゃ」の呪いをとくには?福祉社会学者 竹端寛さん× 僧侶 松本紹圭さん
vol. 122022.11.29「ちゃんとしなきゃ」の呪いをとくには?福祉社会学者 竹端寛さん× 僧侶 松本紹圭さん![]() vol. 112022.10.27“ありのままの自分”を大切にするって、どういうことだろう? しょうぶ学園施設長 福森伸さんをたずねて
vol. 112022.10.27“ありのままの自分”を大切にするって、どういうことだろう? しょうぶ学園施設長 福森伸さんをたずねて![]() vol. 102022.09.27「福祉の現場」と「芸術」の根っこには通ずるものがある? 福祉環境設計士 藤岡聡子さんをたずね、「ケアの文化拠点」ほっちのロッヂへ
vol. 102022.09.27「福祉の現場」と「芸術」の根っこには通ずるものがある? 福祉環境設計士 藤岡聡子さんをたずね、「ケアの文化拠点」ほっちのロッヂへ![]() vol. 092022.09.07“健康”ってなんだろう?ケアの文化拠点「ほっちのロッヂ」紅谷浩之さんをたずねて
vol. 092022.09.07“健康”ってなんだろう?ケアの文化拠点「ほっちのロッヂ」紅谷浩之さんをたずねて![]() vol. 082022.08.12弱さは個人の問題ではなく、構造上の問題だ。公認心理師・臨床心理士 信田さよ子さんと考える“弱さ”のこと
vol. 082022.08.12弱さは個人の問題ではなく、構造上の問題だ。公認心理師・臨床心理士 信田さよ子さんと考える“弱さ”のこと![]() vol. 072022.07.28“違う“の不安をどう乗り越えればいい? グレーではない「色」で表現する発達の特性──星山麻木さん
vol. 072022.07.28“違う“の不安をどう乗り越えればいい? グレーではない「色」で表現する発達の特性──星山麻木さん![]() vol. 062022.04.12「私はどう生きたらいい?」を、一人で抱えない社会へ。医師・西智弘さんに聞く、地域活動と“ケア“の文化づくり
vol. 062022.04.12「私はどう生きたらいい?」を、一人で抱えない社会へ。医師・西智弘さんに聞く、地域活動と“ケア“の文化づくり![]() vol. 042022.02.04居場所・つながり・役割・生産性。「望まない孤独」をめぐる対談でみえたものとは?吉藤オリィさん×奥田知志さん
vol. 042022.02.04居場所・つながり・役割・生産性。「望まない孤独」をめぐる対談でみえたものとは?吉藤オリィさん×奥田知志さん![]() vol. 032021.10.26大切なものを失った悲しみや痛みと共に生きていくには? グリーフサポートが当たり前にある社会を目指す 尾角光美さんをたずねて
vol. 032021.10.26大切なものを失った悲しみや痛みと共に生きていくには? グリーフサポートが当たり前にある社会を目指す 尾角光美さんをたずねて![]() vol. 022021.06.24差別や人権の問題を「個人の心の持ち方」に負わせすぎなのかもしれない。 「マジョリティの特権を可視化する」イベントレポート
vol. 022021.06.24差別や人権の問題を「個人の心の持ち方」に負わせすぎなのかもしれない。 「マジョリティの特権を可視化する」イベントレポート![]() vol. 012021.04.15さまざまな側面をもつ「わたし」と「あなた」をそのまま大切にするには? 美学者 伊藤亜紗さんを訪ねて
vol. 012021.04.15さまざまな側面をもつ「わたし」と「あなた」をそのまま大切にするには? 美学者 伊藤亜紗さんを訪ねて