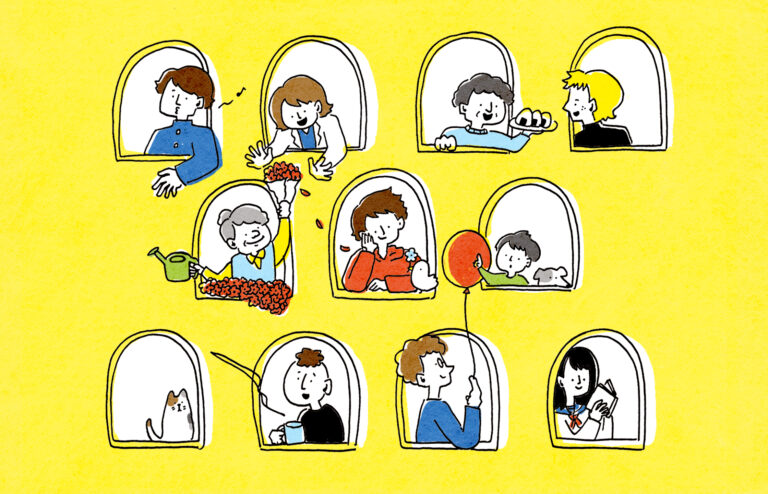「ちゃんとしなきゃ」の呪いをとくには?福祉社会学者 竹端寛さん× 僧侶 松本紹圭さん こここスタディ vol.12
「まわりの人が見てるでしょ、ちゃんとしなさい!」。街なかで、地面に寝転んで泣く子どもを前に、そんな言葉をかける人を見たことがある。子どもはそう言われても泣き続けるばかり。親御さんらしきその人は起き上がろうとしない我が子を見て、焦っている様子だった。
自分がその子どもだったら、「人が見ているから」ちゃんとしなさい、と言われても、どうして? と感じるのではないかと思った。けれどそれ以上に、多くの通行人の視線を受けて、「『ちゃんと』子どもの教育をしていない親だ」と一方的に判断される恐怖にかられ、形だけでもそう言わずにはいられないその人の気持ちも痛いほどわかったから、苦しかった。
「『ちゃんとした』人なら、ここで子どもを叱るはずだ」「常識的にふるまって、『ちゃんとした』人だと思われなきゃ」。
他者のニーズや評価に応え続けようとすることを「ちゃんとする」と定義するならば、私たちは常に「ちゃんとしなきゃ」の呪いにかけられ続けてきたような気がする。「ちゃんとしなきゃ」の手綱をゆるめ、より息苦しくない社会や場の中で生活していくためには、なにが必要なのだろうか?
「ちゃんとする」の価値観をめぐって、『家族は他人、じゃあどうする? 子育ては親の育ち直し』などの著書がある福祉社会学者の竹端寛さん、そして、浄土真宗本願寺派の僧侶で、僧侶・宗教者のためのお寺マネジメントスクール「未来の住職塾」の運営も務める松本紹圭さんのおふたりに、たっぷりとお話をしていただいた。
社会に合わせて生きなければという刷り込みが、「ちゃんとしなきゃ」を生む
──まずはじめに、いまの社会において「ちゃんとしなきゃ」という意識が多くの人の中になぜ芽生えるのか、という問いを出発点にできればと思います。この対談もテーマ通り、あらかじめ決まった筋道を設定して「ちゃんと」進めるというより、自由にお話しいただければと思うので、よろしくお願いします。
竹端寛さん(以下、竹端):お願いします。きょう、松本さんと対談できて嬉しいです。
「ちゃんとしなきゃ」という言葉についてまず思うのが、僕自身、 「ちゃんとしなさい」の呪縛にはまり続けてきたことに、子どもを育てるまで気づいていなかったんですね。それほど深く自分の中に刷り込まれていたんですよ。
大学のゼミ生たちと接していても感じるんですが、学生たちみんな、すっごくちゃんとしてるんですよね。「ちゃんとしなきゃ」と一度思わされると、みんなそれを守ろうと一生懸命になる。そういう真面目な人たちの集まりが日本社会だという気がしているんです。

松本紹圭さん(以下、松本):うん、うん。わかります。「いまの若い人はちゃんとしてる」ってたぶんいろんなところで言われているんでしょうけどね。私にもいま中2と小4の子どもがいるんですが、自分の子どもの頃と比べても、真面目な子どもが多いなという気はします。
竹端:だからなのか日本って、電車もそうそう遅れなければゴミも落ちていない、ものすごくスムーズな社会なんですよね。スムーズでとても心地よいのだけれど、その心地よさは一人ひとりのしんどさの上に成り立っている。つまり、みんなが頑張って「ちゃんとしなきゃ」と意識することでなんとかなってんねんけど、日本社会の生きづらさの根底にあるのは、この「ちゃんとしなきゃ」なんちゃうか、と思って。
子どもを育てていく中で、そう言語化することまではできたんですが、ほなどうしたらいいかとか、その背景に何があるかまではまだよくわかっていないんです。だからきょうは、松本さんにいろいろ教えてもらおうと思ってきました。
松本:たくさんの人たちが「ちゃんとする」ことで世の中がよりなめらかになったかというと、実際にはそれで苦しんでいる人も多かったりしますよね。
竹端:ええ。僕は大学の授業の中で「生きづらさ」をテーマにし始めてから10年以上経ちます。生きづらさってなんやろって考えてみると、生活からそんなに遠いところにある話じゃないと思うんです。たとえば中学校や高校で体育座りとか軍隊式行進をさせる教育って、学校が荒れていた時代から脈々と続いていますけど、ああいう形のコントロールのしかたがうまく機能しすぎてしまったんでしょうね。
いま不登校や引きこもりと呼ばれる人たちが増えているのは、「ちゃんとしなさい」という言葉に対して、言葉でプロテスト(抗議)しづらい分、違った形でプロテストせざるを得ない人たちが多いからかもしれない、なんて思います。「ちゃんとしなさい」のほうが一見するとちゃんとしてるから、抗議しづらいんですよね。抱えている生きづらさを既存の言語で表現できないときに、違った形での発露が必要になってくる人がいるんじゃないかと思うんです。
松本:それぞれ、言葉ではない形でプロテストしているのではないか、ということですよね。
最近、ふと子どもの頃のことを思い出して、ムカムカしたことがあったんです。椅子取りゲームってあったじゃないですか。あの光景、なんか嫌だったなあと思って……。ウロウロしているうちにいつの間にか自分の椅子がなくなってしまう。当時は参加しなきゃいけないものだと思っていたから、悲しいなあと思っていただけだったけれど、競争の中に否応なく放り込まれて、そこでやっていかなければいけないということをすり込まれるような体験だったと思うんです。
振り返ってみると、そういうものが社会の至るところに埋め込まれていて、しかもそれが、竹端さんのおっしゃるとおりうまく機能しすぎてしまっている。資本主義が完成に近づくにつれて崩壊すると言われているようなことが、まさに起きているのかもしれませんね。

竹端:本来は僕らが社会に合わせて生きるのではなく、僕らが生きるのに社会のほうが合ってくれたらいいのだけど、日本社会はまったくそうじゃなくて、社会にどうアジャストするかがすごく大事にされている。それが「ちゃんとしなさい」という言葉につながっていると思うんですよね。
以前、ラグビーの元日本代表の平尾剛さんと対談したときに、「勝ち負けというのは人間が成熟する上での方法論に過ぎない」と平尾さんがおっしゃっていたのが僕の中ですごく腑に落ちたんです。人間の成熟のためには勝つことも負けることも必要だって、学校教育では教わったことがなくて、むしろ勝たなければならないみたいなことを植えつけられるじゃないですか。生き残らなければならない、勝ち続けなければいけないという価値観に支配され続けて、その価値観と「ちゃんとしなさい」が結びついたときには、これほんまにしんどいよなと思うんです。
松本:そうですね。ゲームに参加しているときは勝ち負けに一生懸命になるけれど、一方でそこに没入しきらずに、ゲーム全体を俯瞰するような視点を同時に持っていることが大事なんでしょうね。
仏教に引き寄せた話をするなら、もちろん宗派によっても違いはありますが、ブッダの教えの根本には「あらゆるゲームから降りる目線を持て」という考えがあります。言い換えるなら、執着から離れなさい、ということです。自分の意思でゲームから降りることもできるならいいけれど、それ自体が唯一の依存先になってしまうと苦しいだろうなと思います。
執着を自覚し、終わりなき修行に身を投じる
竹端:いまおっしゃったのは、「執着を自覚する」という理解であっていますか?
松本:ええ。お釈迦様のように執着を完全に手放すことはどうしてもできません、私は人間なので。けれど自分がなにかに執着していると自覚することは、依存先をひとつに絞らないための安全弁のようなものとして機能すると思います。
竹端:子育てしていても、執着を自覚できるかどうかは大事な観点やなと感じます。子どもはコントロールしきれない、けれど親という立場や権力の扱い方次第では、強くコントロールすることも不可能ではない他者として、目の前に存在しているじゃないですか。自分の執着を自覚していないと、無意識に子どもを支配したり虐待してしまう可能性が十分にある。
執着を自覚するためには、まず自分が執着を持っているという事実に向き合わなければいけない。自分の影を影として認めて引き受けるのって、すごく大変で面倒くさいことですよね。
松本:たしかに面倒くさいですよね。しかもそれを自覚した上で克服しているようなふりをしていても、実際にはもっと根深い問題だったりする。
竹端:うん、あたかも克服したふりをしていても、「ちゃんとしなさい」って子どもに言ってしまいたくなるときもあるわけです。子育てって、執着を自覚し、それとうまく付き合っていくための修行のプロセスなんじゃないかと思うことさえあります。
松本:そうでしょうね、きっと。たとえば、曹洞宗の道元禅師は、修行には決まったゴールがあるのではなく、修行していくプロセスの中にこそ悟りがあると説いています。だからこそ、修行の中では「掃除」が大事にされているのかもしれない。掃除って終わりのない営みですからね。
竹端:いまおっしゃった「終わりなき営みとしての掃除」というのは、「終わりなき営みとしてのケア」と言い換えてもいいような気がしました。子育てとか介護とか、生老病死に関わるものがケアだと考えると、ケアはまさに終わりなきものなんですよね。終わりはないけれど、考えようによってはその中で人は成熟していく。
近年、「ケア中心の社会」と言われるようになってきたのは、新自由主義的・資本主義的な契約に基づいた「成長」ではない、別の成熟のあり方を求めている人が増えてきたからなのかもしれないですね。
松本:企業社会は、いまでも右肩上がりでスキルが高まり知識が増えていくことこそ成長だ、という考え方がベースにあるとは思います。ただ私は最近、僧侶が企業の社員や経営陣の方々と1on1の対話をする「産業僧」という取り組みをしているんですが、そんな仕事が成立するということ自体に時代の変化を感じはしますね。
竹端:そうですね、たしかに。
松本:目指すゴールに向かってプロセスがあるのではなく、プロセスの中にこそゴールがあるという、道元禅師の教えのような考え方に、少なくない数の人たちが可能性を感じているのかもしれないなと。
竹端:現代は未来の予測ができない時代と言われますが、その中では決まったゴール、つまり解決すべき課題に対する答えよりも、どんな問いを立てるかのほうがむしろ大事になってくる。内的な自己とつながっていない限り、問いは生み出せない気がするんです。産業僧が求められるのも、そういうニーズがあるからなのかもしれない。
成熟に必要なのは、答えではなくむしろ問いだ、というのは子どもと接していても本当によく思うことなんです。子どもが問うてくることの中に、「ほんまにそれでよかったんやろか?」「ちゃんとするってなんやろ?」と感じさせられるようなことがたくさんあって、それが自分自身と向き合う機会にもなっているなと。
松本:ええ、問いを立てる力というのは本当に大切ですね。これまでの学校教育を通じて、「問いには必ず唯一解があり、それを当てられなければ失格になる」というマインドセットになっている人はとても多いように感じます。企業研修をしていても、マネージャーや人事がどんな正解を求めているかを想定して当てにいこうとする人はいますね。
竹端:いま、大学でもアクティブラーニングが取り入れられ始めているんですが、自由に主体的に発言することのできる場というもの自体がこれまでなかったから、学生がそれを信用してないんですよ。
松本:うん、そうなるでしょうね。
竹端:授業の中で議論していても、「先生、この話の落としどころは?」みたいなことを学生がふつうに聞いてくる。そういうふうに、先生が納得するような方向で喋らへんとスルーされる授業が多かったからって言うんです。
松本:先生がやりたいと思っている授業の理想像みたいなものを満たしてあげよう、想定解を出してあげなきゃと思うんでしょうね。
「不確実さの海」に飛び込んでいくこと
竹端:実を言うと、昔は僕もそういうことを学生に求める教師だったと思うんです。でもここ5~6年で、オープンダイアローグ(※注1)という精神医療で用いられる対話のしかたを学んだことをきっかけに、自分の姿勢が大きく変わったのを感じています。
※注1:オープンダイアローグとは:フィンランドにある精神科の病院で生まれた取り組み。精神障害のある人やその家族の苦悩に耳を傾け、問題を解きほぐしていく対話実践。「オープンダイアローグ・ネットワークジャパン」は「対話実践のガイドライン」を公開している。
竹端:オープンダイアローグでは、「無理に話をひとつにまとめようとせず、いまこの場で出た発言をそのまま引き受けてください」と言われるんだけど、それにほんまにびっくりしたんです。そこで学んだことを自分の生き方に取り入れようと思ったら、学生たちから想定外の発言が出てきても、無視できなくなってしまったんですよ。……これって正直、めっちゃ苦しいんです。
松本:ええ、ええ(笑)。
竹端:教員としては、授業はこんなふうに進めたいという既定路線というか、ある種の執着がやっぱりあるわけです。そこで学生が全然違う方向からボールを投げてきたときに、その発言に着目しようと思うと、教員にとっては不確実さが最大化する。
オープンダイアローグの大切な原則のひとつに、「不確実さに耐える(Tolerance of uncertainty)」というものがあります。相手の言葉を信頼し、先の見えない海の中に一緒に飛び込め、というんです。そんなふうに、いまここで差し出されたことを尊重しながら相手に寄り添うことって、正直めっちゃ面倒くさいし、僕も毎回できてるわけじゃない。でも、たとえば授業の中でそれができたときって、グルーヴ感というか、学生たちと一緒につくりあげている感じがすごくあるんです。
松本:グルーヴ感、わかります。オープンダイアローグ的な姿勢でいることって、本当におっしゃるとおり、しんどさもあるんですよね。なにが起こっても引き受けろって言われても、いやいや、ちょっと引き受けきれないよって思う自分もいる。
竹端:そうなんですよ、ほんとに。
松本:私は産業僧として、企業で働いている会社員の方と1on1の対話をすることがあるんですが、それって出家的時間とも言えるような気がしているんです。企業で働いている方も僧侶である私も、普段はそれぞれに社会的な役割を背負っている。会社員というゲーム、僧侶というゲームを生きていると言ってもいいかもしれない。対話の中でそのゲームから降りて、なにが起きるかわからない不確実さに身を委ねてみようとしているわけです。それを引き受けられたとしても引き受けられなかったとしても、最後はみなさんにお任せというマインドでやってみよう、と最近は思ってますね。
竹端:不確実な海に飛び込む、というね。でも、それがちゃんとした仕事として認められる社会なのかどうかが問題ですよね。「ちゃんとする」ということは筋書きをきちっと決め、それ通りにやりきることだと頑なに思い込んでいる人はどの業界にもいるなと感じます。
きょうの対談は、編集の垣花さんが特に筋書きを決めずに最初のボールだけ投げてくれはったから、松本さんと私が対話を通じて、徐々に「一緒になにかを生み出す」モードに変わってきている。もちろん、最低限の「ちゃんと」は意識してるんだけども(笑)、そのあわいをどんなふうに生きていけるかですよね。
たとえば僕が大学のゼミ生と卒論のテーマについて対話しているとき、研究テーマを掘り下げていった先で自分の中にあった問題意識や生きづらさにぶつかって、涙を流す学生がときどきいるんですよ。教員として「ちゃんと」既定路線に沿った卒論指導をしていたらおそらくそんなことは起こらないんだけど、僕としては、卒論を通じてなにか自分のコアの部分にまでつながるようなことを学生が考えられたんだとしたら、よかったなと思って。その人にとっての成熟のプロセスのようなものとして、卒論を活用してもらえたのかなと思うんです。
松本:なるほど。それで思い出したんですが、実はいま、データサイエンティストの人と組んで、僧侶対話の中でAIの音声感情解析アルゴリズムを活用してみてるんですよ。医療でも用いられているような、声からその人の感情を解析するというものなんですけど。
竹端:AIで? へええ。
松本:それを使って僧侶と対話した人たちの感情を解析してみると、実は悲しみが増している人が多いんです。その結果だけ見ると、わざわざお坊さんと話して社員悲しませてどうするんだって思うかもしれないけれど(笑)、そうじゃないんですよと。
悲しみって、自分自身の痛みや苦しみに気がついたことで生まれるものですから、気がつかずにしんどいままでいると、それがさまざまな形で暴発してしまうこともあるわけです。だから、悲しむことをことさらネガティブに捉える必要はないんですよね。悲しむことって創造性にもつながっていくし、その創造性は、もっと大きな「わからなさ」にも接続していく。
竹端:いまのお話を伺っていて、悲しみを受け入れるというのは、「悲しんではいけない」という思考のリミッターを外すことなんやなと思いました。社会でちゃんとしているためには、至るところに張り巡らされている、「してはいけない」のリミッターを守らなければいけない。このリミッターを切ることは、実は自分自身の束縛から自由になるための第一歩なんだけど、それをしたら社会から外れてしまうんじゃないかという怖さが常につきまとう。それによって、僕たちは自分の悲しみにもなかなか気づくことのできない主体に矮小化されているんじゃないか。
でも、たとえば松本さんのような同伴者がいることで、「悲しんでもいいんだ」って思考のリミッターが外れるんでしょうね。思考のリミッターが外れるということはつまり、わかったふりができる範囲を超えてしまうということやと思うんです。
松本:ええ、そうですね。
竹端:おそらく、それこそが不確実さの海に入るということなんでしょうね。みんな普段は思考にリミッターをつけて、「確実さ」の中に縮減してわかったつもりで生きているから、なんだかよくわからないことがあるというのはすごく不安なんですよね。でも、それについて一緒に考えてくれる人がいたり場があったりすると、それでもいいんやって思えたり、自分がすこし開かれてくるんちゃうかなと。
他者と出会うことで、自分に出会いなおす
竹端:卒論について考えていく中で自分のコアに触れるようなテーマに出会い、思わず泣いてしまう学生を見ていると、彼らは他者と出会うことで自分と出会いなおしてるんやろな、と感じるんです。そういうものを受けとれる関係性や場がいますごく少なくなってるんちゃうかなと思うから、涙を流した学生は「泣いてすみません」って言うけど、僕は「いやいや、よかったやん!」っていつも返すんですよね。
松本:本当にそうですよね。いまは、大学の学生と教員であれ、僧侶と檀家であれ、お互いがお互いを「ちゃんと」させる、記号として利用するだけの関係にはまっていく力学が強くなりすぎているのかもしれないですね。私自身、大学教員でもあるので強く感じるんですが、結局、その部分しか評価されないし飯の種にならないという問題がありそうですよね。
竹端:自戒を込めて言うと、大学教員には、そうじゃないやり方がそもそもわからないという人は多いと思うんですよ。
松本:それに、勇気が出ないというのもありそうですよね。
竹端:どこにいくのかわからない、コントロールできない議論が怖いという?
松本:ええ。そんなことをしてしまったら、ちゃんと授業をやっていない教員だと思われて、授業評価でネガティブなこと書かれるんじゃないかと。
竹端:そうでしょうね。でも、変な話ですけど、僕の場合は固定化された考えだとか学習指導案を手放したあとのほうが、授業評価はよくなりました。
松本:ああ、絶対そうだろうと思います。
竹端:指導案を手放すと、こちらが教えたい内容から授業がどんどんそれていってしまうかというとそんなことはなくて、むしろ根源的な議論ができることが多い。本来の学びというのは、教師が一方的に教え、学生がそれを聞くのではなく、その場で出た論点について考え合う中で、こちらも新しい発見を得て、可能性を探究していくものだと思うんです。
でも、いまは非常に縮減した教育になってしまっている。そっちのほうがわかりやすいし、「ちゃんと」見せやすいんですよ。
「ちゃんとしなくていい」と感じられる場のためには、なにが必要か
──ここまでおふたりのお話をお聞きしていて、「ちゃんとしなくてもいい」関係性や場づくりのためには、そう思えるような安心感を担保するためのカギがなにかあるのではないかと感じたのですが、いかがですか。
松本:ああ、たしかにそうですね。のびのびとプレーできる場や関係性のためには、そうしてもいいという安心感が担保されている必要があると思います。
私の場合、企業の方との対話の中で、「この仕事以外にも生きる道はあるんじゃないですか?」というようなことをあえて言うときがあるんです。ここにしか自分の居場所はない、このゲームを降りたら自分の人生は終わりだと思い込んでしまうと、発想もどんどん縮減していきます。でも、「他にも選択肢はあるけれど、いまはこのゲームをプレーするんだ」と引き受け直すことで、かえってのびのびとプレーできるようになると思うんです。東京大学先端科学技術研究センター当事者研究分野准教授 熊谷晋一郎さんの言葉に「自立とは依存先を増やすこと」というものがありますが、まったくその通りで、依存先をどれだけ多様化できるかが大事だと思います。
それを聞いて「そんなふうにできる人は、そもそも『コミュ力』が高いんだろう」と感じる方もいるでしょうし、それもたしかに一理あると思うんですね。ただ、私は依存先というのは必ずしも複数の職業やコミュニティじゃなくてもいいと思いますし、もっと言えば人間じゃなくてもいいと思う。たとえば、都会で生活していると周囲の人のことだけで頭がいっぱいになりがちですが、ときどき山登りをしたりして自然に触れてみると、動物や植物、微生物の中に人間がいるということを思い出すかもしれませんね。私たちはすでに、いろいろなものに否応なく依存しているんだと確認するのも大切なことだと思います。
竹端:松本さんがおっしゃったこと、まったくその通りやと思います。僕からそこにひとつつけ加えるとしたら、安心できる場をつくっていくためには、自分自身の執着や弱さを自覚した上で、そういう自分を否定しないことも重要だと思うんです。脆弱さを抱えた私と脆弱さを抱えたあなたがいるということを認め合った上で、取り繕わなくてもここにいていいし、取り繕わないあなたの声も聞かせてほしい、そして取り繕わない私の声も聞いてほしい、という姿勢でいることが大切なんじゃないか。
松本:うん、うん。
竹端:「あなたの声は聞きたいけれど、私のほうは何も言いません」ではだめなんですよね。お互いがお互いの声を聞き合うことで初めて、共に支え合う場へと発展していく。その際に、より大きく権力を持っている側、たとえば1on1ミーティングにおける僧侶と会社員であれば僧侶、医療者と患者であれば医療者側が率先して自分を開き、自分の実存を差し出した上で対話することができるかどうかにかかっていると思います。
僕は共鳴というのは、ハーモニー(調和)ではなくポリフォニー(多声)だと思っています。音をひとつに同化して響かせるのではなく、違う音が違う音のまま鳴り合う、という。そのためには、「他者の他者性」を尊重するだけでなく、自分の唯一無二性も大事にしなくてはいけないんですよね。自分の音、つまりふとしたときにぽろっと出てしまう自分らしさを無理に消し去ろうとせず、「あ、この人にはこんな音もあるんや」と、他者の音にも共鳴しようとする。そういう積み重ねの中でポリフォニックな関係性や場が展開していくと、より自分の音も他者の音も豊かになっていくんじゃないかと思うんです。
松本:そうですね。……なんだか、このテーマで呼んでいただくようなふたりということもあって、「わからなさ」に身を投げ出すことに慣れている分、どこに行ってもまあなんとかなるだろうみたいな安心感がお話ししている間ずっとありましたね(笑)。風呂に入りながら喋ってるみたいな。
竹端:風呂ね、たしかに(笑)。
松本:竹端さんのおっしゃるポリフォニー、本当にその通りだなと思いながらいま聞いていました。親鸞の歌の中に「宮商和して自然なり」という言葉があるんですが、宮と商というのは音符のことで、本来このふたつは不協和音なんです。合うはずのない音がポリフォニックに響いている。それが浄土であり、仏の世界なんだみたいなことを親鸞は言うんです。
私は、対話って音楽みたいだなと思うんですよね。親子とか夫婦とか家族というのは、バンドみたいなものかもしれない。メンバーがなかなか入れ替わらないベテランのバンドですかね。その中で徐々に成熟していく音があったり、ときには楽器がうまくなったりもする。きょうみたいなのはセッションですよね。それもまたよしだなって。
竹端:うん、即興演奏ですね。相手の音と自分の音を大事にしながら豊かな即興演奏をし続けることのほうが、「ちゃんと」やるよりもはるかに大事だってことですよね。
松本:うん、うん。そうですね。
Profile
Profile
- ライター:生湯葉シホ
-
1992年生まれ、東京在住。フリーランスのライター/エッセイストとして、おもにWebで文章を書いています。Twitter:@chiffon_06
この記事の連載Series
連載:こここスタディ
![]() vol. 272025.04.18“家庭”ってなんだろう? 子どもと大人が尊重しあう場所を目指す、児童福祉施設「てらす峰夢」をたずねて
vol. 272025.04.18“家庭”ってなんだろう? 子どもと大人が尊重しあう場所を目指す、児童福祉施設「てらす峰夢」をたずねて![]() vol. 262024.12.06差別と関係のない立ち位置ってあるの? 社会のあり方に矢印を向けて考える
vol. 262024.12.06差別と関係のない立ち位置ってあるの? 社会のあり方に矢印を向けて考える![]() vol. 252024.12.06差別ってなんだろう? 現代社会における差別の研究者 阿久澤麻理子さんをたずねて
vol. 252024.12.06差別ってなんだろう? 現代社会における差別の研究者 阿久澤麻理子さんをたずねて![]() vol. 242024.08.14正しい答えを刷り込むのではなく、自分で選ぶ手助けをする「包括的性教育」とは?
vol. 242024.08.14正しい答えを刷り込むのではなく、自分で選ぶ手助けをする「包括的性教育」とは?![]() vol. 232024.07.31「性教育」という言葉から何を想像する? 教育学者 堀川修平さんによる「包括的性教育」解説
vol. 232024.07.31「性教育」という言葉から何を想像する? 教育学者 堀川修平さんによる「包括的性教育」解説![]() vol. 222024.07.17「創造性」はどう育まれる? ブルーノ・ムナーリの軌跡から──デザイナー、現代美術作家、教育者のまなざし
vol. 222024.07.17「創造性」はどう育まれる? ブルーノ・ムナーリの軌跡から──デザイナー、現代美術作家、教育者のまなざし![]() vol. 212024.03.30「個人の心の問題」の多くは環境や政治の問題でもある〜「あなたのため」というバウンダリーの侵害〜
vol. 212024.03.30「個人の心の問題」の多くは環境や政治の問題でもある〜「あなたのため」というバウンダリーの侵害〜![]() vol. 202024.03.26自分と他者を区別する境界線「バウンダリー」とは?ソーシャルワーカー鴻巣麻里香さんによる解説
vol. 202024.03.26自分と他者を区別する境界線「バウンダリー」とは?ソーシャルワーカー鴻巣麻里香さんによる解説![]() vol. 192024.02.01「昔好きだった作品」の表現に戸惑ってしまったら? フィクションが与える2つの影響──文学研究者・小川公代さん
vol. 192024.02.01「昔好きだった作品」の表現に戸惑ってしまったら? フィクションが与える2つの影響──文学研究者・小川公代さん![]() vol. 182023.12.15「合理的配慮」は「ずるい」「わがまま」なのか? インクルージョン研究者 野口晃菜さんによる解説
vol. 182023.12.15「合理的配慮」は「ずるい」「わがまま」なのか? インクルージョン研究者 野口晃菜さんによる解説![]() vol. 172023.04.21“できる/できない”の社会を「ヨコへの発達」で問い直す。社会福祉の父・糸賀一雄を、垂髪あかりさんが研究する理由
vol. 172023.04.21“できる/できない”の社会を「ヨコへの発達」で問い直す。社会福祉の父・糸賀一雄を、垂髪あかりさんが研究する理由![]() vol. 162023.02.08「やさしい日本語」ってなに? 言語学者・庵功雄さんに聞くコミュニケーションの本質
vol. 162023.02.08「やさしい日本語」ってなに? 言語学者・庵功雄さんに聞くコミュニケーションの本質![]() vol. 152023.01.27人を見た目で判断することって全部「差別」になるの? 社会学者 西倉実季さんと、“ルッキズム”について考える
vol. 152023.01.27人を見た目で判断することって全部「差別」になるの? 社会学者 西倉実季さんと、“ルッキズム”について考える![]() vol. 142023.01.16自分の気持ちを話さない自由がある。NPO法人ぷるすあるはと一緒に考えた“きもち”との付き合い方
vol. 142023.01.16自分の気持ちを話さない自由がある。NPO法人ぷるすあるはと一緒に考えた“きもち”との付き合い方![]() vol. 132022.12.14“障害”ってそもそも何だろう? 困難の原因を「社会モデル」から考える──バリアフリー研究者・星加良司さん
vol. 132022.12.14“障害”ってそもそも何だろう? 困難の原因を「社会モデル」から考える──バリアフリー研究者・星加良司さん![]() vol. 112022.10.27“ありのままの自分”を大切にするって、どういうことだろう? しょうぶ学園施設長 福森伸さんをたずねて
vol. 112022.10.27“ありのままの自分”を大切にするって、どういうことだろう? しょうぶ学園施設長 福森伸さんをたずねて![]() vol. 102022.09.27「福祉の現場」と「芸術」の根っこには通ずるものがある? 福祉環境設計士 藤岡聡子さんをたずね、「ケアの文化拠点」ほっちのロッヂへ
vol. 102022.09.27「福祉の現場」と「芸術」の根っこには通ずるものがある? 福祉環境設計士 藤岡聡子さんをたずね、「ケアの文化拠点」ほっちのロッヂへ![]() vol. 092022.09.07“健康”ってなんだろう?ケアの文化拠点「ほっちのロッヂ」紅谷浩之さんをたずねて
vol. 092022.09.07“健康”ってなんだろう?ケアの文化拠点「ほっちのロッヂ」紅谷浩之さんをたずねて![]() vol. 082022.08.12弱さは個人の問題ではなく、構造上の問題だ。公認心理師・臨床心理士 信田さよ子さんと考える“弱さ”のこと
vol. 082022.08.12弱さは個人の問題ではなく、構造上の問題だ。公認心理師・臨床心理士 信田さよ子さんと考える“弱さ”のこと![]() vol. 072022.07.28“違う“の不安をどう乗り越えればいい? グレーではない「色」で表現する発達の特性──星山麻木さん
vol. 072022.07.28“違う“の不安をどう乗り越えればいい? グレーではない「色」で表現する発達の特性──星山麻木さん![]() vol. 062022.04.12「私はどう生きたらいい?」を、一人で抱えない社会へ。医師・西智弘さんに聞く、地域活動と“ケア“の文化づくり
vol. 062022.04.12「私はどう生きたらいい?」を、一人で抱えない社会へ。医師・西智弘さんに聞く、地域活動と“ケア“の文化づくり![]() vol. 052022.03.22偏見がない人はいない。川内有緒さん×木ノ戸昌幸さん『わたしの偏見とどう向き合っていく?』イベントレポート
vol. 052022.03.22偏見がない人はいない。川内有緒さん×木ノ戸昌幸さん『わたしの偏見とどう向き合っていく?』イベントレポート![]() vol. 042022.02.04居場所・つながり・役割・生産性。「望まない孤独」をめぐる対談でみえたものとは?吉藤オリィさん×奥田知志さん
vol. 042022.02.04居場所・つながり・役割・生産性。「望まない孤独」をめぐる対談でみえたものとは?吉藤オリィさん×奥田知志さん![]() vol. 032021.10.26大切なものを失った悲しみや痛みと共に生きていくには? グリーフサポートが当たり前にある社会を目指す 尾角光美さんをたずねて
vol. 032021.10.26大切なものを失った悲しみや痛みと共に生きていくには? グリーフサポートが当たり前にある社会を目指す 尾角光美さんをたずねて![]() vol. 022021.06.24差別や人権の問題を「個人の心の持ち方」に負わせすぎなのかもしれない。 「マジョリティの特権を可視化する」イベントレポート
vol. 022021.06.24差別や人権の問題を「個人の心の持ち方」に負わせすぎなのかもしれない。 「マジョリティの特権を可視化する」イベントレポート![]() vol. 012021.04.15さまざまな側面をもつ「わたし」と「あなた」をそのまま大切にするには? 美学者 伊藤亜紗さんを訪ねて
vol. 012021.04.15さまざまな側面をもつ「わたし」と「あなた」をそのまま大切にするには? 美学者 伊藤亜紗さんを訪ねて