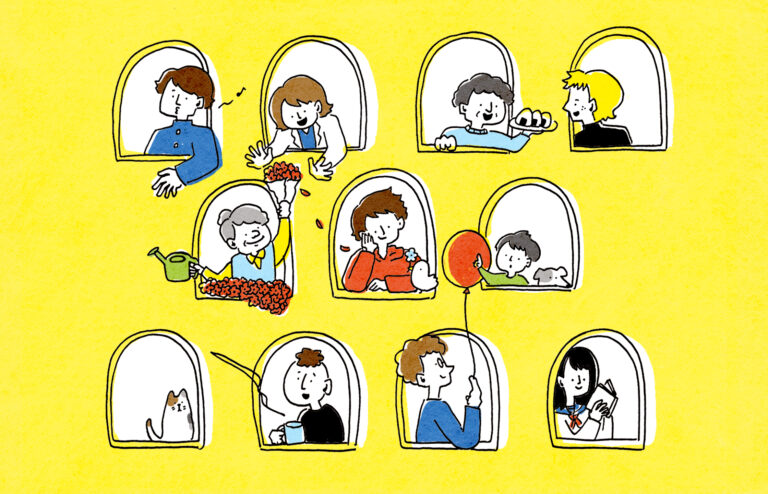「昔好きだった作品」の表現に戸惑ってしまったら? フィクションが与える2つの影響──文学研究者・小川公代さん こここスタディ vol.19
子どものころ夢中になっていた漫画やアニメ、小説。大人になった今見てみると、当時を懐かしく思う一方で、「男らしさ」や「女らしさ」の表現が目についたり、「セクハラ」や「パワハラ」とも取れるシーンが気になったりしてしまって、昔のように無邪気に楽しめなくなることが増えた。
描かれている振る舞いと、現代の価値観とのギャップに少しでも気づいてしまうと、「私、その作品好きだったんだよね」という言葉さえ、もはや言い出しにくい気持ちになる。時代や自分の価値観が変わった……と言ってしまえばそうだけれど、その作品が好きだった過去の自分さえも否定するようで、どこかさみしい。
私たちは、自分の、あるいは社会の変化を受け止めながらも、かつてのめり込んだ“古い”作品を楽しむことはできないのだろうか。
今回たずねたのは、上智大学外国語学部教授で、文学研究者の小川公代さん。著書に『ケアの倫理とエンパワメント』や『ケアする惑星』などがあり、英文学を中心にフィクションに潜む「ケア」の視点を読み解きながら、映画や漫画、アニメ作品などにも幅広く言及している。ジェンダーをはじめとする表象の問題に人一倍気づかれるはずの小川さんは、過去の作品をどのように楽しんでいるのだろう。
小川さんが昔好きだった漫画の話を入口に、物語をどう楽しんでいるか、自らの価値観や気持ちの変化をどう受け止めているのか伺いながら、フィクション作品の役割と、時代を超えて付き合う方法を一緒に考えた。
性役割にルッキズム……問題だらけの“昔”の作品
──昔好きだった作品に触れて、戸惑うことが最近よくあるんです。例えば、夢のある子どもの漫画に急に女の子のお風呂をのぞくシーンがあったり、恋愛モノの小説でも、上司/部下の関係を使った強引な誘い方をしていたり。そういう、「今見たらこれって……」みたいな経験、小川さんはありませんか?
小川公代さん(以下、小川) 私が幼少期に一番影響を受けたのは、漫画雑誌です。毎月姉と少女漫画雑誌を買って交換していたほか、少年漫画にも目を通していましたね。その時はただ夢中でしたけど、読み返してみるとおっしゃるように、本当に開いた口が塞がらない場面はもうあちこちにあります。

──例えばどんな描写で感じますか?
小川 まずはやっぱり、極端な性役割に目が行きます。大抵の少女漫画の主人公の女の子は、好きな男性と思いが通じることを夢見ているんですよね。それって「主人公が憧れているような、すてきな男の子に幸せにしてもらいたい」とか「結婚して家庭に入ることがゴールだ」という恋愛、あるいは結婚志向の未来像を強めてしまうなあと。実際、日本でアメリカやヨーロッパ諸国に比べ性役割がはっきりしている大きな理由に、私は女性が社会の中で活躍する物語が少なかったことがあると思っています。
例えば、私が姉と一緒に没頭して読んだ少女漫画の『ときめきトゥナイト』(作/池野恋)。吸血鬼と狼女を両親に持つ魔界の女の子・江藤蘭世は、将来に夢がなくて、好きな人・真壁俊との結婚を夢見ている主人公として描かれています。またこの作品には、「主人公の女の子が好きな男の子の家になんとか入り込んで、行きがかり上、彼の裸を見る」というシーンもあります。MeToo運動をはじめ、女性の権利は主張されるようになってきたけれど、男性が性的なまなざしで見られることに対する意識はどうなのかなと改めて考えましたよね。
──たしかに、そちら側の議論ってあまり発展してこなかった気がします。
小川 そのことと、例えば芸能事務所における、男性アイドルの性被害の問題って、実は繋がっていると思うんです。被害者が男性だったからこそ、指摘が遅くなった可能性もある。冒頭でおっしゃった女の子のお風呂の場面だけでなくて、今はもう男女関係なく、性的に消費されること自体に問題があるのではないでしょうか。
ただ、そんなことは小学生だった私にはわからなかった。今、被害を訴えておられる方々も、その当時に自分が性的な対象になり得ることを理解するのは難しかっただろうと思います。
──人を性別などのカテゴリーで捉え、モノのように扱っていく視点は、今見ると少なくなかったですよね。
小川 関連して、昔の作品にはルッキズムの問題が現れていることもよくあります。例えば、主人公のライバルの容姿が面白おかしく描かれると、主人公に感情移入している読者は、恋敵の容姿が笑われることについ快楽やユーモアを感じてしまう。それは私自身にも起きる感情です。でも、こうしたことは今の時代には許されないので、大好きな作品だけど倫理的にどうなんだろう……とモヤモヤしちゃいますね。
──容姿に関する表象は、やはり昔の作品ほど気になる気がします。
小川 今だと、仮に不恰好とされる容姿をテーマにしていても、周囲の人々の見え方が変わっていく過程をすごく緻密に描くことで、ルッキズムの問題をどうやってみんなで解決していけばいいか問う物語が増えていますよね。そうした作品に共感する私は、昔の漫画作品などの、容姿を笑って手軽なユーモアを描いてしまえ、みたいなところで複雑な気持ちになることはあります。
ただそれでも、「こんなシーンがあるから、この作品はもう読むことはできない」とはならないんですね。むしろなぜそんな描写があるのかと考えながら、さらに精読していくんです。そのことによって、現代の作品との違いや、当時の社会にあった問題など、いろんな側面が見えてくると私は思っています。
フィクションがもたらす「解放」と「固定観念」
──著書やトークイベントなどでのお話を見ていると、小川さん自身は過去のものも現在のものも、さまざまな作品を楽しまれている印象があります。どのように受け止めているか、具体的に伺えますか?
小川 隅々まで物語を読み込みながら、特定の描写だけで判断せずに保留するようにしています。「問題あるシーン」で嫌になってしまう気持ちも理解しつつ、それだけで読むのをやめてしまうのは、もったいないんじゃないかと思っているんですね。
なぜなら、物語ってそんなに単純ではないから。その中に含まれているさまざまな要素を抽出していくと、同じ作品内で全く逆の、すごく共感できる側面に出会うことも多いんですよ。すべての作品に対してそうするので、どんな物語でも楽しく読んでしまうのかもしれないです。
例えば、先ほど言及した『ときめきトゥナイト』には進歩的な側面もあるんです。性役割が一見パキッと分かれている漫画ですが、正反対の表象も実はちゃんとあって、例えば蘭世のお父さんじゃなく、お母さんのほうがめちゃくちゃ戦うんですね。蘭世自身もたくましいお母さんを見て育っているから、いざとなったら、パートナーの真壁くんよりもリスクを背負って戦いに出るんです。
──単純に「女性は男性の“お嫁さん”になって守られる」という物語ではないんですね。
小川 もちろんそういう場面もちょこちょこは出てくるし、そこに共感する人もいると思うのですが、最近読み返してみて私も新鮮だったのは、「将来〇〇くんの“お嫁さん”になる」という夢見がちな乙女の物語ではないことです。むしろ蘭世は、真正面から「これは正しくてこれは間違っている」と自分の倫理観で判断、抵抗する主人公として描かれていた。私がかつて共感したのは「戦って自分が信じたことを成し遂げる」という部分だったんだ、と改めて気づくことができました。
──作品やそこに現れる表象は一面的ではなく、読み方によってさまざまな捉え方ができるということですね。
小川 そうです。だから作品が人に与える影響にも、実はいろんな側面があるはずなんですよね。
もう1つ作品を挙げると、『ざ・ちぇんじ!』(作/山内直実、原作/氷室冴子)も、私の大大大好きな少女漫画です。平安時代の宮廷貴族社会に生きる双子の男女が入れ替わる物語で、男らしい女性である主人公が自由に生きられる性役割を手に入れて、野心的にいろんなことをするさまをわくわくしながら読みました。一方で、お互いが好きな人を見つけたことをきっかけに元の性に戻ってしまう結末もあり、「やっぱり女性は女性として生きるしかないんだ」と思って、少し悲しかったことも覚えています。
私自身も国際政治を勉強したり、男らしいことを学部生の頃まではしていながら、海外留学を終えたときに結婚をしました。それはこうした作品の影響も大きかったなと思っていて。やっぱり幼少期に読んだものって、自分の魂に刻まれていく気がするんです。
──物語には、読んだ人の人生や価値観を左右してしまう怖さがありますね。
小川 ただ私の場合、結婚をしたことで、自分とは異なる性別の人の気持ちや、違う立場の方との付き合い方がわかるようになった面もあるとは思います。ケアフェミニズムを実践するなかでも、最初は女性の立場から女性の権利を訴えようと思っていたのですが、今では「男性にいかに味方になってもらえるか」ということも考えられるようになりました。それができるようになったのは、近しい男性である夫を信頼できたことが大きいと感じるんです。
そう思うと、少女漫画をたくさん読んでよかったのかなと。私を解放してくれた側面と、私に今もつきまとってくる固定観念の両義性を感じながら、どんな物語も読んでいます。

物語の“文脈”から「ケアの倫理」が見えてくる
──お話を聞いていて、複数の価値観の間で揺れ動くことをとても柔軟にされてるなと感じました。小川さんはなぜ、そのようにしなやかさを保ってこれたのでしょうか?
小川 どうなんでしょう……。ひとつには、私が政治・社会学から転向したことと、新たな研究対象にロマン主義文学を選んだことが関わってくるかもしれません。
実は大学の卒業論文では、パートタイムで働く女性の調査をしていました。女性の権利が主張されている時代にあって、能動的に生きようとしても阻まれている人たちの内面世界を知ろうと、彼女たちにインタビューしたんです。でも、なかなか本心を引き出すことができませんでした。
彼女たち自身も自分の内面世界からブロックされているように感じたとき、じゃあそこを知るために何が残されているかというと、物語(ナラティヴ)だと思ったんです。すでに何百年もかけて、いろんな人たちが自分たちの内面世界を語り、それが文学として残されてきている。誰にも言えなかった苦しみや痛み、思いを、特に女性が書いたものから読み取ることを研究にしようと思って、文学に転向しました。そしてその中でも、近代黎明期における人の「揺らぎ」があったロマン主義の時代を選びました。
──理性的な「近代人」像がつくられていった時代でしょうか?
小川 その少し後と言えます。個として自由な、自立する人間像を描いても、みんながみんな自分の思い通りに生きていけるわけではないんですよね。そこでロマン主義では、政治家や権力者ではなく、ウィリアム・ワーズワースの『ルーシー詩篇』などに代表されるように、名もなき人の生に重きが置かれていくんです。
近代は人の営みを理論化、制度化した時代ですが、「次の瞬間、自分はどう感じるんだろう」とか「全くの他者と出会ったときに、自分はどんな感情を持つんだろう」って、実際はものすごく偶発的にしかわからないですよね。自分のしたことが正しいか誤っているかも、結局は前後の“文脈”の中でしか判断できない。だからこそ、人の物語をもっと精読して、想像力を働かせることが大事じゃないかと私は思ったんです。

──物語に散りばめられたさまざまな要素から、社会における問題も捉えていくということでしょうか。
小川 ええ。メアリ・ウルストンクラフトという先駆的なフェミニストは、「正しいということはその都度変わっていく」ということを強調しています。彼女は、誰かの権利の擁護よりも普遍的な慈愛を大切にしている人で、それは今考えると「ケアの倫理」なわけですよね。近代的な、絶対的な正しさを求める「正義の倫理」では、どうしても特権を持つ人間にとっての正誤という二項対立的な思考になりがちですが、「ケアの倫理」は「正義」を語ることさえできない弱者を含め、あまねく人々に対して何ができるかを考えます。
今の私たちはすでに、生産的な物事にしか反応しなくなってきていて、物語でも、家族の誰かの世話を焼いたり励ましたりするケアの場面を、すっ飛ばしてしまうことが多いです。でも、そういう営みも含め長いスパンで見ないことには、本来の姿は見えてこないのではないかと思います。
現在の価値観を持って、過去の作品に触れていく意味
──たしかにフィクション作品の中には、前後の話があったり、正反対の要素が描かれていたり、文脈を追うから見えてくるものがあります。「ある表象を切り取って評価する」ということ自体が、フィクション作品の意義と少しズレてしまうような気もしてきました。
小川 人の人生をまるまる文脈として捉えないと、本当は人間って判断できないと思うんです。そういう意味で一番わかりやすいのが、山崎ナオコーラさんが最近書かれた『ミライの源氏物語』。1000年の時間を隔て、現在の文脈で『源氏物語』を読み解いたときに何が言えるかということに注目して書かれた本で、本当に面白いんです。『源氏物語』って今の常識で読むと、性暴力や不倫、マウンティングなど問題だらけの作品ですから。
──まさに現代の価値観で読み解くと、違和感がたくさん生まれる作品ですね。
小川 例えば皇女の女三宮は、光源氏の親友の息子にレイプされているのに、夫の光源氏に対して罪の意識を持っています。これは現代の女性にもあることかもしれないですけれど、この時代は「不義密通」と表され、より罪の意識が濃厚なわけです。そして読者としては、女三宮が罪の意識を感じていると、なぜかレイプと思わず、「これは不倫なんだ」と受け入れてしまう部分があるんですよね。
でも今の時代においては「これは性暴力だ」と言えないといけないよね、と山崎さんは書かれています。ある種、教育的な本として『源氏物語』は読めるんだと私も思いました。
──一定の倫理観が浸透していなければ、描かれている性暴力に私たち自身気づくことができないと教えてくれるんですね。
小川 実際に『ミライの源氏物語』がたくさんの人に読まれているのは、1000年前とそう変わらない倫理観が、社会の中に浸透したままだからだと思うんですよね。1000年前と今がラディカルに違っていたら、話題にならないと思うんです。
最近、仕事関連で『源氏物語』を、子どもの頃に読んだ漫画『あさきゆめみし』(作/大和和紀)とあわせて読み返すことがあったのですが、そのときに改めて性暴力が描かれていたと気づきました。なぜ昔は気づかなかったかと思うと、私の倫理観もまだ『源氏物語』の時代と一緒だったんですよ。当時は「こういうこともある、モテる女はしょうがない」と読んでいて、それが悪であると受け取れなかったんです。
──むしろそれが当たり前だと思ってしまいますよね。
小川 物語が怖いのは、読み流すことによって、描かれている表象を内面化してしまうことです。日本の教育の現場では、文学を能動的に解釈する実践がなされていないのではないでしょうか。性に関する、ある物語だけが支配的だと、例えば性暴力の被害にあってもすぐには糾弾できないとか、あるいは自分が性暴力に加担していても気づけない場合も出てくる。性暴力の話を聞いた人もそれを正常化してしまったりする。実際、芸能界の性加害事件について無責任なことをSNSで発信する人も少なくありません。
なのでフィクションには、やはり両義的な働きがあると思うんですよ。1つは「これについてどう思いますか」という問題提起をする作用。もう1つは問題となり得る表象を人の内側に取り込ませて、正常化してしまう作用。ある意味で恐ろしい効果もフィクションにはあるわけで、その力をどう運用するかというのは、実は一人ひとりに委ねられているんだと思います。
「漫画の読み方講座」みたいなのを義務教育で受けさせてもらえれば一番いいんですけど、現状それがないわけで。だから今はすごく危ういな、とも思っています。
「対話」から物語を読む力が育っていく
──さまざまな生き方を読み取ることができる一方で、既存の価値観を強化してしまうことがある。そう思うと、作品選びに慎重になってしまったり、親だったら「もう昔の作品は子どもに見せられないかな」と思ってしまったりするのですが、良い付き合い方はありますか?
小川 私は甥っ子と一緒に住んでいて、よくやるのが、同じアニメを見て、見た作品について感想を話し合うことです。彼は多様な登場人物に共感できるところがあって、話していて私が気づかされることも多いですよ。
だから知識だけの問題じゃなくて、感性も重要かもしれないですね。違う世代の人と一緒に見たり読んだりして、意見を聞く。それを知って「そんなところを見ていたんだ!」と新しい発見をする。そういう対話のプロセスがつくれたら、必ずしも作品選びを管理するような方向に行かないで、いろんな作品からお互いに良い方向性を見つけていくことができると思います。
──子どもの発言から気づかされることも多いので、たしかに対話というのは大きなヒントだなと思いました。暴力や残虐なシーンがあっても大丈夫ですか?
小川 それも一緒に見ていて思いますが、そもそもある程度セレクティブに捉える能力が、人間にはあるのではと感じます。私自身幼い頃、暴力や残酷な場面は「見てはいけないんじゃないか」と思いながら魅了されてしまうところがありました。残虐性の中に、人間の本質を見るのかもしれません。でもそれは、必ずしも暴力を見たら暴力的な人間になるというわけではないと思います。暴力的なシーンの中で伝えようとしているメッセージを理解し、選別しながら受け止めることはできるので、そのサポートができればいいかなと考えています。

──とても参考になります。自分の感情を伝えたりしてもいいかもしれませんね。
小川 感情だけでなく、解釈をして手渡す方法もあると思いました。例えば「ここの暴力的な場面をつくった背景には、もしかしたらこういう展開につなげるための準備だったのかもね」とか。暴力を正当化するんじゃなくて、ナラティブの流れとして理由を一緒に考えると、人間はさまざまなシーンを重ねて毎日物語を紡いで生きているよね、というような方向に行けるかもしれません。
──ありがとうございます。最後にひとつ、物語作品には「一人でのめり込む」という向き合い方もあるかと思うのですが、その場合はいかがでしょうか?
小川 物語の世界にぐっと入って読むときも、常に自分自身と対話していると私は思うんです。その際、日頃誰かと物語について対話していると、それが思考するときの癖になるんですよね。
私の場合、職業的に文学については日々誰かと対話するので、一人で読んでいるときにも、さまざまな人の声が脳内に響きます。そういう意味で、対話の実践がどれぐらい頻繁にできているのかは重要かもしれません。一人でのめり込んでいるからといって、一人で読んでるわけじゃない。それまでに人と対話して培ってきたものこそが、物語を読み解いていくトレーニングになっていると思います。
取材後記:昔の作品を新しく面白がるために
フィクションだからこそ、人の内面世界を知ることができる。その魅力を改めて感じる一方で、小川さんの話を聞くと、やはりある種の価値観が内面化されたり、強化されたりしてしまうことを怖いと思った。振り返ってみると、学校の国語でも、いくつかの選択肢からひとつの正解を選ばされた記憶が強く、私たちは本当の意味で「物語を読む」訓練をしてこなかったのではないか。
小川さんに教えてもらったフィクション作品の楽しみ方──物語のいろいろな側面を捉えること、一部分だけを見るのではなく、文脈を通じて理解すること、そして対話すること──には大きなヒントを感じる。さまざまな人の視点を内在させていくことがきっと、私のこれからのフィクションの楽しみ方を広げてくれるはずだ。私の好きなあの作品、子どもが好きなあの作品、もっともっと一緒に見て、もっともっと対話しよう。そうすることで、昔好きだった、でも今は少し敬遠していた作品も、また新しく面白がることができるかもしれない。
※記事内で紹介した作品の作者情報に一部不足があったため、内容を修正しました(2024/02/02)
Information
〈こここ〉公式LINE、友達募集中!
毎週水曜日に編集部おすすめの新着記事を厳選してお届けしています。
・新着記事を確認するのは大変!
・記事のおすすめはある?
・SNSでは、追いかけきれない!
・プッシュで通知がほしい!
という方におすすめです。
友達追加はこちらから!
Profile
- ライター:福井尚子
-
アート、表現、書籍、暮らし、食、教育などに興味関心を広げながら、執筆や編集をしています。神奈川県二宮町を拠点に、本を紹介する活動や絵本を用いた語り劇がライフワークです。
この記事の連載Series
連載:こここスタディ
![]() vol. 272025.04.18“家庭”ってなんだろう? 子どもと大人が尊重しあう場所を目指す、児童福祉施設「てらす峰夢」をたずねて
vol. 272025.04.18“家庭”ってなんだろう? 子どもと大人が尊重しあう場所を目指す、児童福祉施設「てらす峰夢」をたずねて![]() vol. 262024.12.06差別と関係のない立ち位置ってあるの? 社会のあり方に矢印を向けて考える
vol. 262024.12.06差別と関係のない立ち位置ってあるの? 社会のあり方に矢印を向けて考える![]() vol. 252024.12.06差別ってなんだろう? 現代社会における差別の研究者 阿久澤麻理子さんをたずねて
vol. 252024.12.06差別ってなんだろう? 現代社会における差別の研究者 阿久澤麻理子さんをたずねて![]() vol. 242024.08.14正しい答えを刷り込むのではなく、自分で選ぶ手助けをする「包括的性教育」とは?
vol. 242024.08.14正しい答えを刷り込むのではなく、自分で選ぶ手助けをする「包括的性教育」とは?![]() vol. 232024.07.31「性教育」という言葉から何を想像する? 教育学者 堀川修平さんによる「包括的性教育」解説
vol. 232024.07.31「性教育」という言葉から何を想像する? 教育学者 堀川修平さんによる「包括的性教育」解説![]() vol. 222024.07.17「創造性」はどう育まれる? ブルーノ・ムナーリの軌跡から──デザイナー、現代美術作家、教育者のまなざし
vol. 222024.07.17「創造性」はどう育まれる? ブルーノ・ムナーリの軌跡から──デザイナー、現代美術作家、教育者のまなざし![]() vol. 212024.03.30「個人の心の問題」の多くは環境や政治の問題でもある〜「あなたのため」というバウンダリーの侵害〜
vol. 212024.03.30「個人の心の問題」の多くは環境や政治の問題でもある〜「あなたのため」というバウンダリーの侵害〜![]() vol. 202024.03.26自分と他者を区別する境界線「バウンダリー」とは?ソーシャルワーカー鴻巣麻里香さんによる解説
vol. 202024.03.26自分と他者を区別する境界線「バウンダリー」とは?ソーシャルワーカー鴻巣麻里香さんによる解説![]() vol. 182023.12.15「合理的配慮」は「ずるい」「わがまま」なのか? インクルージョン研究者 野口晃菜さんによる解説
vol. 182023.12.15「合理的配慮」は「ずるい」「わがまま」なのか? インクルージョン研究者 野口晃菜さんによる解説![]() vol. 172023.04.21“できる/できない”の社会を「ヨコへの発達」で問い直す。社会福祉の父・糸賀一雄を、垂髪あかりさんが研究する理由
vol. 172023.04.21“できる/できない”の社会を「ヨコへの発達」で問い直す。社会福祉の父・糸賀一雄を、垂髪あかりさんが研究する理由![]() vol. 162023.02.08「やさしい日本語」ってなに? 言語学者・庵功雄さんに聞くコミュニケーションの本質
vol. 162023.02.08「やさしい日本語」ってなに? 言語学者・庵功雄さんに聞くコミュニケーションの本質![]() vol. 152023.01.27人を見た目で判断することって全部「差別」になるの? 社会学者 西倉実季さんと、“ルッキズム”について考える
vol. 152023.01.27人を見た目で判断することって全部「差別」になるの? 社会学者 西倉実季さんと、“ルッキズム”について考える![]() vol. 142023.01.16自分の気持ちを話さない自由がある。NPO法人ぷるすあるはと一緒に考えた“きもち”との付き合い方
vol. 142023.01.16自分の気持ちを話さない自由がある。NPO法人ぷるすあるはと一緒に考えた“きもち”との付き合い方![]() vol. 132022.12.14“障害”ってそもそも何だろう? 困難の原因を「社会モデル」から考える──バリアフリー研究者・星加良司さん
vol. 132022.12.14“障害”ってそもそも何だろう? 困難の原因を「社会モデル」から考える──バリアフリー研究者・星加良司さん![]() vol. 122022.11.29「ちゃんとしなきゃ」の呪いをとくには?福祉社会学者 竹端寛さん× 僧侶 松本紹圭さん
vol. 122022.11.29「ちゃんとしなきゃ」の呪いをとくには?福祉社会学者 竹端寛さん× 僧侶 松本紹圭さん![]() vol. 112022.10.27“ありのままの自分”を大切にするって、どういうことだろう? しょうぶ学園施設長 福森伸さんをたずねて
vol. 112022.10.27“ありのままの自分”を大切にするって、どういうことだろう? しょうぶ学園施設長 福森伸さんをたずねて![]() vol. 102022.09.27「福祉の現場」と「芸術」の根っこには通ずるものがある? 福祉環境設計士 藤岡聡子さんをたずね、「ケアの文化拠点」ほっちのロッヂへ
vol. 102022.09.27「福祉の現場」と「芸術」の根っこには通ずるものがある? 福祉環境設計士 藤岡聡子さんをたずね、「ケアの文化拠点」ほっちのロッヂへ![]() vol. 092022.09.07“健康”ってなんだろう?ケアの文化拠点「ほっちのロッヂ」紅谷浩之さんをたずねて
vol. 092022.09.07“健康”ってなんだろう?ケアの文化拠点「ほっちのロッヂ」紅谷浩之さんをたずねて![]() vol. 082022.08.12弱さは個人の問題ではなく、構造上の問題だ。公認心理師・臨床心理士 信田さよ子さんと考える“弱さ”のこと
vol. 082022.08.12弱さは個人の問題ではなく、構造上の問題だ。公認心理師・臨床心理士 信田さよ子さんと考える“弱さ”のこと![]() vol. 072022.07.28“違う“の不安をどう乗り越えればいい? グレーではない「色」で表現する発達の特性──星山麻木さん
vol. 072022.07.28“違う“の不安をどう乗り越えればいい? グレーではない「色」で表現する発達の特性──星山麻木さん![]() vol. 062022.04.12「私はどう生きたらいい?」を、一人で抱えない社会へ。医師・西智弘さんに聞く、地域活動と“ケア“の文化づくり
vol. 062022.04.12「私はどう生きたらいい?」を、一人で抱えない社会へ。医師・西智弘さんに聞く、地域活動と“ケア“の文化づくり![]() vol. 052022.03.22偏見がない人はいない。川内有緒さん×木ノ戸昌幸さん『わたしの偏見とどう向き合っていく?』イベントレポート
vol. 052022.03.22偏見がない人はいない。川内有緒さん×木ノ戸昌幸さん『わたしの偏見とどう向き合っていく?』イベントレポート![]() vol. 042022.02.04居場所・つながり・役割・生産性。「望まない孤独」をめぐる対談でみえたものとは?吉藤オリィさん×奥田知志さん
vol. 042022.02.04居場所・つながり・役割・生産性。「望まない孤独」をめぐる対談でみえたものとは?吉藤オリィさん×奥田知志さん![]() vol. 032021.10.26大切なものを失った悲しみや痛みと共に生きていくには? グリーフサポートが当たり前にある社会を目指す 尾角光美さんをたずねて
vol. 032021.10.26大切なものを失った悲しみや痛みと共に生きていくには? グリーフサポートが当たり前にある社会を目指す 尾角光美さんをたずねて![]() vol. 022021.06.24差別や人権の問題を「個人の心の持ち方」に負わせすぎなのかもしれない。 「マジョリティの特権を可視化する」イベントレポート
vol. 022021.06.24差別や人権の問題を「個人の心の持ち方」に負わせすぎなのかもしれない。 「マジョリティの特権を可視化する」イベントレポート![]() vol. 012021.04.15さまざまな側面をもつ「わたし」と「あなた」をそのまま大切にするには? 美学者 伊藤亜紗さんを訪ねて
vol. 012021.04.15さまざまな側面をもつ「わたし」と「あなた」をそのまま大切にするには? 美学者 伊藤亜紗さんを訪ねて