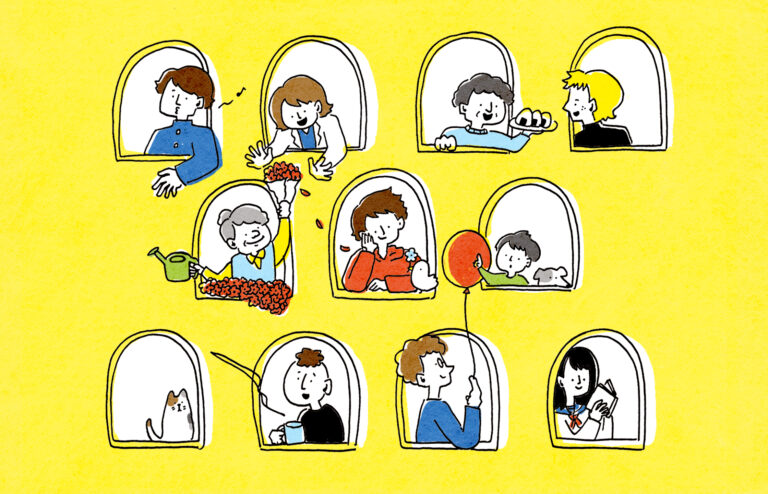“できる/できない”の社会を「ヨコへの発達」で問い直す。社会福祉の父・糸賀一雄を、垂髪あかりさんが研究する理由 こここスタディ vol.17
「上手くなったね!すごい!」
「次はこんなことができたらいいな」
生活や仕事のなかで、自分たちの成長や努力の結果を、“できる/できない”で評価していることは多い。例えば、子育て。「その子らしく生きてくれればいい」と思っていても、ひとりで靴下が履けるようになったとか、言葉を覚えたとか、我が子の“できる”が可視化されていくたびに喜び、褒める私が実際ここにいる。
何かが“できる”ようになることは、もちろんすばらしいし、子ども自身も「できた!」と誇らしそうだ。と同時に、なぜだろう、そこだけに囚われていてはいけないような気もする。“できる”ばかり目指すことは、裏返せば「“できない”とダメ」という価値観なのではないだろうか……とたまに自問する。
その葛藤に対するひとつのヒントになる考え方に、「ヨコへの発達」というものがある。「社会福祉の父」と呼ばれる故・糸賀一雄と、彼の周りの人たちが、障害のある子どもたちと触れ合うなかで形成した考え方だ。目に見える成長や上達を「タテ」の軸、それとは違う形の育ちを「ヨコ」の軸で捉える発達論を、50年以上前に提唱している。
一歳は一歳として、二歳は二歳として、その発達段階はそれぞれの意味をもっているのであって、その時でなければ味わうことのできない独特の力がそのなかにこもっているのである。一歳は二歳ではないからといって低い価値なのではない。
(『糸賀一雄著作集Ⅰ』p168より引用)1960年代までを生きた糸賀の発達論には、“多様性”が叫ばれる現代においてなお、人の生き方や社会のあり方を考えるヒントが詰まっているのではないか——そんな思いから、新生児救命医療や特別支援教育の現場を経験し、現在は糸賀らの思想や実践について研究を続ける、神戸松蔭女子学院大学の垂髪(うない)あかりさんをたずねた。
子どもたちの内側にある「何か」を知りたくて
糸賀を知る前、垂髪さんは助産師として、病院のNICU(新生児集中治療室)に勤務していた。予定日よりも早く生まれた早産児や小さく生まれた低出生体重児、病気のある新生児などの救命や看護が主な仕事だ。そのなかで、障害のある赤ちゃんやその家族に出会うことも多かった、と垂髪さんは話す。
仕事中はとにかく、目の前の命に向き合うのに必死でした。けれどだんだん、「NICUを巣立った子どもは退院したあと、どうなっていくんだろうな」っていうのを知りたくなって、勤務のない日に、特別支援学校や療育施設を訪れるようになりました。
障害のある子どもたちが過ごす学校や施設の印象は、「こんなに楽しい世界があるんだな」だった。ピーンと緊張感が張り詰めたNICUとは違う、笑顔や笑い声あふれる雰囲気に、垂髪さんは魅了されたという。

同時にNICUを出たあと、病院で長く過ごす子どもたちのことも気にかかるように。同じ病院内の小児病棟、「重症心身障害」(重度の肢体不自由と、重度の知的障害とが重複した状態)のある子どもが入院しているフロアを垂髪さんが訪れると、ある寝たきりの少年と目があった。「吸い込まれるような瞳だった」と、当時のことを振り返る。
それからというもの、垂髪さんはNICUの勤務が終わるたびに、その足で少年のベッドをたずねるようになっていった。
「今日も来たよ」みたいな感じでベッドの柵越しに視線を合わせて、だんだんといろんなことを話すようになって。彼はいつも同じ方向を向いて、口角から唾液が出ているんですけれども、私に対して瞬きしてくれたりして、何かをわかってくれているような印象がありました。ミスが許されない緊張感でいっぱいの仕事のあとに、その子の手を握って話しているだけで、なぜか気持ちが落ち着く感覚があったんです。
少年と過ごす日々のなかで、垂髪さんは彼の内側にある「何か」を感じていた。その「何か」をもっと知りたい——。休日に訪れた学校の風景が忘れられなかった垂髪さんは、教員免許を取得し、大阪の特別支援学校が次の勤務先となった。病院での経験を生かして、医療的ケアが必要な子どもたちのクラスを受け持ったり、学校に通えない子どもたちの家々を回る訪問学級を担任したりするようになる。
薬の副作用で眠そうだったり、ずっと目を瞑っていたりする子どもとも、じっくり関わるうちに、表情や仕草から見える“その子らしさ”を現場で感じていたと話す垂髪さん。ただ、職場にはさまざまな考えの教育者がおり、方針の違いで悩むこともあった。事例研究では、心身に重度の障害がある、寝たきりの子どもを対象にしたいと思ったが、それをある先輩に伝えると「あの子を研究しても何も結果が出ないのでは?」と言われてしまったこともあったという。

「よく動く子どものほうが、『何を何回できた』ってすぐ書けるよ」というアドバイスが、私にはショックでした。でも、思えば教育現場のあちこちに、“目に見える成果”を評価する成果主義がそもそもあったんですよね。個別の指導計画でも、「◯◯を味わう」みたいな曖昧な表現ではなく、「◯◯が何回できるようになる」などと書き直しを求められたこともありました。ただ、その評価基準では重い障害のある子どもたちの発達を捉えきれない気がしていて、いいのだろうかと思っていたんです。
重い障害のある子どもたちと触れ合いながら、彼らの個性や反応の違い、それによる自分や周囲の変化を感じていた垂髪さんは、“できる/できない”を軸とした評価とのあいだで揺れ動いていた。
葛藤の出口を探すなかで垂髪さんが出会ったのが、糸賀一雄の言葉と、50年以上も前に生まれていた「発達保障」「ヨコへの発達」という考え方だった。
「福祉の父」糸賀一雄が残したもの
障害をもった子どもたちは、その障害と戦い、障害を克服していく努力のなかに、その人格がゆたかに伸びていく。貧しい狭い人格でなく、豊かなあたたかい人間に育てたい。三歳の精神発達でとまっているように見えるひとも、その三歳という精神発達の中身が無限に豊かに充実していく生きかたがあると思う。生涯かかっても、その三歳を充実させていく値打ちがじゅうぶんにあると思う。
(糸賀一雄『福祉の思想』p177より引用)「福祉の父」糸賀一雄に、垂髪さんが深い関心を抱くようになったきっかけは、のちに恩師となる渡部昭男さん(鳥取大学名誉教授/神戸大学大学院人間発達環境学研究科名誉客員教授/大阪成蹊大学特別招聘教授)をたずねたこと。障害のある子どもたちの教育について研究をしていた渡部さんから、「こういう考え方があるんだよ」と紹介されたのが、糸賀が書いた『福祉の思想』だった。
糸賀一雄の言葉ってすごく優しくてわかりやすくて、ストンと入ってくることが多いんですね。本を読んで、心の琴線に触れるものがありました。糸賀自身が実践のなかで考え続けた言葉から、人の生きる意味の本質や、私たちが今現場で子どもに向き合う意義を教えてもらったと思っています。

垂髪さんの言う「糸賀一雄の実践」とは、どのようなものなのか。「社会福祉の父」「障害福祉の父」と呼ばれるに至る最初の功績として挙げられるのは、滋賀県大津市に児童福祉施設〈近江学園〉を設立したことだ。
学園ができた1946年、戦後の混乱のなかには、路頭に迷う多くの子どもたちがいた。「浮浪児」や「戦争孤児」と呼ばれた彼らのなかには、知的障害のある子ども(当時は「精神薄弱児」の呼称)もいたが、そんな子どもたちに対する福祉制度はほとんど整っていない時代。糸賀は生活に困窮する子どもを集めて、池田太郎・田村一二とともに〈近江学園〉を設立し、初代園長を務めた。

その後、知的障害のある女子のための保護・職業指導施設〈あざみ寮〉をはじめ、多くの福祉施設の立ち上げを経て、1963年に日本で2番目の重症心身障害児施設〈びわこ学園〉を設立。このとき、「重症心身障害児」という概念自体を作り、国に認知させていった中心にも、糸賀の存在があったという。
それまで重い障害のある子どもの多くは、家の奥に閉じ込められ、医療にも福祉にも見放されて行き場がなかったそうです。当時は知的障害に「重症」の概念もなく、IQの差だけで障害が軽いか重いか分けられ、現在は差別用語となっている「白痴」「痴愚」「魯鈍(ろどん)」などと呼ばれて選別的な扱いを受けていました。
そこで糸賀は、日本初の重症心身障害施設〈島田療育園〉を作った小林提樹らと協力しながら、「この子らをしっかり見ていくために、まずは『重症心障害児』という言葉の普及が必要だ」と国に訴えたんです。
また、高度経済成長へと進んでいた当時、「社会の役に立たない」とされた重い障害のある子どもへは、教育すらおこなわれていなかった。そのなかで糸賀は、障害のある子どもはもちろん、すべての人を“発達する”存在と捉え、その発達をみんなで支えていく「発達保障」の理念を提起。現在の教育に大きな影響を与えている。
とはいえ、糸賀自身もはじめからそういう考えだったわけではないんです。
「これも彼の魅力ですが」と言いながら、垂髪さんが付け加えた。
糸賀も最初は、重い障害のある人を差別的な目で見ていた側面がありました。施設を作っていった当初も、そうした子どもたちのことは「永遠の幼児」と呼んで、保護の必要性を述べていたんです。それが、実際に障害の重い子どもたちと過ごすうちに、「この子たちは一人ひとり個性的な存在で、世の光なんだ」という発信に変わっていく。
もちろんその過程には、重い障害のある子どもたちとの生活に入り込み、全力で向き合った時間があります。そのなかで「目の前の子どもの内面をもっと知りたい」「彼らの心と触れ合いたい」と、見方を変化させていったんです。すでにいくつもの施設を設立し、それを率いる立場でもあった人なのに、正直に自分と向き合い、さらに価値観を変えていったのは、私はすごいことだと思います。

比較できない、個性の広がりとしての「ヨコへの発達」
子どもたちとの触れ合いのなか、提起された「発達保障」の考え方。そこで少しずつ形作られ、糸賀の晩年に登場したのが、垂髪さんの研究する「ヨコへの発達」だ。
ただ、これは糸賀自身がパッと言葉にしたわけではない。もともと宗教哲学を専門にしていた糸賀に加え、〈近江学園〉に関わり、その後〈第一びわこ学園〉〈第二びわこ学園〉の初代園長となった医師・岡崎英彦と、発達心理学の立場から学園に関わっていた研究者・田中昌人の、それぞれの思想と実践の往還から生まれたものだ。糸賀本人は「横軸の発達」「横の発達」と表現していたという。
同じ子どもたちと触れ合いながら、それぞれに得た感覚を言語化していったので、実際に使っていた言葉も少しずつ違うんです。岡崎は「“よこ”への育ち」と言っていて、「ヨコへの発達」は田中の言葉。過去の記録からは、お互い影響を受けながら、子どもの内面の変化を捉えている場面も読み取れます。
その解釈については、本や辞書などにもさまざまに書かれていますが、私はやはり糸賀が述べた定義を使うようにしています。1966年、糸賀が口にした「横軸の発達とは、かけがえのない個性の広がり」という表現です。

ここでの「かけがえのない個性の広がり」とは、日常のなかでよく使われている「発達」のイメージ——例えば、寝ている赤ちゃんの首がだんだんと座り、寝返りからお座りへ、ハイハイからつかまり立ちへと増えていく“できること”——とは少し異なるものだ。目で見てわかる変化や、数値化して客観的に評価できるものを「タテへの発達」と捉えたとき、「ヨコへの発達」は感情の豊かさや関係性の広がりなど、目に見えない、心や内面に関わる部分を指すという。
大事なことなのに、それらを人の「発達」として捉える機会ってあまりないですよね。私は大学で今いくつも授業を持っていますが、講義の初めに「みんな、発達ってどんなイメージ?」って聞くと、ほぼ全員が「タテへの発達」のことを言います。“できる”ことが増え、階段のように上がっていくイメージを、授業のなかで時間をかけて、根底にある価値観から揺さぶっていくんです。
また、人の内面が「ヨコ」へ発達するときには、関わる相手の存在は欠かせない。ここでのキーワードに、垂髪さんは「共感」も挙げる。実際、糸賀たちは子どもが変わろうとする姿や気持ちを共に感じ、共に在る存在が「ヨコへの発達」を促すと記していた。
それらの意味を踏まえ、垂髪さんは現代の教育や保育・療育の実践者たちにとって、「ヨコへの発達」が重要な意味を持つと考える。そこには、助産師・教育者として子どもたちと関わりながら、現場で何かを感じていた自らの過去も重なっていた。

資料(※注)のなかで糸賀が使っている言葉で、「ミットレーベン」というドイツ語があるんです。これは「共に生きる」という意味。糸賀は子どもたちの鼻が垂れていたら拭き、おねしょした布団を替え、まさに共に生きていました。その実践のなかで、子どもがさまざまな反応を示すようになっただけでなく、糸賀自身も「価値の転換」をくぐった。同じように、自分の価値観と向き合いながら、障害のある子どもたちと共に生きることが私たちにも必要だと思うんですね。
※注:『ミットレーベン~故郷・鳥取での最期の講義~』(著:糸賀一雄、編:國本真吾)
共に生きる実践のなかで糸賀が感じたのは、「社会が捉える重症心身障害児」と「実際に目の前にいる子どもたち」の差だったのかもしれない。当時は「発達しない」と思われていた、重い障害のある子どもについて語るうえで、あえて「ヨコ」という言葉を作り出さなければならなかったと垂髪さんは言う。
人間の発達って、そもそもそんなに簡単にね、二次元の座標で捉えられるものじゃないとも思います。ただお伝えしたいのは、この「ヨコ」という考え方が、「タテ」しかなかった時代へのアンチテーゼとして必要だった、ということ。学校教育にも福祉の対象にもならなかった障害の重い子どもたちについて、「この子らにも学ぶ権利があるし、可能性があるんだよ」って突きつけるために必要だった概念なんです。
現代に“歴史”をつなぐ、糸賀思想の意義
糸賀らが突きつけたことは、実際に社会制度にも影響を及ぼしている。例えば、普通教育から遅れること30年、1979年には養護学校の義務化が決まった。こうした動きの背景にも、「寝たきりの子どもたちも発達する」という「ヨコへの発達」を思想的に受け継ぎ、教育の必要性を訴え続けた人々の存在がある。
もちろん、「障害のある人に教育は必要ない」「生きる価値がない」といった差別的な思想は、2016年の相模原障害者施設殺傷事件にも代表されるとおり、現代でも完全にはなくなっていない。アンチテーゼとしての「ヨコへの発達」の考えは、今なお忘れてはならない大切な概念だ。
「寝たきりの重い障害の子どもに、生産性はあるのか」という問いに、糸賀は「ある」と言っています。なんだと思われますか、障害の重い子の“生産性”って。
糸賀が言っているのは、その子がその子らしく生き、自己実現していくこと。そして、その創造性が、関わり手の価値観を変容させていくということです。ただモノを作ったりすることを示す意味だけじゃなく、本人や関わる人の価値という側面から捉えると、“生産性”という言葉の見え方も変わってくる気がします。

糸賀が「重症心身障害児の生産性」や「ヨコへの発達」を提唱するまで、障害のある人たちは社会から排除され続けてきた。ずっと“できる/できない”というタテの概念でしか人間の価値が捉えられなかった歴史のなかで、彼らの存在意義を示すこととなった「ヨコへの発達」の意味合いは大きい。
糸賀が、当時の世の中に突きつけた捉え方は、半世紀を経て、私たちにも「タテ」に支配された時代と抗う方法を示唆し続けてくれています。その意味で、「ヨコへの発達」は、私たちも糸賀と“同じ歴史”を生きているんだと思い出させてくれますね。
わずか54歳で亡くなった糸賀の後も、「ヨコへの発達」の考え方はさまざまな人の言葉で紡がれ続けている。
例えば〈第一びわこ学園〉の2代目園長、高谷清さんは「ヨコへの発達」を「存在そのものの絶対肯定」と定義する。「発達」という言葉で想起する「変わっていかなければ」「伸びていかなければ」というイメージを覆し、あるがままのその子を受け止めることこそが大事だと伝えているのだ。
また、現象学を研究している鯨岡峻さん(京都大学名誉教授)が発信しているのは、子どもの発達を「なる」と「ある」に分ける考え方。今の保育や教育の現場では何かに「なる」ことばかりが追い求められ、実際に教育者や保護者、子どもも伸びた結果を喜ぶ風潮が強い。そのなかで、本当に目を向けないといけないのは「ある」の方なのではないか、と問いかけている。垂髪さんは「現代版のタテとヨコだ」と思いながら聞いている、と教えてくれた。

「成果主義」に縛られる自分と社会を、教育から変える
これまでの歴史を受け継ぎながら、これからの歴史を作っていく私たち。糸賀らが遺した「ヨコへの発達」という考え方は、私たちが作っていく社会や教育の仕組みだけでなく、日々の暮らしにまで生かしていけるのではないだろうか。
そう感じるのは、冒頭に記したとおり、自分自身が子どもに“できる”こと、つまり「タテへの発達」を求めていると感じるからだ。
わかります。私も子育てをしながら、やっぱり「タテ」に縛られている自分に気づくことがあるんですよね。
垂髪さん自身もまた、3人のお子さんを育てる親でもある。自らの葛藤について、息子さんが保育園のときの話をしてくれた。
いつもひとりで日向ぼっこしている息子が、先生から「今の時間は友達と遊びなさい」って言われてると知ったんです。そんなふうに言われたら辛いだろうなと、心が苦しくなったことがありました。
ところがあるとき、またひとりでいる息子をつい心配そうに見ていたら、別の先生が「いいんですよ、お母さん」と言ってくれたんです。「外からみんなを観察して一緒に遊んでるつもりになってるのかもしれないし、日光を感じてポカポカ気持ちいいって思ってるかもしれない。これはこれで素敵な時間だから、別に否定しなくていい」って。

そのとき、私自身も「お友達と遊べたら楽しいのに」って期待していたことに気づいて、ハッとしました。当時、私は「ヨコへの発達」という概念を学び始めたばかりでしたが、自分も結局どこかで目に見えることのみに囚われ、息子の気持ちに寄り添えてなかったんですね。
“できる/できない”で判断してしまう社会のあり方だけでなく、自身の価値観にも気付かされたという垂髪さん。子どもたちが大きくなって学校に通うようになっても、テストの結果で今後の進路や道の開け方が変わってくると思えば、「どうしても勉強しなさいと言ってしまう」と打ち明ける。
研究をしていくなかで、障害のある子だけじゃなく、すべての子どもの心の動きや内面の葛藤、揺れ動くところに寄り添える人って素敵だなと、ますます思うようになりました。でも、それってなかなかできないんです。
いい大学に入ったからっていい人生を歩めるとは限らないのに、ちょっとでもいい点を、と思ってしまう自分がいる。その子らしさ、その子の時間や存在を認めてあげたいのに……って行ったり来たりしてますね。どうしてなんでしょう、この日本社会を作り上げてきた教育を、私も受けて来たからなんでしょうか。

垂髪さんがこちらに聞き返してしまうほど、私たちのなかにはまだまだ“できる/できない”の価値観が根強く残っている。社会の仕組みそのものが今も、「できるようにならないと」と人々が考えざるを得ないシステムになっているとも言える。
もちろん、垂髪さんは「タテ」の育ちを否定しているわけではない。目には見えなくても心が揺れ動くような「ヨコ」の動きを大切にしたうえで、「タテ」に発達して、何かができるようになる喜びも大事にしたいと話す。「タテ」と「ヨコ」を複雑に行き来しながら、その子なりの個性を豊かに育んでいく視点は、やはり糸賀の言葉に学んだものだ。
糸賀は「ちょうど木の実が熟してはじけるように、次の段階に入っていく 」と言っています。あとは、「『横軸の発達』が『縦軸の発達』の源泉となる」とも。だからみんな、「タテ」と「ヨコ」を行きつ戻りつしながら、自分らしさや他人との関係性を深めていくんでしょうね。
研究者として10年近く糸賀の思想を学んできた垂髪さんは、同時に子どもを育てる親として、学生たちを導く教員として、社会の変容も少しずつ感じ取っていると語る。
こういった取材や発信のニーズが増えてきたことも含め、いろんな教育現場で新たな取り組みがたくさん生まれていると感じます。入試の方法も学力だけではなく、学生の個性を見るようなユニークなものも増えてきましたよね。
かつての糸賀たちと同じように、そうした良い実践の積み重ねから世の中は変わっていくのではと思います。また私は今、保育や教育に関わる学生を育てていますので、彼らが先生になって子どもたちに伝えてくれることでも広がっていくかなと。そんなふうにして地道に、変わっていったらいいですね。
実際、授業を受ける前と後では、学生たちの価値観は大きく変わったように感じる、と垂髪さん。これからの教育に関わっていく学生たちが「ヨコへの発達」についての概念を持ち合わせていることは、社会を作る大人たちの行動が変わっていくことにもなる。
「“できない”からダメだ」ではなく、「それぞれに個性の広がり方がある」と気づく。そうして揺れながら関わり合い、互いにちょっとずつ「発達」していく先に、未来の社会の価値観が生まれていくのかもしれない。

Profile
- ライター:ウィルソン麻菜
-
「物の向こう側」を伝えるライター。製造業や野菜販売の仕事を経て「背景を伝えることで、作る人も使う人も幸せな世の中になる」と信じて、作り手のインタビュー記事や発信サポートをおこなっている。個人向けのインタビューサービス「このひより」の共同代表。現在は、二児の英語子育てに奮闘中。
この記事の連載Series
連載:こここスタディ
![]() vol. 272025.04.18“家庭”ってなんだろう? 子どもと大人が尊重しあう場所を目指す、児童福祉施設「てらす峰夢」をたずねて
vol. 272025.04.18“家庭”ってなんだろう? 子どもと大人が尊重しあう場所を目指す、児童福祉施設「てらす峰夢」をたずねて![]() vol. 262024.12.06差別と関係のない立ち位置ってあるの? 社会のあり方に矢印を向けて考える
vol. 262024.12.06差別と関係のない立ち位置ってあるの? 社会のあり方に矢印を向けて考える![]() vol. 252024.12.06差別ってなんだろう? 現代社会における差別の研究者 阿久澤麻理子さんをたずねて
vol. 252024.12.06差別ってなんだろう? 現代社会における差別の研究者 阿久澤麻理子さんをたずねて![]() vol. 242024.08.14正しい答えを刷り込むのではなく、自分で選ぶ手助けをする「包括的性教育」とは?
vol. 242024.08.14正しい答えを刷り込むのではなく、自分で選ぶ手助けをする「包括的性教育」とは?![]() vol. 232024.07.31「性教育」という言葉から何を想像する? 教育学者 堀川修平さんによる「包括的性教育」解説
vol. 232024.07.31「性教育」という言葉から何を想像する? 教育学者 堀川修平さんによる「包括的性教育」解説![]() vol. 222024.07.17「創造性」はどう育まれる? ブルーノ・ムナーリの軌跡から──デザイナー、現代美術作家、教育者のまなざし
vol. 222024.07.17「創造性」はどう育まれる? ブルーノ・ムナーリの軌跡から──デザイナー、現代美術作家、教育者のまなざし![]() vol. 212024.03.30「個人の心の問題」の多くは環境や政治の問題でもある〜「あなたのため」というバウンダリーの侵害〜
vol. 212024.03.30「個人の心の問題」の多くは環境や政治の問題でもある〜「あなたのため」というバウンダリーの侵害〜![]() vol. 202024.03.26自分と他者を区別する境界線「バウンダリー」とは?ソーシャルワーカー鴻巣麻里香さんによる解説
vol. 202024.03.26自分と他者を区別する境界線「バウンダリー」とは?ソーシャルワーカー鴻巣麻里香さんによる解説![]() vol. 192024.02.01「昔好きだった作品」の表現に戸惑ってしまったら? フィクションが与える2つの影響──文学研究者・小川公代さん
vol. 192024.02.01「昔好きだった作品」の表現に戸惑ってしまったら? フィクションが与える2つの影響──文学研究者・小川公代さん![]() vol. 182023.12.15「合理的配慮」は「ずるい」「わがまま」なのか? インクルージョン研究者 野口晃菜さんによる解説
vol. 182023.12.15「合理的配慮」は「ずるい」「わがまま」なのか? インクルージョン研究者 野口晃菜さんによる解説![]() vol. 162023.02.08「やさしい日本語」ってなに? 言語学者・庵功雄さんに聞くコミュニケーションの本質
vol. 162023.02.08「やさしい日本語」ってなに? 言語学者・庵功雄さんに聞くコミュニケーションの本質![]() vol. 152023.01.27人を見た目で判断することって全部「差別」になるの? 社会学者 西倉実季さんと、“ルッキズム”について考える
vol. 152023.01.27人を見た目で判断することって全部「差別」になるの? 社会学者 西倉実季さんと、“ルッキズム”について考える![]() vol. 142023.01.16自分の気持ちを話さない自由がある。NPO法人ぷるすあるはと一緒に考えた“きもち”との付き合い方
vol. 142023.01.16自分の気持ちを話さない自由がある。NPO法人ぷるすあるはと一緒に考えた“きもち”との付き合い方![]() vol. 132022.12.14“障害”ってそもそも何だろう? 困難の原因を「社会モデル」から考える──バリアフリー研究者・星加良司さん
vol. 132022.12.14“障害”ってそもそも何だろう? 困難の原因を「社会モデル」から考える──バリアフリー研究者・星加良司さん![]() vol. 122022.11.29「ちゃんとしなきゃ」の呪いをとくには?福祉社会学者 竹端寛さん× 僧侶 松本紹圭さん
vol. 122022.11.29「ちゃんとしなきゃ」の呪いをとくには?福祉社会学者 竹端寛さん× 僧侶 松本紹圭さん![]() vol. 112022.10.27“ありのままの自分”を大切にするって、どういうことだろう? しょうぶ学園施設長 福森伸さんをたずねて
vol. 112022.10.27“ありのままの自分”を大切にするって、どういうことだろう? しょうぶ学園施設長 福森伸さんをたずねて![]() vol. 102022.09.27「福祉の現場」と「芸術」の根っこには通ずるものがある? 福祉環境設計士 藤岡聡子さんをたずね、「ケアの文化拠点」ほっちのロッヂへ
vol. 102022.09.27「福祉の現場」と「芸術」の根っこには通ずるものがある? 福祉環境設計士 藤岡聡子さんをたずね、「ケアの文化拠点」ほっちのロッヂへ![]() vol. 092022.09.07“健康”ってなんだろう?ケアの文化拠点「ほっちのロッヂ」紅谷浩之さんをたずねて
vol. 092022.09.07“健康”ってなんだろう?ケアの文化拠点「ほっちのロッヂ」紅谷浩之さんをたずねて![]() vol. 082022.08.12弱さは個人の問題ではなく、構造上の問題だ。公認心理師・臨床心理士 信田さよ子さんと考える“弱さ”のこと
vol. 082022.08.12弱さは個人の問題ではなく、構造上の問題だ。公認心理師・臨床心理士 信田さよ子さんと考える“弱さ”のこと![]() vol. 072022.07.28“違う“の不安をどう乗り越えればいい? グレーではない「色」で表現する発達の特性──星山麻木さん
vol. 072022.07.28“違う“の不安をどう乗り越えればいい? グレーではない「色」で表現する発達の特性──星山麻木さん![]() vol. 062022.04.12「私はどう生きたらいい?」を、一人で抱えない社会へ。医師・西智弘さんに聞く、地域活動と“ケア“の文化づくり
vol. 062022.04.12「私はどう生きたらいい?」を、一人で抱えない社会へ。医師・西智弘さんに聞く、地域活動と“ケア“の文化づくり![]() vol. 052022.03.22偏見がない人はいない。川内有緒さん×木ノ戸昌幸さん『わたしの偏見とどう向き合っていく?』イベントレポート
vol. 052022.03.22偏見がない人はいない。川内有緒さん×木ノ戸昌幸さん『わたしの偏見とどう向き合っていく?』イベントレポート![]() vol. 042022.02.04居場所・つながり・役割・生産性。「望まない孤独」をめぐる対談でみえたものとは?吉藤オリィさん×奥田知志さん
vol. 042022.02.04居場所・つながり・役割・生産性。「望まない孤独」をめぐる対談でみえたものとは?吉藤オリィさん×奥田知志さん![]() vol. 032021.10.26大切なものを失った悲しみや痛みと共に生きていくには? グリーフサポートが当たり前にある社会を目指す 尾角光美さんをたずねて
vol. 032021.10.26大切なものを失った悲しみや痛みと共に生きていくには? グリーフサポートが当たり前にある社会を目指す 尾角光美さんをたずねて![]() vol. 022021.06.24差別や人権の問題を「個人の心の持ち方」に負わせすぎなのかもしれない。 「マジョリティの特権を可視化する」イベントレポート
vol. 022021.06.24差別や人権の問題を「個人の心の持ち方」に負わせすぎなのかもしれない。 「マジョリティの特権を可視化する」イベントレポート![]() vol. 012021.04.15さまざまな側面をもつ「わたし」と「あなた」をそのまま大切にするには? 美学者 伊藤亜紗さんを訪ねて
vol. 012021.04.15さまざまな側面をもつ「わたし」と「あなた」をそのまま大切にするには? 美学者 伊藤亜紗さんを訪ねて