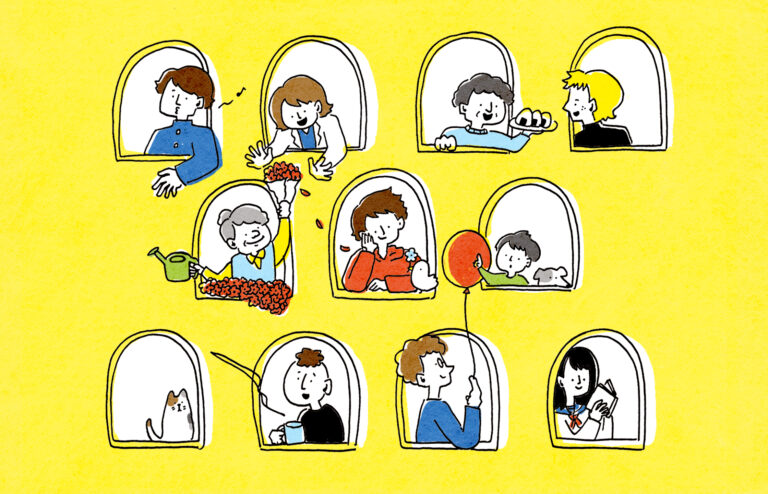“健康”ってなんだろう?ケアの文化拠点「ほっちのロッヂ」紅谷浩之さんをたずねて こここスタディ vol.09
健康ってなんだろう?
病気がないこと、好きな食べ物を気兼ねなく食べられること、あるいは頭痛や腰痛など身体に痛みがないこと、となんとなく答えることはできる。
1948年に世界保健機関(WHO)が定義した「健康」の定義は、「単に疾患がないとか虚弱でない状態ではなく、身体的・精神的・社会的に完全に良好であること」とされている。
「身体的・精神的・社会的に完全に良好であること」ってなんだろう。誰が、どの立場から「完全に良好」と判断するのだろうか。
そんな疑問を持つなかで、長野県軽井沢町の森の中にある「ほっちのロッヂ」という場所を知った。
「症状や状態、年齢じゃなくって、好きなことをする仲間として出会おう」という合言葉を掲げ、「ケアの文化拠点」を育む「大きな台所があるところ」。診療所であり、在宅医療の拠点であり、病児保育室や共生型通所介護、訪問看護ステーションの事業を担う場所。
それが「ほっちのロッヂ」だ。医療サービスを提供する場所ではあるのだけれど、それだけではないのが、公式ウェブサイトの言葉選びから感じられる。
訪問看護ステーションを「家に訪問したり、町全体の健康を考える活動のこと」と説明していたり、診療所を「内科、小児科、緩和ケア、在宅医療。自分の好きな暮らしを医療とともに考えるところ」、病児保育室を「親も子も、自分の回復力を信じて過ごせる場所のこと」、共生型通所介護・児童発達支援・放課後等デイサービスを「大きな台所、本棚、アトリエなどがある、町の人の居場所のこと」と表現している。
ほっちのロッヂでは「健康とはなにか」という問いを考えるヒントがあるのではないか。そんな期待を持ちながら、2021年、本格的な寒さがやってくる前のある日、ほっちのロッヂを訪れ、医療法人社団オレンジ理事長・ほっちのロッヂ共同代表・医師の紅谷浩之さんに話を伺った。
(こここ編集部)



山小屋のような建物の中に入ると、台所やリビングがあり、誰かの家に遊びに来たような懐かしさがある。
そこでは、医師や看護師が、病児保育で訪れた子どものケアをしたり、来客と会議をしていたりする。彼ら彼女らは、動きやすい普段着を身につけており、いわゆる医療者らしいユニフォームを着用している人はいない。



リビングの壁にはプロジェクターで写真が映し出されている。その側で、パソコンをひらき作業をしている人もいれば、小さなトランポリンで飛び跳ねる子もいる。
「会議室」のように部屋が用途で固定されているわけではなく、空間を見つけて誰かが何かを行っているのだ。
台所の上部にはロフトがあり、梯子を昇って向いに目をやると、2階にある診療室が見える。どの場所からもそれとなく皆の気配が感じられる空間になっていた。


「ほっちのロッヂ」立ち上げのきっかけ
これまで出会ってきた医療サービスを提供する場所と景色が違う。見学してあらためて、そんな印象を抱く。そもそも「ほっちのロッヂ」はどのように生まれたのだろうか?
立ち上げのきっかけは、「軽井沢風越学園(以下、風越学園)」の設立を知ったことだ。「どんな子どもにも幸せな子ども時代を過ごしてほしい。遊びが学びへとつながっていく、この人間の自然な育ちを大切にした学校をつくりたい」、「風越学園が触媒になって、人の流れや人の動きができることで、まちづくりにも広がるんじゃないか」。そんな風越学園の想いを聞いた紅谷さんは、同じタイミングで、「子ども」をキーワードに医療福祉で新しく何かできないかと考えた。
子どもが笑って育つまちづくりに一生懸命取り組めば、さまざまな特性を持つ人それぞれが結果的に笑っているのではと思ったんです。子どもを中心にしたまちづくりにおいて、医療福祉は何ができるのか。その実験場をつくりたいという気持ちがありました。

時を同じくして、紅谷さんは、株式会社ReDoの藤岡聡子さんと出会う。藤岡さんは以前から、介護や子育て、まちづくりにまつわる事業に取り組んでいた。そのひとつが東京都豊島区椎名町の商店街にあった「長崎二丁目家庭科室(※注)」だ。
※注:「習い事スペースとセルフカフェから成る、福祉・多世代間の、出会いが生まれる場所」であり、それぞれの知恵や得意を持ち寄り、集まれる場所。2018年2月で運営は終了。
聡子さんは「高齢者施設には、なぜ高齢者しかいないのか」という問いを持っていました。
福祉施設に限らず、病院でも呼吸器科、胃腸科など科ごとに縦割りになっているところが多く、学校教育のシステムでは同じ学年であれば同じクラスにいるのが当たり前になっている。
聡子さんとならば、そこにある違和感を大事にしながら、なにかできるんじゃないかと思いました。
そこから対話を重ねて生まれたのが「症状や状態、年齢じゃなくって、好きなことする仲間として、出会おう」というほっちのロッヂのコンセプトだ。
役割や関係性が固定化されてしまうことで、見えづらくなるもの
取材中、コンセプトを体現している場面に出会った。
ある保育園でほっちのロッヂメンバーが内科検診を行っていたときのことだ。


ほっちのロッヂメンバーは、検診が終わっても、すぐには帰らず、子どもたちと一緒に時間を過ごしていたのだ。
子どもの頃の検診といえば、長い列に並んで順番が来たら、先生の顔を覚える暇もないうちに次の子にバトンタッチするものだった。なぜ検診後も子どもたちと一緒に過ごす時間を取るのか?
僕をお医者さんと思った時点でいい出会い方ができなくなるからです。
「検診です」って前に出ると泣いて大騒ぎしてしまう子もいる。でも、検診が終わって、泣いていた子が遊んでいるところで「何を作っているの? 一緒に作らせてよ」と声をかけたら「いいよー」って、違う関わり方が生まれることもあるんです。
昼食づくりを覗いていた子は、ほっちのロッヂに通っている子です。保育園で外遊びしていたり、他の子たちに混ざっていく姿を見られるのは嬉しいですね。


医者と患者、ケアする人とされる人などの役割や関係性が固定化されてしまうことで、見えづらくなるものがある。ほっちのロッヂのメンバーは、そのことを自覚して、日々働いていると感じた時間だった。
「文化拠点」だからこそ持てた選択肢

ほっちのロッヂは「ケアの文化拠点」を名乗る。そこに対する想いをたずねると紅谷さんは次のように述べる。
隣の人を気遣ったり、あの人どうしているかなと思ったりすることをケアと呼ぶのならば、ケアはもともと日常生活にあった文化と言えるのではないでしょうか。しかし、いつからか介護福祉士とか看護師とか専門家だけが担う分野になってしまった。
ケアが「文化」として思い出されれば、その地域はハッピーになる。子どもたちとの距離感を探すときに、「症状や状態、年齢じゃなくって、好きなことする仲間として、出会おう」があれば、関わる人それぞれがハッピーになるのではと思ったんです。
「文化拠点」を育んでいく活動の一環としては、子ども向けのワークショップや、アーティストが一定期間滞在する「交換留藝」というプログラムも実施している。その取り組みを紅谷さんはどのようにとらえているのか。
サイエンスとアートって違う役割として習ってきたから正直僕は苦手なんだけど(笑)。
でも、医療の現場はサイエンスの視点だけでは足りなくて、アート的な視点、人間味に付き合わないといけないところがあるんです。「窓から見える夕日が見たいから」と、抗癌剤の3回目なのに病院を抜け出して家に帰ろうとする方がいたり。こっちは癌の腫瘍マーカーの数字を話しているのに向こうは夕日の話をしているという矛盾感の中にいて。
大切なのは、家から夕日を見たいというような感覚がなかったら人間らしくないという感覚を医療者が持つことだと思うんです。ただ多くの現場において、その感覚は「個人でなんとかしてください」と言われてしまう場合もある。だからこそ文化拠点としての取り組みがあることはありがたいですね。
それとは別に、一緒に働く仲間がアートをきっかけに人と出会って、触れ合ったり楽しそうにしたりしているのを見るのも、僕はうれしいですね。

紅谷さんは続けて「ほっちのロッヂ」が「文化拠点」だからこそ持てた選択肢についても話してくれる。
ある人から「うつ病かもしれない、家から出ることもできないので往診に来てもらえますか?」と電話があったときのことだ。
家の中に入ったら、その方の作品がいっぱい並んでいました。「アートだけでは食べていけないからアルバイトで働きはじめた。でも、しんどくなって動けなくなった」というアーティストだったんです。
医学的には、まずうつ病のガイドラインに照らし合わせるところですが、この人が合わない職場で無理して働くことに問題があると思って。「医者と患者だけの関係は今日だけにしましょう。次はほっちのロッヂにぜひ来てください」と言って帰ってきたんですよ。
その人は、ほっちのロッヂで自身の好きを大切にする時間を過ごし、大学へ。作品も売れるようになったんです。
これって社会復帰じゃないですか。あのとき、うつ病だと診断して、月に1回薬を処方していたら多分まだ患者だったと思うんですけど、今、彼は自立しています。

オランダ発の健康概念「ポジティヴヘルス」との出会い
「症状や状態、年齢じゃなくって、好きなことする仲間として、出会おう」を合言葉に掲げ、「ケアの文化拠点」を育むほっちのロッヂ。
オランダの家庭医マフトルド・ヒューバー氏が提唱している「ポジティヴヘルス」から影響を受けている。
ほっちのロッヂの運営を担うオレンジは「Be Happy!」をコンセプトに掲げていて。これまで「いい人生だった、ありがとう」と思える生き方にたくさん出会ってきました。
その中で病気を治すこと、延命治療をすること、死なせないことがゴールではなくて、その人にハッピーになってもらうのがゴールだと思うようになって。
この考え方を知る知人が「ポジティヴヘルスの考え方に近いんじゃないか」と、教えてくれたんです。
その後、紅谷さんは実際にオランダの看護チームを訪ね、その実践に衝撃を受けたという。
日本では訪問看護先の方が亡くなるまで行き続けることが多いです。
でもオランダの看護チームは「朝自分で起きて、自分でシャワーを浴びて、自分で服を選ぶことができて、自分でご飯が食べられて、自分で食べたいものを買いに行けて、愛している人に愛していると伝えられたらその人は『健康』だから訪問看護は終わり。それが全部できるようになるまでは手伝うけど、できるようになったら終えていい」と言うんです。
「末期癌であと1か月で亡くなってしまうかもしれないのに行かなくていいんですか?」と聞いたら、「だって自分でできるようになったら必要ないじゃない? 困ったら私を呼ぶ力も備わっているし、これ以上お節介に行き続ける必要はないでしょう?」と。
そのとき、本当にハッとしたんです。病気がありながらパワフルに活動して健康的な人もたくさんいるのに、日本の看護や医療には、利用者が医療から脱出できないように整えてあげてしまうような側面があると思いました。
「社会的、身体的、感情的な問題に直面したときに適応し、本人主導で管理する能力としての健康」をとらえる。それがポジティヴヘルスのコンセプトだ。
「本人主導で管理する能力」。この言葉はともすれば「自己責任」とも勘違いしそうだが、決してそうではない。
「能力」とは、身につけて鍛え上げる力というより、もともと人間が動物的に持っている力を指していると認識しています。たとえば「レジリエンス(回復力)」。
「紙の上のちょうど真ん中にペンを置いて維持させてください」というお題があったときに、凸型に丸めて真ん中に置くのは大変。しかし、凹型に丸めれば多少横に行っても戻ってくる、この戻ろうとする力がレジリエンスです。

人は傷付いたり弱ったりしても、戻ろうとする力が備わっているという意味の「能力」。努力して真ん中に維持するものではなく、今は寄っているけれど、そのうち真ん中に戻ってくる。病気や悩みがある人は失っていると思い込んでいるかもしれないけれど、その人が生まれつき持つ、適応していく力を指すんです。
健康を考えるときの主語はあくまで自分
病気で辛さが自身を覆っているときには思考が内向きになり、自身にすでに備わっているものを前向きにとらえるのは難しいのではないか。
すると、紅谷さんはポジティヴヘルスで活用されるツールをもとにつくった「クモの巣マップ」を教えてくれた。
健康状態を評価するツールではなく、本人が今何を求めているのか、何を変えたいのかを明らかにし、対話の糸口となるものだという。

頭痛が1週間続いて不安を抱いた方が外来にきたんです。「クモの巣マップ」を書いてみると、「身体の状態」は頭が痛いし、「心の状態」は悪い病気だったらどうしようと不安だし、眠れていないしで点数が低かったんです。
でも「社会とのつながり」や「いきがい」の項目は高い点数がつきました。
するとその方は「ここ最近、頭痛に囚われて人生もう終わりかと思っていたけれど、仕事はうまくいっているし、友達もたくさんいる、そんなバランスが見えてきた。自分はとりあえず友達とバーベキューする週末をしんどくなく楽しみたいので、頭痛とどう付き合っていくか答えが欲しかったんだなということがわかりました」と自ら伝えてくれて。
その方が最初に望んでいたのは大学病院の紹介状だったのですが、痛み止めを処方して、それが合うかどうかをみていくことになりました。
「クモの巣マップ」は他人が見て健康かどうかではなく、自分の中から湧き上がるものに意識を向けるきっかけとなる。
あくまで主語は「自分」だ。同じ5点でも、上がろうとしている5点なのか、下がろうとしている5点なのか、自分はどちらに向かうとハッピーなのか。その「プロセス」を見ることも大切だという。
医者は、この6次元のうち「身体」という1次元においての専門家なんですよね。けれど、専門だけにこだわっていたら、他の5次元が見えなくなってしまいます。
僕はいきがいの専門家ではない。でも本人が自分で「したい」と思っていることに気づいたとき、それを推すのも仕事だと思っているんです。
なので「身体の状態はイマイチなんだけど、それよりもいきがいが落ちている状態を先になんとかしたいんだよね」と伝えてもらったら、「それいいですね、じゃあどうしたらいいと思いますか?」と聞くようにしています。

症状と付き合い、なにをどう治したいかを自分で決めてもらう。その姿勢は相手が誰であっても同様だ。
たとえば、小児科で、親がすべてを説明して、医者も親の顔を見ながら喋るような光景をよく見る。それではきっと家に帰ってからも、本人の体調が悪いのに「どうする? 薬飲んだ方がいい?」と親に聞いてから飲むことになるだろう。けれど「ほっちのロッヂ」では、親が後ろにいても、本人に全部聞くようにしている。
定期的に診察に来る小学校高学年の子がいます。健康は本人のものだから、本人にどうしたいか質問を重ねていたんです。最初は親御さんが答えようとしていたのですが、あるときから「あなたの頭痛でしょ」とお子さんの言葉を待ってくれるようになりました。
僕が「どうしたらいいと思う?」と聞くと、「少し痛いときに我慢しちゃうと、結局後から痛くなるということがわかってきた」と本人が言う。続けて「じゃあどうしたらいい?」と聞くと「少し痛い時でも早めに薬飲んだらいいってことかもしれない」と答えてくれたり。
その日は「それいいね。じゃあ1か月間それやってみて、また結果教えて」と言って診察を終えました。
翌月、「紅さん(紅谷さん)、うまくいったよ! だいぶ痛みが少なくて済んだ」と。
「いいね、じゃあ来月までに薬何粒あればいい?」と聞くと、本人が「10粒あれば大丈夫」と自分で決められるようになっていたんです。

ここまで来れば、病気が自分の生活を邪魔する敵じゃなくて、自分の身体の一部であるとして、どう付き合っていくかを自分で見つけていける。
「ほんとに痛い日は1日寝ていれば治る」ということもわかった。「遠足とか休みたくない日に頭痛が出ないようにするにはどうしたらいい?」というような作戦会議には僕も参加しますけど、基本は本人主導でコントロールしてくれるようになるわけです。
「一緒に悩む」という選択肢があること
出会う人の回復力を信じ、サポートする。その人なりの健康を一緒に考える。それがほっちのロッヂで大切にされている姿勢と言えるのかもしれない。
自分自身の健康を考えるとき、一人で答えを探すのではなく、共に考えてくれる人がいるのは心強い。そう伝えると、紅谷さんはこう応える。
「本当はもっとこうしたい」と思っている人のそばで「それはこういう問題が起きるんじゃないか」という視点ばかり指摘するのか、「それすごくいいことだから、難しいことがあっても一緒に悩むよ」と伝えるのか。関わり方によって、見えてくるものも違ってくると思うんですよ。
最後に、風越学園に通う7年生(中学校1年生・取材当時)の話を紹介したい。
その子は「医者になりたい」という夢を持ち、ほっちのロッヂに出入りしていた。そこで働く医師・看護師の姿をみたその子は、学校のアウトプットデイ(年に5回ある学びの成果とプロセスの発表会)である冊子を作った。
そこには、ほっちのロッヂの訪問診療に同行して感じたことが多彩な絵やさまざまな素材、イラスト、文章で描かれていたのだ。



「一緒に悩みますよ」
冊子にはこう記されていた。
「健康は本人のものだから」。紅谷さんが取材中に語った言葉は、決して、人それぞれの健康を自己責任的に突き放しているわけではない。そのことを一人の中学生がほっちのロッヂで体感し、表現している。
それぞれの健康のあり方を安心して見つけていける。それがケアの文化拠点であるほっちのロッヂが確かに担っている役割なのだ。
Profile
Profile
![]()
-
ほっちのロッヂ
ケアの文化拠点
長野県軽井沢町の森の中に佇む。
「症状や状態、年齢じゃなくって、好きなことをする仲間として出会おう」という合言葉を掲げ、「ケアの文化拠点」を育む「大きな台所があるところ」。診療所であり、在宅医療の拠点であり、病児保育室や共生型通所介護、訪問看護ステーションなどの事業を担う場所。
訪問看護ステーションを「家に訪問したり、町全体の健康を考える活動のこと」と説明していたり、診療所を「内科、小児科、緩和ケア、在宅医療。自分の好きな暮らしを医療とともに考えるところ」、病児保育室を「親も子も、自分の回復力を信じて過ごせる場所のこと」、共生型通所介護・児童発達支援・放課後等デイサービスを「大きな台所、本棚、アトリエなどがある、町の人の居場所のこと」と表現している。
- ライター:白坂由里
-
『ぴあ』編集部を経て、アートライター。『美術手帖』『SPUR』、ウェブマガジン『コロカル』などに執筆。共著に『別冊太陽 ディック・ブルーナ』(平凡社、2015)など。美術を体験する鑑賞者の変化に関心がある。
この記事の連載Series
連載:こここスタディ
![]() vol. 272025.04.18“家庭”ってなんだろう? 子どもと大人が尊重しあう場所を目指す、児童福祉施設「てらす峰夢」をたずねて
vol. 272025.04.18“家庭”ってなんだろう? 子どもと大人が尊重しあう場所を目指す、児童福祉施設「てらす峰夢」をたずねて![]() vol. 262024.12.06差別と関係のない立ち位置ってあるの? 社会のあり方に矢印を向けて考える
vol. 262024.12.06差別と関係のない立ち位置ってあるの? 社会のあり方に矢印を向けて考える![]() vol. 252024.12.06差別ってなんだろう? 現代社会における差別の研究者 阿久澤麻理子さんをたずねて
vol. 252024.12.06差別ってなんだろう? 現代社会における差別の研究者 阿久澤麻理子さんをたずねて![]() vol. 242024.08.14正しい答えを刷り込むのではなく、自分で選ぶ手助けをする「包括的性教育」とは?
vol. 242024.08.14正しい答えを刷り込むのではなく、自分で選ぶ手助けをする「包括的性教育」とは?![]() vol. 232024.07.31「性教育」という言葉から何を想像する? 教育学者 堀川修平さんによる「包括的性教育」解説
vol. 232024.07.31「性教育」という言葉から何を想像する? 教育学者 堀川修平さんによる「包括的性教育」解説![]() vol. 222024.07.17「創造性」はどう育まれる? ブルーノ・ムナーリの軌跡から──デザイナー、現代美術作家、教育者のまなざし
vol. 222024.07.17「創造性」はどう育まれる? ブルーノ・ムナーリの軌跡から──デザイナー、現代美術作家、教育者のまなざし![]() vol. 212024.03.30「個人の心の問題」の多くは環境や政治の問題でもある〜「あなたのため」というバウンダリーの侵害〜
vol. 212024.03.30「個人の心の問題」の多くは環境や政治の問題でもある〜「あなたのため」というバウンダリーの侵害〜![]() vol. 202024.03.26自分と他者を区別する境界線「バウンダリー」とは?ソーシャルワーカー鴻巣麻里香さんによる解説
vol. 202024.03.26自分と他者を区別する境界線「バウンダリー」とは?ソーシャルワーカー鴻巣麻里香さんによる解説![]() vol. 192024.02.01「昔好きだった作品」の表現に戸惑ってしまったら? フィクションが与える2つの影響──文学研究者・小川公代さん
vol. 192024.02.01「昔好きだった作品」の表現に戸惑ってしまったら? フィクションが与える2つの影響──文学研究者・小川公代さん![]() vol. 182023.12.15「合理的配慮」は「ずるい」「わがまま」なのか? インクルージョン研究者 野口晃菜さんによる解説
vol. 182023.12.15「合理的配慮」は「ずるい」「わがまま」なのか? インクルージョン研究者 野口晃菜さんによる解説![]() vol. 172023.04.21“できる/できない”の社会を「ヨコへの発達」で問い直す。社会福祉の父・糸賀一雄を、垂髪あかりさんが研究する理由
vol. 172023.04.21“できる/できない”の社会を「ヨコへの発達」で問い直す。社会福祉の父・糸賀一雄を、垂髪あかりさんが研究する理由![]() vol. 162023.02.08「やさしい日本語」ってなに? 言語学者・庵功雄さんに聞くコミュニケーションの本質
vol. 162023.02.08「やさしい日本語」ってなに? 言語学者・庵功雄さんに聞くコミュニケーションの本質![]() vol. 152023.01.27人を見た目で判断することって全部「差別」になるの? 社会学者 西倉実季さんと、“ルッキズム”について考える
vol. 152023.01.27人を見た目で判断することって全部「差別」になるの? 社会学者 西倉実季さんと、“ルッキズム”について考える![]() vol. 142023.01.16自分の気持ちを話さない自由がある。NPO法人ぷるすあるはと一緒に考えた“きもち”との付き合い方
vol. 142023.01.16自分の気持ちを話さない自由がある。NPO法人ぷるすあるはと一緒に考えた“きもち”との付き合い方![]() vol. 132022.12.14“障害”ってそもそも何だろう? 困難の原因を「社会モデル」から考える──バリアフリー研究者・星加良司さん
vol. 132022.12.14“障害”ってそもそも何だろう? 困難の原因を「社会モデル」から考える──バリアフリー研究者・星加良司さん![]() vol. 122022.11.29「ちゃんとしなきゃ」の呪いをとくには?福祉社会学者 竹端寛さん× 僧侶 松本紹圭さん
vol. 122022.11.29「ちゃんとしなきゃ」の呪いをとくには?福祉社会学者 竹端寛さん× 僧侶 松本紹圭さん![]() vol. 112022.10.27“ありのままの自分”を大切にするって、どういうことだろう? しょうぶ学園施設長 福森伸さんをたずねて
vol. 112022.10.27“ありのままの自分”を大切にするって、どういうことだろう? しょうぶ学園施設長 福森伸さんをたずねて![]() vol. 102022.09.27「福祉の現場」と「芸術」の根っこには通ずるものがある? 福祉環境設計士 藤岡聡子さんをたずね、「ケアの文化拠点」ほっちのロッヂへ
vol. 102022.09.27「福祉の現場」と「芸術」の根っこには通ずるものがある? 福祉環境設計士 藤岡聡子さんをたずね、「ケアの文化拠点」ほっちのロッヂへ![]() vol. 082022.08.12弱さは個人の問題ではなく、構造上の問題だ。公認心理師・臨床心理士 信田さよ子さんと考える“弱さ”のこと
vol. 082022.08.12弱さは個人の問題ではなく、構造上の問題だ。公認心理師・臨床心理士 信田さよ子さんと考える“弱さ”のこと![]() vol. 072022.07.28“違う“の不安をどう乗り越えればいい? グレーではない「色」で表現する発達の特性──星山麻木さん
vol. 072022.07.28“違う“の不安をどう乗り越えればいい? グレーではない「色」で表現する発達の特性──星山麻木さん![]() vol. 062022.04.12「私はどう生きたらいい?」を、一人で抱えない社会へ。医師・西智弘さんに聞く、地域活動と“ケア“の文化づくり
vol. 062022.04.12「私はどう生きたらいい?」を、一人で抱えない社会へ。医師・西智弘さんに聞く、地域活動と“ケア“の文化づくり![]() vol. 052022.03.22偏見がない人はいない。川内有緒さん×木ノ戸昌幸さん『わたしの偏見とどう向き合っていく?』イベントレポート
vol. 052022.03.22偏見がない人はいない。川内有緒さん×木ノ戸昌幸さん『わたしの偏見とどう向き合っていく?』イベントレポート![]() vol. 042022.02.04居場所・つながり・役割・生産性。「望まない孤独」をめぐる対談でみえたものとは?吉藤オリィさん×奥田知志さん
vol. 042022.02.04居場所・つながり・役割・生産性。「望まない孤独」をめぐる対談でみえたものとは?吉藤オリィさん×奥田知志さん![]() vol. 032021.10.26大切なものを失った悲しみや痛みと共に生きていくには? グリーフサポートが当たり前にある社会を目指す 尾角光美さんをたずねて
vol. 032021.10.26大切なものを失った悲しみや痛みと共に生きていくには? グリーフサポートが当たり前にある社会を目指す 尾角光美さんをたずねて![]() vol. 022021.06.24差別や人権の問題を「個人の心の持ち方」に負わせすぎなのかもしれない。 「マジョリティの特権を可視化する」イベントレポート
vol. 022021.06.24差別や人権の問題を「個人の心の持ち方」に負わせすぎなのかもしれない。 「マジョリティの特権を可視化する」イベントレポート![]() vol. 012021.04.15さまざまな側面をもつ「わたし」と「あなた」をそのまま大切にするには? 美学者 伊藤亜紗さんを訪ねて
vol. 012021.04.15さまざまな側面をもつ「わたし」と「あなた」をそのまま大切にするには? 美学者 伊藤亜紗さんを訪ねて