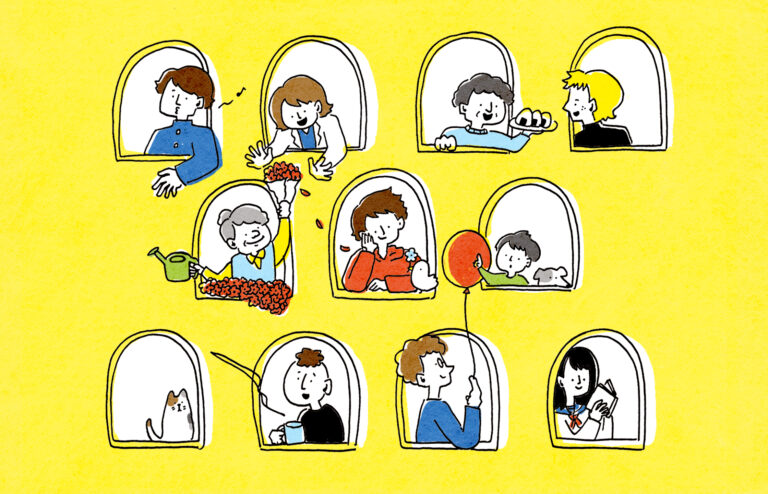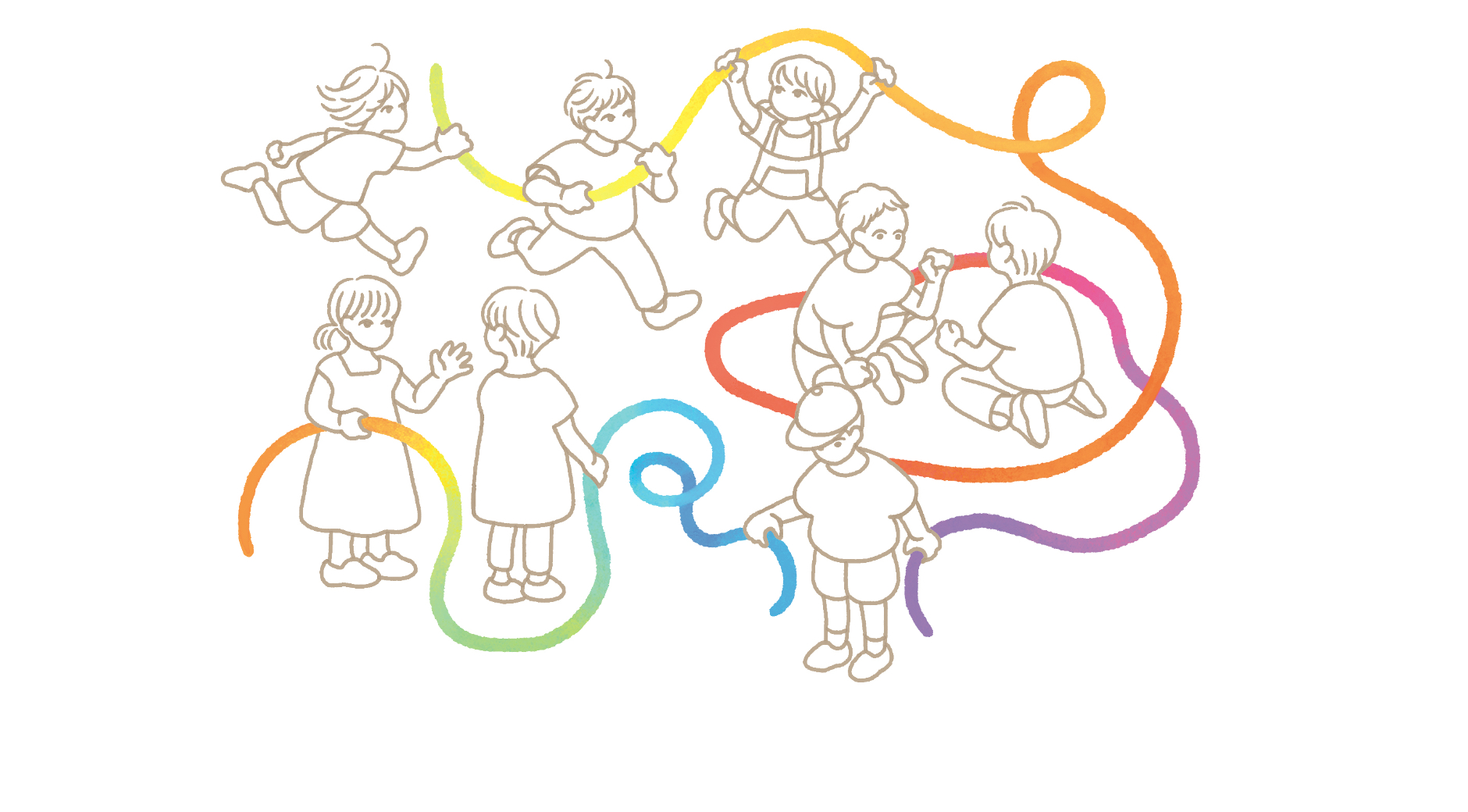

“違う“の不安をどう乗り越えればいい? グレーではない「色」で表現する発達の特性──星山麻木さん こここスタディ vol.07
私たちはもともと、一人ひとりが生まれながらに異なる存在だ。年齢や性、国籍、あるいは障害……そうした「ダイバーシティ(多様性)」については、知られる機会も増えてきている。
ただ、それぞれの“違い”のありかを知っていたとして、いざ「本当にみんなが一緒に生きてられている?」と問われたら、急に不確かで、脆い社会が目についてしまうのはなぜだろうか。
今回主に取り上げる「発達障害」も、近年の言葉の広がりとともに、当事者たちの存在が認知されるようになってきた。自身や身の回りで起きていた問題の本質を知って、救われた人も増えているだろう。一方で、言葉が一人歩きして新たなラベルになり、苦しむ当事者の声が聞こえることもある。身近に生じる障害を受け止めきれず、「どうすればいいの?」と戸惑う人もいる。
インクルーシブな(包摂された)社会を実現するためには、知識の広がりだけでは不十分なのだ。多様な“個”のあり方を認識した上で、その先の社会は私たちが協力してつくっていかなくてはいけない。では具体的にどうすれば、私たちはお互いの特性を尊重し合いながら、“個と個”のまま一緒に生きることができるのだろう。
発達障害について議論の多い「子育て」や「教育」の現場をよく知り、多様な子どもたちの支え方について研究・実践する星山麻木さん(明星大学教授)に、考えるヒントを尋ねた。
“普通”を求める呪いが、大人を苦しめている
「他の子と違うんですけど、どうしたらいいんでしょう」
「どうやったらこの子は普通にじっとしてくれるのかな」
「ノートはこう書きなさい、一度教えたものはちゃんと覚えなさい」
学校や保育園・幼稚園などで、今もよく聞かれる声だ。“多様性が大事”と頭ではわかっていても、いざ人と違うことを目の当たりにすると、矛盾が現れてしまう。親や教師、保育者たちがその言葉を本当の意味で受け止め切れておらず、子どもとの間にさまざまな問題や悩みを生んでいる。
こうした背景について、星山さんは「“ありのままでいい”という考え方そのものが、大人が言われてきた価値観と対立概念なんです」と語る。
今の大人たちだって、本当は多様だったんです。ただそれを押し殺して、否定せざるを得なかった世代だとも思うんですよ。そして、そうやって育つなかで「信じてきた価値観」が、自分の思考のもとになっている。簡単には壊せない枠のようなものがあるわけです。
知識として多様性の大切さはわかっていても、「自分がこうでありたい」と一体どこまで出していいのかはわからない。変化を喜ばしいと思いつつも、それを全部受け入れていいのか自信がない。そんな「不安」を、大人たちは感じているのだと思います。

今のまま、みんなと同じ自分を演じているほうが正しいのではないか。“普通”や“標準”に近いほうが生きやすいのではないか。
そう考えて行動する人がまだ多数派を占める現実を指し、星山さんはより強い言葉で「呪い」と表現する。そして、その呪いを解くことが、発達障害に限らず多様な人同士が一緒に生きるための大事なスタート地点になると話す。
「多数派の流儀に合わせろ」と教えられて育ってきたことが、呪いがかかっているかのように世代を超えて効き続けているんです。子どものために良かれと思って、親や先生が同じことを正義感で押し付けてしまう。変化への不安を押し付けて、人と違うところを「正そうと」してしまうわけですよ。
でも、それは人と人とが“同じ”を前提にしてしまっているからなんです。実際には人は多様で、本当は“違う”がスタート。そこのズレに気づいて、大人たち自身が「いろいろあっていいんだよね」と呪いを解けるようにしていかなければなりません。
そもそも、多数派になれたからと言って幸せになれるとは限らないですからね。
「多数派に近づけさせる」をゴールにするのをやめよう、といつも伝えているという星山さん。そうした考えを持つのは、およそ40年に渡って教育現場で子どもたちと接してきた経験があるからだ。
そのキャリアは養護学校(現在は盲学校・聾学校を含めて特別支援学校に一本化)からスタートしている。最初に担任をしたクラスで出会った、脳性まひ1級の子どもとの出会いが、星山さんの“違う”の捉え方に大きな影響を与えた。
言葉は出てこないし、体の動きはとてもゆっくりで、「自分に教えられるのだろうか」と不安がありました。でも付き合えば付き合うほど、その子からは“人間”を感じることばかりだったんです。誰かが喧嘩をしていると悲しい顔をして涙を流したり、私が洋服を脱がせるときには私を思いやって一生懸命体を寄せてくれたり……。
その子どもに限らず、他にも私が最初に出会った子たちは、それぞれがみんな違っていました。見かけ、言葉がゆっくりなこと、「1+1」がわからないこと。教師としてはそれらに目がいきがちですが、日々の関係の中で「人間って何だろう」と考えたとき、大事なのはそこじゃないんですよね。
“同じ”人として誰もが持つ尊さに目を向けながら、“違う”に自信と誇りを持つこと。それこそが重要じゃないかと、子どもたちと人間として付き合い出したときから、私は考えるようになりました。
少数派への排斥を、乗り越えるための「教育」
“違う”をスタートにしながら、その尊さにまず目を向け、価値観を転換していく。それは確かに社会をつくる上で重要な考え方となる一方で、人間は「異質な存在を排斥する」ことがあるのも、歴史を見れば否定できないように思える。
多様性を学ぶための星山さんのワークショップでも、その傾向ははっきり見て取れるそうだ。
私が開いているワークショップでは、多数派になること、少数派になることをそれぞれ体験してもらいます。例えば特定の色が好きな人ばかりでグループにして、そこに別の色が好きな人を後から加える。すると、私が何かを言う前からその人を強く警戒する空気に、なぜか勝手になるんです。
大人も子どももそうなっていくのを見ると、“違う”と認識するものに対して私たちが恐れと不安を持つのは、本能かもしれないと感じざるを得ません。群れをつくって生きる動物である以上、共通項を見つけて「仲間だ」と認識するようにできているのだと思います。
ワークショップでもうひとつ興味深いのは、グループ全体の特性と違う1人が、だんだん自分らしく振る舞えなくなっちゃうこと。そこに本来優劣はないはずなんですけど、みんなおとなしくなっちゃうんですね。たとえ理念としては「多様性が大事」と掲げられていたとしても、何もしないと少数派は排斥されていくんです。
そんな現実があるからこそ、星山さんは「これを超えていくには、どうしたらいいと思いますか?」と参加者に問いかける。異質なものを拒む特性が人間にあったとしても、それぞれの尊さは守られなければならない。

乗り越えるためにあるのが、私は「教育」なのだと考えています。みなさんにも、そこの可能性を必ず伝えるようにしてます。
なぜなら、人間は本能だけで生きている動物ではなく、知性と経験を伴う存在だからです。“違う”人同士が群れていっても、実は大丈夫なんだと学ぶことができる。教育は、そうした知識や知恵を次の世代に送ることそのものなんです。
星山さんが、大学という教育現場に身を置き続ける理由もここにある。一方で、専門とする発達支援については、独特の難しさもつきまとうと語る。
「ASD(自閉スペクトラム症)」や「ADHD(注意欠如・多動症)」「LD(限局性学習症、学習障害)」などの発達障害は一見しただけではわかりづらいからこそ、気づいてもらえなかったり、過剰に恐れられたりしてしまうこともあるからだ。
ASDであれば、例えば対人コミュニケーションの困難さ、「音が聞こえすぎてしまう」などの感覚の敏感さ、ADHDであれば「もっと動きたいけれど我慢している」状態など、またLDなら「教科書の文字がスムーズに頭に入ってこない」といった困難が生じやすいでしょう。ただ、これらは本質的に脳の特性の違いによるものなので、他人からは見えづらいところで困っているケースも多いんですね。
そこで、多くの学校教育は矛盾に直面しています。一般的な教室では30〜40人の子どもたちに1人の先生が同じ内容を、同じ方法で教えるわけですよ。私は教員養成にも長く携わってきていますが、人間の多様性を知れば知るほど、今のような体制では無理だとわかるんです。
もちろんできることもあります。先ほど、大人については自らの「呪い」に気づくことが大事と話しましたが、子どもに対してのキーワードは「安心」です。一人ひとりに「あなたはそのままでいい」という安心感をまず与えること。保護者に対しては、「この子らしいやり方をわかっていれば、それで大丈夫」とまず伝えること。
診断が気になる保護者もいると思います。ですが本来、診断は療育などの支援機関につながるため、あるいは自分の生き方を知るためのいち手段であって、「診断がついたからこうしましょう」と分けるためのものではないと考えています。結局は目の前の子どもの姿に応じて丁寧にやるという、当たり前のことができるかどうかだけなんです。
グレーゾーンではなく『虹色』で発達障害を考える
発達障害を考える上で重要な概念に「スペクトラム(連続体)」がある。これはさまざまな特性の表れ方が、集団の中で連続的に、切れ目なく分布していることを意味している。本来、「ここまでが障害で、ここからが障害ではない」と区切れるものではないのだ。
また、個人の中にもさまざまな特性が重なり合っている。ASD、ADHDの傾向には知的障害を伴う場合もあれば、そうでない場合もある。ASD、ADHD、LDの傾向が重複し、特性としての表れ方に大きな差が出ることも珍しくない。
特にASD、ADHDについて言えば、ある意味ではみんなが当事者でもあると言えるんです。そのパーセンテージが違うだけで、実は誰だって特性はある。
このことを人間の教養として、全ての大人が学んでほしいと思っています。「自分もこういうところがある」と気づけば、子どもに対する見方が変わっていくはずです。

1人の中に多様な特性があることを、星山さんはよく『虹色』に例えて表現する。ASD、ADHDに特徴的な傾向を7色で示しつつ、そのどれかひとつに当てはまるのではなく、いくつも混ざり合っている存在だと捉える。
この概念を提唱するようになったのは、いわゆる「定型発達」と発達障害の間を示す「グレーゾーン」という表現に、星山さんが強い違和感を抱いていたからだ。
人間は、白と黒じゃない。ましてやグレーでもありません。もしその人が黒だったら、白に近づけなければならないのでしょうか。
すごく多様な私たちを色で表現するとしたら、むしろ虹色になるんじゃないかと。一人ひとりの違いは、その組み合わせの違いです。ダメな色はなくて、豊かな色の組み合わせだけがあります。
それに子どもの場合、本人に診断名だけを伝えても、理解しづらいことがあります。だから、虹色で特性を伝えて、生じやすい困難への対処を知ってもらうんです。知識があれば、生きやすくなる。
星山さんは4歳の子どもにも、「あなたは少数派だ」とはっきりと伝える。「やればできる」「頑張ればできる」と大人は言いがちだが、真面目な子ほど頑張って、普通になろうと苦しむからだ。
普通になれなくても大丈夫と伝えるために、星山さんがこれまで考えてきた表現には、『虹色』以外にもさまざまなものがあるという。
私が関わったなかに、周囲の子どもとよくトラブルを起こす子がいました。先ほどの7色で言うと、「レッド」が一番強い(ASD傾向のあるなかでも、積極的な)タイプの子どもです。その子は車が好きだったので、「君は車で言ったらポルシェくんだよね」と伝えました。子どもの好きな世界において、レアで価値が高いものを例に出すんです。
すると自らの特性を察しつつ、今度は「ポルシェはかっこいいから俺が一番偉いんだ」と言ってくる。そこで、私はもうひとつフォローをしました。「交差点に出てごらん。自家用車も、トラックも、軽自動車もいろんな車が走っているけど、それぞれに役割があるよね。トラックは物を運んでくれるし、軽は小回りが効く。君はスピード抜群で走れるけれど、ほら、よく事故を起こしてメンテナンスしているんじゃない?」と。
こういう表現で、子どもはよくわかってくれます。「君はレアタイプで進化系なんだね」と言ったりもしますが、障害があるかないかではなくて、人間それぞれ得意なものと苦手なものは違うとガイドするんです。
そして、「君の得意なことを、友達は苦手にしているかもしれない。それなら助けられるよね」と伝える。これがわかれば、あとはジグソーパズルの組み合わせです。みんなが自分の輪郭を知っておくことが、人とつながっていくためには大事なんです。

子どもたちに学ぶ「一緒にいる」ための工夫
「ジグソーパズル」も、違う人同士がうまく組み合わさって一緒にいるための、星山さんにとって大切なイメージだ。では、そんなイメージを持ったとして、いざ目の前で誰かが困難に直面していたとき、私たちはどんな工夫が求められるだろうか。
具体的な対応を考えるときに、法律などでも定められる「合理的配慮」(一人ひとりの特徴や状況に応じた調整・変更)はひとつのカギと言えるだろう。その実践について、星山さんは子どもから学ぶことが多いと話す。
少数派への通訳も配慮も、子どもたち同士は柔軟で上手だなと思うことがよくあります。「先生、後ろから呼んでもこの子は気がつかないよ」「『〇〇ちゃん』って手を振ってから呼ぶと来るよ」と教えてくれたりね。それを彼らは「支援」などと考えず、自然にやるんです。
ひとつ、私が感動したエピソードを紹介しましょう。小学校1年生ぐらいで、すぐ怒ってしまってルールを破る子がいたんですよ。自分が負けそうになるとバーンと遊びを壊して、他の子が勝てないようにしてしまう。
他の子たちは考えました。そして「ねえねえ、〇〇くん、怒っていいのは3回にしよう」と言ったんです。見ていると、1回怒ってしまったその子に「あと2回怒っていいよ」なんて言っている(笑)。“俺たちだってそこを譲ってるんだから、お前もなんとか頑張れよな”ということだと思うんですよ。私は「子どもってすばらしいな」と思いました。
大人だったら、例えば「怒ったらおやつをあげません」と言ってしまうかもしれない。そう思うと、大人が考え出すルールよりもっと上位の概念に、子ども同士には仲間意識のようなものがあるわけです。
こうした事例は他にも尽きない。例えば異年齢での「鬼ごっこ」も合理的配慮に溢れていると星山さんは指摘する。小さな子、足の速い子、言葉のゆっくりな子、リーダーシップのある子……そうした多様な子どもたちが、まず「仲間として遊びたい」と思うところから遊びが始まる。そのなかで、自然に「この子は2回タッチで鬼ってしよう」「この子は手をつないでしようか」と、子どもたち同士で助け合っていく。
これらは決して特別なことではない。ただワクワクする楽しいことを、一緒にやるための行為なのだ。

「特別支援」という言葉がある。子どもの数は減っているが、診断数の増加もあり、特別支援学校・学級に通う子どもは年々増加してきた。
もちろん個人の特性に合わせ、適切な支援の場をつくることは重要だ。一方で星山さんは、この言葉を個人の属性と見なすのではなく、「特定の環境においては必要になるもの」と考えることも大切にしている。
トイレに行きたいときに、それを言い出せなくてもじもじしていたら「あなたは今、特別支援が必要だよね」ということになります。つまり、状況と場所によって誰でも対象になり得るんですね。
「ASDだから」「ADHDだから」「LDだから」ではなくて、私たちは人間です。一生の中でも、時に支援が必要だったり必要でなかったりして、循環しているに過ぎない。場面によって少数派になったり多数派になったりもするわけです。みんなが当事者なんですよ。
だから私は、みんなが「困っている人がいたら当たり前に手を貸せる人」であってほしいと思うし、そう子どもたちにも伝えていきたいんです。
大人が「自分の中の多様性」に目を向けるところから
みんなが当事者——。ここまでの話を受けて、それでも「私はマイノリティじゃない」「支援はいらない」と拒否感を抱く人がいたら、私たちを取り巻く“無意識の偏見”が関係しているかもしれない。障害のある人、さまざまな支援が必要な人を、気づかぬうちに“優劣”のうちの“劣”と捉えてしまう可能性がそこには潜む。
しかし、実はごく身近に多様な人々が存在し、互いの関係は循環している。ただそのことを知る機会として、さまざまな人々と出会ったり、友達として鬼ごっこをしたりする経験が、私たちには減っているのだ。
多世代・異年齢のコミュニティをこの国は失いました。それをもう1回、人工的に作るのが、問題解決の方法だと考えています。例えば今の子どもたちが行くようなスポーツ教室や塾では、なかなか「人間力」の育ちにつながらないのではと私は感じているんです。それは、多様性のあるコミュニティではないから。
かといって上から押し付けられるような福祉政策でもなくて、お互いに楽しいことをわいわいとやれる工夫が必要です。そういう場があれば、相手のことがわかるし、そのうちに自分のこともわかってきます。
結局、自分が何者かということは、人と触れ合わないとわからないんですよ。それも、温かくて安心できる仲間とね。
同時に星山さんは、これまで出会ってきた少数派の子どもたちの「思い」を、いただいた手紙を読んだり絵を見せたりすることで発信するようにもしている。当事者の視点をわかりやすく感じてもらえるだけでなく、大人が「そういえば自分にも、小さい頃こんなことがあったかも」と思い出すきっかけにもなるという。
中には絵本として出版され、さまざまな場所で教材として使われているものもある。

先生や親には特に、自分のことを知ってほしいと考える星山さん。研修やワークショップ、講演会を実施するときには、子どもの話のように見せながらも、実際には「大人自身に自分を理解してもらいたい」と思って話をしているそうだ。
自分の考え方の癖を知らないまま、「こうあるべき」「絶対こうなんだ」と大人の側が決めてしまっていると、多様な子どもへの対応がうまくいかないわけですよ。でもそれが、「自分もこういう思考の癖があるんだな」と理解し始めると、大人の側の対応が変わってきます。
俯瞰の視線が入ってくることで、絶対に正解だって決めつけていたところから、「子どもから見るとそうじゃなかったんだ」「正解はいっぱいあるかな」と考えが広がっていくんだと思うんですね。

「多様性が大事だ」と言われる時代。しかし、大事か大事でないかではなく、多様性はすでにここにあるものだ。より重要なのは、そのままを表せる場があること、そして誰もが、互いを支えたり支えられたりする当事者になることではないだろうか。
子どもたちに限った話ではない。星山さんは「大人だって、本当は多様」と何度も話す。知らず知らずのうちに自分の色を隠してしまっているのは、他ならぬ私たち自身かもしれない。
『虹色』のワークショップを小学校でやったとき、ある先生が「僕はオレンジとイエローが多いかな」と言いました。オレンジは多動な傾向が強く、イエローは忘れ物の多い特性。だけど、先生がそう言ったらクラスの子どもたちはみんな「意外!」と言うわけです。「だって先生忘れ物しないし、きちんとしてる」って。
実はその先生、ADHDに近い特性を本当は持っているんだけど、「忘れ物をしてはいけない」「しっかりしていなくてはいけない」と思って努力していたんです。一方で、ダンスがすごく好きなのだけど、そっちの姿は子どもたちに一切見せないようにしていました。
でも、大人が完璧な人を演じてしまうと、子どもは自分の色に自信を持てなくなると思うんです。むしろ特性をちゃんとさらけ出して、苦手なことをカバーするための工夫や、得意なことを誇りに思う姿をどんどん見せてほしい。そうして生きていることを、もっとメッセージとして投げかけてほしいと私は思いますね。
Profile
- ライター:遠藤光太
-
フリーライター。発達障害(ASD・ADHD)の当事者。興味のある分野は、社会的マイノリティ、福祉、表現、コミュニティ、スポーツなど。初単著に『僕は死なない子育てをする』(創元社)。
この記事の連載Series
連載:こここスタディ
![]() vol. 272025.04.18“家庭”ってなんだろう? 子どもと大人が尊重しあう場所を目指す、児童福祉施設「てらす峰夢」をたずねて
vol. 272025.04.18“家庭”ってなんだろう? 子どもと大人が尊重しあう場所を目指す、児童福祉施設「てらす峰夢」をたずねて![]() vol. 262024.12.06差別と関係のない立ち位置ってあるの? 社会のあり方に矢印を向けて考える
vol. 262024.12.06差別と関係のない立ち位置ってあるの? 社会のあり方に矢印を向けて考える![]() vol. 252024.12.06差別ってなんだろう? 現代社会における差別の研究者 阿久澤麻理子さんをたずねて
vol. 252024.12.06差別ってなんだろう? 現代社会における差別の研究者 阿久澤麻理子さんをたずねて![]() vol. 242024.08.14正しい答えを刷り込むのではなく、自分で選ぶ手助けをする「包括的性教育」とは?
vol. 242024.08.14正しい答えを刷り込むのではなく、自分で選ぶ手助けをする「包括的性教育」とは?![]() vol. 232024.07.31「性教育」という言葉から何を想像する? 教育学者 堀川修平さんによる「包括的性教育」解説
vol. 232024.07.31「性教育」という言葉から何を想像する? 教育学者 堀川修平さんによる「包括的性教育」解説![]() vol. 222024.07.17「創造性」はどう育まれる? ブルーノ・ムナーリの軌跡から──デザイナー、現代美術作家、教育者のまなざし
vol. 222024.07.17「創造性」はどう育まれる? ブルーノ・ムナーリの軌跡から──デザイナー、現代美術作家、教育者のまなざし![]() vol. 212024.03.30「個人の心の問題」の多くは環境や政治の問題でもある〜「あなたのため」というバウンダリーの侵害〜
vol. 212024.03.30「個人の心の問題」の多くは環境や政治の問題でもある〜「あなたのため」というバウンダリーの侵害〜![]() vol. 202024.03.26自分と他者を区別する境界線「バウンダリー」とは?ソーシャルワーカー鴻巣麻里香さんによる解説
vol. 202024.03.26自分と他者を区別する境界線「バウンダリー」とは?ソーシャルワーカー鴻巣麻里香さんによる解説![]() vol. 192024.02.01「昔好きだった作品」の表現に戸惑ってしまったら? フィクションが与える2つの影響──文学研究者・小川公代さん
vol. 192024.02.01「昔好きだった作品」の表現に戸惑ってしまったら? フィクションが与える2つの影響──文学研究者・小川公代さん![]() vol. 182023.12.15「合理的配慮」は「ずるい」「わがまま」なのか? インクルージョン研究者 野口晃菜さんによる解説
vol. 182023.12.15「合理的配慮」は「ずるい」「わがまま」なのか? インクルージョン研究者 野口晃菜さんによる解説![]() vol. 172023.04.21“できる/できない”の社会を「ヨコへの発達」で問い直す。社会福祉の父・糸賀一雄を、垂髪あかりさんが研究する理由
vol. 172023.04.21“できる/できない”の社会を「ヨコへの発達」で問い直す。社会福祉の父・糸賀一雄を、垂髪あかりさんが研究する理由![]() vol. 162023.02.08「やさしい日本語」ってなに? 言語学者・庵功雄さんに聞くコミュニケーションの本質
vol. 162023.02.08「やさしい日本語」ってなに? 言語学者・庵功雄さんに聞くコミュニケーションの本質![]() vol. 152023.01.27人を見た目で判断することって全部「差別」になるの? 社会学者 西倉実季さんと、“ルッキズム”について考える
vol. 152023.01.27人を見た目で判断することって全部「差別」になるの? 社会学者 西倉実季さんと、“ルッキズム”について考える![]() vol. 142023.01.16自分の気持ちを話さない自由がある。NPO法人ぷるすあるはと一緒に考えた“きもち”との付き合い方
vol. 142023.01.16自分の気持ちを話さない自由がある。NPO法人ぷるすあるはと一緒に考えた“きもち”との付き合い方![]() vol. 132022.12.14“障害”ってそもそも何だろう? 困難の原因を「社会モデル」から考える──バリアフリー研究者・星加良司さん
vol. 132022.12.14“障害”ってそもそも何だろう? 困難の原因を「社会モデル」から考える──バリアフリー研究者・星加良司さん![]() vol. 122022.11.29「ちゃんとしなきゃ」の呪いをとくには?福祉社会学者 竹端寛さん× 僧侶 松本紹圭さん
vol. 122022.11.29「ちゃんとしなきゃ」の呪いをとくには?福祉社会学者 竹端寛さん× 僧侶 松本紹圭さん![]() vol. 112022.10.27“ありのままの自分”を大切にするって、どういうことだろう? しょうぶ学園施設長 福森伸さんをたずねて
vol. 112022.10.27“ありのままの自分”を大切にするって、どういうことだろう? しょうぶ学園施設長 福森伸さんをたずねて![]() vol. 102022.09.27「福祉の現場」と「芸術」の根っこには通ずるものがある? 福祉環境設計士 藤岡聡子さんをたずね、「ケアの文化拠点」ほっちのロッヂへ
vol. 102022.09.27「福祉の現場」と「芸術」の根っこには通ずるものがある? 福祉環境設計士 藤岡聡子さんをたずね、「ケアの文化拠点」ほっちのロッヂへ![]() vol. 092022.09.07“健康”ってなんだろう?ケアの文化拠点「ほっちのロッヂ」紅谷浩之さんをたずねて
vol. 092022.09.07“健康”ってなんだろう?ケアの文化拠点「ほっちのロッヂ」紅谷浩之さんをたずねて![]() vol. 082022.08.12弱さは個人の問題ではなく、構造上の問題だ。公認心理師・臨床心理士 信田さよ子さんと考える“弱さ”のこと
vol. 082022.08.12弱さは個人の問題ではなく、構造上の問題だ。公認心理師・臨床心理士 信田さよ子さんと考える“弱さ”のこと![]() vol. 062022.04.12「私はどう生きたらいい?」を、一人で抱えない社会へ。医師・西智弘さんに聞く、地域活動と“ケア“の文化づくり
vol. 062022.04.12「私はどう生きたらいい?」を、一人で抱えない社会へ。医師・西智弘さんに聞く、地域活動と“ケア“の文化づくり![]() vol. 052022.03.22偏見がない人はいない。川内有緒さん×木ノ戸昌幸さん『わたしの偏見とどう向き合っていく?』イベントレポート
vol. 052022.03.22偏見がない人はいない。川内有緒さん×木ノ戸昌幸さん『わたしの偏見とどう向き合っていく?』イベントレポート![]() vol. 042022.02.04居場所・つながり・役割・生産性。「望まない孤独」をめぐる対談でみえたものとは?吉藤オリィさん×奥田知志さん
vol. 042022.02.04居場所・つながり・役割・生産性。「望まない孤独」をめぐる対談でみえたものとは?吉藤オリィさん×奥田知志さん![]() vol. 032021.10.26大切なものを失った悲しみや痛みと共に生きていくには? グリーフサポートが当たり前にある社会を目指す 尾角光美さんをたずねて
vol. 032021.10.26大切なものを失った悲しみや痛みと共に生きていくには? グリーフサポートが当たり前にある社会を目指す 尾角光美さんをたずねて![]() vol. 022021.06.24差別や人権の問題を「個人の心の持ち方」に負わせすぎなのかもしれない。 「マジョリティの特権を可視化する」イベントレポート
vol. 022021.06.24差別や人権の問題を「個人の心の持ち方」に負わせすぎなのかもしれない。 「マジョリティの特権を可視化する」イベントレポート![]() vol. 012021.04.15さまざまな側面をもつ「わたし」と「あなた」をそのまま大切にするには? 美学者 伊藤亜紗さんを訪ねて
vol. 012021.04.15さまざまな側面をもつ「わたし」と「あなた」をそのまま大切にするには? 美学者 伊藤亜紗さんを訪ねて