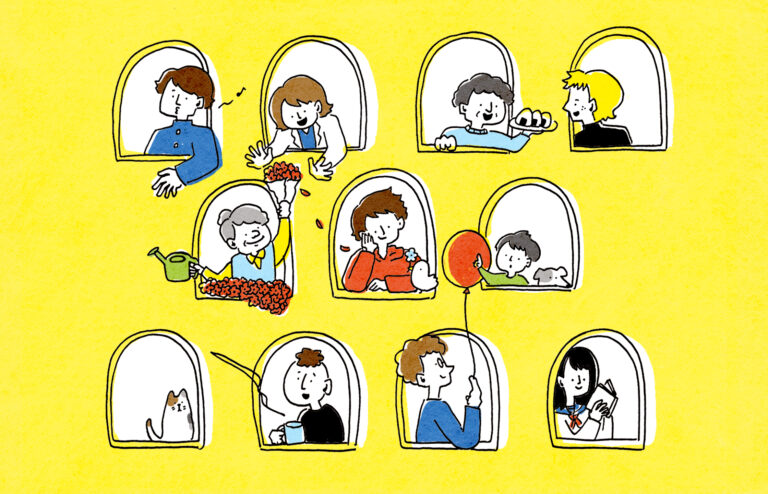「福祉の現場」と「芸術」の根っこには通ずるものがある? 福祉環境設計士 藤岡聡子さんをたずね、「ケアの文化拠点」ほっちのロッヂへ こここスタディ vol.10
一人ひとりの違いに向き合うこと、社会構造によって生まれている差別に抵抗し、なくそうと行動すること、暮らしのなかにある違和感に立ち止まること、これらを1人だけではなく、誰かと共に考えていくこと。
「文化芸術」と呼ばれるもの、そこに携わるアーティストが活動を進める手つきには、上記で挙げたことを大切にするヒント、創造的な工夫と実践が多くあるように思います。
またそれらは「医療」や「福祉」と呼ばれているもの、現場で働く人やその環境を支える人の実践にも既にたくさんあると思うのです。
そんな思いを抱き、調べ物をしている中で出会ったのが福祉環境設計士を名乗る藤岡聡子(ふじおか・さとこ)さんでした。「人の流れの再構築を」をミッションに掲げる株式会社ReDo代取締役を務める藤岡さん。これまでに介護や子育て、まちづくりにまつわる事業に多く携わってきました。そのひとつが東京都豊島区椎名町の商店街にあった「長崎二丁目家庭科室」です。そこは「習い事スペースとセルフカフェから成る、福祉・多世代間の、出会いが生まれる場所」であり、「それぞれの知恵や得意を持ち寄り、集まれる場所」でした。
2020年4月には、長野県軽井沢町の森の中にある「ケアの文化拠点」ほっちのロッヂを、医療法人社団オレンジ理事長・ほっちのロッヂ共同代表・医師の紅谷浩之さんと立ち上げています。
「文化芸術と福祉の現場が出会うことで育めるものとは」。
大きすぎる問いとはわかりつつも、2021年9月都内某所にて、藤岡さんに話を伺いました。またほっちのロッヂという場所やそこにあるものを目撃したいと考え、同年12月ほっちのロッヂをたずね、働き手のみなさんにも話を伺いました。
※ほっちのロッヂとは:
長野県軽井沢町の森の中にある「ケアの文化拠点」。「症状や状態、年齢じゃなくって、好きなことをする仲間として出会おう」という合言葉を掲げる、「大きな台所があるところ」。診療所であり、在宅医療の拠点であり、病児保育室や共生型通所介護、訪問看護ステーションなどの事業を担う場所。
ほっちのロッヂについては、こちらの記事もぜひご覧ください。
・“健康”ってなんだろう?ケアの文化拠点「ほっちのロッヂ」紅谷浩之さんをたずねて
(こここ編集部)
福祉の現場と芸術の根っこには通ずるものがある?
「福祉の現場と芸術の根っこには通ずるものがある」
Twitterラジオ「Radio現場」に出演していた藤岡さんの言葉だ。哲学者の鶴見俊輔が提唱した芸術概念「限界芸術」を知りそう思った、と藤岡さんは語る。
鶴見氏の著作『限界芸術論』によると「限界芸術とは、非専門的芸術家によって作られ、非専門的享受者によって享受される」と記されている。たとえば、日常生活での身振りや労働のなかにあるリズム、それらから生まれる遊び、鼻歌、らくがき、手紙、祭、葬式、会議、家族アルバムなどが「限界芸術」にあてはまる。
藤岡聡子さん(以下、藤岡):福祉の働き手はケアを必要とする人の所作・行為などの表現を支えている。限界芸術という視点にふれて、働き手が毎日当たり前のようにやっていることのかけがえのなさを言葉にしてもらえていると思ったんです。


続けて藤岡さんは、ほっちのロッヂで医師として働く萩原菜緒(おぎはら・なお)さんが持っていた、他者の表現へのまなざしについて教えてくれた。
藤岡:なおさんがある人のことを話してくれて。ペンを持つのも重いと感じる状況にある人でした。「その人は、それでも線が描きたいって言うんだよね」となおさんは語ってくれたんです。身体的な辛さやその人が抱えている症状だけではなく、「〜したい」という気持ちやその人が自分らしいと思えることがなんなのか、見逃さない聞き逃さないようにしていると感じました。つまり人それぞれの「表現」を大事にしていると思ったんです。
なおさんだけではなく、ほっちのロッヂの働き手は、ケアを必要とする人の表現の芽に気づき、表現しようとする人の根っこを当たり前に支えているんです。
その人らしい表現はもちろん、そこに気づき支えることは、かけがえのない価値があります。でも、働き手自身がその価値に気づいていないケースも多々ある。あるいは環境によっては、潜在する表現がそもそも見過ごされている場合もあるのかもしれません。
私は、それらがかけがえのないものだと働き手が気づけば、そこで出会う人と共によろこべることが増えるんじゃないかと思っているんです。
自分の言葉を探し選ぶことも表現活動のひとつ
「症状や年齢、状態じゃなくって、好きなことをする仲間として出会おう」。ほっちのロッヂのコンセプトだ。
ほっちのロッヂの働き手であり、診療所の院長をつとめる坂井雄貴(さかい・ゆうき)さんは、このフレーズをみてほっちのロッヂで働きたいと考えたそう。家庭医としてキャリアを重ねてきた坂井さんには「病気でないと出会えない存在としての医者ではなくて、その人のありのままと向き合えるといい」という思いがあった。
ほっちのロッヂ企画のイベントに登壇した坂井さんは、日々のなかで大切にしているキーワードを次にように挙げている。
坂井:「好きなことする仲間として出会おうーー自分のやりたいを伝え、誰かのやりたいを支える。ケアする・されるではない関係ーー働き手も、まちの人も。人としての関わり、役割や属性で線を引かない。考えること、悩むことを諦めないーーまちの暮らしも、自分の求める暮らしも」
(ほっちのロッヂの働き手トーク#1 ドクターが地域で働くってどんなこと? 坂井さんのスライドより)
ここで惹きつけられるのは「誰かのやりたい」=「他者の表現」を一方的に支えるのではなく、「自分のやりたい」=「自分の表現」も伝え共に支え合おうとする姿勢だ。この姿勢はほっちのロッヂの働き手の言葉遣いにも表れていると藤岡さんは語る。
藤岡:働き手たちは、「訪問診療に行く」のではなく、「出会いに行く」という言葉を使っています。「患者さん」じゃなくて、〇〇さんと固有の名前で呼んでいますし、「お看取り」じゃなく「生きるを終える」と表現していて。
言葉のあらわし方で自分の気持ちが変わってくるし、次に出会うときの気持ちも違う。一緒に現場に居合わせる人たちとの対話のあり方も変わっていく。働き手をみていると、自分の言葉を探し、選ぶことも表現活動のひとつであり、文化を育んでいく具体的な行為なのだとあらためて感じます。

今抱えているものは、あなたひとりで抱えなければいけないわけではない
人の生き死にや暮らしを日々目の当たりにしている働き手。彼ら彼女らに余裕がなければ、自分の言葉を探し選ぶことそれ自体が難しいだろう。ほっちのロッヂではどのように環境を育んでいるのか。
藤岡:話すことが大事だと思うんです。働き手同士で共有できていないことを確認しあう。医師も看護師もタフな現場のなかで、出会う人のことばかり考えている。その結果、自身のことをおざなりにしてしまいやすくて。
「〇〇さんが」という視点で常に考えようとしているからこそ、それだけではなく「あなたはそのときどう思ったのか」も大切にしたい。そして一緒に悩む時間や場を大切にしたいと思っています。
自身の状態はどうなのか、今誰かとコミュニケーションを取りたいか、感情に蓋をしておきたいか、開けたいか。それは本人にしかわからないことかもしれない。でも本人だけに任せるのではなく一緒に悩みたい。
もしかすると今抱えているものは、あなたひとりで抱えなければいけないわけではないかもしれない。誰かと共有できれば楽になることもあるかもしれないから。


ほっちロッヂの働き手の一人菊池郁希(きくち・ゆき)さんにも話を聞いた。医療のサポートが必要な方の家をたずね、その人に必要なケアを行う「訪問看護」の活動を主に担っている。菊池さんはほっちのロッヂという環境を次のように言葉にしてくれた。
菊池郁希さん(以下、菊池):さまざまなことを話しながらいられる状態が日常になっています。でも外から来た人と話をすると、他の場所では当たり前ではないと気付かされることもあるんです。
だからこそ「こういう瞬間が良かった」「どう感じた」「どうしていきたい」というところをすぐ話して、積み重ねていくことは大事にしたいです。まだまだもっとやれることがいっぱいあるとは思っているんですけどね。

話す場や時間をもつこと。大切だと思えていても、限られた時間や人のなかで仕事をしていくと難しい場合もあるのではないか。
菊池:医療現場として効率的にやらなければならない状況もあるから、そこは闘いながらやってますね。効率によって削ぎ落とされてしまっているものがあると自覚しながら、どっちを取るか日々判断してやっている。
効率的に動くこと、一緒に悩む時間を大切にすること、どちらか片方だけを取ってすっきりさせればいいかというとそうじゃない。自分がどう思うのか、どうしたいのかを支えてもらえる環境だとは感じていて。あとは、そこからどうするかを考えていけばいいのかなと思っています。


アーティストと福祉の現場が出会うことで見つかる表現の芽
「在宅医療拠点」と「文化芸術」が交わる「ケアの文化拠点」を育もうとするほっちのロッヂ。藤岡さんは、「ケアの現場から立ち上がっていく光景や文化を一緒にみたい」と語る。そんな「ケアの文化拠点」を育む仕組みのひとつとしてあるのが「交換留藝」だ。
アーティストがほっちのロッヂに滞在し、医師や看護師、介護士や保育士として活動するほっちのロッヂの働き手と対話を重ねながら表現や創作を探る企画である。
藤岡:アーティストとケアの現場が出会うことで、そこにある表現の芽を見つけていけるんじゃないか。表現活動があることで、病気の状態や肩書き、所属などを普段とは違うものにずらして、個と出会うきっかけをつくれるんじゃないか、そう考えています。
ほっちのロッヂに滞在したアーティストが、そこで感じたこと受け取ったものをなんらかの形で発露する。そのとき、ケアの働き手も「ここで過ごしたことで、こんな情景や表現が立ち現れてくるのか」と驚きも生まれると思ったんです。
取材チームがほっちのロッヂをおとずれた時期は「交換留藝」の一環で、写真家 清水朝子(しみず・あさこ)さんの展示が行われている期間だった。

交換留藝のコーディネートを担う唐川恵美子(からかわ・えみこ)さんは、清水さんのプロジェクトがはじまったきっかけを次にように教えてくれた。
唐川恵美子さん(以下、唐川):看護師の菊池から「ほっちのロッヂの訪問看護では、他ではできないことをいろいろやっているねと周りから言われる。でも自分たちでは何が特殊なのかわからなくなっている。それだと自分たちが大切にしている考えや行動を広めていくのは難しいので、言語化・可視化していくことが必要だと思う」という話を聴いていました。
そこで自分たちの活動を見える化するために「写真」という手法が合うんじゃないかと思ったんです。働き手のなかにも普段から写真を撮る人はいますが、撮っている人自身のことは撮れない。なので、写真家さんならではの視点からほっちのロッヂを捉えてもらい、作品を通して私たちがフィードバックを得られる機会にできないかと考えました。

唐川:交換留藝のアーティストは、自ら応募してくれる場合と、私たちがお声がけする場合のどちらもあります。清水さんの場合は、わたしたちからオファーしました。当初は1ヶ月ほど滞在していただく予定だったのですが、実際のところ3ヶ月近くほっちのロッヂの現場と共ににいてくださいました。
結果的に、ミーティングやただのおしゃべり、外来診療、台所の様子、各イベント、アトリエ活動、訪問診療・訪問看護の活動、ガーデニングや畑仕事、軽井沢風越学園での教育連携など、ほっちのロッヂのさまざまな場面を撮影していただきました。
「交換留藝」で実際に生まれている影響をたずねると次のように話す。
唐川:ちゃぶ台を囲み、今の気分や、昨日あったことで情報共有しておきたいことなどを語る「朝タイム」があって。その流れで、撮ってもらった写真をみんなで眺めながら、「このときはこんなことを考えていた」というように語る機会が増えていたように思います。
また写真展が開催されている期間では、外来で来られた方の診療後に写真展を案内していることもありました。来てくださった方と写真を眺めながら「そういえば、ほっちのロッヂのみなさんはなんで私服を着ているんですか?」と聞かれて「暮らしを邪魔しないという姿勢からなんです」と答えるなど、写真を通して、ほっちのロッヂが大切にしていることを伝え、自分たち自身のあり方を見直すきっかけにもなっているんです。


清水さんの前には身体表現者の小林三悠(こばやし・みゆ)さんがプログラムに応募し、滞在していたという。そこで生まれたのが「クリエイティブ・カルテ」。小林さんの滞在期間中に、作品鑑賞や対話の時間を通して、ほっちのロッヂの働き手が小林さんのカルテを作成するという企画だ。小林さんのこれまでの活動や創作のあり方、これから挑戦してみたいことと、ほっちのロッヂの営みが出会い、企画が立ち上がっていった。

ケアの文化拠点を育むほっちのロッヂの活動は、交換留藝だけではない。表現活動としてさまざまな部活が存在する。たとえば、ほっちのロッヂの働き手が訪問看護活動を通して出会った、ヴォーカル教室を主宰されている方のご家族と一緒に立ち上げた「森とうたう部」もそのひとつ。
また、まちの子どもたちと創作活動を共にする「子どもアトリエ」という取り組みも定期的に開催しており、文化拠点として、さまざまな暮らしと共に多様な取り組みを地道に行っているのだ。
文化芸術と福祉の現場が出会うことで育めるものとは?(編集後記)
ここで「文化芸術と福祉の現場が出会うことで育めるものとは?」という最初の問いに立ち戻りたい。
取材中、「文化芸術」や「福祉」をどういうふうにとらえていますか、と藤岡さんにたずねると、次のように応えてくれました。
藤岡:定義的なものはあまり考えていないんです。ただ私が言えるのは、ものが立ち上がる瞬間って現場にしかないということです。
抽象的な定義よりも、目の前にある営み、現場にある実践と模索、そこで大切にされていることから考えたいし、共に考えてほしい。そんな想いを込めて伝えてくれたのだと感じています。
実際に、ほっちのロッヂの働き手の話を聞き、あの場で時間を過ごして、思ったことがありました。
ほっちのロッヂの実践のどれもが、共に生きる人たちの日々の暮らしのために存在しているということです。「交換留藝」をはじめとする文化企画も、働き手が自身の感じたことを大切にしようとする環境も、「ケアする・されるではない関係ーー働き手も、まちの人も。人としての関わり、役割や属性で線を引かない」という姿勢も、「ケアの文化拠点」を育むことも、「症状や状態、年齢じゃなくって、好きなことをする仲間として出会おう」という合言葉を掲げているのも。
そう考えると「文化芸術」と呼ばれるものも、「福祉」と呼ばれるものも手段は違えど「人と人が関わり、『幸せ』を支え合うためになにができるのか」を模索してきた、と言えるのかもしれません。
だとするならば、文化芸術と福祉の現場が出会うことで育めるものってなんなのでしょう? その答えは「福祉」や「文化芸術」の現場、その実践のなかで感じられるように思います。




Profile
![]()
-
藤岡聡子
福祉環境設計士
1985年生まれ、徳島県生まれ三重県育ち。長野県軽井沢町在住。夜間定時制高校出身。人材教育会社を経て24才で介護ベンチャー創業メンバーとして2010年に住宅型有料老人ホームを立ち上げ、アーティスト、大学生や子どもたちとともに町に開いた居場所づくりを実践。
出産を経て2014年より非営利団体「親の思考が出会う場」KURASOU.代表として、国内外のべ200名以上の親が政治や人権など暮らし方について学び対話する場を運営。
2015年デンマークに留学し、幼児教育・高齢者住宅の視察、
民主主義形成について国会議員らと意見交換を重ね帰国。
同年11月 株式会社ReDoを起業。
2016年より東京都豊島区椎名町にて、空き家だった場所を拠点に「しいなまちの茶話会」、「長崎二丁目家庭科室」を立ち上げ、町に住む高齢者から若者が知識・経験を学ぶ場所として0才から80代までのべ1000人が通う場を運営。
2018年から長野県軽井沢町にて、暮らしと医療を結びつける活動として「ほっちのお茶会」、「診療所と大きな台所があるところ ほっちのロッヂ」を医師と共同で立ち上げる。
Profile
![]()
-
ほっちのロッヂ
ケアの文化拠点
長野県軽井沢町の森の中に佇む。
「症状や状態、年齢じゃなくって、好きなことをする仲間として出会おう」という合言葉を掲げ、「ケアの文化拠点」を育む「大きな台所があるところ」。診療所であり、在宅医療の拠点であり、病児保育室や共生型通所介護、訪問看護ステーションなどの事業を担う場所。
訪問看護ステーションを「家に訪問したり、町全体の健康を考える活動のこと」と説明していたり、診療所を「内科、小児科、緩和ケア、在宅医療。自分の好きな暮らしを医療とともに考えるところ」、病児保育室を「親も子も、自分の回復力を信じて過ごせる場所のこと」、共生型通所介護・児童発達支援・放課後等デイサービスを「大きな台所、本棚、アトリエなどがある、町の人の居場所のこと」と表現している。
この記事の連載Series
連載:こここスタディ
![]() vol. 272025.04.18“家庭”ってなんだろう? 子どもと大人が尊重しあう場所を目指す、児童福祉施設「てらす峰夢」をたずねて
vol. 272025.04.18“家庭”ってなんだろう? 子どもと大人が尊重しあう場所を目指す、児童福祉施設「てらす峰夢」をたずねて![]() vol. 262024.12.06差別と関係のない立ち位置ってあるの? 社会のあり方に矢印を向けて考える
vol. 262024.12.06差別と関係のない立ち位置ってあるの? 社会のあり方に矢印を向けて考える![]() vol. 252024.12.06差別ってなんだろう? 現代社会における差別の研究者 阿久澤麻理子さんをたずねて
vol. 252024.12.06差別ってなんだろう? 現代社会における差別の研究者 阿久澤麻理子さんをたずねて![]() vol. 242024.08.14正しい答えを刷り込むのではなく、自分で選ぶ手助けをする「包括的性教育」とは?
vol. 242024.08.14正しい答えを刷り込むのではなく、自分で選ぶ手助けをする「包括的性教育」とは?![]() vol. 232024.07.31「性教育」という言葉から何を想像する? 教育学者 堀川修平さんによる「包括的性教育」解説
vol. 232024.07.31「性教育」という言葉から何を想像する? 教育学者 堀川修平さんによる「包括的性教育」解説![]() vol. 222024.07.17「創造性」はどう育まれる? ブルーノ・ムナーリの軌跡から──デザイナー、現代美術作家、教育者のまなざし
vol. 222024.07.17「創造性」はどう育まれる? ブルーノ・ムナーリの軌跡から──デザイナー、現代美術作家、教育者のまなざし![]() vol. 212024.03.30「個人の心の問題」の多くは環境や政治の問題でもある〜「あなたのため」というバウンダリーの侵害〜
vol. 212024.03.30「個人の心の問題」の多くは環境や政治の問題でもある〜「あなたのため」というバウンダリーの侵害〜![]() vol. 202024.03.26自分と他者を区別する境界線「バウンダリー」とは?ソーシャルワーカー鴻巣麻里香さんによる解説
vol. 202024.03.26自分と他者を区別する境界線「バウンダリー」とは?ソーシャルワーカー鴻巣麻里香さんによる解説![]() vol. 192024.02.01「昔好きだった作品」の表現に戸惑ってしまったら? フィクションが与える2つの影響──文学研究者・小川公代さん
vol. 192024.02.01「昔好きだった作品」の表現に戸惑ってしまったら? フィクションが与える2つの影響──文学研究者・小川公代さん![]() vol. 182023.12.15「合理的配慮」は「ずるい」「わがまま」なのか? インクルージョン研究者 野口晃菜さんによる解説
vol. 182023.12.15「合理的配慮」は「ずるい」「わがまま」なのか? インクルージョン研究者 野口晃菜さんによる解説![]() vol. 172023.04.21“できる/できない”の社会を「ヨコへの発達」で問い直す。社会福祉の父・糸賀一雄を、垂髪あかりさんが研究する理由
vol. 172023.04.21“できる/できない”の社会を「ヨコへの発達」で問い直す。社会福祉の父・糸賀一雄を、垂髪あかりさんが研究する理由![]() vol. 162023.02.08「やさしい日本語」ってなに? 言語学者・庵功雄さんに聞くコミュニケーションの本質
vol. 162023.02.08「やさしい日本語」ってなに? 言語学者・庵功雄さんに聞くコミュニケーションの本質![]() vol. 152023.01.27人を見た目で判断することって全部「差別」になるの? 社会学者 西倉実季さんと、“ルッキズム”について考える
vol. 152023.01.27人を見た目で判断することって全部「差別」になるの? 社会学者 西倉実季さんと、“ルッキズム”について考える![]() vol. 142023.01.16自分の気持ちを話さない自由がある。NPO法人ぷるすあるはと一緒に考えた“きもち”との付き合い方
vol. 142023.01.16自分の気持ちを話さない自由がある。NPO法人ぷるすあるはと一緒に考えた“きもち”との付き合い方![]() vol. 132022.12.14“障害”ってそもそも何だろう? 困難の原因を「社会モデル」から考える──バリアフリー研究者・星加良司さん
vol. 132022.12.14“障害”ってそもそも何だろう? 困難の原因を「社会モデル」から考える──バリアフリー研究者・星加良司さん![]() vol. 122022.11.29「ちゃんとしなきゃ」の呪いをとくには?福祉社会学者 竹端寛さん× 僧侶 松本紹圭さん
vol. 122022.11.29「ちゃんとしなきゃ」の呪いをとくには?福祉社会学者 竹端寛さん× 僧侶 松本紹圭さん![]() vol. 112022.10.27“ありのままの自分”を大切にするって、どういうことだろう? しょうぶ学園施設長 福森伸さんをたずねて
vol. 112022.10.27“ありのままの自分”を大切にするって、どういうことだろう? しょうぶ学園施設長 福森伸さんをたずねて![]() vol. 092022.09.07“健康”ってなんだろう?ケアの文化拠点「ほっちのロッヂ」紅谷浩之さんをたずねて
vol. 092022.09.07“健康”ってなんだろう?ケアの文化拠点「ほっちのロッヂ」紅谷浩之さんをたずねて![]() vol. 082022.08.12弱さは個人の問題ではなく、構造上の問題だ。公認心理師・臨床心理士 信田さよ子さんと考える“弱さ”のこと
vol. 082022.08.12弱さは個人の問題ではなく、構造上の問題だ。公認心理師・臨床心理士 信田さよ子さんと考える“弱さ”のこと![]() vol. 072022.07.28“違う“の不安をどう乗り越えればいい? グレーではない「色」で表現する発達の特性──星山麻木さん
vol. 072022.07.28“違う“の不安をどう乗り越えればいい? グレーではない「色」で表現する発達の特性──星山麻木さん![]() vol. 062022.04.12「私はどう生きたらいい?」を、一人で抱えない社会へ。医師・西智弘さんに聞く、地域活動と“ケア“の文化づくり
vol. 062022.04.12「私はどう生きたらいい?」を、一人で抱えない社会へ。医師・西智弘さんに聞く、地域活動と“ケア“の文化づくり![]() vol. 052022.03.22偏見がない人はいない。川内有緒さん×木ノ戸昌幸さん『わたしの偏見とどう向き合っていく?』イベントレポート
vol. 052022.03.22偏見がない人はいない。川内有緒さん×木ノ戸昌幸さん『わたしの偏見とどう向き合っていく?』イベントレポート![]() vol. 042022.02.04居場所・つながり・役割・生産性。「望まない孤独」をめぐる対談でみえたものとは?吉藤オリィさん×奥田知志さん
vol. 042022.02.04居場所・つながり・役割・生産性。「望まない孤独」をめぐる対談でみえたものとは?吉藤オリィさん×奥田知志さん![]() vol. 032021.10.26大切なものを失った悲しみや痛みと共に生きていくには? グリーフサポートが当たり前にある社会を目指す 尾角光美さんをたずねて
vol. 032021.10.26大切なものを失った悲しみや痛みと共に生きていくには? グリーフサポートが当たり前にある社会を目指す 尾角光美さんをたずねて![]() vol. 022021.06.24差別や人権の問題を「個人の心の持ち方」に負わせすぎなのかもしれない。 「マジョリティの特権を可視化する」イベントレポート
vol. 022021.06.24差別や人権の問題を「個人の心の持ち方」に負わせすぎなのかもしれない。 「マジョリティの特権を可視化する」イベントレポート![]() vol. 012021.04.15さまざまな側面をもつ「わたし」と「あなた」をそのまま大切にするには? 美学者 伊藤亜紗さんを訪ねて
vol. 012021.04.15さまざまな側面をもつ「わたし」と「あなた」をそのまま大切にするには? 美学者 伊藤亜紗さんを訪ねて