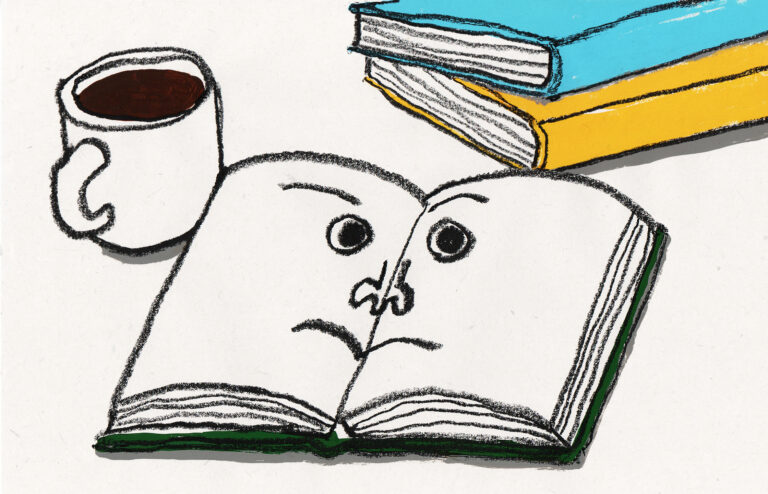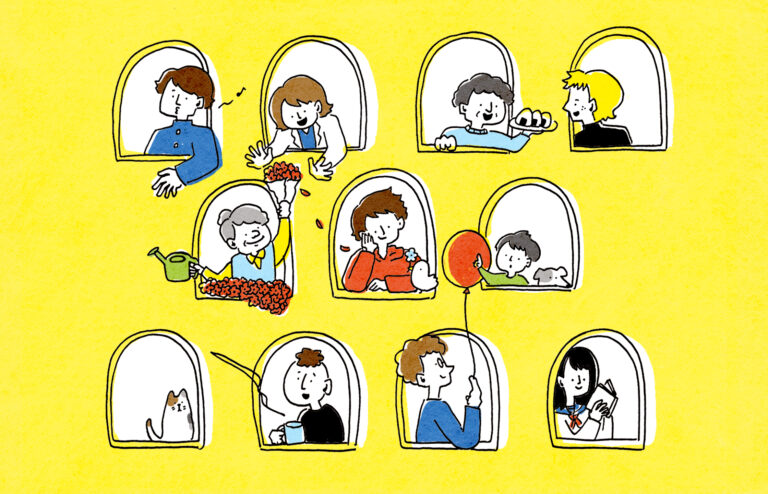専門家じゃないと安全な学びの場って作れないの? ワークショップファシリテーター 栗本敦子さんと考える こここスタディ vol.30
「安全な場は『不当に傷つけられない場』と言えるかもしれません」
こう語るのはFacilitator’s LABO えふらぼの主宰で、現在はフリーランスでワークショップのファシリテーターとして活動している栗本敦子さん。
前編では、栗本さんに「安全な学びの場」を育んでいくヒントを伺った。
【それぞれの安心を尊重できる「学びの場」ってどうすればつくれる?】の記事はこちら
安全な環境を支えるルールや差別的な発言・暴力的なふるまいが発生したときの対応など、一緒に考えていくなかで気づいたのは、「安全な学びの場」を作るには専門的な技術が必要ということだ。
後編では、専門家以外は安全な場をつくれないのか?という問いを入り口に、場の主催者・ファシリテーターのあり方やルールづくりの意味、学びと居心地の悪さの関係を栗本さんと考えてみたい。
専門家以外も安全な学びの場ってつくれる?
専門家でなければ「安全な学びの場」をつくるのは難しいのではないか? 栗本さんに伝えると、そうとも限らないという。
栗本敦子さん(以下、栗本):誰もができるものだというのも、すごく大事だと思うんです。私も誰もができるものだと思っています。やらないとできるようにならない側面もあるじゃないですか。なので、あまりハードルを上げたくはないんですよね。
確かに、誰もが取り組めるものであることは重要だ。安全に学べる環境をつくる人が増えれば増えるほど、そういった環境が増えていく。それぞれの場で安全を尊重するために必要な知見や創意工夫が生まれ、そこに出会った人がさらに、違う環境を育んでいけるだろう。
栗本:難しいのは事実です。やっていく中で、自分がまちがえたことに気付き、それを振り返り、試行錯誤することは、常に求められるのかもしれません。
話を聞きながら、完璧な学びの場において「決して失敗をしてはいけない」「参加者に明快な答えを差し出さなければいけない」と、どこかで思い込んでいた自分に気づく。
栗本:ファシリテーターは、答えではなく、問いを作る人です。
私自身は、ワークショップは参加者にモヤモヤしてもらって終わりたいと考えています。その場でスッキリして終わりではなく普段から考え続けてほしい。ただ参加者がどう受け取るのか正直わかりません。モヤモヤを感じた人が、そのあと考え続けてくれるのか、せっかく行ったけど微妙だったと思ってしまうのか。受け取り方まで細かくコントロールしたくなってしまうこともあるけれど、手放さなきゃいけない。わたしもいつも葛藤していますし、「あのときどうすればよかったのだろう」とモヤモヤを自分の中で反芻したり、「守秘」のルールを守りつつ、特定されないように同業者の仲間と話をしたりすることもあります。
だからこそファシリテーター自身が学ぶことに開かれていることが大事だと思うんです。「自分は“ちゃんと”やってます」と思わないというか。
主催者・ファシリテーターはある種のパワーをもっている
学ぶことに開かれている。自分は“ちゃんとやってます”と思わないこと。それは自身のまちがいや課題に対しての指摘を真摯に受け止めることでもあるだろう。
栗本さん自身も、過去に行った講座の中で、自身の言葉遣いに対して、参加者から「指摘」を受けたことがあるそう。
栗本:ある講座の中で「障害をもつ人」という表現を使っていました。講座が終わってから、参加者に「その人が障害を選んでもっているわけではないから、わたしは『障害のある』という言い方をしています」と伝えてもらったんです。わたしは「そうなんですね」「知り合いでも『もつ』と使っている人もいるので」と自分を正当化するような返答をしました。その時は「もつ」でも「ある」でも大差ないと思っていたんです。
振り返ると、よくわかっていないことから逃げてしまったという感覚がありました。
その後、社会モデル(※注1)を学び、確かに「もつ」ではない、と思うようになって。やっぱりそういうのは、結構年数が経っても覚えています。
※注1 社会モデルとは、「心身機能に制約がある人々にとって、環境に適合しづらい状況を社会の側が生み出していること」を、障害と捉える概念だ。心身機能に制約があるゆえに生活に困難があるわけではなく、環境や制度、世間の価値観など社会を構成しているものが、その人の生活を困難にさせている、と考える。参考はこちら
「言ってくださって、すごくありがたかったです」と栗本さんは続ける。
栗本:そのときは言ってもらえましたけど、指摘しても無駄だとか、ハードルが高くて指摘できないと感じている方もいるはずです。その場合、こちらのまちがいに気付かないまま過ぎてしまう。その可能性を認識していないと、危ういですよね。
場の主催者やファシリテーターは、ある種の権力をもっている側だ。どのような場にするか、どんな思惑をもって場を開くのか、そのために何を用意しておくのか、土台となる要素を選び、事前に準備しておくことができる。いち参加者の立場からみると、この場において「情報量を多くもっている人」「正解を知っている人」「権限をもっている人」というイメージも強いだろう。
その立場を自覚しないと、見逃してしまうものが多くある気がする。ファシリテーターの期待や思惑、その場を肯定する意見は表明しやすく、そこから外れると感じてしまうもの、ファシリテーターのまちがいや場の問題を指摘する発言はハードルが高い。その前提を踏まえて場をつくる必要がありそうだ。だからこそ、安全な学びの場をつくろうとする人自身が「学ぶことに開かれている」のは大切なのかもしれない。
人格でファシリテーターをやってはいけない? 必要なスキルや場のルールの意義とは
栗本:ファシリテーターは「人格」でやってはいけない。「スキル」として出すことが大事だと思うんです。共有したいのが西田真哉さんが提示した「ファシリテーターであるために望ましい条件」です。これらは、安全な学びの場づくりのヒントになるかもしれません。
① 主体的にその場に存在している。
② 柔軟性と決断する勇気がある。
③ 他者の枠組みで把握する努力ができる。
④ 表現力の豊かさ、参加者への反応の明確さがある。
⑤ 評価的な言動は慎むべきとわきまえている。
⑥ プロセスへの介入を理解し、必要に応じて実行できる。
⑦ 相互理解のための自己開示を率先できる、開放性がある。
⑧ 親密性、楽天性がある。
⑨ 自己の間違いや知らないことを認めることに素直である。
⑩ 参加者を信頼し、尊重する。
(『ワークショップ ー新しい学びと創造の場ー』岩波新書、著:中野民夫)
栗本さんは、ファシリテーター向けの研修を担うこともある。「ファシリテーション」がテーマの研修を行う場合、その場におけるルールを一緒に考えてみるそうだ。
栗本:「今日一緒に学びの場を作るために、あったらいいなという心がけやルール」を出してもらいます。それを出したうえで、「自分たちでルールを作ることには、どんな意味があるか」尋ねるんです。後者は「自分たちで作ったからこそ守ろうと思える」とか、「自分たちで作ったからこそ、これは違うなと思ったら変えることができる」みたいな意見が出たりします。
そこで「人権」についてふれることもあります。今の社会には、さまざまな価値観、違いのある人がいて、その人たちが共に生きていくためのルールとしてつくられてきたものが人権。人が時間をかけて獲得し、蓄積し、見える形で整理してきたもの。ルールづくりのプロセスと人権がつくられた根っこの部分は一緒なのかもしれませんよね、と。
この話を聞きながら、文学紹介者の頭木弘樹さんの言葉を思い出した。「オープンダイアローグ」におけるルールに対し「がんじがらめにされる」感覚を抱いていた頭木さんが、ルールに慣れていく中での気づきを述べている部分だ。
「オープンダイアローグのルールになれてくると、『これは素晴らしいぞ!』とだんだん感じるようになっていった。そして、それと同時に、初めて気づいたのが、『これまでの日常の会話がいかに危険なものであったか』ということだった」
「日常の会話にはルールがない。自由な代わりに、ある種の無法地帯だ。傷つけるかもしれないし、傷つけられるかもしれない。 いや、ルールがなくて自由というのは、正確ではない。じつは日常の会話には暗黙のルールがたくさんある」
「オープンダイアローグは、暗黙のたくさんのルールの代わりに、ルールを表に出し、明確にし、数を減らして単純化している。しかし、誰も傷つかないルールになるように配慮してある」
(『専門家なしでやってみよう! オープンダイアローグ――安全な対話のための実践ガイド』晶文社、著:石田月美 頭木弘樹 鈴木大介 樋口直美)
栗本さんの話、頭木さんの文章にふれて思う。誰かを押さえつけたり、権利を奪ったりするためではなく、「暗黙のルール」や「見ている景色」が異なる他者を尊重したり、やみくもに傷つけたりすることを避けるためにルールを使う。そうすることで、特定の「個人」や「人格」に依存しない「安全な学びの場」づくりができるのかもしれない。オープンダイアローグは「安全な対話」におけるルールのため、文脈が異なる点は留意しておきたいが、そこから学べることも多くありそうだ。
安全と居心地の悪さは両立する?
今回の取材テーマを伝えたとき、栗本さんから「場の安全」にまつわるテキストを共有いただいた。そこにはアメリカの多様性教育トレーニングに栗本さんが参加したときのことが綴られている。
わたしがワークショップのはじめに、話し合いのルール作りをするときにも、「安心」にかかわる項目の提案が必ず参加者からでてきます。「意見を否定しない」「相手を批判しない」「肯定する」…。どれも大事だと思う一方、このルールで話し合いを深めることが出来るだろうか、ということも気になっていました。
今年の夏に、アメリカの多様性教育のトレーニングに参加した際、この疑問をトレーナーに尋ねてみました。すると、「Safe(安全)な環境にすることは大切だが、Comfortable(心地よい状態)にする必要はない」という明快な答えが返ってきました。
「新しいことを学ぶ過程では、これまでのあり方をふりかえり、変えていくことも必要になってくる。それは、Comfortable(心地よい状態)ではないだろう。けれど、自分を問われることなく、深く学ぶことはできるだろうか。もちろん、Safeは保障する必要はある。けれど、参加者には、研修の中でUn-Comfortableな(居心地の悪い)状態を Comfortableだと受け止められるようになってもらいたい」
このテキストを読んだとき、「安全(safe)」と「心地よさ(Comfortable)」を混同していると気づいた。学びの場において、安全で居心地の悪い環境は存在するし、むしろその視点を忘れないことが重要な気がする。
栗本:人権や差別の問題に向き合うとき、居心地よく学べている状態は、本当に学べているのだろうか、と思うことがあります。自分自身が問われる状態は、大なり小なり居心地はよくないと思うんですよね。
人権や差別、ハラスメントやマイクロアグレッションがテーマのワークショップを栗本さんが担当するとき「いや、こんなこと言われちゃったら何も言えなくなってしまう……」と懸念を示す人もいるそう。
栗本:そこで優先するのは、誰かの安全が脅かされていないか、ということです。
この場に、差別や偏見にさらされながら生きざるをえない人がいるかもしれない。出た質問や発言、ふるまいによって、その人がしんどさを感じたり、傷ついてしまうことは避けたい。そこを何より優先にします。
今まで差別や暴力、ハラスメントの問題に気づかずに来れた立場の人、多くの場合いわゆる「マジョリティ性」の高い人の居心地の悪さをなんとかしようとはあまり思わないです。ただ、マジョリティ性が高いように一見思える人も、実は表面に出したくないような何かをもっている可能性はもちろんあります。
参加者がなぜその発言やふるまいをしたのか、どんな事情や背景を抱えているのか。各々の水面下でうごめいているものを把握することはできない。その場で伝えたいと思えるかどうかも、参加者が置かれている状況によって異なるだろう。
栗本:常に安全な環境を充分につくれているか問われると、わかりません。わたしが気付けていないようなマイノリティ性をもつ人もいるかもしれない。すべての人に“完璧な安全を”担保するのはとても難しい。差別や暴力、ハラスメントといった問題を“可能な限り最小化する”ために、試み続けるしかないんです。
タバブックスが出版したZINE『セーファースペース』で、社会福祉学者である堅田香緒里さんは「セーファースペース」の要を二つ紹介している。
第一に、「セーフ( safe)」ではなく「セーファー( safer)」を目指している、という点。ここで、「安全な( safe)」ではなく「より安全な( safer)」という形容詞が用いられている背景には、すべての人がいつでも安心できるような完全に「安全」な空間は存在しないという認識がある。しかし、だからといって、「じゃあ、無理だ」と諦めてしまうのではなく、それでも「より安全な」空間を共同して作り続けていくということが大事なのであり、それは終わりのないプロセスだといえよう。
第二に、セーファースペースとは、全体から隔離された「部分」として設けられるような「避難所」や「駆け込み寺」のような場所ではない、という点。つまりそれは、たとえば女性専用車両のように、「より安全な空間」を全体(の車両)と区別して部分的に設けるということではなく、すべての車両を「より安全な」空間にしていく、そのための挑戦であるということだ。(『セーファースペース』タバブックス、編著:皆本夏樹+gasi editorial)
「“可能な限り最小化する”ために、試み続けるしかない」と栗本さんは伝えてくれた。それは、学びの場だけに限った話ではなく、社会に存在する差別や暴力に対して向き合うときにも通ずる。そう考えると専門家だけではなく、さまざまな人が「安全な学びの場」をつくろうとすることはとても大切なことだ。
学びの場にある筋肉痛と居心地の悪さ
専門家ではなくても、「安全な学びの場」はつくっていける。ただし、常に学びに開かれている状態を求められる。別の言い方をすると、自分に生じる「居心地の悪さ」も受け止める必要がある。それは一朝一夕でできるものではなさそうだ。
栗本:『これからの社会を生きていくための人権リテラシー』のあとがきにも書いてあるんですが、学びというのは、マッサージを受けて癒されるような場ではなく、筋トレみたいなものなんですよね。
中には癒やしを目的としたワークショップもあるのかもしれない。けれども、少なくとも学習を意図したワークショップというのは、適度に負荷があって、多少筋肉痛になるぐらいでないと、筋肉はつかないとは思っています。その筋肉痛のようなものが居心地の悪さ(Uncomfortable)のイメージなんです。
「安全な場」をつくるのであれば、適度な負荷や筋肉痛的な居心地の悪さは必要としないのかもしれない。安全な環境であること、それぞれが安全に過ごせることが何より大切だからだ。ただ、「学びの場」においては、「安全」と「学び」というふたつの側面が求められる。
栗本:学びの場やその過程で居心地のよさや癒しを得られることもあるかもしれません。でも、それは目的ではないと思っています。
居心地のよさや癒しが目的ではない。ただ「学びの場」だから「安全」を脅かしてもいいということでも決してない。そんなことを考えていると、栗本さんはある危険性について教えてくれる。
栗本:居心地がいいけど安全じゃない場と出会ってしまうこともあり得ますよね。それはとても危険だと思います。
ワークの場って参加者に適度に負荷がかかるので、あえて強い葛藤を生じさせて、それを解決する鍵をファシリテーターが投げるという構造をつくると「〇〇さんはすごい」と思わせることができる。
「操作する」という英語の「manipulate」とファシリテート(facilitate)をくっつけた、「ファシュピレート(facipulate)」という言葉もあります。参加者を尊重してファシリテートしたように見せかけて、実際は操作する、という意味です。ファシリテーションのテクニックは決して悪用してはいけないんです。
「専門家でなくても安全な学びの場は作れるのだろうか……?」ということを考えながら、栗本さんにお話を聞き、原稿を執筆してきた。印象に残っているのは、「やっていく中で、自分がやらかしたことに気付き、それを振り返り試行錯誤することは、常に求められるのかもしれない」という言葉だ。
場を作ろうと思うと、最初から自分自身に完璧さを求めてしまうのは、自然なことな気もする。自分が主催する場では、参加者が不当に傷つくことのない、安全な状態で学びを深めてほしい。ただ、もし主催者が完璧を求めて、少しの失敗も許されないと思っていたら、その空気感は参加者にも伝わってしまうのではないか、とふと思った。その空気感は、果たして「安全」なのだろうか。
ここで、「セーファースペース」という考え方をもう一度参照したい。すべての人がいつでも安心できるような完全に「安全」な空間は存在しない。それでも「より安全」な空間を共同して作り続けていく。
この考え方は、場を作る主催者にも適応されるのではないだろうか。最初から完璧に安全な場を用意することは難しいかもしれない。人は、完璧ではないからだ。ただ、場を作っていく中で、都度振り返り、参加者の声を聞き、「より安全」な学びの場を作っていくことは可能だろう。そして、それこそが、安全な学びの場を作るための、1番の近道なのではないかとも思うのだ。
前編記事:それぞれの安心を尊重できる「学びの場」ってどうすればつくれる?はこちら
Profile
![]()
-
栗本敦子
Facilitator’s LABO 〈えふらぼ〉
市民団体の事務局職員を経て、現在はフリーランス。ワークショップ(参加型学習)のファシリテーターとして活動。行政・企業・各種法人の人権研修・ハラスメント研修、市民対象の各種講座などの講師、高校・短大・大学でジェンダーや性の多様性、人権やダイバーシティとをテーマとした授業の非常勤講師をつとめる。研修でのおもなテーマは、ジェンダー(性暴力)、人権、コミュニケーション(アサーション)、など。ファシリテーター育成などの担い手養成や教材・プログラムづくりにもとりくむ。
この記事の連載Series
連載:こここスタディ
![]() vol. 292026.02.04それぞれの安心を尊重できる「学びの場」ってどうすればつくれる? ワークショップファシリテーター栗本敦子さんと考える
vol. 292026.02.04それぞれの安心を尊重できる「学びの場」ってどうすればつくれる? ワークショップファシリテーター栗本敦子さんと考える![]() vol. 282025.09.22「男らしさ」で誰かを傷つけたくない、どうすれば? 文筆家、教育学者、写真家、編集者によるおすすめの本
vol. 282025.09.22「男らしさ」で誰かを傷つけたくない、どうすれば? 文筆家、教育学者、写真家、編集者によるおすすめの本![]() vol. 272025.04.18“家庭”ってなんだろう? 子どもと大人が尊重しあう場所を目指す、児童福祉施設「てらす峰夢」をたずねて
vol. 272025.04.18“家庭”ってなんだろう? 子どもと大人が尊重しあう場所を目指す、児童福祉施設「てらす峰夢」をたずねて![]() vol. 262024.12.06差別と関係のない立ち位置ってあるの? 社会のあり方に矢印を向けて考える
vol. 262024.12.06差別と関係のない立ち位置ってあるの? 社会のあり方に矢印を向けて考える![]() vol. 252024.12.06差別ってなんだろう? 現代社会における差別の研究者 阿久澤麻理子さんをたずねて
vol. 252024.12.06差別ってなんだろう? 現代社会における差別の研究者 阿久澤麻理子さんをたずねて![]() vol. 242024.08.14正しい答えを刷り込むのではなく、自分で選ぶ手助けをする「包括的性教育」とは?
vol. 242024.08.14正しい答えを刷り込むのではなく、自分で選ぶ手助けをする「包括的性教育」とは?![]() vol. 232024.07.31「性教育」という言葉から何を想像する? 教育学者 堀川修平さんによる「包括的性教育」解説
vol. 232024.07.31「性教育」という言葉から何を想像する? 教育学者 堀川修平さんによる「包括的性教育」解説![]() vol. 222024.07.17「創造性」はどう育まれる? ブルーノ・ムナーリの軌跡から──デザイナー、現代美術作家、教育者のまなざし
vol. 222024.07.17「創造性」はどう育まれる? ブルーノ・ムナーリの軌跡から──デザイナー、現代美術作家、教育者のまなざし![]() vol. 212024.03.30「個人の心の問題」の多くは環境や政治の問題でもある〜「あなたのため」というバウンダリーの侵害〜
vol. 212024.03.30「個人の心の問題」の多くは環境や政治の問題でもある〜「あなたのため」というバウンダリーの侵害〜![]() vol. 202024.03.26自分と他者を区別する境界線「バウンダリー」とは?ソーシャルワーカー鴻巣麻里香さんによる解説
vol. 202024.03.26自分と他者を区別する境界線「バウンダリー」とは?ソーシャルワーカー鴻巣麻里香さんによる解説![]() vol. 192024.02.01「昔好きだった作品」の表現に戸惑ってしまったら? フィクションが与える2つの影響──文学研究者・小川公代さん
vol. 192024.02.01「昔好きだった作品」の表現に戸惑ってしまったら? フィクションが与える2つの影響──文学研究者・小川公代さん![]() vol. 182023.12.15「合理的配慮」は「ずるい」「わがまま」なのか? インクルージョン研究者 野口晃菜さんによる解説
vol. 182023.12.15「合理的配慮」は「ずるい」「わがまま」なのか? インクルージョン研究者 野口晃菜さんによる解説![]() vol. 172023.04.21“できる/できない”の社会を「ヨコへの発達」で問い直す。社会福祉の父・糸賀一雄を、垂髪あかりさんが研究する理由
vol. 172023.04.21“できる/できない”の社会を「ヨコへの発達」で問い直す。社会福祉の父・糸賀一雄を、垂髪あかりさんが研究する理由![]() vol. 162023.02.08「やさしい日本語」ってなに? 言語学者・庵功雄さんに聞くコミュニケーションの本質
vol. 162023.02.08「やさしい日本語」ってなに? 言語学者・庵功雄さんに聞くコミュニケーションの本質![]() vol. 152023.01.27人を見た目で判断することって全部「差別」になるの? 社会学者 西倉実季さんと、“ルッキズム”について考える
vol. 152023.01.27人を見た目で判断することって全部「差別」になるの? 社会学者 西倉実季さんと、“ルッキズム”について考える![]() vol. 142023.01.16自分の気持ちを話さない自由がある。NPO法人ぷるすあるはと一緒に考えた“きもち”との付き合い方
vol. 142023.01.16自分の気持ちを話さない自由がある。NPO法人ぷるすあるはと一緒に考えた“きもち”との付き合い方![]() vol. 132022.12.14“障害”ってそもそも何だろう? 困難の原因を「社会モデル」から考える──バリアフリー研究者・星加良司さん
vol. 132022.12.14“障害”ってそもそも何だろう? 困難の原因を「社会モデル」から考える──バリアフリー研究者・星加良司さん![]() vol. 122022.11.29「ちゃんとしなきゃ」の呪いをとくには?福祉社会学者 竹端寛さん× 僧侶 松本紹圭さん
vol. 122022.11.29「ちゃんとしなきゃ」の呪いをとくには?福祉社会学者 竹端寛さん× 僧侶 松本紹圭さん![]() vol. 112022.10.27“ありのままの自分”を大切にするって、どういうことだろう? しょうぶ学園施設長 福森伸さんをたずねて
vol. 112022.10.27“ありのままの自分”を大切にするって、どういうことだろう? しょうぶ学園施設長 福森伸さんをたずねて![]() vol. 102022.09.27「福祉の現場」と「芸術」の根っこには通ずるものがある? 福祉環境設計士 藤岡聡子さんをたずね、「ケアの文化拠点」ほっちのロッヂへ
vol. 102022.09.27「福祉の現場」と「芸術」の根っこには通ずるものがある? 福祉環境設計士 藤岡聡子さんをたずね、「ケアの文化拠点」ほっちのロッヂへ![]() vol. 092022.09.07“健康”ってなんだろう?ケアの文化拠点「ほっちのロッヂ」紅谷浩之さんをたずねて
vol. 092022.09.07“健康”ってなんだろう?ケアの文化拠点「ほっちのロッヂ」紅谷浩之さんをたずねて![]() vol. 082022.08.12弱さは個人の問題ではなく、構造上の問題だ。公認心理師・臨床心理士 信田さよ子さんと考える“弱さ”のこと
vol. 082022.08.12弱さは個人の問題ではなく、構造上の問題だ。公認心理師・臨床心理士 信田さよ子さんと考える“弱さ”のこと![]() vol. 072022.07.28“違う“の不安をどう乗り越えればいい? グレーではない「色」で表現する発達の特性──星山麻木さん
vol. 072022.07.28“違う“の不安をどう乗り越えればいい? グレーではない「色」で表現する発達の特性──星山麻木さん![]() vol. 062022.04.12「私はどう生きたらいい?」を、一人で抱えない社会へ。医師・西智弘さんに聞く、地域活動と“ケア“の文化づくり
vol. 062022.04.12「私はどう生きたらいい?」を、一人で抱えない社会へ。医師・西智弘さんに聞く、地域活動と“ケア“の文化づくり![]() vol. 052022.03.22偏見がない人はいない。川内有緒さん×木ノ戸昌幸さん『わたしの偏見とどう向き合っていく?』イベントレポート
vol. 052022.03.22偏見がない人はいない。川内有緒さん×木ノ戸昌幸さん『わたしの偏見とどう向き合っていく?』イベントレポート![]() vol. 042022.02.04居場所・つながり・役割・生産性。「望まない孤独」をめぐる対談でみえたものとは?吉藤オリィさん×奥田知志さん
vol. 042022.02.04居場所・つながり・役割・生産性。「望まない孤独」をめぐる対談でみえたものとは?吉藤オリィさん×奥田知志さん![]() vol. 032021.10.26大切なものを失った悲しみや痛みと共に生きていくには? グリーフサポートが当たり前にある社会を目指す 尾角光美さんをたずねて
vol. 032021.10.26大切なものを失った悲しみや痛みと共に生きていくには? グリーフサポートが当たり前にある社会を目指す 尾角光美さんをたずねて![]() vol. 022021.06.24差別や人権の問題を「個人の心の持ち方」に負わせすぎなのかもしれない。 「マジョリティの特権を可視化する」イベントレポート
vol. 022021.06.24差別や人権の問題を「個人の心の持ち方」に負わせすぎなのかもしれない。 「マジョリティの特権を可視化する」イベントレポート![]() vol. 012021.04.15さまざまな側面をもつ「わたし」と「あなた」をそのまま大切にするには? 美学者 伊藤亜紗さんを訪ねて
vol. 012021.04.15さまざまな側面をもつ「わたし」と「あなた」をそのまま大切にするには? 美学者 伊藤亜紗さんを訪ねて