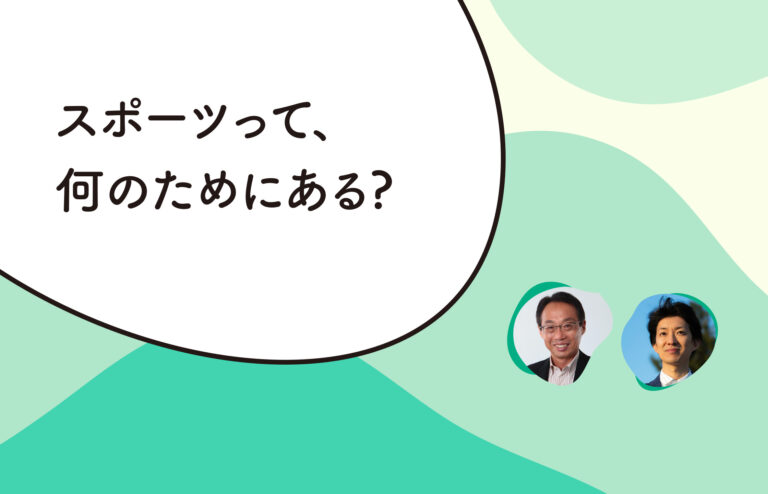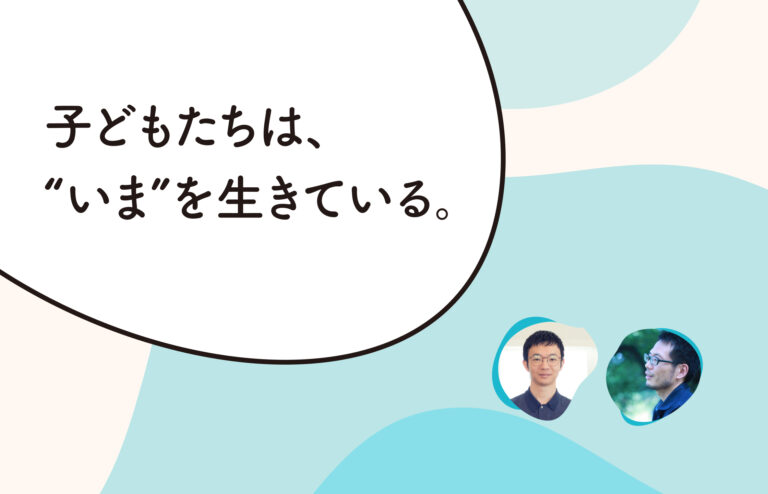だれもが文化でつながるために。クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョーが見据えるこれからの文化施設のあり方とは。 こここインタビュー vol.23
美術館や劇場の気になるプログラムを探し、情報を調べて会場を訪れ、アート作品や舞台を楽しむ。普段、多くの人々が芸術文化にあたりまえのようにアクセスできる一方で、「あたりまえにアクセスできない人たち」もまた数多く存在する。
乳幼児から高齢者、障害のある人もない人も、そして海外にルーツを持つ人たちも。だれもが文化施設やアートプログラムと出会えるように、芸術文化へのアクセシビリティ向上に取り組むプロジェクトが動き出している。「Creative Well-being Tokyo /クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョー」(以下「CWT」)。東京都が主導する「東京文化戦略2030」の一環として2021年に発足したプロジェクトだ。
このプロジェクトを統括するのは、公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京 事業部事業調整課長の森司(もり・つかさ)さん。これまで、地域の担い手とともにアートプロジェクトの拠点をつくる「東京アートポイント計画」や、異なる背景を持つ人たちが出会い・共創する「TURN」のプロジェクトディレクターを歴任してきた知見を活かし、CWTの進行役を担っている。
合理的配慮の提供の義務化や東京2025デフリンピックの開催をはじめ、国内外で「だれもが共に生きる社会の実現」への取り組みが加速する中で、CWTはどのような意義を持ち、どのような活動を行なっているのか。そして、文化施設とアートプログラムのあり方はどのように変わっていくのだろうか。森さんの視点から話をうかがった。
芸術文化はだれのもの?ウェルビーイングの視点から文化施設を問い直す
「誰一人取り残さない(leave no one behind)」。これはSDGsが2030年のアジェンダに掲げる理念だ。この言葉は共生社会の実現を目指す世界各地のアクションの指針となり、東京都でも「東京文化戦略2030」の「誰もが文化でつながるプロジェクト」が始動。文化的にも理念に向かい活動していく機運がここ数年で一気に高まった。
2019年に国際博物館会議(ICOM)が提出したミュージアムの定義案が議論を呼んだことも記憶に新しい。そこでは、過去や未来についての批評的な対話を行うために、ミュージアムはあらゆる人々を迎え入れ、多様な声に耳を傾ける空間であることが示された。これまでの役割から、社会に開かれた場に移り変わることを記した内容は、世界各地の文化施設が社会的役割を再考するきっかけとなった。
こうした国内外の流れを汲み、社会的な要請に応える形でCWTは発足した。

芸術文化をすべてのひとへー。この壮大なプロジェクトの根底には、「尊厳」の問題があると森さんは話す。
文化を享受する権利の前に、人としての尊厳の問題なんです。マジョリティの人たちを前提とした社会設計であるがゆえに、これまで文化施設を利用するユーザー像としてインビジブル(見えない存在)にされてきた人たちがいる。それが文化施設にも問われるようになりました。
とはいえ、実はこの問題は過去50年にわたって議論されてきたことでもあるそうだ。
障害のある人に対するアクセシビリティをどうするか。この問題に対する各館の活動やプログラムはゼロではなかったんです。ただ、それが体系立っていなかったり、ニーズに対してボリュームが足りなかったりと、様々な課題がありました。これからは、アクセシビリティへの意識が高いスタッフだけではなくて、東京都歴史文化財団が一丸となってこの問題に取り組んでいく。その姿勢を明確に打ち出したのがCWTです。

CWTの重要なポイントの一つは「ウェルビーイング」を掲げていることだ。「ウェルビーイング」は、文字通り“Well=良い”と“Being=状態”を表し、身体的、精神的、社会的に満たされている状態を指す言葉。その人の尊厳が保たれている状態であり、人や社会とつながりを感じながら過ごせているということである。
どういう場所がウェルビーイングなのか。ウェルビーイングな状態を文化がつくることはできるのか。CWTのプロジェクトはそうした問いでもあるんです。
事業の全体図を俯瞰する
CWTの事業は、主に「環境を整える」「プログラムを開発する」「ネットワークを築く」の3つに分類される。障害の有無や年齢にかかわらず、あらゆる人が芸術文化に出会い、参画できるような環境をつくること。国内外の文化施設と連携し、社会的な課題と向き合いながら、様々な人に必要とされるプログラムを作成すること。そして、アクセシビリティに関する取り組みを展開する文化施設や担い手などとのネットワークを築き、情報を共有・発信すること──。
もう少し細分化すると、以下の4つの取り組むべき要素がある。
- 都立文化施設・文化事業の環境・体制整備
- 調査・検証・開発
- 国内外の発信・ネットワークの醸成
- 関連事業の実施
誰も取り残されない文化施設をつくる。もちろんそれは理想だが、達成は一筋縄ではいかない。
今はまだ、初期段階の準備がやっと一定レベルの形になったところです。プロジェクトの目標達成までには長い道のりがあります。これからチーム全体で育てていかなければいけません。
森さんは現状についてそう言葉を重ねた。CWTは、2030年までに「あらゆる人が芸術文化を楽しめる共生社会が実現する」ことを目指して、取り組みを進めている。
鑑賞をサポートするだけでは不十分。「来るまで」と「来たあと」の環境を整える
では、CWTは具体的にどのようにプロジェクトを進行しているのだろうか。まずは事業の1本目の柱である「環境を整える」から見ていこう。
CWTが昨年取り組んだのは、ガイドラインの策定を見据えて財団内資料として制作した冊子「アクセシビリティ整備についての考え方」(2023年度版)だ。この冊子には、様々な特性を持つ人が文化施設や文化事業にアクセスする際に配慮すべきことが特性ごとにまとめられている。さらにはこれにもとづき、2025年までに都立文化施設が国内トップレベルのアクセシビリティを実現するための3か年計画の策定に着手した。
計画を実行するにあたり、CWTはアクセシビリティを3つの段階に整理した。利用者に情報を届ける「情報サポート」、文化施設で作品を楽しむための「鑑賞サポート」、そして障害等の当事者がプログラムに主体的に参画するための「参画サポート」。この区分けにより、それぞれの文化施設が共通の認識のもとでアクセシビリティ向上に取り組めるようになったことが、CWTの成果の一つだと森さんは話す。
目が見えない人や耳が聞こえない人は、文化施設の情報を入念にリサーチしてから来る方も多いです。どんなプログラムをやってるんだとか、どう楽しめるんだとか、トイレはどこだとか。事前の情報がしっかりしていないと安心して楽しむことはできないし、そもそも行こうと思わないかもしれません。だからこそ情報サポートが必要なんです。

CWTは現在、障害のある人のウェブアクセシビリティ向上のため、都立文化施設のホームページの見直しを行っている。だれもが同時に・同じ情報にアクセスできる状態を実現するため、当事者とともに検証を重ねるのだ。
さらに、「環境を整える」取り組みの一環として、緊急時の対応も進められている。現在はワークショップとリサーチをもとに災害バンダナや指差しで情報を伝えるコミュニケーションシートなど、ツールの開発に着手している。バリアフリー対応が十分ではない構造の建物において、非常時に車椅子の人が階段をどう降りるか、防災チームとどう連携していくかなど、多様な特性の人を受け入れるために対応すべき課題は多い。
東京都の文化施設の場合、比較的駅に近い場所が多いので、避難場所になるケースもあります。そうした状況も想定しながら、見直しを進めている段階です。


どんなに質の高い鑑賞のサポート機器やプログラムをつくったとしても、その情報を得る機会がなかったり、鑑賞の環境が安全でなければ、障害のある人は文化施設に足を運ぼうと思わないだろう。ホームページのアクセシビリティは? 緊急時の対応は? これまであたりまえだと思っていた環境を見つめ直すことから、CWTのアクションは始まる。
まず当事者に会う。ひとりよがりではないプログラム開発のために
次に、CWTの2本目の柱である「プログラム開発」について見ていこう。
「共に生きる社会」を目指すプロジェクトによくある落とし穴は、取り組みが一方向的になってしまうことだ。「だれもが文化でつながる」ことを掲げるCWTは、プログラムをどのように開発しているのだろうか。
まず、手法として徹底されているのが、ゴールからやるべきことを逆算する「バックキャスティング」。そして手段を論理的に検討していく「ロジックモデル」だ。
現状から進めていくと、ニーズがあるとかないとか、どこまでやるのかという議論が出てしまいます。まずはやるべきゴール設定をする。そしてロジックモデルを組み合わせながら、既存の枠にとらわれない発想を試みています。

CWTが文化施設と連携して進める「パートナープログラム」を例に見てみよう。東京都庭園美術館では、ベビーカーの利用者や車椅子の人が気兼ねなく来館できる「フラットデー」を設けている。今までは、特別鑑賞日として、美術館側が指定した休館日に来てもらうプログラムだった。しかし、CWTでの議論において「特定の日であればゆったりと鑑賞できる状況があるが、一方で利用者が選択できない不自由さがあるのではないか」という意見が上がったという。
行きたいと思った日に行けることと、日時を指定されることでは全然違いますよね。「意思決定できる」ということが重要なんです。
そこで活用したのが予約制度だ。コロナ禍で運用していた仕組みを援用する形で、開館日にフラットデーを設け、試験運用を始めた。


アート・コミュニケーターと共に鑑賞する(撮影:井手大、画像提供:東京都庭園美術館)
当事者の視点に立ったプログラム開発には、障害の個別性にどう対応するかという課題もある。たとえば、同じ「目が見えない」でも、先天的に見えない人と中途失明の人では世界の感じ方が全く異なるからだ。障害のグラデーションを考慮しながら、最終的には単位を個人にすべきだと森さんは話す。
こうした障害のグラデーションへの理解を深めるために森さんが重視しているのは「まず会ってもらう」こと。レクチャーが得意な当事者を招き、職員向けのワークショップを行うことも、プログラム開発の中では重要な取り組みだ。その機会を通じて「できない」ではなく「どうしたらできるか」を考えてもらう。それは自分たちがあたりまえだと思っていたことを問い直すことでもあるだろう。
障害のある人も楽しめるプログラムは、想像だけでつくろうとすると全く的はずれになってしまうことがあります。障害当事者と実際に出会い、対話をする。小さな経験を積み重ねることがプログラム開発のベースになるんです。
とはいえ、新たな環境の中で、各施設の職員が心配や不安を抱くこともあるはずだ。もちろんむずかしさはある。しかし、心配する必要はないと森さんは笑顔でこう続けた。
私だって多くの経験がある専門家ではないし、知らないこともたくさんある。だけど、そんな私でも実際に当事者と会い、対話を重ねることで、少しずつ状況が分かるようになってきたという実感があります。だからみんなもきっとできるようになるはずです。当事者目線に立ったプログラムの開発には、工夫できる余地がたくさんある。それがこの仕事の面白いところだと思います。

社会全体がやわらかく動いて変わる。ネットワークを築く重要性とは
最後は、3本目の柱である「ネットワークを築く」こと。
CWTでは、国内外の様々な文化施設の事業者と積極的につながることで、アクセシビリティが全体として向上していくことを目指している。取り組むべき課題は多く、時間もかかる。だからこそネットワークを築くことを重要視しているのだという。
令和5年度には、国内会議「だれもが文化でつながるサマーセッション2023」を上野の東京都美術館で開催した。「アクセシビリティと共創」をテーマに、前年に行われた国際会議で得た知見やネットワークを広めるとともに、共生社会の実現に向けた取り組みを推進することを目的とした。9日間に渡るセッションにはのべ4,000名もの人が参加し、共有と議論の場になった。
さらに、今後は各文化施設との連携も強化していく。情報共有の質を向上させるため、次年度から各館に社会共生担当を配置し、パートナープログラムも推進していくという。

トークセッションの様子(画像提供:アーツカウンシル東京)
「環境を整える」「プログラムを開発する」「ネットワークを築く」。以上3つの視点が重なりあいながら、CWTのプロジェクトは進行していく。
最終的には、当事者の方々に満足してもらうことがゴールです。だから、“やってるふり”とか“やったからいい”ということでは意味がありません。現実にはまだ初期の準備が形になってきた段階です。ただ、どこかが実現すれば、ほかの領域にも相乗効果が生まれて、一気に実現に近づくんじゃないかという期待があるんです。
一方で、文化施設を現在利用している人に向け、「多様な人が利用できることが当然である」というメッセージを伝える必要性もあるという。
マジョリティ側に立つ人たちへの情報共有も必要だし、社会全体がやわらかく動いて変わっていかなければいけないと思っています。

「視覚障害と鑑賞プログラム」の様子(画像提供:アーツカウンシル東京)
CWTが発足して数年が経ち、プロジェクトが具体的な形になり始めてきた中で、都立の文化施設には今後ますます変化が求められるだろう。過渡期につきものである「不寛容さ」とどう向き合うことができるだろうか。
人と環境との関係には、人が環境をつくる側面と、環境が人をつくる側面とがある。であるならば、東京都の文化施設から新しい環境をつくることで、文化施設に来た人たちが少しずつ変容していくかもしれない。その小さな変化が積み重なることで、社会に新しい「あたりまえ」が広がっていくかもしれない。そうした希望を持つことが、過渡期をしなやかに乗り越える推進力になるのだと思う。
文化施設が社会に参加していく挑戦
筆者が森さんと話す前に抱いていたのは、芸術文化には日常を豊かにする力があり、だからこそ文化施設へのアクセシビリティを向上した方が良いという考え方だった。しかし、森さんは異なる考えを抱いているという。
これまで、文化施設があらゆる特性の人を考慮して来たとは言えません。むしろ権威的な場所でさえありました。しかし、今のままでは社会の大きな流れに取り残されてしまうのは明らかです。だから、このプロジェクトは文化施設がウェルビーイングな状態をつくる場として、社会に参加する挑戦だととらえています。

芸術文化は地域の中で活動するアートプロジェクトをはじめ様々な形に変わりはじめてもいますよね。そうした力を生かすためにも、これまで展示・上演的な役割がメインだった文化施設のあり方そのものを更新していくチャンスなんです。
最後に、これまで現代アートのキュレーションや東京都の文化プロジェクトを歴任してきた森さん自身にとって、CWTはどんな意味を持つのかたずねてみた。
「ウェルビーイング」は、芸術文化に関わる次の世代の人たちがしっかりと背負って、長い年月をかけて取り組むべき分野だと考えています。私はその入口をつくらないといけません。
森さんはこう続ける。
私は、これまで現代アートを中心に、様々なアートプロジェクトに携わってきました。アートとは「そもそもを考える」ことだと思っています。アーティストに話を聞いて、作品の背後にあるものを考え、キュレーションする。それはCWTの仕事にも通じます。「ウェルビーイングを提供する文化施設とはどんな場所か」「あらゆる人が楽しめるプログラムとは何か」。こうした「そもそも」の問いを当事者とともに考えていく。はじめから正解があるのではなく、試行錯誤と学びを重ねながら正解を見つけていくプロセスには、アート作品のキュレーションと同じやりがいを感じています。異なるものに出会い、伴走していくことで、新しい世界に行ける感覚があるんです。

2023年のサマーセッションで、明治学院大学非常勤講師で全盲当事者の半田こづえさんが言っていたのは、「ミュージアムを開いていく動機を、一人ひとりが持たないと結果がついてこない」ということだった。
では、森さんの動機とはなにか。一つは、東京都の文化戦略を統括する第一人者として、これまで「見えづらいもの」とされてきた人たちの尊厳を回復すること。そしてもう一つは、異なる価値観や世界との出会いが、純粋に「面白い」ということだと思う。それは好奇心が刺激されること、自分の世界が広がること、そして新たな可能性をともに開くということ。その「面白さ」に気づく人が増えれば増えるほど、目標までの距離は小さくなるはずだ。
わからなさを引き受け、試行錯誤を繰り返し、「義務感」だけではなく「面白さ」とともに人も文化施設も変化していく。そうしたクリエイティブなプロセスこそが、「だれもが文化でつながる」ための礎となるにちがいない。
Information
クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョー
Profile
![]()
-
森司
公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京事業部事業調整課長、女子美術大学特別招聘教授
1960年愛知県生まれ。水戸芸術館で学芸員を務めた後、公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京事業推進室事業調整課長に就任。2009年より「東京アートポイント計画」を担い、ディレクターとしてNPOなどとの協働によるまちなかでのアートプロジェクトの企画運営を行う。2011~2020年まで「東京都による芸術文化を活用する被災地支援事業(Art Support Tohoku-Tokyo)」のディレクター、 2015~2021年まで東京2020公認文化オリンピアード事業「東京キャラバン」「TURN」のプロジェクトディレクターを務めた。現在「クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョー」を主導し、財団としてのアクセシビリティの向上等にあたっている。
- ライター:椋本湧也
-
1994年、東京生まれ、京都在住。都内の出版社と家具メーカーでの仕事を経て、現在京都で出版社の立ち上げ準備中。書籍の編集や執筆、個人出版なども行う。著作に『26歳計画』『それでも変わらないもの』『日常をうたう〈8月15日の日記集〉』。
この記事の連載Series
連載:こここインタビュー
![]() vol. 332025.09.26遊びと医療ケアの両立をどう目指す? 「そらぷちキッズキャンプ」の“人を信じて待つ”仕事
vol. 332025.09.26遊びと医療ケアの両立をどう目指す? 「そらぷちキッズキャンプ」の“人を信じて待つ”仕事![]() vol. 322025.03.18言葉を超えて誰もがつながる「身体表現」の魅力とは? 福祉を起点に広がるパフォーミングアーツ、生きづらさを変える可能性
vol. 322025.03.18言葉を超えて誰もがつながる「身体表現」の魅力とは? 福祉を起点に広がるパフォーミングアーツ、生きづらさを変える可能性![]() vol. 312024.10.09なぜ自分に価値があるか確認したくなるんだろう? 勅使川原真衣さんと新澤克憲さんによる「評価」を巡る対話
vol. 312024.10.09なぜ自分に価値があるか確認したくなるんだろう? 勅使川原真衣さんと新澤克憲さんによる「評価」を巡る対話![]() vol. 302024.09.13大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 写真家/訪問看護師 尾山直子さんをたずねて
vol. 302024.09.13大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 写真家/訪問看護師 尾山直子さんをたずねて![]() vol. 292024.09.07地域に根ざす園から、子どもも大人も混ざった“絶景“を生み出せたら。〈学校法人thanka〉が新ステートメント「手を繋ぎにいく」に込めた願い
vol. 292024.09.07地域に根ざす園から、子どもも大人も混ざった“絶景“を生み出せたら。〈学校法人thanka〉が新ステートメント「手を繋ぎにいく」に込めた願い![]() vol. 282024.08.30大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 株式会社Blanket 秋本可愛さんをたずねて
vol. 282024.08.30大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 株式会社Blanket 秋本可愛さんをたずねて![]() vol. 272024.07.25気軽な買い物体験から、「未来が良くなる」手応えを。〈フェリシモ〉の新カタログ『GO! PEACE!』制作の裏側
vol. 272024.07.25気軽な買い物体験から、「未来が良くなる」手応えを。〈フェリシモ〉の新カタログ『GO! PEACE!』制作の裏側![]() vol. 262024.04.30蓋された「小さな自分」の声に耳を傾けて。ケアを促す料理レッスンの場、就労支援の場──山口祐加さん×鞍田愛希子さん
vol. 262024.04.30蓋された「小さな自分」の声に耳を傾けて。ケアを促す料理レッスンの場、就労支援の場──山口祐加さん×鞍田愛希子さん![]() vol. 252024.04.10「インクルーシブ」は誰のための言葉? 老舗メーカー〈ジャクエツ〉×医師・紅谷浩之さんの、子どもに“遊びと友だち“を返す遊具
vol. 252024.04.10「インクルーシブ」は誰のための言葉? 老舗メーカー〈ジャクエツ〉×医師・紅谷浩之さんの、子どもに“遊びと友だち“を返す遊具![]() vol. 242024.03.29文化施設のウェブアクセシビリティを向上する。障害当事者との「建設的な対話」に必要なこととは?──伊敷政英さん×森司さん
vol. 242024.03.29文化施設のウェブアクセシビリティを向上する。障害当事者との「建設的な対話」に必要なこととは?──伊敷政英さん×森司さん![]() vol. 222023.12.22人のためってなんだろう? 他者にコントロールされない「LOVOT」から、“人間らしさ“を考える──伊藤亜紗さん×林要さん
vol. 222023.12.22人のためってなんだろう? 他者にコントロールされない「LOVOT」から、“人間らしさ“を考える──伊藤亜紗さん×林要さん![]() vol. 212023.11.08保育料ゼロを実現し、子育てを“みん営化”する。 学童保育施設〈fork toyama〉岡山史興さん
vol. 212023.11.08保育料ゼロを実現し、子育てを“みん営化”する。 学童保育施設〈fork toyama〉岡山史興さん![]() vol. 202023.05.29ともだちってなんだろう? 答えを出す必要はないけれど。新澤克憲さんとテンギョー・クラさんの対話から考える
vol. 202023.05.29ともだちってなんだろう? 答えを出す必要はないけれど。新澤克憲さんとテンギョー・クラさんの対話から考える![]() vol. 192023.05.23歌人・岡本真帆さん×西淡路希望の家・金武啓子さん対談。「感動」の発見、どう他者と分かち合いますか?
vol. 192023.05.23歌人・岡本真帆さん×西淡路希望の家・金武啓子さん対談。「感動」の発見、どう他者と分かち合いますか?![]() vol. 182023.03.20“みる”から始める、アーティストと支援現場のつなぎ役。日常の関係性を変える「TURN LAND プログラム」の挑戦
vol. 182023.03.20“みる”から始める、アーティストと支援現場のつなぎ役。日常の関係性を変える「TURN LAND プログラム」の挑戦![]() vol. 172023.03.15アート活動で、「できる/できない」を揺さぶる。日常の価値を言葉に変えるコーディネーターの役割
vol. 172023.03.15アート活動で、「できる/できない」を揺さぶる。日常の価値を言葉に変えるコーディネーターの役割![]() vol. 162023.03.03唯一の答えを探しすぎていないか? 下地ローレンス吉孝さん×なみちえさんと“わかりやすさ”について考える
vol. 162023.03.03唯一の答えを探しすぎていないか? 下地ローレンス吉孝さん×なみちえさんと“わかりやすさ”について考える![]() vol. 152023.02.15“わたし”と“あなた”それぞれの複雑さを大切にするには?──なみちえさん×下地ローレンス吉孝さんと共に考える
vol. 152023.02.15“わたし”と“あなた”それぞれの複雑さを大切にするには?──なみちえさん×下地ローレンス吉孝さんと共に考える![]() vol. 142022.12.23出会いを広げながら、協働を生む「メディア」を目指して──〈こここ〉シーズン2を振り返る
vol. 142022.12.23出会いを広げながら、協働を生む「メディア」を目指して──〈こここ〉シーズン2を振り返る![]() vol. 132022.12.19働くことも、映画祭も「みんなが心地よい」を目指して。GOOD NEWSとTHEATRE for ALLのインクルーシブな場づくり
vol. 132022.12.19働くことも、映画祭も「みんなが心地よい」を目指して。GOOD NEWSとTHEATRE for ALLのインクルーシブな場づくり![]() vol. 122022.10.14バリアフリーの映画祭を通して、「その人のまま」でいられる社会に。作家・川内有緒さん×THEATRE for ALL・金森香さん
vol. 122022.10.14バリアフリーの映画祭を通して、「その人のまま」でいられる社会に。作家・川内有緒さん×THEATRE for ALL・金森香さん![]() vol. 112022.09.13スポーツの可能性って何だろう? 「プロスポーツ」「ゆるスポーツ」から考える──岡田武史さん×澤田智洋さん
vol. 112022.09.13スポーツの可能性って何だろう? 「プロスポーツ」「ゆるスポーツ」から考える──岡田武史さん×澤田智洋さん![]() vol. 102022.03.31まだみぬ「表現」との出会いを、誰もが体験できる社会へ。障害のある人の芸術・文化活動を支える窓口が全国に
vol. 102022.03.31まだみぬ「表現」との出会いを、誰もが体験できる社会へ。障害のある人の芸術・文化活動を支える窓口が全国に![]() vol. 092022.02.09コロナ禍で「消される」声に、どう耳を傾ける? 次の社会をつくる言葉と対話のあり方──荒井裕樹さん×青山誠さん
vol. 092022.02.09コロナ禍で「消される」声に、どう耳を傾ける? 次の社会をつくる言葉と対話のあり方──荒井裕樹さん×青山誠さん![]() vol. 082021.12.24福祉をたずねて1年。編集部は何に出会い、悩んできた?──〈こここ〉振り返り座談会
vol. 082021.12.24福祉をたずねて1年。編集部は何に出会い、悩んできた?──〈こここ〉振り返り座談会![]() vol. 072021.11.24コロナ禍を経て新たな表現の協働へ ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[後編]
vol. 072021.11.24コロナ禍を経て新たな表現の協働へ ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[後編]![]() vol. 062021.11.24アートプロジェクトは福祉の現場で何を生み出す? ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[前編]
vol. 062021.11.24アートプロジェクトは福祉の現場で何を生み出す? ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[前編]![]() vol. 052021.10.18福祉施設が学びあいの拠点になることで育まれるものとは?ライフの学校・田中伸弥さん
vol. 052021.10.18福祉施設が学びあいの拠点になることで育まれるものとは?ライフの学校・田中伸弥さん![]() vol. 042021.06.03VR認知症を体験して気づいた、わからない世界へ手を伸ばし続ける大切さ。シルバーウッド 下河原忠道さん
vol. 042021.06.03VR認知症を体験して気づいた、わからない世界へ手を伸ばし続ける大切さ。シルバーウッド 下河原忠道さん![]() vol. 032021.04.15まだ名付けられていない感覚に出会う「遊び」の可能性とは? インタープリター 和田夏実さん
vol. 032021.04.15まだ名付けられていない感覚に出会う「遊び」の可能性とは? インタープリター 和田夏実さん![]() vol. 022021.04.15「助けて」とお互いに言い合えるのが、成熟した社会。ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ代表 志村季世恵さん
vol. 022021.04.15「助けて」とお互いに言い合えるのが、成熟した社会。ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ代表 志村季世恵さん![]() vol. 012021.04.15「お笑い」や「演劇」は他者の世界に寄り添うヒントをくれる。りんたろー。さん×菅原直樹さんが語る「介護の話」
vol. 012021.04.15「お笑い」や「演劇」は他者の世界に寄り添うヒントをくれる。りんたろー。さん×菅原直樹さんが語る「介護の話」