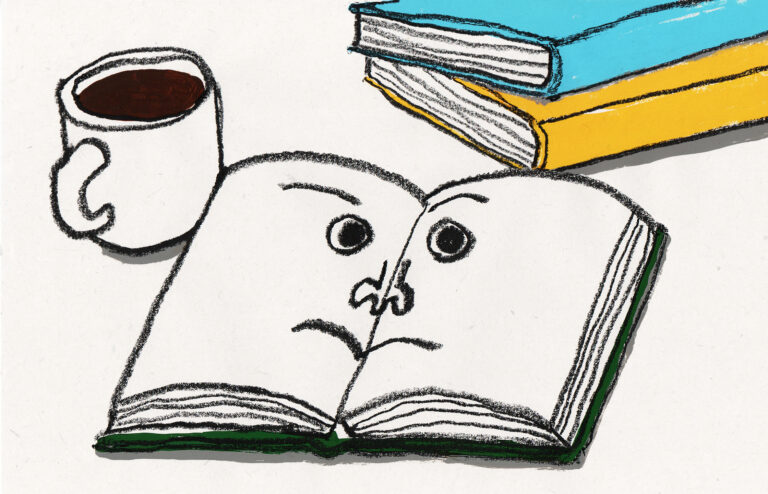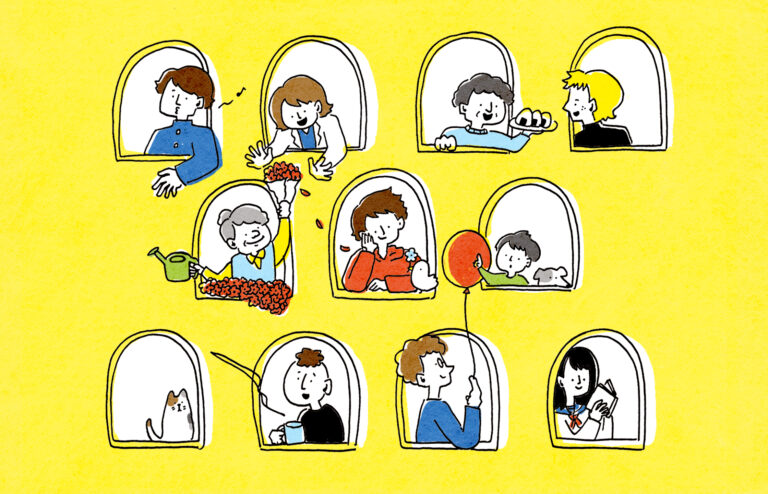“ありのままの自分”を大切にするって、どういうことだろう? しょうぶ学園施設長 福森伸さんをたずねて こここスタディ vol.11
「利用者さんのなかには、ひと月にひと針しか縫わない人もいます」。
鹿児島県にある福祉施設 「しょうぶ学園」の布の工房を見学していたとき、私たちを案内してくださっていた職員の壽浦(じゅうら)直子さんがそう言った。
裂き織り・刺繍を中心とした作品がつくられている工房のなかでは、黙々と刺繍を進める人もいれば、作業に飽きてラジオに耳を傾けていたり、私たちに話しかけてイラストを配ってくださったりと、制度上「利用者」と呼ばれる人がさまざまな過ごし方をしていた。
ひと月にひと針、という言葉に驚くと、壽浦さんも「すごいですよね。私にはできない」と言う。たしかに自分にもできないだろうと思った。仮に布と刺繍糸を渡されたら、なんのノルマや目的を伝えられていなくても、できるだけたくさんの作品をつくろうと躍起になってしまいそうなのは簡単に想像できた。
布の工房に限らず、しょうぶ学園のなかを歩いていると、さまざまな場所でのびのびと、自由な過ごし方をしている方々に出会った。施設長の福森伸さんは、そんな彼らのあり方を、“ありのまま”と呼ぶ。
“ありのままの自分”という言葉は至るところで耳にするけれど、実際のところ、“ありのまま”とはどんな状態だろう。そして、“ありのままの自分”を受け入れ、そんな自分自身を大切にするとは、どういうことなのだろう。
しょうぶ学園の“ありのまま”が、どのような意識や環境づくりのもとで実現してきたかを伺うことは、“ありのままの自分”について考えるためのヒントになりそうだ。訪問記に続き、施設長の福森伸さんにお話を伺った。
しょうぶ学園とは
社会福祉法人太陽会が運営する福祉施設。自立支援事業(ささえあう)、文化創造事業(つくりだす)、地域交流事業(つながりあう)という3つの事業を柱とした、知的障害や精神障害がある方が集まる複合型の施設です。しょうぶ学園の開設は1973年。1985年からは、利用者による創作を「工房しょうぶ」と位置づけ、それぞれの個性や特性を活かした“ものづくり”を活動の中心としています。木工やテキスタイルなどをはじめとした「工房しょうぶ」のプロダクトにはファンが多く、これまでにも国内外で多数の展覧会が開催されてきました。
過去記事:[劇場と4つの工房を持つ福祉施設 しょうぶ学園をたずねて]
過去記事:[手彫り角盆&角膳〈しょうぶ学園〉]
「社会に出ていく」から「ここを社会にする」へ

創作に黙々と没頭する人もいれば、作業に飽き、手を止めてのんびりと時間を過ごす人もいる。「利用者」の自由で自然体な振る舞いが印象的なしょうぶ学園だが、福森さんが学園で働きはじめた約40年前は、現在とはまったく違った方針を掲げていたという。
僕は、もともとは利用者を変えようとしていましたから。社会復帰のために頑張って訓練してもらって、成長することで「僕らの世界においで」という考え方だったんです。自分たちを「ノーマル」と捉え、利用者に対して「ノーマルにおいで」と呼びかけていたようなもの。利用者からすれば向こうが「ノーマル」なんですけどね。

福森さんが利用者を変え、“成長”させようと躍起になっていた背景には、「障害者ががんばってつくったもの」というストーリー抜きで社会に通用するような作品を、福祉施設の利用者や職員の手によって供給したいという思いがあった。
そのためには、プロがつくる作品と比べても見劣りしないものをつくらなければならない。知的障害のある利用者たちにも根気強くものづくりの方法を教えていけば、いつか、教えたステップ通りに木工作品を完成させることができるはずだ──。1985年に立ち上げた木の工房「工房しょうぶ」では当初、そのような考えのもとで利用者たちの技術向上を目指していた。
しかし、1から10まで教えた通りのステップを踏んで作品をつくることのできる利用者は、ほとんどいなかった。福森さんはやがて、“教えた通りにつくらせる”ことの無意味さに気づいたという。
簡単に言うと、無理だとわかった。自分はどうやら間違ったことを教えているな、というか……こうやって「教えている」って言っちゃうのも当時の癖ですよね。利用者たちに間違ったことを伝えている、と思ったんです。利用者と接していくうちにそれには薄々気づいていたんだけど、自分のなかで革新的に方針を変えたのは、働きはじめて20年ほど経ってからでした。
利用者に「がんばって」と言うと「うん、がんばる」と返ってくるんですね。最初はその言葉だけを真に受けていたんだけど、彼らの様子を見ていると、興味のない作業をするときと興味のある作業をするときとでは、目の色や取りかかる勢いがまったく違うのがわかってきた。本当に見るべきは言葉ではなく、目の動きや行動なんだと気づきました。


働くという言葉の意味を、健常者にとっての一元的な基準で捉えるべきではない、と福森さんは考えた。しょうぶ学園の利用者のなかには、作業に没頭して彫り進めた木をすべて木くずにしてしまう人や、「穴を掘ってほしい」と頼まれ、自分の背丈以上もある深い穴を掘ってしまう人たちがいた。彼らの行為は一元的な基準や価値観だけから見ると、“労働”しているとは言い難いかもしれない。けれど、“働いている”ことに変わりないと思った。
僕たちはどうしても、働くことには目的が伴うと思ってしまう。けれど、利用者の多くはもっと“無目的的”な働き方や生き方をしているのだから、僕らがすべきことは、彼らがそのままで生きられるような環境を保障し、協働していくことだと考えを変えたんです。

ただひたすらに手を動かし続けるという行為を見つめていると、うまく縫う、削るといった結果ではなく、目的や常識から逸脱することにかける無意識のエネルギーがそこに生まれていることに気づいた。
それは私が思い描く目的を簡単に無視して、それどころかあまりにも目的から外れているがゆえに無目的な行為に見えてしまう。だが無目的なのではなく「無目的的」なのだ。」(『ありのままがあるところ』p32-33 著 福森伸 晶文社)
もちろん、がんばりたい、成長したいと思う人にはそのためのサポートが必要です。でも、無目的的なことをしていても咎められない環境さえあればもっとありのままで楽に生きていける、という人たちのサポートもしたいと思った。
しょうぶ学園は地球上のほんのわずかな一点だけれど、100人ぐらいの人たちが、そういう考えを持って集まっているわけです。それがもっと増えていけば、いずれ社会の一部になりますよね。わざわざ社会に出ていって足並みを揃えるのではなく、ここをひとつの社会にしてしまおう、と考えたんです。
見通しが悪いこと、すぐにはわからないことに不安を感じる人が多いかもしれないけれど
利用者たちのような“無目的的”なものづくりへの姿勢には、他者との過剰な比較や評価の目から距離を置くためのヒントがあるのではないか、と福森さんは言う。しょうぶ学園の各工房でつくられた作品は多くの人々を魅了し、国内外のさまざまな場所で販売されたり展示されたりしている。しかし、それを「商品」だと捉えている利用者はほとんどいないのだそうだ。


たとえば、延々と団子をつくっている人に「なんでつくっているの?」と聞いたら、もちろん楽しいからって言う人もいるんだけど、「わからない」って言う方が多い。わからないって自然なことですよね。そういう自然さのなかで、決してバランスを意識していないのにどこかバランスがとれている、格好いい作品が生まれるんじゃないかと思います。
自然の木、たとえば山のなかにある木を見て「あの枝はバランスがよくない」なんて言う人はいないのに、その木を庭に植えようとした途端、「バランスが……」とつい言いたくなってしまうじゃないですか。僕たち職員がすべきことは、その枝を剪定することではないと思っています。あくまで自然なバランスの美しさを尊重した上で、見る人にそれが気持ちよく伝わるようコーディネートするのが役割だと思うんです。
学園そのものをひとつの社会とするため、そして利用者の自然な生き方、働き方を尊重する施設であるために、変化してきたのは福森さんたち職員の意識だけではない。施設としての環境面も、試行錯誤を重ね、さまざまなアレンジが加えられてきた。
たとえば、しょうぶ学園の敷地内には形も大きさもばらばらな建物が多くあるが、その建物と建物のあいだにはたくさんの木々が植えられ、水が流れている。アンバランスなものを自然物で繋ぐことによって、心地よさや統一感が生まれている。


また、建物の設計に“カーブ”が多用されていることも特徴的だ。カーブの建物は、直線的に柱が並ぶ建築物と比べて強度が高いという利点がある。さらに、カーブの先が完全には見通せないようになっていることにも意味があると福森さんは言う。
カーブしている建物が多いので、ガラス越しにその奥を見ようと思っても、ちょっとしか見えないんです。人が隠れやすい分、自由に過ごしやすい。それに先が見えないと、その向こうに何があるか、気になってつい見にいきたくなる。
いまは見通しが悪いこと、すぐにはわからないことを不安に感じる人のほうが多いかもしれません。けど、どうしたって、わかんないことはわかんないじゃないですか(笑)。だからむしろわからないことをプラスに捉えて、「これから探検だ、何があるんだろう」と楽しみに思えるような心持ちになれればいいんじゃないか。
「僕は『ありのままの自分でいい』とは思えていない」

わからない、ということを肯定することは難しい。職員のなかには、利用者に作品をつくる理由を尋ねて「わからない」と言われたとき、「どうしてわからないのだろう」と分析しようとしたり、その理由を考えてもらおうとする人もいるという。
「『わかんないでつくっているの? 格好いい』って拍手できるようになるともっといいんですけどね」と福森さんは言いつつも、つい“目的”や“成長”に囚われてしまう私たちのあり方を、決して否定はしない。私たちの多くは結局そういうものから逃れられないし、むしろそこで勝負していくしかないのかもしれない、と言う。
僕はこれまでずっと利用者たちがありのままでいられるような環境を整えようと思ってやってきたけれど、それは彼らがありのままで生きられたほうが楽なんだろうな、と感じるし、僕らにはその環境を整える義務があるとも思うからです。
僕は利用者と自分とを比較して考えることが多いので、こうやって“彼ら”とか“僕ら”って表現をあえて使うんですが、結局、成長とか目的みたいなものに対する考え方は、僕は彼らとは全然違いますよ。僕なんて、成長イズビューティフルって価値観だから、ありのままでいいとは正直思えていない。自分のありのままに満足している人って少ないんじゃないですか?
たしかに、現状の自分にとても満足している、と言い切れる人は少なそうだ。では、ありのままの自分を全肯定するとはいかないまでも、“目的”や“成長”に囚われすぎず、背伸びしていない自分を尊重するためにはどうすればいいのだろう。
そう尋ねると、福森さんは、しょうぶ学園の先代の理事長が言っていたというこんな言葉を教えてくれた。
先代の理事長は、「50点は満点だからね」ってよく言っていたんですよ。半分できたらもうOKだって。20代とか30代の頃はその意味があまりわからなかったんだけど、いまは「50点は満点だ」って思っています……というか、思うようにしています。
僕たちが“ありのまま”でいるにはどうしたらいいんでしょうね。言ってしまえば、50点は満点だと思い込もうとしている自分もありのままだし、負けたくないって欲のある自分もありのままだろうから、それを正直に言えたらいちばん楽なのかもしれない。
以前、僕がゴルフのキャディーをしたときに、その日のスコアが78ですごく悔しがっている人がいたんです。聞いてみたらベストスコアが75で、74を狙ってたって言うんですよ(笑)。僕らはそうやって常に、最高点を自分の基準にしてしまいがちですよね。本当はベストスコアなんて奇跡みたいなものなのに、それを自分の“ありのまま”だと思い込んでしまう。

作品の創作に打ち込む利用者の多くは、その過程そのものを目的にしているように見える、と福森さんは言う。結果だけでなく、過程の一つひとつに目を向けようとすることは、社会のなかで見逃されているものに価値を見出すことにもつながる。
社会的に価値が高いものとか金銭的に価値のあるもの、美しいものだけに着目していると、人のストレングス(強み、長所)を見つけられないんです。でもそれだけでなく、汚いとされるものや嘘、目を背けたくなるようなものさえも価値として認めていけば、人のストレングスってたくさんあるじゃないですか。そういったものが価値として認められる世界のひとつがアートでもあると思うんです。
もちろん、福祉に携わる人間としては、当人が嫌な思いをしていたり、苦しみながらつくったものをアートだと呼ぶことはしたくありませんし、彼らの作品を僕らがアートだアートだと騒ぎ立てることは、しょせんエゴだとも思います。
でも、たとえば目の前に誰かがつくった10万個の団子があったら「おお、格好いいな」と思うし、それを誰かに見せたくもなる。少なくともそれは僕にとっての喜びではあるし、それを見た誰かが幸せな気持ちになるのならいいんじゃないか、というある種の開き直りもありますよね。だから僕たちとしては、つくる人の内面ができるだけそっくり、無理せずに作品に出るよう、サポートするわけです。
他者だけでなく自分自身も、矛盾やわからなさに満ちた存在だ
福森さんは取材のなかでたびたび「答えを出さないようにしている」とか、「昔はわかろうとしていたけど、最近はそう思わなくなった」という言葉を口にした。そして、わからないものはわからないというある種の諦めを持った上で折り合いをつけていくことが、人と関係を築いていく上で大切なのではないか、と言った。
人のことを「自分にはわからない」と感じた上で尊重しようとするのは、言葉の上では簡単でも、実際にはとても難しいことのように思う。しかし、本当は他者だけでなく自分自身も、矛盾やわからなさに満ちた存在だ(「50点は満点」と感じている自分と、もっと成長したいと感じているふたりの自分がいるように)。
他者のわからなさを「わからない」ままで受け入れ、尊重しようとすること。それはそのまま、自分自身のありのままを大切にするということに、ゆるやかに繋がっているのかもしれない。


Profile
![]()
-
しょうぶ学園
知的障がい者支援施設
1973年に知的障害者援護施設としてスタート。「ささえあうくらし―自立支援事業」「つくりだすくらし―文化創造事業」「つながりあうくらし―地域交流事業」をテーマに、障害のある人たちが地域社会でよりよく暮らしていくための、創造的で刺激的なコミュニティづくりを目指す。針一本で独特の刺繍の世界をつくり上げる〈nui project〉や、心地よい「不揃いな音」を楽しむ民族楽器による音パフォーマンスグループ〈otto & orabu〉など、メンバーの個性が光る表現活動を次々と発信。1985年に〈工房しょうぶ〉、1999年には在宅デイサービスセンター〈Doしょうぶ〉、2019年にはアートホールを備えた子どもたちの支援施設〈アムアの森〉を開設するなど、地域福祉と地域貢献に力を入れている。
- ライター:生湯葉シホ
-
1992年生まれ、東京在住。フリーランスのライター/エッセイストとして、おもにWebで文章を書いています。Twitter:@chiffon_06
この記事の連載Series
連載:こここスタディ
![]() vol. 282025.09.22「男らしさ」で誰かを傷つけたくない、どうすれば? 文筆家、教育学者、写真家、編集者によるおすすめの本
vol. 282025.09.22「男らしさ」で誰かを傷つけたくない、どうすれば? 文筆家、教育学者、写真家、編集者によるおすすめの本![]() vol. 272025.04.18“家庭”ってなんだろう? 子どもと大人が尊重しあう場所を目指す、児童福祉施設「てらす峰夢」をたずねて
vol. 272025.04.18“家庭”ってなんだろう? 子どもと大人が尊重しあう場所を目指す、児童福祉施設「てらす峰夢」をたずねて![]() vol. 262024.12.06差別と関係のない立ち位置ってあるの? 社会のあり方に矢印を向けて考える
vol. 262024.12.06差別と関係のない立ち位置ってあるの? 社会のあり方に矢印を向けて考える![]() vol. 252024.12.06差別ってなんだろう? 現代社会における差別の研究者 阿久澤麻理子さんをたずねて
vol. 252024.12.06差別ってなんだろう? 現代社会における差別の研究者 阿久澤麻理子さんをたずねて![]() vol. 242024.08.14正しい答えを刷り込むのではなく、自分で選ぶ手助けをする「包括的性教育」とは?
vol. 242024.08.14正しい答えを刷り込むのではなく、自分で選ぶ手助けをする「包括的性教育」とは?![]() vol. 232024.07.31「性教育」という言葉から何を想像する? 教育学者 堀川修平さんによる「包括的性教育」解説
vol. 232024.07.31「性教育」という言葉から何を想像する? 教育学者 堀川修平さんによる「包括的性教育」解説![]() vol. 222024.07.17「創造性」はどう育まれる? ブルーノ・ムナーリの軌跡から──デザイナー、現代美術作家、教育者のまなざし
vol. 222024.07.17「創造性」はどう育まれる? ブルーノ・ムナーリの軌跡から──デザイナー、現代美術作家、教育者のまなざし![]() vol. 212024.03.30「個人の心の問題」の多くは環境や政治の問題でもある〜「あなたのため」というバウンダリーの侵害〜
vol. 212024.03.30「個人の心の問題」の多くは環境や政治の問題でもある〜「あなたのため」というバウンダリーの侵害〜![]() vol. 202024.03.26自分と他者を区別する境界線「バウンダリー」とは?ソーシャルワーカー鴻巣麻里香さんによる解説
vol. 202024.03.26自分と他者を区別する境界線「バウンダリー」とは?ソーシャルワーカー鴻巣麻里香さんによる解説![]() vol. 192024.02.01「昔好きだった作品」の表現に戸惑ってしまったら? フィクションが与える2つの影響──文学研究者・小川公代さん
vol. 192024.02.01「昔好きだった作品」の表現に戸惑ってしまったら? フィクションが与える2つの影響──文学研究者・小川公代さん![]() vol. 182023.12.15「合理的配慮」は「ずるい」「わがまま」なのか? インクルージョン研究者 野口晃菜さんによる解説
vol. 182023.12.15「合理的配慮」は「ずるい」「わがまま」なのか? インクルージョン研究者 野口晃菜さんによる解説![]() vol. 172023.04.21“できる/できない”の社会を「ヨコへの発達」で問い直す。社会福祉の父・糸賀一雄を、垂髪あかりさんが研究する理由
vol. 172023.04.21“できる/できない”の社会を「ヨコへの発達」で問い直す。社会福祉の父・糸賀一雄を、垂髪あかりさんが研究する理由![]() vol. 162023.02.08「やさしい日本語」ってなに? 言語学者・庵功雄さんに聞くコミュニケーションの本質
vol. 162023.02.08「やさしい日本語」ってなに? 言語学者・庵功雄さんに聞くコミュニケーションの本質![]() vol. 152023.01.27人を見た目で判断することって全部「差別」になるの? 社会学者 西倉実季さんと、“ルッキズム”について考える
vol. 152023.01.27人を見た目で判断することって全部「差別」になるの? 社会学者 西倉実季さんと、“ルッキズム”について考える![]() vol. 142023.01.16自分の気持ちを話さない自由がある。NPO法人ぷるすあるはと一緒に考えた“きもち”との付き合い方
vol. 142023.01.16自分の気持ちを話さない自由がある。NPO法人ぷるすあるはと一緒に考えた“きもち”との付き合い方![]() vol. 132022.12.14“障害”ってそもそも何だろう? 困難の原因を「社会モデル」から考える──バリアフリー研究者・星加良司さん
vol. 132022.12.14“障害”ってそもそも何だろう? 困難の原因を「社会モデル」から考える──バリアフリー研究者・星加良司さん![]() vol. 122022.11.29「ちゃんとしなきゃ」の呪いをとくには?福祉社会学者 竹端寛さん× 僧侶 松本紹圭さん
vol. 122022.11.29「ちゃんとしなきゃ」の呪いをとくには?福祉社会学者 竹端寛さん× 僧侶 松本紹圭さん![]() vol. 102022.09.27「福祉の現場」と「芸術」の根っこには通ずるものがある? 福祉環境設計士 藤岡聡子さんをたずね、「ケアの文化拠点」ほっちのロッヂへ
vol. 102022.09.27「福祉の現場」と「芸術」の根っこには通ずるものがある? 福祉環境設計士 藤岡聡子さんをたずね、「ケアの文化拠点」ほっちのロッヂへ![]() vol. 092022.09.07“健康”ってなんだろう?ケアの文化拠点「ほっちのロッヂ」紅谷浩之さんをたずねて
vol. 092022.09.07“健康”ってなんだろう?ケアの文化拠点「ほっちのロッヂ」紅谷浩之さんをたずねて![]() vol. 082022.08.12弱さは個人の問題ではなく、構造上の問題だ。公認心理師・臨床心理士 信田さよ子さんと考える“弱さ”のこと
vol. 082022.08.12弱さは個人の問題ではなく、構造上の問題だ。公認心理師・臨床心理士 信田さよ子さんと考える“弱さ”のこと![]() vol. 072022.07.28“違う“の不安をどう乗り越えればいい? グレーではない「色」で表現する発達の特性──星山麻木さん
vol. 072022.07.28“違う“の不安をどう乗り越えればいい? グレーではない「色」で表現する発達の特性──星山麻木さん![]() vol. 062022.04.12「私はどう生きたらいい?」を、一人で抱えない社会へ。医師・西智弘さんに聞く、地域活動と“ケア“の文化づくり
vol. 062022.04.12「私はどう生きたらいい?」を、一人で抱えない社会へ。医師・西智弘さんに聞く、地域活動と“ケア“の文化づくり![]() vol. 052022.03.22偏見がない人はいない。川内有緒さん×木ノ戸昌幸さん『わたしの偏見とどう向き合っていく?』イベントレポート
vol. 052022.03.22偏見がない人はいない。川内有緒さん×木ノ戸昌幸さん『わたしの偏見とどう向き合っていく?』イベントレポート![]() vol. 042022.02.04居場所・つながり・役割・生産性。「望まない孤独」をめぐる対談でみえたものとは?吉藤オリィさん×奥田知志さん
vol. 042022.02.04居場所・つながり・役割・生産性。「望まない孤独」をめぐる対談でみえたものとは?吉藤オリィさん×奥田知志さん![]() vol. 032021.10.26大切なものを失った悲しみや痛みと共に生きていくには? グリーフサポートが当たり前にある社会を目指す 尾角光美さんをたずねて
vol. 032021.10.26大切なものを失った悲しみや痛みと共に生きていくには? グリーフサポートが当たり前にある社会を目指す 尾角光美さんをたずねて![]() vol. 022021.06.24差別や人権の問題を「個人の心の持ち方」に負わせすぎなのかもしれない。 「マジョリティの特権を可視化する」イベントレポート
vol. 022021.06.24差別や人権の問題を「個人の心の持ち方」に負わせすぎなのかもしれない。 「マジョリティの特権を可視化する」イベントレポート![]() vol. 012021.04.15さまざまな側面をもつ「わたし」と「あなた」をそのまま大切にするには? 美学者 伊藤亜紗さんを訪ねて
vol. 012021.04.15さまざまな側面をもつ「わたし」と「あなた」をそのまま大切にするには? 美学者 伊藤亜紗さんを訪ねて