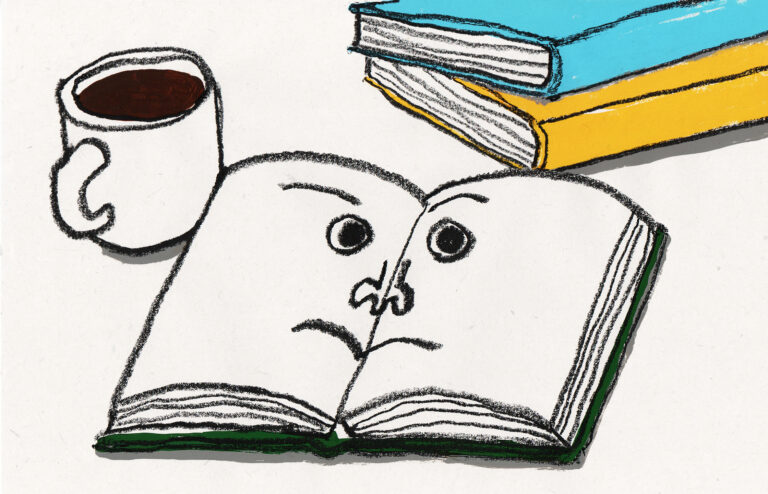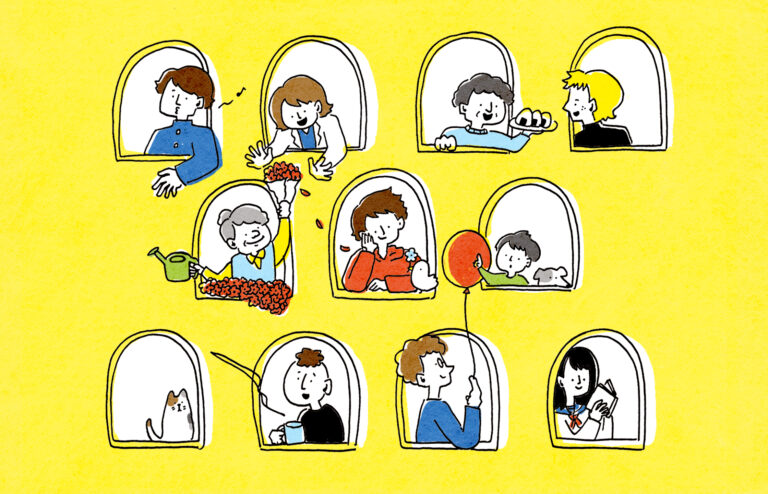“家庭”ってなんだろう? 子どもと大人が尊重しあう場所を目指す、児童福祉施設「てらす峰夢」をたずねて こここスタディ vol.27
“家庭”ってなんだろう?
意味を調べると、「夫婦・親子などが生活をともにする、小さな集団。また、その生活する所」(大辞泉)とある。だけどその説明以上に“家庭”という言葉から捉える幅は広く、受け取るイメージも様々だ。
「安心できる場所」や「自分らしく居られる場所」と答える人もいれば、「できるだけ居たくない場所」「自分を押し殺して生活する場所」と感じている人もいるかもしれない。「こども庁」が最終的に「こども家庭庁」の名称に変更された際、その賛否をめぐって議論が起きたのは、“家庭”に込める意味や機能が、人によって大きく異なることの裏返しでもあっただろう。
今、子どもの福祉にまつわる制度のあちこちに“家庭”という言葉が実際出てくるのを見ると、それが人の育ちに重要な役割を果たすことはわかる。なら、私たちが本当の意味で目指したい家庭とはどのようなものなのだろうか?
そのヒントを探るため、私たちが訪ねたのは京都府の北部、京丹後にある児童養護施設「てらす峰夢」。“家庭的な施設”を目指してつくられ、建築デザインの視点からも注目されるこの施設の施設長・櫛田啓(くしだ・たすく)さんにお話を伺った。
児童養護施設「てらす峰夢」とは
「てらす峰夢」を運営するのは、京丹後市を中心に児童福祉事業・高齢者福祉事業・障害福祉事業を展開する〈社会福祉法人みねやま福祉会〉だ。1950年に戦災孤児の受け皿として乳児院を開設することから始まり、1955年には児童養護施設にあたる幼児寮を併設した。
かつては親が亡くなった子どもの命を守るために、衣食住を提供することが大きな役割だったが、近年ではなんらかの事情で実親と生活できない子どもの個別的ケアを主な目的に運営されている。

訪れてすぐ、櫛田さんに全体を案内してもらう。風合いの異なる3つの建物に、「“家庭的な空間”で、子どもたちが自分の居場所を選択できるようにしたい」と考えた櫛田さんの思想が反映された施設だ。
まず案内してもらったのは「石ころの家」。
ここには、地域とのつながりを深める「地域交流センター」や、保護者と子どもが一緒に家庭生活への復帰練習を行う「親子訓練室」などが置かれている。こうした機能は児童養護施設としては重要だけど、子どもの日常生活には不必要だ。櫛田さんはそうした“ふつうの家にはない機能”を切り出して、この建物に集約した。
地域交流センターなどには様々な人が訪れます。「施設だし」と当たり前に思うかもしれませんが、自分の家に知らない人が入ってくることってまずないですよね。専門的な機能を生活機能と切り離すことで、子どもが過ごす空間に外部の人が入らないようにしました。



石ころの家のお隣、敷地の真ん中にある木造2階建の家は、女子児童が生活する「積み木の家」。定員6名の施設に現在は小・中学生5名が住んでいて、中には乳児院から10年近く暮らしている子どももいる。
扉を開けると、広々とした玄関があり、そばに天井まである大きな収納棚がある。靴が並んでいる様や、無造作に置かれているボールや虫かごに生活感が現れている。中に進むと、リビングダイニングや水回りがあり、そこから子ども部屋のある2階へつながっていく。


一方、男子児童が生活するのが「ロボの家」。こちらも定員6名のところに現在小・中学生5名が入居している。基本的な構造は「積み木の家」のシンメトリーで、照明や家具のカラーリングなど細かいところが異なる。


これら独立した3棟を緩やかにつなぎ一体感を生むのが、建物に囲まれるようにある庭だ。テラスに置かれた木製ベンチには、子どもや職員がよく座って休憩したりする。石ころの家で仕事をするとき、櫛田さんはそうした様子を、大きな窓越しに眺めながら見守っているそうだ。

子どもたちが自慢できる「家」としての空間デザイン
まるで一般の住宅のようなハードが整ったてらす峰夢。そのコンセプトは内装の至る所にも落とし込まれている。
例えば、部屋の間取り。安全を確保するため、スタッフがよくいる場所から部屋全体を見渡せるようにし、死角をなくしている福祉施設は多い。しかし、てらす峰夢ではあえて見えづらいポイントを階段下につくり、生活空間の中にも子どもが一人になれる余白を残した。
子どもが怪我や喧嘩をするのを防ごうと考えると、死角を無くしたくなります。でも、何か起きた際にその瞬間を大人が見ていなかったこと自体は、大きな問題ではありません。リスクはもっと手前にあるんです。子どもの様子を見ながら、問題が起こりそうな時にこちらが先回りして対応していれば、大きな事故の発生には至らないと思っています。
何より子どもも、誰かにいつも見られながら生活するのは嫌だと思いますよ。僕も嫌ですから。


水回りの動線もポイントだ。実はてらす峰夢を建てるにあたり、櫛田さんはあえて福祉施設の設計経験がない建築士に依頼をしている。子どもたちが暮らしやすい「家」を相談するなかで提案があったのが、キッチンやリビングからシームレスにつながる洗面所だった。
料理をするとき、ご飯を食べるとき、洗面所でサッと手を洗えるこの設計は、通常の住宅でもその後採用されているという。2018年のオープン前、一般の住宅見学会のように施設見学会を実施した際は、その建築士がこれまで開催してきたなかで最も多くの来場者が訪れ、「同じような水回りの設計で家を建ててほしい」という希望が殺到するほどの人気ぶりだった。



ここまで案内してもらい、積み木の家とロボの家で「施設らしさ」をほとんど感じなかったことに気づく。設置を義務付けられている110番非常通報装置とスプリンクラーが、壁や天井にあったくらいだ。
こうした設計に櫛田さんがこだわった背景には、てらす峰夢が移転する前の、幼児寮での経験があった。社会的養護(※注)の必要な子どもたちを、数多く受け入れてきた児童養護施設だ。
長い歴史の中でその役割を果たしてきたが、外観はコンクリートでできた「施設っぽさ」のある建物。生活空間としても、十数人が大きな部屋で暮らす状態だった。そこに住んでいることを友人に隠したがる子どもがいるのも、櫛田さんは気になっていた。
虐待相談対応件数が増加し、子どもたちの傷つきもますます深刻化するなか、「個別的なケア」の実現がとても重要になっています。そこにしっかり対応しながら、もっと子どもたち自身が友達に自慢できる家にしたい、と思って建てました。
※注:「保護者のない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童を、公的責任で社会的に養育し、保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うこと」(こども家庭庁)。近年は里親などの「家庭養護」を優先させつつ、「施設養護」(児童養護施設、乳児院など)でも、できる限り家庭的な養育環境(小規模グループケアなど)に近づけることが目指されている
“家庭”とは本来、互いの権利を尊重しあえる場所
様々な工夫を凝らして完成した「てらす峰夢」は、2019年には『第7回 京都建築賞・優秀賞』を受賞するなどし、建築業界や福祉業界で注目を浴びていった。しかし、そうしたハード面への評価に対して、櫛田さんは複雑そうな表情も見せる。
「建物は確かに良いし、子どもたちも喜んでくれた一方で、そこだけが整っても“家庭的な”児童養護施設はできなかった」と悔しそうに振り返った。
開所から数年が経った頃、「家庭的になった?」と職員に聞くと、口を揃えて「いいえ」「建物だけな気がする」と答えました。そこで改めて「そもそも“家庭”ってなんだろう?」「“家庭的養護”ってなんだろう?」と話し合ったんです。
家庭と言えば、「保護者と子どもが一緒に暮らす空間」のようにイメージする人も多いかもしれない。でも、社会的養護の必要な子どもたちの存在を考えたとき、果たしてそれだけでいいのか。社会のあちこちで“家庭”という言葉が重視されるなかで、子どもが幸せに生きられるために、この言葉をどう定義していけばいいのだろう。
僕らは職員間で何度も話し合いを重ね、「人と人の関係こそが、家庭には大切なのではないか」というひとつの結論に至りました。ハードが整った一つ屋根の下に人が集い、一緒に暮らせば家庭的になるかというと、決してそうではないなと。

子どもが安心できる家庭を形成する上で、欠かすことのできないと気づいた人と人の関係性。具体的にどのようなものなのだろうか。
まず櫛田さんが指摘するのが、「気配を感じあって生きている」間柄であること。「今日は機嫌がいいな」「良いことあったのかな」「疲れていそうだな」などと、お互いを気遣いあいながら生活できる関係であることが、同じ家庭の一員といえるかの大切なポイントになる。
特に虐待を受けた子どもたちとの暮らしでは、気配を感じられることはすごく重要なんです。例えば、何か嫌な事があったあと、部屋に閉じこもって自傷行為をしようとする場合があります。関係性ができていれば、「あの表情で2階に上がっていったということは、もしかしたら……」と気づくことができる。
ならば次に職員はどうするか。施設で真っ先に考えるのは、おそらく子どもを管理下に置き、死角をなくすことだと思います。でも、気配がわかれば、「なかなか部屋から出てこないな」「でも、物音がしているから大丈夫だろう」「静かすぎるから様子を見に行ってみよう」と、一方的に子どもを縛ることなく柔軟に判断できる。そうやっててらす峰夢では、相手を気にかけながらいつでもヘルプに飛んでいける体制もつくっています。

加えて、「お互いの権利を尊重しあえる」場であることが、家庭という言葉に本来欠かせない要素だと櫛田さんは続ける。
成長途上にある子どもたちは、まだ知らないことも多く、どうしても選択肢が狭くなりがちです。大人に支えられながら、徐々に自分の人生の可能性を広げていく必要がある。そうした時、人生を主体的に生きていく権利を侵害したりされたりせずに、お互いをサポートしあえる空間が、目指すべき“家庭”の状態ではないかと僕たちは考えました。
逆に虐待が起きている家庭は、人としての権利を尊重するとか、生き方を選択できるとか、そういうことが侵害されてしまっている状態ですよね。だからこそ、様々な困難な背景を抱える子どもが住む児童養護施設には、本来の家庭機能を提供し、回復のためのケアをすることが求められているのだと思います。
その上で、「時には子どもから大人に何かを与えることもあるような関係性も大事」と櫛田さんは続ける。
例えば、誕生日。家庭では、子どもだけではなく親や祖父母など共に生活をする人の誕生日もお祝いすることは珍しくない。しかし、施設では職員の誕生日をお祝いすることはほとんどなかった。それって「おかしいのでは?」という疑問から、てらす峰夢では、子どもたちと職員が作戦会議をして、誕生日の職員のサプライズパーティーをすることにしたそうだ。
子どもに一方的に与えるのではなく、双方向の関係が大切なんですよ。お互いの足りない部分やつらいことを支え合って、一緒に生きていく。それができる小さなコミュニティこそが、子どもたちに必要な“家庭”だと思うんです。
本来、家庭という言葉に「上下」の意味はありません。なのに上下関係が生まれるような場をつくり出してしまったことで、子どもの周りに様々な歪みが生まれているのではないでしょうか。

対話を通じて、「諦めなくていい」と伝える
双方向の関わりを意識してから、てらす峰夢でも子どもたちに少しずつ変化が見られるようになったという。例えば、「食」を通じた新しいチャレンジだ。
てらす峰夢ではもともと、食に興味を持てるように管理栄養士を各家に現場配置し、一般の家庭のように子どもがキッチンで料理をする様子を見たり、手伝ったりできるようにしていた。児童養護施設から巣立った後、それまで整えられた食事を提供されていたが故に自分で食生活を組み立てられず、暮らしが乱れて、社会と不適合を起こすケースがあったからだ。
双方向性を大事にしていくうちに、日々の料理に興味を持つだけでなく、職員の力を借りながら、自分から進んでいろいろなものを作るようになりました。「この料理は何?」と会話が弾みますし、「ちょっと甘い」「からすぎる」などと試行錯誤するなかでうまくいく体験が、自分自身の存在価値を見出すことにもつながっていると感じます。
今ロボの家では、世界の料理を作って毎月食べる企画もしています。ある男の子は小学生の時からパン作りに興味を持ち、様々なパンを焼いては職員やお世話になっているご近所さんにお裾分けするようになりました。将来は料理人になりたいと話してましたね。


また、対等な関係性を意識したコミュニケーションから、子どもたちが自分の考えを話すことも増えてきたと感じている。
うちに入ってきたとき、「どうせ大人が決めるんやろ」「どうせ無理やろ」が口癖になっている子どもも多いんです。それまでの家庭環境で、大人の意見を押し付けられてきたからでしょう。だから、その都度「あなたが決めたらいいんだよ」「あなたの選択次第で可能性が広がるんだよ」と伝えています。
例えば、てらす峰夢では毎年決められた予算で旅行をしており、行き先をみんなで決めている。相談の末、車で3時間近くかけてUSJへ行った年もあった。一方で、「私は不参加でいい。その分の予算をアイドルグループのLIVEに使いたい」など、個人としての率直な希望も伝えてくれるようになったという。
他の家庭と同じですね。何でもかんでもお金を出せるわけではないけど、大人が一方的に決めると子どもは不満を抱きます。うちでは毎月子ども会議を実施して、どうする? ってみんなで考えています。一つひとつは小さな取り組みですけど、子どもが自己決定の機会を通じて、「諦めなくていい」と気づけることがとても大切だと捉えています。

子どもが主体的に何かを決め、行動していく。その可能性を広げるために、傍にいる大人には何ができるのだろうか。
てらす峰夢では、子どもの権利を侵害するような声かけや言動はなかっただろうかと、毎月振り返りを行う。一方で、「対等な関係の上で、職員自身が主体性を持つことも子どもの選択肢を広げることにつながる」と櫛田さんはいう。
USJに一度行ってみたら楽しくて、それしか知らない子どもは「また行きたい」と言うかもしれません。でも、職員であればディズニーランドという別の選択肢を知っていて、提示する事ができます。最終的に決めるのは子どもたちですが、大人が関わることで、二つの選択肢が生まれるわけですよね。そうやって世界が広がっていくんだと思うんです。
子どもたちは家庭の中で、自己決定をして修正をする、その繰り返しの体験をして社会に出ていく準備をします。社会に一歩出れば、もっと多くのことを自分で選択しながら生きていかなければなりません。その勇気が湧くよう、てらす峰夢でいろんな成功体験を積み重ねられるようにしたいんです。

子どもの権利を学ぶことから始めよう
子どもにとって、安心して過ごせる“家庭”とは何なのか。櫛田さんの話からは、この言葉の本当の意味を考えるヒントがいくつも見えてくる。
社会的養護の中で生活をしている子ども、親と共に暮らしている子ども、それぞれ環境は異なるが、傍にいる大人が大切にしたい姿勢や考え方に本来大きな違いはないはず。ならばそれは、ハードのあり方や立場に関係なく、一人ひとりの学びや行動で変えていける。
まず大人が、子どもも権利の主体者であると表明した、「子どもの権利条約」 (児童の権利に関する条約)をきちんと学ぶことです。1989年に国連で採択され、1994年に日本が批准してからも30年が経ちますが、まだまだ浸透していません。お互いの権利を尊重し合うためにはどうしたらいいか、これを読み解きながら、もっとみんなで考えていきたいですね。

これまで〈みねやま福祉会〉では、多くの子どもたちの傷つきからの回復をサポートし、社会に羽ばたいていくお手伝いをしてきた。新たな施設、てらす峰夢にも一定の手応えを感じられるようになった今、実践を通じて得られた気づきや学びを外に伝えていくことも、児童養護施設としての役割ではないかと櫛田さんは考え始めている。
ソーシャルワークスキルを持った人が学校や地域の居場所にもっといれば、要保護家庭の子どもにより適切な支援が提供できるんです。特に社会的養護に携わった実経験のある人は、一般に「問題」とされる子どもの行動に対しても、個々の背景を踏まえた上での関わりができます。施設はつい内側に閉じがちですが、そうやって僕らの専門性を地域に開いていくことは大事だと思います。

社会的養護に関わる人々の発信を、子どもに関わる多くの大人が受け取り、実践することができたら。一人ひとり安心して育つことのできる場が今よりも増え、“家庭”という言葉自体にも、互いの権利を尊重しあう関係性が意味として取り戻されていくのではないだろうか。
子どもは幼く、か弱く、守るべきもの。確かにその面はあるが、同時に子どもは一人の人間であり、権利を持つ主体者だ。そのことを、どうしても立場が強くなりがちな大人こそが肝に銘じないといけないのだと、何度も反芻しながらてらす峰夢をあとにした。
Profile
![]()
-
櫛田啓
てらす峰夢(児童養護施設)施設長
社会福祉士。2025年6月より、社会福祉法人みねやま福祉会 理事長。出身は京都府京丹後市峰山町。学生時代に「Jリーガー」を夢見てサッカーに明け暮れたのち、恩師の一言から「福祉」の道を志すことに。大阪や福岡での生活を経て、10年振りに帰郷し故郷の衰退を目の当たりにした時、自らの運命を受け止める覚悟を決める。現在は、子ども・大人・お年寄りという世代に関わらず、また、年齢や疾患、障がいの有無に関わらず、地域の中で人と人の支え合いを大切にする「ごちゃまぜ」の社会づくりを通じて、人々のこころ豊な暮らしの創造に貢献する。社会福祉の変革に取り組む職員の想いを社会に届けるイベント「社会福祉HERO’S TOKYO 2018」初代ベストヒーロー賞受賞。
Profile
- ライター:北川由依
-
「いかしあうつながりがあふれる幸せな社会」を目指すWebマガジン「greenz.jp」や京都で暮らしたい人を応援する「京都移住計画」などで、執筆と編集をしています。京都を拠点に全国各地の人(法人)や場を訪ねがら、人とまちの関わりを編む日々。イチジクとカフェラテが大好きです。
この記事の連載Series
連載:こここスタディ
![]() vol. 282025.09.22「男らしさ」で誰かを傷つけたくない、どうすれば? 文筆家、教育学者、写真家、編集者によるおすすめの本
vol. 282025.09.22「男らしさ」で誰かを傷つけたくない、どうすれば? 文筆家、教育学者、写真家、編集者によるおすすめの本![]() vol. 262024.12.06差別と関係のない立ち位置ってあるの? 社会のあり方に矢印を向けて考える
vol. 262024.12.06差別と関係のない立ち位置ってあるの? 社会のあり方に矢印を向けて考える![]() vol. 252024.12.06差別ってなんだろう? 現代社会における差別の研究者 阿久澤麻理子さんをたずねて
vol. 252024.12.06差別ってなんだろう? 現代社会における差別の研究者 阿久澤麻理子さんをたずねて![]() vol. 242024.08.14正しい答えを刷り込むのではなく、自分で選ぶ手助けをする「包括的性教育」とは?
vol. 242024.08.14正しい答えを刷り込むのではなく、自分で選ぶ手助けをする「包括的性教育」とは?![]() vol. 232024.07.31「性教育」という言葉から何を想像する? 教育学者 堀川修平さんによる「包括的性教育」解説
vol. 232024.07.31「性教育」という言葉から何を想像する? 教育学者 堀川修平さんによる「包括的性教育」解説![]() vol. 222024.07.17「創造性」はどう育まれる? ブルーノ・ムナーリの軌跡から──デザイナー、現代美術作家、教育者のまなざし
vol. 222024.07.17「創造性」はどう育まれる? ブルーノ・ムナーリの軌跡から──デザイナー、現代美術作家、教育者のまなざし![]() vol. 212024.03.30「個人の心の問題」の多くは環境や政治の問題でもある〜「あなたのため」というバウンダリーの侵害〜
vol. 212024.03.30「個人の心の問題」の多くは環境や政治の問題でもある〜「あなたのため」というバウンダリーの侵害〜![]() vol. 202024.03.26自分と他者を区別する境界線「バウンダリー」とは?ソーシャルワーカー鴻巣麻里香さんによる解説
vol. 202024.03.26自分と他者を区別する境界線「バウンダリー」とは?ソーシャルワーカー鴻巣麻里香さんによる解説![]() vol. 192024.02.01「昔好きだった作品」の表現に戸惑ってしまったら? フィクションが与える2つの影響──文学研究者・小川公代さん
vol. 192024.02.01「昔好きだった作品」の表現に戸惑ってしまったら? フィクションが与える2つの影響──文学研究者・小川公代さん![]() vol. 182023.12.15「合理的配慮」は「ずるい」「わがまま」なのか? インクルージョン研究者 野口晃菜さんによる解説
vol. 182023.12.15「合理的配慮」は「ずるい」「わがまま」なのか? インクルージョン研究者 野口晃菜さんによる解説![]() vol. 172023.04.21“できる/できない”の社会を「ヨコへの発達」で問い直す。社会福祉の父・糸賀一雄を、垂髪あかりさんが研究する理由
vol. 172023.04.21“できる/できない”の社会を「ヨコへの発達」で問い直す。社会福祉の父・糸賀一雄を、垂髪あかりさんが研究する理由![]() vol. 162023.02.08「やさしい日本語」ってなに? 言語学者・庵功雄さんに聞くコミュニケーションの本質
vol. 162023.02.08「やさしい日本語」ってなに? 言語学者・庵功雄さんに聞くコミュニケーションの本質![]() vol. 152023.01.27人を見た目で判断することって全部「差別」になるの? 社会学者 西倉実季さんと、“ルッキズム”について考える
vol. 152023.01.27人を見た目で判断することって全部「差別」になるの? 社会学者 西倉実季さんと、“ルッキズム”について考える![]() vol. 142023.01.16自分の気持ちを話さない自由がある。NPO法人ぷるすあるはと一緒に考えた“きもち”との付き合い方
vol. 142023.01.16自分の気持ちを話さない自由がある。NPO法人ぷるすあるはと一緒に考えた“きもち”との付き合い方![]() vol. 132022.12.14“障害”ってそもそも何だろう? 困難の原因を「社会モデル」から考える──バリアフリー研究者・星加良司さん
vol. 132022.12.14“障害”ってそもそも何だろう? 困難の原因を「社会モデル」から考える──バリアフリー研究者・星加良司さん![]() vol. 122022.11.29「ちゃんとしなきゃ」の呪いをとくには?福祉社会学者 竹端寛さん× 僧侶 松本紹圭さん
vol. 122022.11.29「ちゃんとしなきゃ」の呪いをとくには?福祉社会学者 竹端寛さん× 僧侶 松本紹圭さん![]() vol. 112022.10.27“ありのままの自分”を大切にするって、どういうことだろう? しょうぶ学園施設長 福森伸さんをたずねて
vol. 112022.10.27“ありのままの自分”を大切にするって、どういうことだろう? しょうぶ学園施設長 福森伸さんをたずねて![]() vol. 102022.09.27「福祉の現場」と「芸術」の根っこには通ずるものがある? 福祉環境設計士 藤岡聡子さんをたずね、「ケアの文化拠点」ほっちのロッヂへ
vol. 102022.09.27「福祉の現場」と「芸術」の根っこには通ずるものがある? 福祉環境設計士 藤岡聡子さんをたずね、「ケアの文化拠点」ほっちのロッヂへ![]() vol. 092022.09.07“健康”ってなんだろう?ケアの文化拠点「ほっちのロッヂ」紅谷浩之さんをたずねて
vol. 092022.09.07“健康”ってなんだろう?ケアの文化拠点「ほっちのロッヂ」紅谷浩之さんをたずねて![]() vol. 082022.08.12弱さは個人の問題ではなく、構造上の問題だ。公認心理師・臨床心理士 信田さよ子さんと考える“弱さ”のこと
vol. 082022.08.12弱さは個人の問題ではなく、構造上の問題だ。公認心理師・臨床心理士 信田さよ子さんと考える“弱さ”のこと![]() vol. 072022.07.28“違う“の不安をどう乗り越えればいい? グレーではない「色」で表現する発達の特性──星山麻木さん
vol. 072022.07.28“違う“の不安をどう乗り越えればいい? グレーではない「色」で表現する発達の特性──星山麻木さん![]() vol. 062022.04.12「私はどう生きたらいい?」を、一人で抱えない社会へ。医師・西智弘さんに聞く、地域活動と“ケア“の文化づくり
vol. 062022.04.12「私はどう生きたらいい?」を、一人で抱えない社会へ。医師・西智弘さんに聞く、地域活動と“ケア“の文化づくり![]() vol. 052022.03.22偏見がない人はいない。川内有緒さん×木ノ戸昌幸さん『わたしの偏見とどう向き合っていく?』イベントレポート
vol. 052022.03.22偏見がない人はいない。川内有緒さん×木ノ戸昌幸さん『わたしの偏見とどう向き合っていく?』イベントレポート![]() vol. 042022.02.04居場所・つながり・役割・生産性。「望まない孤独」をめぐる対談でみえたものとは?吉藤オリィさん×奥田知志さん
vol. 042022.02.04居場所・つながり・役割・生産性。「望まない孤独」をめぐる対談でみえたものとは?吉藤オリィさん×奥田知志さん![]() vol. 032021.10.26大切なものを失った悲しみや痛みと共に生きていくには? グリーフサポートが当たり前にある社会を目指す 尾角光美さんをたずねて
vol. 032021.10.26大切なものを失った悲しみや痛みと共に生きていくには? グリーフサポートが当たり前にある社会を目指す 尾角光美さんをたずねて![]() vol. 022021.06.24差別や人権の問題を「個人の心の持ち方」に負わせすぎなのかもしれない。 「マジョリティの特権を可視化する」イベントレポート
vol. 022021.06.24差別や人権の問題を「個人の心の持ち方」に負わせすぎなのかもしれない。 「マジョリティの特権を可視化する」イベントレポート![]() vol. 012021.04.15さまざまな側面をもつ「わたし」と「あなた」をそのまま大切にするには? 美学者 伊藤亜紗さんを訪ねて
vol. 012021.04.15さまざまな側面をもつ「わたし」と「あなた」をそのまま大切にするには? 美学者 伊藤亜紗さんを訪ねて