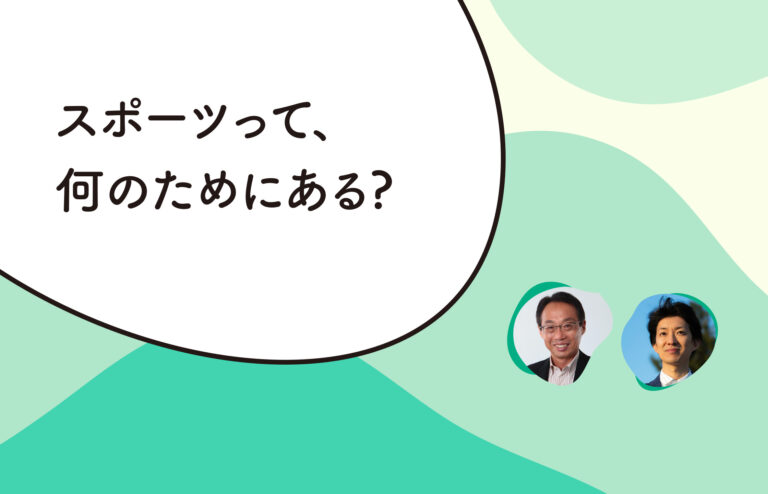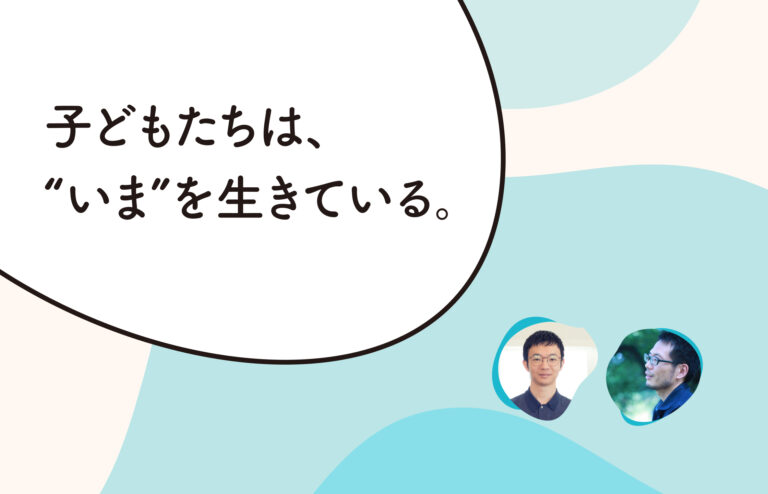大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 写真家/訪問看護師 尾山直子さんをたずねて こここインタビュー vol.30
祖父の死を経験して以来、老いや死に対するどうしようもない恐れが、私の中で日々膨らんでいる。
若い頃からブティックを経営し、いつもきちんとした格好をしていた祖父。背筋もしゃんとしていて、水彩画を描くことと英語の勉強を趣味にする、かっこいい人だった。
そんな祖父も、だんだんと身体が衰え、ひとりでの暮らしにほころびが生じているのは、たまにしか会わない私ですら何となく感じていた。
何でも自分でできる人だったからこそ、日々できないことが増えていくことが、祖父自身、とても辛かったのだと思う。と同時に、近くにいた母もまた、娘としてたくさんの変化に直面してきたはずで、そのたびにどんな気持ちだったのか、想像すると今でも胸が苦しくなる。
人は老いや病気によって、いのちを閉じるまでにたくさんの変化が起こる。それは抗えないことなのだと、理解しているつもりだ。それでも、大切な人の変化を目の当たりにしたら、心は冷静ではいられない。
訪問看護師であり写真家でもある尾山直子さんは、さまざまな人の暮らしやいのちが閉じる瞬間に寄り添い続けてきた。そして、本人を支える人の思いや葛藤にふれてきた人でもある。
いのちの終わりに向かっていく大切な人の変化と、どう向き合っていけばいいのか。本人の気持ちを尊重しながら、残された時間をともに穏やかに過ごすためには、何ができるのか。尾山さんへのインタビューを通して、考えてみたいと思う。
※尾山さんの活動については、こちらの記事をご覧ください。
「暮らしのなかで閉じる命をつないでいく 写真家/訪問看護師 尾山直子さん」
私たちはすでに“老いの途中”にいる
人はいのちを閉じるまでにどんな変化を辿るのか。なんとなく、右肩下がりにゆるやかな曲線を描くように衰えていくイメージはあるけれど、実際のところは意外と知らない。
尾山さんが制作に携わった冊子『人のさいご』はまさに、いのちが閉じていく過程で起こる自然な変化について、丁寧に綴られた一冊だ。担当する患者さんたちから“人は死ぬときにどう変化していくのか”と問われてきた経験から生まれたという。

たとえば、自然な老いや認知症では身体の機能*が少しずつ衰えていき、癌の場合は直前まで身体の機能が保たれる傾向があります。
図のように老いや病気によって異なったプロセスを経ていきますが、その先に訪れる「人のさいご」は、自宅で医療やケアを受けながら自然にいのちが閉じられていく場合、おおむね共通した経過を辿っていきます。
*身体の機能:歩くことや声を出すこと、飲み込むことなどの身体の動きや、食べ物を消化したり腎臓で尿をつくったりする内臓の動きなどをいいます。
(医療法人社団プラタナス 桜新町アーバンクリニック発行『人のさいご』p.8)

尾山直子さん(以下、尾山):人間は20歳くらいをピークに、少しずつ老いていっているんですよね。たとえば、40歳くらいになると、白髪が増えたり、20代のときのような無理がきかなくなってきたりするじゃないですか。私たちもすでに今“老いの途中”にいて、日常の小さな変化が続いた先に、いのちの終わりがあるんです。

変化が突然やってきたと思うからこそ、私たちは戸惑ってしまうのかもしれない。
実際は身体も気持ちも、日々少しずつ、少しずつ、それまでとは変わっていっている。考えてみれば、前より肌が乾燥するようになったり、揚げ物を食べるとすぐに胃もたれしたりするのだって、まさに老いの途中に起きている変化だ。
そしていのちを閉じることもまた、日々の変化の延長線上にある、人間としてごく自然なものなのだと、あらためて気づかされる。
大切な人の最期を支える「家族」は、血縁者だけじゃない
訪問看護師として、これまでにたくさんの患者の自宅を訪問し、慢性期(病気の進行はあるものの病状は比較的安定していて穏やかな時期)の疾患のケアや、終末期における看取りをしてきた尾山さん。
看取りの場にいるのは、本人と血縁関係のある家族であることが多いものの、そうではないケースも何度も経験してきた。たとえば、友人が看取る場合もあれば、一人暮らしの方などで、看護師や医師、介護職などの専門家のみで看取ることもある。
そうした経験も踏まえ、『人のさいご』の序盤では、「家族」という言葉を「あなた(本人)が信頼している誰か」と定義している。
尾山:パートナーと別れて、お子さんも早くに亡くした方の訪問看護を担当していたことがありました。本人は「まあ、俺はひとりでいくわ」なんて言っていたけれど、アパートでお看取りをしたときに、ヘルパーのおばちゃんがすごく泣いてくれたんですね。それを見て、「あ、家族だったんだな」って。この患者さんには、亡くなった今もこうやって泣いてくれる人がいたんだと思って、私自身すごく救われたというか。
そうやって、血縁関係がなくても相手を大切に思って、最期を支える人たちがいて。本人と、それを看取る家族というふうに分けたときに、こぼれ落ちてしまう人たちの存在や気持ちを大切にしたかったんですよね。だからこそ、そばにいて信頼し合えている人たちを「家族」って言っていいんじゃないかなって。

血縁関係がなくても「家族」と呼べるくらい、人の最後に真摯に向き合い、支えてくれる人たちがいる。それは、大切な人の変化に対する戸惑いや悲しみをひとりだけで抱えず、分け合える人がいるということでもある。
大切な人の最後の望みは、できるだけ叶えたいと思うからこそ、ケアや看取りに対して大きなプレッシャーを感じてしまうこともあるかもしれない。そんなとき、信頼できる専門家のサポートを受けながら、ひとつのチームとして一緒にやっていけたら、とても心強いはずだ。
変化の状況に応じて頼れる専門家たち
尾山さんが制作にかかわった、在宅療養のためのガイドブック『LIFE これからのこと 在宅療養・ACP(アドバンス・ケア・プランニング)ガイドブック』には、心身の変化に応じてどんな専門家に頼れるのか、具体例が書かれたページがある。


医療や介護の専門家のサポートを得たいと思ったときのために、まず覚えておきたいのが「地域包括支援センター」だ。身体が動きづらくなり、生活にほころびを感じはじめた段階で、本人が住むエリアの「地域包括支援センター」に相談するといいそう。専門知識を持った職員が、状況に合ったサービスや制度を無料で教えてくれる。今後ひとりで暮らすことに不安を感じている場合は、「どんな施設が自分に合っているのか」なども、この窓口で相談できる。
尾山さんのような訪問看護師がサポートに入るのは、本人が自宅で暮らすことを望んだときだ。在宅医療の場合は、ケアマネジャーを中心に、医師や看護師、訪問介護員(ホームヘルパー)などが連携しながら、本人や家族が穏やかに最期を迎えられるよう、サポートしてくれる。
尾山:私が訪問看護で自宅に行く段階では、すでにケアマネジャーさんがいらっしゃることが多いんですが、家族の中に馴染みすぎて、名刺をいただくまでどの方がケアマネジャーさんなのかわからなかったりして(笑)。
ヘルパーさんも、それぞれに持ち味があるんです。てきぱきしていて受け答えが気持ちがいいとか、熟練の料理の技で胃袋を掴んじゃうとか。訪問看護師も、訪問診療の医師も、皆さん違う役割を持ちながら本当に親身になって本人や家族に接してくれる方ばかりだなと思います。

尾山さんは訪問看護師として、本人やその家族たちの“こうありたい”という気持ちに寄り添いながら関わっていく。
親密な関係性を持ち、死の迎え方の希望まで話し合って決めている家族の場合は、それを実現できるようにサポートする。一方で、本人と家族だけだと話しづらそうな場合は、間に入って上手く橋渡しをすることもある。
尾山:他人だから本音を言えるってことも、やっぱりあるんですよね。たとえば、「自分が亡くなったあと、家族の心の負担を少なくするために、みんなには『大丈夫』って言っていたい。でも、本当はちょっと辛いんだよね」とおっしゃる方がいたりとか。それは家族側も同じで、「本人にはケアすることに負担を感じていると思ってほしくないから『大丈夫』って言いたい。でも正直ちょっと大変なんだよね」って。
そういう本音をこぼせる相手として、私たちのような医療やケアの専門職が存在している部分もあると思っています。必ずしも本音をぶつけ合うことを良しとするんじゃなくて、本人や家族、それぞれの“こういう自分でありたい”も含めて、私たちは支えたいなと。
「最期の時間をどう過ごしたいか」は、これまでの人生から見えてくる
どんな医療やケアを望むのか、そして、最期の時間をどう過ごしたいのか。その考えや根本にある思いを、家族やパートナーなどの大切な人たち、医療・介護の担当者と繰り返し話し合うことを、「ACP(アドバンス・ケア・プランニング、人生会議)」という。
大切な人の思いや願いを尊重したいと考えると、本人が自分の意思で選択できるうちに、今後のことをできるだけ話し合っておきたいところ。医療・介護を担当してくれるスタッフにとっても、この本人の思いや願いがケアの方針を決める上でも大事なカギになる。
ただ、話し合うことが大事だとわかってはいても、切り出すにはなかなか勇気がいるテーマでもある。ともすれば、今を懸命に生きている本人を傷つけてしまわないかと、少し躊躇ってしまう。
どんなタイミングで、どう切り出すといいのだろう。
尾山:たしかに、難しいですよね。でも、きっかけはテレビや映画でも何でもいいんです。介護について特集していたりとか、誰かを看取るシーンが出てきたりとか。そういうきっかけをしっかり掴むことに意識的であることが大事なのかなと思います。
先ほど紹介した、『LIFE これからのこと 在宅療養・ACPアドバンス・ケア・プランニング)ガイドブック』 の中に、話し合いをする上での助けになりそうなページがある。その名も、「価値観のかけら」。

全部で8ぺージにわたる質問は、7つのテーマに分かれていて、それぞれに答えを直接書き記せる余白が並んでいる。
「好きな食べ物は?甘党?辛党?」や「好きな匂いは?」などライトなものから、「人生の譲れないこだわりは?」「どういう自分でありたい?」「あなたの大切な人はだれ?」など、ちょっと踏み込んで考えさせられるものまでさまざま。
尾山:死というのは、暮らしの延長線上にあるもの。今までどう生きてきて、何を大事にして、どんな価値観を持ってきたかを聞いていけば、「最期をどう過ごしたいか」の答えが自ずと見えてくるところもあるんですよね。
ちょっと遠回りなようだけど、一つひとつの小さな「価値観のかけら」を集めていくと、その人らしさや大事にしたいものが浮かび上がってくる。尾山さんも、自分の親御さんにこの「価値観のかけら」を書いてもらったら、「結構よかった」らしい。
尾山:きっと親としても、自分から子どもにわざわざ話すことには躊躇してしまうんじゃないかなと。だから、私から「読みたいから、これ書いてよ」って意思表示をしてみたんです。そうしたら一生懸命たくさん書いてくれたから、「ああ、伝えたい思いがあったんだな」と思って。

たしかにこれは、将来の変化に備えることを目的としたものではありつつ、シンプルに相手をより深く知るためのツールにもなる。「大切だから、あなたのことをもっと知りたい」という気持ちでコミュニケーションを始められたら、すごく素敵だなと思った。
もちろん親に限らず、パートナーや友人に書いてもらってもいい。大切な人とそれぞれ書いてお互いに見せあう、というのもいいかもしれない。
そうして大切な人が自分の手で書き残してくれたものは、そばで見守る人たちにとって、どのように向き合えばいいのか考えるための羅針盤のような存在にもなるという。尾山さんは以前担当していた患者さんと、その家族のエピソードを教えてくれた。
尾山:その方に「価値観のかけら」を書いてもらったときの、「家が安住の場です」という言葉が印象に残っていて。でもそのときは、いろいろな事情があり自宅で暮らすのが難しく、グループホームに入ることになったんです。
その後一度入院をする機会があり、転院するかどうかを決めるタイミングで、娘さんが1〜2年ぶりに「価値観のかけら」を読み返してくれたんですね。「そうだ、家がいいって言ってたよね」って。その頃にはある程度家族の事情も解決していたため、本人の希望をあらためて確認した上で、在宅医療に移行することに。そのまま、自宅で最期を看取りました。
そこで感じたのが、本人が書き残した言葉の強さです。少し経ってから読み返したとき、状況が変わっていれば、新たに捉えなおせるかもしれない。亡くなったあと、本当にこれでよかったのかと考えてしまうときも、「本人がこう書いていたもんね」と思える。そういう羅針盤みたいなものになってくれるんじゃないかなって。
もちろん、本人が一度こう書いたからといって、勝手に話を押し進めていいというわけではない。人の気持ちは揺れるし、時間が経てば考えも変わる。だから、「価値観のかけら」も何度書き直してもいいし、繰り返し話し合いをしていくことが大事だと、尾山さんは話す。
目をそらさずに向き合うことで、いのちの終わりの見え方が変わる
今や、8割以上の人が病院や施設で最期を迎える時代(※)。家族だとしても、老いて、いのちを閉じていくまでの変化のプロセスを目の当たりにする機会は、とても少ない。たまにお見舞いや面会に行くことはあっても、じっくりと腰を据えて話すこともあまりないかもしれない。
※厚生労働省「厚生統計要覧(令和5年度)」及び「在宅医療の最近の動向」を参照。
そのように変化のプロセスが日常と切り離された状態で、いきなり大切な人のいのちの期限が迫っている状況に直面すれば、戸惑うのは当たり前のこと。でも、「大切な人との残された時間を、ただ戸惑うことで終わらせてしまったらすごくもったいない」と尾山さんは言う。
尾山:時間が限られているからこそ、できればその戸惑っている時間を、これから相手とどう過ごしたいのかを考えることに使いたいじゃないですか。
そこでもし、今まで積み重ねてきた時間があれば、いざというときも、ある程度心づもりができているかもしれない。だから、大切な人の変化にも目をそむけず、向き合う機会をできるだけたくさん持つことができていた方が、のちのちの後悔を少なくできると思うんですよね。

大切な人の変化と向き合うのは辛いし、つい目をそらしたくもなってしまう。でも、いざというときに過度に戸惑わず、残された時間をともに穏やかに過ごすためには、前々から自分のできる範囲で関わっていくことが大事なのだ。
それは、本人と会って話をすることかもしれないし、専門家に教えてもらってケアの一部を自分で担ってみることかもしれない。小さなことを積み重ね、大切な人の最期を受け入れるための心を耕していく。
尾山:介護も看取りも、ケアする側が一方的に与えることばかりじゃないんです。老いて、いのちを閉じていく。誰もがいつかは辿るその道のりを、先に歩んでいる人たちが、全身を使って私たちに教えてくれているということだから。
それに対して目をそらさず向き合うことは、本当に大きな学びになるし、いのちの終わりを受け入れる土壌をもつ人になることは、人間としての成長につながる。相手から受け取ることもたくさんあるんですよね。

それを聞いて、老いや死に対して、どうしようもなく怖いと思ってしまうほの暗い気持ちに、光が差したような気がした。
これまでずっと、老いや病いは身体の自由を奪い、その人を変えてしまうものだと思っていた。でもそれもきっと、距離があるところから断片的に見ていたからこそ、恐怖の部分だけが膨らんでしまっていたのだと思う。もしかしたら母も私の知らない間に、祖父の変化を間近で見続けながら、少しずつ覚悟を育てていたのかもしれない。
もちろん、大切な人が老いて、亡くなることはどうしようもなく悲しいことだ。それでも、身体をもって「人のいのちがどう閉じられていくのか」を教えてくれているのだとしたら、その変化にもきちんと向き合いたいと、今は思い始めている。必要なときは、信頼できるケアの専門家たちにも力を借りながら。
尾山:どうしたって、みんな何かしらの後悔はするものなんです。大切な人が生きていてくれる間に、もっとこうすればよかったって。でも、その後悔をなるべく少なくすることはできるから、私も訪問看護師としてできる限りサポートしたいなと思っています。
Profile
![]()
-
尾山直子
看護師/写真家
1984年埼玉県生まれ。看護師/写真家。「桜新町アーバンクリニック」在宅医療部にて訪問看護師、広報として勤務。高校で農業を学んだのち看護師の道に進み、複数の病院勤務を経て2012年より現職。訪問看護師の勤務の傍ら、2020年京都造形芸術大学美術科写真コースを卒業し、現在同大学大学院に在籍。かつて暮らしのなかにあった看取りの文化を現代に再構築するための取り組みや、老いた人との対話や死生観・看取りの意味を模索し、写真を通じた作品制作を行っている。2021年よりデザインリサーチャーの神野真実と共同で写真展「ぐるり。」を開催し、各地を巡回。
- ライター:むらやまあき
-
1995年長野生まれ、フリーのライター・編集者。主にインタビュー記事やエッセイの執筆を行う。関心領域はエンタメ、ローカル、社会課題など。頑張らなくてもしあわせに生きる方法を模索中。
この記事の連載Series
連載:こここインタビュー
![]() vol. 332025.09.26遊びと医療ケアの両立をどう目指す? 「そらぷちキッズキャンプ」の“人を信じて待つ”仕事
vol. 332025.09.26遊びと医療ケアの両立をどう目指す? 「そらぷちキッズキャンプ」の“人を信じて待つ”仕事![]() vol. 322025.03.18言葉を超えて誰もがつながる「身体表現」の魅力とは? 福祉を起点に広がるパフォーミングアーツ、生きづらさを変える可能性
vol. 322025.03.18言葉を超えて誰もがつながる「身体表現」の魅力とは? 福祉を起点に広がるパフォーミングアーツ、生きづらさを変える可能性![]() vol. 312024.10.09なぜ自分に価値があるか確認したくなるんだろう? 勅使川原真衣さんと新澤克憲さんによる「評価」を巡る対話
vol. 312024.10.09なぜ自分に価値があるか確認したくなるんだろう? 勅使川原真衣さんと新澤克憲さんによる「評価」を巡る対話![]() vol. 292024.09.07地域に根ざす園から、子どもも大人も混ざった“絶景“を生み出せたら。〈学校法人thanka〉が新ステートメント「手を繋ぎにいく」に込めた願い
vol. 292024.09.07地域に根ざす園から、子どもも大人も混ざった“絶景“を生み出せたら。〈学校法人thanka〉が新ステートメント「手を繋ぎにいく」に込めた願い![]() vol. 282024.08.30大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 株式会社Blanket 秋本可愛さんをたずねて
vol. 282024.08.30大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 株式会社Blanket 秋本可愛さんをたずねて![]() vol. 272024.07.25気軽な買い物体験から、「未来が良くなる」手応えを。〈フェリシモ〉の新カタログ『GO! PEACE!』制作の裏側
vol. 272024.07.25気軽な買い物体験から、「未来が良くなる」手応えを。〈フェリシモ〉の新カタログ『GO! PEACE!』制作の裏側![]() vol. 262024.04.30蓋された「小さな自分」の声に耳を傾けて。ケアを促す料理レッスンの場、就労支援の場──山口祐加さん×鞍田愛希子さん
vol. 262024.04.30蓋された「小さな自分」の声に耳を傾けて。ケアを促す料理レッスンの場、就労支援の場──山口祐加さん×鞍田愛希子さん![]() vol. 252024.04.10「インクルーシブ」は誰のための言葉? 老舗メーカー〈ジャクエツ〉×医師・紅谷浩之さんの、子どもに“遊びと友だち“を返す遊具
vol. 252024.04.10「インクルーシブ」は誰のための言葉? 老舗メーカー〈ジャクエツ〉×医師・紅谷浩之さんの、子どもに“遊びと友だち“を返す遊具![]() vol. 242024.03.29文化施設のウェブアクセシビリティを向上する。障害当事者との「建設的な対話」に必要なこととは?──伊敷政英さん×森司さん
vol. 242024.03.29文化施設のウェブアクセシビリティを向上する。障害当事者との「建設的な対話」に必要なこととは?──伊敷政英さん×森司さん![]() vol. 232024.03.27だれもが文化でつながるために。クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョーが見据えるこれからの文化施設のあり方とは。
vol. 232024.03.27だれもが文化でつながるために。クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョーが見据えるこれからの文化施設のあり方とは。![]() vol. 222023.12.22人のためってなんだろう? 他者にコントロールされない「LOVOT」から、“人間らしさ“を考える──伊藤亜紗さん×林要さん
vol. 222023.12.22人のためってなんだろう? 他者にコントロールされない「LOVOT」から、“人間らしさ“を考える──伊藤亜紗さん×林要さん![]() vol. 212023.11.08保育料ゼロを実現し、子育てを“みん営化”する。 学童保育施設〈fork toyama〉岡山史興さん
vol. 212023.11.08保育料ゼロを実現し、子育てを“みん営化”する。 学童保育施設〈fork toyama〉岡山史興さん![]() vol. 202023.05.29ともだちってなんだろう? 答えを出す必要はないけれど。新澤克憲さんとテンギョー・クラさんの対話から考える
vol. 202023.05.29ともだちってなんだろう? 答えを出す必要はないけれど。新澤克憲さんとテンギョー・クラさんの対話から考える![]() vol. 192023.05.23歌人・岡本真帆さん×西淡路希望の家・金武啓子さん対談。「感動」の発見、どう他者と分かち合いますか?
vol. 192023.05.23歌人・岡本真帆さん×西淡路希望の家・金武啓子さん対談。「感動」の発見、どう他者と分かち合いますか?![]() vol. 182023.03.20“みる”から始める、アーティストと支援現場のつなぎ役。日常の関係性を変える「TURN LAND プログラム」の挑戦
vol. 182023.03.20“みる”から始める、アーティストと支援現場のつなぎ役。日常の関係性を変える「TURN LAND プログラム」の挑戦![]() vol. 172023.03.15アート活動で、「できる/できない」を揺さぶる。日常の価値を言葉に変えるコーディネーターの役割
vol. 172023.03.15アート活動で、「できる/できない」を揺さぶる。日常の価値を言葉に変えるコーディネーターの役割![]() vol. 162023.03.03唯一の答えを探しすぎていないか? 下地ローレンス吉孝さん×なみちえさんと“わかりやすさ”について考える
vol. 162023.03.03唯一の答えを探しすぎていないか? 下地ローレンス吉孝さん×なみちえさんと“わかりやすさ”について考える![]() vol. 152023.02.15“わたし”と“あなた”それぞれの複雑さを大切にするには?──なみちえさん×下地ローレンス吉孝さんと共に考える
vol. 152023.02.15“わたし”と“あなた”それぞれの複雑さを大切にするには?──なみちえさん×下地ローレンス吉孝さんと共に考える![]() vol. 142022.12.23出会いを広げながら、協働を生む「メディア」を目指して──〈こここ〉シーズン2を振り返る
vol. 142022.12.23出会いを広げながら、協働を生む「メディア」を目指して──〈こここ〉シーズン2を振り返る![]() vol. 132022.12.19働くことも、映画祭も「みんなが心地よい」を目指して。GOOD NEWSとTHEATRE for ALLのインクルーシブな場づくり
vol. 132022.12.19働くことも、映画祭も「みんなが心地よい」を目指して。GOOD NEWSとTHEATRE for ALLのインクルーシブな場づくり![]() vol. 122022.10.14バリアフリーの映画祭を通して、「その人のまま」でいられる社会に。作家・川内有緒さん×THEATRE for ALL・金森香さん
vol. 122022.10.14バリアフリーの映画祭を通して、「その人のまま」でいられる社会に。作家・川内有緒さん×THEATRE for ALL・金森香さん![]() vol. 112022.09.13スポーツの可能性って何だろう? 「プロスポーツ」「ゆるスポーツ」から考える──岡田武史さん×澤田智洋さん
vol. 112022.09.13スポーツの可能性って何だろう? 「プロスポーツ」「ゆるスポーツ」から考える──岡田武史さん×澤田智洋さん![]() vol. 102022.03.31まだみぬ「表現」との出会いを、誰もが体験できる社会へ。障害のある人の芸術・文化活動を支える窓口が全国に
vol. 102022.03.31まだみぬ「表現」との出会いを、誰もが体験できる社会へ。障害のある人の芸術・文化活動を支える窓口が全国に![]() vol. 092022.02.09コロナ禍で「消される」声に、どう耳を傾ける? 次の社会をつくる言葉と対話のあり方──荒井裕樹さん×青山誠さん
vol. 092022.02.09コロナ禍で「消される」声に、どう耳を傾ける? 次の社会をつくる言葉と対話のあり方──荒井裕樹さん×青山誠さん![]() vol. 082021.12.24福祉をたずねて1年。編集部は何に出会い、悩んできた?──〈こここ〉振り返り座談会
vol. 082021.12.24福祉をたずねて1年。編集部は何に出会い、悩んできた?──〈こここ〉振り返り座談会![]() vol. 072021.11.24コロナ禍を経て新たな表現の協働へ ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[後編]
vol. 072021.11.24コロナ禍を経て新たな表現の協働へ ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[後編]![]() vol. 062021.11.24アートプロジェクトは福祉の現場で何を生み出す? ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[前編]
vol. 062021.11.24アートプロジェクトは福祉の現場で何を生み出す? ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[前編]![]() vol. 052021.10.18福祉施設が学びあいの拠点になることで育まれるものとは?ライフの学校・田中伸弥さん
vol. 052021.10.18福祉施設が学びあいの拠点になることで育まれるものとは?ライフの学校・田中伸弥さん![]() vol. 042021.06.03VR認知症を体験して気づいた、わからない世界へ手を伸ばし続ける大切さ。シルバーウッド 下河原忠道さん
vol. 042021.06.03VR認知症を体験して気づいた、わからない世界へ手を伸ばし続ける大切さ。シルバーウッド 下河原忠道さん![]() vol. 032021.04.15まだ名付けられていない感覚に出会う「遊び」の可能性とは? インタープリター 和田夏実さん
vol. 032021.04.15まだ名付けられていない感覚に出会う「遊び」の可能性とは? インタープリター 和田夏実さん![]() vol. 022021.04.15「助けて」とお互いに言い合えるのが、成熟した社会。ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ代表 志村季世恵さん
vol. 022021.04.15「助けて」とお互いに言い合えるのが、成熟した社会。ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ代表 志村季世恵さん![]() vol. 012021.04.15「お笑い」や「演劇」は他者の世界に寄り添うヒントをくれる。りんたろー。さん×菅原直樹さんが語る「介護の話」
vol. 012021.04.15「お笑い」や「演劇」は他者の世界に寄り添うヒントをくれる。りんたろー。さん×菅原直樹さんが語る「介護の話」