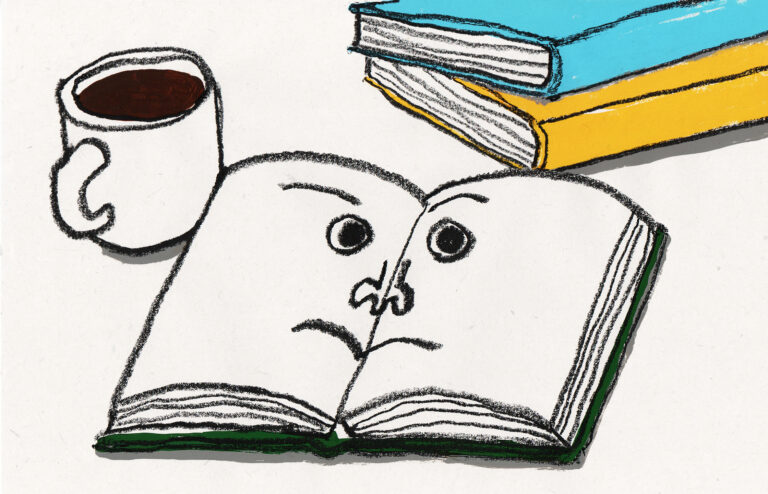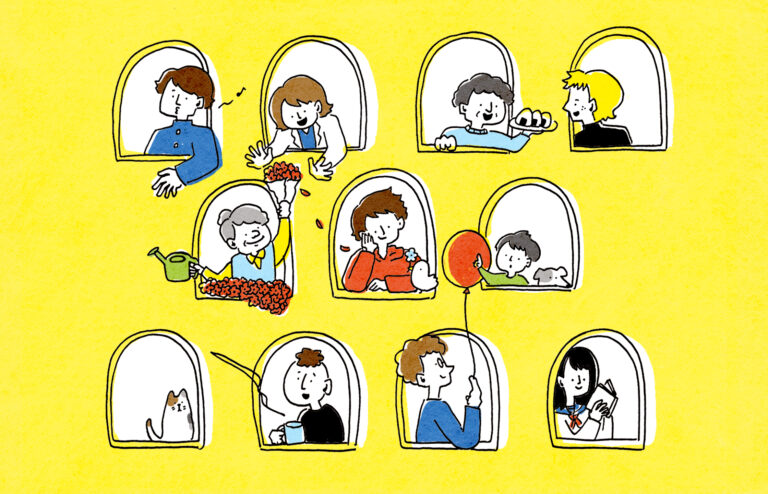差別や人権の問題を「個人の心の持ち方」に負わせすぎなのかもしれない。 「マジョリティの特権を可視化する」イベントレポート こここスタディ vol.02
職場やSNSで見聞きする、さまざまな差別やハラスメント。
「なんでこんなことが起こるのだろう」「もっと平等な社会になったらいいのに」「人としての権利が当たり前に守られるべき」と、当事者の叫びに胸を痛める人は少なくないはずだ。
「私は“中立”。差別なんてしないのにな」と思うことだって、正直あるだろう。
けれど実際には、“中立”で何もしなければ差別にはあたらないという意識そのものが、差別的な社会構造に加担してしまう危険性をはらんでいる。
こう指摘したうえで、問題を個人の態度に由来するものではなく、「マジョリティの特権」から捉えようとするのが、上智大学外国語学部教授の出口真紀子さんだ。
差別や人権の問題は、これまで差別されるマイノリティ側、社会的に弱い立場の人に焦点を当てて論じられてきた。しかし、マイノリティ側が被る不利益の裏側にあるマジョリティの特権について考えなくては問題は解決しない。
そう考える出口さんの視点を学びたいと、こここ編集部は2021年5月9日、彼女が登壇するオンライン講演「マジョリティの特権を可視化する」(対話と共生推進ネットワーク主催)を取材した。
“労なくして”優位性を得ているアイデンティティはどれか
出口さんは幼少期を含め、アメリカで30年間過ごした経験を持つ。自ら「人種的マイノリティ」として、アメリカ人との違いや人種に起因する差別を肌で感じてきたことから、「文化心理学」を学ぶ道を歩む。
さらに研究者として、差別が個人ではなく構造的な問題であるという前提に立ち『特権』(Privilege)について考えるようになった。
『特権』という言葉から、私が教えている学生たちがよくイメージするのは、「学生の特権で学割が使える」など“一時的に”優遇される立場です。ただ、差別の問題を考えるときには、異なった捉え方をしています。
私の定義は「マジョリティ性を多く持つ社会集団にいることで、労なくして得ることのできる優位性」。
一番のポイントは、“労なくして”です。たとえば、セクシュアル・マイノリティと言われる方々が利用できない制度を、シスジェンダー(出生時の性別と性自認が一致している人)・ヘテロセクシュアル(性的指向が異性に向く人)はさほど苦労せず使えたりしますよね。
日本での代表的な例が結婚制度です。努力して手にしたものではなく、たまたまその属性を持って生まれたことで得られる恩恵が『特権』なんです。

この『特権』は、既に持っている側には意識しづらく、「持っていない人にははっきりと感じられるものだ」と出口さんは話す。
わかりやすくたとえるなら、“自動ドア”。自分が特権を有する側に属していれば、前に向かって進みたいときドアが勝手に開いてくれるし、ドアの存在そのものに気づかないことすらある。
ところが、特権を持たない人には同じドアが自動で開かない。他の人が横でスムーズにドアを通り抜けていくさまを見ながら、「これを自分の手でこじ開けていかないといけないんだ……」と思い知らされてしまう。

ここで“自動ドア”の恩恵を受けやすいのが、いわゆる「マジョリティ」だ。もともと多数派を意味するこの言葉は、日本では差別の問題を考えるときにそのままの意味で使われている。
しかし、出口さんが「マジョリティ」という言葉を使うときには、英語の「dominant identity」(支配的なアイデンティティ)の意味を込めるときが多いという。
「マジョリティか、マイノリティか」は、ここでは数の問題ではなく、権力を「より多く持つ側か、持たない側か」と考えます。
また、この2つは「どちら側なのか」が明確にわかれるものではありません。私たちはそれぞれ多様なアイデンティティを抱え、マジョリティ性とマイノリティ性を両方持って生きているんです。
たとえば、差別の問題に絡みやすい7つのアイデンティティをこれから挙げます。そのなかで自分はマジョリティ性をいくつ、マイノリティ性をいくつ抱えているか、まずは数えてみてください。

もし、この7つすべてがマジョリティ側だという人は、実は今の社会ではかなり強者側にいると言えます。私自身はジェンダーが女性で、その他がマジョリティ側に属しています。
特権は自覚が難しいため、こうして意図的にアイデンティティを振り返らないとなかなか気づくことはできません。差別や人権を考える上で、この視点は特に重要だと思っています。
差別と特権は、「表裏一体」の関係
「差別をしてはいけません」。学校や家庭における教育のなかで、多くの人はこのように学んできているが、差別は一向になくならない。出口さんは、差別を「個人の心の持ち方」に負わせ過ぎていることが、こうした状況を生んでいると説明する。
たとえば侮辱的な発言をしたり、人を排除したりしたら、「その行為をとった人が悪い」と考える。個人間でイメージされやすいこうした差別は、社会心理学では『直接的差別』と言われるものだ。だが、これは3つに分類される差別形態の1つに過ぎないという。
『直接的差別』以外に、『制度的差別』と呼ばれるものがあります。法律、教育、政治、メディア、企業といった大きな枠組みのなかで、もっとシステマティックに行われるものですね。
個人の意識でなくすことが難しく、既存の仕組みや育成カリキュラムから時間をかけて変えていく必要があります。
もう1つは、『文化的差別』です。人々が無意識に共有している価値観、「こうするのが当然だ」といった空気感が、逸脱する存在や行為をタブーにしていきます。
「シスジェンダー・ヘテロセクシュアルが普通である」「男は仕事、女は家庭」などの考え方はその代表ですね。こういった価値観は、差別を訴えることすらもタブー視されるので、マイノリティにとっては非常に息苦しい状況をつくってしまいます。
こうした抑圧構造に目を向けないと、差別を本質的に理解することはできません。構造の恩恵を最初から受けている人だけが前に進める、そんな状況がいつまでも続いてしまうことになります。
差別が生まれるとき、そこには何らかの理由で差別された「かわいそうな人」と、そこに関係のない「ふつうの人」がいる、という理解をされることがある。だが、出口さんはこの発想こそが問題だと指摘する。
構造的な差別を受ける人がいるのであれば、その裏には必ず「構造のおかげで差別を受けずにすんでいる」人がいるからだ。
たとえばマイノリティは、個人としてよりも、何らかの属性の人として見られやすくなります。実際、私はアメリカで「日本人として」「アジア人として」の意見をよく求められました。
けれど、隣に座っている白人は決して「白人としての意見はどう?」と聞かれることはないんですよね。
そのようにマイノリティが感じているものを、マジョリティは全く感じなくてすむ。この非対称性にマジョリティが気づくことは簡単ではありません。けれど気づかない限り、自らが「免れているもの」や、それによって手にした優位性を理解することはできないんです。
“気づかないもの”に気づくために
ではマジョリティ側にいる人は、どうすれば“自動ドア”の恩恵を受けていると気づくことができるのか。出口さんはいくつかの事例をヒントとして提示していく。
その1つが、アメリカの女性学の研究者ペギー・マッキントッシュさんが1988年に発表した『White Privilege: Unpacking the Invisible Knapsack』(白人の特権:見えないナップサックをあけてみる)という文章。
白人女性である彼女は、男性中心の社会でマイノリティだと思っていた自分にも、実は「住みたい場所に同じ人種と住める」「自分たちの民族・人種の存在を肯定する教材を与えらえる」「政府を堂々と批判できる」など、非白人女性にはない特権があると述べている。
彼女がそういったことに気づけたのには、ある体験があった。1970年代に、それまで男性中心で構成されていた大学カリキュラムを改革する委員会を率いたときのことだ。
そこに集まった男性教員は「とてもいい人たち」で先進的な考え方を持っていたという。にもかかわらず、1年後に女性メンバー全員が男性メンバーを抑圧的に感じ、プロジェクトは失敗に終わった。
「あんなにいい人ばかりだったのになぜ……」とマッキントッシュさんは何年も悩みながらも、議事録を詳細に検討するなかで、たとえば女性作家の小説を教材に入れようという提案を「文学の基礎を学ぶ課程に周縁的なものは入れられない」と却下するような抑圧的言動の数々を見出します。
並行して非白人女性から「白人女性は抑圧的だ」と非難される経験をします。そのときに彼女は、「そんなことはない」と不満に思う一方で、「これは同じことかもしれない」と気づくわけです。
委員会のとき、女性メンバーたちが主張した「男性の抑圧性」には彼女自身も同感していました。ならば同様に、白人女性に対する非白人女性の批判にも、必ず正当な理由があるはず。「いい人であること」と「抑圧的であること」は両立するんだと、彼女は考えるようになりました。
エピソードからだけではなく、マジョリティの特権を擬似的に体験できる方法も出口さんは紹介した。教室などで行えるアクティビティで、用意するのは「ゴミ箱」と1人1枚の「紙」。それぞれの座席から、丸めた紙を前のゴミ箱に向かって投げてもらい、入った人は「社会階層を上がることができる」と仮定する。
これを全員でやると、ゴミ箱から遠い座席の人はほとんど入らず「不公平だ」と声を上げる。だが、投げ入れることのできた人が多かった前列からは、入らなかった人も含めてそういった声は上がらない。ただ自分とゴミ箱だけに意識を向けて、一生懸命投げ入れることだけ考えるのだという。

このアクティビティで、“位置”が表すのがマジョリティ性とマイノリティ性だ。前列にいけばいくほどマジョリティ側で、まさに特権を有する。一方で“投げる”という行為は、それぞれの立場での努力を示すと出口さんは説明する。
一番前にいる人たちも何もしていないわけではありませんが、それほどたくさんの努力をしなくても、入れることは難しくない。ところが、後ろに行くほど相当訓練しないと投げ入れることはできないでしょう。
このとき、後ろになればなるほど出てくるのが、「何に向けて投げているのかよくわからない」「投げてもどうせ入らない」といった諦めの声です。なかには、「前の人に当たるかもしれない」と遠慮する人も現れてきます。
同時に気づくのは、目標がはっきり捉えられなくても、「全体の仕組み」は後列の人々のほうが見えているということだ。前のほうの人は、自分の背後がどうなっているか、そもそも振り向く必要すらない。
これはフェミニストの思想家、サンドラ・ハーディングさんの『立場理論』にも通じる。権力を持つ者は、自分の下にいる人間について知ろうとしないし、自分が強者としての地位につけている構造について知ろうとしない。それでも問題なく生きられるからだ。
しかし、権力を持たない(あるいは制限されている)者は、権力を持つ側の考え方を「熟知せずには生きられない」状況に置かれるのである。
他人事から自分事へ。「私にはこんな特権がある」を知る
「特権への自覚がない」「全体の構造を知らない」といったこと以外にも、特権を持つ集団に属する人には共通する特徴がある。
まずは、「社会的な抑圧がある」という現実を突きつけられたときに、それを否定したり回避したりしがちだということ。さらに、自らが「差別を生む特権集団の側にいる」という認識に抵抗を示す傾向があるという。
アメリカでも「白人特権」について教えると、やはり白人の学生から「そんな特権はない」と抵抗がありました。「むしろ自分は貧しい家庭で育ったんだ」と言われることもあります。
でも私は、「特権がある=バラ色の人生を送っている」と言っているわけではないんですね。他の抑圧構造のなかで生きてきた人も、当然たくさんいるでしょう。ただ「人種」というアイデンティティに限って言えば、白人として抑圧される経験はあまりないんじゃないか、と考えているわけです。
こうした特徴を持つマジョリティとマイノリティが、対話をしていくにはどうすればいいのか。
「そもそもマジョリティ性を持った側が、自分の特権に自覚的になってはじめて対話が成立する。変わらなくてはならないのは、マジョリティ性を持った側なんです」と出口さんは主張する。
もちろんマジョリティに属する人が、自分の考え方を変えていくことは簡単ではない。社会全体で「自らのマジョリティ性を見直す」ことそのものへの接点がもっと広がらなくては、特権を自覚する人も増えていかないだろう。
そのとき、個人に罪悪感や負担感を覚えさせるのではなく、公正な社会のために「自分にできることを学ぶ機会」という視点で認知を得ていくことが変化への大切な足がかりになる。近年アメリカで展開されている『Check Your Privilege(特権を自覚せよ)』運動は、まさにこれを形にしたものだという。

さらに、日々のなかで個人ができることもあると出口さんは述べる。その1つが、「私にはこんな特権がある」という視点を持つ訓練だ。たとえば駅で車イスに乗る人を見かけたとき、自分が何気なくとる行動と具体的に比較することで、持っているマジョリティ性に気づきやすくなる。
「最寄りの出入口を利用できる」「エレベーターがあるのかを事前に確認しなくてもすむ」「どの交通機関を使うか瞬時に、自由に選べる」など、駅の利用ひとつにも、多くの人が無自覚に持つ特権はたくさんあります。こういった視点を日常生活に落とし込んでいくことが、非常に大事なんですね。
それまで他人事だったものも、自分のことになると意識が変化する。ただ遠くから「かわいそうだな」と思っているだけでは、なかなか社会は変わらないだろうと思います。
差別問題に“中立な立場”はない

構造的な抑圧があるなかで、その流れに積極的に加担するのが「差別主義者」。流れに逆らう抵抗をするのが「人権主義者」だと一般に言われる。ただ、多くの人はこうした問題に関与せず、自らを「中立な立場」と捉えがちだ。
だが、ここまで見てきたように、マイノリティが受ける差別とマジョリティが持つ特権は常に表裏の関係にある。そして、制度的な抑圧、文化的な抑圧は個人の意思を超えて差別を生み出し続ける。果たして「中立な立場」は存在するのだろうか。
私も昔は、自分を中立だと思っていました。でも、やっぱり中立なんてないんです。社会的な抑圧を防いでいない以上、どれだけ消極的でも差別に加担している。その意味では「受け身な差別主義者」と言えるのではないでしょうか。
差別をなくしたいと思うのであれば、やはり流れに逆らい、抑圧構造に向かって小さくても一歩を踏み出す必要があります。行動を起こす『アライ』に、みなさん自身がなっていただきたいと思うんです。
出口さんが監訳した『真のダイバーシティをめざして―特権に無自覚なマジョリティのための社会的公正教育―』(上智大学出版)によると、『アライ』(Ally)とは、「特権集団の人々の中で、自らの意志で被抑圧集団の人々の権利を支持する、あるいは社会的公正を求めて立ち上がることを選択する人々」を指す。
差別社会のなかでは、マジョリティ側の発言の方が好意的に受け入れられやすいため、特権を有する人がアライとして発言することが有効な場合もあると出口さんは語る。
例として挙げたのは、2019年に話題を呼んだアメリカの国立衛生研究所(NIH)のフランシス・コリンズ所長の、「男性ばかりが登壇者の科学会議には、招かれても辞退する」と宣言した話。さらに日本でも、起業家の若宮和男さんが書いたnote「ジェンダーギャップなイベントの登壇をお断りすることにしました」が多くシェアされるなど、アライとして発言する人が少しずつ増え、注目を集めるようになっている。

特権に無自覚なままの善意の危険性
そして、こうした議論を増やすためにもう1つ忘れてはいけない視点がある。「教育」の重要性だ。
たとえばアメリカでカウンセラーになるためには、大学院の修士課程で自分自身の文化的アイデンティティや特権について学ぶことが基本的に義務づけられているという。マイノリティ性を持つ人から生きづらさを相談されたとき、自らの特権に無自覚であると「ポジティブになったら?」「努力してみようよ」などと問題を個人に押し付け、逆に相談者を傷つけてしまうことになるからだ。
「人の役に立ちたい」「困っている人を救いたい」という善意や共感だけで人に寄り添うのは危険であり、適切な知識が本来必要となる。これはカウンセラーに限らず、あらゆる職業で本質的に求められるものであり、「人として知っておくべきこと」になると出口さんは指摘する。
こうしたマジョリティへの教育を行うのは、みなさんは誰の役目だと思いますか? 私は、マジョリティの教育はマジョリティ自身が担うべきだと考えます。
マイノリティはマイノリティとしての問題を抱えています。自分のアイデンティティに目を向け、受け入れたり絆をつくったりしなくてはいけません。そこで優先されるべきは自分自身のケアであり、マジョリティへの教育まで任せるのは、私は違うと思うんです。
「マイノリティの声が届きやすい社会にしていく」。それがマジョリティの責任であり、アライとしての姿だと話す出口さん。そして、マイノリティにとって生きやすい社会は、マジョリティにとっても生きやすい社会なのである。
90分の講義のなかで彼女が繰り返し語ったのは、日本社会に『特権』という言葉を広め、それを可視化していきたいということ。この背景には、「気づきにくいものを表す言葉がなければ、今恩恵を受けている人たちだけが得をし続ける」という思いが強くある。
差別について語り、特権を可視化していくことで、社会の抑圧構造が見えやすくなる。自分が労せず持っていた優位性に気づきやすくなる。逆に差別や特権について何も語らなければ、それはいつまでも目に見えない形で残り続けるのだろう。
「子どもをレイシスト(人種差別主義者)に育てるには、差別について語らなければよい」——講義中にこの一文が紹介された。
自らのなかに入り混じるマジョリティ性・マイノリティ性と正面から対峙することの意味を深く考えさせられる。「自分の持っている特権に向き合ってください」と語る出口さんの言葉から私たちが学ぶものは、とても大きい。
Information
・上智大学オープンコースウェア 立場の心理学:マジョリティの特権を考える/PSYCHOLOGY OF THE PRIVILEGED 講義映像一覧
・対話と共生推進ネットワーク:ウェブサイト
共に学ぶ、働く、食べる、買う、書く、語る、生きる。シンプルなはずが、なぜこれほどまでに難しいのか。皆で考えていきたいとの想いから、「共生」をテーマに研究や実践を行う有志が集まり、2020年に活動を開始しました。
Profile
![]()
-
出口真紀子
上智大学外国語学部英語学科教授/上智大学グローバル・コンサーン研究所およびアメリカ・カナダ研究所所員
1966年生まれ。アメリカ・ボストンカレッジ人文科学大学院心理学科(文化心理学)博士課程修了。ニューヨーク州のセント・ローレンス大学心理学部、神戸女学院大学文学部英文学科で教鞭をとり、2012年より上智大学外国語学部英語学科准教授、2019年より教授。専門は文化心理学。文化変容のプロセスやマジョリティ・マイノリティの差別の心理について研究。本学では「差別の心理学」「立場の心理学:マジョリティの特権を考える」などの科目を担当している。監訳書に『真のダイバーシティをめざして――特権に無自覚なマジョリティのための社会的公正教育』(上智大学出版、2017)、共訳書に『世界を動かす変革の力――ブラック・ライブズ・マター共同代表からのメッセージ』(明石書店、2021)がある。
・上智大学オープンコースウェア 立場の心理学:マジョリティの特権を考える/PSYCHOLOGY OF THE PRIVILEGED 講義映像一覧
- ライター:佐々木 将史
-
1983年生まれ。編集者。保育・幼児教育の出版社に10年勤め、’17に滋賀へ移住。保育・福祉をベースに、さまざまな領域での情報発信、広報、経営者の専属編集業などを行う。個人向けのインタビューサービス「このひより」の共同代表。保育士で4児(双子×双子)の父。2021年8月よりこここ編集部に参画、以降は執筆ではなく主に企画・編集側を担当。
この記事の連載Series
連載:こここスタディ
![]() vol. 302026.02.04専門家じゃないと安全な学びの場って作れないの? ワークショップファシリテーター 栗本敦子さんと考える
vol. 302026.02.04専門家じゃないと安全な学びの場って作れないの? ワークショップファシリテーター 栗本敦子さんと考える![]() vol. 292026.02.04それぞれの安心を尊重できる「学びの場」ってどうすればつくれる? ワークショップファシリテーター栗本敦子さんと考える
vol. 292026.02.04それぞれの安心を尊重できる「学びの場」ってどうすればつくれる? ワークショップファシリテーター栗本敦子さんと考える![]() vol. 282025.09.22「男らしさ」で誰かを傷つけたくない、どうすれば? 文筆家、教育学者、写真家、編集者によるおすすめの本
vol. 282025.09.22「男らしさ」で誰かを傷つけたくない、どうすれば? 文筆家、教育学者、写真家、編集者によるおすすめの本![]() vol. 272025.04.18“家庭”ってなんだろう? 子どもと大人が尊重しあう場所を目指す、児童福祉施設「てらす峰夢」をたずねて
vol. 272025.04.18“家庭”ってなんだろう? 子どもと大人が尊重しあう場所を目指す、児童福祉施設「てらす峰夢」をたずねて![]() vol. 262024.12.06差別と関係のない立ち位置ってあるの? 社会のあり方に矢印を向けて考える
vol. 262024.12.06差別と関係のない立ち位置ってあるの? 社会のあり方に矢印を向けて考える![]() vol. 252024.12.06差別ってなんだろう? 現代社会における差別の研究者 阿久澤麻理子さんをたずねて
vol. 252024.12.06差別ってなんだろう? 現代社会における差別の研究者 阿久澤麻理子さんをたずねて![]() vol. 242024.08.14正しい答えを刷り込むのではなく、自分で選ぶ手助けをする「包括的性教育」とは?
vol. 242024.08.14正しい答えを刷り込むのではなく、自分で選ぶ手助けをする「包括的性教育」とは?![]() vol. 232024.07.31「性教育」という言葉から何を想像する? 教育学者 堀川修平さんによる「包括的性教育」解説
vol. 232024.07.31「性教育」という言葉から何を想像する? 教育学者 堀川修平さんによる「包括的性教育」解説![]() vol. 222024.07.17「創造性」はどう育まれる? ブルーノ・ムナーリの軌跡から──デザイナー、現代美術作家、教育者のまなざし
vol. 222024.07.17「創造性」はどう育まれる? ブルーノ・ムナーリの軌跡から──デザイナー、現代美術作家、教育者のまなざし![]() vol. 212024.03.30「個人の心の問題」の多くは環境や政治の問題でもある〜「あなたのため」というバウンダリーの侵害〜
vol. 212024.03.30「個人の心の問題」の多くは環境や政治の問題でもある〜「あなたのため」というバウンダリーの侵害〜![]() vol. 202024.03.26自分と他者を区別する境界線「バウンダリー」とは?ソーシャルワーカー鴻巣麻里香さんによる解説
vol. 202024.03.26自分と他者を区別する境界線「バウンダリー」とは?ソーシャルワーカー鴻巣麻里香さんによる解説![]() vol. 192024.02.01「昔好きだった作品」の表現に戸惑ってしまったら? フィクションが与える2つの影響──文学研究者・小川公代さん
vol. 192024.02.01「昔好きだった作品」の表現に戸惑ってしまったら? フィクションが与える2つの影響──文学研究者・小川公代さん![]() vol. 182023.12.15「合理的配慮」は「ずるい」「わがまま」なのか? インクルージョン研究者 野口晃菜さんによる解説
vol. 182023.12.15「合理的配慮」は「ずるい」「わがまま」なのか? インクルージョン研究者 野口晃菜さんによる解説![]() vol. 172023.04.21“できる/できない”の社会を「ヨコへの発達」で問い直す。社会福祉の父・糸賀一雄を、垂髪あかりさんが研究する理由
vol. 172023.04.21“できる/できない”の社会を「ヨコへの発達」で問い直す。社会福祉の父・糸賀一雄を、垂髪あかりさんが研究する理由![]() vol. 162023.02.08「やさしい日本語」ってなに? 言語学者・庵功雄さんに聞くコミュニケーションの本質
vol. 162023.02.08「やさしい日本語」ってなに? 言語学者・庵功雄さんに聞くコミュニケーションの本質![]() vol. 152023.01.27人を見た目で判断することって全部「差別」になるの? 社会学者 西倉実季さんと、“ルッキズム”について考える
vol. 152023.01.27人を見た目で判断することって全部「差別」になるの? 社会学者 西倉実季さんと、“ルッキズム”について考える![]() vol. 142023.01.16自分の気持ちを話さない自由がある。NPO法人ぷるすあるはと一緒に考えた“きもち”との付き合い方
vol. 142023.01.16自分の気持ちを話さない自由がある。NPO法人ぷるすあるはと一緒に考えた“きもち”との付き合い方![]() vol. 132022.12.14“障害”ってそもそも何だろう? 困難の原因を「社会モデル」から考える──バリアフリー研究者・星加良司さん
vol. 132022.12.14“障害”ってそもそも何だろう? 困難の原因を「社会モデル」から考える──バリアフリー研究者・星加良司さん![]() vol. 122022.11.29「ちゃんとしなきゃ」の呪いをとくには?福祉社会学者 竹端寛さん× 僧侶 松本紹圭さん
vol. 122022.11.29「ちゃんとしなきゃ」の呪いをとくには?福祉社会学者 竹端寛さん× 僧侶 松本紹圭さん![]() vol. 112022.10.27“ありのままの自分”を大切にするって、どういうことだろう? しょうぶ学園施設長 福森伸さんをたずねて
vol. 112022.10.27“ありのままの自分”を大切にするって、どういうことだろう? しょうぶ学園施設長 福森伸さんをたずねて![]() vol. 102022.09.27「福祉の現場」と「芸術」の根っこには通ずるものがある? 福祉環境設計士 藤岡聡子さんをたずね、「ケアの文化拠点」ほっちのロッヂへ
vol. 102022.09.27「福祉の現場」と「芸術」の根っこには通ずるものがある? 福祉環境設計士 藤岡聡子さんをたずね、「ケアの文化拠点」ほっちのロッヂへ![]() vol. 092022.09.07“健康”ってなんだろう?ケアの文化拠点「ほっちのロッヂ」紅谷浩之さんをたずねて
vol. 092022.09.07“健康”ってなんだろう?ケアの文化拠点「ほっちのロッヂ」紅谷浩之さんをたずねて![]() vol. 082022.08.12弱さは個人の問題ではなく、構造上の問題だ。公認心理師・臨床心理士 信田さよ子さんと考える“弱さ”のこと
vol. 082022.08.12弱さは個人の問題ではなく、構造上の問題だ。公認心理師・臨床心理士 信田さよ子さんと考える“弱さ”のこと![]() vol. 072022.07.28“違う“の不安をどう乗り越えればいい? グレーではない「色」で表現する発達の特性──星山麻木さん
vol. 072022.07.28“違う“の不安をどう乗り越えればいい? グレーではない「色」で表現する発達の特性──星山麻木さん![]() vol. 062022.04.12「私はどう生きたらいい?」を、一人で抱えない社会へ。医師・西智弘さんに聞く、地域活動と“ケア“の文化づくり
vol. 062022.04.12「私はどう生きたらいい?」を、一人で抱えない社会へ。医師・西智弘さんに聞く、地域活動と“ケア“の文化づくり![]() vol. 052022.03.22偏見がない人はいない。川内有緒さん×木ノ戸昌幸さん『わたしの偏見とどう向き合っていく?』イベントレポート
vol. 052022.03.22偏見がない人はいない。川内有緒さん×木ノ戸昌幸さん『わたしの偏見とどう向き合っていく?』イベントレポート![]() vol. 042022.02.04居場所・つながり・役割・生産性。「望まない孤独」をめぐる対談でみえたものとは?吉藤オリィさん×奥田知志さん
vol. 042022.02.04居場所・つながり・役割・生産性。「望まない孤独」をめぐる対談でみえたものとは?吉藤オリィさん×奥田知志さん![]() vol. 032021.10.26大切なものを失った悲しみや痛みと共に生きていくには? グリーフサポートが当たり前にある社会を目指す 尾角光美さんをたずねて
vol. 032021.10.26大切なものを失った悲しみや痛みと共に生きていくには? グリーフサポートが当たり前にある社会を目指す 尾角光美さんをたずねて![]() vol. 012021.04.15さまざまな側面をもつ「わたし」と「あなた」をそのまま大切にするには? 美学者 伊藤亜紗さんを訪ねて
vol. 012021.04.15さまざまな側面をもつ「わたし」と「あなた」をそのまま大切にするには? 美学者 伊藤亜紗さんを訪ねて