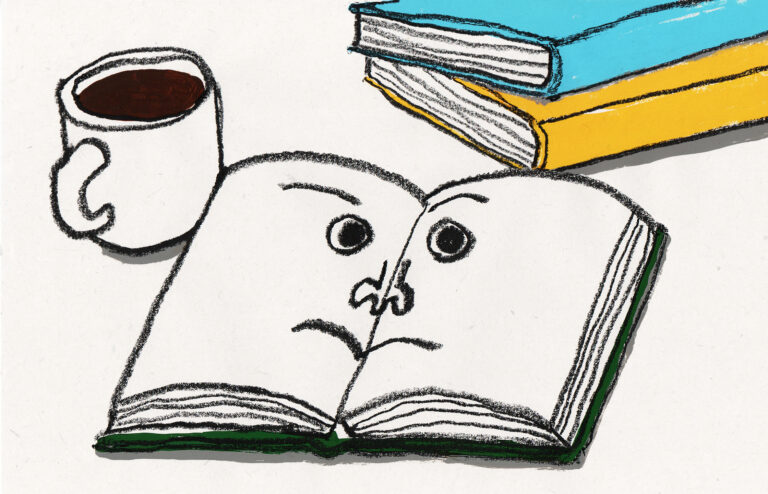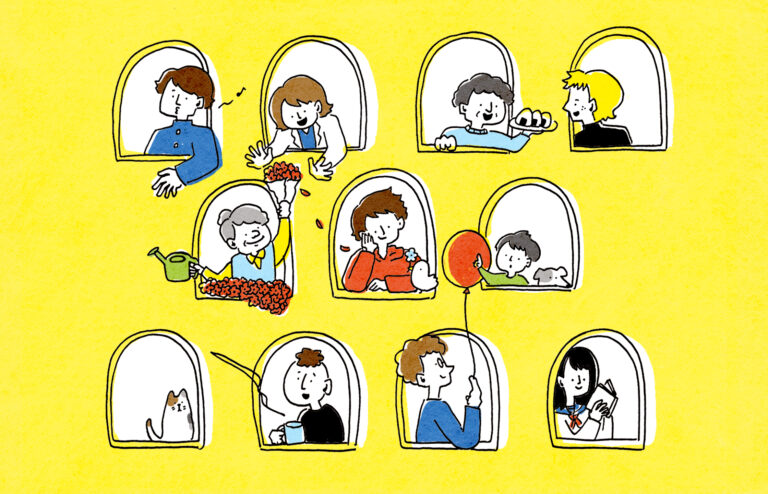人を見た目で判断することって全部「差別」になるの? 社会学者 西倉実季さんと、“ルッキズム”について考える こここスタディ vol.15
「それはルッキズムでは?」という批判をメディアやSNS上で目にするたび、はっと体が緊張する。批判されている対象について調べてみると、「それはたしかに差別だ」と怒りを覚えることもあれば、「言われてみればそうかもしれない」と自身を省みて不安になることもある。
人を外見で差別するのは不当だという思いはもちろんある。けれど、正直に言えば、自分が人の外見にとらわれていない、と言い切れる自信はない。私たちは日常生活のなかで、他者の視線にさらされ、人を外見の印象で判断したりされたりすることにあまりにも慣れすぎている。
なにがルッキズムにあたるか明確にはわかるとは言えないし、誰かを無意識のうちに外見で差別している可能性だってある、というのが自分自身の率直な思いだ。そして、同じような悩みと不安を抱えている人はほかにもいるのではないかと想像している。
けれど、重要なのはおそらく、個別の事例がルッキズムかどうかを闇雲にジャッジして考えるのをやめるのではなく、ルッキズムという概念について一から知り、外見に基づく差別の問題点やその解消の手立てを考えようとすることであるはずだ。
ルッキズムをめぐる現状についてあらためて学ぶため、『顔にあざのある女性たち―「問題経験の語り」の社会学』の著者であり、外見を理由にした差別についての研究者、社会学者の西倉実季さんにお話を伺った。
「ルッキズム」という言葉をどのようにとらえるべきか
──ルッキズムという言葉は、ここ数年で社会のなかに急激に広まってきたように感じています。そもそも、ルッキズムとは何を指す言葉なのでしょうか?
西倉実季さん(以下、西倉):現状の「ルッキズム」の用いられ方を見ると、ふたつの側面があるようです。
不当な差別を把握するための網として学術研究で使われてきた「ルッキズム」という言葉と、社会のなかでみんなが「これはルッキズムだ」と名指したいと感じている現象です。
──それが現在は、どちらもまとめてルッキズムと呼ばれているということでしょうか?
西倉:そのように思います。外見が絡む問題をなんでも「ルッキズム」と名指してしまうと、その背景にある差別の不当さが見えなくなってしまうことがある。だから、ただ言葉の幅を広げればいい、というわけではないと思うんですね。
とはいえ(定義の)幅が狭すぎると今度は、不当な差別を受けているにも関わらず、その網にかからないというケースが出てくる。
──当事者は「外見に基づく差別を受けている」と感じているにも関わらず、「それはルッキズムにはあたらない」とみなされてしまう、と。
西倉:ええ。だからこそ、ルッキズムという言葉を定義することはとても大事だと思います。ただ、ルッキズムの研究はまだ途上にあり、どこまでどのように焦点を当てるべきか私自身まだ悩んでいます。
その上で、これまでの研究もふまえて、「場面と関係のない外見評価」によって不利益を被ることはルッキズムと呼びたいと私は考えています。たとえば、就職活動における面接や学校の成績評価において、本来は関係ないはずの外見が評価基準に入ってくることで不利益を被るといった問題は、やっぱり不当な差別ですよね。
──そうですね。就職活動における面接や学校の成績評価の場において外見がジャッジされることは、たしかに差別だと感じます。
他方で、職場でのちょっとした雑談や家族や友人との会話といったより日常的なやりとりのなかでも、不意に人から外見評価を受けて戸惑ったり傷ついたりすることもあるように思うのですが。
西倉:そうですね。英語圏で積み重ねられてきたルッキズムに関する議論の多くは、職場での採用や昇進における不利益など、比較的把握しやすい問題を前提にしてきました。しかし、私たちにとってより日常的なのは、そのように思わぬ場面で外見のジャッジにさらされることかもしれません。
ルッキズムはもともと、ふくよかな人に対しての偏見に基づいた差別に抗議する「ファット・アクセプタンス運動」の問題意識を表現するなかで生まれた言葉です。その運動は、職場に限らずさまざまな社会的な場面において、「太っている」というだけで尊厳を傷つけられることに対しての抵抗運動でした。その起源を考えてみても、職業に限らずさまざまなシーンが想定されるというのはおっしゃるとおりだと思います。
──外見をジャッジされることの不当さに関して、なかには「外見のよさも個人の努力の成果なのだから、それを評価することは不当ではない」と考える人もいそうですよね。
西倉:そういった意見もあると思います。そこですこし立ち止まって考えてみる必要があるのは、私たちの美醜観、たとえば「どんな外見を魅力的だと感じるか」には通常考えられているほどの多様性はなく、知らず知らずのうちに社会的に決められている部分も大きいのではないか、ということです。
一例として、美容整形手術の国際的なデータを見てみると、女性に対して行われた手術のなかでいちばん多いのが豊胸手術、その次がまぶたの手術で、若返りを目的とした手術も非常に人気です。一方で男性の場合は、乳腺の発達などで大きくなった胸を小さくする手術が上位に入ってきます。そのデータから見ても、美容整形で追求されている外見とは、いわゆるジェンダー規範に則った「女らしさ/男らしさ」にまつわるものであり、なおかつ若々しい外見であることが多いのがわかると思います。
まぶたの手術は、二重を形成するもので「東アジア人」に多いとされる目頭部分の皮膚「蒙古襞(もうこひだ)」をとることになります。ここには人種的な偏りもありそうです。
つまり、私たちの思う「よい外見」は、ジェンダー規範に当てはまり、若さや非アジア人的な外見を理想としているという偏りがあります。「外見のよさは個人の努力の結果なのだから、それを評価するのは何ら問題ではない」というときに、背景にそういったジェンダーや年齢、人種などの問題が絡んでいないかどうかも考えてみることが大切だと思うんです。
──なるほど。「よい外見」という評価の背景には、性差別や人種差別といった従来的な差別の問題が存在している可能性があると。
西倉:ええ。加えて、外見がよいという評価の前提には「健常」な身体が想定されているケースも多いです。そのことからも、障害差別との関係も考えなくてはいけないと思います。
ですから、ルッキズムについて議論する上で、「場面と関係のない外見評価をしていないか」「社会の美醜観に、これまでの差別の問題が絡んでいないか」という二点は注視する必要があると思っています。
私たちは、画一化された「美の規範」に苦しめられている
──私たちの美醜観にはそれほど多様性がないというお話がありました。近年、メディアや広告のなかでは「美はこんなにも多様だ」というメッセージが発せられる機会が増えていますし、メッセージを体現しているように感じるモデルやタレントも多くなってきているように思います。
その一方で、実際にはまだ、かなり画一的な外見を「美しい」とみなしやすい社会であるようにも感じています。
西倉:メディアやSNSにおいても、美白やアンチエイジングといった美容法が人気を集めている状況は変わっていませんし、「美の規範」と呼べるものはやっぱり依然として存在していますよね。
そういった話をすると、「でも、最近はあえて肌を焼く人もいますよ」といった例を持ち出されることがありますが、それも既存の美の規範を前提とした上での「多様性」に過ぎないのではないか、という視点は持っていたほうがよいと思うんですよね。
──従来のスリムなモデルだけでなくプラスサイズモデルが活躍している現状はすばらしい。しかし、プラスサイズというネーミングの背景には、「標準」として想定されているスタンダードサイズがある。その「標準」の存在に目を向けなくていいのだろうか、ということでしょうか。
西倉:まさにそうだと思います。問題にすべきは、現状の美というものがかなり偏っていて、それがよいとされるときに誰かが不利な状況に置かれ、自分の身体に対して羞恥心を覚えてしまったり、直接的ないし間接的に否定された気分になってしまうことだと思うんです。
そういった前提が抜け落ちて、「多様な美を受け入れられないのは個人の心持ちの問題だ」「よい外見になるための努力をしていない人が悪い」などと、個人の問題に矮小化された議論が日本では起きてしまいやすいと感じています。外見の問題を、個人ではなく社会的な問題として考えていく視点が必要ではないでしょうか。
──ルッキズムが「個人の心持ち」の問題にされてしまいやすい空気は、たしかに感じます。なかには、「自分の外見を変えたい、よくしたいと思う気持ちもルッキズムからきているんだろうか」と悩んだことがある人もいると思うのですが……。
西倉:そうですよね。もちろん、どうしてそんなに痩せたいと思うんだろうとか、どうして若々しいことに価値を感じるんだろうとか、自分が持っている美醜観について、ときおり立ち止まって考えてみることは大切です。でも、個々人がどんな外見になりたいかはあくまでその人の自由であって、「こんなふうになりたい」という気持ちそのものは尊重されるべきだと思います。
──では、「他者のこういった外見に心惹かれる」という気持ちも、同じように尊重されるべきでしょうか?
西倉:多くの研究は、それは個人の判断に委ねられるという立場をとっています。恋愛や結婚のパートナーを外見で選ぶことと、たとえば就職の採用試験で外見を評価基準にすることの間には線引きをしています。
ですが、やはり考えたいのは「ある外見に惹きつけられる」という気持ちのなかにもジェンダーや年齢、人種や障害などの偏りが含まれてしまっているということです。
そういう意味で、たとえば「あの人はこういう見た目をしているから恋人候補にはならない」という個人の考えが手放しに正当化されるかというと……難しいですね……。そこには倫理的な問題が存在しているように思います。その点は、ルッキズムの研究がまだじゅうぶんにはリーチできていないところかもしれません。
私たちがルッキズムから離れるために、いま足りていないもの
──ときには自分自身も無意識のうちに、他者に対して外見に基づいた差別をしてしまっていることもありそうです。日常生活のなかでそういった差別をしないためには、どのような姿勢でいることが大事だと思いますか?
西倉:やっぱり、さきほどお伝えしたように「私たちの美醜観には偏りがある」という点を認識していないと、その偏りがさまざまなコミュニケーションの場面で出てしまうのではないでしょうか。繰り返しになりますが、外見の問題を個人ではなく、社会的な問題として把握しようとする視点が大切だと思います。
自分自身の体験を振り返って考えてみると、思春期に、雑誌やテレビに出ている芸能人と自分の外見を比べて「こんなに綺麗な人がいるのに、自分は……」とコンプレックスを感じていました。その一因には、メディアを通して伝えられるイメージが「つくられたもの」であるという視点が抜け落ちていたことが挙げられると思うんです。
商業雑誌やメディアが追い求めている美はある種のファンタジーであって必ずしも現実の反映ではないし、そこに登場する人たちの美のありかたにも偏りがある。そういうことを批判的に見られるリテラシーがあったほうがよさそうですよね。
──たしかに、画一化された美のイメージを全肯定するのではなく、批判的に見る力は大切ですね。ただ、その視点を思春期に自分自身で身につけることは難しそうだとも感じます。
西倉:そうですね。国際的には、包括的セクシュアリティ教育の文脈で、人の身体はすでに多様であることが認識できる教育の重要性が指摘されています。けれど日本では、狭義の性教育自体がまだまだじゅうぶんにおこなわれていない状況があります。それゆえに、子どもが身体の多様性について知ったり、肯定的なボディイメージを形成したりできるような機会が少ないという問題はありそうです。
近年では中学校や高校における「理不尽な校則」が話題になることも多いです。なぜその校則が必要なのか、必ずしも合理的な説明がなされないまま、髪の色や長さ、パーマの有無など、かなり画一的な外見を子どもが学校側から強制されてしまうケースもあると聞きます。
──実際に自分の学生時代にも、髪の毛が黒くない生徒は黒染めをするか「地毛証明書」を提出することを求められていました。もともと髪の色が明るい同級生がすごく悩んでいたのを覚えています。
西倉:そうやって自分の外見を直接的ないしは間接的に否定されて育ってきた子どもたちが、自分自身の外見や、自分とは違う外見をした他者を尊重することがはたしてできるのでしょうか。外見は単なる「見た目」の問題ではなく、個人の尊厳やアイデンティティに関わる問題である、ということを知る機会自体がないわけですから。
ルッキズムという概念は、当事者の苦しさを解消する手立てになる?
──ここまでお話を伺って、ルッキズムが生まれる背景には社会的な構造や教育の問題も大いにありそうだと感じています。
一方で考えたいのは、社会構造上の問題だと認識できたとしても、外見に基づく差別に悩む当事者がいま感じている痛みや苦しさ、モヤモヤがそれだけで消えるわけではないということです。
ルッキズムという言葉が社会のなかにこれほど広まってきたことは、その痛みや苦しさが解消されていくためのひとつの手立てになりうると西倉さんは思いますか?
西倉:「性差別」の文脈では語れなかった問題が「ルッキズム」だとなぜ語れるかという問いにも通ずる話だと思うのですが、率直に言えば私自身、まだじゅうぶんに整理できていないのが正直なところです。
ただ、言葉の定義はさておき、「これまで外見に関して理不尽な目に遭ってきたのは自分自身のせいだ」と考えていた人が、問題の所在が社会の側にあるというとらえ返しによってなにかを語れるようになったり、共通の言語を用いて他者と問題を共有できるようになることには大きな意味があると考えています。
けれど、問題の所在が社会構造にあるとわかったとしても、実際には私たちはそのなかを生き抜いていくしかありませんから、それでなにかがいますぐ変わるのか、という問いはたしかに残りますよね。
──そうですね……自分自身、社会的な美の規範と自分を比べて落ち込んだり、他者から外見をジャッジするような言葉を不意にかけられて傷ついたりすることはいまだにあります。
西倉:でも、美の規範が「つくられた」ものだとすれば、別の形にもつくり変えられるはずだと考えることはできるのではないでしょうか。たとえば、「こうじゃないと」と思っていた外見のありかたの許容範囲が広がって、「こうじゃなくても別にいいよね」「こういう外見もありだよね」と思えるようになったり。
──そうですね、それももちろんあります。ただ、自分の置かれている環境がなかなか変わっていかないことにもどかしさを感じることも多いです。
西倉:なるほど。環境が変わっていかず、同じ問題を何度も繰り返しているなと感じることはたしかにありますよね……。
ルッキズムに関しては、「外見を気にするのはよくない」などと他者のジャッジに苦しんでいる人自身が変わることを期待したり、あるいはせいぜい「人を外見で判断するのはよくない」とジャッジする側をたしなめたりするだけで終わってしまうことが多いようです。いずれにしても個々人の問題にされていて、社会の美醜観や外見に関する慣習そのものを問題にするには至っていません。
近年では、たとえば、就職活動における履歴書の写真は不要なのではないかという問題提起は既になされていますし、もうすこし、政策的ないし組織的な取り組みの水準で変えられることがないかを考えていくことも必要かもしれませんね。
──たしかにおっしゃるとおり、そういった働きかけや批判がもっとあってもいいはずですね。
西倉:社会からの画一的な美の発信に対して、それを受けとる側の批判的な読み解きも大切だというのはお話ししたとおりですが、メディアにおけるボディイメージの発信が偏っていることや、教育自体が不十分であることに対するアプローチもあるべきですよね。
ボディポジティブという言葉は近年すごく広まりましたし、その考え方に救われている方ももちろん多いはずです。でも、規範的な美はなかなか変わらないのに個人にはポジティブでいよう、というのはかなりハードルの高いことだよなと。「社会がポジティブでいさせてくれよ……!」と個人的には思います。

自分の理不尽さを媒介にして、他者の困難を知る
──外見の問題に限らずですが、私たちが他者の尊厳や権利というものをいまよりも尊重できるような土壌を耕していくためには、なにが必要だと西倉さんは思いますか。
西倉:とても難しいですが、私自身は、自分がかつて経験した理不尽さが、他者が経験している理不尽さを理解する際のひとつの媒介にならないだろうかと考えているところがあります。
授業で学生に差別の問題について話すときなどは、その可能性にかけているところがあるかもしれません。仮に相手に「共感すること」はできなくても、相手の状況を「知ること」で、自分が経験した理不尽さを媒介にしながら、その困難を「想像すること」はできるのではないか、と。
──西倉さんは著書『顔にあざのある女性たち』のなかで、取材対象者の女性の言葉を受けて、実際にご自分の顔に赤いあざのメイクを施して外出した体験を綴られていました。その体験によって、あざのある人が他者からどのような視線を向けられるかを知ったと書かれた上で、「執拗な視線の対象になる苦しみを理解することはできなかった」とも語られていましたね。
西倉:あざのメイクを自分の顔に施した体験も、まさに「共感すること」ではなく「知ること」だったと思います。洗えばすぐに落ちるあざのメイクで私がした経験と、顔にあざのある女性たちがしてきた経験とを「同じ」だと言うことは当然できません。
でも、そういった経験を媒介にすることで、他者にじろじろ見られたり望まない言及をされたりすることの悔しさや不当さをほんのすこし知ることができたわけです。
この経験を通して私が理解したのは、赤あざのある顔に向けられる他者の視線や行為がどんなものであるかということである。じっと見つめる、見ないふりをして見る、いったん視線をそらしてまた見る、いぶかしそうな目つきで見つめる、避けて通る、隣の人にこそこそ耳打ちをする、『なに、あの顔!?』とつぶやく、顔を見てのけぞる・・・・・・。赤あざの化粧をしても、鏡に映さない限り自分には見えず、いつもと何ら変わりがない。にもかかわらず、通りすがりの人たちの反応は普段とはまるで違っていたのである。つまり私が身をもって経験したのは、顔にあざのある当事者の苦しみではなく、他者といつも取り交わしている視線や行為との歴然とした違いであった。そしてそれは、普段はお互いに払いあっているはずの敬意を他者から一方的に剥奪されるような相互行為なのであった。
(『顔にあざのある女性たち』p362-363より)西倉:ただ、マジョリティ性を多く持つ人など、構造的に社会的マジョリティの立場に立ちやすい人ほど、社会との関係において理不尽な経験をせずに済んでいる面があると思います。そのため、自分の感じた理不尽な思いや苦しさをスタート地点にして考えるのが困難な場合もあって、差別の問題を伝えようとすることは、本当に難しいといつも悩んでしまいます。
──そういった人は、構造上の不公平さを訴えられると、マジョリティ性を持っていること自体を責められているような感覚になってしまうのかもしれないですね。
西倉:そうですね。ただ、問題なのは、誰かがマジョリティであることそれ自体ではなくて、マジョリティの視点でしか社会を見ておらず、社会の偏りに気がついていないことですよね。それに気がつくことで、誰に・どのようなしわ寄せがいっているのか、偏りはどのようにすれば是正できるかを考えられるようになるはずです。ルッキズムの何が問題なのかが認識されて、個人の尊厳がきちんと尊重される土壌をつくっていくために、すこしでも建設的な議論をしていけたらいいですよね。

連載「ルッキズムに立ち止まる」|NPO法人マイフェイス・マイスタイル
Information
・『顔にあざのある女性たち―「問題経験の語り」の社会学」』(生活書院、2009年)
・『だれが校則を決めるのか―民主主義と学校』(岩波書店、2022年)※「第6章 外見校則とルッキズム」を担当
・『ルッキズムってなんだろう? みんなで考える外見のこと』(平凡社、2025年8月)発売中
Profile
- ライター:生湯葉シホ
-
1992年生まれ、東京在住。フリーランスのライター/エッセイストとして、おもにWebで文章を書いています。Twitter:@chiffon_06
この記事の連載Series
連載:こここスタディ
![]() vol. 302026.02.04専門家じゃないと安全な学びの場って作れないの? ワークショップファシリテーター 栗本敦子さんと考える
vol. 302026.02.04専門家じゃないと安全な学びの場って作れないの? ワークショップファシリテーター 栗本敦子さんと考える![]() vol. 292026.02.04それぞれの安心を尊重できる「学びの場」ってどうすればつくれる? ワークショップファシリテーター栗本敦子さんと考える
vol. 292026.02.04それぞれの安心を尊重できる「学びの場」ってどうすればつくれる? ワークショップファシリテーター栗本敦子さんと考える![]() vol. 282025.09.22「男らしさ」で誰かを傷つけたくない、どうすれば? 文筆家、教育学者、写真家、編集者によるおすすめの本
vol. 282025.09.22「男らしさ」で誰かを傷つけたくない、どうすれば? 文筆家、教育学者、写真家、編集者によるおすすめの本![]() vol. 272025.04.18“家庭”ってなんだろう? 子どもと大人が尊重しあう場所を目指す、児童福祉施設「てらす峰夢」をたずねて
vol. 272025.04.18“家庭”ってなんだろう? 子どもと大人が尊重しあう場所を目指す、児童福祉施設「てらす峰夢」をたずねて![]() vol. 262024.12.06差別と関係のない立ち位置ってあるの? 社会のあり方に矢印を向けて考える
vol. 262024.12.06差別と関係のない立ち位置ってあるの? 社会のあり方に矢印を向けて考える![]() vol. 252024.12.06差別ってなんだろう? 現代社会における差別の研究者 阿久澤麻理子さんをたずねて
vol. 252024.12.06差別ってなんだろう? 現代社会における差別の研究者 阿久澤麻理子さんをたずねて![]() vol. 242024.08.14正しい答えを刷り込むのではなく、自分で選ぶ手助けをする「包括的性教育」とは?
vol. 242024.08.14正しい答えを刷り込むのではなく、自分で選ぶ手助けをする「包括的性教育」とは?![]() vol. 232024.07.31「性教育」という言葉から何を想像する? 教育学者 堀川修平さんによる「包括的性教育」解説
vol. 232024.07.31「性教育」という言葉から何を想像する? 教育学者 堀川修平さんによる「包括的性教育」解説![]() vol. 222024.07.17「創造性」はどう育まれる? ブルーノ・ムナーリの軌跡から──デザイナー、現代美術作家、教育者のまなざし
vol. 222024.07.17「創造性」はどう育まれる? ブルーノ・ムナーリの軌跡から──デザイナー、現代美術作家、教育者のまなざし![]() vol. 212024.03.30「個人の心の問題」の多くは環境や政治の問題でもある〜「あなたのため」というバウンダリーの侵害〜
vol. 212024.03.30「個人の心の問題」の多くは環境や政治の問題でもある〜「あなたのため」というバウンダリーの侵害〜![]() vol. 202024.03.26自分と他者を区別する境界線「バウンダリー」とは?ソーシャルワーカー鴻巣麻里香さんによる解説
vol. 202024.03.26自分と他者を区別する境界線「バウンダリー」とは?ソーシャルワーカー鴻巣麻里香さんによる解説![]() vol. 192024.02.01「昔好きだった作品」の表現に戸惑ってしまったら? フィクションが与える2つの影響──文学研究者・小川公代さん
vol. 192024.02.01「昔好きだった作品」の表現に戸惑ってしまったら? フィクションが与える2つの影響──文学研究者・小川公代さん![]() vol. 182023.12.15「合理的配慮」は「ずるい」「わがまま」なのか? インクルージョン研究者 野口晃菜さんによる解説
vol. 182023.12.15「合理的配慮」は「ずるい」「わがまま」なのか? インクルージョン研究者 野口晃菜さんによる解説![]() vol. 172023.04.21“できる/できない”の社会を「ヨコへの発達」で問い直す。社会福祉の父・糸賀一雄を、垂髪あかりさんが研究する理由
vol. 172023.04.21“できる/できない”の社会を「ヨコへの発達」で問い直す。社会福祉の父・糸賀一雄を、垂髪あかりさんが研究する理由![]() vol. 162023.02.08「やさしい日本語」ってなに? 言語学者・庵功雄さんに聞くコミュニケーションの本質
vol. 162023.02.08「やさしい日本語」ってなに? 言語学者・庵功雄さんに聞くコミュニケーションの本質![]() vol. 142023.01.16自分の気持ちを話さない自由がある。NPO法人ぷるすあるはと一緒に考えた“きもち”との付き合い方
vol. 142023.01.16自分の気持ちを話さない自由がある。NPO法人ぷるすあるはと一緒に考えた“きもち”との付き合い方![]() vol. 132022.12.14“障害”ってそもそも何だろう? 困難の原因を「社会モデル」から考える──バリアフリー研究者・星加良司さん
vol. 132022.12.14“障害”ってそもそも何だろう? 困難の原因を「社会モデル」から考える──バリアフリー研究者・星加良司さん![]() vol. 122022.11.29「ちゃんとしなきゃ」の呪いをとくには?福祉社会学者 竹端寛さん× 僧侶 松本紹圭さん
vol. 122022.11.29「ちゃんとしなきゃ」の呪いをとくには?福祉社会学者 竹端寛さん× 僧侶 松本紹圭さん![]() vol. 112022.10.27“ありのままの自分”を大切にするって、どういうことだろう? しょうぶ学園施設長 福森伸さんをたずねて
vol. 112022.10.27“ありのままの自分”を大切にするって、どういうことだろう? しょうぶ学園施設長 福森伸さんをたずねて![]() vol. 102022.09.27「福祉の現場」と「芸術」の根っこには通ずるものがある? 福祉環境設計士 藤岡聡子さんをたずね、「ケアの文化拠点」ほっちのロッヂへ
vol. 102022.09.27「福祉の現場」と「芸術」の根っこには通ずるものがある? 福祉環境設計士 藤岡聡子さんをたずね、「ケアの文化拠点」ほっちのロッヂへ![]() vol. 092022.09.07“健康”ってなんだろう?ケアの文化拠点「ほっちのロッヂ」紅谷浩之さんをたずねて
vol. 092022.09.07“健康”ってなんだろう?ケアの文化拠点「ほっちのロッヂ」紅谷浩之さんをたずねて![]() vol. 082022.08.12弱さは個人の問題ではなく、構造上の問題だ。公認心理師・臨床心理士 信田さよ子さんと考える“弱さ”のこと
vol. 082022.08.12弱さは個人の問題ではなく、構造上の問題だ。公認心理師・臨床心理士 信田さよ子さんと考える“弱さ”のこと![]() vol. 072022.07.28“違う“の不安をどう乗り越えればいい? グレーではない「色」で表現する発達の特性──星山麻木さん
vol. 072022.07.28“違う“の不安をどう乗り越えればいい? グレーではない「色」で表現する発達の特性──星山麻木さん![]() vol. 062022.04.12「私はどう生きたらいい?」を、一人で抱えない社会へ。医師・西智弘さんに聞く、地域活動と“ケア“の文化づくり
vol. 062022.04.12「私はどう生きたらいい?」を、一人で抱えない社会へ。医師・西智弘さんに聞く、地域活動と“ケア“の文化づくり![]() vol. 052022.03.22偏見がない人はいない。川内有緒さん×木ノ戸昌幸さん『わたしの偏見とどう向き合っていく?』イベントレポート
vol. 052022.03.22偏見がない人はいない。川内有緒さん×木ノ戸昌幸さん『わたしの偏見とどう向き合っていく?』イベントレポート![]() vol. 042022.02.04居場所・つながり・役割・生産性。「望まない孤独」をめぐる対談でみえたものとは?吉藤オリィさん×奥田知志さん
vol. 042022.02.04居場所・つながり・役割・生産性。「望まない孤独」をめぐる対談でみえたものとは?吉藤オリィさん×奥田知志さん![]() vol. 032021.10.26大切なものを失った悲しみや痛みと共に生きていくには? グリーフサポートが当たり前にある社会を目指す 尾角光美さんをたずねて
vol. 032021.10.26大切なものを失った悲しみや痛みと共に生きていくには? グリーフサポートが当たり前にある社会を目指す 尾角光美さんをたずねて![]() vol. 022021.06.24差別や人権の問題を「個人の心の持ち方」に負わせすぎなのかもしれない。 「マジョリティの特権を可視化する」イベントレポート
vol. 022021.06.24差別や人権の問題を「個人の心の持ち方」に負わせすぎなのかもしれない。 「マジョリティの特権を可視化する」イベントレポート![]() vol. 012021.04.15さまざまな側面をもつ「わたし」と「あなた」をそのまま大切にするには? 美学者 伊藤亜紗さんを訪ねて
vol. 012021.04.15さまざまな側面をもつ「わたし」と「あなた」をそのまま大切にするには? 美学者 伊藤亜紗さんを訪ねて