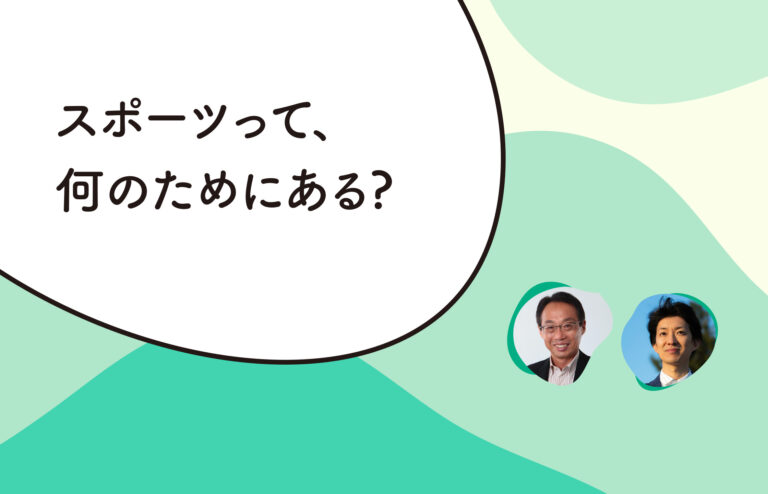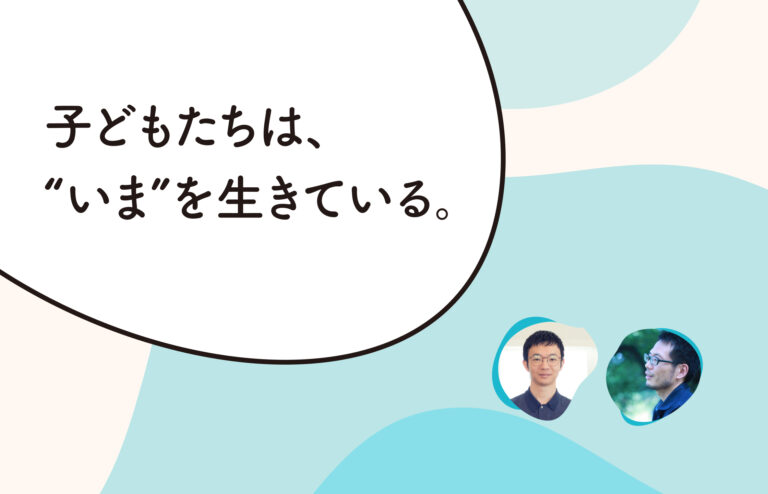なぜ自分に価値があるか確認したくなるんだろう? 勅使川原真衣さんと新澤克憲さんによる「評価」を巡る対話 こここインタビュー vol.31
人からの評価を気にしないこと、人をいたずらに評価しないこと。頭では分かっているつもりでも、それらを実践するのはむずかしい。自分にはどんな価値があるのかをどこかで気にしてしまうし、この人は何をもたらしてくれるのかと考えてしまうことだってある。それだけ「評価」は私たちの内面に根を下ろしている。
とはいえ、評価それ自体が悪いものかといえば、必ずしもそうは言い切れない気もするから一筋縄にはいかない。私たちはなぜこれほどまでに評価に振り回されてしまうのだろう?そもそも「評価」って何なのだろう?むやみに評価したりされない環境をつくるにはどうすればいいだろう?答えを急ぐのではなく、立ち止まって考えてみたいーー。
そこで今回、『働くということ 「能力主義」を超えて』(集英社)などの文筆家としても活動する組織開発コンサルタントの勅使川原真衣さんと、就労継続支援B型事業所ハーモニーの新澤克憲さんをお招きし、「評価」を巡る対話を行った。
対話の場には、こここ編集部の垣花つや子さんと、本記事の執筆を務める椋本湧也が同席し、事前に下記の方針が共有された。
*
「論理的」や「わかりやすい」言葉への期待や要請に必ずしも応える必要はありません。また、素早いリアクションによる「良い会話のテンポ」を維持することだけが正ではなく、無言の時間があっても構いません。参加者各々が、そのとき、そのタイミングにおいて、のぞむリズム、生まれるペースで行われる対話を大切にしたいです。
「評価」は必ずしも悪いものではない?
「人はえてしてことを一面相で整理したがる」という言葉があるように、私たちはついつい目の前の対象を「こういうものだ」と決めつけてしまいがちだ。けれども、対象を一面的に捉えることは、ほんらい対象が持つさまざまな側面を見えなくすることでもある。
では、今回のテーマである「評価」もすぐに決めつけずに検討することで、一体どんな側面が見えてくるだろう。テーマを受けてそれぞれが感じたことを共有することから対話はスタートした。
勅使川原真衣さん(以下、勅使川原):6月と7月に立て続けに本を刊行して、最近は毎週のように対談イベントをしています。本は「能力主義を問いなおす」というテーマなので、お客さんもそこに関心があって来てくれていると思うのですが、自分も相手も対談というショーにおいては高いコミュニケーション能力や言語化能力を求められる気がしてジレンマを感じていました。
椋本湧也(以下、椋本):「呼ばれたからには良いことを言わないと!」というプレッシャーがはたらくのかもしれないですね。
勅使川原:だから登壇者として立つことも、やっぱり評価にさらされている気持ちになるんでしょうね。それが悪いということではなくて。人間って強さにはすごく差があるけど、弱さは案外似た者同士なんだろうなぁと思いながらやっています。
新澤克憲さん(以下、新澤):僕は今回のテーマを読みながら、1995年にハーモニーを始めた時のことを思い出しました。当時、通所者募集のチラシに〈いたずらに人を評価しない、評価されない場所〉って書いたんです。いま振り返ると、自分でもよく分からずに書いていた気もするのですが。
垣花つや子(以下、垣花):その「いたずらに」という表現にすごくリアリティがあると思うんです。30年前、当時の新澤さんが直感的にその言葉を見つけていたことに信頼感があるといいますか。
新澤:言っちゃったからにはちょっと頑張ってみるしかない(笑)。2000年前後から、私たちの仕事の中に「アセスメント」という考え方が定着しました。「アセスメント」って日本語に直すと「評価」なんですよね。福祉分野におけるアセスメントとは支援を必要とする人が困っている課題を、見出し、客観的に評価・分析することであると言えます。それで評価表のテンプレートを用意して、「今日これやるからね」と言ったら、メンバー(利用者)のひとりが「えーー!」って(笑)。「お前評価しないって書いただろう!」って。
勅使川原:先日、ある福祉施設を訪ねた時にもアセスメントの話になったんですよ。その時に思ったのは、アセスメントや評価そのものが不必要だとか絶対いけないわけではないかもしれないということです。状態を観察するとか、観察した情報をもとに人と仕事を組み合わせるために使う分には、むしろ必要な可能性すらある。ただ、そういう目的や機能を持った評価ではなくて、「あなたはこういう人」と決めつけたり、人と比べるために評価すること、あとはその評価をもとに人間を序列化するのは問題だと思うんです。新澤さんはこのあたりどうお考えですか?
新澤:まさしくその通りだと思います。現実的に人を評価しないことはありえないというか。人と会ったときに「いいな」とか「ちょっと苦手だな」と自分の心が動くのはあたりまえで、そのこと自体を否定することはないんだろうなという気がします。逆に言うと、心の動きを隠して「私は公平ですよ」と思い込もうとすることに違和感がありますよね。
*
評価の概念を「決めつけない」ことによって見えてきたのは、評価は必ずしも悪いものではないということだった。むしろ「心が動くことはあたりまえ」であると新澤さんは言う。この言葉が胸を突くのは、これまで自分が相手の機嫌や場の空気を気にするあまり、心が暗いときに明るい顔をつくろうとしたり、こだわりのあるときに率直に振る舞おうとしてきた数多くの場面が思い起こされるからだろう。
とはいえ、心が動くままに発言をすることは、同時に相手を傷つけたり、関係を悪化させる要因にもなるように思える。そのジレンマをどう考えればいいのだろうか。
私たちは心が動くことをあまりになかったことにしている
「心の動き」に素直でいられる環境や関係はどのようにしてあり得るだろう。新澤さんは、ハーモニーを運営してきた30年間で相手と関係を続けるための「ある心構え」が身についたと言う。
勅使川原:たとえば学校で驚いた瞬間に「キャー!」って叫んだり、本当にやりたくないことをやらないでいると怒られるじゃないですか。そういう集合的な規範に自分を合わせるプレッシャーの下で育ってきたから、私たちは「心が動く」ことをあまりになかったことにしてますよね。
新澤: とりあえず何かが出来なかったり苦手だったりするから福祉のサービスを受けるわけなんですが、認定調査や相談の場面で、何かが「できない」ことを本人が訴えるわけです。それでサービスを受けながら、「できるように頑張りましょう」ということになる。それは大事なんだけど、何か、今の自分ではよくない。「より良い自分」を目指さなくてはいけないという気分になる。
勅使川原:心が動くって、ドキドキでもザラザラでもワクワクでもなんでもよくて、どれも「自分」なのに。最近は「自分の機嫌は自分で取れ」とか「いつも笑顔でポジティブに」とか、「良い心の動き」と「悪い心の動き」に分けられてしまっていますよね。それは自分自身もなんですけど。
新澤:障害者就労支援施設も似ていて、「長く働くのが偉い」「正確にやるのが良い」という考え方が内面化されて、まったく自信が持てない人たちとまず僕らは会うわけです。だからハーモニーを立ち上げるときに「いたずらに評価しない」って僕が直感的に思ったのは、そういう考え方を外したところからスタートしたかったんだろうなと今は思います。
勅使川原:私も、まともだと思い込んでいたことが絶えず揺れている状態です。
新澤:僕は割とすぐ「ごめん」って言います(笑)。メンバーとやり取りすると、やっぱり心が動くわけじゃないですか。「いいね」とか「いやだな」とか思わず言ってしまう。その時、「そんなことないよ」と相手が言ってきたり、違うぞというそぶりが見えたら、すぐに「ごめんね」と言える勇気があれば関係は続くかなという気がします。
勅使川原:訂正、大事ですね。すてきだなぁ。心の動きを決めつけずに泳がせておく、宙ぶらりんに耐えるのって難しい。新澤さんがそれを30年間やられているのは、日々どんな心持ちなんですか? 決めつけそうになるじゃないですか。
新澤:メンバーの人たちが毎日の生活の中で見たり感じたりしたことを伝えてくれるわけですが、私自身が見えている世界は、本当に限られた狭いものだと痛感します。気がつくと虚心に耳を傾けたりしている。話の中には妄想だと片づけられてしまうものもあるけど、その人にとってはリアルなことで、私の体験にはない現実を生きていらっしゃると考えて、心を自由にして聞くことにしています。それから、彼らの生活に近いところにいると、悲しいこと、悔しいことが沢山、起きるわけだけれど、あちらからやってくる出来事に、その場その場で大事なものを守ろうと対応するしかない、その場に居続けるしかないところがあって。だから僕には案外主体性はないのかもしれないです。
*
自分の心の動きに素直でいることは、同時に相手の心の動きを尊重することでもある。そんな二人の話を聞きながら思ったのは、人と人との関係はもともと出来上がっているものではなく、出会った瞬間から育まれていくものであるということだ。最初から「良い関係」なんてありえなくて、ともに過ごし、時間や感情を分かち合うことを通じて、関係の実質は少しずつ築かれていくにちがいない。
主体的であることの困難さ
主体的であれることの特権性
対話はここから、新澤さんの「主体性」という言葉を糸口に展開していった。昨今、教育やキャリア形成の分野では「主体性」が大切だとされているが、そもそも「主体的である」とはどういうことなのだろう。勅使川原さんは「主体性」という言葉にはパラドックス(逆説)があると指摘する。
勅使川原:企業が求める「主体性」という言葉の意味の変遷をめぐる研究(武藤浩子 2024年)によると、最初は「主体的に考える」という意味で語られていたのが、徐々に「主体的に考え行動する」という行動力の意味を含むようになって、最近では「主体的に考え・行動し・他者とつながるために発信する」という発信力にまで意味が拡張してきているそうです。新澤さんは「主体性」をどう考えていますか?
新澤:僕はある種、その主体性を手放した状態なのかもしれないです。
勅使川原:……! 目から鱗です。教育関係者や企業の人材開発担当者の方でも「主体性を育む」ってまだおっしゃることが多いんです。「主体性」という言葉自体がもうマジックワードなのに、どうやってやるのかなと思っていたところで。
新澤:「主体的に生きる」こと自体はとても困難という気がしますよね。きっとそれは、僕がハーモニーで重度の精神障害のある人と会う中で、彼らにとっての主体性ってなんだろうという視点を持ったからだと思うんです。もし彼ら自身に主体性なるものがあるとしたら、次々にそういうものを奪われてきたわけですから。
勅使川原:なるほど。
新澤:いろんな評価でがんじがらめにされて、主体性が入り込む余地もないような毎日を送ってるように感じることもあります。だからどこか突破口を見つけたい。絵に描いたモチかもしれないけど、まず、彼らが楽にいられる場所を30年間目指し続けてきました。
勅使川原:そういう実践なんですね。お話を聞いてて、改めて主体性って発揮できることがすでにものすごい特権なんだと思いました。
新澤:うん、特権ですよね。
勅使川原:私がやろうとしているのは、特権性に気づいていない人に「それは特権だから周りに同じように求めるのはやめたらどうですか?」と伝えることなのかなと思うんです。特権のある人はそれがあたりまえに備わっているものだと思っているから、特権に気づきづらいんですよね。
新澤:そうですね。
勅使川原:もともとは能力主義って、身分制度や封建的な仕組みに対する世紀の発明として生まれたんですね。でも、今は社会の配分原理がそれしかないので限界が見えてきている。それでも、これまで競争に勝って特権を振りかざしてきた側の人たちの根強い声でループが回り続けているんですよね。人が優越感みたいなものを手放すことって、こんなにも難しいんだなってよく思います。
*
勅使川原さんが指摘するように、自分の力でレースに勝ってきたと信じる人たちにとって、その特権性に気づき、勝ち得てきたものを手放すのは難しい。だからこそ、既存のシステムは維持され、レースの新たな参加者が増え続けるのだ。
レースを勝ち抜くために、未来への見通しやさまざまな能力が求められるようになった。けれども、現実というのは本当に人の「力」でなんとかできるようなものなのだろうか?
現実の人間はもっとたくましくバラバラ
新澤さんは、30年前の福祉の世界ではもっと「のびのび自由にやろうよ」という空気があったと振り返る。しかし、近年では国の法律や社会の仕組みの中にそもそも評価が組み込まれ、一定の筋道が出来上がってしまっていると言う。
新澤:もちろん筋道が必要な場面もあるんだけど、その範囲の外にも人は生きていてそれぞれの人生があるよね、ということに気づきにくくなってきてるのかもしれません。あるいは生きづらさを感じている人のことを他人ごとだと見なして、どんどん自分のテリトリーを狭めて守ってしまう気もするのです。
勅使川原:ビジネスの世界でも「筋道」、つまり見通しがないとダメなんですよ。未来を予測して、現実をコントロールしようとする。でもさっきから話しているのは、そもそもコントロールなんかできないということですよね。
垣花:若者に近い立場としては、コントロールできる範囲を持たせてくれないと自分の余裕がなくなってしまうという気持ちもあるなと思います。ほかの生活のことにいっぱいいっぱいで、目の前の仕事まで「不確実性」とか言われると、ここだけはせめてコントロールさせてよと感じてしまうというか。
勅使川原:VUCA(不確実性)の時代って誰が言い出したんでしょう。未来が確実に読めた時代がいつあったんですか?って。それで「汎用的な能力を伸ばせ」と言われたり、「コスパ」「タイパ」わかりやすい「リーダーシップ」やら「ウェルビーイング」やらが重視されたりする。
新澤:そういうのが嫌で、僕はこの世界に逃げてきたと言ってもいいと思うんです。もちろん施設を経営しなきゃいけないのは当然のことですが、現実の当事者たちはそうではないので。結構たくましくバラバラで、毎日問題が起きるのが当たり前。若いスタッフには大変かもしれない。生ま身の人間というのは、学校で学んできた理屈とは違うんですよね。
勅使川原:それは企業の採用も同じですよね。学生のコンパクトでフックのあるエピソードトークを求めて、それでその人のことを分かった気になって評価を下す。
新澤:ハーモニーにも学生のインターンが来てくれるんですけど、日中は何時間かハーモニー参加して、その後バイトがあって、そのあと何かの講座に行って……と忙しそうな人が多いです。自身のことも話すのもうまいし、夢も語ってくれるんだけど、ちょっと待って、まずメンバーとゆっくりしなさいよとか、目の前の人と時間を過ごして、時として途方にくれなさいよと思います。そうじゃないとその人のすごいところとか面白いところが分からないと思うんですけどね。
*
「結果のために」「お金のために」「将来のために」……行動の意味が、その行動の結果へと外化するとき、「目の前の相手」に意識を向けることは難しくなる。新澤さんがハーモニーで培ってきた「それよりも障害当事者の人とゆっくりしたらいいのに」という感覚はおそらく、より良い未来へ夢中で走り抜ける人々を「今ここ」へ引き戻そうとする磁場ようなものである。
一方で、能力主義が支配する社会のただなかを走りながら、そのことに気づき、ペースを落としたり立ち止まることは難しいことでもある。私たちは日々の生活のなかでどのように実践できるだろうか。
相手を「いたずらに」評価しないために
新澤さんが取り出したのは、30年前にハーモニーのマークを作ろうとしたときに、メンバーの一人が「これ俺なんだ」と言って持ってきたという一枚の絵の写真だった。
新澤:これは70年代に流行った『丸出だめ夫』という漫画のキャラクターがモチーフなんです。自虐と言われてしまうかもしれないけど、「まるでダメ」って思ってる人と一緒に笑い合えるようなところから関係を始めていければいいかなって思っているんです。それは「いたずらに評価しない」にも通ずるかなと。
勅使川原:そうですね、良いも悪いもないんですよね。
垣花:他からの評価が自分の存在価値にまで結びついてくる社会、本当に怖いなと思います。じゃあそれがどこから刷り込まれたんだろうと考えると、心当たりがあまりにも多すぎて具体的に分からないくらいなんですよね。その呪いはたかが数年で解くのは本当に難しいんじゃないかなって思うんです。
勅使川原:私の場合、やっぱり2020年の夏に進行がんが見つかったのがきっかけで、思うようにできないことが増え、闘病に翻弄されつつも、自分の特権に気づかされました。そしたら、いわゆる「ままならなさ」を体感した人たちとの連帯のようなものをすごく感じるようになったんです。そういう「ままならなさ」と日々対峙されているのが新澤さんなのかな。
新澤:ままならない。まあ、ままならないとすらも思わないぐらいままならないのかもしれません。何年もかけて積み上げてきたものがとつぜん崩れてしまうこともありますし、次に何が来るか分からない。だから何が来てもいいという心持ちでいないとやっていけないです。もちろんそのたびに悲しかったり、こちらの気持ちは動くんだけど。
勅使川原:うん、うん。
新澤:でもそこで、不安だからって道筋を作っちゃうと、どんどん自分たちを窮屈にしちゃう。筋道を決めたくなるんですけどね、僕たちの人生も。だけど、そもそも物事ってほとんど偶然に決まるものだと思うんです。たまたま入学式のとき隣にいた人が一生の友達になったり、結婚する相手との出会いも偶然であったり。そういう「出会いの偶然性」を彼らは奪われているんです。だからハーモニーにはどんどん外から人を入れちゃうし、筋道を決めないことが彼らに対する僕の決意の表れというか。もちろん、それと制度とをどう両立していくかという課題はあるし、職員にもさまざまな考え方や価値観があるから、なかなか大変だよなと思いつつ、それもままならないままほっとくみたいなところはあります。
垣花:わたしが新澤さんに対して感じているのは、「でもこれからも関わり続けるよね」という考えが前提にあるんじゃないかということです。関心がないわけではなくて、これからも時々すれ違うし、一緒にご飯を食べるかもしれない。続けることが前提の「ほっとく」なんだよなって。
新澤:ほっとけないを前提にしたほっとく、ですかね。その上で、それぞれの人を価値で測るというよりも、上下を決めないただの差異として、その人がその人としてただいられる場所を模索しています。
椋本:「ただいるだけでいい」という感覚や、「偶然の出会い」に開かれることって、職場ではどのようにあり得るでしょうか?
勅使川原:職場でできることとして私がよくお伝えしているのは、「謝意」から始める組織開発ということです。やっぱり「いてくれてありがとう」なんですよね。こんなご時世にうちみたいな会社来てくれてありがとうって。企業側は選んでいる気になってるけど、実は選び・選ばれて、偶然の重なりによってそこに居合わせている状態だと思うんです。でも、立場がある人はこの提案に難色を示すことも多いです。ありがとうって言うことで何かが減ると思ってるのかな。新澤さんがおっしゃっていた「ごめんね」を伝えることも、「いや、謝るべきじゃない」と言う人が多い。
新澤:うんうん、「男らしくない」とか言われるんでしょうね。
勅使川原:「男に二言はない」とか。新澤さんの「いたずらに」っていうワードは「ともするとやりがちだけど」という意味でもあるのかなと思っています。今すぐに能力主義にもとづく評価の正しさが流布される社会を変えることは難しいと思うのですが、その一歩はやっぱり、「すぐ決めつけてしまいがち」とか「枠に閉じられてしまいがち」ということに自覚的であれるかだと思います。
垣花:「しかたない」とか「ほっておく」という今日のお話がつながってくる気がするものがあります。ハーモニーが出版した『超・幻聴妄想かるた』のインタビューの中で、新澤さんが「ハーモニーにたどり着いて、何年も一緒に過ごす。だんだん仲良くもなるのだけれどなかなか認め合えないことも多い。だんだん『仕方ないなあ』と思い始める。ここではお互いを『認める』っていうのは限りなく『あきらめる』にも近いのです」と書いていて。
勅使川原:面白いなあ。学校で言われる規範の真逆ですよね、今日の話って。でもそれがリアルですよね。諦めながらでも居続けるとか。そんな道徳とか美化されて語られるようなことじゃなくて。
新澤:それを楽しめるといいなと思いますよね。
*
哲学者の九鬼周造は、『偶然性の問題』のなかで「あらゆる事象はゆくりないめぐり逢いである」と述べた。よく考えてみると「出会い」とは不思議な現象である。過去の無数の分かれ道からその道を進んできた二人の人生がたまたま交差する。もしもどちらか一方が一つでも違う道を選び、少しでも駆け足で進んでいたら、出会うことはおろか、相手の存在を知ることすらなかったかもしれない。すなわち、出会いとは「無数の偶然」の産物に他ならない。とするならば、あなたとわたしが今ここでともに在ることは奇跡のようなものである。
勅使川原さんが「謝意を伝える」と言うとき、また新澤さんが「目の前の人ともっとゆっくり過ごせばいいのに」と言うとき、二人に共通するのは「今ここに、ともに在ることのかけがえなさ」の感覚から関係が出発しているということだ。だからこそ個々の持つ特性や体験が生きてくるということを、二人は生ま身の経験から掴んできたのだと思う。
どんなにうつくしい理想を抱いたとしても、私たちは目の前の相手を「いたずらに決めつけてしまう」ことがある。しかし、それを悪いことだと一面的に否定するのではなく、そうあってしまうことを自覚しながら、ちゃんと「ありがとう」や「ごめんね」を伝えたり受け入れること。その繰り返しがより良い関係を育んでいくのだろう。
二人が言及するように、もちろん関係は永遠には続かないし、社会全体への影響力は微々たるものかもしれない。それでも、そのことを受けとめた上で、出会いの面白さやかけがえなさとともに目の前の相手と関係していけるかどうかが分かれ道となるにちがいない。偶然居合わせた一人の相手とそう関係しようとするとき、それだけの領域において、社会はすでに新しい。
Information
【勅使川原真衣さん著書】
・『「能力」の生きづらさをほぐす』(どく社)
・『働くということ 「能力主義」を超えて』(集英社新書)
・『職場で傷つく~リーダーのための「傷つき」から始める組織開発』(大和書房)
【新澤克憲さん著書】
・『同じ月を見あげて -ハーモニーで出会った人たち』(道和書院)
Profile
![]()
-
勅使川原真衣
組織開発専門家
1982年横浜生まれ。組織開発専門家。東京大学大学院教育学研究科修士課程修了。外資コンサルティングファーム勤務を経て、2017年に組織開発を専門とする「おのみず株式会社」を設立。二児の母。2020年から乳がん闘病中。「紀伊國屋じんぶん大賞2024」8位にランクインした初めての著書『「能力」の生きづらさをほぐす』(どく社)が大きな反響を呼ぶ。近刊に『働くということ 「能力主義」を超えて』(集英社新書)、『職場で傷つく リーダーのための「傷つき」から始める組織開発』(大和書房)がある。PHP研究所の論壇誌『Voice』や教育開発研究所月刊誌『教職研究』で連載中。写真撮影:Shohei Ishida
Profile
![]()
-
新澤克憲
NPO法人やっとこ 理事長
大学院中退後、デイサービスの職員、塾講師、木工修行を経て、共同作業所ハーモニー施設長(1995~2011)就労継続支援B型事業所ハーモニー施設長(2011~2022)。現在は特定非営利活動法人やっとこ理事長。基本的に人見知り、ひきこもり気質に加え体重増加中のため、あまり動かない。記憶と記録、語りと言葉、そして人びとの居場所について関心がある。休日はパンクバンド「ラブ・エロ・ピース」のノイジーなギタリストとして活動する。2024年4月には、30年の間にハーモニーで出会った人たちとの日々の出来事を記録した『同じ月を見あげて ハーモニーで出会った人々』を道和書院より刊行した。他にも共著書『超・幻聴妄想かるた』(2018年、やっとこ)。写真撮影:田中ハル
- ライター:椋本湧也
-
1994年、東京生まれ、京都在住。都内の出版社と家具メーカーでの仕事を経て、現在京都で出版社の立ち上げ準備中。書籍の編集や執筆、個人出版なども行う。著作に『26歳計画』『それでも変わらないもの』『日常をうたう〈8月15日の日記集〉』。
この記事の連載Series
連載:こここインタビュー
![]() vol. 332025.09.26遊びと医療ケアの両立をどう目指す? 「そらぷちキッズキャンプ」の“人を信じて待つ”仕事
vol. 332025.09.26遊びと医療ケアの両立をどう目指す? 「そらぷちキッズキャンプ」の“人を信じて待つ”仕事![]() vol. 322025.03.18言葉を超えて誰もがつながる「身体表現」の魅力とは? 福祉を起点に広がるパフォーミングアーツ、生きづらさを変える可能性
vol. 322025.03.18言葉を超えて誰もがつながる「身体表現」の魅力とは? 福祉を起点に広がるパフォーミングアーツ、生きづらさを変える可能性![]() vol. 302024.09.13大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 写真家/訪問看護師 尾山直子さんをたずねて
vol. 302024.09.13大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 写真家/訪問看護師 尾山直子さんをたずねて![]() vol. 292024.09.07地域に根ざす園から、子どもも大人も混ざった“絶景“を生み出せたら。〈学校法人thanka〉が新ステートメント「手を繋ぎにいく」に込めた願い
vol. 292024.09.07地域に根ざす園から、子どもも大人も混ざった“絶景“を生み出せたら。〈学校法人thanka〉が新ステートメント「手を繋ぎにいく」に込めた願い![]() vol. 282024.08.30大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 株式会社Blanket 秋本可愛さんをたずねて
vol. 282024.08.30大切な人の変化に戸惑ったとき、どうすれば? 株式会社Blanket 秋本可愛さんをたずねて![]() vol. 272024.07.25気軽な買い物体験から、「未来が良くなる」手応えを。〈フェリシモ〉の新カタログ『GO! PEACE!』制作の裏側
vol. 272024.07.25気軽な買い物体験から、「未来が良くなる」手応えを。〈フェリシモ〉の新カタログ『GO! PEACE!』制作の裏側![]() vol. 262024.04.30蓋された「小さな自分」の声に耳を傾けて。ケアを促す料理レッスンの場、就労支援の場──山口祐加さん×鞍田愛希子さん
vol. 262024.04.30蓋された「小さな自分」の声に耳を傾けて。ケアを促す料理レッスンの場、就労支援の場──山口祐加さん×鞍田愛希子さん![]() vol. 252024.04.10「インクルーシブ」は誰のための言葉? 老舗メーカー〈ジャクエツ〉×医師・紅谷浩之さんの、子どもに“遊びと友だち“を返す遊具
vol. 252024.04.10「インクルーシブ」は誰のための言葉? 老舗メーカー〈ジャクエツ〉×医師・紅谷浩之さんの、子どもに“遊びと友だち“を返す遊具![]() vol. 242024.03.29文化施設のウェブアクセシビリティを向上する。障害当事者との「建設的な対話」に必要なこととは?──伊敷政英さん×森司さん
vol. 242024.03.29文化施設のウェブアクセシビリティを向上する。障害当事者との「建設的な対話」に必要なこととは?──伊敷政英さん×森司さん![]() vol. 232024.03.27だれもが文化でつながるために。クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョーが見据えるこれからの文化施設のあり方とは。
vol. 232024.03.27だれもが文化でつながるために。クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョーが見据えるこれからの文化施設のあり方とは。![]() vol. 222023.12.22人のためってなんだろう? 他者にコントロールされない「LOVOT」から、“人間らしさ“を考える──伊藤亜紗さん×林要さん
vol. 222023.12.22人のためってなんだろう? 他者にコントロールされない「LOVOT」から、“人間らしさ“を考える──伊藤亜紗さん×林要さん![]() vol. 212023.11.08保育料ゼロを実現し、子育てを“みん営化”する。 学童保育施設〈fork toyama〉岡山史興さん
vol. 212023.11.08保育料ゼロを実現し、子育てを“みん営化”する。 学童保育施設〈fork toyama〉岡山史興さん![]() vol. 202023.05.29ともだちってなんだろう? 答えを出す必要はないけれど。新澤克憲さんとテンギョー・クラさんの対話から考える
vol. 202023.05.29ともだちってなんだろう? 答えを出す必要はないけれど。新澤克憲さんとテンギョー・クラさんの対話から考える![]() vol. 192023.05.23歌人・岡本真帆さん×西淡路希望の家・金武啓子さん対談。「感動」の発見、どう他者と分かち合いますか?
vol. 192023.05.23歌人・岡本真帆さん×西淡路希望の家・金武啓子さん対談。「感動」の発見、どう他者と分かち合いますか?![]() vol. 182023.03.20“みる”から始める、アーティストと支援現場のつなぎ役。日常の関係性を変える「TURN LAND プログラム」の挑戦
vol. 182023.03.20“みる”から始める、アーティストと支援現場のつなぎ役。日常の関係性を変える「TURN LAND プログラム」の挑戦![]() vol. 172023.03.15アート活動で、「できる/できない」を揺さぶる。日常の価値を言葉に変えるコーディネーターの役割
vol. 172023.03.15アート活動で、「できる/できない」を揺さぶる。日常の価値を言葉に変えるコーディネーターの役割![]() vol. 162023.03.03唯一の答えを探しすぎていないか? 下地ローレンス吉孝さん×なみちえさんと“わかりやすさ”について考える
vol. 162023.03.03唯一の答えを探しすぎていないか? 下地ローレンス吉孝さん×なみちえさんと“わかりやすさ”について考える![]() vol. 152023.02.15“わたし”と“あなた”それぞれの複雑さを大切にするには?──なみちえさん×下地ローレンス吉孝さんと共に考える
vol. 152023.02.15“わたし”と“あなた”それぞれの複雑さを大切にするには?──なみちえさん×下地ローレンス吉孝さんと共に考える![]() vol. 142022.12.23出会いを広げながら、協働を生む「メディア」を目指して──〈こここ〉シーズン2を振り返る
vol. 142022.12.23出会いを広げながら、協働を生む「メディア」を目指して──〈こここ〉シーズン2を振り返る![]() vol. 132022.12.19働くことも、映画祭も「みんなが心地よい」を目指して。GOOD NEWSとTHEATRE for ALLのインクルーシブな場づくり
vol. 132022.12.19働くことも、映画祭も「みんなが心地よい」を目指して。GOOD NEWSとTHEATRE for ALLのインクルーシブな場づくり![]() vol. 122022.10.14バリアフリーの映画祭を通して、「その人のまま」でいられる社会に。作家・川内有緒さん×THEATRE for ALL・金森香さん
vol. 122022.10.14バリアフリーの映画祭を通して、「その人のまま」でいられる社会に。作家・川内有緒さん×THEATRE for ALL・金森香さん![]() vol. 112022.09.13スポーツの可能性って何だろう? 「プロスポーツ」「ゆるスポーツ」から考える──岡田武史さん×澤田智洋さん
vol. 112022.09.13スポーツの可能性って何だろう? 「プロスポーツ」「ゆるスポーツ」から考える──岡田武史さん×澤田智洋さん![]() vol. 102022.03.31まだみぬ「表現」との出会いを、誰もが体験できる社会へ。障害のある人の芸術・文化活動を支える窓口が全国に
vol. 102022.03.31まだみぬ「表現」との出会いを、誰もが体験できる社会へ。障害のある人の芸術・文化活動を支える窓口が全国に![]() vol. 092022.02.09コロナ禍で「消される」声に、どう耳を傾ける? 次の社会をつくる言葉と対話のあり方──荒井裕樹さん×青山誠さん
vol. 092022.02.09コロナ禍で「消される」声に、どう耳を傾ける? 次の社会をつくる言葉と対話のあり方──荒井裕樹さん×青山誠さん![]() vol. 082021.12.24福祉をたずねて1年。編集部は何に出会い、悩んできた?──〈こここ〉振り返り座談会
vol. 082021.12.24福祉をたずねて1年。編集部は何に出会い、悩んできた?──〈こここ〉振り返り座談会![]() vol. 072021.11.24コロナ禍を経て新たな表現の協働へ ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[後編]
vol. 072021.11.24コロナ禍を経て新たな表現の協働へ ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[後編]![]() vol. 062021.11.24アートプロジェクトは福祉の現場で何を生み出す? ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[前編]
vol. 062021.11.24アートプロジェクトは福祉の現場で何を生み出す? ―小茂根福祉園とダンサー・大西健太郎さんが過ごした6年間[前編]![]() vol. 052021.10.18福祉施設が学びあいの拠点になることで育まれるものとは?ライフの学校・田中伸弥さん
vol. 052021.10.18福祉施設が学びあいの拠点になることで育まれるものとは?ライフの学校・田中伸弥さん![]() vol. 042021.06.03VR認知症を体験して気づいた、わからない世界へ手を伸ばし続ける大切さ。シルバーウッド 下河原忠道さん
vol. 042021.06.03VR認知症を体験して気づいた、わからない世界へ手を伸ばし続ける大切さ。シルバーウッド 下河原忠道さん![]() vol. 032021.04.15まだ名付けられていない感覚に出会う「遊び」の可能性とは? インタープリター 和田夏実さん
vol. 032021.04.15まだ名付けられていない感覚に出会う「遊び」の可能性とは? インタープリター 和田夏実さん![]() vol. 022021.04.15「助けて」とお互いに言い合えるのが、成熟した社会。ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ代表 志村季世恵さん
vol. 022021.04.15「助けて」とお互いに言い合えるのが、成熟した社会。ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ代表 志村季世恵さん![]() vol. 012021.04.15「お笑い」や「演劇」は他者の世界に寄り添うヒントをくれる。りんたろー。さん×菅原直樹さんが語る「介護の話」
vol. 012021.04.15「お笑い」や「演劇」は他者の世界に寄り添うヒントをくれる。りんたろー。さん×菅原直樹さんが語る「介護の話」